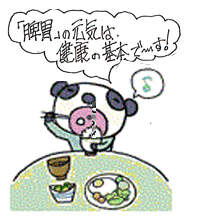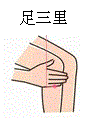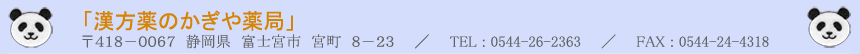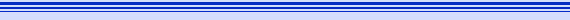

2018年6月
 「脾胃」の働きと養生法
「脾胃」の働きと養生法

梅雨~夏にかけては、湿気や暑さで「脾胃(ひい:消化器系)」の不調を感じやすい時季。
”後天の本”と呼ばれる「脾胃」は、 飲食物を消化吸収して、生命力の源となる「気(エネルギー)」や「血」を生む大切な臓器です。
今回は、これらの季節を元気に乗り切るために「脾胃」の働きと養成法について、ご紹介したいと思います。
漢方では、「内傷脾胃、百病由生(脾胃が傷ついて食事をしっかりとれなくなると、 元気な身体を保てず病気にかかりやすくなってしまう)」という言葉があります。
| ・脾胃 | が元気で栄養をしっかりとることができる ―基本的な体力、免疫力が養われ、健康な身体をつくることができる。 |
| ・脾胃 |
の機能が弱くなる
―食欲不振や消化不良、下痢といった症状を招き、栄養やエネルギーが不足しがちに。
体調を崩しやすくなり、夏バテや疲労、冷えといった不調も起きやすくなってしまいます。 |
これからの季節、どのような事に気をつけていったらよいか、3つのタイプに分けてみました。
| ① | 湿が溜まる食の不摂生タイプ |
|---|---|
| 「脾」は”湿を嫌い、燥を好む”、「胃」は”冷え”を苦手とする臓器です。
ところが、梅雨~夏は湿邪(自然界の邪気)が身体に侵入しやすく、冷たいものや水分も過剰に摂ってしまいがち。 すると、脾胃に負担がかかって機能が落ち、体内に「湿(余分な水分や汚れ)」 がたまり、いろいろな症状をひきおこします。 |
| <気になる症状> | 吐き気、胃の膨満感、胃のムカつき、げっぷ、下痢、軟便、 舌の苔が多い |
| <おすすめ食材> | 脾胃の働きを整え、湿を取り除くものを
はと麦、しそ、梅干し、チンピなど |
| <おすすめ漢方薬> | 藿香正気散、清香散など |
| ② | 冷房に注意! 冷えタイプ |
|---|---|
| 飲食物を消化吸収する「脾胃」の働きは、体内の「陽気(エネルギー)」によって守られています。
ところが、夏は過剰な冷房や冷たいものの取り過ぎなどで、陽気を消耗しがちになり、 いろいろな症状をひきおこします。 |
| <気になる症状> | 胃痛、腹痛、下痢、お腹の冷え、身体の冷え、顔色が白い |
| <おすすめ食材> | 冷えた身体を温めるものを
しょうが、ねぎ、にんにく、にら、山椒の実、八角、シナモン、みようが、ナツメグなど |
| <おすすめ漢方薬> | 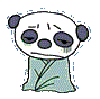 胃の痛みに ―開気丸 胃の痛みに ―開気丸
お腹の冷えに―人参湯、半夏瀉心湯 身体の冷えに―婦宝当帰膠 など |
| ③ | 慢性的な胃腸虚弱タイプ |
|---|---|
| 不摂生な食生活を続けている人、慢性疾患がある人などは、慢性的に脾胃の働きが弱くなっていることも少なくありません。
このタイプの人は、普段から栄養を十分摂ることができない・脾胃の働きを支える「陽気」も不足してしまうことで、 色々な症状をひきおこします。 |
| <気になる症状> | 食欲不振、慢性的な胃腸不調、全身の疲労感、息切れ、めまい、かぜをひきやすい |
| <おすすめ食材> | 脾胃の働きを良くして、体力を養うものを
米、もち米、いんげん豆、山芋、じゃがいも、キャベツ、大豆製品、りんご、豚肉など |
| <おすすめ漢方薬> | 参苓白朮散、清暑益気湯など |
| 脾胃を元気にするツボ | |
| ひざのお皿のすぐ下、外側のくぼみに人さし指をおき、指幅4本そろえて、小指があたっているところ |