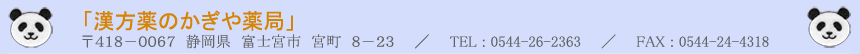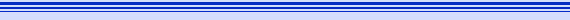

2013年9月
 『潤い養生』で秋の乾燥対策いたしましょう!
『潤い養生』で秋の乾燥対策いたしましょう!

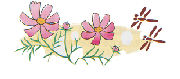
9月に入ってせき・ぜんそくでお困りのご相談増えています。
夏の疲れや空気の乾燥が影響していると思われます。
今月は寒い季節に備えるためにも、体調を整える季節・
秋の養生について、お話ししたいと思います。
| 夏の疲れとは、 | ● 大量の発汗による潤いの流失 |
|---|---|
| ● 過度な冷房による皮ふの乾燥 | |
| ● 日焼けによる皮ふの乾燥と疲労 | |
| ● 睡眠不足による体内の潤い消耗 | |
| ● 食欲不足による体力不足、栄養不足 |
そして秋は、空気の乾燥による邪気「燥邪」の影響を受けやすい季節です。
つまり夏の消耗と秋の燥邪による乾燥の影響が重なると、 夏を過ぎても疲労や食欲不振が続く秋バテを起こしてしまう心配もあります。
五行色体表より
| 五行 | 五季 | 五臓 | 五腑 | 五主 | 五竅 | 五悪 | 五味 | 五色 |
| 金 | 秋 | 肺 | 大腸 | 皮 | 鼻 | 燥 | 辛 | 白 |
漢方でいう「肺」とは、呼吸機能(呼吸は、鼻や口からだけでなく、皮ふ呼吸もおこなっているので皮ふも肺の一部とみます。) をコントロールする。体温の保持・発汗・防衛・嗅覚をコントロールする。よぶんな水分を尿として排出する。などの作用があります。 このため肺は、乾燥によるダメージを受けやすく、風邪をひきやすくなったり、 肌が乾燥してカサカサしたり、かゆみが出たり、気管支炎やのどの痛み、 から咳などの症状が現れやすくなります。
まず夏の疲れを回復して、食事や生活習慣に気を配り、 不足しがちな潤いをしっかり養うよう心がけましょう!
〈 暮らしの養生 〉
 | 肺や皮ふに潤いを補給しましょう。 |
| 肺は、「潤いを好み、乾燥を嫌う」という特徴があります。 食事などで肺の潤いを保つことはもちろん、保湿剤を利用して皮ふの潤いを守りましょう。 |

 | 深呼吸で肺を鍛えましょう。 |
| とても簡単な事ですが、これをくりかえすことで、呼吸機能を着実に高めることができます。
朝の時間に、1日15回程度がおすすめ。 |
のどのトラブルレシピ
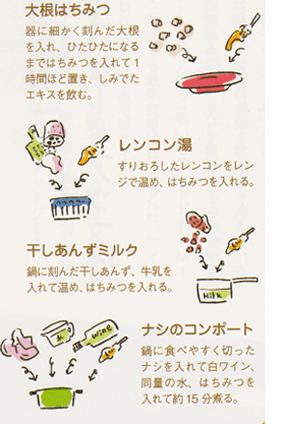
〈 食養生 〉
| 白い食材‐ | れんこん・長いも・梨・大根 |
|---|---|
| 白きくらげ・百合根・銀杏
豆ふ・豆乳・牛乳・白ごま はちみつ など |
白い食材は、肺に潤いを与えるといわれていますので、ちょっと意識して、 毎日の食事に取り入れてみて下さいね。
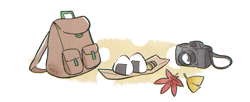
春夏秋冬ゆる膳薬。より(池田陽子著)