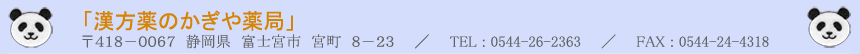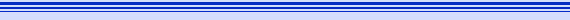

2012年1月  関節痛・腰痛・神経痛・・・
関節痛・腰痛・神経痛・・・
辛い痛みをやわらげるには?

1月21日は大寒。一年でもっとも寒い日ですねェ。 寒さが厳しくなるこの時期、関節痛・腰痛・神経痛などの辛い痛みに悩まされることも多いのでは・・・
漢方では、関節や筋肉の痛みを特徴とする症状を『痺証(ひしょう)』といいます。『痺』には”つまる・通じない”という意味があり、 関節痛・腰痛・神経痛などの痛みの症状は、 体内を巡る「気(エネルギー)・血」の流れがつまって通じなくなることで起きると考えます。 この流れを停滞させる原因と考えられているのが、気温や湿度といった気候条件に伴う 「風邪・寒邪・湿邪」の邪気(外因)です。 では痛みの原因についてくわしくみていきましょう。

Ⅰ.初期の痛みの原因<邪気の侵入>
→ 体内の邪気は早めに発散し長期化を防ぎましょう!
邪気の侵入の特徴は「風邪」が他の邪気を連れて一緒に体内に入ってくること。
冬の寒さや冷房などで「寒邪」が入りこむと、体が冷えて経絡が滞り痛みとなります。
また、梅雨や雨の日には「湿邪」が侵入しやすく、体内に湿(余分な水分や汚れ)が停滞して痛みを引き起こす原因に。
寒と湿の邪気が同時に侵入することもあり、その場合は痛みも強くなるので注意が必要です。
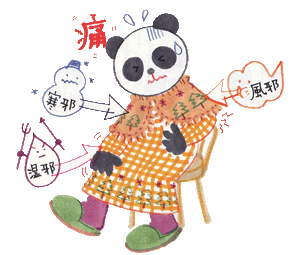
Ⅱ.痛みの長期化を招く<気・血の流れの悪化>
→慢性化で痛みが強くなることも。まずは気・血の流れの改善を。
初期の痛みを引き起こす邪気の侵入も、長期化すると気・血の流れを妨げる原因に。
風邪・寒邪・湿邪などが体内に長く滞ると身体の冷えや湿の停滞から気・血の巡りが悪くなり、痛みも強くなります。
こうした痛みの症状は慢性化しやすいので、早めの改善を心がけることが大切です。
Ⅲ.邪気が侵入しやすい<虚弱体質>
→ 体力不足でバリア機能が低下。加齢による「腎」の衰えにも注意。
体内を十分な気・血が巡り、陽気が満ちていれば、痛みの原因となる邪気の侵入から身体を守ることができます。
反対に、加齢や疲労、病後などによる虚弱体質で気・血が不足していると、身体のバリア機能が低下して邪気が侵入し、
痛みが起きやすくなってしまうのです。また、「腎」は骨の生育、
「肝」は筋(筋肉と骨についている腱、筋膜、じん帯)
の働きと深いかかわりがあるため、加齢によって腎や肝の働きが衰えていると関節が老化していることも。

痛みを予防する冬の養生法
痛みの原因となる風邪・寒邪・湿邪の侵入を防ぎ、
免疫力を高めるためにも「体の中なら病気を治す」
食生活が大切です。特に冷えは禁物。
体を温めて新陳代謝を促進する下記の食材を上手に取り入れましょう。
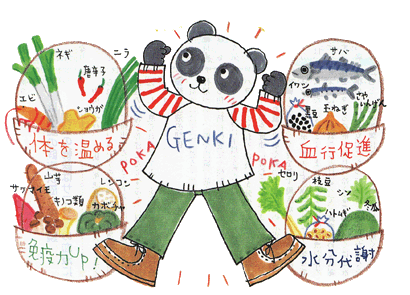
痛みの養生は、原因を取り除き、体内の「気・血」の流れをスムーズにすることが基本。
身体を冷えから守る、血流を良くする、体力をつけるなど、体質を整えることで根本的なチカラを養い、
身体の中から痛みを改善することが大切です。