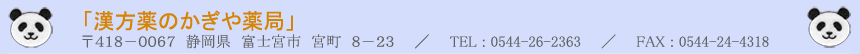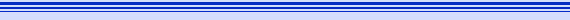

2016年10月
 お屠蘇のはなし
お屠蘇のはなし

元旦の朝、雑煮やおせち料理をいただく前に、飲むのがお屠蘇。 日本古来の良き風習<邪気を払い、無病長寿を祈願する>を見直してみませんか。

< お屠蘇の由来 >
中国・三国時代に名医・華陀(かだ)が、一年間の災難厄除けのために、山椒・防風・細辛・桔梗・大黄など数十種類の薬草を調合して、 お酒に浸して飲んだのが始まりといわれています。日本には、平安時代に伝わり、 嵯峨天皇の頃に宮中の正月行事として始められ、江戸時代には、一般に広まったそうです。
< 屠蘇散に使われる生薬 >
書物によって違いますが、一般的には、オケラの根(白朮)・サンショウの果皮(山椒)・ボウフウの根(防風)・ キキョウの根(桔梗)・ニッケイの樹皮(桂皮)・ ミカンの皮(陳皮)など、身体を温めたり、胃腸の働きを助けたり、風邪の予防に効果的といわれる生薬を含んでいます。
< お屠蘇の作り方 >
屠蘇散一包を大晦日の夜、清酒または本みりん、または、清酒と本みりんをブレンドしたものに一晩浸し、 元旦の朝、雑煮やおせち料理をいただく前に、お屠蘇を年少者から年長者へ飲み回します。