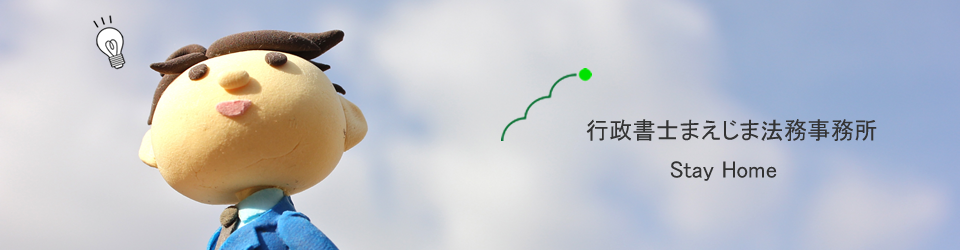



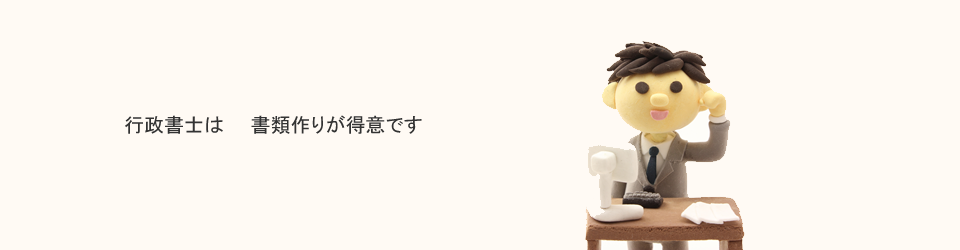

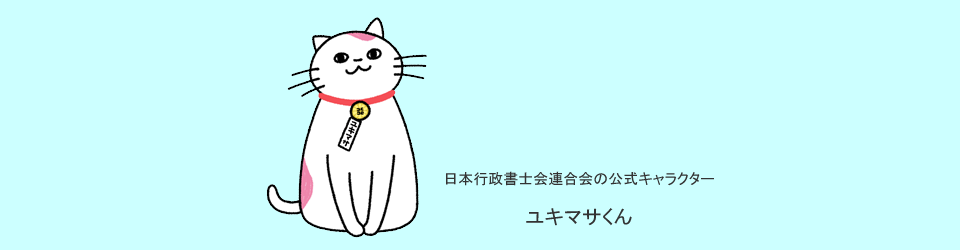
富士、富士宮、静岡東部の遺言相続のことなら
ご相談・来所の際はご予約下さい。時間外でも可能な限り対応します。
090-3933-0099 受付:9~19時 休日:土日祝日
執筆:令和2年4月20日
一部訂正:令和2年5月12日
令和2年7月10日から新しく「自筆証書遺言書保管制度」がスタートします。
このページでは、この自筆証書遺言書保管制度について、現在判明している内容をまとめた上で解説しています。
今後変更される可能性があります。ご了承ください。
詳細サイト:法務省民事局「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」
参考資料:法務省民事局パンフレット「自筆証書遺言書保管制度のご案内」令和2年4月作成(PDF 2.6MB)
概要
自筆証書遺言書保管制度とは、ご自分で作った遺言書(自筆証書遺言書)を法務局が保存してくれる制度です。
法務局という公的機関が保管することで、遺言の紛失や改ざんなどの管理に対する心配がなくなると同時に、発見のされやすさが格段にアップします。
遺言書の原本だけでなく、遺言書をスキャンして画像データとしても保管されます。
保管の手数料は1通3,900円です。
令和2年7月10日からの制度開始を予定されています。
制度のメリット
① 検認手続きが不要に!
自筆証書遺言で必要だった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
② 紛失・隠匿・改ざん・破棄、発見されないなどの心配が不要に!
原本は法務局に保管されますし、他人がこの制度の手続きをすることはできません。
③ 形式的不備による無効がなくなる!
保管を申請するときに、有効な遺言書として成立するか外形的なチェックをしてくれます。
大まかな流れ
ⅰ 遺言書の作成
↓
ⅱ 法務局にて遺言書の保管の申請、保管証の受取り
↓
(あれば保管の申請の撤回や内容の変更の届出)
↓
ⅲ 遺言者の死亡
↓
ⅳ 相続人が遺言の検索(遺言書保管事実証明書の交付)、遺言書情報証明書の交付
↓
ⅴ 名義変更などの相続手続き
遺言書の保管の申請
まずは、注意事項をよく見て自筆証書遺言を作成します。(引用:法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」5,6頁)
完成したら法務局に対して遺言書の保管の申請をします。保管されると保管証が交付されるので大切に保管しておきます。
保管後は、いつでも遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出をすることが出来ます。
保管証があれば、手続きを行うときに便利ですし、相続人などに対して遺言書の存在を示す手掛かりを残すことにもなります。
保管証の再発行はできませんが、失くしてしまっても手続きをすることができるので心配はありません。
遺言書原本の保管期間は死後50年、データの保存期間は死後150年です。長期間に渡り保存されるので安心です。また、生死が分からないときの保存期間は出生から120年です。
| 遺言書の保管の申請の手数料 | 1通3,900円 |
遺言書の閲覧の請求
法務局で遺言書の保管をした人はいつでもどこの法務局に対しても、閲覧の請求により内容を確認することができます。たとえ内容を忘れてしまっても大丈夫です。
閲覧の請求は、遺言者がまだ生きている間は本人のみすることができます。
遺言者が亡くなったあとであれば、相続人などもすることができます。
保管している法務局では原本の閲覧をすることができますし、それ以外の法務局であってもスキャンされた遺言書をデータとして閲覧することができます。
そして(遺言者が亡くなったあとに)誰かが閲覧をすると、その他の相続人などに対して法務局から遺言書を保管している旨の通知が送られます。知らないところで勝手に手続きが進められてしまうようなおそれがないので安心です。
| 遺言書の閲覧(原本)の手数料 | 1回1,700円 |
| 遺言書の閲覧(データ)の手数料 | 1回1,400円 |
保管の申請の撤回
遺言者は、まだ生きている間であれば、保管の申請の撤回の手続きにより遺言書の返却を受けることができます。
例えば、一度書いた遺言を書き直したいときなどに利用します。
遺言書は、遺言者が亡くなったときにはじめて効力が発生します。状況や心境の変化に合わせて、いつでも何度でも書き直しましょう。
この保管の撤回は、法務局での遺言書の保管を止めて返却を受けることを言います。保管の撤回をしただけでは、遺言書そのものを撤回をしたことにはなりません。
遺言書そのものを撤回をしたいときには、新しい遺言書にその旨の記載をしたり、破ったり燃やしたりして物理的に破棄することが必要です。
保管の申請の撤回は遺言者本人のみが、保管されている法務局に対してすることができます。
| 遺言書の保管の申請の撤回の手数料 | かかりません |
氏名や住所が変わったときは変更の届出
保管の申請後に、遺言者本人や遺言の中に登場する人の氏名や住所などに変更があったときはその変更の届出をする必要があります。
変更後の事項が確認できるもの(住民票や戸籍など)をもって届け出ます。
氏名や住所の変更の届出は、遺言者又はその代理人が、どこの法務局に対してももすることができます。
| 遺言書の変更の届出の手数料 | かかりません |
氏名や住所ではないところを変更したいときは?
氏名や住所ではない部分の変更(たとえば相続させる財産の変更や、相続させる人の変更など)は届出ではすることができません。
概ね次のような方法があります。
① 保管の申請の撤回をし、新しい遺言書の保管の申請をする。
② 保管の申請の撤回をせずに、新しい遺言書の保管の申請をする。
③ 保管の申請の撤回をせずに、新しい遺言書を手元に作っておく。(保管の申請はしない。)
どの方法でも可能ですが、個人的には①をお勧めします。
遺言書は何通でも作成しておくことができますし、その中で内容が抵触する部分があれば新しい遺言書の方が有効になりますが、②では争いのもとを増やすことになりかねません。
また、③では保管がされませんので従来と同じ心配が残ります。
しかし、手続きをしている時間がない、法務局へ持参できないなどの特殊な理由があるときには②③も柔軟に検討すべきです。
ここで「相続人など」とは、相続人、受遺者、遺言執行者として指定された者、それらの相続人・法定代理人などの関係者のことを指します。
遺言書保管事実証明書の交付請求
相続人などは、遺言者が亡くなったあとに、法務局で遺言書が保管されているか確認することができます。
証明される内容は、請求者と関係のある遺言書が保管されているか否かです。
保管されていたときはその旨が付された遺言書保管事実証明書が交付されます。(保管がないときは保管がない旨の証明書が交付されます。)
全国どこの法務局に対しても請求できます。
保管されていたときは、遺言書の閲覧の請求をしたり、遺言書情報証明書の交付を受け遺言書の内容を確認しましょう。
| 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 1通 800円 |
遺言書情報証明書の交付請求
自分に関係のある遺言書があることが判明した相続人などは、法務局で保管されている遺言書の内容を証明する証明書の交付を受けることができます。もちろん、遺言者が死亡したあとしか請求はできません。
この証明書には、誰がいつ作った遺言書か、関係者は誰か、そして遺言書の内容の写しなどが記載されています。
遺言書原本は法務局から外へ持ち出すことができないので、名義変更などの相続手続きはこの証明書を使って行います。
全国どこの法務局に対しても請求できます。
相続人らの誰かが遺言書情報証明書の交付を受けると、その他の相続人などに対して法務局から遺言書を保管している旨の通知が送られます。
遺言書情報証明書の例(PDF 1.3MB)(引用:法務局 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00026.html)
| 遺言書情報証明書の交付請求 | 1通1,400円 |
遺言書の閲覧の請求
遺言者がまだ生きている間は、遺言者本人のみしかできませんが、遺言者が死亡したあと(相続発生後)であれば、相続人などもすることができます。
誰かが閲覧をすると、その他の相続人などに対しても法務局から遺言書を保管している旨の通知が送られます。
原本を保管している法務局においては原本の閲覧をすることができますし、それ以外の法務局であってもスキャンされた遺言書をデータとして閲覧することができます。
| 遺言書の閲覧(原本)の手数料 | 1回1,700円 |
| 遺言書の閲覧(データ)の手数料 | 1回1,400円 |
相続人などの誰かが遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合には、その他の相続人などの関係者に対して法務局から遺言書が保管されている旨の通知が送られます。
自分に関係のある相続が発生したということですので遺言書の閲覧の請求や、遺言書情報証明書の交付を受けましょう。
決して放置してはいけません。
また、今後はこんな通知が来ることがあるということも予め覚えておくといいですね。
| 遺言書の保管の申請 | 1通3,900円 |
| 遺言書の閲覧(原本) | 1回1,700円 |
| 遺言書の閲覧(データ) | 1回1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書の交付 | 1通 800円 |
| 遺言書情報証明書の交付 | 1通1,400円 |
| 遺言書の保管の申請の撤回 遺言書の変更の届出 |
かかりません |
大きく分けて2つあります。遺言書が成立するための法律要件を満たしているかと、保管制度を利用するための要件を満たしているかです。
① 遺言書が成立するための法律要件を満たしているか
本文自筆、日付、署名、捺印などです。
② 保管制度を利用するための要件を満たしているか
A4サイズ、余白があるか、長期間の保存に耐えられるものであるかなどです。
こちらの注意事項を参考にしてみてください。(引用:法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」5,6頁)
そんなことはありません。
法務局に預けられるようになったのであり、法務局に預けなくても構いませんし、預けた遺言書が自筆証書遺言であることも変わりありません。
法務省からは推奨されていません。
原本の閲覧をすれば色分けされていることが判別できますが、遺言書の執行をする際に用いる遺言書事項証明書は白黒で印刷されてしまいます。したがって色分けすることは推奨されていません。
保管できますが、注意が必要です。
保管の申請をする際には、封印がないもの(封筒に入っていないもの)が必要です。また、A4サイズであることや余白があることなどが要求されますので、要件に沿っているのか確認が必要です。
必ず予約をしてから訪問してください。
保管の申請のみならず他の手続きにおいても予約が必要です。事前に連絡をしておけばスムーズに手続きが進められます。
また、予約の受付は令和2年7月1日から予定されています。(令和2年4月20日現在)
収入印紙です。(現金や収入証紙ではありません。)
法務局の窓口か、近くの郵便局等でお求めになれます。
特に支障がない限り、伝えておくことをお勧めします。
自筆証書遺言で心配なことは死後遺言書が発見されないことでしたが、この制度を利用すればそんなことはありません。法務局へ預けてあることを伝えておくほうがスムーズに手続きを進めることができます。
また、預けた際には保管証が交付されますので、お手元においておくことで相続人らが発見しやすくなります。
大丈夫です。
保管証の再発行はできませんが、失くしてしまっても手続きをすることができます。
保管の申請の撤回によって返却してもらうことができますし、何度も書き換えることができます。
内容を変更するには概ね次のような方法があります。
① 保管の申請の撤回をし、新しい遺言書の保管の申請をする。
② 保管の申請の撤回をせずに、新しい遺言書の保管の申請をする。
③ 保管の申請の撤回をせずに、新しい遺言書を手元に作っておく。(保管の申請はしない。)
どの方法でも可能ですが、個人的には①をお勧めします。また、保管の申請をするたびに手数料がかかりますので注意しましょう。
遺言書の保管の申請の撤回は、法務局に預けた遺言書を返却してもらうだけのものです。
返却を受けただけでは自筆証書遺言としての効力が残り続けます。
遺言書そのものの効力を失わせたいのであれば、その旨の新しい遺言をする、又は破り捨てるなど物理的に破棄することが必要です。
遺言書が複数存在していても法的には問題ありませんが、要らぬ争いを招くおそれがあります。要らなくなった遺言書は破棄することをお勧めします。
基本的にはお近くの法務局でできるほか、郵送や法定代理人によってもすることができます。詳しくは窓口へお問い合わせください。
| 保管されている法務局でしかできないもの | 全国どの法務局でもできるもの |
| 保管の申請 保管の申請の撤回 遺言書の閲覧(原本) |
遺言書の閲覧(データ) 遺言書保管事実証明書の交付 遺言書情報証明書の交付 |
また、保管の申請をすることができる法務局は次のいずれかです。
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
(誤記があったので訂正しました。(令和2年5月12日))
できません。
保管の申請には本人が窓口へ出向くことが必要です。しかし、お身体が不自由な際などに同伴者がいることは問題ありません。
できません。
例え家族(相続人や関係者など)であっても申請の撤回の手続きはできませんし、遺言者が亡くなったあとは遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求で内容を確認することになります。