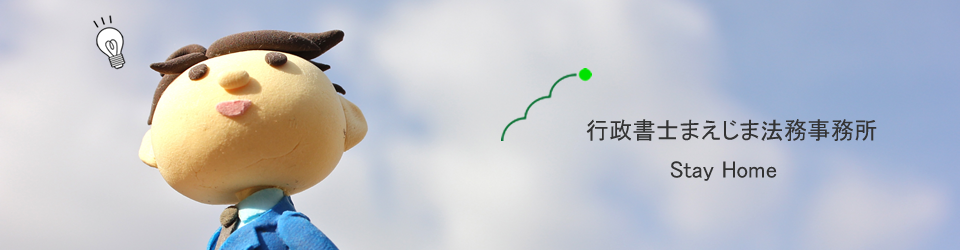



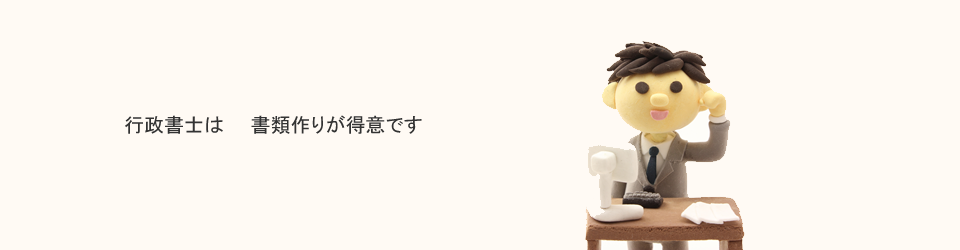

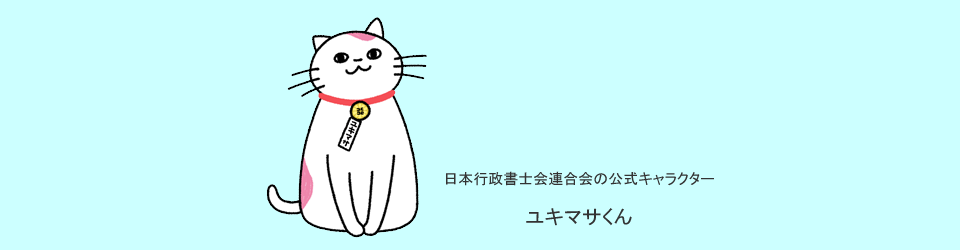
富士、富士宮、静岡東部の遺言相続のことなら
ご相談・来所の際はご予約下さい。時間外でも可能な限り対応します。
090−3933−0099 受付:9〜19時 休日:土日祝日
遺言や相続に関する一問一答のコーナーです。
よくある質問、疑問についてお答えしていきます。クリックすると解説がでてきます。
15歳以上の人であれば誰でも、いつでも自由にすることができます。しないことも自由です。また、いつでも撤回することができます。
法律で定められた方式に従って作らなければなりません。その方式を満たしていない場合、残念ながら遺言としての効力が認められないことになります。
無効となった遺言には法的な効果は発生しません。意味があるとすれば、ご本人の最後の気持ちとしてご遺族が大切に扱ってくれるかもしれない…程度のものです。
やはり大切なのは効力のある遺言を残すことです。
大きく分けて、普通方式と特別方式があります。
普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、特別方式には「危急時遺言」「隔絶地遺言」があります。
遺言者ご本人が、お一人で作成する方式の遺言書です。その要件は以下の通りです。
長所としては、もっとも簡単で手軽であること、費用の掛からない方式であること、遺言の内容や存在を秘密にできること、いつでも作り直しや訂正ができることなどがあげられます。
短所としては、変造・偽造・紛失・滅失の危険があること、発見が遅れる又は発見されないおそれがあること、方式の不備・言葉の解釈で問題になるおそれがあることなどがあげられます。
公証人と証人の立会いのもとで行われる方式で、原本が公証役場に保管されます。その要件は以下の通りです。
長所としては、方式の不備や言葉の解釈による問題が少ないこと、変造・偽造・紛失の危険性がないこと、公証役場の遺言検索システムによって容易に探すことができること、検認手続きが不要なこと、文字を書くことができない人でも作成できることなどがあります。
短所としては、手続きが多少面倒であること、費用が掛かること、証人を用意しなければならないこと、内容を他人に知られてしまうことなどがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあるような方式です。その要件は以下の通りです。
ポイントは、自筆証書遺言とは違い、署名さえ自書できれば他は代筆でもパソコンで作成しても良いところです。また、秘密証書遺言としての要件を備えていなかったとしても、自筆証書遺言の要件を備えていた場合には自筆証書遺言として有効なものになります。
長所としては、遺言書の存在を明らかにしながら内容を秘密にできること、自書できない人でもすることができることなどがあげられます。
短所としては、内容について公証人が関わらないために方式の不備や言葉の解釈による問題が起きるおそれがあること、公証役場に原本が保管されるわけではないので紛失や未発見のおそれがあることなどがあげられます。
それぞれの特徴を表にまとめてみました。
| 方式 | 手軽さ | 作成費用 | 存在の 秘密性 |
内容の 秘密性 |
偽造・変造 紛失・滅失 |
発見の されやすさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 公正証書遺言 | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 秘密証書遺言 | △ | △ | × | ○ | × | △ |
保管上注意すべき点といえば、やはり遺言の偽造・変造・紛失・滅失についてです。当然厳重に管理したほうがよいのですが、厳重に管理しすぎて未発見に終わることがないようにも注意しなければなりません。さらに、発見者による隠匿(隠されること)にも注意が必要です。考えてみると遺言はその保存方法がとても難しいものなのです。
遺言書の保管方法はご本人の自由ですが、オススメしたいのは、利害関係のない公正な第三者に依頼する方法です。われわれ行政書士や弁護士、遺言執行者や友人・知人などです。この場合、ご本人が亡くなったことを保管者に通知する方法についても合わせて検討しておきます。
ご自身で保管するならば、厳重に管理しつつ、やはりその存在をご家族に知らせておくことや、分かりやすい場所にメモを残しておくことなどがよいでしょう。
公正証書遺言については、公証役場に原本が保管されているので偽造や変造のおそれがなく、遺言検索システムを使って探し出すことも容易です。よって元々安全に保管されていることになります。
遺言書は大事な書類ですし、ご家族の立場からも内容について早く確認したいというお気持ちがあるかもしれません。しかし、公正証書遺言以外の遺言書を開封するには家庭裁判所において検認手続きを経なければなりません。封がされていな遺言の場合にも同様に検認の申し立てをする必要があります。
検認手続きを経ずに開封したり、その遺言内容を執行した場合には5万円以下の過料に処されます。
検認とは、公正証書遺言以外の遺言書を発見したときに、家庭裁判所において遺言書の状態などを調査し確定させるものです。検認を経ることにより、その後の偽造や変造を防ぐことができます。
勘違いされがちなのは、その状態を確定される手続きであって、遺言書に書かれている内容についての有効性を判断するような手続きではないということです。また、検認を経なかったことにより遺言が無効になるようなこともありませんが、怠った場合には5万円以下の過料に処されます。その後の相続手続きにおいても検認がされていない遺言書をもって所有権移転登記などをすることはできません。
なお、公正証書遺言の場合に検認手続きが不要とされている理由は、公証人が関与し厳格に作成されていること、そもそも原本が公証役場に存在することなどから、検証する必要がないからです。