松陰寺の境内に良寛の書の碑とその内容を解説した案内板 が建っており、その時はたいして気にならなかったが、良寛の経歴を調べて行くうちになんで白隠と良寛の接点があるのか興味が湧く。白隠は1625~1768良寛は1758~1831で白隠がなくなった年には良寛は11歳ほど。直接の交流はなさそう。

気になる歌人/歌 |
このページは何気なく目にした歌のなかからいろいろと詮索したくなる歌人を取り上げ、メモした内容のあくまでも私個人の記録です。
気になる歌人の生い立ち、生き方などを調べ、気に入った歌を載せていこうと思います。例えば「西行」についてインターネット検索すると、相当の情報が得られます。学者でも専門家でもないので自分で理解できる程度のことで、簡単なメモ程度のことで充分かと。あくまで自分の気になる歌、好きな歌 百人一首からも気に入った歌を選んで載せていこうかと。ボチボチ気の付いたことから進めてみます。
参考のコーナー ||万葉集||古今集||神代の時代||新古今集||
||若山牧水||石川啄木||斉藤茂吉||北原白秋||折口信夫||与謝野晶子||正岡子規||伊藤左千夫||島木赤彦||
||柿本人麻呂 ||高市 黒人||山部赤人||大伴家持||在原業平||紀貫之||壬生忠岑||和泉式部||式子内親王||
||源 経信||源俊頼||西行||藤原定家||寂蓮||源実朝||小沢蘆庵||良寛||香川景樹||橘曙覧||
| 佐藤 義清(さとう のりきよ)。 平清盛と同年 |
元永元年(1118年) - 文治6年2月16日(1190年3月23日) |
| 生涯(抜粋) | 秀郷流武家藤原氏の出自で、藤原秀郷の9代目の子孫。佐藤氏は義清の曽祖父公清の代より称し、家系は代々衛府に仕える 16歳ごろから徳大寺家に仕え、この縁で後にもと主家の実能や公能と親交を結ぶこととなる。保延元年(1135年)18歳で左兵衛尉(左兵衛府の第三等官)に任ぜられ、同3年(1137年)鳥羽院の北面武士としても奉仕していたことが記録に残る。和歌と故実に通じた人物として知られていたが、同6年(1140年)23歳で出家して円位を名のり、後に西行とも称した。 出家直後は鞍馬などの京都北麓に隠棲し、天養初年(1144年)ごろ奥羽地方へはじめての旅行。(27歳) 久安4年(1149年)前後に高野山(和歌山県高野町)に入り、仁安3年(1168年)に中四国への旅を行った。 文治2年(1186年)(69歳)に東大寺勧進のため二度目の奥州下りを行い、伊勢に数年住ったあと河内弘川寺(大阪府河南町)に庵居。建久元年(1190年)にこの地で入寂した。 かつて「願はくは花の下にて春死なん、そのきさらぎの望月のころ」と詠んだ願いに違わなかったとして、その生きざまが藤原定家や僧慈円の感動と共感を呼び当時名声を博した。 |
| 歴史の勉強ではないが、NHK大河ドラマ「平の清盛」及び源氏の時代へと動乱の時代はややこしく,把握しておかなければならない。 | 保元の乱、平治の乱で平家の世になり、その後「源 頼朝」の鎌倉幕府までの経緯など、飛鳥、奈良、平安時代の勉強が、西行を理解するうえで必要になってきた。 弘法大師と西行の関係も知る必要が。近場の「修禅寺」も弘法大師が開祖で、「独鈷の湯」は弘法大師が掘り当てているらしい。 空海の生涯を読んでみたのですが、出生からして神がかり的なこともあり、何処までが本当か疑問な点もある。当時の歴史と仏教とは切り離して考えることは出来ない。少し勉強してみたい気がする。 |
| 歌に対する心のあり方は | 1189年(71歳)、西行は京都高尾の神護寺へ登山する道すがら、まだ少年だった明恵上人に、西行自身がたどり着いた集大成ともいえる和歌観を語っている。「歌は即ち如来(仏)の真の姿なり、されば一首詠んでは一体の仏像を彫り上げる思い、秘密の真言を唱える思いだ」。 「和歌はうるはしく詠むべきなり。古今集の風体を本として詠むべし。中にも雑の部を常に見るべし。但し古今にも受けられぬ体の歌少々あり。古今の歌なればとてその体をば詠ずべからず。心にも付けて優におぼえん其の風体の風理を詠むべし」・・・古今集について調べてみよう 「和歌はつねに心澄むゆゑに悪念なくて、後世(ごせ)を思ふもその心をすすむるなり」(『西行上人談抄』)。 |
「もののふの里 葛山」 のページで紹介している「景ヶ島にある依京寺」は空海が開祖らしい。そこに西行の手植えの松と歌があり空海と西行とのかかわりがある。
依京寺の案内板に(依京寺にある景ヶ島之図にはお手植えの松が描かれている)
ひさたえて 我が後の世を 問へよ松 あとしのぶべき 人もなき身を
某HPより
弘法大師ゆかりの地に庵を結び、西行は自然に親しみをこめて呼びかける。讃岐国善通寺にて
久にへて我が後の世を とへよ松 跡したふべき 人もなき身ぞ
以上同じ歌だが、はたしてこの歌は依京寺の手植えの松を読んだのだろうか。疑問
平成24年2月3日記
最近、東海地震と連動して富士山が噴火するとか、言われ始めています。この頃(冬)の富士山は意図してみなくても毎日目にすることの出来る時期です。私の歌の中にもついつい富士山を入れてしまいます。西行はどんな富士を詠んでいるか気になり、そこで富士を詠んだ歌をネットで検索してみました。
注釈 「よだけき」 仰々しい、おおげさ 「たけき」 猛々しい 「するが 」は恋をする と駿河を掛けている。
富士山は煙を吐いていたんだ。掛詞にする場合、ひらがなで書くのかな。
この歌の解釈は以下の様らしい。
某HPより
「この明澄でなだらかな調べこそ、西行が一生をかけて到達せんと した境地であり、ここにおいて自然と人生は完全な調和を形づくる。万葉集の山部赤人の富士の歌と比べてみるがいい。その大きさと美しさにおいて何の遜色もないばかりか、万葉集以来、脈々と生きつづけたやまと歌の魂の軌跡をそこに見る思いがする。」
(新潮社版 白州正子氏著「西行」から抜粋)
「東海の広大な眺望にふり仰いだ富士の頂から立ちのぼって大空にかすれ消えてゆく噴煙のさまは万感に満ちた西行の胸郭を解放したにちがいない。「行方も知らぬ」は、富士の煙であるのとともに西行の胸に湧いては消え消えては湧くといった、とどまることのない思念であって、それは来し方行く方を自分自身に対しても問うのである。」
(河出書房新社刊 宮柊二氏著「西行の歌」から抜粋)
この境地は次の歌にも、見受けられます
某HPより
「俊成が千載集に採らなかった理由は何か。思うに、彼は下句のこの景を賞しつつも、作者自身の意識や姿勢をあからさまに表明したこの上句に対して、反撥めいたものを感じたのではないであろうか。(中略)上句は・・・説明的である。・・・いはば押し付けのようなものが感じられる。(中略)西行にとっては、どうしてもこのように自己の心情を説明しないことにはすまなかったのであろう。彼にとっては風景の描写は(鴫立つ澤の秋の夕暮)という下句だけで十分なのであって、問題はそれに向う(心なき身)である自身の(心)にあったのだろう。
(久保田淳氏著「山家集入門」から抜粋)
「鴫」 ”しぎ”と読むらしい 「心なき」が自分ではどう解釈していいか迷う所です。某注釈では・・・「物の情趣を解さない身」「煩悩を去った無心の身」の二通りの解釈に大別できよう。前者と解すれば出家の身にかかわりなく謙辞の意が強くなる。
辞世の歌かと思ったらなくなる10年前のものらしい。当時の人は「如月の望月」でお釈迦様の亡くなった日が連想されるのか。
(牧水)聞きゐつつ たのしくもあるか 松風の 今は夢とも うつつともきこゆ
の歌をついつい思い出す。
来世では心のなかにあらわそう 満足いかないままでたえてしまった月の光を
「願はくは」と「来む世には」の二首は
『御裳濯河歌合』の七番に載せられている。
『御裳濯河歌合』は歌合の形態をとった西行の自撰歌集である。
西行が晩年期に撰んだ歌のなかにこれら二首が並んである。
(「来む世には」の)一首で西行は、
この世で存在的にとらえていた月を、
来世では「心の中にあらわす」、すなわち心に月を宿らすこと、
内面的に月をとらえて、月による心的境地を築きあげよう
という月輪観の深い希求をあらわしているのである。
西行の歌の本質は やはり以下の様らしい
生きていく人間の心、このわかりづらく、どうにもとらえ難いものを生涯にわたって追求し、それを歌にした。そこに西行の傑出した歌人としての特異さがあり、その歌は古びず、今に至るまで多くの人に追慕され、愛されている
鈴鹿山うき世をよそにふり捨てて いかになりゆくわが身なるらむ
うき世を振り捨てて今こうやって鈴鹿山を越えていって いるが、このわが身は一体どうなってしまうのだろうか
西行出家の動機は色々臆されている。平成24年NHK平清盛ドラマでは歌会などを通して仲を深めた鳥羽院の妃・待賢門院(崇徳天皇の母)と一夜の契りを交わしたが、それを詮索され妻子と別れて出家したことになっていた。その時の歌も紹介されていた。
<内容>出家した人は悟りや救いを求めており本当に世を捨てたとは言えない。出家しない人こそ自分を捨てているのだ
何か問答集みたいな歌である。
出家後小倉山、鞍馬山、吉野山、高野山(ここに三十年、真言霊場)弘川寺(ひろかわでら)で没(行基、空海もこの寺で修行)
出来たら以上の場所を歩いてみたい。西行は空海の何かを求めていたように思えるのだが。空海とはどんな人かあらためて調べてみます。
弘川寺を調べると・・・
役小角によって創建されたと伝えられ、676年にはこの寺で祈雨法が修せられて天武天皇から山寺号が与えられたという。平安時代の弘仁3年(812年)空海によって中興され、文治4年(1188年)には空寂が後鳥羽天皇の病気平癒を祈願している。翌、文治5年(1189年)には空寂を慕って歌人と知られる西行法師がこの寺を訪れ、この地で没している。・・・西行は空寂を慕ってこの寺を訪れたとある 空海ではないようだが。400年余のスパンがあるからか。
空寂とは 万物はみな実体のないものであり、生死もまた仮のものであるということ。 執着・欲望などの煩悩(ぼんのう)を消し去った悟りの境地。
えらい名前の坊さんのようです。西行の出家はやはり悟りを目指したものでは、そして空海の信ずる仏門に向かい、その中で歌を詠むことにより己を表現したのでは。そうすれば西行の歌を詠む姿勢、歌自体に空寂を求めているのが解かり納得できます。この結論はあまりにも単純かな。も少し調べていきます。
新古今和歌の最期の歌(1979)は西行の歌で終わっている。新古今和歌集の月に絡んだ歌が多く、ここに抜粋してみました。花(桜)に関する歌も多く、それもおいおいここに取り上げてみようかと思います。
煩悩の闇も晴れ、心の中には清浄な真如の月が宿っていることを自覚した西行法師の自信が表現されているのである。その上で、西方浄土に極楽往生というゆるぎなき自己完成の姿を見ているのである。次の歌と比較しても、その辺の心境の変化がうかがえる
来む世には 心のうちにあらはさむ あかでやみぬる 月の光を
以下に月の入った歌を列挙しました。各々の歌の背景、詞書がなければ歌の本当の意味は解らないことを西行の歌を詠むにつけつくづく思いました。
570 月を待つたかねの雲は晴れにけり こころあるべき初時雨かな
603 をぐら山ふもとの里に木の葉散れば 梢に晴るる月を見るかな
885 君いなば月待つとてもながめやらむ 東のかたの夕暮れの空
937 都にて月をあはれと思ひしは 数にもあらぬすさびなりけり
938 月見ばと契りおきてしふるさとの 人もや今宵袖ぬらすらむ
1185 おもかげの忘らるまじきわかれかな なごりを人の月にとどめて
1267 月のみやうはの空なる形見にて 思ひも出ではこころ通はむ
1268 隈もなき折りしも人を思ひ出でて こころと月をやつしつるかな
1269 物思ひて眺むる頃の月の色に いかばかりなるあはれ添ふらむ
1530 月を見て心うかれしいにしへの 秋にもさらにめぐり逢ひぬる
1631 山かげに住まぬ心はいかなれや 惜しまれて入る月もある世に
1680 これや見し昔住みけむ跡ならむ よもぎが露に月のかかれる
1779 月のゆく山に心を送り入れて やみなる跡の身をいかにせむ
1845 ねがはくは花のもとにて春死なむ その如月の望月のころ
1878 神路山月さやかなる誓ありて 天の下をば照らすなりけり
1879 さやかなる鷲の高嶺の雲井より 影やはらぐる月よみの森
追 以下某ホームページより
年たけてまたこゆべしと思ひきや 命なりけり小夜の中山
こんなに年老いて、この小夜の中山を再び 越えることができると思っただろうかそれなのに今またこうして小夜の中山を越えようとは、まことに命があるおかげであるよ。
この歌には、三十前後の初度の陸奥の旅と、今回 の六十九歳という高齢での再度の旅、その二つが、 久しい時間を経て、一つに把握され、自己が自然に
とりこまれ、自然と一体化した安らかさが感じられ 、人生的な深い味わいのある作品となっている。
さやのなかやま(小夜の中山) 遠見国の歌枕。現在の静岡県掛川市にある峠。 箱根とともに東海道の難所の一つである。
「風になびくーーー」と「年たけてーーー」の二首 を「自然と人間とを一如に観じる宗教的に至り得た 境地」「求めてやまない求道心と文学的資質とが 一つになっていて観念的に割り切れず生きつづけて いる人間の声」。さらにこの歌 は「西行の文学を象徴する意味をもち」「いかにも 健康的で明るいことである。老いの艶という味わい が濃厚である。それが深さをもっている」と言う
[没]建仁2(1202).7.20. 京都
平安時代末期~鎌倉時代初期の歌人。僧俊海の子。俗名,藤原定長。伯父の藤原俊成の養子となり,官は中務少輔となったが,応保2 (1162) 年定家が誕生したので家督を譲って出家し,寂蓮と称した。以後歌道に専念し,和歌所寄人となり,『新古今和歌集』の撰者にもなった。勅撰集に
117首入集。能書家という伝称はないが,書は江戸時代に古筆として愛好され,切目王子社,滝尻王子社などで詠んだ『熊野懐紙』や消息が現存する。このほか『右衛門切』『元暦校本万葉集巻六』『西本願寺三十六人集兼輔集』『田歌切』など,寂蓮筆と伝称される書跡があるが確証はない。家集『寂蓮法師集』。
「風体あてやかにうつくしきさまなり。よわき所やあらむ。小野小町が跡をおもへるにや。美女のなやめるをみる心ちこそすれ」(歌仙落書)。
「寂蓮は、なほざりならず歌詠みし者なり。あまり案じくだきし程に、たけなどぞいたくは高くはなかりしかども、いざたけある歌詠まむとて、『龍田の奥にかかる白雲』と三躰の歌に詠みたりし、恐ろしかりき。折につけて、きと歌詠み、連歌し、ないし狂歌までも、にはかの事に、故あるやうに詠みし方、真実の堪能と見えき」(後鳥羽院御口伝)。
以上が寂蓮の評価の参考になる。新古今和歌集から抜粋してみる。
今はとてたのむの雁もうちわびぬ朧月夜の明けぼのの空(新古58)
通釈】今はもう北の国へ帰らなければならない時だというので、田んぼにいる雁も歎いて鳴いたのだ。朧ろ月の春の夜が明けようとする、曙の空を眺めて…。
【通釈】葛城の高間山の桜が咲いたのだった。竜田山の奧の方に、白雲がかかっているのが見える。
思ひたつ鳥はふる巣もたのむらんなれぬる花のあとの夕暮(新古154)
【通釈】谷へ帰ろうと思い立った鶯は、昔なじみの巣をあてにできるだろう。馴れ親しんだ花が散ってしまったあとの夕暮――。しかし家を捨てた私は、花のほかに身を寄せる場所もなく、ただ途方に暮れるばかりだ。
散りにけりあはれうらみの誰なれば花の跡とふ春の山風(新古155)
【通釈】桜は散ってしまったよ。ああ、この恨みを誰のせいにしようとして、花の亡き跡を訪れるのだ、山から吹く春風は。花を散らしたのは、ほかならぬお前ではないか、春風よ。
暮れてゆく春の湊はしらねども霞におつる宇治の柴舟(新古169)
【通釈】過ぎ去ってゆく春という季節がどこに行き着くのか、それは知らないけれども、柴を積んだ舟は、霞のなか宇治川を下ってゆく。
さびしさはその色としもなかりけり槙立つ山の秋の夕暮(新古361)
【通釈】なにが寂しいと言って、目に見えてどこがどうというわけでもないのだった。杉檜が茂り立つ山の、秋の夕暮よ。
月はなほもらぬ木の間も住吉の松をつくして秋風ぞ吹く(新古396)
通釈】住吉の浜の松林の下にいると、月は出たのに、繁り合う松の梢に遮られて、相変わらず光は木の間を漏れてこない。ただ、すべての松の樹を響かせて秋風が吹いてゆくだけだ。
【通釈】私が庵を結んでいる深山に、今宵、あわれ深い鹿の声が響いてくる。先日野分が吹いて、草原の寝床が荒れ果ててしまったのだ。
物思ふ袖より露やならひけむ秋風吹けばたへぬものとは(新古469)
【通釈】物思いに涙を流す人の袖から学んだのだろうか、露は、秋風が吹けば堪えきれずに散るものだと。
ひとめ見し野辺のけしきはうら枯れて露のよすがにやどる月かな(新古488)
【通釈】このあいだ来た時は人がいて、野の花を愛でていた野辺なのだが、秋も深まった今宵来てみると、その有様といえば、草木はうら枯れて、葉の上に置いた露に身を寄せるように、月の光が宿っているばかりだ。
むら雨の露もまだひぬ槙の葉に霧立ちのぼる秋の夕暮(新古491)
【通釈】秋の夕暮、俄雨が通り過ぎていったあと、その露もまだ乾かない針葉樹の葉群に、霧がたちのぼってゆく
かささぎの雲のかけはし秋暮れて夜半には霜やさえわたるらむ(新古522)
【通釈】カササギが列なって天の川に渡すという空の橋――秋も終り近くなった今、夜になれば霜が降りて、すっかり冷え冷えとしているだろうなあ。
たえだえに里わく月の光かな時雨をおくる夜はのむら雲(新古599)
【通釈】月の光が、途切れ途切れに里の明暗を分けているなあ。時雨を運び地に降らせる、夜半の叢雲の間から、月の光が射して。
ふりそむる今朝だに人の待たれつる深山の里の雪の夕暮(新古663)
【通釈】雪が降り始めた今朝でさえ、やはり人の訪問が待たれたよ。今、山奥の里の夕暮、雪は深く降り積もり、いっそう人恋しくなった。この雪では、誰も訪ねてなど来るまいけれど。
老の波こえける身こそあはれなれ今年も今は末の松山(新古705)
【通釈】寄る年波を越え、老いてしまった我が身があわれだ。今年も歳末になり、「末の松山波も越えなむ」と言うが、このうえまた一年を越えてゆくのだ。
思ひあれば袖に蛍をつつみても言はばや物をとふ人はなし(新古1032)
【通釈】昔の歌にあるように、袖に蛍を包んでも、その光は漏れてしまうもの。私の中にも恋の火が燃えているので、胸に包んだ想いを口に出して伝えたいのだ。この気持ちを尋ねてくれる人などいないのだから。
ありとても逢はぬためしの名取川くちだにはてね瀬々の埋れ木(新古1118)
【通釈】生きていても、思いを遂げられない例として浮き名を立てるだけだ。名取川のあちこちの瀬に沈んでいる埋れ木のように、このままひっそりと朽ち果ててしまえ。
うらみわび待たじ今はの身なれども思ひなれにし夕暮の空(新古1302)
【通釈】あの人のつれなさを恨み、嘆いて、今はもう待つまいと思う我が身だけれど、夕暮れになると、空を眺めて待つことに馴れきってしまった。
里は荒れぬ空しき床のあたりまで身はならはしの秋風ぞ吹く(新古1312)
【通釈】あの人の訪れがさっぱり絶えて、里の我が家は荒れ果ててしまった。むなしく独り寝する床のあたりまで、壁の隙間から秋風が吹き込んで来る――身体の馴れ次第では、気にもならないほどの隙間風が…。
涙川身もうきぬべき寝覚かなはかなき夢の名残ばかりに(新古1386)
【通釈】恋しい人を夢に見て、途中で目が覚めた。その儚い名残惜しさに、川のように涙を流し、身体は床の上に浮いてしまいそうだ。なんて辛い寝覚だろう。
高砂の松も昔になりぬべしなほ行末は秋の夜の月(新古740)
【通釈】高砂の老松も、いつかは枯れて昔の思い出になってしまうだろう。その後なお、将来にわたって友とすべきは、秋の夜の月だ。
尋ねきていかにあはれと眺むらん跡なき山の嶺のしら雲(新古836)
【通釈】遠く高野までたずねて来て、どんなに悲しい思いで山の景色を眺めておられることでしょう。亡き兄上は煙となって空に消え、ただ山の峰には白雲がかかっているばかりです。
立ち出でてつま木折り来し片岡のふかき山路となりにけるかな(新古1634)
【通釈】庵を立ち出ては薪を折って来た丘は、住み始めた頃に比べると、すっかり木深い山道になったものだ。
数ならぬ身はなき物になしはてつ誰ためにかは世をも恨みむ(新古1838)
【通釈】物の数にも入らない我が身は、この世に存在しないものとして棄て果てた。今はもう、誰のために世を恨んだりするだろうか。
紫の雲路にさそふ琴の音にうき世をはらふ嶺の松風(新古1937)
【通釈】浮世の迷妄の雲を払う峰の松風が吹き、紫雲たなびく天上の道を極楽浄土へと誘う琴の音が響きあう。
これや此のうき世のほかの春ならむ花のとぼそのあけぼのの空(新古1938)
【通釈】これこそが、現世とは別世界にあると聞いていた極楽の春なのだろう。美しい浄土の扉を開くと、曙の空に蓮華の花が咲き満ちている。
以上の歌を通して 月や空や風や雲など一つのパターンで謡われている。歌の状況は解らぬが
僧侶からの視点からか、日々の景色や気候の変化を敏感に、あの世に通じる気持ち、この世のはかなさなどが多く見受けられる。生きとし生けるものの諸行無常か?西行に非常に近い歌い方。
参考にしたい。
平成29年11月 記
色々と昔の歌人を調べれば、一人欠けていた気がする。僧侶の歌はなんとなく把握できた気がするが、宮廷歌人の心など知らねばと和泉式部、式子内親王の女流歌人は以前終わったが公家の一人として藤原定家を調べる必要もありそうだ。ここに簡単にまとめてみました。・・・2017/11/6寂蓮の歌を整理。(ウイキペデイアを主に)
応保2年(1162年)生誕 仁治2年8月20日(1241年9月26日死没
藤原北家御子左流で藤原俊成の二男。最終官位は正二位権中納言。京極殿または京極中納言と呼ばれた。法名は明静(みょうじょう)。歌人の寂蓮は従兄、太政大臣の西園寺公経は義弟にあたる。
平安時代末期から鎌倉時代初期という激動期を生き、御子左家の歌道における支配的地位を確立。日本の代表的な歌道の宗匠として永く仰がれてきた歴史がある。
2つの勅撰集、『新古今和歌集』、『新勅撰和歌集』を撰進。ほかにも秀歌撰に『定家八代抄』がある。歌論書に『毎月抄』『近代秀歌』『詠歌大概』があり、本歌取りなどの技法や心と詞との関わりを論じている。
人物
「美の使徒」、「美の鬼」、「歌聖」、「日本最初の近代詩人」などと呼ばれることがある日本を代表する詩人の一人。美への執念は百人一首の選歌に見られるように晩年まで衰えることがなかった。
玉葉によると文治元年11月に少将雅行と言い争い、脂燭(ししょく)で相手を打ち除籍となり、古今著聞集によると父俊成から和歌によって取りなして貰い、後鳥羽天皇から許しを得たとあるほど気性が激しく、また後鳥羽院御口伝によると「さしも殊勝なりし父の詠をだにもあさ/\と思ひたりし上は、ましてや余人の歌沙汰にも及ばず」、「傍若無人、理(ことわり)も過ぎたりき。他人の詞(ことば)を聞くに及ばず」と他人の和歌を軽んじ、他人の言葉を聞き入れない強情さを指摘されている。また、どんなに後鳥羽院が褒めても、自詠の左近の桜の述懐の歌が自分では気に入らないからと、新古今に入撰することに頑強に反対するなど、折り紙付きの強情な性格だった。順徳天皇歌壇の重鎮として用いられるも、承久二年の内裏歌会への出詠歌が後鳥羽院の勅勘を受け、謹慎を命じられた。しかし、この謹慎の間、さまざまな書物を書写した結果、多くの平安文学が後世に残ったと言える。
歌風 (定家の和歌の性格について風巻景次郎著『新古今時代』の「『拾遺愚草』成立の考察」に要約より)
定家は平安朝生活の伝統を多分に承け、それにふさわしく繊細な神経で夢の世界を馳せ、その天性によって唯美的な夢の文学を完成した。しかし表現せんとするものが縹渺(ひょうびょう)として遥かであるほど、それを生かすには辞句の選択、着想の考案のために心を用いることは大でなければならぬ。そして定家はそれに耐えるほどの俊敏な頭脳をもっていた。かれの歌の成功はこの頭脳の力にある。しかしまた、その失敗も頭脳のためであった。かれの歌の大半は、優艶なる夢をいかにして表現しようかと努力した理知の影を留め、その表現のために尽くした努力はその措辞(そじ)の上に歴々として現れた。かれはじつに夢の詩人で、理知の詩人で、そして言葉の詩人であった。
「定家美(妖艶)のなかには、多くの非正常的・怪奇的なものがある。あまりに華麗幻燿にすぎて、人を誑(たぶら)かさずにはおかないこと、つよい阿片性・麻薬性があって、人を麻痺、昏酔させる毒性をもつこと、あまりにつよい性欲性・獣性があって、人を頽廃・好婬に誘わずにおかないこと、つよい幽鬼性・悪魔性があって、人を悪魔的世界に誘おうとすること、死や亡びのもつ非生命性・空無性・滅亡性等に美を感じさせ、死や亡びのなかに投身させようとする性質をもつこと等々がそれである」。
谷山茂は以下のように指摘
「定家が恋歌を最も得意としたということは、彼を知る上で極めて重要な事実である。「定家などは智慧の力をもってつくる歌作り也」(『井蛙抄』)と自認していたというが、その智巧的態度に立って、幻想世界を縦横に描き出そうとする定家にとっては、現実にしばられ易い四季自然歌よりも、智巧(利巧)や空想(そらごと)の恣意を多分に許容される恋歌のほうが得意であったことは、全く当然のことなのである。すなわち、定家ーー少なくとも新古今撰進期における定家をして、恋歌を本領とさせたのは、その恋の体験の深さや広さではなくて、彼の智巧的超現実的な芸術至上主義の魔力的意欲であるというべきである。そういう点では、さすがの俊成も西行も家隆も俊成女(としなりのむすめ)も、遥かに遠く及ばない古今独歩の境地を極めているのである。しかも、そういう行き方が、恋歌からさらに四季自然歌にまで拡充されているのだから、全く驚くべき魔術師である。そして、新古今の歌人たちは、ほとんど例外なく、及ばぬながらにも、多かれ少なかれ、一応はこの道に追従していったのである
春
以上の文面で性格、歌風が見て取れる。実際の歌を取り上げてみる。(新古今和歌集より)
大空は梅のにほひにかすみつつ曇りもはてぬ春の夜の月(新古40)
通釈】広大な空は梅の香に満ちておぼろに霞みながら、すっかり曇りきることもない春の夜の月よ。
梅の花にほひをうつす袖のうへに軒もる月のかげぞあらそふ(新古44)
【通釈】梅の花が匂いを移し染める袖の上に、軒を漏れてくる月影も涙に映って、香りと光が競い合っている。
霜まよふ空にしをれし雁がねの帰るつばさに春雨ぞ降る(新古63)
【通釈】
桜色の庭の春風あともなしとはばぞ人の雪とだに見む(新古134)
通釈】桜の色に染まって吹いた庭の春風は、もはや跡形もない。今や花が地面に散り敷いているだけで、人が訪れたならば、せめて雪とでも見てくれようが。
春の夜の夢の浮橋とだえして峰にわかるる横雲の空(新古38)
【通釈】春の夜の、浮橋のように頼りない夢が、遂に中途で絶えてしまって、空を見遣れば、横に棚引く雲が峰から別れてゆく。
夏
【通釈】あの人が通りすがりの人に託す伝言も絶えて久しい、長く降り続ける五月雨の空よ。
夕暮はいづれの雲のなごりとて花橘に風の吹くらむ(新古247)
【通釈】夕暮れ時になると、庭の花橘に風が吹き、しきりと昔を偲ばせる。一体如何なる雲のなごりを運んで来たというので、これほど昔を懐かしませる香りがするのであろう。
秋
見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮(新古363)
【通釈】あたりを見渡してみると、花も紅葉もないのだった。海辺の苫屋があるばかりの秋の夕暮よ。
さむしろや待つ夜の秋の風ふけて月をかたしく宇治の橋姫(新古420)
【通釈】冷たい莚――そこに臥して待つ夜の秋風は、更けるにつれて吹きつのり、月光を敷いて独り寝する宇治の橋姫よ。
ひとりぬる山鳥の尾のしだり尾に霜おきまよふ床の月影(新古487)
【通釈】独りで寝ている山鳥の尾、その垂れ下がった尾に、霜が置いているのかと迷うばかりに、しらじらと床に射す月影よ。
時わかぬ波さへ色にいづみ川ははその
【通釈】季節によって違いはないはずの波さえ、秋が色に顕れている泉川よ。上流の柞の森に嵐が吹いているらしい。
冬
駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野のわたりの雪の夕暮(新古671)
【通釈】馬を停めて、袖に積もった雪を払う物陰もありはしない。佐野の渡し場の雪降る夕暮どきよ。
待つ人の麓の道はたえぬらむ軒端の杉に雪おもるなり(新古672)
【通釈】待つ人が通って来る麓の道は行き止まりになってしまったのだろう。我が家の軒端の杉に雪が重みを増しているようだ
恋
年もへぬ祈る契りははつせ山をのへの鐘のよその夕暮(新古1142)
【通釈】何年も経った。長谷観音に祈る恋の成就の願掛けは、これ以上続ける甲斐もない。折から山上の鐘が入相を告げるけれど、私にはもはや無縁な夕暮時であるよ。
あぢきなくつらき嵐の声も憂しなど夕暮に待ちならひけむ(新古1196)
【通釈】苦々しくも、激しい嵐の声さえ厭わしい。どうして夕暮に人を待つ習慣ができたのだろう。
帰るさのものとや人のながむらん待つ夜ながらの有明の月(新古1206)
【通釈】よそからの帰り道に眺めるものとして、あの人は今頃この有明の月を眺めているのだろう。私にとっては、あの人の来訪を待つ夜、ずっと眺め続けていた月を――。
忘れずは馴れし袖もや氷るらむ寝ぬ夜の床の霜のさむしろ(新古1291)
【通釈】私から心を移していないのなら、馴れ親しんだあの人の袖も、今頃氷りついているだろうか。眠れずに過ごす夜の寝床、そこに敷いた筵には、いちめんに涙の霜が置いている。
消えわびぬうつろふ人の秋の色に身をこがらしの杜の下露(新古1320)
【通釈】消えようにも消えきれず、苦しんでいたよ。私に飽きて心を移す人の、秋の木の葉の如く変わりゆく有様に、我が身を焦がし――まるで木枯しの森の下露のように。
むせぶとも知らじな心かはら屋に我のみ消たぬ下の煙は(新古1324)
【通釈】私がいくら咽ぼうとも、あの人は知るまいな。瓦屋に消さずにある煙のように、心変わらず、ひそかに燃やす恋情は私ばかりが消さずにいることは。
白妙の袖の別れに露おちて身にしむ色の秋風ぞ吹く(新古1336)
【通釈】差し交わしていた白い袖を引き離して別れる時となり、私の袖には露のようなしずくが落ちて――そこへ身に染みるような秋風が吹きつける。色などないはずなのに、こんなにもあわれ深く身に染みとおる風が。
かきやりしその黒髪のすぢごとにうち臥すほどは面影ぞたつ(新古1390)
【通釈】独り横になる折には、あの人の面影が鮮やかに立ち現われる。我が手で掻きやったその黒髪が、ひとすじごとにくっきり見えるかのように。
たづね見るつらき心の奥の海よ潮干のかたのいふかひもなし(新古1332)
【通釈】探って見る、つれない人の心の奧――それはあたかも遥かな
哀傷
たまゆらの露も涙もとどまらず亡き人こふる宿の秋風(新古788)
【通釈】露も涙も、ほんの一瞬も留まることはない。亡き人を恋しく思い出す宿に吹きつける秋風のために。
旅
こととへよ思ひおきつの浜千鳥なくなく出でし跡の月かげ(新古934)
【通釈】言葉をかけてくれよ。思いを残してやって来たこの興津の浜――ここで悲しげに鳴いている浜千鳥ではないが、私が泣く泣く出て行ったあとの都の空に残っていた月、あの時と同じ月の光よ――。
旅人の袖ふきかへす秋風に夕日さびしき山の
【通釈】旅人の袖をひるがえして吹く秋風――あたかも故郷の方へ人を戻すように吹くその風と共に、夕日が寂しく照らす山の
都にもいまや衣をうつの山夕霜はらふ蔦の下道(新古982)
【通釈】故郷の都でも、今頃妻が私を慕い、衣を
雑
忘るなよ宿るたもとはかはるともかたみにしぼる夜はの月影(新古891)
【通釈】忘れないでくれ。共に別れの涙を流し、濡れた袂に月の光を宿した――その袂は変わるとしても、その夜お互いに絞った月の光のことは。
藻塩くむ袖の月影おのづからよそに明かさぬ須磨の浦人(新古1557)
【通釈】藻塩のために海水を汲む袖はしとどに濡れ、その上に月の光が映じて、須磨の浦の海人はおのずと月をよそにすることなく一夜を明かす。
契りありてけふみや河のゆふかづら永き世までにかけてたのまむ(新古1872)
【通釈】前世からの因縁があって、今日伊勢の
時代が違い当時の生活習慣が違えば中々和歌を理解するのは容易ではないと改めて感じるものがある。
現代の科学の時代、情報化の世界、AIの時代にもなってくる現代にいにしえびとがどんな歌を詠んでいたかを察することは日本人の心のふるさとをかいま見る手段にはなる。それが現代を生きるものにとり心の潤い、「人間とはなんだ?」という根本的な問いに対する歴史からの回答が含まれているかも。定家の芸術至上主義もそんな視点で見て行けば歌の根本が理解できてくるかも。当時の公家の心の在り様も垣間見ることが出来るかも。
「歌とはなんだ?」自分なりに把握できればよいが。...2017/11/23勤労感謝の日
良寛 りょうかん 宝暦八~天保二(1758-1831)号:大愚
幼少時より読書に耽り、家の蔵書を渉猟したという。明和五年(1768)、儒者大森子陽の狭川塾に入り、漢学を学ぶ。その後名主見習となるが、安永四年(1775)、十八歳の時、隣町尼瀬の曹洞宗光照寺に入り、禅を学ぶ。同八年(二十二歳)、光照寺に立ち寄った備中国玉島曹洞宗円通寺の大忍国仙和尚に随って玉島に赴く。剃髪して良寛大愚と名のったのはこの頃のことかという(出家を十八歳の時とする説もある)。以後円通寺で修行し、寛政二年(1790)、三十三歳の時、国仙和尚より印可の偈を受ける。翌年国仙は入寂し、良寛は諸国行脚の旅に出る。同七年、父以南は京都桂川に投身自殺。京都で法要の列に加わった良寛は、その足で越後国に帰郷し、出雲崎を中心に乞食生活を続けた。
四十七歳の頃、国上山(くがみやま)にある真言宗国上寺(こくじょうじ)の五合庵に定住。近隣の村里で托鉢を続けながら、時に村童たちと遊び、或いは詩歌の制作に耽り、弟の由之や民間の学者阿部定珍(さだよし)らと雅交を楽しんだ。またこの頃万葉集に親近したという
文化十四年(1817)、江戸にのぼり、さらに東北各地を巡遊。文政九年(1826)、自活に支障を来たし、三島郡島崎村の能登屋木村元右衛門方に身を寄せ、屋敷内の庵室に移る。同年、貞心尼(当時二十九歳)の訪問を受け、以後愛弟子とする。天保元年(1830)秋、疫痢に罹り、翌年一月六日、円寂。七十四歳
貞心尼
越後長岡藩士奥村五兵衛の娘。俗名マス。十六歳頃、望まれて医師関長温に嫁すが、二十代で夫と離別し、やがて柏崎で剃髪して貞心を称す。
文政十年(1827)頃、古志郡福島村(現在長岡市)の閻魔堂に独居する。この頃良寛を知ったらしく、敬慕の思いを手紙にしたため、のち島崎の庵に良寛を訪ねた。時に貞心尼二十九歳、良寛六十九歳。以後、良寛の死までの五年間、たびたび消息を通わせ、また庵を訪問し合う。天保元年(1830)歳末、良寛危篤の報を受け、島崎の庵に駆けつけたが、年が明けて正月六日、良寛は示寂した。天保六年(1835)、良寛の歌を集めて家集『はちすの露』を編む
「白隠の里」
松陰寺の境内に良寛の書の碑とその内容を解説した案内板 が建っており、その時はたいして気にならなかったが、良寛の経歴を調べて行くうちになんで白隠と良寛の接点があるのか興味が湧く。白隠は1625~1768良寛は1758~1831で白隠がなくなった年には良寛は11歳ほど。直接の交流はなさそう。


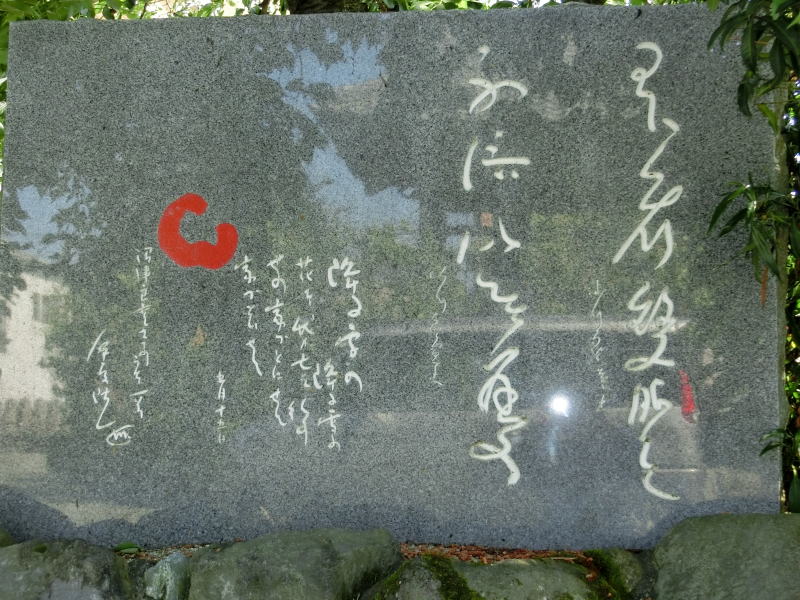
簡単にその内容をかいつまんで載せてみる
君看雙眼色 不語似無憂
読み きみ看よ双眼の色、語らされば憂いなきに似たり
語訳 妾の二つの眼ををよくよく看てください。何も言ってくれないと憂い(その気)がないように見えますよ
白隠禅師の著「槐安国語」巻五にある語 「千峰雨霄露光冷」千峰雨晴れて露光冷じ の句につけた白隠下語の一部
歌として
降る雪の、降る雪の、雪の花を吾が後の世の家づとにせん家づとにせん
沼津良寛さまの一首
(降りに降る雪の花を来世の私のためにその家のおみやげにしたいものだ、おみやげにしたいものだ)
良寛は白隠に共感してこの語を書いた。その書は良寛最高傑作の一つでここに白隠と良寛の深い結びつきがうかがえる。
良寛のイメージは子供と遊ぶ 無心な僧侶としかイメージがなかったが、果たしてその真相は、歌を通して少しでもその人物を理解できればと思う。
【経歴】
生涯をたどる手立ては極めて少ない。それは良寛が禅僧でありながら、いかに宗派や僧籍にこだわる事なく生きていたかを物語っている
1758年11月2日 越後国出雲崎(現・新潟県三島郡出雲崎町)に生まれた
(1768)、儒者大森子陽の狭川塾に入り、漢学を学ぶ
(1775)、十八歳の時、隣町尼瀬の曹洞宗光照寺に入り、禅を学ぶ
(全国各地に米騒動が頻発した。越後にも天災・悪疫が襲い、凶作により餓死者を出した。村人の争いを調停し、盗人の処刑に立ち会わなければならなかった良寛が見たものは、救いのない人間の哀れな世界であった)
(1779)22歳の時、良寛の人生は一変する。玉島(岡山県倉敷市)の円通寺の国仙和尚を"生涯の師"と定める
(1790)印加(修行を終えた者が一人前の僧としての証明)を賜る。翌年、良寛34歳の時「好きなように旅をするが 良い」と言い残し世を去った国仙和尚の言葉を受け、諸国を巡り始めた
(1805)48歳の時、越後国蒲原郡国上村(現燕市)国上山(くがみやま)国上寺(こくじょうじ)の五合庵(一日五合 の米があれば良い、と農家から貰い受けたことからこの名が付けられた)にて書を学ぶ
(五合庵の良寛は何事にもとらわれず、何者にも煩わせることもない、といった生活だった。筍が顔を覗かせれば居間を譲り、子供にせがまれれば、日が落ちるまで鞠付きに興じる。良寛独自の書法を編み出す。それは、上手に見せようとするのではなく、「一つの点を打つ」「一つの棒を引く」その位置の僅かなズレが文字の命を奪う。
(1818)61歳の時、乙子神社境内の草庵に居を構えた。円熟期に達した良寛の書はこの時に生まれている。70歳の時、島崎村(現長岡市)の木村元右衛門邸内にそれぞれ住んだ。無欲恬淡な性格で、生涯寺を持たず、諸民に信頼され、良く教化に努めた。良寛自身、難しい説法を民衆に対しては行わず、自らの質素な生活を示す事や簡単な言葉(格言)によって一般庶民に解り易く仏法を説いた。その姿勢は一般民衆のみならず、様々な人々の共感や信頼を得ることになった。
(1830)秋、疫痢に罹り、翌年一月六日、円寂。七十四歳
(1835)貞心尼、良寛の歌を集めて家集『はちすの露』を編む
書家で生涯寺を持たず、難しい説法はせず、庶民に信頼され、質素な生活や簡単な言葉で仏法を説き人々の共感や信頼を得る。時代背景は白隠と変わらず、白隠も禅画は有名、臨済宗中興の祖と言われ積極的に仏法を説いたのに対してその生き方は太陽対月か星の如く控えめなものかも そんな気がする。
良寛の歌は愛弟子の貞心尼により、まとめられ、良寛が亡くなった後にも生涯を通して慕い続けたようだ。二人の関係は師弟であり、愛人のような関係?歌の友? 彼女の四十四歳以後の作を集めた家集『もしほ草』があり、『はちすの露』には良寛との贈答歌がある。良寛を知るうえで貴重な人物ではあるようだ。
以下に歌の幾つかを某HPより収集しました
春の歌
あしびきのこの山里の
雪の夜にねざめて聞けば雁がねも
この里に手まりつきつつ子供らと遊ぶ春日は暮れずともよし
あしびきの青山越えてわが来れば
山住みのあはれを誰に語らましあかざ
夏の歌
さ苗ひくをとめを見ればいそのかみ古りにし御代の思ほゆるかも
あしびきの山田の
ひさかたの雨の晴れ間にいでて見れば青みわたりぬ四方の山々
秋の歌
月よみの光を待ちてかへりませ山路は栗のいがの多きに
秋の雨の晴れまに出でて子どもらと山路たどれば
冬の歌
水や汲まむ
きて見ればわが古里は荒れにけり庭もまがきも落葉のみして
哀傷
都良子が死にけりと人のいひければ
秋のゆふべ虫の音ききに僧ひとり
相聞
師常に手毬をもてあそびたまふとききて
これぞこの仏の道に遊びつつつくやつきせぬ御のりなるらむ 貞心
つきてみよひふみよいむなやここのとを十とをさめてまた始まるを 良寛
春のはじめつかた、
おのづから冬の日かずの暮れゆけば待つともなきに春は来にけり 貞心
或夏の頃まうでけるに、いづちへか出で給ひけむ見え給はず、ただ花がめに
来て見れば人こそ見えね
みあへするものこそなけれ
あくる日はとくとひ来給ひければ
歌や詠まむ手毬やつかむ野にや出でむ君がまにまになして遊ばむ 貞心
歌もよまむ手毬もつかむ野にも出む心ひとつを定めかねつも 良寛
あづさゆみ春になりなば草の
雑
紀の国の高野のおくの古寺に杉のしづくを聞きあかしつつ
たらちねの母がかたみと朝夕に佐渡の島べをうち見つるかも
いにしへにかはらぬものは
いざここにわが身は老いむあしびきの国上の山の松の下いほ
里べには笛や太鼓の音すなり
こき走る 鱈にもわれは 似たるかも あしたには かみにのぼり かげろふの 夕さりくれば 下るなり
大めしを食うて眠りし報いにやいわしの身とぞなりにけるかな
★平成27年10月18日 「良寛の書館」を偶然に見る
平成27年10月18日 「良寛の書館」を偶然に見る機会があり、段ボールに入った分厚い、さも高そうな本です。
自筆らしき文が何点か掲載され、発行は昭和47年、定価は当時の金額で一万六千円。BSN新潟放送で出しています。当時の初任給が3万円程度の時代、立派な本であることですがなんせ書体が崩され私には読めません。有名な書家とは聞いていたが。内容は日々の手紙や礼状が年代順に書かれていて当時の時代を想像するのには役立つかもしれない。オークションで一万円からスタート、落札価格は知らない。飾っておくだけでも充実感がありそう。良寛は書物をほとんど人から借りたそうです。従って書物を持たなかったらしい。私もほとんどの知識はネットで検索し、本は持たない(もっとも本を買う金が惜しいのが動機なのだけれど)
平成24年1月28日
先日某新聞の住友信託銀行の某相談役のコラムに・・・・・ノーベル物理学賞受賞者「湯川秀樹」が天才として弘法大師、石川啄木、ゴーゴリ、ニュートン、を上げていた。啄木は西行と共に長く残り、日本を越えて世界性をもつ。啄木と同じような歌を作りたくなる、そういった歌人が偉いのだと述べ、一番好きな歌を「一握の砂」から選んでいる。・・・・・
以前に石川啄木の歌は眼にしたことがありましたが、自分としては(なんとめそめそした歌を歌う人だ〉と思っていましたが、今回の記事をみて、再度検討してみることにしました。湯川秀樹さんを信用して(科学者も短歌に造詣があることに注目)。湯川秀樹さんの好きな歌は
「一握の砂」を一通り読んでみましたが、(青空文庫で、ここ十年本を買ったことがない)読み方が悪いのか今一の感じ。今のところ気に入った歌をあげて見ますと以下のものでした。
特に好きな歌は「目になれし 山にはあれど 秋くれば 神すまむとか かしこみて見る」です。山登りなどしていますが、季節を問はず、時々私もそんな気持ちを抱くときがありますが、秋は格別です。「神」と「かしこみ」が調子を盛り上げています。
忘れていました。以下の歌は短歌に興味のないときより、諳んじていました。
| 本名 一 | 1886.2.20-1912.4.13 享年26歳 今年が(2012年)亡くなった時から百年 岩手県生まれ。1歳の時に父が渋民村・宝徳寺の住職となり同村が啄木の「ふるさと」になる。小学校を首席で卒業し、地元では神童と呼ばれる。 17歳の時に初めて“啄木”の号を名乗り『明星』に長詩を発表、注目される。 |
| 19歳(1905年) | 処女詩集『あこがれ』を刊行!一部で天才詩人と評価される。 |
| 20歳 | 小学校の代用教員として働き始める(年末に長女生れる)。 |
| 21歳 | 住職再任運動に挫折した父が家出。啄木は心機一転を図って北海道にわたり、函館商工会議所の臨時雇い、代用教員、新聞社社員などに就くが、どの仕事にも満足できず、函館、札幌、小樽、釧路を転々とする。 |
| 22歳 | どうしても文学への夢を捨てきれない啄木は、郁雨に家族を預けると旧友の金田一京助を頼って再び上京する 夢が打ち砕かれた啄木は、彼にとって気持ちを吐き出すための“玩具”、すなわち三行の短歌に日々の哀しみを歌い込んだ。 |
| 23歳 | 前年に与謝野鉄幹に連れられて鴎外の歌会に参加したことをきっかけに、雑誌「スバル」創刊に参加。相変わらず小説は評価されず、失意のうちに新聞の校正係に就職する。 家族の上京後、生活苦から妻と姑との対立が深刻化し、妻が子どもを連れて約一ヶ月実家へ帰ってしまう。年末に父が上京。 |
| 24歳 | 新聞歌壇の選者に任命されるも、暮らしは依然厳しかった。貧困生活の中で左翼的な思想に傾いていた啄木は、6月に大逆事件(天皇暗殺未遂事件=後に当局のデッチ上げと判明)が起きると、国家による思想統制・言論弾圧を深く憂慮して評論『時代閉塞の現状』を書く 無政府主義者とは“最も性急なる理想家”であるのだ 12月、「我を愛する歌」「煙」「秋風のこころよさに」「忘れがたき人々」「手套を脱ぐとき」の5章551首からなる処女歌集『一握の砂』を刊行。 |
| 25歳 | 前年に続いて大逆事件の公判を追っていた彼は、独自に手に入れた陳弁書から“(主犯とされる)幸徳は決して自ら今度のような無謀をあえてする男でない”と判断していた。それだけに、被告26名中、11名死刑(半世紀後に全員無罪の再審判決)という結果に大きな衝撃を受ける。この頃の詩稿が死後の詩集『呼子と口笛』になった。 |
| 26歳(1912年) | 年明けに漱石から見舞金が届く。3月に母が肺結核で亡くなり、翌月に啄木もまた肺結核で危篤に陥る。 若山や友人たちが啄木の創作ノートを持って奔走し、第2歌集『悲しき玩具』の出版契約を結びとる。 啄木が26歳の若さで死に至る最晩年の様子は、親友の金田一京助、若山牧水によって書き残されている。 |
文学に夢を託した啄木の、貧困の生活との葛藤の生き方が歌の中ににじみ出ている。そうした中で漱石、牧水、金田一京助、与謝野晶子など、友人、知人の豊富なことに目が行く。「悲しき玩具」目を通したが、病人の日記、メモの感じで今のところこれと言って気に入った歌はない。没後100年、行事などに注意しなければ。牧水は啄木よりも一才年上かな。私の歌のきっかけになった牧水については色々調べていましたが、記憶が薄れており、再度メモがてらにまとめてみたい。
先日、朝日新聞「文化の扉」で石川啄木を取り上げていました。
以下、面白いので簡単に内容を書きました。
1.神童時代
やはらかに 柳あおめる 北上の 岸辺目に見ゆ 泣けと如くに
5歳 通常より1歳早く小学校に入学、主席で卒業
12歳 盛岡尋常中学校に入学 金田一京助と知り合う
16歳 10月に退学( カンニングがバレる )上京して与謝野鉄幹・晶子と出会う
19歳 第一詩集「あこがれ」を刊行 同郷の堀節子と結婚(披露宴に向かう途中寄り道し、すっぽかす)
2・ 人生修業
東海の 小島の磯の 白浜に われ泣きぬれて 蟹とたはむる
函館の 青柳町こそ かなしけれ 友の恋歌 矢車の花
20歳 3月、渋民村の代用教員となる 12月長女京子生まれる
21歳 4月、小学校を免職される(校長を辞めさせようとして自分が止める羽目に)
5月、函館に渡り、、宮崎郁雨と出会う。以後北海道を転々として代用教員、新聞記者などをする
22歳 4月、家族を函館に残して上京
5月、本郷菊坂の金田一京助と同じ下宿に住み小説を書く 部屋代を滞納金田一が自分の蔵書を売り
一緒に別の下宿に引っ越す
3・生活者啄木
皮膚がみな 耳にてありき しんとして 眠れる街の 重き足音
京橋の 滝山町の 新聞社 灯ともる頃の いそがしさかな
23歳 3月、東京朝日新聞に公正係として就職(月給を前借しては浅草で遊興した)
6月、妻子と母が上京(借金の額、現在の金額で680万円以上)
24歳 9月、「朝日歌壇」選者になる(10月、長男真一誕生後、まもなく死亡)
12月1日、第一歌集「一握の砂」刊行
4・晩年
庭のそとを 白き犬ゆけり ふりむきて 犬を飼はむと 妻にはかれる
石川は ふびんな奴だ ときにかう 自分でいひて かなしみてみる
25歳 体調を崩し、2月に慢性腹膜炎と診断される
26歳 肺結核で死去。6月「悲しき玩具」刊行
啄木を称して・・・泣いたり悲しんだりと感傷的で貧しさの中で早世した不遇の詩人のイメージがある。実は「天才気取りで生意気な、明るい浪費家であった」と言うことが書かれている。可愛い”うそつき”の啄木は愛された。金田一京助は一時自分の給料で啄木を養い、函館の文学仲間の宮崎郁雨は啄木上京後、残された家族の面倒をみた。師の与謝野鉄幹、晶子もかわいがった。(注 ローマ字日記では、啄木は与謝野鉄幹を評価していない)啄木が死んだ時、晶子は啄木の”うそ”を懐かしむ歌を歌っている。
啄木が 嘘を言う時 春かぜに 吹かるる如く おもいしもわれ
啄木は本当は小説家になりたかった。小説は売れず、行き詰った時に書いたのが短歌だった。啄木は短歌を(玩具=おもちゃ)と軽蔑し続けた。(注「歌は色々」では短歌につて、将来残って行くか、様式などについて述べている)「それが新境地をもたらし、立派な歌を読む気がないから、飾らない言葉で何げない出来事や心の動きを詠うことが出来た。青春の文学だった短歌を、働く人々の日常の心の動きをすくい取るものへ広げ、100年後の今に続く短歌のスタンダードを作った」と某歌人は述べている。歌集は「一握の砂」「悲しき玩具」だけだけれど、そこには青春、病気、貧乏、望郷、都会の孤独、社会変革の意識、家族といった近代日本の、そして現代に続く重要な主題が全部入っている。
「啄木の歌には万人が自分のふるさとへの思いを託せる普遍性がある」で結んでいる。
(注は私のコメント)
23歳頃の公正係の頃の生活の様子は「ローマ字日記」に具体的に書かれており、ローマ字で書けば妻の節子にはわからないと思っていたようです。(読まれたくなかった。)タバコ代工面のために本を質入したり、売ったり、会社からの前借は常習。浅草通いの遊び人であった。年配の方も、若い頃は諸々の葛藤や、青春時代の淡い思い出があり、啄木の歌や、生き方に共感する方も多いのでは。うそつき啄木の残した歌は、それぞれ読む人の年代、経歴と融合して評価され、共感され今後も読まれて行くこと間違いはなし。歌人の歌の背景の一面を掘り下げて行くのも面白いものがあるとつくづく思いました。啄木の友人の一人の牧水はどのように評価していたか、機会があったら取り上げてみようと思います。
当時の思想は如何に
(強権、純粋自然主義の最後および明日の考察)
見よ、我々は今どこに我々の進むべき路を見いだしうるか。ここに一人の青年があって教育家たらむとしているとする。彼は教育とは、時代がそのいっさいの所有を提供して次の時代のためにする犠牲だということを知っている。しかも今日においては教育はただその「今日」に必要なる人物を養成するゆえんにすぎない。そうして彼が教育家としてなしうる仕事は、リーダーの一から五までを一生繰返すか、あるいはその他の学科のどれもごく初歩のところを毎日毎日死ぬまで講義するだけの事である。もしそれ以外の事をなさむとすれば、彼はもう教育界にいることができないのである。また一人の青年があって何らか重要なる発明をなさむとしているとする。しかも今日においては、いっさいの発明はじつにいっさいの労力とともにまったく無価値である――資本という不思議な勢力の援助を得ないかぎりは。
時代閉塞の現状はただにそれら個々の問題に止まらないのである。今日我々の父兄は、だいたいにおいて一般学生の気風が着実になったといって喜んでいる。しかもその着実とはたんに今日の学生のすべてがその在学時代から
文学――かの自然主義運動の前半、彼らの「真実」の発見と承認とが、「批評」として刺戟をもっていた時代が過ぎて以来、ようやくただの記述、ただの説話に傾いてきている文学も、かくてまたその眠れる精神が目を
折口信夫 歌の円寂する時(歌論) 短歌と近代詩と
で啄木につきて以下のように評している
啄木のことは、自然主義の唱えた「平凡」に注意を蒐あつめた点にある。彼は平凡として見逃され勝ちの心の微動を捉えて、抒情詩の上に一領域を拓(ひら)いたのであった 併し其も窮極境になれば、万葉人にも、平安歌人にも既に一致するものがあったのである。唯、新様式の生活をとり入れたものに、稍(やや)新鮮味が見えるばかりだ。そうして、全体としての気分に統一が失われている。此才人も、短歌の本質を出ることは出来なかったのである
平成24年2月10日
久々に海が見たくて千本浜に出かけました。防波堤をブラブラしていたところ、牧水記念館を想いだし、二百円はらって見学しました。以前より一度入ってみたいとは思っていましたが、なんとなく敷居が高そうで見合わせていました。何処の記念館にもあるような内容で原稿、手紙、写真、掛け軸、本などが展示してあります。下書き、手帳の類を見ましたが、字がそれほど綺麗でないのにホットしました。以前より牧水にかかわるHPなどで色々調べ,大方の知識は持っていました。また牧水の歌碑を写真に撮って歌碑のページに載せていました。
牧水は私が短歌を詠むきっかけの人で、酒にまつわる歌に感銘を覚えました。細かいことは牧水記念館のHPとか、生誕の地のHPで細かいことが紹介されています。従ってここでは自分の知識の整理を兼ねて紹介していきます。
館内に与謝野晶子没後70年短歌文学賞のチラシがあり、投稿には一首につき千円かかる。角川短歌は二千円とか。どうも相場はこんな所か。ただなら投稿してもと思います。与謝野晶子の歌を以前何点か読んだことがあり、面白い人だと思っていました。チラシの中に「歌はどうして作る。じっと観、じっと愛し、じっと抱きしめて作る。なにを。真実を。」が書かれていました。参考にしたい。 夫である与謝野鉄幹の歌碑が御瀬崎にあるようなので機会があったら写真に撮りたいと思います。
 |
 |
 この掛け軸は十万円 (長野県哲西町二本松峠で詠む) |
 千本浜の公園にある歌碑「幾山河・・・」 全国で最初の歌碑だそうです |
 |  |
西伊豆の土肥の旅館で土肥館(牧水館)にも牧水にまつわる品が展示されているそうです。
| 明治18年(1885) 0歳 | 8月24日 宮崎県東臼杵郡東郷村坪谷に医師である父立蔵と母マキとの間に生まれる。 |
| 明治29年(1896) 10歳 | 延岡高等小学校に入学。 |
| 明治32年(1899) 14歳 | 県立延岡中学に入学。 |
| 明治34年(1901) 16歳 | 延岡中学「校友会雑誌」第1号に短歌と俳句を発表。「中学文壇」に短歌を投稿。佐佐木信綱選で入選。 |
| 明治36年(1903) 18歳 | 「中学世界」に「牧水」の名で投稿。以後はすべて牧水の名で発表。 |
| 明治37年(1904) 19歳 | 早稲田大学に入学。 同級の中林蘇水、北原射水(白秋)と「早稲田の三水」と称した。 |
| 明治39年(1906) 21歳 | 土岐善麿、佐藤緑葉らと回覧雑誌「北斗」を発行。 帰省の途中、友人の下宿先で園田小枝子と出会う。 |
| 明治40年(1907) 22歳 | 次第に小枝子に惹かれる。この頃から純文学者として身を立てる決意を固め、短編小説を発表する。 |
| 明治41年(1908) 23歳 | 7月 第1歌集『海の声』出版。 文芸誌「新文学」創刊の計画を進めるが、資金難で断念。 |
| 明治42年(1909) 24歳 | 中央新聞社に入社。しかし5ヶ月後に退社。 |
| 明治43年(1910) 25歳 | 1月 第2歌集『独り歌へる』出版。 4月 第3歌集『別離』出版。歌壇の注目を集める。 |
| 明治44年(1911) 26歳 | 1月 創作社を興し雑誌「創作」を編集。歌人太田水穂の家で後に妻となる太田喜志子と出会う。 9月 第4歌集『路上』出版。 |
| 明治45年(1912) 27歳 | 3月 「牧水歌話」出版。 4月 石川啄木の臨終に立ち合う。 5月 太田喜志子と結婚。 |
| 大正 2年(1913) 28歳 | 4月 長男旅人誕生。 8月 「創作」復活号の編集に取りかかる。 9月 第6歌集『みなかみ』出版。 |
| 大正 3年(1914) 29歳 | 4月 第7歌集『秋風の歌』出版。 「創作」の経営に行き詰まる。 |
| 大正 4年(1915) 30歳 | 3月 喜志子の健康上の理由で神奈川県北下浦に転居。 4月 「傑作歌選若山牧水」「行人行歌」出版。 10月 第8歌集『砂丘』出版。 11月 長女みさき誕生。 |
| 大正 5年(1916) 31歳 | 6月 散文集「旅とふる郷」、第9歌集『朝の歌』出版。 11月 自選歌集「若山牧水集」出版。 12月 北下浦から東京へ戻る。 |
| 大正 6年(1917) 32歳 | 2月 「創作」を復刊。同月「和歌講話」 4月 「わが愛誦歌」出版。 8月 喜志子との合著となる第10歌集『白梅集』出版。 |
| 大正 7年(1918) 33歳 | 5月 第12歌集『渓谷集』出版。 7月 第11歌集『さびしき樹木』、散文集「海より山より」出版。 |
| 大正 8年(1919) 34歳 | 4月 次女真木子誕生。 9月 紀行文集「比叡と熊野」を出版。 |
| 大正 9年(1920) 35歳 | 2月 選歌集「花さける廣野」出版。 東京から沼津への移住を決意。8月15日に沼津町在 楊原村上香貫折坂へ移住した。 12月 「批評と添削」を出版。 |
| 大正10年(1921) 36歳 | 3月 第13歌集『くろ土』出版。 6月 前田夕暮選による「若山牧水選集」出版。 7月 紀行文集「静かなる旅をゆきつつ」出版。 |
| 大正11年(1922) 37歳 | 6月 選歌集「路行く人々の歌」出版。 10月 「みなかみ紀行」として有名な旅に出る。東京、小諸草津、暮坂峠、沼田、金精峠を経て日光を回る。 12月 「短歌作法」出版。 |
| 大正12年(1923) 38歳 | 4月 沼津で「創作社全国社友大会」を開催。 5月 第14歌集『山桜の歌』出版。 |
| 大正13年(1924) 39歳 | 5月 童謡集「小さな鶯」出版。 7月 紀行文集「みなかみ紀行」出版。 |
| 大正14年(1925) 40歳 | 2月 沼津市本字に500坪の土地を買う。 2月 随筆集「樹木とその葉」出版。 10月 念願かない約80坪の新居が完成する。 12月 自選歌集「野原の郭公」出版。 |
| 大正15年(1926) 41歳 | 5月 宿望であった詩歌総合雑誌「詩歌時代」を創刊。多方面から称賛を受ける。 8月 静岡県当局の千本松原伐採計画が持ちあがる。新聞に伐採反対意見の寄稿をし、計画は中止される。 「詩歌時代」は資金難のため10月号をもって廃刊。 |
| 昭和 2年(1927) 42歳 | 5月 喜志子を伴い朝鮮へ揮毫旅行に出かける。 |
| 昭和 3年(1928) 43歳 | 8月 健康がすぐれなくなる。 9月 初旬から衰弱が目立つ。17日永眠。享年43歳。千本山乗運寺に眠る。 |
| 昭和13年(1938) | 9月 牧水没後満10年を記念して第15歌集『黒松』が喜志子夫人と大悟法利雄氏によって編まれる。 |
 |
香貫山にある歌碑 この歌碑をみて、若山牧水について調べる内に 「酒」の歌に感心して短歌の真似事を始めました。 |
香貫山の香稜台の歌碑
始めの頃は、この歌を見て、何も感じませんでした。
千本浜公園の歌碑
この歌は調子よく、かつ奥が深そうだと思って見ていました。
私も酒は好きな方で、以下の歌はまさに同感し、思い当たる所が多い
冨士を詠んだ歌は歌碑のページに、他『黒土』『山桜の歌』『渓谷集』に多く出てくる
牧水の歌碑(静岡県)の多くに,富士を詠んだ歌が多い。
香貫山の近くに、城山公園がありますが、そこの歌碑が気に入っています
気になる歌
白浜や居ればいよいよ海とろみ冬日かぎろひ遠霞立つ『寂しき樹木』
たのしきはわれを忘れて暁の峰はなれゆく雲あふぐ時『寂しき樹木』
膳にならぶ飯も小鯛も松たけも可笑しきものか酒なしにして『寂しき樹木』
瀬のなかにあらはれし岩のとびとびに秋のひなたに白みたるかな『渓谷集』
なだらかにのびきはまれる富士が嶺の裾野にも今朝しら雪の見ゆ『渓谷集』
人の世にたのしみ多し然れども酒なしにしてなにのたのしみ『黒土』
愛鷹の真くろき峯にうづまける天雲の奥に富士はこもりつ『黒土』
ゆく水のとまらぬこころ持つといへどをりをり濁る貧しさゆゑに『黒土』
うす雲と沖とひといろに煙りあひて浜は濡れゆく今朝の時雨に『黒土』
笠なりのわが呼ぶ雲の笠雲は富士の上の空に三つ懸りたり『山桜の歌』
わがゆくやかがやく砂の白砂の浜の長手にかぎろひの燃ゆ『山桜の歌』
夏雲の垂りぬる蔭にうす青み沼津より見ゆ富士の裾野は『山桜の歌』
うすべにに葉はいちはやく萌えいでて咲かむとすなり山桜花『山桜の歌』
女郎花咲きみだれたる野辺のはしに一むら白きをとこへしの花『山桜の歌』
さびしさよ落葉がくれに咲きてをる深山りんだうの濃むらさきの花『山桜の歌』
わが登る天城の山のうしろなる 富士のたかきは仰ぎ見あかぬ
むらさきに澄みぬる富士は短夜の あかつき起きに見るべかりけり
山川にわける霞の昇りなづみ しきたなびけば富士は晴れたり
火の山の老樹の樅のしろがねの みきを叩けば葉の散り来る
光なき命のありて天地に 生くとふことにいかに寂しき
てつびんのふちに枕しねむたげに とくり傾くいさわれもねむ
園の花つぎつぎに 秋に咲きうつる このごろの日の 静けかりけり
かすみあふ四方のひかりの春の日の はるけき崎に浪の寄る見ゆ
寄り来りうすれて 消ゆる水無月の 雲たえまなし富士の 山辺に
ひむがしの白み そむれば物陰に 照りてわびしき 短夜の月
みづ痩せし秋の川原のかたすみに しづかにめぐる水ぐるまかな
めぐらせる籬の楓もみぢして 桐のはたけは寂びにけるかも
つめたきは山ざくらのさがにあるやらむ ながめつめたきやまざくら花
冬山にたてる煙ぞなつかしき ひとすぢ澄めるむらさきにして
ふるさとの尾鈴のやまのかなしさよ 秋もかすみのたなびきてをり
なまけつつ心くるしきわが肌の 汗ふきからす夏の日の風
いついつと待ちし桜の咲きいでて 今はさかりか風ふけど散らず
わが庭の竹のはやしの浅けれど 降る雨みれば春は来にけり
をさなくて見しふるさとの春の野の わすられかねて野火は見るなり
よる歳のとしごとに願ふわがねがひ 心おちいて静かなれかし
松の実や楓の はなや仁和寺の 夏なほ若し山 ほととぎす
石こゆる水のまろみを眺めつつ こころかなしも秋の渓間に
いざゆかむゆきてまだ見ぬ山をみむ このさびしさに君はたふるや
かんがへてのみはじめたる一合の 二合のさけの夏のゆふぐれ
ひそまりてひさしく見ればとほ山の ひなたの冬木かぜさわぐらし
ときをおき老樹 の雫おつるごと 静けき酒は 朝にこそあれ
うらうらと照れる光にけぶりあひて 咲きしづもれる山ざくら花
牧水の墓に刻まれているこの歌かと思ったが
つぎの作品らしい
令和2年5月31日 記
「かきのもとのひとまろ」については調べる必要も感ぜずに思ってきたが、矢張り最低限度の知識は必要かと思い記録としてメモしてみました。
色々調べてみたがよくわからないのが本音、かってに目にしたHPを目を通して漠然と知識が整理された感じがする。その内容を以下に記した。
某HP「古代探訪」より抜粋
柿本人麻呂の一生を邪推してみる。邪推ですから、変更可能。
654年 大和郡、生まれ(人麻呂の若い時の歌が、大和国高市郡や、磯城郡の地名が多い。)
672年 19歳 壬申の乱(高市皇子と同年、壬申の乱で高市皇子の軍にいた か、目の当たりにしたか、戦の体験をしている。)
673年 20歳 舎人としてつかえる。(初めてみやつかえするものを、大舎人に仕えさせ、才能によって当職にあてよとある)
680年 27歳 人麻呂歌集の七夕歌の一首が「庚辰」の年に作られている。
681年 28歳 小錦下の位を賜う。(12月に柿本猿が賜うとある)
683年 30歳 朝臣の姓を賜う。(11月に52氏が朝臣姓になっている、八色の姓で真人の次に高い位)
689年 35歳(持統3年)草壁皇子崩御の歌を歌う。
696年 42歳 高市皇子崩御の歌を歌う。
700年 46歳 宮廷歌の終わり。
701年 47歳 羇旅の歌の始まり。(瀬戸内海→筑紫→長門→石見)
708年 54歳 従四位下で亡くなる
一線部分は邪推です。歌の聖と後世の歌人から尊敬される、天才のすごさを少し探ってみたいのである。
まず、人麻呂の歌の表記法の移り変わりは、略体歌→非略体歌→作歌の順に年代と共にかわっている。略体歌とは、助詞、助動詞、動詞の語尾などを省略したものである。
例をあげると、
略体歌-------水上 如数書 吾命 妹相 受日鶴鴨 (水の上に数書く如き吾が命妹に逢わむと祈誓ひつるかも)
以下、某HP「万葉集を読む」より抜粋
柿本人麻呂の生涯については、わからぬことも多いが、持統天皇の時代に、宮廷歌人として多くの儀礼的な歌を作ったことを、万葉集そのものが物語っている。その歌は、古代の神話のイメージを喚起させて、雄大なものがある。宮廷歌人としての人麻呂は、天皇や皇子たちの権威をたたえたり、皇族の死を悼んだり、折に触れて宮廷の意向に応えていたと思われる。こうした宮廷歌人の役割は、古代における部曲の一つのあり方だったように思われる。
柿本人麻呂は相次いで失った二人の妻のために、哀切きわまる挽歌を作っている。また、旅の途中に目にした死者を見ては、彼らの不運に感情移入して、歌わずにはいられなかった。それらの歌に響く人麻呂の人間的な感情は、時代を超えて人びとの心を打つ。日本の詩歌の歴史は、柿本人麻呂を得ることによって、豊饒さを持つことができたと言える。
万葉集の歌を見る限り、宮廷を離れた人麻呂は、和銅元年(708)以降、筑紫に下ったり(3-303,304)、讃岐国に下ったり(2-220~222)した後、石見国で妻に見取られることなく死んでいる(2-223)。
万葉集には少なくとも八十首以上の歌を残している。また万葉集中に典拠として引かれている「人麻呂歌集」は後世の編纂と思われるが、そのうち少なからぬ歌は人麻呂自身の作と推測されている。勅撰二十一代集には二百六十首程の歌が人麿作として採られている。
古来、至高・別格の歌人、というより和歌の神として尊崇されてきた。大伴家持は倭歌の学びの道を「山柿之門」と称し(万葉集巻十七)、紀貫之は人麿を「うたのひじり」と呼び(古今集仮名序)、藤原俊成は時代を超越した歌聖として仰いだ(古来風躰抄)。石見国高津の人麻呂神社創建は神亀元年(724)と伝えられている。
以下に歌を抜粋しました。
羇旅歌
玉藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島の崎に舟近づきぬ(3-250)
【通釈】海女たちが海藻を刈る敏馬を過ぎて、夏草が生い茂る野島の崎に私の乗る舟は近づいた。
荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我を(3-252)
【通釈】土地の人々は藤江の浦で鱸を釣る漁夫と見ていることだろうか、舟に乗り旅をする私を。
ともしびの明石大門に入らむ日や榜ぎ別れなむ家のあたり見ず(3-254)
【通釈】明石の海峡に船が入って行く日には、故郷から漕ぎ別れてしまうのだろうか、もう家族の住む大和の方を見ることもなく。
もののふの八十宇治川の網代木にいさよふ波の行くへ知らずも(3-264)
【通釈】宇治川の網代木に阻まれてたゆたう波は進むべき方向を知らない。そのように、我らの人生も様々の障害に突き当たり、行方は知れないのだ。
淡海の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(3-266)
【通釈】淡海の海の夕波に立ち騒ぐ千鳥たちよ、おまえたちが啼くと、心も撓うばかりに昔のことが偲ばれるのだ。
相聞
をとめらが袖ふる山の瑞垣の久しき時ゆ思ひき我は(4-501)
【通釈】少女たちが袖を振る――その「ふる」ではないが、布留山に古くからある瑞垣――そのように久しい昔から、ずっとあの人を思い続けていたのだ、私は。
夏野ゆく牡鹿の角のつかの間も妹が心を忘れて思へや(4-502)
【通釈】草深い夏の野をゆく牡鹿の、生えそめの角ではないが、ほんの短い間もあなたの気持を忘れることなどあろうか。
雑歌
【通釈】今頃、鳴呼見の浦で船に乗っているおとめたちの美しい裾に、潮が満ちて寄せているだろうか。
大船に真楫しじ貫き海原を漕ぎ出て渡る月人壮士(15-3611)
〔妻死にし後に、
うつせみと 思ひし時に 取り持ちて 我が二人見し 走出の 堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 茂きがごとく 思へりし 妹にはあれど 頼めりし 子らにはあれど 世の中を 背きしえねば かぎろひの 燃ゆる荒野に 白栲の 天領巾隠り 鳥じもの 朝発ち行して 入日なす 隠りにしかば 我妹子が 形見に置ける 若き児の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる 物しなければ 男じもの 脇ばさみ持ち 我妹子と 二人我が寝し 枕付く 妻屋のうちに 昼はも うらさび暮らし 夜はも 息づき明かし 嘆けども 為むすべ知らに 恋ふれども 逢ふよしをなみ 大鳥の 羽易の山に 我が恋ふる 妹はいますと 人の言へば 岩根さくみて なづみ来し よけくもぞなき うつせみと 思ひし妹が 玉かぎる ほのかにだにも 見えなく思へば(2-210)
去年見た秋の月は今年も同じように照っているけれども、その月を一緒に見た妻は、年月とともにますます遠ざかって行く。
引手の山に妻を残して独り山道を行けば、生きている心地もしない。
草枕旅の宿りに誰が夫か国忘れたる家待たまくに(3-426)
【通釈】旅の宿りで、誰の夫なのだろうか。故郷へ帰るのも忘れて臥せっている。家では妻が待っているであろうに。
こもりくの泊瀬の山の山の際にいさよふ雲は妹にかもあらむ(3-428)
【通釈】泊瀬の山の山あいにたゆたう雲は、亡くなった娘子なのだろうか。
八雲さす出雲の子らが黒髪は吉野の川の沖になづさふ(3-430)
【通釈】盛んに湧き上がる雲のようだった出雲娘子の黒髪は、吉野川の沖に漂っている。
柿本朝臣人麻呂、石見の国に在りて死に臨む時に、自ら
鴨山の磐根し枕ける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(2-223)
通釈】鴨山の岩を枕にして死んでゆく私のことを知らずに、妻は私の帰りをずっと待っているのだろうか。
―人麻呂歌集歌―
天の海に雲の波立ち月の船星の林に榜ぎ隠る見ゆ(7-1068)
【通釈】天空の海に雲の波が立ち、月の舟が星の林に漕ぎ隠れて行くのが見える。
あしひきの山河の瀬の鳴るなへに弓月が岳に雲立ち渡る(7-1088)
いにしへにありけむ人も我がごとか三輪の檜原に挿頭折りけむ(7-1118)
【通釈】昔ここを訪れた人も、私のする通りに、三輪の山林で檜(ひのき)の枝を挿頭に折ったのだろうか。
【通釈】いとしいあの子と思いながら眺めよう。沖の藻の花が咲いたら、私に告げてほしい。
巻向の山辺響みて行く水の水沫の如し世の人吾等は(7-1269)
【通釈】巻向山のあたりを轟かせて流れてゆく水の、あっという間に消えてしまう泡のようであるよ、この世の人間である私たちは。
【通釈】雲がたなびき、山は覆い隠されている。そのようにひたすら隠した私のひそかな思いを、木の葉だけは知っているだろう。
久方の天の香具山この夕へ霞たなびく春立つらしも(10-1812)
【通釈】天の香具山は、今日の夕方、霞がたなびいている。春がすがたを現したようであるよ
人の寝る味寐は寝ずてはしきやし君が目すらを欲りて嘆くも(11-2369)
【通釈】世の人が寝る快い眠りを私は寝ることができずに、愛しいあなたに一目逢いたいと、そればかりを願って歎くことだ。
大野らに小雨降りしく木のもとに時と寄り来ね我が思ふ人(11-2457)
【通釈】広い野に小雨が降りしきる。木蔭に、ちょうどよいと、寄ってらっしゃいな。我が恋する人よ。
―付録:勅撰集に採られた伝人麻呂作歌より―
龍田川もみち葉ながる神なびのみむろの山に時雨ふるらし(拾遺219)
あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む(拾遺778)
荒ち男の狩る矢のさきに立つ鹿もいと我ばかり物は思はじ(拾遺954)
秋萩のさき散る野辺の夕露にぬれつつ来ませ夜はふけぬとも(新古333)
秋されば雁の羽風に霜ふりてさむき夜な夜な時雨さへふる(新古458)
秋風に山とびこゆる雁がねのいや遠ざかり雲がくれつつ(新古498)
やたの野に浅茅色づくあらち山峯のあは雪さむくぞあるらし(新古657)
平成24年3月の静岡新聞に、「万葉の富士賛歌引越し」の記事が出ていました。沼津の隣の富士市の田子の浦港富士埠頭にある山部赤人の万葉歌碑が、「ふじのくに田子の浦みなと公園」に移設されるとのこと。
田子の浦ゆ 打ち出て見れば 真白にそ ふじの高嶺に 雪はふりける
百人一首では
田子の浦に うち出でてみれば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ
以前よりこの歌は知っていましたが、歌碑があることを始めて知りました。この作者をもっと調べてみようと思いました。
この歌は長歌に対する反歌とのこと
長歌は
天地の別れし時ゆ、神さびて、高く貴き駿河なる富士の高嶺を、天の原振り放け見れば、渡る日の影も隠らひ、照る月の光も見えず、白雲もい行きはばかり、時じくぞ雪は降りける、語り継ぎ言ひ継ぎ行かむ、富士の高嶺は
意味: 天地が分かれてこの地ができて以来、神々しく高く貴い、駿河の国の富士の山を、空に向かって仰ぎ見ると、太陽の光も隠れ、月の光も見えず、雲(くも)も山に行く手をさえぎられ、ひっきりなしに雪が降っています。この富士の山のことをいつまでも語り継いで行こうと思うのです。
長歌と反歌について
今まで、長歌のある歌は読まないようにしていました。なんかめんどくさくて、避けていました。今回この歌を契機に読むように心がける。反歌と長歌が一体となって、詠み人の意図が詠われているのかな。
この歌は富士山が以下に高く雄大であるかを長歌で述べ、現実の富士の雪降る景色を反歌で詠っている。やはりセットで霊峰富士の雄大さが現れてくる。
平成24年3月4日万葉歌碑が、「ふじのくに田子の浦みなと公園」に移設されたと新聞にあり、翌日雨の中を見に行く。
公園は駿河湾に面して造園され、今年中には完成されるとのこと。河津桜、サルスベリ、黒松など色々な植物が植えられて駐車場、トイレ、遊戯場などかなり広い。今度は天気のよい、富士の見れるときに又来たい。田子の浦はシラスの名産地として有名。
 |
|
 |
 |
| 平成25年11月19日以下の写真撮影 | |
 |
|
 |
|
山部 赤人-山部宿禰赤人(やまべのすくねあかひと)(やまべ の あかひと、生年不詳 - 天平8年(736年)?)は、奈良時代の歌人。三十六歌仙の一人
その経歴は定かではないが、『続日本紀』などの史書に名前が見えないことから、下級官人であったと推測されている。神亀・天平の両時代にのみ和歌作品が残され、行幸などに随行した際の天皇讃歌が多いことから、聖武天皇時代の宮廷歌人だったと思われる。
作られた和歌から諸国を旅したとも推測される。同時代の歌人には山上憶良や大伴旅人がいる
柿本人麻呂とともに歌聖と呼ばれ称えられている
自然の美しさや清さを詠んだ叙景歌で知られる。
万葉集には五十首載っているらしい。
要するに奈良時代の叙景歌を詠み、宮廷歌人で、歌聖といわれ、同時代に山上憶良や大伴旅人がいたということらしい。ここで気になることは、歌聖と呼ばれているもう一人の柿本人麻呂とはどんな歌を詠んだのか、山上憶良、大伴旅人とは。そもそも万葉集とは聞いたことがあるが具体的なことは知りません。そんな所も加味して調べてみようと思います。万葉集については参考コーナーで素朴な疑問から調べて載せる予定です。
叙景歌・・・自然の美しさ、清さを詠んだもの
山部赤人の歌として
み吉野の象山(きさやま)の際(ま)の木末(こぬれ)には ここだも騒く鳥の声かも
春の野に菫摘みにと来し我そ 野をなつかしみ一夜寝にける
我も見つ人にも告げむ 勝鹿の真間の手児名が奥つ城ところ
叙景歌として―歌六首
繩の浦ゆ背向(そがひ)に見ゆる沖つ島榜ぎ廻(た)む舟は釣しすらしも
武庫の浦を榜ぎ廻む小舟粟島を背向に見つつ羨(とも)しき小舟
阿倍の島鵜の住む磯に寄する波間なくこのごろ大和し思ほゆ
潮干なば玉藻苅り籠め家の妹(も)が浜苞(はまつと)乞はば何を示さむ
秋風の寒き朝開(あさけ)を狭野(さぬ)の岡越ゆらむ君に衣貸さましを
みさご居る磯廻に生ふる名乗藻(なのりそ)の名は告らしてよ親は知るとも
富士を詠んだ歌が日々富士を眺めている自分には、またスケールの点で一番気に入っています。
沼津アルプスの一つに徳倉山があり、別名を動物のゾウに似ていることから象山(ぞうやま)と呼んでいますが次の歌が気になっていました。「きさやま」とは?
歌をネットで調べると
山部宿禰赤人の作る歌二首 并せて短歌
やすみしし 我ご大君の 高知らす 吉野の宮は たたなづく 青垣(あをかき)ごもり 川なみの 清き河内(かふち)ぞ 春へは 花咲きををり 秋されば 霧立ち渡る その山の いや益々(しくしく)に この川の 絶ゆること無く ももしきの 大宮人は 常に通はむ
反歌二首
み吉野の 象山(きさやま)の際(ま)の 木末(こぬれ)には ここだも騒く 鳥の声かも
通釈】[長歌]
我らの大君が堂々と営まれる吉野の宮は、幾重にも重なる青垣のような山に囲まれ、川波の清らかな川内である。春の頃は花が枝もたわわに咲き誇り、秋になればいちめん霧が立ちこめる。その山のようにさらに幾たびも幾たびも、この川のように絶えることなく、大宮人はいつの世もこの宮に通うことであろう。
[反歌一] 吉野の象山の山あいの梢では、こんなにも数多く鳥が鳴き騒いでいることよ。
[反歌二] 夜が更けてゆくにつれ、久木の生える清らかな川原で千鳥がしきりに鳴いている。
長歌に対する反歌の一つとして詠われていました。◇象山 吉野宮滝の南正面の山。「きさ」は動物の象の古名。◇と解説されていました。やはり動物の象でした。この頃すでに象がいた?
そこで更に検索して行くと以下のページが見つかりました。
・・・・・
象山(きさやま)は奈良県吉野町宮滝の南正面にあり、稜線が象の形に見えるところから
その名があります。
「きさ」は象の古名で象牙の横断面に?(キサ)すなわち木目に似た文様が
見えることに由来するそうです。
象の渡来は江戸時代とされていますが、万葉人は正倉院御物に描かれた絵や
象にまたがる普賢菩薩像を見てその姿形を知っていたのでしょう。
この歌は725年聖武天皇が吉野離宮へ行幸された折に詠われたもので、
長短歌3首で構成されています。
長歌で柿本人麻呂以来の土地褒めの伝統を踏まえて天皇を讃え、短歌二首では
朝廷賛歌より自然の叙景を前面に打ち出しており、従来の行幸歌の殻を破った
万葉傑作の詠とされています。
・・・・・以上
以下の写真が象山らしいが、象のかげなし。沼津アルプスの象山のほうが俄然象山といえる。なにはともあれ、ゆっくりこの歌を賞味できれば幸いです。

深々(しんしん)と更けゆく夜。
静寂(しじま)の間から鳥の声が聞こえてくる。
耳をすますと玲瓏と響く川の音と千鳥の澄んだ声。
瞑想することしばし。
昼間に見た清々しい川原と緑鮮やかな木々。
そして飛び交う様々な鳥たちの姿が目に浮かぶ。
それはあたかも眼前でその情景を見ているようだ。
やがて口元から朗々とした調べが。
「 ぬばたまの 夜の更けゆけば 久木生ふる - -」
かくして1300年後に絶賛される名歌が誕生しました。
それは、心の集中から生まれた鮮やかな写生とも言える静寂の極致です。
こんな感じで歌を味わうらしい。味わい方のサンプルとして載せてみました。

平成24年3月24日 狩野川河口より象山を写す(沼津の象山 沼津アルプスの一つ徳倉山の別名)
左より、鼻で頭で胴体と 象に見えます
代表的な歌の解釈
【通釈】春の野に菫を摘みにやって来た私は、その野に心引かれ、離れ難くて、とうとう一夜を過ごしてしまったよ。
あしひきの山桜花日並べてかく咲きたらばいと恋ひめやも
【通釈】山桜が何日も続けてこのように咲くのであったら、これ程ひどく恋しがったりするだろうか。
我が背子に見せむと思ひし梅の花それとも見えず雪の降れれば
【通釈】いとしいあの方にお見せしようと思った梅の花――どれがその花とも見分けがつかない。枝に雪が積もっているので。
明日よりは春菜摘まむと標めし野に昨日も今日も雪は降りつつ
【通釈】明日からは春の若菜を摘もうと標縄を張っていた野に、昨日も今日も雪が降ってばかりで…。
恋しけば形見にせむと我が屋戸に植ゑし藤波今咲きにけり
【通釈】恋しい時には、あの人を思い出すよすがにしようと、我が家の庭に植えた藤――その花が今咲いたことだ。
縄の浦ゆそがひに見ゆる沖つ島榜ぎ廻る舟は釣しすらしも
【通釈】縄の浦から背後に見える沖の島――その島を漕ぎ巡る舟は、釣をしているところらしい。
【通釈】阿倍の島の鵜の棲む磯に寄せる波のように、絶え間なくこの頃大和のことが思われることだ。
みさご居る磯廻に生ふる名告藻の名はのらしてよ親は知るとも
【通釈】みさごの棲んでいる磯辺に生える名告藻ではないが、名前は名告ってくれ、たとえ親が気づいても。
【通釈】男子の官人たちは天皇の御狩の場に臨まれ、一方年若い女官たちは赤裳の裾を引きながら歩いて行くよ、清らかな浜辺を。
昨日こそ年は暮れしか春霞かすがの山にはやたちにけり
【通釈】昨日年は暮れたばかりなのに、春霞が春日の山に早くも現れたのだった。
我が背子をならしの岡のよぶこどり君よびかへせ夜の更けぬ時
【通釈】我が夫を馴れ親しませるという名のならしの岡の呼子鳥よ、あの人を呼び返してその名の通り私に馴れ親しませておくれ、夜の更けない内に。
ももしきの大宮人はいとまあれや桜かざして今日も暮らしつ
【通釈】宮廷に仕える人たちは暇があるのだろうか。桜の花を頭に挿して今日も一日遊び暮らしていた。
春雨はいたくなふりそ桜花まだ見ぬ人に散らまくも惜し
【通釈】春雨はひどく降らないでくれ。桜をまだ見ない人にとって、花が散ることは惜しい。
山の端に月のいざよふ夕暮は檜原がうへも霞みわたれり
【通釈】山の端に月が出るのをためらっている春の夕暮は、檜林の上もすっかり霞が立ちこめている。
あしびきの八重山こえてほととぎす卯の花がくれ鳴きわたるなり
【通釈】幾重もの山を超えて、時鳥は卯の花に隠れ、鳴き渡っている。
柿本人麻呂、山上 憶良の歌風など
柿本人麻呂(かきのもと の ひとまろ、斉明天皇6年(660年)頃 - 養老4年(720年)頃)は、飛鳥時代の歌人。名は「人麿」とも表記される。後世、山部赤人とともに歌聖と呼ばれ、称えられている。また三十六歌仙の一人
一般には天武天皇9年(680年)には出仕していたとみられ、天武朝から歌人としての活動をはじめ、持統朝に花開いたとみられることが多い。ただし、近江朝に仕えた宮女の死を悼む挽歌を詠んでいることから、近江朝にも出仕していたとする見解もある。確実に年代の判明している人麻呂の歌は持統天皇の即位からその崩御にほぼ重なっており、この女帝の存在が人麻呂の活動の原動力であったとみるのは不当ではないと思われる。
彼は『万葉集』第一の歌人といわれ、長歌19首・短歌75首が掲載されている。人麻呂の歌は、讃歌と挽歌、そして恋歌に特徴がある。格調の高い歌風
代表歌 [編集]
山上 憶良(やまのうえ の おくら、(斉明天皇6年(660年)? - 天平5年(733年)?)は、奈良時代初期の貴族・歌人。仏教や儒教の思想に傾倒していたことから、死や貧、老、病などといったものに敏感で、かつ社会的な矛盾を鋭く観察していた。そのため、官人という立場にありながら、重税に喘ぐ農民や防人に狩られる夫を見守る妻など社会的な弱者を鋭く観察した歌を多数詠んでおり、当時としては異色の社会派歌人として知られる。抒情的な感情描写に長けており、また一首の内に自分の感情も詠み込んだ歌も多い。
代表的な作品
以上柿本人麻呂、山上 憶良、山部 赤人の歌風が際立って違っているのが面白い。
大伴 旅人(おおとも の たびと、天智天皇4年(665年) - 天平3年7月25日(731年8月31日)は、奈良時代初期の貴族、歌人。大納言・大伴安麻呂の子。官位は従二位・大納言。養老5年(721年)正月5日に従三位に叙せられる。神亀年間(724年-729年)には、大宰帥として妻・大伴郎女を伴って大宰府に赴任し、山上憶良とともに筑紫歌壇を形成した。天平2年(730年)10月に大納言に任じられ京に戻り、翌天平3年(731年)従二位に昇進するが、まもなく病を得て没した。
『万葉集』に和歌作品が78首選出されているが、和歌の多くは大宰帥任官以後のものである。酒を讃むるの歌十三首を詠んでおり、酒をこよなく愛した人物として知られる。
歌風は、大陸的風雅心・老荘的自由思想と位置付けられている
以上が大伴旅人の解説に載っていた内容ですが、歌風どおりの人で大伴旅人の歌にはおおらかさと、風雅な情緒が溢れている様です。柿本人麻呂、山上 憶良、山部 赤人とは異質の歌人らしい。酒を讃むるの歌十三首を詠んでおり、酒をこよなく愛したとのこと。この辺がきになり、牧水の酒にかかわる歌と較べてみようと思いました。
以下某HPより抜粋
―太宰帥大伴の卿の酒を讃めたまふ歌十三首(338)
験(しるし)なき物を思はずは一坏(ひとつき)の濁れる酒を飲むべくあらし(339)
酒の名を聖(ひじり)と負ほせし古の大き聖の言の宣しさ(340)
古の七の賢(さか)しき人たちも欲(ほ)りせし物は酒にしあらし(341)
賢しみと物言はむよは酒飲みて酔哭(ゑひなき)するし勝りたるらし(342)
言はむすべ為むすべ知らに極りて貴き物は酒にしあらし(343)
中々に人とあらずは酒壷(さかつぼ)に成りてしかも酒に染みなむ(344)
あな醜(みにく)賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似む(345)
価(あたひ)なき宝といふとも一坏の濁れる酒に豈(あに)勝らめや(346)
夜光る玉といふとも酒飲みて心を遣るに豈及(し)かめやも(347)
世間(よのなか)の遊びの道に洽(あまね)きは酔哭するにありぬべからし(348)
今代(このよ)にし楽しくあらば来生(こむよ)には虫に鳥にも吾は成りなむ(349)
生まるれば遂にも死ぬるものにあれば今生なる間は楽しくを有らな(350)
黙然(もだ)居りて賢しらするは酒飲みて酔泣するになほ及かずけり(351)
人麻呂の恋でもなく、赤人の自然でもなく、酒を詠んだこれらの歌は、万葉の世界の中に新しい息吹を持ち込んだ。広い意味では、述懐の歌といえようが、酒に寄せて人生の快楽を謳歌するような作品は、旅人以前の万葉の歌にはなかったものである。
酒は聖であるといい、古の七賢人も欲したといい、また言いようもなく尊いものであって、価なき玉や夜光る玉にも替えがたいものだと歌う。賢者ぶって生きているより、酒を飲んで酔泣きするほうがどれほどすばらしいことかわからない。賢者ぶって酒を飲まぬものをよくみれば、猿にそっくりではないか。さあさあ、酒を飲むべしというわけである。
以上
牧水の酒にかかわる歌が庶民的な酒飲みを歌った感がするが、こちらは酒賛歌そのもので、スケールが大きいのが解かる。やや独断的な気もするが。再度一首づつ味わってみます。酒飲みの正当化の武装理論の勉強を兼ねて。
大伴 家持(おおとも の やかもち、養老2年(718年)頃 - 延暦4年8月28日(785年10月5日))は奈良時代の貴族・歌人。大納言・大伴旅人の子。官位は従三位・中納言。三十六歌仙の一人。長歌・短歌など合計473首が『万葉集』に収められており、『万葉集』全体の1割を超えている。このことから家持が『万葉集』の編纂に拘わったと考えられている。・・・・・日本最古の歌集「万葉集」は、大伴家持という一官人の手によって集大成され、完成形を与えられた。全二十巻のうち、最後の四巻は家持自身が自分のために書きためた私的な歌日記である。・・・・・との解説もある。家持が旺盛な作歌活動を示し、また万葉集の編纂に取り組んだのは、越中国司時代だとされる。彼は29歳のときにこの任に赴き、数年間越中に留まった。この間に、彼は先人たちの残した業績を歌集として編纂すると同時に、身辺から集めた歌や、自ら歌った歌を精力的に書き溜めた。それらが、今日に伝わる万葉集として結実したのだと思われる。
以上参考に
某新聞に斉藤茂吉の記事があり、歌が幾つか載っており、それをきっかけに歌集に目を通していましたが、何が良くて、評価されているか恥ずかしながら読解力の無さか、よく解からず。以前箱根の強羅に紫陽花列車で行ったことがありますが(平成23年6月)、その時に歌碑(
おのづから寂しくもあるかゆふぐれて雲は大きく谿に沈みぬ
-大正14ともしび)のあったこともあり、茂吉の経歴を確認すると伴に、その時々の歌集を把握して行けばもう少し理解が出来るのではと思い、今まで同様簡単なメモ程度にここにまとめてみました。
某新聞とは
2013年6月1日 日本経済新聞「文化」にタイトル 斎藤茂吉 新たな輝き 歌集「赤光」刊行100年
---茂吉の業績を振り返る全国短歌コンクール、記念のシンポジウムが開かれ、ベテランから若手まで、茂吉の現代的な表現に改めて学ぼうとしている。---
この時に諸々の茂吉の短歌の見方を載せてありました。掻い摘んで見ると
若手の歌人には 自分の居場所をどうやって見つけるか手探りしている、自分の立ち位置の指標になっている。茂吉の歌には---見える我への執着と多様な表現への挑戦--があるとのこと
其の他幾つかの見方を歌を挙げて解説されていたので参考に載せました。
1 出し抜けの飛躍 茂吉の文学の不思議な魅力(実験的)「赤光」
ゴオガンの自画像みればみちのくに山蚕(やまこ)殺ししその日おもほゆ
2 映像的 走っている茂吉のカメラで暗い道だけを移動撮影しているような印象「赤光」
ひた走るわが道暗ししんしんと堪(こら)へかねたるわが道暗し
3 リアルの塊みたい 言葉の向こうに茂吉という生き物がうごめいている「赤光」
ひとり居て朝の飯(いい)食(は)む我が命は短かからむと思ひて飯はむ
自分としては写生短歌がMAINの人かと。柿本人麻呂の研究をしており、和歌の古典的なものを近代短歌として表現しているのではと思うのですが。歌の多くに自然と向き合い、それを素直に、日記調に詠っているのが目立つ。歌の師伊藤左千夫(その師は松岡子規)の影響がありそうなのでそのうち両人の歌も読んで見ようと思います。はっきりいえることは、以上の三首を読んでも解説にあるようには自分の力では理解は出来ず力量不足を痛感。自分としては「こころの琴線」に自然に触れてくるもの、「普遍的な歌」をよしとするので悲観するに当らずと自己弁護するしかない。
| 1882年(明15)5月14日(戸籍では7月27日 | 山形県南村山郡金瓶(かなかめ)村=現上山(かみのやま)市金瓶=の農家守谷伝右衛門の三男として生まれました。金瓶は蔵王連峰を東に仰ぐ仏教信仰の厚い養蚕の村で、その自然に親しみながら素朴な農家の子として育った茂吉は、菩提寺であった宝泉寺の住職や周囲の人々の影響で、宗教心や書画などへの関心を芽生えさせました |
| 1896年(明29)14歳 | 茂吉の資質を目にとめていた住職の仲介で、東京浅草で淺草医院を開業していた同郷出身の斎藤紀一のもとに寄寓し、開成尋常中学校(現在の開成中学校・高等学校)に編入学 上京した茂吉は開成中学から旧制第一高校(東京大学の前身)へと進学します。第三学部(医学部)の学生となった |
| 1905年(明38)23歳 | 斎藤家の婿養子として入籍(23歳)、1910年(明43)卒業 |
| 1906年(明39)24歳 | 子規の流れを汲む伊藤左千夫に入門し、本格的に短歌の道を歩み初めます。歌誌「馬酔木」が「アララギ」へと変わってからはその中心的な歌人となりました。 |
| 1910年(明43・28歳) | 東京帝国大学医科を卒業した茂吉は、同大学助手として付属巣鴨病院に勤め精神医学を専攻 |
| 1913年(大2)30歳 | 第一歌集『赤光』(しゃっこう)を発表し、大きな反響をよびました |
| 1914年(大3)31歳 | 斎藤紀一の二女輝子と結婚 |
| 1917年(大正6)35歳 | 長崎医学専門学校の教授に任じられ長崎に赴任 |
| 1921年(大10)39歳 | 精神医学と法医学を講じた後、同年10月渡欧留学。オーストリアのウィーン大学、その後ドイツのミュンヘンの国立精神病学研究所で研究を 第2歌集『あらたま』を出版 |
| 1927年(昭2)45歳 | 再建した帝国脳病院の院長となります。翌年、養父紀一が死去。そして戦時色が濃くなってゆくなか、平福百穂、中村憲吉など心を通じ合った歌友との死別、妻のスキャンダルなどの心痛事に次々と襲われます。それらを堪えるよすがとするかのように取り組んだのが柿本人麿の研究 |
| 1934年(昭9) | 『柿本人麻呂(総論篇)』をはじめ1940年(昭15)の『柿本人麻呂(雑纂篇)』まで全5冊の出版となって結実します。この業績により、帝国学士院賞を受賞しました。 |
| 1940年発刊58歳 | 歌集『暁紅』(1940年発刊)の作中に反映されることとなる永井ふさ子との出会いや、激しさを増してゆく戦時の色に準じて多くの戦争詠などの作品を残した |
| 1945年(昭20)63歳 | 3月の東京大空襲の翌月、茂吉はふるさとの金瓶に疎開、そこで終戦を迎えます。翌年、芭蕉の足跡が残る最上川畔の大石田町へと移り、蔵王や最上川の自然に育まれたふるさとの風土と人々の真心につつまれ、歌集『小園』・『白き山』(1949年出版)に結晶する数多くの秀歌を詠み続けたのでした。 |
| 1947年(昭22) | 11月に東京に戻る |
| 1949年出版 | 歌集『小園』・『白き山』 |
| 1951年(昭26)69歳 | 文化勲章を受章(69歳)。翌年には「斎藤茂吉全集」全56巻(岩波書店)も発行され、茂吉はようやく晴れがましい日々を取り戻します |
| 1953年(昭28)2月25日71歳 | 、新宿大京町の自宅で心臓ぜんそくに見舞われて死去 |
HP{短歌案内}に載っている歌集
| 赤光(しゃっこう) | 明治38年~大正2年8月(23歳~31歳)834首 |
本格的に作歌をはじめた頃の明治38年(23歳)から、実母いくと歌の師伊藤左千夫が死去した大正2年8月(31歳)に至る9年間の作品834首を逆年順に収載し、大正2年10月15日東雲堂書店よりアララギ叢書第2篇として発刊(初版)した。芥川龍之介・佐藤春夫など歌壇以外にも広く注目をあび高く評価され大正8年まで5版を重ねる。 歌集名『赤光』は、仏説阿弥陀経「黄色黄光赤色赤光白色白光」から採ったもの |
| あらたま | 大正2年9月~大正6年 746首 (31歳~35歳) |
東京帝国大学医科大学助手・付属病院勤務の頃の大正2年9月(31歳)から、養父紀一の次女輝子と結婚し青山脳病院を継ぐことが運命づけられた大正3年を経、長崎医学専門学校に赴任した大正6年12月(35歳)までの作品746首が作歌年順に収められている。 歌集名『あらたま』は、茂吉が敬愛する一人森鴎外の文章中「次第に璞(あらたま)から玉が出来るやうに…」から採ったことが編集手記に記されてあり、茂吉自身もその中で「僕は自分の歌集が佳い内容を有つてゐることを其の名が何となし指示してゐるやうな気がして秘かに喜んでゐた。云々」と述べている。 |
| ともしび | 大正14年1月~昭和3年 912首 (43歳~46歳) |
渡欧留学を終えて、神戸に帰着し上京途次の大正14年1月(43歳)から再建した病院の院長の職に就くなど多忙な生活を送っていた頃の昭和3年(46歳)までの歌907首。帰国途次に焼失した病院再建、歌友島木赤彦没後の「アララギ」発行に尽力、養父紀一の死去など、苦難の日々を送りながら作歌意欲に燃え、茂吉自身「辛うじて作歌をつづけることが出来、(中略)飛躍は無かつたが、西洋で作つたもののやうな、日記の域から脱することが出来た。」と述べている 集名『ともしび』は、「艱難暗澹たる生に、辛うじて『ともしび』をとぼして歩くといふやうな暗指でもあつただらうか。」と後記中に記している |
| 白桃(しろもも) | 昭和8年~昭和9年 1033首 (51歳~52歳) |
親交した平福百穂と中村憲吉との死別、妻の私行に関する新聞記事が出たりするなど、相次ぐ精神的負傷が多かった頃であったが、歌論研究に没頭して『柿本人麿』(総論編)の刊行と蔵王山上歌碑の一首「陸奥(みちのく)をふたわけざまに聳(そび)えたまふ蔵王(ざわう)の山(やま)の雲の中に立つ」など、代表的作品が多く作られた時期でもある。 『白桃』は歌集に収載されている歌「ただひとつ惜(を)しみて置きし白桃(しろもも)のゆたけきを吾(われ)は食(く)ひをはりけり」の一首に因んでつけられた名である |
| 暁紅(ぎょうこう) | 昭和10年~昭和11年 968首 (53歳~54歳) |
、「昭和八年昭和九年あたりの歌に比して、幾分変化の跡を見ることが出来るやうにおもふ。ひとつは抒情詩としての主観に少しく動きを認め得るのではないかと思ふ」と作者自らが或る新しい抒情の心持が現れて来たことを言っているとおり、「ガレージへトラックひとつ入らむとす少しためらひ入りて行きたり」などの意図ある作品が見られる |
| 白き山 | 昭和21年~昭和22年 850首 (64歳~65歳) |
郷里金瓶から大石田に移居した昭和21年(64歳)から、昭和22年
(65歳)暮に帰京するまでの大石田滞在期間の歌824首(『全集』では増補のため編集清書してあった「紅色の靄」23首と、「酒田」補遺3首を加え850首となる)を収め、昭和24年8月20日岩波書店よりアララギ叢書第138篇として発刊した 作歌については、「従来の手法どほりのものもあり、いくらか工夫、変化を試みたものもある。出来のわるいものもあり幾分出来のいいのもある」と自評しているが、「最上川逆白波(さかしらなみ)のたつまでにふぶくゆふべとなりにけるかも」など、この歌集の特徴とされる病臥後の新たな作歌意欲、積極的工夫・変化の努力と、ひたむきな最上川詠が各処に見られ、そのため茂吉の代表作とされる歌も多い 昭和23年7月から8月にかけて整理清書されたもので、歌集の名『白き山』は「別にたいした意味はない。大石田を中心とする山々に雪つもり、白くていかにも美しいからである。」と後記中で述べている |
某HPに茂吉の素顔を知る内容があり、参考になる
妻輝子とは
結婚前の歌2首
茂吉の結婚した相手は輝子(1914年斎藤紀一の二女輝子と結婚)
性格が全然違っていた様です。
二人の長男齋藤茂太さんが「茂吉と輝子」(『回想の父茂吉 母輝子』所収)に書いている。父は「内省的かつ非主導的であり、内向性」、母は「非内省的で主導権をにぎり、外向性」であると分析していう。「基本的には茂吉と輝子は「油と水」の関係である」「これは常識的に会いっこない夫婦である」「両者の最悪の要因はニュアンスは異なるが頑固で融通が利かない点にある。さらに要求水準が高い点も共通している」云々。そしてこう加えている。「輝子への不満が茂吉の文学活動を大きく推進したという考え方も成立する」
「医博、課長夫人等々 不倫・恋のステップ 銀座ホールの不良教師検挙で 有閑女群の醜行暴露」(東京朝日新聞)
有閑女群のなかに、青山脳病院長でアララギ派の歌人齋藤茂吉医学博士夫人の名前も……。
茂吉は輝子に別居を命じる。さらに反省を求め、輝子を郷里上山の弟が経営する旅館「山城屋」に預ける。そして茂吉は心痛を紛らわせるように人麿研究に邁進する
永井ふさこ との出会い
明治四十三年、ふさ子は愛媛県松山市に医院の四女として生まれる。子規と遠縁に当たる。アララギに入会したてで、歌会への参加は初めてだったが、子規との縁で話が弾んだらしい。ときに茂吉五十二歳、ふさ子二十四歳。ふさ子は茂吉の家庭事情を知り、同情がやがて恋情へとうつろってゆく。平成四年、生涯嫁ぐこなく、ふさ子死去。享年八十三。
合作の歌(上の句 茂吉 下の句 ふさこ)
光放つ神に守られもろともに あはれひとつの息を息づく
この一首を評して茂吉は言った。「人麿以上だ」
こんな一首も詠まれている
狼になりてねたましき咽笛を噛み切らむとき心和まむ
ふさ子に茂吉が送った書簡は百五十通にのぼり、その都度、恋歌が添えられてあった。読み終わった後は必ず焼却するように求められ、ふさ子はそれを誓った。(ふさ子が焼いたのは僅かで、百三十通余りは持ち続けた)
○四国なるをとめ恋しもぬば玉の夢にもわれにえみかたまけて
○こいしさのはげしき夜半は天雲をい飛びわたりて口吸わましを
○白玉のにほふをとめをあまのはらいくへのおくにおくぞかなしき
茂吉の十周忌にすべての恋文が「小説中央公論」に公表され、歌壇は騒然となる。ふさ子は終世、独り身を通す。「茂吉ほどの人に愛された以上、他の人の愛を受け入れることはできない」彼女はその信念を貫いたのである。平成五年、八十三歳で亡くなっている。松山市御幸の長建寺にふさ子の一人墓がある。永井家累代の墓に入らず、間を置いた場所に小さな墓はひっそりと佇む
以上こんなことがあったんだ。茂吉の歌を読む上での参考になれば
母を看取る
五十九歳で世を去った母親へ寄せる彼の想いは深く、「死に給う母」五十九首は不朽の名作として世評が高い。
「赤口」
齋藤茂吉「死にたまふ母」(初版『赤光』による)
死にたまふ母
大正2年5月16日、茂吉は母 ・守谷いく危篤の報に接し急遽帰省、23日その死を見送りました。
その後、酢川温泉(今の蔵王温泉)に2泊して 母を偲び、30日帰京しました。
茂吉31歳(満年齢)、東京帝国大学医科大 学の助手として附属病院(東京府巣鴨病院)に勤務
其の一 (母危篤の報を受けて上山停車場に着くまで)
ひろき葉は樹にひるがへり光りつつかくろひにつつしづ心なけれ
白ふぢの垂花(たりはな)ちればしみじみと今はその實(み)の見えそめしかも
みちのくの母のいのちを一目(ひとめ)見ん一目みんとぞいそぐなりけれ
うち日さす都の夜(よる)に灯(ひ)はともりあかかりければいそぐなりけり
ははが目を一目を見んと急ぎたるわが額(ぬか)のへに汗いでにけり
灯(ともし)あかき都をいでてゆく姿(すがた)かりそめ旅とひと見るらんか
たまゆらに眠(ねむ)りしかなや走りたる汽車ぬちにして眠りしかなや
吾妻(あづま)やまに雪かがやけばみちのくの我(わ)が母の國に汽車入りにけり
朝さむみ桑の木の葉に霜ふれど母にちかづく汽車走るなり
沼の上にかぎろふ靑き光よりわれの愁(うれへ)の來むと云(い)ふかや
上(かみ)の山(やま)の停車場に下り若(わか)くしていまは鰥夫(やもを)のおとうと見たり
其の二 (母の傍らにあっての看護とその死)
はるばると藥(くすり)をもちて來(こ)しわれを目守(まも)りたまへりわれは子(こ)なれば
寄り添へる吾を目守(まも)りて言ひたまふ何かいひたまふわれは子なれば
長押(なげし)なる丹(に)ぬりの槍に塵は見ゆ母の邊(べ)の我(わ)が朝目(あさめ)には見ゆ
山いづる太陽光(たいやうくわう)を拜みたりをだまきの花咲きつづきたり
死に近き母に添寝(そひね)のしんしんと遠田(とほた)のかはづ天(てん)に聞(きこ)ゆる
桑の香の靑くただよふ朝明(あさあけ)に堪(た)へがたければ母呼びにけり
死に近き母が目(め)に寄(よ)りをだまきの花咲きたりといひにけるかな
春なればひかり流れてうらがなし今は野(ぬ)のべに蟆子(ぶと)も生(あ)れしか
死に近き母が額(ひたひ)を撫(さす)りつつ涙ながれて居たりけるかな
母が目をしまし離(か)れ來て目守(まも)りたりあな悲しもよ?(かふこ)のねむり
我が母よ死にたまひゆく我(わ)が母よ我(わ)を生(う)まし乳足(ちた)らひし母よ
のど赤き玄鳥(つばくらめ)ふたつ屋梁(はり)にゐて足乳(たらち)ねの母は死にたまふなり
いのちある人あつまりて我が母のいのち死行(しゆ)くを見たり死ゆくを
ひとり來て?(かふこ)のへやに立ちたれば我(わ)が寂しさは極まりにけり
其の三 (母の火葬)
楢(なら)わか葉照りひるがへるうつつなに山?(やまこ)は靑(あを)く生(あ)れぬ山?は
日のひかり斑(はだ)らに漏りてうら悲(がな)し山?は未(いま)だ小さかりけり
葬(はふ)り道(みち)すかんぼの華(はな)ほほけつつ葬り道べに散りにけらずや
おきな草口(くち)あかく咲く野の道に光ながれて我(われ)ら行きつも
わが母を燒(や)かねばならぬ火を持てり天(あま)つ空(そら)には見るものもなし
星のゐる夜ぞらのもとに赤赤とははそはの母は燃えゆきにけり
さ夜ふかく母を葬(はふ)りの火を見ればただ赤くもぞ燃えにけるかも
はふり火を守(まも)りこよひは更けにけり今夜(こよひ)の天(てん)のいつくしきかも
火を守(も)りてさ夜ふけぬれば弟は現身(うつしみ)のうた歌ふかなしく
ひた心目守(まも)らんものかほの赤くのぼるけむりのその煙(けむり)はや
灰のなかに母をひろへり朝日子(あさひこ)ののぼるがなかに母をひろへり
蕗の葉に丁寧に集めし骨くづもみな骨瓶(こつがめ)に入れ仕舞ひけり
うらうらと天(てん)に雲雀は啼きのぼり雪斑(はだ)らなる山に雲ゐず
どくだみも薊(あざみ)の花も燒けゐたり人葬所(ひとはふりど)の天(あめ)明(あ)けぬれば
其の四 (酢川温泉(今の蔵王温泉)に2泊して母を偲び、30日帰京 茂吉31歳)
かぎろひの春なりければ木の芽みな吹き出(いづ)る山べ行きゆくわれよ
ほのかにも通草(あけび)の花の散りぬれば山鳩のこゑ現(うつつ)なるかな
山かげに雉子が啼きたり山かげの酸(す)つぱき湯こそかなしかりけれ
酸(さん)の湯に身はすつぽりと浸りゐて空にかがやく光を見たり
ふるさとのわぎへの里にかへり來て白ふぢの花ひでて食ひけり
山かげに消(け)のこる雪のかなしさに笹かき分けて急ぐなりけり
笹はらをただかき分けて行きゆけど母を尋ねんわれならなくに
火のやまの麓にいづる酸(さん)の温泉(ゆ)に一夜(ひとよ)ひたりてかなしみにけり
ほのかなる花の散りにし山のべを霞ながれて行きにけるはも
はるけくも峽(はざま)のやまに燃ゆる火のくれなゐと我(あ)が母と悲しき
山腹(やまはら)に燃ゆる火なれば赤赤とけむりはうごくかなしかれども
たらの芽を摘みつつ行けり寂しさはわれよりほかのものとかはしる
寂しさに堪へて分け入る我が目には黑ぐろと通草の花ちりにけり
見はるかす山腹なだり咲きてゐる辛夷(こぶし)の花はほのかなるかも
蔵王山(ざわうさん)に斑(はだ)ら雪かもかがやくと夕さりくれば岨(そば)ゆきにけり
しみじみと雨降りゐたり山のべの土赤くしてあはれなるかも
遠天(をんてん)を流らふ雲にたまきはる命(いのち)は無しと云へばかなしき
やま峽(かひ)に日はとつぷりと暮れたれば今は湯の香(か)の深かりしかも
湯どころに二夜(ふたよ)ねぶりて蓴菜(じゆんさい)を食へばさらさらに悲しみにけれ
山ゆゑに笹竹の子を食(く)ひにけりははそはの母よははそはの母よ (五月作)
「白き山」
(64歳~65歳)今の自分に近いころの作品で、最上川とか自分が昔3年を過ごした秋田の鳥海山、酒田、男鹿半島や田沢湖など懐かしく想い、この歌集を興味をもって読む。自分の生まれたころの作品でもあるらしい。自分には冨士の山や天城の山、愛鷹山や香貫山、箱根の山や駿河湾など自然との接点はいくつもありこの地で生まれたことを感謝感謝。以下に幾つかの歌を挙げてみました。
雪ふりて白き山よりいづる日の光に今朝は照らされてゐぬ
山峡を好みてわれはのぼり来ぬ雪の氷柱のうつくしくして
みちのくに生れしわれは親しみぬ蔵王のやま鳥海のやま
彼岸に何をもとむるよひ闇の最上川のうへのひとつ蛍は
うつせみは常なきものと知りしかど君みまかりてかかる悲しさ
ながらへてあれば涙のいづるまで最上の川の春ををしまむ
かぎりなく稔らむとする田のあひの秋の光にわれは歩める
秋の日は対岸の山に落ちゆきて一日ははやし日月ははやし
つばくらめいまだ最上川にひるがへり遊ぶを見れば物な思ひそ
日ごと夜毎いそぐがごとく赤くなりしもみぢの上に降る山の雨
いただきに黄金のごとき光もちて鳥海の山ゆふぐれむとす
栗の實の落ちつくしたる秋山をわれは歩めりときどきかがみて
最上川逆白波のたつまでにふぶくゆふべとなりにけるかも
人皆のなげく時代に生きのこりわが眉の毛も白くなりにき
あまづたふ日は高きより照らせども最上川の浪しづまりかねつ
最上川の流れのうへに浮かびゆけ行方なきわれのこころの貧困
最上川のながれの上に冬虹のたてるを見れば春は来むかふ
もも鳥が峡をいづらむ時とへど鳥海の山しろくかがやく
谷うつぎむらがり咲きて山越ゆるわれに見しむと言へるに似たり
猿羽根峠ののぼりきはめしひと時を汗はながれていにしへ思ほゆ
したしくも海苔につつみしにぎり飯さばね越えきて取りいだすなり
太蕗の並みたつうへに降りそそぐ秋田の梅雨見るべかりけり
あかあかと開けはじむる西ぞらに男鹿半島の低山うかぶ
おほどかに春は逝かむと田沢湖の大森山ゆ蝉のこゑする
山を越え峡をわたりて来し人らいつくしみあふ古りし代のごと
あけび一つ机の上に載せて見つ惜しみ居れども明日は食はむか
りんだうの匂へる山に入りにけり二たびを来む吾ならなくに
象潟の海のなぎさに人稀にそそぐ川ひとつ古き世よりの川
最上川の水嵩ましたる彼岸の高き平に穂萱なみだつ
もみぢ葉のからくれなゐの溶くるまで山の光はさしわたりけり
はるかなる南の方へ晴れとほる空ふりさけて名残を惜しむ
以前より童謡作家、作詞家として名は聞いており、啄木、牧水、茂吉を調べていると歌人としても取り上げられている。そこで改めて白秋について調べてみようと思いました。童謡をはじめ懐かしの童謡歌が相当にあり、新たな詠い方が展開されてはいないか、興味のあるところです。
年譜
| 1885年(明治18年)1月25日 | 熊本の南関に生まれ、まもなく福岡の柳川にある家に帰る。父・長太郎、母・シケ。北原家は江戸時代以来栄えた商家(油屋また古問屋と号し、海産物問屋であった)で、当時は主に酒造を業としていた |
| 1897年(明治30年) | 柳河高等小学校より県立伝習館中学(現・福岡県立伝習館高等学校)に進むも、1899年(明治32年)には成績下落のため落第。この頃より詩歌に熱中し、雑誌『文庫』『明星』などを濫読する。ことに明星派に傾倒したとされている。 |
| 1904年(明治37年) | 無断で中学を退学し、早稲田大学英文科予科に入学。上京後、同郷の好によって若山牧水と親しく交わるようになる。この頃、号を「射水(しゃすい)」と称し、同じく友人の中林蘇水・牧水と共に「早稲田の三水」と呼ばれた。 |
| 1906年(明治39年)21歳 | 与謝野鉄幹、与謝野晶子、木下杢太郎、石川啄木らと知り合う。 |
| 1907年(明治40年) | 鉄幹らと九州に遊び(『五足の靴』参照)、南蛮趣味に目覚める。また森鴎外によって観潮楼歌会に招かれ、斎藤茂吉らアララギ派歌人とも面識を得るようになった。 |
| 1908年(明治41年) | 新詩社を脱退した。木下杢太郎を介して、石井柏亭らのパンの会に参加。この会には吉井勇、高村光太郎らも加わり、象徴主義、耽美主義的詩風を志向する文学運動の拠点になった。 |
| 1909年(明治42年)24歳 | 処女詩集『邪宗門』上梓。官能的、唯美的な象徴詩作品が話題となるも、年末には実家が破産し、一時帰郷を余儀なくされた。 |
| 1912年(明治45年・大正元年) | 母と弟妹を東京に呼び寄せ、年末には一人故郷に残っていた父も上京する。白秋は隣家にいた松下俊子と恋に落ちたが、俊子は夫と別居中の人妻だった。2人は夫から姦通罪により告訴され、未決監に拘置された。2週間後、弟らの尽力により釈放され、後に和解が成立して告訴は取り下げられた |
| 1913年(大正2年)29歳 | 初めての歌集『桐の花』と、詩集『東京景物詩及其他』を刊行。特に『桐の花』で明星派のやわらかな抒情をよく咀嚼した歌風を見せ、これによって白秋は歌壇でも独特の位置を占めるようになる。春、俊子と結婚。 |
| 1914年(大正3年) | 肺結核に罹患した俊子のために小笠原父島に移住するも、ほどなく帰京。父母と俊子との折り合いが悪く、ついに離婚に至る。1916年(大正5年)、江口章子と結婚し、葛飾紫烟草舎に転居 |
| 1917年(大正6年)33歳 | 小田原に転居。鈴木三重吉の慫慂(しょうよう、しきりに強く勧める事の意味)により『赤い鳥』の童謡、児童詩欄を担当。優れた童謡作品を次々と発表 |
| 1920年(大正9年)35歳 | 『白秋詩集』刊行開始。伝肇寺境内の住宅の隣に山荘を新築した際の祝宴は、小田原の芸者総出という派手なものであった。それに白秋の生活を金銭的に支えて来た弟らが反発し、章子を非難する。着物ほとんどを質入れしたと言う章子は非難されるいわれもなく反発。章子はその晩行方をくらまし、白秋が不貞を疑い章子と離婚 |
| 1921年(大正10年) | 佐藤菊子(国柱会会員、田中智學のもとで仕事)と結婚。長男・隆太郎誕生。文化学院で講師となる。また山田耕筰と共に『詩と音楽』を創刊。山田とのコンビで数々の童謡の傑作を世に送り出す |
| 1924年(大正13年) | 田中智學の招きで両親、妻菊子、長男隆太郎らとともに静岡県三保の田中智學の最勝閣へ旅行、龍華寺、羽衣の松などを観光、長歌1首、短歌173首を作る。同年短歌雑誌『日光』を創刊。反アララギ派の歌人が大同団結し、象徴主義的歌風を目指す。 |
| 1930年(昭和5年) | 南満洲鉄道の招聘により満洲旅行 |
| 1935年(昭和10年)50歳 | 新幽玄体を標榜して多磨短歌会を結成し、歌誌『多磨』を創刊する。大阪毎日新聞の委託により朝鮮旅行。この年、50歳を祝う催しが盛大に行われる |
| 1937年(昭和12年)52歳 | 糖尿病および腎臓病の合併症のために眼底出血を引き起こし、入院。視力はほとんど失われたが、さらに歌作に没頭する |
| 1941年(昭和16年) | 、数十年ぶりに柳川に帰郷し、南関で叔父のお墓参りをし、さらに宮崎、奈良を巡遊。またこの年、芸術院会員に就任するも、年末にかけて病状が悪化 |
| 1942年(昭和17年)57歳 | 11月2日逝去。享年57。墓所は多磨霊園(東京都府中市)にある。 |
作品
歌集
北原白秋 歌集 解説に以下のコメント(某HPより)
白秋短歌の流れを全体的に眺めると,動から静へ,絢爛から枯淡へ,小から大へ,というふうに変化している.そうして,変わることなく一貫しているのは,言葉の響きの美しさ,しなやかさである.現実の強い手ざわり,という点では物足りなさを覚える人もあろうが,リアリズムは白秋の目指すところではなかった.自分の心をあらわす言葉をいかに〈音楽〉に近づけるか.それがこの歌人の最も究めたかったことのように私には思われる
以下に各々の歌集の中より幾つか独断で選歌してみました。
桐の花
白秋の隣家に俊子という美しい人妻が住んでいました。彼女は夫から暴力を受けており、白秋は彼女をいつも気遣っていました。ある日俊子への想いの強さに耐えきれなくなった白秋は、引っ越しをするのですが、しばらくすると夫に離婚宣言をされた俊子が転居先を訪ねてきます。離婚したと聞き白秋は俊子と一夜を共にするのですが、俊子の元夫は法的にはまだ離婚が成立していないことを理由に姦通罪で二人を訴えました。白秋は2週間ほど拘置されたのち、家族の尽力ものおかげで釈放されました。しかしこのスキャンダルによって、世間の評判はがた落ちし、同業の詩人・歌人からも罵倒されることになってしまいました。さらに同時期に裕福であった白秋の生家が没落し、莫大な借金が白秋の肩にのしかかってくることになります。
枇杷の木に黄なる枇杷の実かがやくとわれ驚きて飛びくつがへる 『桐の花』
君と見て一期の別れする時もダリヤは紅しダリヤは紅し 『桐の花』
わがゆめはおいらん草の香のごとし雨ふれば濡れ風吹けばちる 『桐の花』
雲母集
白秋は雲母集発表の際にこの作品についてこういう風に述べています。
『此の雲母集一巻は純然たる三崎歌集である。而してこれらの歌が全く自分のものであり、私の信念が又、真実に自分の心の底から燦めき出したものに相違ないといふ事は、自分ながらただただ難有く感謝してゐる。自分を救ふものは矢張自分自身である・』(雲母集余言より)
深潭(しんたん)の崖の上なる赤躑躅(あかつつじ)二人ばつかり照らしけるかも 『雲母集』
水の面に白きむく犬姿うつし口には燃ゆる紅の肉 『雲母集』
わが父を深く怨むと鰻籠蹴りころばしてゐたりけりわれ 『雲母集』
秋の田の稲の刈穂の新藁の積藁のかげに誰か居るぞも『雲母集』
しみじみと海に雨ふり澪の雨利休鼠となりてけるかも『雲母集』
一心に遊ぶ子どもの聲すなり赤きとまやの秋の夕ぐれ『雲母集』
雀の卵
二度目の妻を迎え、どん底生活と闘いながらも、新しい歌境を求めて苦吟に苦吟を重ねた時代でもあったのです。葛飾における苦境について自らこの歌集の大序の中で、「私と妻は食うや食わずになった。着のみ着のままになった。私は詩作のために親には不幸の子となった。弟妹には不信の兄になった。しかして私の妻を飢えさせ、その衣をはいだ」、「つくづく慕わしいのは芭蕉である。光悦である。利休である。私はどうかしてあそこまで行きたい」とも言ってます。白秋はこの歌集で日本的、古典的なものへの思慕を強め、新しい幽玄の境地を切り拓いています。この歌集における雀たちは、白秋をそうした幽玄の歌境に導く小さな天使たちであったのです。
父嶋よ仰ぎ見すれば父恋し母嶋見れば母ぞ恋しき『雀の卵』
しら玉の雀の卵寂しければ人に知られで春過ぎむとす『雀の卵』
寒天に吹きさらさるるいちゐの木いちゐひびけりふかき夜霜に『雀の卵』
薄野に白くかぼそく立つ煙あはれなれども消すよしもなし『雀の卵』
霧雨のこまかにかかる猫柳つくづく見れば春たけにけり『雀の卵』
貧しさに堪へてさびしく一本の竹を植ゑ居りこのあかつきに『雀の卵』
海阪(うなさか)
この空の澄みの寒さや満月の辺に立ち騰る黄金の火の立『海阪』
印旛沼津々の荻原風ふけば見ゆるかぎりが皆そよぐなり『海阪』
軒並は旅籠の名のみゆゆしくてこの追分の宿も荒れたり『海阪』
馬子ぶしの古き追分夕陽さしぺんぺん草の二三本の花『海阪』
雪しろくいとど晴れたれ御殿場の真上の不二は低く厚く見ゆ『海阪』
天つ辺にただに凌げば不二が嶺のいただき白う冴えにけるかも『海阪』
ひさかたの天つをとめがゆり掛けし羽ごろもの松はこれのこの松『海阪』
時化後の海ひたくらし向ひ立つ女の子がふふむほほづきの音『海阪』
まなかひに落ち来る濤の後濤の立ちきほひたる峯のゆゆしさ『海阪』
あの光るのは千曲川ですと指さした山高帽の野菜くさい手 『海阪』
黒檜
照る月の冷えさだかなるあかり戸に眼凝らしつつ盲ひてゆくなり『黒檜』
吾が犬の呆けてあくなきい寝ざまにうらら春日の照りこそなごめ『黒檜』
蝶の飛ぶ春なるかなと見てをるを小鳥ぞといふ微笑尽きず『黒檜』
鳥籠に黒き蔽布(おほひ)をかけしめて灯は消しにけり今は寝ななむ 『黒檜』
くわうくわうと鴨は呼べどもよるべなき池のまなかの水の上にして 『橡』
白秋の歌に付き、解説とか、感想は不要の気がします。言葉の響や表現はまさに作詞家のそれであり、十分に味わうことで彼の心情が理解できる。
歌人として「釈 迢空」(しゃくちょうくう)の名が気になっており、近代歌人のマトメとして知る必要があるようです。
折口 信夫(おりぐちしのぶ) 明治20年(1887年)2月11日~昭和28年(1953年)9月3日民俗学者、国文学者、「釈 迢空」と号した詩人、歌人。
歌人としては、正岡子規の「根岸短歌会」、後「アララギ」に「釈迢空」の名で参加し、作歌や選歌をしたが、やがて自己 の作風と乖離し、アララギを退会する。1924年(大正13年)北原白秋と同門の古泉千樫らと共に反アララギ派を結成して『日光』を創刊した。
経歴は後で調べるとして、気にかかっていることは彼の歌論、歌人論です。青空文庫で調べてみると
歌の円寂する時(歌論)
世々の人々(歌人論)
以上を万葉集の口語訳、国文学者としての知性からどのように考えているか、調べようと思いました。自分も最近歌の本質は何なのか疑問に思う時もあり、今までは歌の麗しさ、心の琴線に触れる歌、永遠性の歌、調べ、リズムのある歌が良いのかなと思っていました。現代の歌人は知らず、歌を読んだことがないのですが、色々新聞の文芸欄に投稿されている歌を目にするに付け感銘するとこもあるが、ちょっと違和感もある。自分の能力不足を感じているこの頃、この方の歌論、歌人論を理解することは今後の自分の指針になりはしないか。自分なりにここでまとめて見ようと思います。
とり合えず以下の歌集があるそうです。
以下の歌が代表歌として取り上げてあったHPがありました
海やまのあひだ
日本の歌人、釈迢空の最初の個人歌集。276頁、歌数691首。1925年5月30日に改造社より出版。
葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり
たびごゝろもろくなり来ぬ。志摩のはて 安乗の崎に、灯の明り見ゆ
大正12年、釈迢空(シャクチョウクウ)は『供養塔』という五首の連作をしました。
その冒頭にある一首です。
ついている詞書(コトバガキ…説明文)です。
「数多い馬塚の中に、ま新しい馬頭観音(バトウカンノン…冠に馬がいる観音様)の石塔婆の立ってゐるのは、あはれである。
又殆(ホトン)ど、峠毎に、旅死にの墓がある。
中には、業病(ゴウビョウ…快癒の難しい病気)の姿を家から隠して、死ぬまでの出た人のなどもある。」
残りの4首
道に死ぬる馬は、仏となりにけり。行くとどまらむ旅ならなくに
邑(ムラ)山の松の木(コ)むらに、日はあたり ひそけきかもよ。旅人の墓
ひそかなる心をもりて、をはりけむ。命のきはに、言うこともなく
ゆきつきて 道にたふるゝ生き物のかそけき墓は、草つゝみたり
いきどほる心すべなし。手にすゑて、蟹のはさみをもぎはなちたり
水底に、うつそみの面わ沈透(シヅ)き見ゆ。來む世も、我の寂しくあらむ
谷々に、家居ちりぼひ ひそけさよ。山の木の間に息づく。われは
春のことぶれ
道なかに人かへりみずたちつくす道祖神とわれとさびしと言はむ
櫻の花ちりじりにしもわかれ行く遠きひとりと君もなりなむ
歌の円寂する時(歌論)
<<歌論の中で述べてある文章の一部部分を抜粋して、後で検討する時の参考までに載せました。>>
畏友(いゆう)島木赤彦を、湖に臨む山墓に葬った.
はなやかであった万葉復興の時勢が、ここに来て向きを換えるのではないか
批評のない歌壇
近い将来に、歌がどうなって行こうとして居るか、其が言うて見たい。まず歌壇の人たちの中で、憚(はばか)りなく言うてよいことは、歌はこの上伸びようがないと言うことである。更に、も少し臆面ない私見を申し上げれば、歌は既に滅びかけて居ると言う事である。
真の意味の批評の一向出て来ないことである
歌壇に唯今、専ら行われて居る、あの分解的な微に入り、細に入り、作者の内的な動揺を洞察――時としては邪推さえしてまで、丁寧心切を極めて居る批評は、批評と認めない
主題と言うものは、人生及び個々の生命の事に絡んで、主として作家の気分にのしかかって来た問題――と見る事すら作家の意識にはない事が多い――なのである。其をとり出して具体化する事が、批評家のほんとうの為事(しごと)である
批評家は此点で、やはり哲学者でなければならぬ。
当来の人生に対する暗示や、生命に絡んだ兆しが、作家の気分に融け込んで、出て来るものが主題である。
短詩形の持つ主題
俳句は遠心的であり、表現は撒叙式 短歌の方は、求心的であり、集注式の表現を採って居る。だから作物に出て来る拍子は、しなやかでいて弾力がある短歌は俳句よりも、一層生命に迫って行く適応性を持って居ることは訣(わか)るであろう。唯、明治・大正の新短歌以前は、その発生の因縁からして、かけあい・頓才(とんさい)問答・あげ足とり・感情誇張・劇的表出を採る癖が離れきらないで居た。短歌の匂いを襲(つ)いで、而も釈教歌から展開して来たさびを、凡人生活の上に移して基調とした芭蕉の出た所以(ゆえん)も、納得がゆく。同時に長い年月を空費した短歌から見ると、江戸の俳句の行きあしは遥かに進んで居る。
而も俳句がさびを芸の醍醐味(だいごみ)とし、人生に「ほっとした」味を寂しく哄笑(こうしょうして居る外なかった間に、短歌は自覚して来て、値うちの多い作物を多く出した。が、批評家は思うたようには現れなかった。
島木赤彦が苦しんで引き出した内律、そうして更に其に伴って出た生命は、一片の技工に化して了った様な場合の多かった事を思う。茂吉さんの見出した新生命は、其知識を愛する――と言うより、知識化しようと冀ねがう――性癖からして、『赤光』時代には概念となり、谷崎潤一郎の前型と現れた。
芭蕉には「さび」の意識があり過ぎて、概念に過ぎないものや、自分の心に動いた暗示を具体化し損じて、とんでもない見当違いの発想をしたものさえ多い。「くたぶれて、宿かる頃や 藤の花」などの「しおり」は、俳句にはじまったのではなく、短歌の引き継ぎに過ぎない。でも「さび」に囚(とら)われないで、ある生命――実は、既に拓かれた境地だが――を見ようとして居る。「山路来て 何やら、ゆかし。菫(すみれ)ぐさ」。これなどは確かに新しい開拓であった。「何やら」と概念的に言う外に、表し方の発見せられなかった処に、仄ほの)かな生命に動きが見える。これも「しおり」の領分である。歌は早くから「しおり」には長(た)けて居た。「さび」は芭蕉が完成者でもあり、批評家でもあったのだ。
注 さび---、寺田寅彦によれば、古いものの内側からにじみ出てくるような、外装などに関係しない美しさのことだという。古びた様子に美を見出す態度 茶の湯では「侘」の中に単に粗末であるというだけでなく質的に(美的に)優れたものであることを求める
しおり---山道などを歩く際、迷わないように木の枝を折って道しるべとする事から、目印にするという意味から「枝折」と書く。生命の暗示
子規の歌の暗示
子規は月並風の排除に努めて来た習わしから、ともすれば、脚をとる泥沼なる「さび」に囚われまいと努め努めして、とどのつまりは安らかな言語情調の上に、「しおり」を持ち来しそうになって居た
平明な表現や、とぼけた顔のうちに、何かを見つけようとしている。空虚な笑いをねらったばかりと見ることは出来ないが、尻きれとんぼうの「しおり」の欠けた姿
霜ふせぐ 菜畠の葉竹 早立てぬ。筑波嶺おろし 雁(がん)を吹くころ
若松の芽だちの葉黄(みどり) ながき日を 夕かたまけて、熱いでにけり
注 夕方まけて --- 夕方になって まく 推量の助動詞の「未然形」「ま」に活用語を名詞化する接尾語「く」が連なったもの
本質的に見た短歌としては、ある点まで完成に近づいたもの
此歌の如きは、主観融合の境に入って居ながら、序歌は調和以上に利いて居る。頓才さえ頭を出して居るではないか。「夕かたまけて……」も内律と調和せぬほどの朗らかさと張りとがある。
新生命の兆しは、完全に紙の上に移されて居る。根岸派では、子規はじめ門流一同進むべき方向を見つけた気のしたこと、正風に於ける「古池や」と一つ事情にあるものである 畳と藤の花ぶさの距離に注意が集って、そこに瞬間の驚異に似て、もっと安らかな気分に誘う発見感があったのである。これを淡い哀愁など言う語で表す事は出来ない。常臥(とこぶ)しの身の、臥しながら見る幽(かす)かな境地である 主観排除せられて、虚心坦懐きょしんたんかい)の気分にぽっかり浮き出た「非人情」なのではなかろうか。結局藤の花の歌は、こうした高士の幽情とは違った、凡人の感得出来る「かそけさ」の味いを詠んだものなのであろう。
最近の茂吉さんの歌に、良寛でもないある一つの境地が顕(あらわ)れかけたのは、これの具象せられて来たのではないかと心愉(こころたの)しんで見て居る。氏は用語に於いて、子規よりも内律を重んじた先師左千夫の気質を承(つ)いで、更に古語によらなければ表されない程の気魄(きはく)を持って居る
文芸の批評は単に作家の為に方角を示すのみならず、我々の生命に深さと新しさとを抽(ひ)き出して来ねばならぬ。その上、我々の生活の上に、進んだ型と、普通の様式とを示さねば、意義がない
私は、歌壇の批評が、実はあまりに原始の状態に止って居るのを恥じる。もっと人間としてのひろさと、祈りと、そうして美しい好しみがあってよいと思うのである。
歌人の生活態度から来る歌の塞り
短歌の前途を絶望と思わせる第二の理由は、歌人が人間として苦しみをして居な過ぎることである 生みの苦しみをわりあいに平気で過している人が多い 作物の短い形であると言う事は、安易な態度を誘い易いものと見えて、口から出任せや、小技工に住しながら、あっぱれ辛苦の固りと言った妄覚を持って居る人が多い
人間価値も技工過程に於て高められて来るのである。併しながらそこまでのこらえじょうのないのが、今の世の歌人たちの心いきである。それは鼻唄もどきの歌ばかり作って居た私自身の姿を解剖しても、わかることである。
この表現の苦悩を積むほかに、唯一つの違った方法が、技工の障壁を突破させるであろう。古代詩に著しく現れた情熱である。その激しい律動が、表現の段階を一挙に飛躍せしめたのである 我々の内生活を咄嗟(とっさ)に整理統一して、単純化してくれる感激を待ち望むことが出来ないとすれば、もっと深い反省、静かな観照から、ひそかな内律をひき出す様にする事が、更に歌をよくし、人間としての深みを加えることになる。
万葉集による文芸復興
赤彦が教職を棄てて上京して以来の辛苦は、誠に『十年』である。而も其間に、酬(むく)いられ過ぎるほどに、世間は響応した。却(かえっ)て、世間が文芸復興に似た気運に向いていた処だから、「アララギ」の働きが、有力にとりこまれたもの、と見る方が正しいのかも知れぬ
子規以来の努力は、万葉びとの気魄(きはく)を、今の心に生かそうとすることにあった。そうした「アララギ」歌風が世間にとり容れられ、もてはやされた。時勢が古代人の純な生命をとりこもうとし、又多少、そうした生活様式に近づいて来ていたから、とも言うことが出来よう
万葉の気魄や律動を、適当に感じ、受け入れることが出来る様になったとしても、短歌の作者が、必しも皆強く生きて居るものとは、きめられない。事実、流行化した文芸復興熱にひきずられた盲動に過ぎなかったことは、悲観する外はない
アララギ派ではすべての人が、新しい発想法を見出して貰った程の喜びで、なぞって行った。茂吉帰朝後、作る歌にも作る歌にも、すべての人が不満の意を示した。が、私は茂吉自身の心にひらめく暗示を、具体化しようとしてあせっているのだと思い、時としては、其が大分明らかに姿を見せかけて来るのを喜び眺めた。此が的をはずれて(?)、従来の持ち味及び、子規流の「とぼけ」からする、変態趣味の外皮を破って「家をいでてわが来し時に、渋谷川(?)卵の殻が流れ居にけり」の代表する一類の歌となって現れた
茂吉風・文明風が、今後「アララギ」の上で、著しい違い目を見せて来るであろうと思う。こうして懐しい万葉ぶりの歌風は過ぎ去って、竟(つい)におさまるべき処におさまる事になるのであろう。そうして、万葉調に追随して来た人々は、又更に新しい調子の跡を追おうとして居る。
歌の上に於て、我々を喜ばした文芸復興は、これで姑(しば)らくは、中入りになるのであろう。
歌人の享楽学問
信頼出来る様に見えた古人の気魄(きはく)再現の努力も、一般の歌人には、不易性を具(そな)えぬ流行として過ぎ去りそうである。其程感に堪えた万葉風の過ぎ去るのは、返す返すも惜しまれる
私の今一つ思案にあぐねて居るのは、歌人の間における学問ばやりの傾向である
此は一見頗(すこぶる)結構な事に似て、実は困った話なのである。文学の絶えざる源泉は古典である。だからどんな方法ででも、古典に近づく事は、文学者としてはわるい態度ではない。けれども、其も、断片知識の衒燿(ひけらかし)や、随筆的な気位の高い発表ばかりが多いのでは困る
私は、気鋭の若人どもの間に行き渉(わた)って居る一種の固定した気持ち、語を換えて言えば、宗匠風な態度に、ぞっとさせられる。こうした人々の試みる短歌の批評が、分解批評や、統一のない啓蒙(けいもう)知識の誇示以上に出ないのは、尤もっとも)である。私は、此等の人々に、ある期間先輩の作風をなぞった後、早く個性の方角を発見して、若きが故の賚(たまもの)なる鮮やかな感覚を自由に迸(ほとばし)らそう、となぜ努めないのか、と言いたい
何にしても、あまりに享楽者が多い。短詩国の日本に特有の、こうした「読者のない文学」と言った、状態から脱せない間は、清く厳かに澄みきった人々の気息までも、寝ぐさい息吹きが濁し勝ちなのである。
短歌の宿命
何物も、生れ落ちると同時に、「ことほぎ」を浴びると共に、「のろい」を負って来ないものはない。短歌は、ほぼ飛鳥(あすか呪言(じゅごん)・片哥(かたうた)・叙事詩の三系統の神言が、専門家の口頭に伝承せられていたのが、国家以前からの状態である。其が各、寿詞(よごと)・歌垣の唱和(かけあい)・新叙事詩などを分化した)朝の末に発生した
古く、片哥と旋頭歌(せどうか)を標準の形とした歌垣の唱和が、一変して短歌を尊ぶ様になって、ここに短歌は様式が定まったのである。だから発生的に、性欲恋愛の気分を離れることが出来ない。奈良朝になっても、そうした意味の贈答を主として居た為、兄妹・姉妹・姑姪(おばおい)の相聞往来にも、恋愛気分の豊かなものを含めた短歌が用いられている
民謡から段々遠くなって来ても、やはり恋愛気分は持ち続けられた。そう言う長い歴史が、短歌を宿命的に抒情詩とした。だから、抒情詩として作られたものでなくとも、抒情気分を脱却することが出来ないのである
短歌と近代詩と
古典としての短歌は、恋愛気分が約束として含まれていなければならなかったのである。こう言う本質を持った短歌は、叙事詩としては、極めて不都合な条件を具えて居る訣(わけ)だ。抒情に帰せなければならない短歌を、叙事詩に展開さしょうと試みて、私は非常に醜い作物を作り作りした。そうしてとどのつまり、短歌の宿命に思い臻(いた)った。
唯啄木のことは、自然主義の唱えた「平凡」に注意を蒐(あつ)めた点にある。彼は平凡として見逃され勝ちの心の微動を捉えて、抒情詩の上に一領域を拓(ひら)いたのであった
併し其も窮極境になれば、万葉人にも、平安歌人にも既に一致するものがあったのである。唯、新様式の生活をとり入れたものに、稍(やや)新鮮味が見えるばかりだ。そうして、全体としての気分に統一が失われている。此才人も、短歌の本質を出ることは出来なかったのである
古典なるが故に、稍変造せねば、新時代の生活はとり容れ難く、宿命的に纏綿(てんめん)している抒情の匂いの為に、叙事詩となることが出来ない。これでは短歌の寿命も知れて居る
抒情詩である短歌の今一つの欠陥は、理論を含む事が出来ない事だ
詩歌として概念を嫌わないものはないが、短歌は、亦病的な程である。概念的叙述のみか、概念をとりこんでも、歌の微妙な脈絡はこわれ勝ちなのである。近代生活も、短歌としての匂いに燻(いぶ)して後、はじめて完全にとりこまれ、理論の絶対に避けられねばならぬ詩形が、更に幾許(いくばく)の生命をつぐ事が出来よう。
口語歌と自由小曲と
単に形式が57577の三十一字詩形である、と言う点ばかりの一致を持っただけの口語歌が、これ程すき嫌いの激しい詩形の中に、割りこもうとしているのは、おか目の私共にとっては、あまりに前の見え透いた寂しい努力だと思われる。
言語を基礎とする詩歌が、言語・文章の根本的の制約なる韻律を無視してよい訣(わけ)はない。
口語歌は、一つの刺戟(しげき)である。けれども、永遠に一つの様式として、存在の価値を主張することは出来ない。私は、口語歌の進むべき道は、もっと外に在ると思う。自由な音律に任せて、小曲の形を採るのがほんとうだと思う。而も短歌の形を基準としておいて、自由に流れる拍子を把握するのが、肝腎かんじん)だと考える。将来の小曲が、短歌に則(のっと)るべきだと言うのは、琉歌・なげぶし等の形から見ても見当がつく。日本の歌謡は、古代には、偶数句並列であったものが、飛鳥・藤原に於て、奇数句の排列となり、其が又平安朝に入って、段々偶数句並列になって、後世に及んだ。私は民謡として(こうしょう)せられた短歌形式は、終に二句並列の四行詩になったのだと思う。それで試みに、音数も短歌に近く、唯自由を旨とした四行詩を作って見た。そうしてそこに、短歌の行くべき道があるのを見出した様に考えている
三十一字形の短歌は、おおよそは円寂(えんじゃく)の時に達している。祖先以来の久しい生活の伴奏者を失う前に、我々は出来るだけ味い尽して置きたい。或は残るかも知れないと思われるのは、芸術的の生命を失うた、旧派の短歌であろう。私どもにとっては、忌むべき寂しい議論であったけれども、何としよう。是非がない。
以上
世々の人々(歌人論)はネットで検索したが無し。機会があれば読んで見たい。ここで述べている「しおり」と「さび」との違いも未だはっきりしないのが本音。短歌は円寂に時に達しているとのこと。
以上の論文があり、折口信夫のアララギから半アララギに向かった動機の一片が垣間見れそうなので今後の検討事項も含めてここにメモとして載せました。
アララギ流 「かなし」「わびしの」使い方を「さびし」で表現。放散より抑制、外的なものより観照(本質を見極める)
「かなし」---異常な事象を通して「生の根源」へ切り込む先鋭な感覚
「さびし」---淡々とした日常の生活情調を通し「生の根源」に触れる要素を持つ
折口は島木赤彦から以下のことを教わったと言う
「感傷を沈潜させ、昇華した形で表出する」感傷そのものが文学価値を構成すると思っていた私を、根本から鍛えなおしてくれた
感傷---物事に感じて心を痛めること 物事に感じやすく、すぐ悲しんだり同情したりする心の傾向
昇華---物事が一段上の状態に高められること。気体が直接固体にまたはその逆のこと
そこから「かそけさ」「ひそけさ」により通常の意義内容を超え特殊な寂寥(せきりょう)の境地を現出
寂寥---心が満ち足りず、もの寂しいさま
補足 似た言葉に「せつなさ」などはどのように捕えればよいのかな
せつなさ---悲しさや恋しさで、胸が締め付けられる やりきれない、やるせない
短歌の観賞のサンプルに「
その子二十櫛に流るる黒髪のおごりの春の美しきかな
」とりあげてある。今まで自分とは関係のない歌人かと思い全然知識を得る気がなかた。鎌倉の大仏にある歌


などは以前鎌倉に訪れて知ってはいた。やはり一度は経歴を初め調べていく必要に駆られる。やっとその気になった(2017/01/06記)
与謝野 晶子
(正字: 與謝野 晶子、よさの あきこ、1878年(明治11年)12月7日 - 1942年(昭和17年)5月29日)は、日本の歌人、作家、思想家。
本名与謝野 志よう(よさの しょう)。旧姓鳳(ほう)。ペンネームの「晶子」の「晶」は、本名の「しょう」から取った。夫は与謝野鉄幹(与謝野寛)。
経歴
鳳志ようは、堺県和泉国第一大区甲斐町(現在の大阪府堺市堺区甲斐町東1丁・甲斐町西1)で老舗和菓子屋「駿河屋」を営む、父・鳳宗七、母・津祢の三女として生まれた。9歳で漢学塾に入り、琴・三味線も習った。堺市立堺女学校(現・大阪府立泉陽高等学校)に入学すると『源氏物語』などを読み始め古典に親しんだ。
20歳ごろより店番をしつつ和歌を投稿するようになる。浪華青年文学会に参加の後、1900年(明治33年)、浜寺公園の旅館で行なわれた歌会で歌人・与謝野鉄幹と不倫の関係になり、鉄幹が創立した新詩社の機関誌『明星』に短歌を発表。翌年家を出て東京に移り、女性の官能をおおらかに謳う処女歌集『みだれ髪』(鳳晶子)を刊行し、浪漫派の歌人としてのスタイルを確立した。のちに鉄幹と結婚、子供を12人出産している
1904年(明治37年)9月、『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表。1911年(明治44年)には史上初の女性文芸誌『青鞜』創刊号に「山の動く日きたる」で始まる詩を寄稿
1912年(明治45年)、晶子は鉄幹の後を追ってフランスのパリに行くことになった。洋行費の工面は、森鴎外が手助け
1921年(大正10年)に建築家の西村伊作と、画家の石井柏亭そして夫の鉄幹らとともにお茶の水駿河台に文化学院を創設する。男女平等教育を唱え、日本で最初の男女共学を成立させる。
1940年5月に脳出血で右半身不随になり、1942年(昭和17年)1月4日意識不明になる。同年5月、死去。墓は多磨霊園にある
作家・歌人
情熱的な作品が多いと評される歌集『みだれ髪』(1901年)や、日露戦争の時に歌った『君死にたまふことなかれ』が有名である。『源氏物語』の現代語訳でも知られる。
歌集『みだれ髪』では、女性が自我や性愛を表現するなど考えられなかった時代に女性の官能をおおらかに詠い、浪漫派歌人としてのスタイルを確立した。伝統的歌壇から反発を受けたが、世間の耳目を集めて熱狂的支持を受け、歌壇に多大な影響を及ぼすこととなった。所収の短歌にちなみ「やは肌の晶子」と呼ばれた。
1904年(明治37年)9月、半年前に召集され日露戦争の旅順攻囲戦に予備陸軍歩兵少尉として従軍していた弟を嘆いて『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表した
「嫌戦の歌人」という印象が強いが、1910年(明治43年)に発生した第六潜水艇の沈没事故の際には、「海底の 水の明りにしたためし 永き別れの ますら男の文」等約十篇の歌を詠み、第一次世界大戦の折は『戦争』という詩のなかで、「いまは戦ふ時である 戦嫌ひのわたしさへ 今日此頃は気が昂る」と極めて励戦的な戦争賛美の歌を作っている
日露戦争後から新聞や雑誌に警世の文を書くようになり、評論活動をはじめる。評論は、女性の自立論と政治評論に分類できる。教育問題なども評論している。女性の自立論は、女性が自分で自己鍛錬・自己修養し、人格陶冶することを説いた。英米思想的な個人主義である。数学が大変得意であり、女性も自然科学を学ぶべきと主張した
反良妻賢母主義を危険思想だと見ていた文部省の取り締まり強化に対し、妊娠・出産を国庫に補助させようとする平塚らいてうの唱える母性中心主義は、形を変えた新たな良妻賢母にすぎないと論評し、平塚らいてう、山田わからを相手に母性保護論争を挑んで「婦人は男子にも国家にも寄りかかるべきではない」と主張した。ここで論壇に登場した女性解放思想家・山川菊栄は、保護(平塚)か経済的自立(与謝野)かの対立に、婦人運動の歴史的文脈を明らかにし、差別のない社会でしか婦人の解放はありえないと社会主義の立場で整理した。文部省の意向とは全く違う次元で論争は終始した。
代表歌
・・・以上ウィキペディアより抜粋
歌集
「みだれ髪」から始まって「流星の道」「瑠璃光」まで20ほどの歌集がある。(某ホームページより)
「流星の道」「瑠璃光」は箱根、伊豆など自分の近場の歌が目立つがそれ程記憶には残らず。すべての歌集に目を通すのもつかれるので評判に合っている歌をネットから広い取りあえず観賞します。
「やは肌の晶子」と呼ばれていた与謝野晶子の短歌には、情熱的といわれるものが多くあります。その一方で、寂しさを感じるような自然の風景を詠んだものも多く残されています。そして、晶子が生涯で詠んだ短歌は5万首にも及ぶといわれています。
「ジャパノート-日本の文化と伝統を伝えるブログ」のカテゴリー「短歌」の100選より
【恋の歌】
美くしさ 恋のごとしとほめて見ぬ ほろびやすかる磁のうつはもの
清水へ 祇園をよぎる桜月夜 こよひ逢ふ人みなうつくしき
くろ髪の 千すじの髪のみだれ髪 かつおもひみだれおもいみだるる
小百合さく 小草がなかに君待てば 野末(のずえ)にほひて虹あらわれぬ
その子二十 櫛にながるる黒髪の おごりの春のうつくしきかな
罪おほき 男こらせと肌きよく 黒髪ながくつくられし我れ
なにとなく 君に待たるるここちして 出でし花野の夕月夜かな
春みじかし 何に不滅の命ぞと ちからある乳を手にさぐらせぬ
人の子の 恋をもとむる唇に 毒ある蜜をわれぬらむ願い
みだれ髪 おもひ動くぞ秋によき 恋の二十を袂(たもと)に秘めな
みだれ髪を 京の島田にかへし朝 ふしていませの君ゆりおこす
道を云はず 後を思はず名を問はず ここに恋ひ恋ふ君と我と見る
むねの清水 あふれてつひに濁りけり 君の罪の子我も罪の子
やは肌の あつき血汐にふれも見で さびしからずや道を説く君
わが恋は 虹にもまして美しき いなづまとこそ似むと願ひぬ
【その他】
六月の同じ夕ゆふべに簾しぬ娘かしづく絹屋と木屋と
人とわれおなじ十九のおもかげをうつせし水よ石津川の流れ
石津川ながれ砂川髪をめでてなでしこ添へし旅の子も見し
御供養の東寺舞楽の日を見せて桜ふくなり京の山かぜ
杉のうへに茅渟の海見るかつらぎや高間の山に朝立ちぬ我れ
瀬田いでて宇治に流るる春のみず柳ながうて京の子見えぬ
山山と湖水巴に身を組みて夜の景色となりにけるかな
心にも山にも雲のはびこりて風の冷たくなりにけるかな
山風の浴室に入るところより少し覗かる大ぞらの星
春の夜の月のひかりの
散ることと見えず盛りの余りをば人に贈れる桜ならまし
1912年(明治45年)5月5日日本を出発した与謝野晶子(34歳)は、5月19日、パリ北駅に到着した。 駅には、前年の11月、ひと足さきに渡欧した夫の寛が晶子を迎えてくれた。わずか半年ばかりの別離 ではあったが、夫を見送り、寛の居ない東京の家で淋しさをかこち、晶子は下記のように歌詠している。
君こひし寝てもさめてもくろ髪を梳きても筆の柄をながめても 晶子
ああ皐月仏蘭西の野は火の色す君の雛罌粟われも雛罌粟 晶子
雛罌粟(コクリコ)・・・ひなげし
私は『源氏物語』は知りませんが、晶子はそれの現代語訳をしたのだから、その物語から多くの影響を受けて人生の、青春の短歌を読み上げたとしか言いようがない。
今様ならばその内容もそれほど激しいものではないと思うが、綺麗に愛というか、性というか、その辺を詠んだものとして見事と思う。「流星の道」「瑠璃光」の歌集を一通り読んでは見た。紀行の歌も素直でいいかな。
この歌人はこれ以上は深読みは出来ないかも。『乱れ髪』イコール与謝野晶子です。
平成30年(2018)3月静岡新聞の夕刊に「歌人が語る ―正岡子規―(大辻隆弘)」が連載され、その中の「墨汁一滴」を読んで子規の歌も調べる気になった。今まで子規については俳句のヒトと思い、また古今集選者の紀貫之をぼろくそに批判する一風変わった人かなと避けていたが、夏目漱石の友人と聞き改めて近代の短歌の走りの人物とも思い(根岸会)、調べる必要性を感じる。
※日付は1872年までは旧暦
生年:慶応3.9.17(1867.10.14)
明治時代の俳人,歌人。本名常規。幼名は最初処之助,のち升。号は獺祭書屋主人,竹の里人ほか。伊予国(愛媛県)生まれ。常尚,八重の長男。松山藩の下級武士だった父は明治5(1872)年に40歳で死亡。母の裁縫の内職によって生計は支えられた。幼少時,外祖父大原観山(1875年死亡)の私塾で漢学を学ぶ。松山中学入学,明治16年同校退学,上京する。翌年松山藩常盤会給費生となり大学予備門(一高)に入学,夏目金之助(漱石)を知る。18年ごろから俳句,短歌の実作に入る。21年,前年に本郷で創立された常盤会寄宿舎に入舎。8月初めて喀血。22年内藤鳴雪が舎監として就任。鳴雪はのち子規の従弟藤野古白らと共に子規に俳句指導を受け,子規派の重鎮となる。5月約1週間にわたり喀血。血を吐くまで啼くと俗にいわれるホトトギスにちなんで「子規」と号する。23年帝大哲学科に入学。翌年2月国文科に転科。このころ松山中学の後輩河東秉五郎(碧梧桐),高浜清(虚子)が書を寄せ,指導を受ける。松山からはこうして明治の俳句革新運動の担い手が輩出した。 明治25年6月の試験に落第し,退学を決意(翌年3月中退),母と妹を東京に呼ぶ。母の弟加藤拓川の紹介で陸羯南の日本新聞社に入社。月給15円だった。子規は日本新聞社入社以前より「獺祭書屋俳話」を同紙に連載し,のち明治28年に,加筆された『増補再版獺祭書屋俳話』が同社より刊行された。これは子規の最初の評論集で,俳句革新の第一声となる。彼は同時代の俳句界に覚醒をうながす見解を次々に披瀝したが,その機知と諧謔に富んだ文章は,20代半ばですでに堂々たる指導者の風格を備えていた。この一書生の啓蒙的俳論がまきおこした反響は大きく,子規は驚くべき短期間に俳句革新の仕事を成しとげた。26年ごろから洋画家浅井忠,中村不折,下村為山らを知り,写生に眼を開かれた子規はこれを俳句の方法に応用する。28年,日清戦争に従軍記者として赴き,喀血,病を悪化させて帰国。当時松山中学で英語教師をしていた漱石の下宿に2カ月ほど同居,帰京後長い病床生活に入る。 30年,柳原極堂 が松山で『ほとゝぎす』を創刊,翌31年これが東京に移され,虚子により続刊,誌名は『ホトトギス』となる。同年「歌よみに与ふる書」を発表,短歌革新に乗り出し,根岸短歌会を始める。「歌よみに与ふる書」は書簡体の形式で,直截に思うところを述べようとするジャーナリストとしての子規の鋭い感覚がよくうかがえる。「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候」という冒頭の強烈な断定は有名である。31年ごろから写生文を試み,「墨汁一滴」(1901),「病牀六尺」(1902),「仰臥漫録」(1901~02)などを書く。晩年は脊椎カリエスによりほとんど病床で過ごすが,甚だしい痛苦のなか,不屈の意志力をもって,快活さと創造性を備えた韻文,散文作品を生みつづけ,その後の近代俳句,近代短歌史全体にはかり知れない影響を与えた。「いちはつの花咲きいでて我が目には今年ばかりの春行かんとす」(1901),「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」(1902,絶筆)などの作がある。
(大岡信)
「墨汁一滴」の随筆を読んでみた(以下その一辺を垣間見てみる))
出だしは1/16日(1901年)
病める
(一月十六日)
墨汁一滴を書く動機
年頃苦しみつる局部の
(一月二十四日)
人に物を贈るとて実用的の物を贈るは
(一月二十八日)
人の希望は初め漠然として大きく後
(一月三十一日)
平賀元義 ひらがもとよし 寛政十二~慶応一(1800-1865) 号:石楯(いわだて)・楯之舎(たてのや)ほか
備前岡山藩士平尾新兵衛長春の長男。岡山城下富田町で育つ。十九歳の時小林氏より妻を迎えるが、翌年離婚。以後、四十九歳まで独身であった。二人目の妻長浜富子との間には二人の男子をもうけた。
賀茂真淵などの影響を受け、若くして古学を独習し、文政三年(1820)、同士を集めて日本書紀の講義をするなどした。学問に志を立てて二十五歳の時家督を弟に譲り、祖母の実家に寄寓し興津(沖津)姓を名乗ったが、天保三年(1832)、三十三歳の時本姓に復し、以後平賀左衛門太郎源元義を名乗る(平賀氏は生家平尾氏の遠祖)。同年、脱藩し、備前・備中・美作などを放浪した。安政四年(1857)、五十八歳の時、美作勝田郡飯岡村に楯之舎塾を創設、古学を講じ、また歌会を開くなどした。学才を認められて岡山藩主に召されることに決まった矢先の慶応元年(1865)十二月二十日、備前上道郡(現岡山市内)の路上で倒死した。六十六歳。
兵学・神道・史学などに研鑽を重ねる一方、余技として万葉調の歌を作った。生前は無名に等しかったが、明治時代になって羽生永明により初めて世に紹介され、次いで正岡子規によって激賞され万葉調歌人として広く知られるようになった。家集は岡山の歌人有元稔らによって編集され、明治三十九年(1906)に初めて刊行された。
万葉以後において歌人四人を得たり。
曙覧は
四家の歌を見るに、実朝と宗武とは気高くして時に独造の処ある相似たり。
二月十三日~平賀左衛門太郎源元義の歌の万葉調を述べる
(二月二十六日)
菫謹勤などの終りの横画は三本なり。二本に書くは非なり。活字にもこの頃二本の者を
達の字の下の処の横画も三本なり、二本に非ず。
切の字の
助の字の扁は且なり。目扁に書く人多し。
一部抜粋
(三月一日)
不平十ヶ条
(三月十二日)
散歩の
(三月十五日)
ある日左千夫
三月二十六日)
『明星』所載落合氏の歌
(三月二十九日)~(四月三日)
をかしければ笑ふ。悲しければ泣く。しかし痛の烈しい時には仕様がないから、うめくか、叫ぶか、泣くか、または黙つてこらへて居るかする。その中で黙つてこらへて居るのが一番苦しい。盛んにうめき、盛んに叫び、盛んに泣くと少しく痛が減ずる。
(四月十九日)
夕餉したため了りて仰向に寝ながら左の方を見れば机の上に藤を活けたるいとよく水をあげて花は今を盛りの有様なり。
おだやかならぬふしもありがちながら病のひまの筆のすさみは日頃
(四月二十八日)
病室のガラス障子より見ゆる処に裏口の木戸あり。木戸の
(四月三十日)
しひて筆を取りて
心弱くとこそ人の見るらめ。
(五月四日)
今になりて思ひ得たる事あり、これまで余が
(五月九日)
根岸に移りてこのかた、
(五月十一日)
遠洋へ乗り出して
(五月二十二日)
こんなとこれで止めておきます。正岡子規の病状や、交友関係短歌や、俳句の意気込み、その他料理や漢字の注意点など取り上げて読むほどに楽しくなる。次にどんな歌を詠んでいたか抜粋入てみたい。(俳句は抜きに)
※以下の歌を 大辻隆弘は子規の最高傑作と言う
「歌よみに与ふる書」の戦略がことごとく変更され、短歌の結句に作者の詠嘆を表す終助詞「も」「かも」が頻出している
過剰な助辞の使用は和歌改革の中で否定していたと言う
しひて筆を取りて
佐保神の別れかなしも来ん春にふたゝび逢はんわれならなくに
いちはつの花咲きいでゝ我目には今年ばかりの春行かんとす
病む我をなぐさめがほに開きたる牡丹の花を見れば悲しも
世の中は常なきものと我愛づる山吹の花散りにけるかも
別れ行く春のかたみと藤波の花の長ふさ絵にかけるかも
夕顔の棚つくらんと思へども秋待ちがてぬ我いのちかも
くれなゐの薔薇ふゝみぬ我病いやまさるべき時のしるしに
薩摩下駄足にとりはき杖つきて萩の芽摘みし昔おもほゆ
若松の芽だちの緑長き日を夕かたまけて熱いでにけり
いたつきの癒ゆる日知らにさ庭べに秋草花の種を蒔かしむ
心弱くとこそ人の見るらめ。
◯その他の歌を取り上げてみました。
天つ空 青海原も 一つにて つらなる星か いさりする火か
朝日さす 小池の氷 半ば解けて 尾をふる鯉の うれしくもあるか
小鮒取る 童去りて 門川の 河骨の花に 目高群れつつ
春風の 利根のわたりに舟待てば 雲雀鳴くなり筵(むしろ)帆の上に
カナリヤの囀り高し 鳥彼も人わが如く 晴を喜ぶ
くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の 針やはらかに 春雨のふる
一うねの 青菜の花の 咲き満つる 小庭(さには)の空に 鳶舞ふ春日
潮早き 淡路の瀬戸の海狭み 重なりあひて 白帆行くなり
もののふが 太刀沈めにし鎌倉の 稲村が崎に鴎飛ぶなり
久方の アメリカ人びとのはじめにし ベースボールは見れど飽かぬも
今やかの 三つのベースに人満ちて そぞろに胸のうたさわぐかな
義仲が 兎を狩りて遊びけん 木曾の深山は檜生いたり
真砂なす 数なき星の 其の中に 吾に向ひて 光る星あり
空はかる台うてなの上に登り立つ 我をめぐりて 星かがやけり
神の我に 歌をよめとぞのたまひし 病ひに死なじ 歌に死ぬとも
病みて臥す 窓の橘 花咲きて 散りて実になりて 猶病みて臥す
詩人去れば 歌人座にあり歌人去れば 俳人来り永き日暮れぬ
病みふせる わが枕辺に運びくる 鉢の牡丹の 花ゆれやまず
みずから病中の像をつくねて
わが心 世にしのこらば あら金の この土くれのほとりにかあらん
『歌よみに与ふる書』(うたよみに あたうる しょ)は、正岡子規が1898年(明治31年)2月から10回にわたって新聞「日本」紙上に発表した歌論。
それまで新聞「日本」や雑誌ホトトギスを中心に俳句の近代化に傾注していた子規が、短歌(和歌)の改革に軸足を移す決意表明とも言えるもので、それまでの伝統的な和歌から現在まで続く近代短歌への転機となった。
歌よみに与ふる書
仰《おおせ》の如《ごと》く近来和歌は一向に振ひ不申《もうさず》候。正直に申し候へば万葉以来|実朝《さねとも》以来一向に振ひ不申候。実朝といふ人は三十にも足らで、いざこれからといふ処にてあへなき最期を遂げられ誠に残念致し候。あの人をして今十年も活《い》かして置いたならどんなに名歌を沢山残したかも知れ不申候。とにかくに第一流の歌人と存《ぞんじ》候。強《あなが》ち人丸《ひとまろ》・赤人《あかひと》の余唾《よだ》を舐《ねぶ》るでもなく、固《もと》より貫之《つらゆき》・定家《ていか》の糟粕《そうはく》をしやぶるでもなく、自己の本領|屹然《きつぜん》として山岳《さんがく》と高きを争ひ日月と光を競ふ処、実に畏《おそ》るべく尊むべく、覚えず膝《ひざ》を屈するの思ひ有之《これあり》候。古来凡庸の人と評し来りしは必ず誤《あやまり》なるべく、北条氏を憚《はばか》りて韜晦《とうかい》せし人か、さらずば大器晩成の人なりしかと覚え候。人の上に立つ人にて文学技芸に達したらん者は、人間としては下等の地にをるが通例なれども、実朝は全く例外の人に相違|無之《これなく》候。何故と申すに実朝の歌はただ器用といふのではなく、力量あり見識あり威勢あり、時流に染まず世間に媚《こ》びざる処、例の物数奇《ものずき》連中や死に歌よみの公卿《くげ》たちととても同日には論じがたく、人間として立派な見識のある人間ならでは、実朝の歌の如き力ある歌は詠《よ》みいでられまじく候。真淵《まぶち》は力を極めて実朝をほめた人なれども、真淵のほめ方はまだ足らぬやうに存候。真淵は実朝の歌の妙味の半面を知りて、他の半面を知らざりし故に可有之《これあるべく》候。
真淵は歌につきては近世の達見家にて、万葉崇拝のところ抔《など》当時にありて実にえらいものに有之候へども、生《せい》らの眼より見ればなほ万葉をも褒《ほ》め足らぬ心地《ここち》致《いたし》候。真淵が万葉にも善き調《ちょう》あり悪《あし》き調ありといふことをいたく気にして繰り返し申し候は、世人が万葉中の佶屈《きっくつ》なる歌を取りて「これだから万葉はだめだ」などと攻撃するを恐れたるかと相見え申候。固より真淵自身もそれらを善き歌とは思はざりし故に弱みもいで候ひけん。しかしながら世人が佶屈と申す万葉の歌や、真淵が悪き調と申す万葉の歌の中には、生の最も好む歌も有之と存ぜられ候。そを如何《いか》にといふに、他の人は言ふまでもなく真淵の歌にも、生が好む所の万葉調といふ者は一向に見当り不申候。(尤《もっと》もこの辺の論は短歌につきての論と御承知|可被下《くださるべく》候)真淵の家集《かしゅう》を見て、真淵は存外に万葉の分らぬ人と呆《あき》れ申候。かく申し候とて全く真淵をけなす訳にては無之候。楫取魚彦《かとりなひこ》は万葉を模したる歌を多く詠みいでたれど、なほこれと思ふ者は極めて少く候。さほどに古調は擬しがたきにやと疑ひをり候処、近来生らの相知れる人の中に歌よみにはあらでかへつて古調を巧《たくみ》に模する人少からぬことを知り申候。これに由《よ》りて観れば昔の歌よみの歌は、今の歌よみならぬ人の歌よりも、遥《はるか》に劣り候やらんと心細く相成《あいなり》申候。さて今の歌よみの歌は昔の歌よみの歌よりも更に劣り候はんには如何《いかが》申すべき。
長歌のみはやや短歌と異なり申候。『古今集《こきんしゅう》』の長歌などは箸《はし》にも棒にもかからず候へども、箇様《かよう》な長歌は古今集時代にも後世にも余り流行《はや》らざりしこそもつけの幸《さいわい》と存ぜられ候なれ。されば後世にても長歌を詠む者には直《ただち》に万葉を師とする者多く、従つてかなりの作を見受け申候。今日とても長歌を好んで作る者は短歌に比すれば多少|手際《てぎわ》善く出来申候。(御歌会派《おうたかいは》の気まぐれに作る長歌などは端唄《はうた》にも劣り申候)しかし或《ある》人は難じて長歌が万葉の模型を離るる能《あた》はざるを笑ひ申候。それも尤《もっとも》には候へども歌よみにそんなむつかしい事を注文致し候はば、古今以後|殆《ほとん》ど新しい歌がないと申さねば相成|間敷《まじく》候。なほいろいろ申し残したる事は後鴻《こうこう》に譲《ゆず》り申候。不具。
[#地から2字上げ](明治三十一年二月十二日)
再び歌よみに与ふる書
貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候。其貫之や古今集を崇拝するは誠に気の知れぬことなどと申すものゝ実は斯く申す生も数年前迄は古今集崇拝の一人にて候ひしかば今日世人が古今集を崇拝する気味合は能く存申候。崇拝して居る間は誠に歌といふものは優美にて古今集は殊に其粋を抜きたる者とのみ存候ひしも三年の恋一朝にさめて見ればあんな意気地の無い女に今迄ばかされて居つた事かとくやしくも腹立たしく相成候。先づ古今集といふ書を取りて第一枚を開くと直に「去年《こぞ》とやいはん今年とやいはん」といふ歌が出て来る実に呆れ返つた無趣味の歌に有之候。日本人と外国人との合の子を日本人とや申さん外国人とや申さんとしやれたると同じ事にてしやれにもならぬつまらぬ歌に候。此外の歌とても大同小異にて佗洒落か理窟ッぽい者のみに有之候。それでも強ひて古今集をほめて言はゞつまらぬ歌ながら万葉以外に一風を成したる処は取餌[#「餌」に「ママ」の注記]にて如何なる者にても始めての者は珍らしく覚え申候。只之を真似るをのみ芸とする後世の奴こそ気の知れぬ奴には候なれ。それも十年か二十年の事なら兎も角も二百年たつても三百年たつても其糟粕を嘗《な》めて居る不見識には驚き入候。何代集の彼ン代集のと申しても皆古今の糟粕の糟粕の糟粕の糟粕ばかりに御座候。
貫之とても同じ事に候。歌らしき歌は一首も相見え不申候。嘗《かつ》て或る人に斯く申し候処其人が「川風寒く千鳥鳴くなり」の歌は如何にやと申され閉口致候。此歌ばかりは趣味ある面白き歌に候。併し外にはこれ位のもの一首もあるまじく候。「空に知られぬ雪」とは佗洒落にて候。「人はいざ心もしらず」とは浅はかなる言ひざまと存候。但貫之は始めて箇様な事を申候者にて古人の糟粕にては無之候。詩にて申候へば古今集時代は宋時代にもたぐへ申すべく俗気紛々と致し居候処は迚も唐詩とくらぶべくも無之候得共さりとて其を宋の特色として見れば全体の上より変化あるも面白く宋はそれにてよろしく候ひなん。それを本尊にして人の短所を真似る寛政以後の詩人は善き笑ひ者に御座候。
古今集以後にては新古今稍すぐれたりと相見え候。古今よりも善き歌を見かけ申候。併し其善き歌と申すも指折りて数へる程の事に有之候。定家といふ人は上手か下手か訳の分らぬ人にて新古今の撰定を見れば少しは訳の分つて居るのかと思へば自分の歌にはろくな者無之「駒とめて袖うちはらふ」「見わたせば花も紅葉も」抔が人にもてはやさるゝ位の者に有之候。定家を狩野派の画師に比すれば探幽と善く相似たるかと存候。定家に傑作無く探幽にも傑作無し。併し定家も探幽も相当に練磨の力はありて如何なる場合にも可なりにやりこなし申候。両人の名誉は相|如《し》く程の位置に居りて〈定〉家以後歌の門閥を生じ探幽以後画の門閥を生じ両家とも門閥を生じたる後は歌も画も全く腐敗致候。いつの代如何なる技芸にても歌の格画の格などゝいふやうな格がきまつたら最早進歩致す間敷候。
香川景樹《かがはかげき》は古今貫之崇拝にて見識の低きことは今更申す迄も無之候。俗な歌の多き事も無論に候。併し景樹には善き歌も有之候。自己が崇拝する貫之よりも善き歌多く候。それは景樹が貫之よりえらかつたのかどうかは分らぬ只景樹時代には貫之時代よりも進歩して居る点があるといふ事は相違無ければ従て景樹に貫之よりも善き歌が出来るといふも自然の事と存候。景樹の歌がひどく玉石混淆である処は俳人でいふと蓼太《れうた》に比するが適当と被思《おもはれ》候。蓼太は雅俗巧拙の両極端を具へた男で其句に両極端が現れ居候。且満身の覇気でもつて世人を籠絡《ろうらく》し全国に夥《おびただ》しき門派の末流をもつて居た処なども善く似て居るかと存候。景樹を学ぶなら善き処を学ばねば甚だしき邪路に陥り可申今の景樹派などゝ申すは景樹の俗な処を学びて景樹よりも下手につらね申候。ちゞれ毛の人が束髪に結びしを善き事と思ひて束髪にいふ人はわざ/\毛をちゞらしたらんが如き趣有之候。こゝの処よくよく闊眼《くわつがん》を開いて御判別可有候。古今上下東西の文学など能く比較して御覧|可被成《なさるべく》くだらぬ歌書許り見て居つては容易に自己の謎を醒まし難く見る所狭ければ自分の汽車の動くのを知らで隣の汽車が動くやうに覚ゆる者に御座候。不尽。
香川景樹《かがはかげき》
鳥取藩軽輩荒井小三次の次男に生まれ、銀之助といったが、7歳で父に死別し、伯父奥村定賢の養子となって奥村純徳と改めた。年少のころから学問を好み、清水貞固(さだかた)に和歌を学んだ。26歳で和歌修業のため京都に上り、荒井玄蔵の変名で按摩(あんま)をしながら刻苦勉励し、29歳で二条派地下(じげ)の宗匠香川梅月堂景柄(かげもと)の養子となり、香川式部景樹といった。このころ小沢蘆庵(ろあん)の「ただこと歌」に啓発されて、古今伝授を伝統的権威とする二条派和歌に反発し、37歳で梅月堂を離縁となり、独立して桂園派の一派をたてた。景樹の主張の一つは中世的伝統歌学の否定であり、他の一つは復古主義歌学の否定である。賀茂真淵(かもまぶち)の『新学(にいまなび)』に対して『新学考』(1815年に『新学異見』として出版)を書いて、真淵の『万葉集』尊重と古代精神復活の主張を批判し、『古今集』を尊重しながらも「今の世の歌は今の世の詞(ことば)にして今の世の調(しらべ)にあるべし」と「調の説」をたてて和歌の現代性を強調し、近世歌論に新しい展開を示し、熊谷直好(くまがいなおよし)、木下幸文(たかふみ)をはじめとして概数1000人の門人たちは全国に桂園派の新歌風を拡大した。
三たび歌よみに与ふる書
前略。歌よみの如く馬鹿な、のんきなものは、またと無之候。歌よみのいふ事を聞き候へば和歌ほど善き者は他になき由いつでも誇り申候へども、歌よみは歌より外の者は何も知らぬ故に、歌が一番善きやうに自惚《うぬぼれ》候次第に有之候。彼らは歌に最も近き俳句すら少しも解せず、十七字でさへあれば川柳《せんりゅう》も俳句も同じと思ふほどの、のんきさ加減なれば、まして支那の詩を研究するでもなく、西洋には詩といふものがあるやらないやらそれも分らぬ文盲浅学、まして小説や院本《いんぽん》も、和歌と同じく文学といふ者に属すと聞かば、定めて目を剥《む》いて驚き可申候。かく申さば、讒謗《ざんぼう》罵詈《ばり》礼を知らぬしれ者と思ふ人もあるべけれど、実際なれば致方《いたしかた》無之候。もし生の言が誤れりと思《おぼ》さば、いはゆる歌よみの中よりただの一人にても、俳句を解する人を御指名|可被下《くださるべく》候。生は歌よみに向ひて何の恨《うらみ》も持たぬに、かく罵詈がましき言を放たねばならぬやうに相成候心のほど御察被下《おさっしくだされ》たく候。
歌を一番善いと申すは、固《もと》より理窟もなき事にて、一番善い訳は毫《ごう》も無之候。俳句には俳句の長所あり、支那の詩には支那の詩の長所あり、西洋の詩には西洋の詩の長所あり、戯曲院本には戯曲院本の長所あり、その長所は固より和歌の及ぶ所にあらず候。理窟は別とした処で、一体歌よみは和歌を一番善い者と考へた上でどうするつもりにや、歌が一番善い者ならば、どうでもかうでも上手でも下手でも三十一文字《みそひともじ》並べさへすりや、天下第一の者であつて、秀逸と称せらるる俳句にも、漢詩にも、洋詩にも優《まさ》りたる者と思ひ候者にや、その量見が聞きたく候。最も下手な歌も、最も善き俳句漢詩等に優り候ほどならば、誰も俳句漢詩等に骨折る馬鹿はあるまじく候。もしまた俳句漢詩等にも和歌より善き者あり、和歌にも俳句漢詩等より悪《あし》き者ありといふならば、和歌ばかりが一番善きにてもあるまじく候。歌よみの浅見《せんけん》には今更のやうに呆《あき》れ申候。
俳句には調がなくて和歌には調がある、故に和歌は俳句に勝《まさ》れりとある人は申し候。これは強《あなが》ち一人の論ではなく、歌よみ仲間には箇様《かよう》な説を抱く者多き事と存候。歌よみどもはいたく調といふ事を誤解致しをり候。調にはなだらかなる調も有之、迫りたる調も有之候。平和な長閑《のどか》な様を歌ふにはなだらかなる長き調を用うべく、悲哀とか慷慨《こうがい》とかにて情の迫りたる時、または天然にても人事にても、景象《けいしょう》の活動甚しく変化の急なる時、これを歌ふには迫りたる短き調を用うべきは論ずるまでもなく候。しかるに歌よみは、調は総《すべ》てなだらかなる者とのみ心得候と相見え申候。かかる誤《あやまり》を来すも、畢竟《ひっきょう》従来の和歌がなだらかなる調子のみを取り来りしに因《よ》る者にて、俳句も漢詩も見ず、歌集ばかり読みたる歌よみには、爾《し》か思はるるも無理ならぬ事と存候。さてさて困つた者に御座候。なだらかなる調が和歌の長所ならば、迫りたる調が俳句の長所なる事は分り申さざるやらん。しかし迫りたる調、強き調などいふ調の味は、いはゆる歌よみには到底分り申す間敷《まじき》か。真淵は雄々《おお》しく強き歌を好み候へども、さてその歌を見ると存外に雄々しく強き者は少く、実朝の歌の雄々しく強きが如きは真淵には一首も見あたらず候。「飛ぶ鷲《わし》の翼もたわに」などいへるは、真淵集中の佳什《かじゅう》にて強き方の歌なれども、意味ばかり強くて調子は弱く感ぜられ候。実朝をしてこの意匠を詠ましめば箇様な調子には詠むまじく候。「もののふの矢なみつくろふ」の歌の如き、鷲を吹き飛ばすほどの荒々しき趣向ならねど、調子の強き事は並ぶ者なく、この歌を誦《しょう》すれば霰《あられ》の音を聞くが如き心地致候。真淵既にしかりとせば真淵以下の歌よみは申すまでもなく候。かかる歌よみに、蕪村派《ぶそんは》の俳句集か盛唐《せいとう》の詩集か読ませたく存候へども、驕《おご》りきつたる歌よみどもは、宗旨以外の書を読むことは、承知致すまじく、勧めるだけが野暮《やぼ》にや候べき。
御承知の如く、生は歌よみよりは局外者とか素人《しろうと》とかいはるる身に有之、従つて詳《くわ》しき歌の学問は致さず、格が何だか文法が何だか少しも承知致さず候へども、大体の趣味|如何《いかん》においては自ら信ずる所あり、この点につきてかへつて専門の歌よみが不注意を責むる者に御座候。箇様に悪口をつき申さば生を弥次馬《やじうま》連と同様に見る人もあるべけれど、生の弥次馬連なるか否かは貴兄は御承知の事と存候。異論の人あらば何人《なんぴと》にても来訪あるやう貴兄より御伝へ被下《くだされ》たく、三日三夜なりともつづけさまに議論|可致《いたすべく》候。熱心の点においては決して普通の歌よみどもには負け不申候。情激し筆走り候まま失礼の語も多かるべく御海容可被下《ごかいようくださるべく》候。拝具。
(明治三十一年二月十八日)
四たび歌よみに与ふる書
拝啓。空論ばかりにては傍人に解しがたく、実例につきて評せよとの御言葉御尤《ごもっとも》と存候。実例と申しても際限もなき事にて、いづれを取りて評すべきやらんと惑《まど》ひ候へども、なるべく名高き者より試み可申候。御思《おんおも》ひあたりの歌ども御知らせ被下《くだされ》たく候。さて人丸《ひとまろ》の歌にかありけん
もののふの八十氏川《やそうじがわ》の網代木《あじろぎ》にいざよふ波のゆくへ知らずも
といふがしばしば引きあひに出されるやうに存候。この歌万葉時代に流行せる一気|呵成《かせい》の調にて、少しも野卑なる処はなく、字句もしまりをり候へども、全体の上より見れば上三句は贅物《ぜいぶつ》に属し候。「足引《あしびき》の山鳥の尾の」といふ歌も前置の詞《ことば》多けれど、あれは前置の詞長きために夜の長き様を感ぜられ候。これはまた上三句全く役に立ち不申候。この歌を名所の手本に引くは大たはけに御座候。総じて名所の歌といふはその地の特色なくては叶《かな》はず、この歌の如く意味なき名所の歌は名所の歌になり不申候。しかしこの歌を後世の俗気紛々たる歌に比ぶれば勝ること万々に候。かつこの種の歌は真似すべきにはあらねど、多き中に一首二首あるは面白く候。
月見れば千々《ちぢ》に物こそ悲しけれ我身一つの秋にはあらねど
といふ歌は最も人の賞する歌なり。上三句はすらりとして難なけれども、下二句は理窟なり蛇足《だそく》なりと存候。歌は感情を述ぶる者なるに理窟を述ぶるは歌を知らぬ故にや候らん。この歌下二句が理窟なる事は消極的に言ひたるにても知れ可申、もしわが身一つの秋と思ふと詠《よ》むならば感情的なれども、秋ではないがと当り前の事をいはば理窟に陥《おちい》り申候。箇様な歌を善しと思ふはその人が理窟を得《え》離れぬがためなり、俗人は申すに及ばず、今のいはゆる歌よみどもは多く理窟を並べて楽《たのし》みをり候。厳格に言はばこれらは歌でもなく歌よみでもなく候。
芳野山霞《かすみ》の奥は知らねども見ゆる限りは桜なりけり
八田知紀《はったとものり》の名歌とか申候。知紀の家集はいまだ読まねど、これが名歌ならば大概底も見え透《す》き候。これも前のと同じく「霞の奥は知らねども」と消極的に言ひたるが理窟に陥り申候。既に見ゆる限りはといふ上は見えぬ処は分らぬがといふ意味は、その裏に籠《こも》りをり候ものを、わざわざ知らねどもとことわりたる、これが下手と申すものに候。かつこの歌の姿、見ゆる限りは桜なりけりなどいへるも極めて拙《つたな》く野卑《やひ》なり、前の千里《ちさと》の歌は理窟こそ悪《あし》けれ姿は遥《はるか》に立ちまさりをり候。ついでに申さんに消極的に言へば理窟になると申しし事、いつでもしかなりといふに非《あら》ず、客観的の景色を連想していふ場合は消極にても理窟にならず、例へば「駒とめて袖うち払ふ影もなし」といへるが如きは客観の景色を連想したるまでにて、かくいはねば感情を現す能《あた》はざる者なれば無論理窟にては無之候。また全体が理窟めきたる歌あり(釈教の歌の類)、これらはかへつて言ひ様にて多少の趣味を添ふべけれど、この芳野山の歌の如く、全体が客観的即ち景色なるに、その中に主観的理窟の句がまじりては殺風景いはん方なく候。また同人の歌にかありけん
うつせみの我世の限り見るべきは嵐の山の桜なりけり
といふが有之候由、さてさて驚き入つたる理窟的の歌にては候よ。嵐山の桜のうつくしいと申すは無論客観的の事なるに、それをこの歌は理窟的に現したり、この歌の句法は全体理窟的の趣向の時に用うべき者にして、この趣向の如く客観的にいはざるべからざる処に用ゐたるは大俗のしわざと相見え候。「べきは」と係《か》けて「なりけり」と結びたるが最《もっとも》理窟的殺風景の処に有之候。一生嵐山の桜を見ようといふも変なくだらぬ趣向なり、この歌全く取所《とりどころ》無之候。なほ手当り次第|可申上《もうしあぐべく》候也。
(明治三十一年二月二十一日)
五たび歌よみに与ふる書
心あてに見し白雲は麓《ふもと》にて思はぬ空に晴るる不尽《ふじ》の嶺《ね》
といふは春海《はるみ》のなりしやに覚え候。これは不尽の裾《すそ》より見上げし時の即興なるべく、生も実際にかく感じたる事あれば面白き歌と一時は思ひしが、今見れば拙き歌に有之候。第一、麓といふ語|如何《いかが》や、心あてに見し処は少くも半腹《はんぷく》位の高さなるべきを、それを麓といふべきや疑はしく候。第二、それは善しとするも「麓にて」の一句理窟ぽくなつて面白からず、ただ心あてに見し雲よりは上にありしとばかり言はねばならぬ処に候。第三、不尽の高く壮《さかん》なる様を詠まんとならば、今少し力強き歌ならざるべからず、この歌の姿弱くして到底不尽に副《そ》ひ申さず候。几董《きとう》の俳句に「晴るる日や雲を貫く雪の不尽」といふがあり、極めて尋常に叙《じょ》し去りたれども不尽の趣はかへつて善く現れ申候。
もしほ焼く難波《なにわ》の浦の八重霞《やえがすみ》一重《ひとえ》はあまのしわざなりけり
契沖《けいちゅう》の歌にて俗人の伝称する者に有之候へども、この歌の品下りたる事はやや心ある人は承知致しをる事と存候。この歌の伝称せらるるは、いふまでもなく八重一重の掛合《かけあわせ》にあるべけれど、余の攻撃点もまた此処《ここ》に外ならず、総じて同一の歌にて極めてほめる処と、他の人の極めて誹《そし》る処とは同じ点にある者に候。八重霞といふもの固《もと》より八段に分れて霞みたるにあらねば、一重といふこと一向に利き不申、また初《はじめ》に「藻汐《もしお》焼く」と置きし故、後に煙とも言ひかねて「あまのしわざ」と主観的に置きたる処、いよいよ俗に堕《お》ち申候。こんな風に詠まずとも、霞の上に藻汐焚《や》く煙のなびく由尋常に詠まば、つまらぬまでもかかる厭味《いやみ》は出来申間敷候。
心あてに折らばや折らむ初霜《はつしも》の置きまどはせる白菊の花
この躬恒《みつね》の歌、百人一首にあれば誰も口ずさみ候へども、一文半文のねうちも無之《これなき》駄歌に御座候。この歌は嘘《うそ》の趣向なり、初霜が置いた位で白菊が見えなくなる気遣《きづかい》無之候。趣向嘘なれば趣も糸瓜《へちま》も有之不申《これありもうさず》、けだしそれはつまらぬ嘘なるからにつまらぬにて、上手な嘘は面白く候。例へば「鵲《かささぎ》のわたせる橋におく霜の白きを見れば夜ぞ更《ふ》けにける」面白く候。躬恒のは瑣細《ささい》な事をやたらに仰山に述べたのみなれば無趣味なれども、家持《やかもち》のは全くない事を空想で現はして見せたる故面白く被感《かんぜられ》候。嘘を詠むなら全くない事、とてつもなき嘘を詠むべし、しからざればありのままに正直に詠むがよろしく候。雀が舌を剪《き》られたとか、狸《たぬき》が婆《ばば》に化けたなどの嘘は面白く候。今朝は霜がふつて白菊が見えんなどと、真面目《まじめ》らしく人を欺《あざむ》く仰山的の嘘は極めて殺風景に御座候。「露の落つる音」とか「梅の月が匂ふ」とかいふ事をいふて楽《たのし》む歌よみが多く候へども、これらも面白からぬ嘘に候。総《すべ》て嘘といふものは、一、二度は善けれど、たびたび詠まれては面白き嘘も面白からず相成申候。まして面白からぬ嘘はいふまでもなく候。「露の音」「月の匂《におい》」「風の色」などは最早《もはや》十分なれば、今後の歌には再び現れぬやう致したく候。「花の匂」などいふも大方は嘘なり、桜などには格別の匂は無之、「梅の匂」でも古今以後の歌よみの詠むやうに匂ひ不申候。
春の夜の闇はあやなし梅の花色こそ見えね香《か》やは隠るる
「梅闇に匂ふ」とこれだけで済む事を三十一文字に引きのばしたる御苦労加減は恐れ入つた者なれど、これもこの頃には珍しき者として許すべく候はんに、あはれ歌人よ、「闇に梅匂ふ」の趣向は最早打どめに被成《なされ》ては如何《いかが》や。闇の梅に限らず、普通の梅の香も『古今集』だけにて十余りもあり、それより今日までの代々の歌よみがよみし梅の香は、おびただしく数へられもせぬほどなるに、これも善い加減に打ちとめて、香水香料に御用ゐ被成候は格別、その外歌には一切これを入れぬ事とし、鼻つまりの歌人と嘲《あざけ》らるるほどに御遠ざけ被成ては如何や。小さき事を大きくいふ嘘が和歌腐敗の一大原因と相見え申候。
[#地から2字上げ](明治三十一年二月二十三日)
六たび歌よみに与ふる書
御書面を見るに愚意を誤解被致《いたされ》候。殊《こと》に変なるは御書面中四、五行の間に撞著《どうちゃく》有之候。初《はじめ》に「客観的景色に重きを措《お》きて詠むべし」とあり、次に「客観的にのみ詠むべきものとも思はれず」云々《うんぬん》とあるは如何。生は客観的にのみ歌を詠めと申したる事は無之候。客観に重きを置けと申したる事もなけれどこの方は愚意に近きやう覚え候。「皇国の歌は感情を本《もと》として」云々とは何の事に候や。詩歌に限らず総ての文学が感情を本とする事は古今東西相違あるべくも無之、もし感情を本とせずして理窟を本としたる者あらばそれは歌にても文学にてもあるまじく候。ことさらに皇国の歌はなど言はるるは例の歌より外に何物も知らぬ歌よみの言かと被怪《あやしまれ》候。「いづれの世にいづれの人が理窟を読みては歌にあらずと定め候哉《や》」とは驚きたる御問《おんとい》に有之候。理窟が文学に非《あら》ずとは古今の人、東西の人尽《ことごと》く一致したる定義にて、もし理窟をも文学なりと申す人あらば、それは大方日本の歌よみならんと存候。
客観主観感情理窟の語につきて、あるいは愚意を誤解|被致《いたされ》をるにや。全く客観的に詠みし歌なりとも感情を本としたるは言を竢《ま》たず。例へば橋の袂《たもと》に柳が一本風に吹かれてゐるといふことを、そのまま歌にせんにはその歌は客観的なれども、元《も》とこの歌を作るといふはこの客観的景色を美なりと思ひし結果なれば、感情に本づく事は勿論《もちろん》にて、ただうつくしいとか、綺麗《きれい》とか、うれしいとか、楽しいとかいふ語を著《つ》くると著けぬとの相違に候。また主観的と申す内にも感情と理窟との区別有之、生が排斥するは主観中の理窟の部分にして、感情の部分には無之候。感情的主観の歌は客観の歌と比して、この主客両観の相違の点より優劣をいふべきにあらず、されば生は客観に重きを置く者にても無之候。但《ただし》和歌俳句の如き短き者には主観的佳句よりも客観的佳句多しと信じをり候へば、客観に重きを置くといふも此処《ここ》の事を意味すると見れば差支《さしつかえ》無之候。また主観客観の区別、感情理窟の限界は実際判然したる者に非ずとの御論《ごろん》は御尤《ごもっとも》に候。それ故に善悪可否巧拙と評するも固《もと》より画然たる区別あるに非ず、巧の極端と拙の極端とは毫《ごう》も紛《まぎ》るる所あらねど、巧と拙との中間にある者は巧とも拙とも申し兼《かね》候。感情と理窟の中間にある者はこの場合に当り申候。
「同じ用語同じ花月にてもそれに対する吾人《ごじん》の観念と古人のと相違する事珍しからざる事にて」云々、それは勿論の事なれど、そんな事は生の論ずることと毫も関係無之候。今は古人の心を忖度《そんたく》するの必要無之、ただ此処にては、古今東西に通ずる文学の標準(自らかく信じをる標準なり)を以て文学を論評する者に有之候。昔は風帆船《ふうはんせん》が早かつた時代もありしかど、蒸気船を知りてをる眼より見れば、風帆船は遅しと申すが至当の理に有之、貫之は貫之時代の歌の上手とするも、前後の歌よみを比較して貫之より上手の者外に沢山有之と思はば、貫之を下手と評することまた至当に候。歴史的に貫之を褒《ほ》めるならば生も強《あなが》ち反対にては無之候へども、只今の論は歴史的にその人物を評するにあらず、文学的にその歌を評するが目的に有之候。
「日本文学の城壁ともいふべき国歌」云々とは何事ぞ。代々の勅撰集《ちょくせんしゅう》の如き者が日本文学の城壁ならば、実に頼み少き城壁にて、かくの如き薄ツぺらな城壁は、大砲一発にて滅茶滅茶《めちゃめちゃ》に砕《くだ》け可申候。生は国歌を破壊し尽すの考にては無之、日本文学の城壁を今少し堅固に致したく、外国の髯《ひげ》づらどもが大砲を発《はな》たうが地雷火を仕掛《しか》けうが、びくとも致さぬほどの城壁に致したき心願《しんがん》有之、しかも生を助けてこの心願を成就《じょうじゅ》せしめんとする大檀那《おおだんな》は天下一人もなく、数年来鬱積《うっせき》沈滞せる者頃日《けいじつ》漸《ようや》く出口を得たる事とて、前後《ぜんご》錯雑《さくざつ》序次《じょじ》倫《りん》なく大言《たいげん》疾呼《しっこ》、われながら狂せるかと存候ほどの次第に御座候。傍人より見なば定めて狂人の言とさげすまるる事と存候。なほこのたび新聞の余白を借り得たるを機とし思ふ様愚考も述べたく、それだけにては愚意分りかね候に付、愚作をも連ねて御評願ひたく存じをり候へども、あるいは先輩諸氏の怒に触れて差止めらるるやうな事はなきかと、それのみ心配罷《まかり》あり候。心配、恐懼《きょうく》、喜悦、感慨、希望等に悩まされて従来の病体益神経の過敏を致し、日来《ひごろ》睡眠に不足を生じ候次第、愚とも狂とも御笑ひ可被下《くださるべく》候。
従来の和歌を以て日本文学の基礎とし、城壁と為《な》さんとするは、弓矢剣槍《けんそう》を以て戦はんとすると同じ事にて、明治時代に行はるべき事にては無之候。今日軍艦を購《あがな》ひ、大砲を購ひ、巨額の金を外国に出すも、畢竟《ひっきょう》日本国を固むるに外ならず、されば僅少《きんしょう》の金額にて購ひ得べき外国の文学思想抔《など》は、続々輸入して日本文学の城壁を固めたく存候。生は和歌につきても旧思想を破壊して、新思想を注文するの考にて、随《したが》つて用語は雅語、俗語、漢語、洋語必要次第用うるつもりに候。委細後便。
追て、伊勢の神風、宇佐の神勅云々の語あれども、文学には合理非合理を論ずべき者にては無之、従つて非合理は文学に非ずと申したる事無之候。非合理の事にて文学的には面白き事不少《すくなからず》候。生の写実と申すは、合理非合理事実非事実の謂《いい》にては無之候。油画師は必ず写生に依り候へども、それで神や妖怪《ようかい》やあられもなき事を面白く画き申候。しかし神や妖怪を画くにも勿論写生に依るものにて、ただありのままを写生すると、一部一部の写生を集めるとの相違に有之、生の写実も同様の事に候。これらは大誤解に候。
(明治三十一年二月二十四日)
七たび歌よみに与ふる書
前便に言ひ残し候事今少し申上候。宗匠的俳句と言へば、直ちに俗気を聯想するが如く、和歌といへば、直ちに陳腐を聯想致候が年来の習慣にて、はては和歌といふ字は陳腐といふ意味の字の如く思はれ申候。かく感ずる者和歌社会には無之と存候へど、歌人ならぬ人は大方箇様《かよう》の感を抱き候やに承り候。をりをりは和歌を誹《そし》る人に向ひて、さて和歌は如何様《いかよう》に改良すべきかと尋ね候へば、その人が首をふつて、いやとよ和歌は腐敗し尽したるに、いかでか改良の手だてあるべき、置きね置きねなど言ひはなし候様は、あたかも名医が匙《さじ》を投げたる死際《しにぎわ》の病人に対するが如き感を持ちをり候者と相見え申候。実にも歌は色青ざめ呼吸絶えんとする病人の如くにも有之候よ。さりながら愚考はいたく異なり、和歌の精神こそ衰へたれ、形骸《けいがい》はなほ保つべし、今にして精神を入れ替へなば、再び健全なる和歌となりて文壇に馳駆《ちく》するを得べき事を保証致候。こはいはでもの事なるを或《ある》人が、はやこと切れたる病人と一般に見做《な》し候は、如何にも和歌の腐敗の甚しきに呆《あき》れて、一見して抛棄《ほうき》したる者にや候べき。和歌の腐敗の甚しさもこれにて大方知れ可申候。
この腐敗と申すは趣向の変化せざるが原因にて、また趣向の変化せざるは用語の少きが原因と被存《ぞんぜられ》候。故に趣向の変化を望まば、是非《ぜひ》とも用語の区域を広くせざるべからず、用語多くなれば従つて趣向も変化可致候。ある人が生を目して、和歌の区域を狭くする者と申し候は誤解にて、少しにても広くするが生の目的に御座候。とはいへ如何に区域を広くするとも非文学的思想は容《い》れ不申、非文学的思想とは理窟の事に有之候。
外国の語も用ゐよ、外国に行はるる文学思想も取れよと申す事につきて、日本文学を破壊する者と思惟《しい》する人も有之《これある》げに候へども、それは既に根本において誤りをり候。たとひ漢語の詩を作るとも、洋語の詩を作るとも、将《は》たサンスクリツトの詩を作るとも、日本人が作りたる上は日本の文学に相違無之候。唐制に模して位階も定め、服色も定め、年号も定め置き、唐《から》ぶりたる冠衣《かんい》を著《つ》け候とも、日本人が組織したる政府は日本政府と可申候。英国の軍艦を買ひ、独国の大砲を買ひ、それで戦に勝ちたりとも、運用したる人にして日本人ならば日本の勝と可申候。しかし外国の物を用うるは、如何にも残念なれば日本固有の物を用ゐんとの考ならば、その志には賛成致候へども、とても日本の物ばかりでは物の用に立つまじく候。文学にても馬、梅、蝶、菊、文等の語をはじめ、一切の漢語を除き候はば、如何なる者が出来候べき。『源氏物語』、『枕草子《まくらのそうし》』以下漢語を用ゐたる物を排斥致し候はば、日本文学はいくばくか残り候べき。それでも痩《やせ》我慢に、歌ばかりは日本固有の語にて作らんと決心したる人あらば、そは御勝手次第ながら、それを以て他人を律するは無用の事に候。日本人が皆日本固有の語を用うるに至らば日本は成り立つまじく、日本文学者が皆日本固有の語を用ゐたらば、日本文学は破滅可致候。
あるいは姑息《こそく》にも馬、梅、蝶、菊、文等の語はいと古き代より用ゐ来りたれば、日本語と見做《な》すべしなどいふ人も可有之《これあるべく》候へど、いと古き代の人は、その頃新しく輸入したる語を用ゐたる者にて、この姑息論者が当時に生れをらば、それをも排斥致し候ひけん。いと笑ふべき撞著《どうちゃく》に御座候。仮に姑息論者に一歩を借《か》して、古き世に使ひし語をのみ用うるとして、もし王朝時代に用ゐし漢語だけにても十分にこれを用ゐなば、なほ和歌の変化すべき余地は多少可有之候。されど歌の詞《ことば》と物語の詞とは自《おのずか》ら別なり、物語などにある詞にて歌には用ゐられぬが多きなど例の歌よみは可申候。何たる笑ふべき事には候ぞや。如何なる詞にても美の意を運ぶに足るべき者は皆歌の詞と可申、これを外にして歌の詞といふ者は無之候。漢語にても洋語にても、文学的に用ゐられなば皆歌の詞と可申候。
(明治三十一年二月二十八日)
八たび歌よみに与ふる書
悪《あし》き歌の例を前に挙げたれば善き歌の例をここに挙げ可申候。悪き歌といひ善き歌といふも、四つや五つばかりを挙げたりとて、愚意を尽すべくも候はねど、なきには勝《まさ》りてんと聊《いささ》か列《つら》ね申候。先づ『金槐和歌集《きんかいわかしゅう》』などより始め申さんか。
『「金槐和歌集」(きんかいわかしゅう)は、鎌倉時代前期の源実朝の家集(歌集)』
武士《もののふ》の 矢並つくろふ 小手の上に 霰《あられ》たばしる 那須の篠原
八並(やなみ)・・・
といふ歌は万口《ばんこう》一斉《いっせい》に歎賞《たんしょう》するやうに聞き候へば、今更取り出でていはでもの事ながら、なほ御気のつかれざる事もやと存候まま一応申上候。この歌の趣味は誰しも面白しと思ふべく、またかくの如き趣向が和歌には極めて珍しき事も知らぬ者はあるまじく、またこの歌が強き歌なる事も分りをり候へども、この種の句法が殆《ほとん》どこの歌に限るほどの特色を為《な》しをるとは知らぬ人ぞ多く候べき。普通に歌はなり、けり、らん、かな、けれ抔《など》の如き助辞を以て斡旋《あっせん》せらるるにて名詞の少きが常なるに、この歌に限りては名詞極めて多く「てにをは」は「の」の字三、「に」の字一、二個の動詞も現在になり(動詞の最《もっとも》短き形)をり候。かくの如く必要なる材料を以て充実したる歌は実に少く候。新古今の中には材料の充実したる、句法の緊密なる、ややこの歌に似たる者あれど、なほこの歌の如くは語々活動せざるを覚え候。万葉の歌は材料極めて少く簡単を以て勝《まさ》る者、実朝一方にはこの万葉を擬し、一方にはかくの如く破天荒《はてんこう》の歌を為す、その力量実に測るべからざる者有之候。また晴を祈る歌に
時により すぐれば民の なげきなり 八大竜王《はちだいりゅうおう》雨やめたまへ
といふがあり、恐らくは世人の好まざる所と存候へども、こは生の好きで好きでたまらぬ歌に御座候。かくの如く勢強き恐ろしき歌はまたと有之間敷《これあるまじく》、八大竜王を叱《しった》する処、竜王も懾伏《しょうふく》致すべき勢《いきおい》相現れ申候。八大竜王と八字の漢語を用ゐたる処、雨やめたまへと四三の調を用ゐたる処、皆この歌の勢を強めたる所にて候。初三句は極めて拙《つたな》き句なれども、その一直線に言ひ下して拙き処、かへつてその真率《しんそつ》偽《いつわ》りなきを示して、祈晴《きせい》の歌などには最も適当致しをり候。実朝は固より善き歌作らんとてこれを作りしにもあらざるべく、ただ真心より詠み出でたらんが、なかなかに善き歌とは相成り候ひしやらん。ここらは手のさきの器用を弄《ろう》し、言葉のあやつりにのみ拘《こだわ》る歌よみどもの思ひ至らぬ所に候。三句切《さんくぎれ》の事はなほ他日|詳《つまびらか》に可申候へども、三句切の歌にぶつつかり候故一言|致置《いたしおき》候。三句切の歌詠むべからずなどいふは守株《しゅしゅ》の論にて論ずるに足らず候へども、三句切の歌は尻軽くなるの弊《へい》有之候。この弊を救ふために、下二句の内を字余りにする事しばしば有之、この歌もその一にて(前に挙げたる大江千里《おおえのちさと》の月見ればの歌もこの例、なほその外にも数へ尽すべからず)候。この歌の如く下を字余りにする時は、三句切にしたる方かへつて勢強く相成申候。取りも直さずこの歌は三句切の必要を示したる者に有之候。また
物いはぬ よものけだもの すらだにも あはれなるかなや 親の子を思ふ
の如き何も別にめづらしき趣向もなく候へども、一気呵成の処かへつて真心を現して余りあり候。ついでに字余りの事ちよつと申候。この歌は第五句字余り故に面白く候。或《ある》人は字余りとは余儀なくする者と心得候へども、さにあらず、字余りには凡《およそ》三種あり、第一、字余りにしたるがために面白き者、第二、字余りにしたるがため悪《あし》き者、第三、字余りにするともせずとも可なる者と相分れ申候。その中にもこの歌は字余りにしたるがため面白き者に有之候。もし「思ふ」といふをつめて「もふ」など吟じ候はんには興味索然《さくぜん》と致し候。ここは必ず八字に読むべきにて候。またこの歌の最後の句にのみ力を入れて「親の子を思ふ」とつめしは情の切なるを現す者にて、もし「親の」の語を第四句に入れ、最後の句を「子を思ふかな」「子や思ふらん」など致し候はば、例のやさしき調となりて切なる情は現れ不申、従つて平凡なる歌と相成可申候。歌よみは古来助辞を濫用《らんよう》致し候様、宋人の虚字を用ゐて弱き詩を作ると一般に御座候。実朝の如きは実に千古の一人と存候。
前日来生は客観詩をのみ取る者と誤解被致候ひしも、そのしからざるは右の例にて相分り可申、那須の歌は純客観、後の二首は純主観にて、共に愛誦《あいしょう》する所に有之候。しかしこの三首ばかりにては、強き方に偏しをり候へば、あるいはまた強き歌をのみ好むかと被考《かんがえられ》候はん。なほ多少の例歌を挙ぐるを御待可被下《おまちくださるべく》候。
(明治三十一年三月一日)
九たび歌よみに与ふる書
一々に論ぜんもうるさければただ二、三首を挙げ置きて『金槐集』以外に遷《うつ》り候べく候。
山は裂け 海はあせなん 世なりとも 君にふた心 われあらめやも
箱根路をわが越え来れば伊豆の海やおきの小島に波のよる見ゆ
世の中は つねにもがもな なぎさ漕ぐ海人の小舟の綱手かなしも
大海のいそもとどろによする波われてくだけてさけて散るかも
箱根路の歌極めて面白けれども、かかる想は古今に通じたる想なれば、実朝がこれを作りたりとて驚くにも足らず、ただ「世の中は」の歌の如く、古意古調なる者が万葉以後において、しかも華麗を競ふたる新古今時代において作られたる技倆《ぎりょう》には、驚かざるを得ざる訳にて、実朝の造詣《ぞうけい》の深き今更申すも愚かに御座候。大海の歌実朝のはじめたる句法にや候はん。
新古今に移りて二、三首を挙げんに
なごの海の 霞のまより ながむれば 入日《いりひ》を洗ふ沖つ白波
(実定《さねさだ》)
この歌の如く客観的に景色を善く写したるものは、新古今以前にはあらざるべく、これらもこの集の特色として見るべき者に候。惜むらくは「霞のまより」といふ句が疵《きず》にて候。一面にたなびきたる霞に間といふも可笑《おか》しく、縦《よ》し間ありともそれはこの趣向に必要ならず候。入日も海も霞みながらに見ゆるこそ趣は候なれ。
ほのぼのと 有明の月の 月影に 紅葉吹きおろす 山おろしの風
(信明《のぶあき》)
これも客観的の歌にて、けしきも淋《さび》しく艶《えん》なるに、語を畳みかけて調子取りたる処いとめづらかに覚え候。
さびしさに 堪へたる人の またもあれな 庵《いお》を並べん冬の山里
(西行《さいぎょう》)
西行の心はこの歌に現れをり候。「心なき身にも哀れは知られけり」などいふ露骨的の歌が世にもてはやされて、この歌などはかへつて知る人少きも口惜《おし》く候。庵を並べんといふが如き斬新にして趣味ある趣向は、西行ならでは得《え》言はざるべく、特に「冬の」と置きたるもまた尋常歌よみの手段にあらずと存候。後年芭蕉が新《あらた》に俳諧を興せしも寂《さび》は「庵を並べん」などより悟入《ごにゅう》し、季の結び方は「冬の山里」などより悟入したるに非ざるかと被思《おもわれ》候。
閨《ねや》の上に かたえさしおほひ 外面《とのも》なる 葉広柏《はびろがしわ》に 霰《あられ》ふるなり
(能因《のういん》)
これも客観的の歌に候。上三句複雑なる趣を現さんとてやや混雑に陥りたれど、葉広柏に霰のはじく趣は極めて面白く候。
岡の辺《べ》の 里のあるじを 尋ぬれば 人は答へず 山おろしの風
(慈円《じえん》)
趣味ありて句法もしつかりと致しをり候。この種の歌の第四句を「答へで」などいふが如く、下に連続する句法となさば何の面白味も無之候。
ささ波や 比良《ひら》山風の 海吹けば 釣する蜑《あま》の 袖かへる見ゆ
(読人しらず)
実景をそのままに写し些《さ》の巧《たくみ》を弄《もてあそ》ばぬ所かへつて興多く候。
神風や 玉串の葉を とりかざし 内外《うちと》の宮に 君をこそ祈れ
(俊恵《しゅんえ》)
神祇《じんぎ》の歌といへば千代の八千代のと定文句《きまりもんく》を並ぶるが常なるにこの歌はすつぱりと言ひはなしたる、なかなかに神の御心《みこころ》にかなふべく覚え候。句のしまりたる所、半ば客観的に叙したる所など注意すべく、神風やの五字も訳なきやうなれど極めて善く響きをり候。
阿耨多羅三藐三菩提《あのくたらさんみゃくさんぼだい》の仏たち わが立つ杣《そま》に 冥加《めいか》あらせたまへ
(伝教《でんぎょう》)
いとめでたき歌にて候。長句の用ゐ方など古今未曾有《みぞう》にて、これを詠みたる人もさすがなれど、この歌を勅撰集に加へたる勇気も称するに足るべくと存候。第二句十字の長句ながら成語なればさまで口にたまらず、第五句九字にしたるはことさらとにもあらざるべけれど、この所はことさらとにも九字位にする必要有之、もし七字句などを以て止めたらんには、上の十字句に対して釣合取れ不申候。初めの方に字余りの句あるがために、後にも字余りの句を置かねばならぬ場合はしばしば有之候。もし字余りの句は一句にても少きが善しなどいふ人は、字余りの趣味を解せざるものにや候べき。
(明治三十一年三月三日)
十たび歌よみに与ふる書
先輩崇拝といふことはいづれの社会にも有之候。それも年長者に対し元勲に対し相当の敬礼を尽すの意ならば至当の事なれども、それと同時に、何かは知らずその人の力量技術を崇拝するに至りては愚の至りに御座候。田舎の者などは御歌所《おうたどころ》といへばえらい歌人の集り、御歌所長といへば天下第一の歌よみの様に考へ、従てその人の歌と聞けば、読まぬ内からはや善き者と定めをるなどありうちの事にて、生も昔はその仲間の一人に候ひき。今より追想すれば赤面するほどの事に候。御歌所とてえらい人が集まるはずもなく、御歌所長とて必ずしも第一流の人が坐《すわ》るにもあらざるべく候。今日は歌よみなる者皆無の時なれど、それでも御歌所連より上手なる歌よみならば民間に可有之《これあるべく》候。田舎の者が元勲を崇拝し、大臣をえらい者に思ひ、政治上の力量も識見も元勲大臣が一番に位する者と迷信致候結果、新聞記者などが大臣を誹《そし》るを見て「いくら新聞屋が法螺《ほら》吹いたとて、大臣は親任官《しんにんかん》、新聞屋は素寒貧《すかんぴん》、月と泥鼈《すっぽん》ほどの違ひだ」などと罵《ののし》り申候。少し眼のある者は元勲がどれ位無能力かといふ事、大臣は廻《まわ》り持《もち》にて、新聞記者より大臣に上りし実例ある事位は承知致し説き聞かせ候へども、田舎の先生は一向無頓著にて、あひかはらず元勲崇拝なるも腹立たしき訳に候。あれほど民間にてやかましくいふ政治の上なほしかりとすれば、今まで隠居したる歌社会に老人崇拝の田舎者多きも怪むに足らねども、この老人崇拝の弊を改めねば歌は進歩不可致《いたすべからず》候。歌は平等無差別なり、歌の上に老少も貴賤も無之候。歌よまんとする少年あらば、老人抔《など》にかまはず、勝手に歌を詠むが善かるべくと御伝言可被下《くださるべく》候。明治の漢詩壇が振ひたるは、老人そちのけにして青年の詩人が出たる故に候。俳句の観を改めたるも、月並連《つきなみれん》に構はず思ふ通りを述べたる結果に外ならず候。
縁語を多く用うるは和歌の弊なり、縁語も場合によりては善けれど、普通には縁語、かけ合せなどあれば、それがために歌の趣を損ずる者に候。縦《よ》し言ひおほせたりとて、この種の美は美の中の下等なる者と存候。むやみに縁語を入れたがる歌よみは、むやみに地口《じぐち》駄洒落《だじゃれ》を並べたがる半可通《はんかつう》と同じく、御当人は大得意なれども側《はた》より見れば品の悪き事夥《おびただ》しく候。縁語に巧《たくみ》を弄《ろう》せんよりは、真率に言ひながしたるがよほど上品に相見え申候。
歌といふといつでも言葉の論が出るには困り候。歌では「ぼたん」とは言はず「ふかみぐさ」と詠むが正当なりとか、この詞《ことば》はかうは言はず、必ずかういふしきたりの者ぞなど言はるる人有之候へども、それは根本において已に愚考と異りをり候。愚考は古人のいふた通りに言はんとするにてもなく、しきたりに倣《なら》はんとするにてもなく、ただ自己が美と感じたる趣味をなるべく善く分るやうに現すが本来の主意に御座候「ただ自己が美と感じたる趣味をなるべく善く分るやうに現すが本来の主意に御座候」。故に俗語を用ゐたる方その美感を現すに適せりと思はば、雅語を捨てて俗語を用ゐ可申、また古来のしきたりの通りに詠むことも有之候へど、それはしきたりなるが故にそれを守りたるにては無之《これなく》、その方が美感を現すに適せるがためにこれを用ゐたるまでに候。古人のしきたりなど申せども、その古人は自分が新《あらた》に用ゐたるぞ多く候べき。
牡丹《ぼたん》と深見草《ふかみぐさ》との区別を申さんに、生らには深見草といふよりも牡丹といふ方が牡丹の幻影早く著《いちじるし》く現れ申候。かつ「ぼたん」といふ音の方が強くして、実際の牡丹の花の大きく凛《りん》としたる所に善く副《そ》ひ申候。故に客観的に牡丹の美を現さんとすれば、牡丹と詠むが善き場合多かるべく候。
新奇なる事を詠めといふと、汽車、鉄道などいふいはゆる文明の器械を持ち出す人あれど大《おおい》に量見が間違ひをり候。文明の器械は多く不《ぶ》風流なる者にて歌に入りがたく候へども、もしこれを詠まんとならば他に趣味ある者を配合するの外無之候。それを何の配合物もなく「レールの上に風が吹く」などとやられては殺風景の極に候。せめてはレールの傍に菫《すみれ》が咲いてゐるとか、または汽車の過ぎた後で罌粟《けし》が散るとか、薄《すすき》がそよぐとか言ふやうに、他物を配合すればいくらか見よくなるべく候。また殺風景なる者は遠望する方よろしく候。菜の花の向ふに汽車が見ゆるとか、夏草の野末を汽車が走るとかするが如きも、殺風景を消す一手段かと存候。
いろいろ言ひたきまま取り集めて申上候。なほ他日|詳《つまびら》かに申上ぐる機会も可有之《これあるべく》候。以上。月日。
(明治三十一年三月四日)
経歴は定かでなく、『万葉集』によって、大宝元年(701年)持統上皇の吉野宮行幸および大宝2年(702年)の三河国行幸に従駕して歌を詠んだことが知られる。また、平城京遷都後の作品は確認されないため、持統・文武朝(687年-707年)ごろに活躍したかといわれる。推定作を含めて短歌18首が残るが、すべての歌が 旅先での作と思われる。下級の地方官人であったとみる説が有力。。「羈旅の歌八首」 (巻3)が代表的。「旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ舟沖に漕ぐ見ゆ」「いづくにか舟泊てすらむ安礼の崎漕ぎたみ行きし棚なし小舟」のごとく、好んで舟を素材とし、漠とした旅愁を漂わせる作品に特色がある。柿本人麻呂より少しく遅れて登場したらしく、集団的な感情を歌う風潮から離れ、個性を打ち出す方向に進んでいる点が注目される。「桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る」など、観照的な叙景の態度をも示しつつあり、山部赤人の作風の先駆をなす役割を果たしていよう。・・・ウィキペディアより
過ぎ去ってしまった遠い昔――そんな時代を生きた人で私はあるのだろうか。そんなはずもないのに、楽浪の古い都の跡を見れば、心が切なくてならない。
楽浪の国つ御神のうらさびて荒れたる都見れば悲しも
楽浪の地を支配される神の御心がさびれて、荒れてしまった都――その跡を見れば悲しいことよ
今頃、どこに碇泊しているだろうか。安礼の崎を漕ぎ廻って行った、あの棚無し小舟は
大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる
象の中山を、人を呼びながら越えてゆく呼子鳥――大和の方へ行って、鳴いているだろうか。
故郷の都を思いやる私の心を、家族に伝えてくれるだろうか。
旅にあって何となく家恋しい気分でいたところ、さっき山の下にあった朱塗りの船が、今は沖の方を漕いで行くのが見える
桜田の方へ、鶴が鳴いて渡ってゆく。年魚市潟は潮が引いたのであるらしい。鶴が干潟の上を鳴きながら渡ってゆく。
四極山うち越え見れば笠縫の島漕ぎ隠る棚なし小舟
四極山を越えて見やれば、笠縫の島の影に漕ぎ隠れてゆく棚無し小舟よ。
磯の崎を漕ぎ廻ってゆくと、近江の湖の数知れぬ港で鶴がたくさん群れて鳴いている。なんと賑やかな豊かな土地だことよ
我が舟は比良の港に漕ぎ泊てむ沖へな離りさ夜更けにけり
今晩、我等の乗るこの船は比良の船着場に停泊しよう。岸近くを漕いで。沖へ遠く離れるな、もう夜が更けたのだ。
いづくにか我が宿りせむ高島の勝野の原にこの日暮れなば
いったい我らはどこに宿をとろうか。高島の勝野の原で今日のこの日が暮れてしまったら
あなたも私も一体だからでしょうか、三河の二見の別れ道で、別れようとしてなかなか別れられないのは
早来ても見てましものを山背の多賀の槻群(つきむら)散りにかるかも
もっと早く来て見たかったものを。山背の多賀の欅林の紅葉は散ってしまったよ
いざ子ども大和へ早く白菅の真野の榛原手折りて行かむ
さあ皆の者よ、大和へ早く帰ろう。白菅の茂る真野の榛(はん)の木の林で小枝を手折って行こう。
住吉の得名津に立ちて見わたせば武庫の泊りゆ出づる船人
住吉の得名津に立って見渡すと、武庫の泊から、今しも船人たちが大勢漕ぎ出してゆく。
かく故に見じと言ふものをささなみの古き都を見せつつもとな
率ひて漕ぎ去にし舟は高島の安曇の港に泊てにけむかも
婦負の野の薄を一面なびかして降る雪の中、見知らぬ土地で宿を借りる今日という日はことに悲しく思える。
感想
どの歌が気に入ったと言う事はないが、何回か読んでいるうちに、雄大な景色と、素朴な気持ち、その中に旅の不安な気持ちとかが伝わってくる。人麻呂と赤人の間をつなぐ歌人で、赤人に限りなく近いかも
0370 秋来れば常磐の山の松風もうつるばかりに身にぞしみける
秋が来ると常盤の山の常緑の松に吹く風も紅葉の色が移るかのように身に染みてきます。
0408 たのめたる人はなけれど秋の夜は 月見て寝べきここちこそせね秋の月を詠じていくのに、和泉式部の世界が鮮明に表現されている。恋人との関係を踏まえた上でそれ以上に月にあくがれている彼女であるのだ。自己の世界がある歌はいいなと思う。
世の中に猶もふるかなしぐれつつ雲間の月のいでやと思へど
野辺を見ると、尾花の下の思い草が枯れてゆく冬になってしまったのだった
0702 かぞふれば年の残りもなかりけり 老ぬるばかり悲しきはなし
恋多き和泉式部のことを思うと、この歌は一層深刻になってくる。老いのつらさを単なる観念としているだけでなく、実感として歌い上げているところにこの歌の魅力がある。
0775 置くと見し露もありけりはかなくて消えにし人を何に譬へむ
「小式部内侍(和泉式部女)露置きたる萩織りたる唐衣を着て侍りけるを身まかりて後」と詞書にはある。露よりもはかなく消えてしまった我が子のはかなさに茫然としている作者の姿が伝わってくる歌である。
0783 ねざめする身を吹きとほす風の音を 昔は袖のよそに聞きけむ
夜中にふと目覚めてしまう我が身を突き通して吹いてゆく風の音――昔は耳遠いものとして聞いていたのだろうか。こんなに寂しい音だったと、独り寝の今になって初めて知ったのだ。
「弾正為尊親王におくれてなげき侍りける頃」と詞書にある。悲しみのために夜も寝覚めがちで、その悲しみを・・・孤独の・・・さらに掻き立てる風の音である。その風の音にせつなさをふと感じたとき、昔の思い出が蘇りその幸せであった世界がよりいっそう思われてくるのであろう
0816 戀ひわぶと聞きにだに聞け鐘の音に うち忘らるる時の間ぞなき
和泉式部の情念の強さが伝わってくる。こういう強さこそが歌を必然のものとするのであろう。写生ということなど眼中にはない。そんなものを超越した作者の思いの強さが発露されているのである
1012 今日も又かくやいぶきのさしも草 さらばわれのみ燃えや渡らむ
言葉の働きをさまざまな点で駆使した歌である。「伊吹のさしも草」は「もぐさ」で、「燃え」の序詞となっている。さらに「いふき」には「言ふ」が掛けられている。その上で、女の一途な恋心をすっきりと歌い上げているのである。
1023 あとをだに草のはつかに見てしがな 結ぶばかりの程ならずとも
本歌は、「春日野の雪間を分けて生ひ出づる草のはつかに見えし君はも」(古今十一)である。少々、舌足らずな感じもするが、下の句になり、全ての様子が明確になる。和泉式部らしい世界を作り上げているが、言葉の響きに難点がある。
枕さえ知らないのですから、告げ口はしないでしょう。ですからあなた、見たままに人に語ったりしないで下さい、私たちの春の夜の夢を。
1178 今朝はしも歎きもすらむいたづらに 春の夜ひと夜夢をだに見で
「春の夜の夢」の世界の艶にしてはかない世界を底流とした恋の歌である。恋の思いの深まる中で、満たされない心の<たゆたい>を作者自身も吹っ切るようにその原因を歌い上げているのがおもしろい。
1344 いまこんといふことの葉もかれゆくによな/\つゆのなにゝをくらん
男に代わって女のもとに送った歌で、遊びの世界そのものといったらよかろう。男の気持ちを推測しての歌で、言の葉は枯れ、そうしたら、涙の露はどこに宿ればよいのかと機知を働かせたのである。
1401 いかにしていかにこの世にありへばか 暫しも物を思はさるべき
恋する女として著名な作者が、恋する悲哀をふと吐露した歌である。どうしたら恋をしなくてすむのだろうか。そんな思いが頭をよぎる。しかし、作者は、恋へと一層傾斜してゆくのであろう。それにしても「いかにしていかにこの世・・・」という詠い出しは斬新である
1458 をる人のそれなるからにあぢきなく 見しわが宿の花の香ぞする
公任の歌への返しである。公任が、折り取って送ってくれたその花へのお礼の気持ちが充満した香となっている。作者の感謝の念に溢れた返歌となっている。人の心を、作者は、素直に表現し、生き生きと生活している様子が伝わってくる。
1493 思ひあらば今宵の空は問ひてまし 見えしや月のひかりなりけむ
。「思ひ」の「火」があれば、螢の飛ぶという雨の今夜は尋ねてくれそうなのに、贈ってくれたのは、「火」のない「月」の光であったと言うのである。男の不誠実さを言いながら、裏返しに、男への愛情を表現しているのである。「見えしや月のひかりなりけむ」には、作者の豊かな才能を思わずにはいられない。
1527 住みなれし人影もせぬわが宿に 有明の月のいく夜ともなく
よく通って来てくれた人の気配も絶えた我が家に、有明の月明りが幾夜ともなく射して――。
1638 世をそむく方はいづくもありぬべし 大原山はすみよかりきや
少将井の尼が大原から出たということを聞いて送った歌である。作者と尼との親しい関係が伝わってくる。「すみ」は「住み」と「炭」との掛詞で、大原へ籠もった尼に「どうして大原なの?」「住みよかったの?炭もよかったの?」と冗談めかしているところに二人の関係が表現されているという作品だ。
1714 潮のまに四方のうらうら尋ぬれど今は我が身のいふかひもなし
。「かひ」は、「甲斐」と「貝」との掛詞となっている。海岸での貝拾いのイメージとこの世を生きる甲斐とが重なり合う。そして、その答えは、「かひもなし」として結ばれる。様々な体験の中で結局は確かなものを持ち得なかった作者の思いへとつながってゆく。
1734 命だにあらば見つべき身のはてを 忍ばむ人のなきぞ悲しき
恋多き女性として有名な作者ではあるが、その心の奥には、人間不信とそのせつなさが厳然としているのである
1806 夕暮は雲のけしきを見るからに眺めじと思ふ心こそつけ
作者の日常生活の感慨を詠じたものである。夕暮の雲をむると寂しさが募るから、もう見まいと決心する。「じ」「こそつけ」という言葉によって強調された決心である。しかし、強調されればされるほど、夕暮になると雲を繰り返し見なければならない作者の悲しみが伝わってくる。
日は暮れてしまったようだ。こんなふうにして何日を過ごしたのだろう。入相の鐘を撞き、また撞きする音をつくづくと聞くばかりで…。
1811 かくばかり憂きを忍びて長らへば これよりまさる物もこそ思へ
詞書には「尼にならむと思ひ立ちけるを、人のとどめ侍りければ」とある。この世への未練は、「もこそ思へ」という言葉によって、断定的な理屈ではないが、情感として拒絶されるのである。作者の現実生活の苦悩がしみじみとした言葉で伝えられる歌である。
1821 秋風はすごく吹けども葛の葉の うらみがほには見えじとぞ思ふ
前歌・赤染衛門への返歌である。「秋風」には「飽く」が掛けられていて、道貞が自分を嫌になっているという気持ちが込められている。葛の葉といえば、裏返って「裏見」につながるし、それは「恨み」ともなる。「葛の葉」をキーワードにした贈答歌で、作者が、赤染衛門の忠告を聞き入れ、道貞への未練を歌ったものである。
千八百二十番 赤染衛門
うつろはでしばし信太の森を見よ かへりもぞする葛のうら風
詞書には、「和泉式部、道貞に忘られて後、程なく敦道親王かよふと聞きて遣はしける」とある。親友であった恋多き和泉式部への忠告を込めての歌である。「信太の森」は葛の名所の歌枕であると同時に和泉国で道貞を暗示している。さらに、風に翻って裏葉を見せる葛から、夫である道貞の心が戻ってくることを伝えたのである。歌が生活の中で生き生きしている様子が伺える。
母はうたた寝を叱ったものであるが、こうして物思いに耽りながら寝転んでいるのを、どうしたのかと今は尋ねてくれる人もいない。◇たらちめの諌(いさ)めしものを 親に諌められた行いとは、うたた寝のこと。
あらざらむこの世のほかの思ひいでに今ひとたびの逢ふこともがな(後拾遺763)
私はじきにこの世からいなくなってしまうでしょう――今生(こんじょう)の外へと携えてゆく思い出として、もう一度だけあなたにお逢いすることができたなら。
【語釈】◇あらざらむこの世 やがて私がいなくなるであろうこの世。◇この世のほか この世以外の世。あの世。
はかなしとまさしく見つる夢の世をおどろかでぬる我は人かは(続集)
儚いものだと、まざまざと思い知った夢の如き世――それなのにこの世から目を醒まさず眠りに耽っている私は人と言えようか。
夕暮はいかなる時ぞ目にみえぬ風の音さへあはれなるかな(続集)
夕暮とは一体どのような時なのか。目に見えない風の音さえしみじみと感じられるよ
生きていられそうには思えないなあ。別れてしまった人の心が、私の命であったのだ。
【語釈】◇今日や我が世の 拾遺集の歌「侘びつつも昨日ばかりはすぐしてき今日やわが身のかぎりなるらむ」などに拠るか。今日が最期の日か、の意。◇別れにし… 別れていった恋しい人と共に、私の命も我が身を去ってゆくのか。
和泉式部の人生の夫の多くを経験し、恋の歌が多く、私には理解が乏しい面もあるが当時の女の境遇などを考えれば結構生きたいように生きた方では。枕だに知らねば言はじ見しままに君語るなよ春の夜の夢 の歌に結構気が強い面があるのかも。次に新古今和歌集に多く取り上げている式子内親王 しょくしないしんのう 久安五~建仁一(1149~1201)について調べてみようと思います。これで当時の女流歌人の理解がおおよそながらできるのでは。「彼女の歌の特色は、上に才氣溌剌たる理知を研いて、下に火のやうな情熱を燃燒させ、あらゆる技巧の巧緻を盡して、内に盛りあがる詩情を包んでゐることである。即ち一言にして言へば式子の歌風は、定家の技巧主義に萬葉歌人の情熱を混じた者で、これが本當に正しい意味で言はれる『技巧主義の藝術』である。そしてこの故に彼女の歌は、正に新古今歌風を代表する者と言ふべきである」(萩原朔太郎『戀愛名歌集』)・・・以上ウィキペディアより
朔太郎の言うところを理解できればと、また和泉式部との違いが分かれば自分としては十分と思い、新古今和歌から歌を拾って読んでみました。生涯独身、出家して法名は承如法
新古今和歌より
眺め入った今日は過去になるとしても、軒端の梅は私を忘れずにいておくれ
0101 はかなくて過ぎにしかたをかぞふれば花に物思ふ春ぞ経にける
とりとめもなく過ぎてしまった年月を数えれば、桜の花を眺めながら物思いに耽る春ばかりを送ってしまった。
花は散り果てて、これというあてもなく眺めていると、空虚な空にただ春雨が降っている。
0308 うたた寝の朝けの袖にかはるなり馴らす扇の秋の初風
転た寝した明け方の袖に、変わったと感じる。なれ親しんだ扇の風が、今年最初の秋風に――。
0321 ながむれは衣手涼し久かたの天の川原の秋の夕暮
じっと眺めていると、自分の袖も涼しく感じられる。川風が吹く、天の川の川原の秋の夕暮よ。
0349 花すすきまだ露ふかし穂に出でて
薄の穂にも又私の涙のように露が深く置いていて、じっと眺めないでおこうと思う、まだ秋の真最中なのに。
0368 それながら昔にもあらぬ秋風にいとどながめをしづの
それはそれ、月は同じ月であるのに、やはり昔とは異なる月影――その光に、いよいよ物思いに耽って眺め入ってしまった、繰り返し飽きもせず】◇しづのをだまき 倭文(しづ)を織るのに用いた苧環。苧環を繰ると言うことから「繰り返し」の意を呼び込む。「しづ」には「(ながめを)しつ」の意を掛ける。
0380 ながめ侘びぬ秋よりほかの宿りかな野にも山にも月やすむらん
つくづく眺め疲れてしまった。季節が秋でない宿はないものか。野にも山にも月は澄んでいて、どこへも遁れようはないのだろうか。
0474 跡もなき庭の浅茅に結ぼほれ露の底なる松虫の声
人の通った跡もなく生い茂る庭の浅茅――その草葉にぎっしりと絡みつかれ、露の底から聞こえてくる、人を待つような松虫の声よ。】◇浅茅 丈の低いチガヤ。王朝文芸では、屋敷などの荒廃を表わすのに用いられた。◇むすぼほれ 「むすぼほる」は絡み合い結び合ってほどけない状態になること
0484 千度うつ
果てしなく擣つ砧の音に夢から醒めて、悲しい物思いに耽る私の涙が落ち、袖に砕け散る。
0534 桐の葉も踏み分けがたくなりにけり必ず人を待つとなけれど
桐の落葉も踏み分け難いほど積もってしまったなあ。必ずしも人を待つというわけではないけれど
0662 さむしろの夜半の衣手さえさえて初雪しろし岡の辺の松
寝床の上の夜の袖が冷え冷えとしていたが、今朝見れば初雪が白く積もっているよ、岡のほとりの松は。
私の玉の緒よ、切れてしまうなら切れてしまえ。もし持続すれば、堪え忍ぶ力が弱ってしまうのだ】◇玉の緒 魂と身体を結び付けていると考えられた緒。命そのものを指して言うこともある。◇絶えなば絶えね 絶えてしまうなら絶えてしまえ。「な」「ね」は、完了の助動詞「ぬ」のそれぞれ未然形・命令形。
1035 忘れてはうち歎かるる夕べかな我のみ知りて過ぐる月日を
そのことをふと忘れては、思わず歎息してしまう夕べであるよ。この思いは私だけが知っていて、あの人に知らせず過ごしてきた長い月日であるのに。
1036 我が恋はしる人もなしせく床の涙もらすな
】私の恋心は知る人とてない。堰き止めている床の涙を洩らすな、黄楊(つげ)の枕よ。
1153 逢ふことをけふ松が枝の手向草いく夜しをるる袖とかは知る
初めての逢瀬を今日待つことになりましたが、これまで幾夜涙に濡れ弱った袖か御存知ないでしょう。
1309 今はただ心のほかに聞くものを知らず顔なる荻の上風
歌の世界の奥のほうへと誘われてしまう歌である。恋人の訪れを待ち、荻の葉づれの音に心をときめかせたあの幸せは、もはや、失われてしまった。しかし、「荻のうはかぜ」の音にふと昔の世界へと戻されてゆく自分に作者の悲しみは沈潜して行くのであろう
1328 さりともと待ちし月日ぞうつりゆく心の花の色にまかせて
日常のありふれた言葉の組み合わせであるが、作者独自の世界を構築している。男の心変わりを静かに見つめている作者の姿が浮かび上がる。その冷静さの中に「色見えで移ろふ物は世の中の人の心の花にぞありける」(古今十五)を思い浮かべ、寂しい心に納得するのであろうか。
1392 はかなくぞ知らぬ命を歎きこし我がかねごとのかかりける世に
未来への希望をさえ絶たれたことを自覚したときの気持ちが嘆きとして表出されている。恋への憧れが強く、その思いだけを支えとして生きてきたそんな作者の姿が伺える。しかし、その強い意志も無常の認識の上に成り立っていることを知らざるを得ないのである。
1810 暁のゆふつけ鳥ぞあはれなる長き
暁の鶏の声こそ身に沁みてあわれ深い。無明長夜の眠りを嘆かわしく思っている寝覚めの枕で。
1847 暮るるまも待つべき世かはあだし野の末葉の露に嵐たつなり
上の句の強い無常認識が「べき」「かは」という言葉で支えられている。その認識は、下の句の風景描写で明確になる。「あだし野」という地名、末葉に宿るはかない露。さらに、露を散らす強風。認識とその心象風景をが一体になった歌である。
静かな暁ごとに自身を観ずれば、まだ深い迷妄の夢の中にあることが悲しい。
以上読んでみて比較的に作者の心情が偲ばれる。品のある静かな歌の中に寂しさが漂って理解できる。和泉式部もそんな歌を詠んでもいるが結構気の強いところがあるようです。何はともあれ人生のもののあわれはひしひしと伝わって、人の一生、女の一生を垣間見れた気がする 簡単すぎるかも、折々にまた読んでみよう
2018/6/20記
名前をよく聞くがいまいち記憶に乏しい感じ、改めて調べてみた。
在原業平(825~880)平安時代前期~中期の歌人。六歌仙,三十六歌仙の一人。平城天皇皇子阿保 (あぼ) 親王の第5子。母は桓武天皇皇女伊登 (いと) 内親王。天長3 (826) 年在原姓を賜わり,従四位上,右近衛権中将にいたった。在中将,在五中将とも呼ばれる。『伊勢物語』の主人公に擬せられ,その奔放な行動と情感のあふれた歌によって小野小町と並称される。『古今集』以下の勅撰集に 90首近く入集。容姿が美しく,後世,美男の代名詞とされた。
どんな歌があるか調べれば古今集などで目にしている歌が多く見受けられる。美男子であり小野小町と並び称される情感の溢れる歌を改めて理解できればとのテーマを心の隅に入れて歌を読んでみようと思う。古今和歌集より以下の歌をざっと洗い出す。伊勢物語の主人公とも言われており、伊勢物語のことも知りたい。小野小町についても伊勢物語と同様生誕地から謎であるらしい。こちらの歌もメモしておこう。
【通釈】神々の霊威で不可思議なことがいくらも起こった大昔にも、こんなことがあったとは聞いていない。龍田川の水を美しい紅色に括り染めするとは。
世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし
【通釈】この世の中に全く桜というものが無かったならば、春を過ごす心はのどかであったろうよ。
忘れては 夢かとぞ思ふ 思ひきや 雪踏みわけて 君を見むとは
【通釈】ふとこの現実を忘れては、これはやはり夢ではないかと思うのです。まさか思いもしませんでした、かくも深い雪を踏み分けて、殿下にお目にかかろうとは。
から衣 きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞ思ふ
【通釈】衣を長く着ていると褄(つま)が熟(な)れてしまうが――そんなふうに馴れ親しんで来た妻が都にいるので、遥々とやって来たこの旅をしみじみと哀れに思うことである。
名にし負はば いざこと問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと
【通釈】「都」というその名を持つのに相応しければ、さあ尋ねよう、都鳥よ。私が恋しく思う人は無事でいるかどうかと。
月やあらぬ 春や昔の 春ならぬ 我が身ひとつは もとの身にして
【通釈】自分ひとりは昔ながらの自分であって、こうして眺めている月や春の景色が昔のままでないことなど、あり得ようか。昔と同じ晴れ晴れとした月の光であり、梅の咲き誇る春景色であるはずなのに、これほど違って見えるということは、もう自分の境遇がすっかり昔とは違ってしまったということなのだ。
立ち別れ いなばの山の 峰におふる 松とし聞かば 今かへりこむ
【通釈】あなたと別れて(因幡の国へ)行くけれども、稲葉の山の峰に生えている松のように、あなたが待っていると聞いたなら、すぐにも都に帰ってまいりましょう。
つひにゆく 道とはかねて 聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを
【通釈】いつか最後に通る道とは以前から聞いていたけれど、まさか昨日今日その道を通ろうとは思いもしなかったのに。
世の中に さらぬ別れの なくもがな 千代もとなげく 人の子のため
【通釈】この世に、避けられない別れなどなければよいのに。千年も長生きしてほしいと悲しむ、人の子のために。
伊勢物語
定家本によれば全125段からなり、ある男の元服から死にいたるまでを数行程度(長くて数十行、短くて2~3行)の仮名の文と歌で作った章段を連ねることによって描く。章段の冒頭表現にちなんで、この主人公の男を「昔男」と呼ぶことも古くから行われてきたが、歌人在原業平の和歌を多く採録し、主人公を業平の異名で呼んだりしている(第63段)ところから、主人公には業平の面影がある。ただし主人公が業平とあらわに呼ばれることはなく(各章段は「昔、男…」と始まることが多い)、王統の貴公子であった業平とは関わらないような田舎人を主人公とする話)も含まれている。中には業平没後の史実に取材した話もあるため、作品の最終的な成立もそれ以降ということになる。
話の内容は男女の恋愛を中心に、親子愛、主従愛、友情、社交生活など多岐にわたるが、主人公だけでなく、彼と関わる登場人物も匿名の「女」や「人」であることが多いため、単に業平の物語であるばかりでなく、普遍的な人間関係の諸相を描き出した物語となりえている
『伊勢物語』の作者論は、作品そのものの成立論と不即不離の関係にあり、『古今和歌集』と『後撰和歌集』の成立時期の前・間・後のいずれの時期で成立したかについても説が分かれていた。しかし近年では、『伊勢物語』と実在した業平とのあいだには一線を画す必要があると考えられている
現在行われている成立論のひとつとして、片桐洋一の唱えた「段階的成長」説がある。元来業平の歌集や家に伝わっていた話が、後人の補足などによって段階的に現在の125段に成長していったという仮説である。ただし増補があったとするには、現行の125段本以外の本がほぼ確認できないという弱みがあり、段階的な成長を説くことに対する批判もある。また、最終的に秩序だって整理されたとするならば、その整理者をいわゆる作者とすべきではないか、という指摘も見られる。近代以前の作品の有り方は、和歌にせよ散文にせよそれ以前の作品を踏まえるのが前提であると考えられ、現代的な著作物の観念から見た作者とは分けて考える必要がある。
そのような場合も含めて、個人の作者として近年名前が挙げられる事が多いのは紀貫之らである。しかし作者論は現在も流動的な状況にある。
ウィキペディアより抜粋
小野小町(生没年不詳 生誕地なども不明)も載せました。業平と同じ歌の調子が似ているのは当時の歌詠みの手法が同じとも思えるが、係言葉、掛詞にも当時の歌の流行であろうか。
花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
【通釈】花の色は褪せてしまったなあ。我が身を徒にこの世に置き、むなしく時を経る――春の長雨が降り続ける中、物思いに耽っていた、その間に。
思ひつつ 寝ればや人の 見えつらむ 夢と知りせば 覚めざらましを
【通釈】恋しく思いながら寝入ったので、その人が現れたのだろうか。夢だと知っていたら、目覚めたくはなかったのに。
いとせめて 恋しき時は むばたまの 夜の衣を 返してぞきる
【通釈】どうにもならぬほど恋しい時は、夜の衣を裏返して着るのです。
うつつには さもこそあらめ 夢にさへ 人目をもると 見るがわびしさ
【通釈】現実にあっては、人目をうかがうということもあるだろう。でも夢の中でさえ、私は他人の目を気にしている。そんな夢を見ることの侘びしさよ。
夢ぢには 足も休めず かよへども うつつにひと目 見しごとはあらず
【通釈】夢の中の通り路では、足も休めずにあなたのもとへ通いますけれども、いくら夢でお逢いできても現実に一目お逢いした時にはかないません。
色見えで うつろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける
【通釈】花は色に見えて変化するものだが、色には見えず、知らぬうちに変化するもの、それは恋仲にあって人の心に咲く花だったのだ
わびぬれば 身を浮草の 根を絶えて さそふ水あらば いなむとぞ思ふ
【通釈】侘び暮らしをしていたので、我が身を憂しと思っていたところです。浮草の根が切れて水に流れ去るように、私も誘ってくれる人があるなら、一緒に都を出て行こうと思います。
壬生 忠岑(みぶ の ただみね、貞観2年(860年)頃 - 延喜20年(920年)頃)は、平安時代前期の歌人。三十六歌仙の一人。身分の低い下級武官であったが、歌人としては一流と賞されており、『古今和歌集』の撰者として抜擢された。後世、藤原定家、藤原家隆から『古今和歌集』の和歌の中でも秀逸であると作風を評価されている。
・・・以上ウィキペディアより抜粋
壬生忠岑は古今集の選者であるばかりでなく藤原定家、藤原家隆から『古今和歌集』の和歌の中でも秀逸であると作風を評価されている。どんな歌が秀逸であるか気になり、一度取り上げてみたい人物でした。古今和歌集から歌を洗い出し、検討してみます。古今和歌集より、歌を洗い出しました。きぬと 人は言へども うぐひすの 鳴かぬかぎりは あらじとぞ思ふかと 見れば明けぬる 夏の夜を あかずとや鳴く 山郭公
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どの歌も模範的に歌われている様で鋭い感性が感じられるが個人的な感情も昇華しておりその点でインパクトが弱いように感じます。恋の歌も寂しく想う歌で侘しさが残る。和泉式部や式子内親王という女流歌人とは、通じるようで弱いようも感じる。また歌を詠む内容に歌のための歌(作意のための心情のない歌が見受けられる 藤衣・・・住吉と・・・隠れ沼の・・・など0836番以後の歌など 平安当時の歌の模範サンプルとして当時の歌人を理解する点で参考になる
みなもとのつねのぶ 長和五~永長二(1016-1097)
三河権守・ 刑部少輔・左馬頭・少納言などを経て、康平3年(1062年)右中弁に任ぜられ、以後蔵人頭などを経て、治暦3年(1067年)参議として公卿に列す。
治暦4年(1068年)兼伊予権守、治暦5年(1069年)従三位・東宮権大夫、延久2年(1070年)兼大蔵卿、延久3年(1071年)正三位、延久4年(1072年)左大弁、延久5年(1073年)兼播磨権守、延久6年(1074年)皇后宮権大夫・兼勘解由長官、承保2年(1075年)権中納言、承保4年(1077年)正二位、承暦5年(1081年)兼民部卿、永保3年(1083年)69歳で権大納言に進み、兼皇后宮大夫。寛治5年(1091年)大納言、寛治8年(1094年)大宰権帥に任命され、翌嘉保2年(1095年)現地に下向し、承徳元年(1097年)大宰府で没している。82歳。
詩歌・管絃に秀で、有職故実にも通じ、その多芸多才は藤原公任に比較された。長久2年(1041年)の「祐子内親王家名所歌合」をはじめとして、多くの歌合に参加している。当代一の歌人とされたが、経信をさしおいて藤原通俊が撰集した『後拾遺和歌集』に対して『後拾遺問答』・『難後拾遺』を著してこれを批判した。
以上取りあえずこまごまと経歴、人物などが紹介されているが、目を通しても意味がない。今回取り上げたのは
「かの大納言の歌の風体は、又殊にたけをこのみ、ふるき姿をのみこのめる人とみえ」(俊成『古来風体抄』)
「大納言経信、殊にたけもあり、うるはしくして、しかも心たくみに見ゆ」(『後鳥羽院御口伝』)
の文面のたけについて知りたかったからです。
調べると
たけ 調子の張った上に単調を救う曲折のあること
静けさ、温かみ、しなやかさ、美しさ、粘り強さ などがうたわれているか
この辺の意味が生半可なため、”歌を通して理解できるか” をテーマにして、新古今和歌より抜粋して、歌を検討してみようかな。
見山花といへる心を
山ふかみ杉のむらだち見えぬまで尾上の風に花の散るかな(新古122)
山が深いので、群生する杉木立も見えないほど、尾上を吹く風によって花が散り乱れている。
尾上(をのへ) 山の峰つづき。尾根。
ふるさとの花の盛りは過ぎぬれど面影さらぬ春の空かな(新古148)
古里の花の盛りは過ぎてしまったけれど、その幻影が消え去ることのない春の空であるなあ
◇ふるさと 昔馴染みの懐かしい里、あるいは古い由緒のある里。
どうとでもなれ、暮れてゆく春も――。「雲の上」すなわち内裏で、散ることを知らぬ桜の花が色美しく咲いているのなら。
五月五日、薬玉つかはし侍りける人に
あかなくに散りにし花の色々は残りにけりな君が袂に(新古222)
見飽きないままに散ってしまったさまざまな色の花は、あなたの袂のうちに残っていたのですね
五月の節句、薬玉を贈ってくれた人に届けた歌。薬玉は袖から肩に廻して結ぶので、袂に花が残っていると言ったのだろう。
山畦早苗といへる心を
早苗とる山田のかけひもりにけり引くしめなはに露ぞこぼるる(新古225)
早苗を取る山田に引いた樋(とい)――その水が漏れてしまったな。引き渡した注連縄に露がこぼれている
早苗(さなへ)とる 若苗を田へ移し替えるために苗代から採る かけひ 懸樋。水を通す樋(とい)。
三島江の入江のまこも雨ふればいとどしをれて苅る人もなし(新古228)
三島江の入江の真菰(まこも)は、雨が降るので、ますます萎れて、刈る人もいない
筑紫に侍りける時、秋野を見てよみ侍りける
花見にと人やりならぬ野辺に来て心のかぎりつくしつるかな(新古342)
花を見ようと、人に行かされたのでなく自分の意志で野辺までやって来て 、心の限界まで尽くして花を愛で憔悴してしまった。つくしつるかな 「尽くし」に「筑紫」を掛ける 景を言わずただ心を詠むことで、野一面を埋め尽くす秋の花々のイメージが髣髴する
月影のすみわたるかな天の原雲吹きはらふ夜はの嵐に(新古411)
月の光が澄み渡っていることよ。大空の雲を吹き払う夜の嵐によって
ふるさとに衣うつとは行く雁や旅の空にも鳴きてつぐらむ(新古481)
故郷で私が衣を打っているとは、飛び行く雁よ、旅の空にある夫にも鳴いて告げてくれるだろうか
ちりかかる紅葉ながれぬ大井川いづれ井せきの水のしがらみ(新古555)
散り落ちる紅葉が一向に流れない大井川――どこに水を堰き止める柵(しがらみ)があるのだろうか
み山路に今朝や出でつる旅人の笠しろたへに雪つもりつつ(新古928)
深山の道に今朝出たばかりなのだろうか。旅人のかぶる笠が真白になって雪が降り積もっている。
家にて、月照水といへる心を、人々よみ侍りけるに
すむ人もあるかなきかの宿ならし蘆間の月のもるにまかせて(新古1530)
住む人もいるのかいないのか分からない家と見える。蘆の繁る隙間から月の光が池に漏れ射すままに放置して。 蘆草の名。アシ
以上の歌を読むにつけ、発想は万葉、古今と変わらずに「古き姿を好める」事が解る。上の句を下の句で誇張などなくスラリと受け流す歌が目立つ。”たけ”とはこの辺の感覚を意味しているか。
平成24年09月22日(彼岸)
古今集は何なのか、以前より短歌を詠むための教本かと思い、某HPで最初より一首づづ読んできましたが、全部で1100首あり、読み始めると内容の理解が出来ず、直飽きてしまい眠くなる。したがって気が向いたときに読む結果、忘れてしまい、同じ箇所を何回か読んだりしてこの一年かかっても終らない。これではいけないと思い、再度目的意識を持って整理してみようと思いました。全部読まなくても気に入った歌、有意義な情報、勘所が解かればいいと思うようになりました。
以下は、いろいろなHPを参考にコピー、ペーストで貼り付け、自分なりの考えなども入れた自分なりのメモ文としています。
目的
『古今和歌集』は仮名で書かれた仮名序と真名序の二つの序文を持つが仮名序によれば、醍醐天皇の勅命により『万葉集』に撰ばれなかった古い時代の歌から撰者たちの時代までの和歌を撰んで編纂し、延喜5年(905年)4月18日に奏上された。ただし現存する『古今和歌集』には、延喜5年以降に詠まれた和歌も入れられており、奏覧ののちも内容に手が加えられたと見られ、実際の完成は延喜12年(912年)ごろとの説もある。
選者
撰者は紀友則、紀貫之、凡河内躬恒(おおしこうち の みつね)、壬生忠岑(みぶ の ただみね)の4人である。序文では友則が筆頭にあげられているが、真名序の署名が貫之であること、また巻第十六に「紀友則が身まかりにける時によめる」という詞書で貫之と躬恒の歌が載せられていることから、編纂の中心は貫之であり、友則は途上で没したと考えられている。
構成
評価の遷移
藤原俊成はその著書『古来風躰抄』に、「歌の本躰には、ただ古今集を仰ぎ信ずべき事なり」と述べており、これは『古今和歌集』が歌を詠む際の基準とすべきものであるということである。この風潮は明治に至っても続いた。ただし江戸時代になるとその歌風は賀茂真淵などにより、『万葉集』の「ますらをぶり」と対比して「たをやめぶり」すなわち女性的であると言われるようになる。
西行は 「和歌はうるはしく詠むべきなり。古今集の風体を本として詠むべし。中にも雑の部を常に見るべし。但し古今にも受けられぬ体の歌少々あり。古今の歌なればとてその体をば詠むべからず。心にも付けて優におぼえん其の風体の風理を詠むべし」と言っている。
正岡子規が『再び歌よみに与ふる書』のなかで「貫之は下手な歌よみにて古今集は下らぬ集にて有之候」と述べて以降、『古今和歌集』の評価は著しく下がった。その背景には当時、古今集の歌風の流れを汲む桂園派への批判もあったといわれるが、『古今和歌集』は人々から重要視されることがなくなり、そのかわりに『万葉集』の和歌が雄大素朴であるとして高く評価されるようになった。
和辻哲郎は直截には言わないが『古今和歌集』の和歌が総体として「愚劣」であるとしており、
萩原朔太郎にいたっては「笑止な低能歌が続出」「愚劣に非ずば凡庸の歌の続出であり、到底倦怠して読むに耐へない」とまで罵倒する。そして現在は「愚劣」という言葉こそ使われないものの、『万葉集』を尊び『古今和歌集』はそれよりも劣ったものとする前代からの風潮は、大勢として変わってはいない。
以上より、評価の点で、正岡子規、和辻哲郎、萩原朔太郎の評価は手厳しい。自分にはこの当りが理解不能。確かに西行も、「受け付けられぬ体の歌あり、その体をば詠ずべからず。心にも付けて優におぼえん其の風体の風理を詠むべし」
と言っている。17巻、18巻当りを読み込めと言うことか。何を捕えて低能歌、凡庸の歌、愚劣というか。六歌仙の歌も出ているでは。それも愚劣で凡庸か。この辺を見極め、西行の風体の風理を理解することを主眼に再度読んでいこうと思います。
以下に仮名の序より、20巻まで自分の気に入った歌、参考になる歌、気になる歌を巻ごとに洗い出し、メモしました。其の過程を通して風体の風理を理解出来れば幸い。
やまと歌は
人の心を種として
よろづの言の葉とぞなれりける
世の中にある人
事 業しげきものなれば
心に思ふことを見るもの聞くものにつけて
言ひいだせるなり
花に鳴くうぐひす
水に住むかはづの声を聞けば
生きとし生けるもの
いづれか歌をよまざりける
力をも入れずして天地を動かし
目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ
男女のなかをもやはらげ
猛きもののふの心をもなぐさむるは歌なり
この歌 天地の開け始まりける時よりいできにけり
天の浮橋の下にて 女神男神となりたまへることを言へる歌なり
しかあれども
世に伝はることは
久方の天にしては下照姫に始まり
下照姫とは 天わかみこの妻なり
兄の神のかたち 丘谷にうつりて輝くをよめるえびす歌なるべし
これらは 文字の数も定まらず 歌のやうにもあらぬことどもなり
あらがねの地にしてはすさのをの命よりぞおこりける
ちはやぶる神世には歌の文字も定まらず
すなほにして
言の心わきがたかりけらし
人の世となりて
すさのをの命よりぞ
三十文字あまり一文字はよみける
すさのをの命は 天照大神のこのかみなり
女と住みたまはむとて 出雲の国に宮造りしたまふ時に
そのところに八色の雲の立つを見て よみたまへるなり
現代語 訳追加 和歌の起りと詩形の成立
和歌と言うものは天地が分れて、この世界が生まれた時から作られて来た。(天浮橋の下でイザナギ、イザナミの神が夫婦になられたことを歌った歌のこと)
しかしながら実際に世間に伝わったものは、高天原の話としては下照姫に始まり、(下照姫とは天稚彦の妻で、天稚彦の姿が岡や谷に映って輝いたのを詠んだ歌であり、文字の数もばらばらで歌の形をなしていないものてだった)地上の話としては素戔鳴命から始まった。神代には文字の数も定まっておらず、思ったとおりを言葉にするので、言っている意味がよくわからないようなものであったらしい。
人の世の中になって素戔鳴命から三十一文字の歌の形になった。(素戔鳴命は天照大神の兄である。ある女性と結婚しようとして出雲の国に宮殿を造った時その場所に雲が立ち昇ったのを見て歌を作られた)
八雲立つ 出雲八重垣妻ごめに 八重垣つくる その八重垣を
(ここで素戔鳴命を天照大神の兄と言っているのは、明らかに弟の間違いである。なお素戔鳴命を神ではなく人としているところがおもしろい)
や雲立つ出雲八重垣妻ごめに八重垣作るその八重垣を
かくてぞ花をめで
鳥をうらやみ
霞をあはれび
露をかなしぶ
心 言葉多く
様々になりにける
遠き所もいでたつ足もとより始まりて
年月をわたり
高き山も麓の塵ひぢよりなりて
天雲たなびくまで生ひのぼれるごとくに
この歌もかくのごとくなるべし
難波津の歌は帝の御初めなり
おほさざきの帝の 難波津にて皇子ときこえける時
東宮をたがひに譲りて 位につきたまはで 三年になりにければ
王仁といふ人のいぶかり思ひて よみてたてまつりける歌なり
この花は梅の花を言ふなるべし
安積山の言葉は采女のたはぶれよりよみて
葛城王を陸奥へつかはしたりけるに
国の司 事おろそかなりとて まうけなどしたりけれど
すさまじかりければ 采女なりける女の かはらけとりてよめるなり
これにぞおほきみの心とけにける
この二歌は歌の父母のやうにてぞ手習ふ人のはじめにもしける
(歌の様の解説)
そもそも歌の様六つなり
唐の歌にもかくぞあるべき
その六種の一つにはそへ歌
おほさざきの帝をそへたてまつれる歌 (仁徳天皇を梅の花になぞらえて王仁が詠んだ歌。)
難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花
(難波の都に美しく梅の花が咲いているなあ。寒い冬を凌いで、今は春だと咲いているのだなあ)
と言へるなるべし
二つにはかぞへ歌
咲く花に思ひつくみのあぢきなさ身にいたづきのいるも知らずて
と言へるなるべし
(咲き誇っている花のように美しいからと言って、あの人に身も心も奪われてしまうなんてよしたほうが良い。そんなことをしていると病気になってしまうかも知れないのに)
(注)○思いつくみ・・・つぐみを詠み込んでいる。
○いたづき・・・・病気、ただし、いたつきだと矢尻の一種で、つぐみに掛けてある。つまりつぐみが花に浮かれていると矢で射殺されてしまうよと言う意味も引っ掛けてある.
これはただ事に言いひて
物にたとへなどもせぬものなり
この歌いかに言へるにかあらむ
その心得がたし
五つにただこと歌と言へるなむ
これにはかなふべき
三つにはなずらへ歌
君に今朝あしたの霜のおきていなば恋しきごとに消えやわたらむ
と言へるなるべし
これは物にもなずらへて
それがやうになむあるとやうに言ふなり
この歌よくかなへりとも見えず
たらちめの親のかふこの繭ごもりいぶせくもあるかいもにあはずて
かやうなるやこれにはかなふべからむ
四つにはたとへ歌
わが恋はよむともつきじ荒磯海の浜の真砂はよみ尽くすとも
と言へるなるべし
(わたしの恋は数限りないので、浜の砂の粒の数は数えられても、わたしの恋の数は数えきれないでしょう)
「たとえ歌」と言うのはあらゆるものに例えて自分の心を述べる歌である。この歌はどこにもわからないところはないけれど、はじめの「そえ歌」と同じようだから、すこし趣好を変えたものであろう。
これはよろづの草木鳥けだものにつけて心を見するなり
この歌は隠れたる所なむなき
されどはじめのそへ歌と同じやうなれば
少し様をかへたるなるべし
須磨のあまの塩焼く煙風をいたみ思はぬ方にたなびきにけり
この歌などや、かなふべからむ
五つには ただこと歌
いつはりのなき世なりせばいかばかり人の言の葉うれしからまし
と言へるなるべし
これは事のととのほり正しきを言ふなり
この歌の心さらにかなはず
とめ歌とや言ふべからむ
山ざくらあくまで色を見つるかな花散るべくも風吹かぬ世に
六つには いはひ歌
この殿はむべも富みけりさき草の三つ葉四つ葉に殿造りせり
と言へるなるべし
これは世をほめて神に告ぐるなり
この歌 いはひ歌とは見えずなむある
春日野に若菜つみつつよろづ世を祝ふ心は神ぞ知るらむ
これらや少しかなふべからむ
おほよそ六種にわかれむ事は
えあるまじき事になむ
1,そえ歌・・・・物にことよせて思う心を詠んだ歌。
2,かぞえ歌・・・物に例えることをしないで、心を直接詠んだ歌。
3,なずらえ歌・・他の物に例えて詠んだ歌。
4,たとえ歌・・・他の物に例えて詠んだ歌。
5,ただごと歌・・物に例えることにより間接に言わないで、直接に詠んだ歌。
6,いわい歌・・・世の中の栄えをたたえて神に申し上げる歌。
と言うことになる。ここでは6,の祝い歌だけは性格がはっきりしているが、2,のかぞえ歌と5,のただごと歌はまったく同じであり、1,のそえ歌、3,のなずらえ歌、4,のたとえ歌もまったく同一で区別しようがない。とすれば、実は三体が本当で、六体と言うのはまったくナンセンスだと言うことになる。
今の世の中
色につき人の心花になりにけるより
あだなる歌 はかなき言のみいでくれば
色好みの家に 埋れ木の人知れぬこととなりて
まめなるところには
花すすき穂にいだすべきことにもあらずなりにたり
その初めを思へば かかるべくなむあらぬ
いにしへの世々の帝
春の花のあした 秋の月の夜ごとに
さぶらふ人々をめして
事につけつつ歌をたてまつらしめたまふ
あるは花をそふとてたよりなき所にまどひ
あるは月を思ふとてしるべなき闇にたどれる心々を見たまひて
さかしおろかなりと
知ろしめしけむ
しかあるのみにあらず
さざれ石にたとへ 筑波山にかけて君を願ひ
喜び身に過ぎ 楽しび心に余り
富士の煙によそへて人をこひ
松虫のねに友をしのび
高砂 住の江の松もあひ生ひのやうにおぼえ
男山の昔を思ひいでて 女郎花の一時をくねるにも
歌をいひてぞなぐさめける
また春のあしたに花の散るを見
秋の夕ぐれに木の葉の落つるを聞き
あるは年ごとに鏡の影に見ゆる雪と浪とを嘆き
草の露水の泡を見てわが身をおどろき
あるは昨日は栄えおごりて時を失ひ世にわび
親しかりしもうとくなり
あるは松山の浪をかけ 野なかの水をくみ 秋萩の下葉を眺め
暁のしぎの羽がきを数へ
あるはくれ竹のうき節を人に言ひ
吉野川をひきて世の中をうらみきつるに
今は富士の山も煙たたずなり 長柄の橋も造るなり
と聞く人は歌にのみぞ心をなぐさめける
いにしへよりかく伝はるうちにも奈良の御時よりぞ広まりにける
かの御代や歌の心を知ろしめしたりけむ
かの御時に 正三位柿本人麿なむ歌の聖なりける
これは君も人も身をあはせたりといふなるべし
秋の夕べ竜田川に流るるもみぢをば 帝の御目に錦と見たまひ
春のあした吉野の山のさくらは人麿が
心には雲かとのみなむおぼえける
また山の辺赤人といふ人ありけり
歌にあやしく妙なりけり
人麿は赤人が上に立たむことかたく
赤人は人麿が下に立たむことかたくなむありける
奈良の帝の御歌
竜田川もみぢみだれて流るめりわたらば錦なかやたえなむ
人麿
梅の花それとも見えず久方のあまぎる雪のなべて降れれば
ほのぼのと明石のうらの朝霧に島がくれ行く舟をしぞ思ふ
赤人
春の野にすみれつみにとこし我ぞ野をなつかしみひと夜寝にける
わかの浦に潮満ちくれば方をなみ葦辺をさしてたづ鳴きわたる
この人々をおきて またすぐれたる人も くれ竹の世々に聞こえ
片糸のよりよりに絶えずぞありける
これよりさきの歌を集めてなむ 万葉集と名づけられたりける
ここにいにしへのことをも歌の心をもしれる人わづかに一人二人なりき
しかあれど これかれ得たるところ得ぬところたがひになむある
かの御時よりこの方 年は百年あまり 世は十継になむなりにける
いにしへのことをも歌をも知れる人よむ人多からず
今このことを言ふに つかさ位高き人をば
たやすきやうなれば入れず
そのほかに 近き世に その名きこえたる人は
すなはち僧正遍照は 歌の様は得たれども まこと少し
たとへば絵にかける女を見て いたづらに心を動かすがごとし
浅緑糸よりかけて白露を玉にもぬける春の柳か
はちす葉のにごりにしまぬ心もてなにかは露を玉とあざむく
嵯峨野にて馬より落ちてよめる
名にめでて折れるばかりぞ女郎花我おちにきと人に語るな
在原業平は その心余りて言葉たらず
しぼめる花の色なくて にほひ残れるがごとし
月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身ひとつはもとの身にして
(月は同じではないのか、春は昔の春ではないのか、この自分だけが元のままで)
おほかたは月をもめでじこれぞこの積もれば人の老いとなるもの
(今の気持ちをおおまかに言えば、月をも愛でる気がしない、これはつまり、積もれば老いつながるものだからさ)
ねぬる夜の夢をはかなみまどろめばいやはかなにもなりまさるかな
(一緒に寝た昨日の夜の夢をはかなく思って、まどろむと、ますますはかない気持ちが増してしまった)
文屋康秀は 言葉はたくみにて そのさま身におはず
いはば商人のよき衣着たらむがごとし
吹くからに野辺の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ
深草の帝の御国忌に
草深き霞の谷にかげかくし照る日のくれしけふにやはあらぬ
宇治山の僧喜撰は 言葉かすかにして 初め終はり確かならず
いはば秋の月を見るに暁の雲にあへるがごとし
わが庵は都のたつみ鹿ぞ住む世をうぢ山と人は言ふなり
よめる歌多く聞こえねば かれこれを通はして よく知らず
小野小町は いにしへの衣通姫の流なり
あはれなるやうにて強からず
いはばよき女の悩めるところあるに似たり
強からぬは 女の歌なればなるべし
思ひつつぬればや人の見えつらむ夢と知りせばさめざらましを
色見えでうつろふものは世の中の人の心の花にぞありける
わびぬれば身をうき草の根をたえてさそふ水あらばいなむとぞ思ふ
衣通姫の歌
わがせこがくべきよひなりささがにのくものふるまひかねてしるしも
大友黒主は そのさまいやし
いはば薪負へる山びとの 花のかげに休めるがごとし
思ひいでて恋しき時は初かりの鳴きてわたると人は知らずや
鏡山いざたちよりて見てゆかむ年へぬる身は老いやしぬると
このほかの人々 その名聞こゆる
野辺に生ふるかづらの這ひ広ごり
林にしげき木の葉のごとくに多かれど
歌とのみ思ひてその様知らぬなるべし
かかるに今 天皇の天の下知ろしめすこと
四つの時、九のかへりになむなりぬる
あまねき御うつくしみの浪 八州のほかまで流れ
ひろき御めぐみのかげ 筑波山の麓よりもしげくおはしまして
よろづのまつりごとをきこしめすいとま
もろもろの事を捨てたまはぬあまりに いにしへのことをも忘れじ
古りにしことをも興したまふ とて
今もみそなはし、後の世にも伝はれ とて
延喜五年四月十八日に 大内記紀友則 御書の所の預り紀貫之
前の甲斐の少目凡河内躬恒(おほしこうちのみつね) 右衛門の府生壬生忠岑(みぶのただみね)らに仰せられて
万葉集に入らぬ古き歌 みづからのをもたてまつらしめたまひてなむ
それが中に梅をかざすよりはじめて ほととぎすを聞き
紅葉を折り 雪を見るにいたるまで
また 鶴亀につけて君を思ひ 人をも祝ひ
秋萩 夏草を見て妻をこひ あふさか山にいたりて 手向けを祈り
あるは春夏秋冬にも入らぬ種々の歌をなむ 選ばせたまひける
すべて千歌二十巻 名づけて 古今和歌集 と言ふ
かくこのたび集め選ばれて
山した水の絶えず 浜の真砂の数多く積もりぬれば
今は飛鳥川の瀬になる恨みも聞こえず
さざれ石の巌となる喜びのみぞあるべき
それまくらことは 春の花にほひ少なくして
むなしき名のみ秋の夜の長きをかこてれば
かつは人の耳におそり
かつは歌の心に恥ぢ思へど
たなびく雲のたちゐ 鳴く鹿の起きふしは
貫之らがこの世に同じく生まれて
このことの時にあへるをなむ喜びぬる
人麿なくなりにたれど 歌のこととどまれるかな
たとひ時移り 事去り 楽しび哀しびゆきかふとも
この歌の文字あるをや
青柳の糸絶えず 松の葉のちり失せずして
まさきのかづら長く伝はり
鳥のあと久しくとどまれらば 歌の様をも知り
ことの心を得たらむ人は
大空の月を見るがごとくにいにしへを仰ぎて
今をこひざらめかも
補足 須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)=「『素戔嗚尊』スサノオのミコトについて(日本神話について)
日本神話の始まりはギリシア神話に類似した『混沌(カオス)』から始まりますが、天上世界である高天原(たかまのはら)に最初に出現するのは、天之御中主神(アメノミナカヌシ)という天上の摂理を司る独神
(天上の至高神としての位置づけ)
アメノミナカヌシに続いて現れた神が、高御産巣日神(タカミムスビ)と神産巣日神(カミムスビ)という独神
「農作物を豊かに実らせ男女を結合させて生命を生み出す産霊(むすび)の神」
その3柱に宇摩志阿斯詞備比古遲神(ウマシアシカビヒコヂ)と天之常立神(アメノトコタチ)を加えて始原の『別天つ神五柱』
タカミムスビとカミムスビの後には、神世七代の神々が生み出されたとされますが、その最後に生まれたのが『国生み・国土形成の二神』として知られる伊邪那岐神(イザナギ)と伊邪那美神(イザナミ)の夫婦神です
イザナギとイザナミは二度目の性の交わりによって、淡路島・四国・九州・隠岐・壱岐・対馬・佐渡・本州という『大八洲・大八島(おおやしま)』を産むことに成功して、ここに日本列島が誕生する『国生み』が行われたことになります
火の神カグツチを産んだ際の火傷が元でイザナミ(女神)が死に、黄泉国にまでイザナミ(女神)を追いかけていったイザナギ(男神)が腐乱したイザナミを見て恐怖し離婚に至る。激怒したイザナミに追いかけられたイザナギは命からがら現世へと逃げ延びますが、土着的なケガレ思想に基づく『死の穢れ(死穢,しえ)』を払い清めるために、九州・日向国(宮崎県)小戸にある橘の阿波岐原(たちばなのあわきはら)という海岸で全身を洗って、禊・祓(みそぎ・はらえ)を行う
左目を洗うと女神の天照大神(アマテラスオオミカミ)が生まれ、右目を洗うと月読命(つきよみのみこと)、鼻を洗うと男神の建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)=「『素戔嗚尊』が生まれました。
イザナギはアマテラスオオミカミに高天原(たかまのはら)、ツキヨミに夜の食国(おすくに)、スサノオに海原を統治させました。
アマテラスはスサノオが高天原を侵略しに来たと勘違いして、弓矢で武装して男の姿に変わり厳しくスサノオを詰問しました。スサノオはウケヒ(神聖な占い)を天の河原で行って自分に悪意(侵略の意図)がないことを明らかにしますが、調子に乗って乱暴物の本性を現し始めたスサノオはアマテラスの治める高天原を散々に荒らしまわります。
スサノオの暴力的な性格・行動に恐怖を感じたアマテラスオオミカミは、『天石屋(あめのいわや)・天岩戸(あめのいわと)』という高天原の奥深い洞窟に身を隠して入り口を塞いでしまいました。これをアマテラスオオミカミの『岩戸隠れ』といいます。
アマテラスオオミカミ(天照大神)は日の神=太陽神なので『岩戸隠れ』によってその姿を隠してしまうと、世界に太陽の光が届かなくなり闇に閉ざされてしまい、様々な災厄や病気、苦悩が溢れ出して闇を好む悪神たちの勢力が強まってしまいます。天の安河に集まった『八百万の神々』は何とかしてアマテラスオオミカミを天岩戸から引っ張り出さなければならないと考えて一計を案じます。常世(とこよ)の思兼神が、賑やかな祭りを岩戸の周りで執り行えば、その楽しそうな喧騒に釣られてアマテラス様が姿を現すのではないだろうかと意見を出し、八百万の神々で協力して盛大なお祭りを開催することが決まりました。天児屋命(あめのこやねのみこと)は神聖な祝詞(のりと)を唱えて祭りに厳粛さを与え、太玉命(ふとだまのみこと)は巨大な榊の木を立ててそこに鏡・玉・幣(しで)をぶらさげて飾りつけをしました。女神の天宇受売命(あめのうずめのみこと)はセクシーで扇情的な踊りを踊って祭りを盛り上げます。それは受舟(うけふね)という桶の上で乳房・女性器をあらわにして神懸りになって踊るという大胆なものであり、その狂気的な盛り上がりを楽しんで神々が大声で笑い声を上げています。外の喧騒と笑い声を聞いて、『いったい何が起こっているのだろうか』と好奇心をそそられたアマテラスが、岩戸から少し身を乗り出して外を見ようとした時に、岩戸の横で待ち構えていた力自慢の天手力男(あめのたちからお)がアマテラスを引っ張り出して、世界に日の光と平和な秩序が戻ってきました
スサノオはこの騒動を引き起こした乱暴狼藉の責任を問われて、高天原から地上の世界へと追放されますが、スサノオが自身の無実を証明するためにウケヒを行った時に、アマテラスも物を用いたウケヒを行っており、その時に以下の5柱の神々が生み出されています
天忍穂耳命(あめのおしほのみみ) 天穂日命(あめのほひ) 天津彦根命(あまつひこね)
活津彦根命(いくつひこね) 熊野樟日命(くまのくすび)
アマテラスオオミカミは地上の葦原中国(あしわらのなかつくに)に食物の神・保食(うけもち)がいると聞いて、ツキヨミに視察に赴かせるのですが、保食が自分の口からご飯や魚、鳥獣を出してもてなそうとした為、ツキヨミが『そんな不潔不浄なものを食べさせる気か』と激怒して斬り殺してしまいます。ツキヨミの暴挙を聞いたアマテラスは不快になり怒って、『お前のような悪しき神の顔など見たくない』と絶縁を宣言したので、アマテラスは『昼の神』、ツキヨミは『夜の神』となり互いが顔を合わせることも無くなったといいます。
ツキヨミに殺された保食(ウケモチ)の様子を天熊人(アメノクマヒト)に見に行かせると、保食の死体からは『人々の食糧』となる様々なものが化成してきており、頭から牛馬が、額から粟が、眉から蚕が、眼から稗が、腹から稲が、女性器から麦・大豆・小豆が産出されていました。アマテラスオオミカミは保食(ウケモチ)の死体からそれら食糧の起源を取り出して、地上の人々がもう飢えに苦しまなくて良くなるように(継続的・計画的に食糧を確保できるようになるために)『農耕』を教えたのでした。
日本神話に書かれている大国主神(オオクニヌシ)・大己貴命(オオナムチ)が支配する出雲国は、地上の『葦原中国(あしわらのなかつくに=日本全体)』に相当する大きな国であり、大国主神はスサノオの息子とされています。
出雲国の肥河(ひのかわ)の上流にある鳥上(鳥髪山)に下ったスサノオは、乙女を囲んだ足名椎(あしなつち)と手名椎(てなつち)の老夫婦が泣いている場面に遭遇して事情を聞きます。この土地の村を荒らして人々を恐れさせている八岐大蛇(ヤマタノオロチ)という巨大な蛇の怪物がいて、毎年、若い娘を生け贄として要求してくるという事であり、最後に残ったのがこの櫛名田比売(奇稲田姫・くしなだひめ)という少女だといいます。ヤマタノオロチは頭が八つ、尾が八つという強力な化け物でしたが、スサノオは天津神としての出自を明らかにして、自分が櫛名田比売を妻としてヤマタノオロチを退治してやるという約束をします。
八頭八尾の恐ろしい怪物であるヤマタノオロチを退治するために、スサノオノミコトが立てた謀略的な作戦は、大量の酒を満たした8つの木の桶(酒槽・さかぶね)を準備して待ち構え、その酒を飲んでヤマタノオロチが酔いつぶれたところを襲うというものでした。スサノオは好きになった櫛名田比売を歯の多い『櫛』に変えて髪に挿していきましたが、酒をぐびぐびと飲んで酔いつぶれたヤマタノオロチを十拳剣・十束剣(とつかのつるぎ)で切り殺すことに成功しました。肥の川はヤマタノオロチの血で赤く染まり、切り裂いた尾からは『草薙剣(くさなぎのつるぎ)』という三種の神器となる霊剣が出てきて、スサノオはその草薙剣をアマテラスオオミカミに献上しました。スサノオはクシナダヒメと結婚して、出雲国須賀の里に拠点を定めましたが、その6世の孫に当たる人物が、葦原中国の支配者となる大国主命(オオクニヌシノミコト)・大己貴命(オオナムチ)なのです。
稲羽の白兎
、『稲羽の白兎(いなばのしろうさぎ)』と呼ばれるように白い毛を持ったウサギの姿になりました。すっかり良くなった因幡(稲羽)の白兎は、『兄の八十神はヤガミヒメを決して得ることができない。袋を背負って後から行ったとしても、オオナムチ様がヤガミヒメと結婚することになるでしょう』という予言の言葉を述べました。
果たしてその白兎の予言の通りに、オオナムチがヤガミヒメと結婚することになったのですが、それに激怒した兄の八十神たちは弟・オオナムチに復讐を企てて、イノシシと偽った焼けた大石を転がしてオオナムチを焼き殺してしまいました。オオナムチの母親(一説にはクシナダヒメ)の願いで、カミムスビが蘇生の特殊能力を持つ赤貝・蛤(はまぐり)の女神を遣わして、オオナムチを生き返らせますが、八十神の兄は再び大木の割れ目の中にオオナムチを押し込んで圧殺します。母のクシナダヒメはもう一度オオナムチを生き返らせて、紀伊のイタケルの元に逃げさせますが、八十神の兄の追撃が激しいので、夫のスサノオが住んでいる『根の国(黄泉の国)』へと逃がしました。
オオナムチ(大国主命)は根の国へと行ったのですが、スサノオはオオナムチを助けてはくれず、逆に『蛇の室(むろや)・ムカデの室・蜂の室』など恐ろしい爬虫類や毒虫のいる部屋にオオナムチを閉じ込めました。オオナムチは婚約者であるスサノオの娘のスセリビメ(須勢理毘売)から不思議な防御力を持つ『比礼(布)』を貰っていたので、何とか危険な部屋から自分を守ることができました。
オオナムチはスサノオの髪を垂木(たるき)に結びつけて、妻のスセリビメを連れて『生大刀(いくたち)・生弓矢(いくゆみや)・天の詔琴(あめののりごと)』といった宝物を持って逃げ出しました。生大刀・生弓矢というのは蘇生の特殊能力を持つ神々の武具であり、天の詔琴というのは詔勅(権威ある命令)を出すときに奏でる神器でした。スサノオは結び付けられた髪をほどして追いかけてきましたが、根の国との国境に来た時に二人の結婚を遂に認めます。
宝物の武具を持って葦原中国(日本国)に帰った大国主命(オオナムチ)は、兄の八十神を打ち倒してこの国の統治者(主人)となり、ウツシクニダマノカミとなって宇迦(うか)の山麓に拠点を構え、国づくりの作業を始めました。大国主命が出雲の美保岬にいた時、海の沖合いから天の羅摩船(あめのかがみのふね)に乗って、鵝(蛾)の皮を来た小さな神がやってきた。小さな神は神産巣日神(カミムスビ)の子の少名毘古那神(スクナビコナ)である』と答えました。その後にスクナビコナは粟の茎に弾き飛ばされてしまい、常世国へと去っていってしまった。一人でどのようにして国づくりを完成させれば良いのかと大国主命が孤独に悩んでいると、再び海原を照らしながら近づいてくる神があり、幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)というその神が『私を丁重に大和の地に祀れば、国づくりが順調に進む』というので、大和の御諸山(三輪山)に祀りました。この三輪山に祭祀された幸魂奇魂という不思議な神が、大物主神(おおものぬしのかみ)となりました。
以下省略 いずれにしても神話とは意外性があり、ユダヤ、仏教など地球創世記の神話として似ているようです。ビッグバンに始まり、宇宙の創生、地球誕生、生物、人間の誕生から現代に至る過程において神話の世界のいろいろな神が出雲大社、氏神様としての「天照大神」として神として現代にも残っていることはおもしろい。
(追) 古事記のうんちく
天武天皇が古事記の原型となる国の成り立や天皇の系譜を暗記させたのが稗田阿礼(ひえだのあれい)。編纂作業は686年の天武天皇の死で中断したが、711年に天武天皇の甥・元明天皇の指示で、阿礼が読み上げたものを太安万侶(おおのやすまろ)が書き写し、翌年完成。阿礼について「一度目や耳にしたことは忘れなかった」驚異的な記憶力の持ち主で彼が居なかったら古事記は完成されなかったらしい。
初春から梅、桜と載せている
| 0003 | 春霞 立てるやいづこ み吉野の 吉野の山に 雪は降りつつ | 読人知らず |
| 0004 | 雪の内に 春はきにけり うぐひすの こほれる涙 今やとくらむ | 二条后 |
| 0006 | 春たてば 花とや見らむ 白雪の かかれる枝に うぐひすの鳴く | 素性法師 |
| 0008 | 春の日の 光に当たる 我なれど かしらの雪と なるぞわびしき | 文屋康秀 |
| 0012 | 谷風に とくる氷の ひまごとに うち出づる浪や 春の初花 | 源当純 |
| 0017 | 春日野は 今日はな焼きそ 若草の つまもこもれり 我もこもれり | 読人知らず |
| 0021 | 君がため 春の野にいでて 若菜つむ 我が衣手に 雪は降りつつ | 仁和帝 |
| 0027 | 浅緑 糸よりかけて 白露を 珠にもぬける 春の柳か | 僧正遍照 |
| 0034 | 宿近く 梅の花植ゑじ あぢきなく 待つ人の香に あやまたれけり | 読人知らず |
| 0038 | 君ならで 誰にか見せむ 梅の花 色をも香かをも 知る人ぞ知る | 紀友則 |
| 0042 | 人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香に匂ひける | 紀貫之 |
| 0051 | 山桜 我が見にくれば 春霞 峰にもをにも 立ち隠しつつ | 読人知らず |
| 0053 | 世の中に 絶えて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし | 在原業平 |
| 0056 | 見渡せば 柳桜を こきまぜて みやこぞ春の 錦なりける | 素性法師 |
| 0060 | み吉野の 山辺にさける 桜花 雪かとのみぞ あやまたれける | 紀友則 |
| 0065 | 折りとらば 惜しげにもあるか 桜花 いざ宿かりて 散るまでは見む | 読人知らず |
| 0068 | 見る人も なき山里の 桜花 ほかの散りなむ のちぞ咲かまし | 伊勢 |
| 0070 | 待てと言ふに 散らでしとまる ものならば 何を桜に 思ひまさまし | 読人知らず |
| 0073 | 空蝉の 世にも似たるか 花桜 咲くと見しまに かつ散りにけり | 読人知らず |
| 0076 | 花散らす 風の宿りは 誰か知る 我に教へよ 行きてうらみむ | 素性法師 |
| 0081 | 枝よりも あだに散りにし 花なれば 落ちても水の 泡とこそなれ | 菅野高世 |
| 0084 | 久方の 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ | 紀友則 |
| 0085 | 春風は 花のあたりを よぎて吹け 心づからや うつろふと見む | 藤原好風 |
| 0086 | 雪とのみ 降るだにあるを 桜花 いかに散れとか 風の吹くらむ | 凡河内躬恒 |
| 0088 | 春雨の 降るは涙か 桜花 散るを惜しまぬ 人しなければ | 大友黒主 |
| 0090 | ふるさとと なりにし奈良の みやこにも 色はかはらず 花は咲きけり | 奈良帝 |
| 0092 | 花の木も 今はほり植ゑじ 春たてば うつろふ色に 人ならひけり | 素性法師 |
| 0097 | 春ごとに 花のさかりは ありなめど あひ見むことは 命なりけり | 読人知らず |
| 0098 | 花のごと 世のつねならば すぐしてし 昔はまたも かへりきなまし | 読人知らず |
| 0102 | 春霞 色のちぐさに 見えつるは たなびく山の 花のかげかも | 藤原興風 ふじはらのおきかぜ |
| 0108 | 花の散る ことやわびしき 春霞 たつたの山の うぐひすの声 | 藤原後蔭 |
| 0110 | しるしなき 音をも鳴くかな うぐひすの 今年のみ散る 花ならなくに | 凡河内躬恒 おほしこうちのみつね |
| 0113 | 花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに | 小野小町 |
| 0118 | 吹く風と 谷の水とし なかりせば み山隠れの 花を見ましや | 紀貫之 |
| 0120 | 我が宿に 咲ける藤波 立ち返り すぎがてにのみ 人の見るらむ | 凡河内躬恒 |
| 0123 | 山吹は あやなな咲きそ 花見むと 植ゑけむ君が 今宵来なくに | 読人知らず |
| 0127 | 梓弓 春たちしより 年月の いるがごとくも 思ほゆるかな | 凡河内躬恒 |
| 0139 | 五月待つ 花橘の 香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする | 読人知らず |
| 0141 | 今朝き鳴き いまだ旅なる 郭公 花橘に 宿はからなむ | 読人知らず |
| 0142 | 音羽山 今朝越えくれば 郭公 梢はるかに 今ぞ鳴くなる | 紀友則 |
| 0145 | 夏山に 鳴く郭公 心あらば 物思ふ我に 声な聞かせそ | 読人知らず |
| 0148 | 思ひいづる ときはの山の 郭公 唐紅の ふりいでてぞ鳴く | 読人知らず |
| 0152 | やよやまて 山郭公 ことづてむ 我れ世の中に 住みわびぬとよ | 三国町 |
| 0153 | 五月雨に 物思ひをれば 郭公 夜深く鳴きて いづち行くらむ | 紀友則 |
| 0156 | 夏の夜の ふすかとすれば 郭公 鳴くひと声に 明くるしののめ | 紀貫之 |
| 0157 | くるるかと 見れば明けぬる 夏の夜を あかずとや鳴く 山郭公 | 壬生忠岑 |
| 0160 | 五月雨の 空もとどろに 郭公 何を憂しとか 夜ただ鳴くらむ | 紀貫之 |
| 0164 | 郭公 我とはなしに 卯の花の うき世の中に 鳴き渡るらむ | 凡河内躬恒 |
| 0165 | はちす葉の にごりにしまぬ 心もて 何かは露を 珠とあざむく | 僧正遍照 |
| 0166 | 夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいづこに 月宿るらむ | 清原深養父 きよはらのふかやぶ |
| 0168 | 夏と秋と 行きかふ空の かよひぢは かたへ涼しき 風や吹くらむ | 凡河内躬恒 |
天の川(七夕)を詠んだ歌が多いい。他に萩、女郎花(おみなえし)、虫の声などで占められている。
| 0169 | 秋きぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる | 藤原敏行 |
| 0170 | 川風の 涼しくもあるか うちよする 浪とともにや 秋は立つらむ | 紀貫之 |
| 0184 | 木の間より もりくる月の 影見れば 心づくしの 秋はきにけり | 読人知らず |
| 0186 | 我がために くる秋にしも あらなくに 虫の音聞けば まづぞかなしき | 読人知らず |
| 0191 | 白雲に 羽うちかはし 飛ぶ雁の 数さへ見ゆる 秋の夜の月 | 読人知らず |
| 0200 | 君しのぶ 草にやつるる ふるさとは 松虫の音ぞ かなしかりける | 読人知らず |
| 0202 | 秋の野に 人まつ虫の 声すなり 我かとゆきて いざとぶらはむ | 読人知らず |
| 0213 | 憂きことを 思ひつらねて 雁がねの 鳴きこそわたれ 秋の夜な夜な | 凡河内躬恒 |
| 0215 | 奥山に もみぢ踏みわけ 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋はかなしき | 読人知らず |
| 0218 | 秋萩の 花咲きにけり 高砂の 尾上の鹿は 今や鳴くらむ | 藤原敏行 |
| 0241 | 主知らぬ 香こそ匂へれ 秋の野に たが脱ぎかけし 藤ばかまぞも | 素性法師 |
| 0244 | 我のみや あはれと思はむ きりぎりす 鳴く夕影の 大和撫子 | 素性法師 |
| 0248 | 里は荒れて 人はふりにし 宿なれや 庭もまがきも 秋の野らなる | 僧正遍照 |
紅葉に関連した歌が多い。
| 0253 | 神無月 時雨もいまだ 降らなくに かねてうつろふ 神なびのもり | 読人知らず |
| 0267 | 佐保山の ははその色は 薄けれど 秋は深くも なりにけるかな | 坂上是則 |
| 0268 | 植ゑし植ゑば 秋なき時や 咲かざらむ 花こそ散らめ 根さへ枯れめや | 在原業平 |
| 0269 | 久方の 雲の上にて 見る菊は 天つ星とぞ あやまたれける | 在原業平 |
| 0278 | 色かはる 秋の菊をば ひととせに ふたたび匂ふ 花とこそ見れ | 読人知らず |
| 0281 | 佐保山の ははそのもみぢ 散りぬべみ 夜さへ見よと 照らす月影 | 読人知らず |
| 0286 | 秋風に あへず散りぬる もみぢ葉の ゆくへさだめぬ 我ぞかなしき | 読人知らず |
| 0290 | 吹く風の 色のちぐさに 見えつるは 秋の木の葉の 散ればなりけり | 読人知らず |
| 0294 | ちはやぶる 神世もきかず 竜田川 唐紅に 水くくるとは | 在原業平 |
| 0302 | もみぢ葉の 流れざりせば 竜田川 水の秋をば 誰か知らまし | 坂上是則 |
| 0303 | 山川に 風のかけたる しがらみは 流れもあへぬ 紅葉なりけり | 春道列樹 |
| 0310 | み山より 落ちくる水の 色見てぞ 秋はかぎりと 思ひ知りぬる | 藤原興風 |
| 0312 | 夕月夜 小倉の山に 鳴く鹿の 声の内にや 秋は暮るらむ | 紀貫之 |
雪、年の暮れ、雪を花に見立てた歌など
| 0317 | 夕されば 衣手寒し み吉野の 吉野の山に み雪降るらし | 読人知らず |
| 0324 | 白雪の ところもわかず 降りしけば 巌にも咲く 花とこそ見れ | 紀秋岑 |
| 0325 | み吉野の 山の白雪 つもるらし ふるさと寒く なりまさるなり | 坂上是則 |
| 0330 | 冬ながら 空より花の 散りくるは 雲のあなたは 春にやあるらむ | 清原深養父 |
| 0332 | 朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪 | 坂上是則 |
| 0333 | 消ぬがうへに またも降りしけ 春霞 立ちなばみ雪 まれにこそ見め | 読人知らず |
| 0339 | あらたまの 年の終りに なるごとに 雪も我が身も ふりまさりつつ | 在原元方 |
| 0341 | 昨日と言ひ 今日とくらして 明日香河 流れて早き 月日なりけり | 春道列樹 |
| 0312 | 夕月夜 小倉の山に 鳴く鹿の 声の内にや 秋は暮るらむ | 紀貫之 |
| 0343 | 我が君は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで | 読人知らず |
| 0345 | しほの山 さしでの磯に 住む千鳥 君が御代をば 八千代とぞ鳴く | 読人知らず |
| 0352 | 春くれば 宿にまづ咲く 梅の花 君が千歳の かざしとぞ見る | 紀貫之 |
| 0354 | ふして思ひ おきて数ふる 万代は 神ぞ知るらむ 我が君のため | 素性法師 |
| 0360 | 住の江の 松を秋風 吹くからに 声うちそふる 沖つ白浪 | 凡河内躬恒 |
| 0364 | 峰高き 春日の山に いづる日は 曇る時なく 照らすべらなり | 藤原因香 ふじはらのよるか |
| 0365 | 立ち別れ いなばの山の 峰におふる 松とし聞かば 今かへりこむ | 在原行平 |
| 0371 | 惜しむから 恋しきものを 白雲の たちなむのちは なに心地せむ | 紀貫之 |
| 0372 | 別れては ほどをへだつと 思へばや かつ見ながらに かねて恋しき | 在原滋春 |
| 0375 | 唐衣 たつ日は聞かじ 朝露の 置きてしゆけば けぬべきものを | 読人知らず |
| 0379 | 白雲の こなたかなたに 立ち別れ 心をぬさと くだく旅かな | 良岑秀崇 よしみねのひでをか |
| 0383 | よそにのみ 恋ひや渡らむ 白山の 雪見るべくも あらぬ我が身は | 凡河内躬恒 |
| 0387 | 命だに 心にかなふ ものならば なにか別れの かなしからまし | 白女(しろめ) |
| 0389 | したはれて きにし心の 身にしあれば 帰るさまには 道も知られず | 藤原兼茂 |
| 0391 | 君がゆく 越の白山 知らねども 雪のまにまに あとはたづねむ | 藤原兼輔 |
| 0393 | 別れをば 山の桜に まかせてむ とめむとめじは 花のまにまに | 幽仙法師 |
| 0399 | 別るれど うれしくもあるか 今宵より あひ見ぬ先に 何を恋ひまし | 凡河内躬恒 |
| 0402 | かきくらし ことはふらなむ 春雨に 濡衣きせて 君をとどめむ | 読人知らず |
| 0406 | 天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に いでし月かも | 安倍仲麻呂 |
| 0407 | わたの原 八十島かけて こぎいでぬと 人には告げよ 海人の釣り舟 | 小野篁 をののたかむら |
| 0409 | ほのぼのと 明石の浦の 朝霧に 島隠れ行く 舟をしぞ思ふ | 読人知らず |
| 0410 | 唐衣 きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ | 在原業平 |
| 0411 | 名にしおはば いざ言問はむ みやこ鳥 我が思ふ人は ありやなしやと | 在原業平 |
| 0413 | 山かくす 春の霞ぞ うらめしき いづれみやこの さかひなるらむ | 乙 |
| 0417 | 夕月夜 おぼつかなきを 玉くしげ ふたみのうらは あけてこそ見め | 藤原兼輔 |
| 0420 | このたびは ぬさもとりあへず たむけ山 紅葉の錦 神のまにまに | 菅原朝臣 |
| 0422 | 心から 花のしづくに そほちつつ うくひすとのみ 鳥の鳴くらむ | 藤原敏行 |
| 0424 | 浪の打つ 瀬見れば玉ぞ 乱れける 拾はば袖に はかなからむや | 在原滋春 |
| 0426 | あなうめに つねなるべくも 見えぬかな 恋しかるべき 香は匂ひつつ | 読人知らず |
| 0428 | 今いくか 春しなければ うぐひすも ものはながめて 思ふべらなり | 紀貫之 |
| 0437 | 白露を 玉にぬくとや ささがにの 花にも葉にも いとをみなへし | 紀友則 |
| 0439 | をぐら山 峰たちならし 鳴く鹿の へにけむ秋を 知る人ぞなき | 紀貫之 |
| 0443 | ありと見て たのむぞかたき 空蝉の 世をばなしとや 思ひなしてむ | 読人知らず |
| 0446 | 山高み つねに嵐の 吹く里は 匂ひもあへず 花ぞ散りける | 紀利貞 |
| 0455 | あぢきなし なげきなつめそ うきことに あひくる身をば 捨てぬものから | 兵衛 |
| 0458 | かの方に いつから先に わたりけむ 浪ぢはあとも 残らざりけり | 阿保経覧 あぼのつねみ |
| 0459 | 浪の花 沖から咲きて 散りくめり 水の春とは 風やなるらむ | 伊勢 |
| 0461 | あしひきの 山辺にをれば 白雲の いかにせよとか 晴るる時なき | 紀貫之 |
| 0467 | のちまきの おくれておふる 苗なれど あだにはならぬ たのみとぞ聞く | 大江千里 おほえのちさと |
殆んどが「読み人知らず」
| 0469 | 郭公 鳴くや五月の あやめ草 あやめも知らぬ 恋もするかな | 読人知らず |
| 0471 | 吉野川 岩波高く 行く水の 早くぞ人を 思ひそめてし | 紀貫之 |
| 0475 | 世の中は かくこそありけれ 吹く風の 目に見ぬ人も 恋しかりけり | 紀貫之 |
| 0481 | 初雁の はつかに声を 聞きしより 中空にのみ 物を思ふかな | 凡河内躬恒 |
| 0486 | つれもなき 人をやねたく 白露の 置くとはなげき 寝とはしのばむ | 読人知らず |
| 0489 | 駿河なる 田子の浦浪 立たぬ日は あれども君を 恋ひぬ日ぞなき | 読人知らず |
| 0495 | 思ひいづる ときはの山の 岩つつじ 言はねばこそあれ 恋しきものを | 読人知らず |
| 0503 | 思ふには 忍ぶることぞ 負けにける 色にはいでじと 思ひしものを | 読人知らず |
| 0513 | 朝な朝な 立つ河霧の 空にのみ うきて思ひの ある世なりけり | 読人知らず |
| 0522 | 行く水に 数かくよりも はかなきは 思はぬ人を 思ふなりけり | 読人知らず |
| 0525 | 夢の内に あひ見むことを たのみつつ くらせる宵は 寝む方もなし | 読人知らず |
| 0528 | 恋すれば 我が身は影と なりにけり さりとて人に そはぬものゆゑ | 読人知らず |
| 0534 | 人知れぬ 思ひをつねに するがなる 富士の山こそ 我が身なりけれ | 読人知らず |
| 0535 | とぶ鳥の 声も聞こえぬ 奥山の 深き心を 人は知らなむ | 読人知らず |
| 0546 | いつとても 恋しからずは あらねども 秋の夕べは あやしかりけり | 読人知らず |
| 0553 | 思ひつつ 寝ればや人の 見えつらむ 夢と知りせば 覚めざらましを | 小野小町 |
| 0544 | いとせめて 恋しき時は むばたまの 夜の衣を 返してぞきる | 小野小町 |
| 0559 | 住の江の 岸による浪 よるさへや 夢のかよひぢ 人目よぐらむ | 藤原敏行 |
| 0565 | 川の瀬に なびく玉藻の み隠れて 人に知られぬ 恋もするかな | 紀友則 |
| 0571 | 恋しきに わびてたましひ 惑ひなば むなしき殻の 名にや残らむ | 読人知らず |
| 0577 | ねになきて ひちにしかども 春雨に 濡れにし袖と とはば答へむ | 大江千里 |
| 0583 | 秋の野に 乱れて咲ける 花の色の ちぐさに物を 思ふころかな | 紀貫之 |
| 0585 | 人を思ふ 心は雁に あらねども 雲ゐにのみも なき渡るかな | 清原深養父 |
| 0586 | 秋風に かきなす琴の 声にさへ はかなく人の 恋しかるらむ | 壬生忠岑 |
| 0590 | 我が恋に くらぶの山の 桜花 間なく散るとも 数はまさらじ | 坂上是則 |
| 0592 | たぎつ瀬に 根ざしとどめぬ 浮草の 浮きたる恋も 我はするかな | 壬生忠岑 |
| 0594 | 東ぢの 小夜の中山 なかなかに なにしか人を 思ひそめけむ | 紀友則 |
| 0597 | 我が恋は 知らぬ山ぢに あらなくに 惑ふ心ぞ わびしかりける | 紀貫之 |
| 0601 | 風吹けば 峰にわかるる 白雲の 絶えてつれなき 君が心か | 壬生忠岑 |
| 0605 | 手もふれで 月日へにける 白真弓 おきふし夜は いこそ寝られね | 紀貫之 |
| 0611 | 我が恋は ゆくへも知らず はてもなし あふをかぎりと 思ふばかりぞ | 凡河内躬恒 |
| 0614 | たのめつつ あはで年ふる いつはりに こりぬ心を 人は知らなむ | 凡河内躬恒 |
| 0620 | いたづらに 行きてはきぬる ものゆゑに 見まくほしさに いざなはれつつ | 読人知らず |
| 0621 | あはぬ夜の 降る白雪と つもりなば 我さへともに けぬべきものを | 読人知らず |
| 0625 | 有明の つれなく見えし 別れより 暁ばかり 憂きものはなし | 壬生忠岑 |
| 0627 | かねてより 風に先立つ 浪なれや あふことなきに まだき立つらむ | 読人知らず |
| 0628 | 陸奥に ありと言ふなる 名取川 なき名とりては くるしかりけり | 壬生忠岑 |
| 0633 | しのぶれど 恋しき時は あしひきの 山より月の いでてこそくれ | 紀貫之 |
| 0634 | 恋ひ恋ひて まれに今宵ぞ あふ坂の ゆふつけ鳥は 鳴かずもあらなむ | 読人知らず |
| 0640 | しののめの 別れを惜しみ 我ぞまづ 鳥より先に なきはじめつる | 寵(うつく) |
| 0641 | 郭公 夢かうつつか 朝露の おきて別れし 暁の声 | 読人知らず |
| 0645 | 君やこし 我や行きけむ 思ほえず 夢かうつつか 寝てかさめてか | 読人知らず |
| 0647 | むばたまの 闇のうつつは さだかなる 夢にいくらも まさらざりけり | 読人知らず |
| 0656 | うつつには さもこそあらめ 夢にさへ 人目をもると 見るがわびしさ | 小野小町 |
| 0658 | 夢ぢには 足も休めず かよへども うつつにひと目 見しごとはあらず | 小野小町 |
| 0633 | 笹の葉に 置く初霜の 夜を寒み しみはつくとも 色にいでめや | 凡河内躬恒 |
| 0666 | 白川の 知らずともいはじ 底清み 流れて世よに すまむと思へば | 平貞文 たひらのさだふん |
| 0670 | 枕より また知る人も なき恋を 涙せきあへず もらしつるかな | 平貞文 |
| 0673 | あふことは 玉の緒ばかり 名の立つは 吉野の川の たぎつ瀬のごと | 読人知らず |
| 0675 | 君により 我が名は花に 春霞 野にも山にも 立ち満ちにけり | 読人知らず |
| 0676 | 知ると言へば 枕だにせで 寝しものを 塵ならぬ名の 空に立つらむ | 伊勢 |
| 0679 | いそのかみ ふるのなか道 なかなかに 見ずは恋しと 思はましやは | 紀貫之 |
| 0689 | 君と言へば 見まれ見ずまれ 富士の嶺の めづらしげなく もゆる我が恋 | 藤原忠行 |
| 0684 | 春霞 たなびく山の 桜花 見れどもあかぬ 君にもあるかな | 紀友則 |
| 0690 | 君やこむ 我やゆかむの いさよひに 真木の板戸も ささず寝にけり | 読人知らず |
| 0695 | あな恋し 今も見てしか 山がつの かきほにさける 大和撫子 | 読人知らず |
| 0708 | 須磨の海人の 塩やく煙 風をいたみ 思はぬ方に たなびきにけり | 読人知らず |
| 0709 | 玉かづら はふ木あまたに なりぬれば 絶えぬ心の うれしげもなし | 読人知らず |
| 0712 | いつはりの なき世なりせば いかばかり 人の言の葉 うれしからまし | 読人知らず |
| 0714 | 秋風に 山の木の葉の うつろへば 人の心も いかがとぞ思ふ | 素性法師 |
| 0719 | 忘れなむ 我をうらむな 郭公 人の秋には あはむともせず | 読人知らず |
| 0721 | 淀川の よどむと人は 見るらめど 流れて深き 心あるものを | 読人知らず |
| 0728 | 曇り日の 影としなれる 我なれば 目にこそ見えね 身をば離れず | 下野雄宗 |
| 0729 | 色もなき 心を人に 染めしより うつろはむとは 思ほえなくに | 紀貫之 |
| 0731 | かげろふの それかあらぬか 春雨の 降る日となれば 袖ぞ濡れぬる | 読人知らず |
| 0733 | わたつみと 荒れにし床を 今さらに はらはば袖や 泡と浮きなむ | 伊勢 |
| 0735 | 思ひいでて 恋しき時は 初雁の なきて渡ると 人知るらめや | 大友黒主 |
| 0743 | 大空は 恋しき人の 形見かは 物思ふごとに ながめらるらむ | 酒井人真 |
| 0746 | 形見こそ 今はあたなれ これなくは 忘るる時も あらましものを | 読人知らず |
恋の終わり、別れの歌
| 0747 | 月やあらぬ 春や昔の 春ならぬ 我が身ひとつは もとの身にして | 在原業平 |
| 0750 | 我がごとく 我を思はむ 人もがな さてもや憂きと 世をこころみむ | 凡河内躬恒 |
| 0753 | 雲もなく なぎたる朝の 我なれや いとはれてのみ 世をばへぬらむ | 紀友則 |
| 0755 | うきめのみ おひて流るる 浦なれば かりにのみこそ 海人は寄るらめ | 読人知らず |
| 0760 | あひ見ねば 恋こそまされ みなせ川 何に深めて 思ひそめけむ | 読人知らず |
| 0762 | 玉かづら 今は絶ゆとや 吹く風の 音にも人の 聞こえざるらむ | 読人知らず |
| 0763 | 我が袖に まだき時雨の 降りぬるは 君が心に 秋や来ぬらむ | 読人知らず |
| 0766 | 恋ふれども あふ夜のなきは 忘れ草 夢ぢにさへや おひしげるらむ | 読人知らず |
| 0770 | 我が宿は 道もなきまで 荒れにけり つれなき人を 待つとせしまに | 僧正遍照 |
| 0771 | 今こむと 言ひて別れし あしたより 思ひくらしの 音をのみぞ鳴く | 僧正遍照 |
| 0776 | 植ゑていにし 秋田刈るまで 見え来ねば 今朝初雁の 音にぞなきぬる | 読人知らず |
| 0779 | 住の江の 松ほどひさに なりぬれば あしたづの音に なかぬ日はなし | 兼覧王 |
| 0781 | 吹きまよふ 野風を寒み 秋萩の うつりもゆくか 人の心の | 雲林院親王 |
| 0795 | 世の中の 人の心は 花染めの うつろひやすき 色にぞありける | 読人知らず |
| 0797 | 色見えで うつろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける | 小野小町 |
| 0799 | 思ふとも かれなむ人を いかがせむ あかず散りぬる 花とこそ見め | 素性法師 |
| 0805 | あはれとも 憂しとも物を 思ふ時 などか涙の いとなかるらむ | 読人知らず |
| 0806 | 身を憂しと 思ふに消えぬ ものなれば かくてもへぬる 世にこそありけれ | 読人知らず |
| 0809 | つれなきを 今は恋ひじと 思へども 心弱くも 落つる涙か | 菅野忠臣 |
| 0814 | うらみても 泣きても言はむ 方ぞなき 鏡に見ゆる 影ならずして | 藤原興風 |
| 0819 | 葦辺より 雲ゐをさして 行く雁の いや遠ざかる 我が身かなしも | 読人知らず |
| 0821 | 秋風の 吹きと吹きぬる 武蔵野は なべて草葉の 色かはりけり | 読人知らず |
| 0823 | 秋風の 吹き裏返す くずの葉の うらみてもなほ うらめしきかな | 平貞文 |
| 0817 | 浮きながら けぬる泡とも なりななむ 流れてとだに たのまれぬ身は | 紀友則 |
| 0829 | 泣く涙 雨と降らなむ わたり川 水まさりなば かへりくるがに | 小野篁 をののたかむら |
| 0831 | 空蝉は 殻を見つつも なぐさめつ 深草の山 煙だにたて | 僧都勝延 |
| 0833 | 寝ても見ゆ 寝でも見えけり おほかたは 空蝉の世ぞ 夢にはありける | 紀友則 |
| 0835 | 寝るが内に 見るをのみやは 夢と言はむ はかなき世をも うつつとは見ず | 壬生忠岑 |
| 0838 | 明日知らぬ 我が身と思へど 暮れぬ間の 今日は人こそ かなしかりけれ | 紀貫之 |
| 0846 | 草深き 霞の谷に かげ隠し 照る日の暮れし 今日にやはあらぬ | 文屋康秀 |
| 0848 | うちつけに さびしくもあるか もみぢ葉も 主なき宿は 色なかりけり | 近院右大臣 |
| 0850 | 花よりも 人こそあだに なりにけれ いづれを先に 恋ひむとか見し | 紀茂行 |
| 0856 | 誰見よと 花咲けるらむ 白雲の たつ野とはやく なりにしものを | 読人知らず |
| 0858 | 声をだに 聞かで別るる たまよりも なき床に寝む 君ぞかなしき | 読人知らず |
| 0859 | もみぢ葉を 風にまかせて 見るよりも はかなきものは 命なりけり | 大江千里 |
| 0861 | つひにゆく 道とはかねて 聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを | 在原業平 |
| 0862 | かりそめの 行きかひぢとぞ 思ひこし 今はかぎりの 門出なりけり | 在原滋春 |
| 0863 | 我が上に 露ぞ置くなる 天の河 と渡る舟の 櫂のしづくか | 読人知らず |
| 0872 | 天つ風 雲のかよひぢ 吹きとぢよ 乙女の姿 しばしとどめむ | 僧正遍照 |
| 0875 | かたちこそ み山隠れの 朽ち木なれ 心は花に なさばなりなむ | 兼芸法師 |
| 0877 | 遅くいづる 月にもあるかな あしひきの 山のあなたも 惜しむべらなり | 読人知らず |
| 0878 | 我が心 なぐさめかねつ 更級や をばすて山に 照る月を見て | 読人知らず |
| 0882 | 天の河 雲のみをにて はやければ 光とどめず 月ぞ流るる | 読人知らず |
| 0886 | いそのかみ ふるから小野の もとかしは もとの心は 忘られなくに | 読人知らず |
| 0887 | いにしへの 野中の清水 ぬるけれど もとの心を 知る人ぞくむ | 読人知らず |
| 0888 | いにしへの しづのをだまき いやしきも よきもさかりは ありしものなり | 読人知らず |
| 0895 | 老いらくの 来むと知りせば 門さして なしと答へて あはざらましを | 読人知らず |
| 0899 | 鏡山 いざ立ち寄りて 見てゆかむ 年へぬる身は 老いやしぬると | 読人知らず |
| 0900 | 老いぬれば さらぬ別れも ありと言へば いよいよ見まく ほしき君かな | 業平朝臣母 |
| 0901 | 世の中に さらぬ別れの なくもがな 千代もとなげく 人の子のため | 在原業平 |
| 0905 | 我見ても 久しくなりぬ 住の江の 岸の姫松 幾世へぬらむ | 読人知らず |
| 0909 | 誰をかも 知る人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに | 藤原興風 |
| 0910 | わたつみの 沖つ潮あひに 浮かぶ泡の 消えぬものから 寄る方もなし | 読人知らず |
| 0917 | 住吉と 海人は告ぐとも 長居すな 人忘れ草 おふと言ふなり | 壬生忠岑 |
| 0919 | あしたづの 立てる川辺を 吹く風に 寄せてかへらぬ 浪かとぞ見る | 紀貫之 |
| 0925 | 清滝の 瀬ぜの白糸 くりためて 山わけごろも 織りて着ましを | 神退法師 |
| 0928 | 落ちたぎつ 滝の水上 年つもり 老いにけらしな 黒き筋なし | 壬生忠岑 |
| 0930 | 思ひせく 心の内の 滝なれや 落つとは見れど 音の聞こえぬ | 三条町 さんでうのまち |
| 0932 | かりてほす 山田の稲の こきたれて なきこそわたれ 秋の憂ければ | 坂上是則 |
| 0933 | 世の中は 何か常なる 飛鳥川 昨日の淵ぞ 今日は瀬になる | 読人知らず |
| 0933 | 世の中は 何か常なる 飛鳥川 昨日の淵ぞ 今日は瀬になる | 読人知らず |
| 0935 | 雁の来る 峰の朝霧 晴れずのみ 思ひつきせぬ 世の中の憂さ | 読人知らず |
| 0938 | わびぬれば 身を浮草の 根を絶えて さそふ水あらば いなむとぞ思ふ | 小野小町 |
| 0941 | 世の中の うきもつらきも 告げなくに まづ知るものは 涙なりけり | 読人知らず |
| 0942 | 世の中は 夢かうつつか うつつとも 夢とも知らず ありてなければ | 読人知らず |
| 0944 | 山里は もののわびしき ことこそあれ 世の憂きよりは 住みよかりけり | 読人知らず |
| 0945 | 白雲の 絶えずたなびく 峰にだに 住めば住みぬる 世にこそありけれ | 惟喬親王 |
| 0947 | いづこにか 世をばいとはむ 心こそ 野にも山にも 惑ふべらなれ | 素性法師 |
| 0953 | あしひきの 山のまにまに 隠れなむ うき世の中は あるかひもなし | 読人知らず |
| 0956 | 世を捨てて 山にいる人 山にても なほ憂き時は いづち行くらむ | 凡河内躬恒 |
| 0959 | 木にもあらず 草にもあらぬ 竹のよの 端に我が身は なりぬべらなり | 読人知らず |
| 0965 | ありはてぬ 命待つ間の ほどばかり うきことしげく 思はずもがな | 平貞文 |
| 0977 | 身を捨てて ゆきやしにけむ 思ふより 外なるものは 心なりけり | 凡河内躬恒 |
| 0983 | 我が庵は みやこのたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人は言ふなり | 喜撰法師 |
| 0984 | 荒れにけり あはれ幾世の 宿なれや 住みけむ人の おとづれもせぬ | 読人知らず |
| 0987 | 世の中は いづれかさして 我がならむ 行きとまるをぞ 宿とさだむる | 読人知らず |
| 0989 | 風の上に ありかさだめぬ 塵の身は ゆくへも知らず なりぬべらなり | 読人知らず |
| 0996 | 忘られむ 時しのべとぞ 浜千鳥 ゆくへも知らぬ 跡をとどむる | 読人知らず |
長歌 誹諧歌
| 1001 | あふことの まれなる色に 思ひそめ 我が身は常に 天雲の 晴るる時なく 富士の嶺の もえつつとはに 思へども あふことかたし 何しかも 人をうらみむ わたつみの 沖を深めて 思ひてし 思ひは今は いたづらに なりぬべらなり ゆく水の 絶ゆる時なく かくなわに 思ひ乱れて 降る雪の けなばけぬべく 思へども えぶの身なれば なほやまず 思ひは深し あしひきの 山下水の 木隠れて たぎつ心を 誰にかも あひかたらはむ 色にいでば 人知りぬべみ 墨染めの 夕べになれば ひとりゐて あはれあはれと なげきあまり せむすべなみに 庭にいでて 立ちやすらへば 白妙の 衣の袖に 置く露の けなばけぬべく 思へども なほなげかれぬ 春霞 よそにも人に あはむと思へば |
読人知らず |
| 1005 | ちはやぶる 神無月とや 今朝よりは 雲りもあへず 初時雨 紅葉と共に ふるさとの 吉野の山の 山嵐も 寒く日ごとに なりゆけば 玉の緒とけて こき散らし あられ乱れて 霜こほり いや固まれる 庭の面に むらむら見ゆる 冬草の 上に降りしく 白雪の つもりつもりて あらたまの 年をあまたも すぐしつるかな |
凡河内躬恒 |
| 1007 | うちわたす をち方人に もの申す我 そのそこに 白く咲けるは 何の花ぞも | 読人知らず |
| 1008 | 春されば 野辺にまづ咲く 見れどあかぬ花 まひなしに ただ名のるべき 花の名なれや | 読人知らず |
| 1011 | 梅の花 見にこそきつれ うぐひすの ひとくひとくと いとひしもをる | 読人知らず |
| 1012 | 山吹の 花色衣 主や誰 問へど答へず くちなしにして | 素性法師 |
| 1015 | むつごとも まだつきなくに 明けぬめり いづらは秋の 長してふ夜は | 凡河内躬恒 |
| 1017 | 秋くれば 野辺にたはるる 女郎花 いづれの人か つまで見るべき | 読人知らず |
| 1020 | 秋風に ほころびぬらし 藤ばかま つづりさせてふ きりぎりす鳴く | 在原棟梁 |
| 1022 | いそのかみ ふりにし恋の かみさびて たたるに我は いぞ寝かねつる | 読人知らず |
| 1026 | 耳なしの 山のくちなし えてしがな 思ひの色の 下染めにせむ | 読人知らず |
| 1028 | 富士の嶺の ならぬ思ひに もえばもえ 神だにけたぬ むなし煙を | 紀乳母 |
| 1030 | 人にあはむ 月のなきには 思ひおきて 胸はしり火に 心やけをり | 小野小町 |
| 1033 | 春の野の しげき草葉の 妻恋ひに 飛び立つきじの ほろろとぞ鳴く | 平貞文 |
| 1039 | 思へども 思はずとのみ 言ふなれば いなや思はじ 思ふかひなし | 読人知らず |
| 1041 | 我を思ふ 人を思はぬ むくいにや 我が思ふ人の 我を思はぬ | 読人知らず |
| 1048 | あふことの 今ははつかに なりぬれば 夜深からでは 月なかりけり | 平中興 |
| 1055 | ねぎことを さのみ聞きけむ やしろこそ はてはなげきの もりとなるらめ | 讃岐 |
| 1058 | 人恋ふる ことを重荷と になひもて あふごなきこそ わびしかりけれ | 読人知らず |
| 1061 | 世の中の うきたびごとに 身を投げば 深き谷こそ 浅くなりなめ | 読人知らず |
| 1064 | 身は捨てつ 心をだにも はふらさじ つひにはいかが なると知るべく | 藤原興風 |
| 1065 | 白雪の ともに我が身は 降りぬれど 心は消えぬ ものにぞありける | 大江千里 |
| 1066 | 梅の花 咲きてののちの 身なればや すきものとのみ 人の言ふらむ | 読人知らず |
| 1069 | 新しき 年のはじめに かくしこそ 千歳をかねて 楽しきをつめ | 読人知らず |
| 1070 | しもとゆふ かづらき山に 降る雪の 間なく時なく 思ほゆるかな | 読人知らず |
| 1074 | 神がきの みむろの山の さかき葉は 神のみまへに しげりあひにけり | 読人知らず |
| 1077 | み山には あられ降るらし と山なる まさきのかづら 色づきにけり | 読人知らず |
| 1083 | みまさかや 久米のさら山 さらさらに 我が名は立てじ 万代までに | 読人知らず |
| 1086 | 近江のや 鏡の山を 立てたれば かねてぞ見ゆる 君が千歳は | 大友黒主 |
| 1087 | 阿武隈に 霧立ちくもり 明けぬとも 君をばやらじ 待てばすべなし | 読人知らず |
| 1089 | 我が背子を みやこにやりて 塩釜の まがきの島の 松ぞ恋しき | 読人知らず |
| 1093 | 君をおきて あだし心を 我がもたば 末の松山 浪も越えなむ | 読人知らず |
| 1100 | ちはやぶる 賀茂のやしろの 姫小松 よろづ世ふとも 色はかはらじ | 藤原敏行 |
平成24年9月7日三島の楽寿園に出かけたとき、「万葉の森」があり、実際の植物と、其の歌が160首ほど紹介されていました。気になる歌人のページで、山部赤人と、当時の歌人を取り上げて簡単に紹介しましたが、いずれ「万葉集とは」何なのか調べようと思っており、そのままになっていましたが、今回再度万葉集の歌を目にして、とりあえず調べたのが、以下のメモ書き(亡備禄)です。
概要
7世紀後半から8世紀後半ころにかけて編まれた日本に現存する最古の和歌集である。天皇、貴族から下級官人、防人などさまざまな身分の人間が詠んだ歌を4500首以上も集めたもので、成立は759年(天平宝字3年)以後とみられる。
万葉集は最初から20巻あったのではなくて、もともと巻1と巻2の内容があって、これらにいろいろな歌集や歌の資料をもとに増えていったと考えられています。
書名の由来
「万の言の葉」を集めたとする説で、「多くの言の葉=歌を集めたもの」と解するものである。『古今和歌集』の「仮名序」にやまとうたは人の心をたねとしてよろづのことのはとぞなれりける
「末永く伝えられるべき歌集」(契沖や鹿持雅澄)
葉をそのまま木の葉と解して「木の葉をもって歌にたとえた」とする説
研究者の間で主流になっているのは、『古事記』の序文に「後葉(のちのよ)に流(つた)へむと欲ふ」とあるように、「葉」を「世」の意味にとり、「万世にまで末永く伝えられるべき歌集」ととる考え方
編者と成立年代
成立の過程は不明。七世紀に柿本人麻呂らが集めた歌集を底本に,八世紀に大伴家持が個人的な歌集も加えて取り纏めたことは間違いないと思われるが,最終的にいつ,誰の手によって成立したものかはわからないままである。
『万葉集』の成立に関しては詳しくわかっておらず、勅撰説、橘諸兄説、大伴家持説など古来種々の説があるが、現在では家持説が最有力である。ただ、『万葉集』は一人の編者によってまとめられたのではなく、巻によって編者が異なるが、家持の手によって二十巻に最終的にまとめられたとするのが妥当とされている。
巻1~~巻16 天平16年(744)以前?
巻17~~巻20 天平16年(744)以後?
巻17~~巻20が家持の身辺詠を日時を追って記しておりこれが天平18年(746)以後のものであり、先立つ巻16が天平16年(744)までの歌であるといわれているので、天平16年を境として巻1~~巻16がこれ以前、巻17~~巻20がこれ以降の成立と思われます。
万葉集の構成と内容
内容上から雑歌(ぞうか)・相聞歌・挽歌の三大部類になっている。
表現様式からは、
などに分けられる。
巻十四だけが東歌(あずまうた)の名をもっている。この卷には、上総・下総・常陸・信濃四国の雑歌、遠江・駿河・伊豆・相模・武蔵・上総・下総・常陸・信濃・上野・下野・陸奥十二国の相聞往来歌、遠江・駿河・相模・上野・陸奥五国の譬喩歌・国の分からないものの雑歌、相聞往来歌・防人歌・譬喩歌・挽歌・戯咲歌などが収められている。
歌を作った時期により4期に分けられる。
万葉集の楽しみ方
なんせ4500首を初から読む気力は無い。以下のことなどをきっかけに、あくまでも楽しむことを主眼にして行きたい。
1.万葉集には、植物を詠んだ歌が約千五百首もあるんだそうです。楽寿園には160首ほど これらを収集してみようかと思います。
2.ココロ・ニ・マドヲ万葉集 present by JR で映像がらみで万葉集の紹介があり、それをまとめました。
平成25年11月14日箱根の強羅に一泊し、帰りに楽寿園の菊祭りを見学。その時に「万葉の森」で紹介されている歌について事務所の方に問い合せし、資料を頂きました。改めてその一覧をここに載せました。
| 番号 | 万葉 植物名 |
定説 植物名 |
歌詞 | 作者 | 万葉集番号 |
| 1 | あかね | アカネ | あかねさす昼は物思ひぬば玉の 夜はすがらに哭(ね)のみし泣かゆ |
中臣宅守 なかとみのやかもり |
15-3732 |
| 2 | あきのか | マツタケ | 高松のこの峯も狭(せ)に笠立てて 盈(み)ち盛りたる秋の香のよさ |
10-2231 | |
| 3 | あさ | アサ | 麻衣着(け)ればなつかし紀の国の 妹背(いもせ)の山に麻蒔く吾妹(わぎも) |
藤原 卿 ふじわらのまえつきみ |
07-1195 |
| 4 | あさがほ | キキョウ | 朝顔はあさつゆ負(お)いて咲くといえど 夕陰にこそ咲きまさりけれ |
10-2104 | |
| 5 | あし | アシ(ヨシ) | 若の浦に潮みちくれば潟(かた)を無み 葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る |
山部赤人 | 06-0919 |
| 6 | あしつき | アシツキノリ | 雄神河(おかみがは)くれなゐにほふ少女らし 葦附(あしつき)採ると瀬に立たすらし |
10-4021. | |
| 7 | あは | アワ | 足柄の箱根の山に粟まきて 実とはなれるを逢はなくもあやし |
東歌 | 14-3364 |
| 8 | あふひ | フユアオイ | 梨棗(なしなつめ)黍(きみ)に粟つぎ延(は)ふ田葛(くず)の 後も逢はむと葵花(あふひばな)咲く |
16-3834 | |
| 9 | あやめ | ショウブ | 雀公鳥(ほととぎす)まてど来鳴かず菖蒲草(あやめぐさ) 玉に貫(つ)く日をいまだ遠(とほ)みか |
大伴家持 | 08-1490 |
| 10 | あおな | カブ | 食薦(すこも)敷き青菜煮持ち来(こ)梁(うつはり)に 行縢(むかばき)懸けて息むこの公(きみ) |
長忌寸意吉麿 ながのいみきおきまろ |
16-3825 |
| 11 | いちし | ヒガンバナ | 路の辺の壱師(いちし)の花のいちしろく 人皆知りぬわが恋妻を |
11-2480 | |
| 12 | いね | イネ | 稲春(いねつ)けば皸(かか)る吾が手を今夜もか 殿の若子(わくご)が取りて嘆かむ |
14-3459 | |
| 13 | いはゐづら | スベリヒユ | 入間道(いりまぢ)の大家が原のいはゐ蔓(つら) 引かばぬるぬる吾にな絶えそね |
14-3378 | |
| 14 | うきまなご | ウキクサ | 解衣(とききぬ)の恋ひ乱れつつ浮渉(うきまなご) 生(う)きてもわれはあり渡るかも |
11-2504 | |
| 15 | うけら | オケラ | 恋しけば袖も振らむを武蔵野の うけらが花の色に出(づ)なゆめ |
14-3376 | |
| 16 | うはぎ | ヨメナ | 春日野に煙(けぶり)立つ見ゆ少女らし 春野のうはぎ採みて煮らしも |
10-1876 | |
| 17 | うも | サトイモ | 蓮葉(はちすば)は斯くこそあるもの意吉麿(おきまろ)が 家(け)にあるものは芋(うも)の葉にあらし |
長意吉麿 ながのおきまろ |
16-3826 |
| 18 | うり | マクワウリ | 瓜食(は)めば子等(こども)思ほゆ栗食めば 況(ま)してしぬばゆ何処(いづく)より来たりしものぞ 眼交(まなかひ)にもとな懸かりて安寝(やすい)し為さぬ |
山上億良 やまのうへのおくら |
05-0802 |
| 瓜を食べれば子どものことを思い出す。栗を食べれば子どもがいとおしい。子どもはどこからやってきたのだろう。子どものことが目の前に浮かんで、なかなか寝付けないなぁ。 | |||||
| 19 | おほゐぐさ | フトイ | 上毛野(かみつけの)伊奈良の沼の大藺(おほゐ)草 よそに見しよは今こそまされ |
14-3417 | |
| 20 | おもひぐさ | ナンバンギセル | 道の辺の尾花がしたの思ひ草 今さらになど物か思はむ |
10-2270 | |
| 21 | かきつばた | カキツバタ | 杜若(かきつばた)衣に摺りつけ丈夫(ますらを)の きそひ狩りする月は来にけり |
大友家持 | |
| 22 | かたかご | カタクリ | 物部(もののふ)の八十(やそ)少女らが汲み乱(まが)ふ 寺井の上の堅香子(かたかご)の花 |
大友家持 | 19-4143 |
| 23 | かほばな | ヒルガオ | 高円(たかまど)の野辺の容花(かほばな)面影に 見えつつ妹は忘れかねつも |
大友家持 | 08-1630 |
| 24 | からあゐ | ケイトウ | 秋さらば写しもせむと吾が蒔きし 韓藍(からあゐ)の花を誰か採みけむ |
07-1362 | |
| 25 | きみ | キビ | 古りにし人の食(をさ)せる吉備の酒 病めばすべなし貫簀(ぬきす)賜(たば)らむ |
丹生女王 にうのおほきみ |
04-0554 |
| 26 | くくみら | ニラ | 伎波都久(きはつく)の岡の茎韮(くくみら)我摘めど 籠(こ)にも満た無ふ夫(せな)と摘まさね |
14-3444 | |
| 27 | くず | クズ | 雁がねの寒く鳴きしゆ 水茎の 岡の葛葉(きずは)は色づきにけり |
10-2208 | |
| 28 | くそかづら | ヘクソカズラ | 皀莢(かはらふぢ)に延(は)ひおぼとれる 屎葛(くそかづら) 絶ゆることなく宮仕(みやづかへ)せむ |
高宮 王 たかみやのおほきみ |
16-3855 |
| 29 | くれなゐ | ベニバナ | 外のみに見つつ恋せむくれなゐの 末摘花(すえつむはな)の色に出(い)でずしも |
10-1993 | |
| 30 | こけ | コケ類の総称 | 何時の間も神(かむ)さびけるか香具山の 鉾椙(ほこすぎ)が本に薛(こけ)生(む)すまでに |
鴨君足人 かものきみたるひと |
03-0259 |
| 31 | こなぎ | コナギ | 上毛野(かみつけの)伊香保の沼に殖子水葱(うゑこなぎ) かく恋ひむとや種求めけむ |
13-3415 | |
| 32 | こも | マコモ | 飼飯(けひ)の海の庭好くあらし刈薦(かりこも)の 乱れ出づ見ゆ海人の釣船 |
柿本人人麿 かきのもとのひとまろ |
03-0256 |
| 33 | しだくさ | ノキシノブ | 我が屋戸(やど)は軒の子太草(しだくさ)生ひたれど 恋忘草見れど生ひなく |
11-2475 | |
| 34 | しば | チカラシバ | 立ちかはり古き都となりぬれば 道の芝草長く生ひにけり |
田辺福麿 歌集 たなべのさきまろ |
06-1048 |
| 35 | しりくさ | サンカクイ | 湖葦(みなとあし)に交じれる草の知草の 人みな知りぬわが下思ひ |
11-2468 | |
| 36 | すげ | カサスゲ | 三嶋菅いまだ苗なり時待たば 著(き)ずやなりなむ三嶋菅笠 |
11-2836 | |
| 37 | すすき | ススキ | めづらしき君が家なるはなすすき 穂に出づる秋の過ぐらく惜しも |
石川広成 いしかわのひろなり |
08-1601 |
| 38 | すみれ | スミレ | 春の野に菫摘みしと来(こ)し吾ぞ 野をなつかしみ一夜寝にける |
山部赤人 | 08-1424 |
| 39 | せり | セリ | あかねさす昼はただびてぬばたまの 夜の暇(いとま)に採(つ)める芹子(せり)これ |
葛城王 かつらぎのおほきみ |
20-4455 |
| 40 | たで | ヤナギタデ | わが屋戸(やど)の穂蓼古幹(ほたでふるから)採み生(おほ)し 実になるまでに君をしまたむ |
11-2759 | |
| 41 | たまばはき | コウヤボウキ | 始春(はつはる)の初子(はつね)の今日(けふ)の玉箒(たまばはき) 手に執るからにゆらく玉の緒(を) |
大伴家持 | 20-4493 |
| 42 | つきくさ | ツユクサ | 鴨頭草(つきくさ)に衣色どり摺らめども 変(うつろ)ふ色といふが苦しき |
07-1339 | |
| 43 | つぎね | ヒトリシズカ | つぎねふ山城道(やましろぢ)を他夫(ひとつま)の馬より行くに 己夫(おのづま)し歩(かち)見るごとにより行けば哭(ね)のみし泣かゆ |
13-3314 | |
| 44 | つちはり | メハジキ | 吾が屋前(には)に生ふる土針(つちはり)心ゆも 想はぬ人の衣(きぬ)に摺らゆな |
07-1338 | |
| 45 | つばな | チガヤ | 茅(つばな)抜く浅茅(あさぢ)が原のつぼすみれ 今盛りなり吾が恋ふらくは |
田村家の毛の大嬢 たむらのいえのけのおほいらつめ |
08-1449 |
| 46 | ところづら | トコロ | 皇祖神(すめがみ)の神の宮人冬薯蕷葛(ところづら) いや常重(とこしく)に吾かへり見む |
07-1133 | |
| 47 | なぎ | ミズアオイ | 醤酢(ひしほす)に蒜搗(つ)き合(か)てて鯛願ふ 吾にな見せそ水葱(なぎ)の羹(あつもの) |
長意吉麿 ながのおきまろ |
16-3829 |
| 48 | なでしこ | カワラナデシコ | 野辺見れば瞿麦(なでしこ)の花咲きにけり わが待つ秋は近づくらしも |
10-1972 | |
| 49 | なのりそ | ホンダワラ | みさどゐる磯廻(いそみ)に生うる名乗藻(なのりそ)の 名は告(の)らしてよ親はしるとも |
山部赤人 | 03-0362 |
| 50 | なはのり | ウミソウメン | わたつみの沖つ縄海苔(なはのり)来る時と 妹が待つらむ月は経につつ |
15-3663 | |
| 51 | にこぐさ | ハコネシダ | 足柄の箱根のねろのにこぐさの 花つ妻なれや紐解かず寝む |
14-3370 | |
| 52 | ぬなは | ジュンサイ | 吾が情(こころ)ゆたにやゆたに浮蓴(うきぬなは) 辺にも奥(おき)にも依りかつましじ |
07-1352 | |
| 53 | ぬばたま | ウオウギ | 居(ゐ)明かして君をば待たむぬばたまの 吾が黒髪に霜は降れども |
古歌集 | 02-0089 |
| 「黒」や「夜」、またその他の「黒」をイメージさせる言葉を導きます。「ぬばたま」はヒオウギの黒い実のことです。 | |||||
| 54 | ねつこぐさ | オキナグサ | 芝付の御宇良崎(みうらさき)なる根都古草(ねつこぐさ) 逢ひ見ずあらば恋ひめやも |
14-3508 | |
| 55 | はちす | ハス | ひさかたの雨も降らぬか蓮葉(はちすば)に 渟(たま)れる水の玉にあらむ見む |
右兵衛 うひゃうゑ |
16-3837 |
| 56 | はなかつみ | ヒメシャガ | をみなへし佐紀沢に生うる花かつみ かつても知らぬ恋もするかも |
中臣女郎 まかじんじょろう |
04-0675 |
| 女郎花(おみなえし)が咲く佐紀沢(さきさわ)に咲いている花かつみ、という風に、かつてない恋に落ちているのです、私は。 | |||||
| 57 | はまゆふ | ハマオモト | み熊野の浦の浜木綿(はまゆふ)百重(ももへ)なす 心は思へど直(ただ)に逢うはむかも |
柿本人麿 かきのもとのひとまろ |
04-0496 |
| 熊野(くまの)の浦の浜木綿(はまゆう)が幾重にも重なり合っているように、心では思っているけれど、じかには逢えないですよねぇ | |||||
| 58 | ひえ | ノビエ | 打つ田には稗は数多にありといへど 択(え)らえしわれそ夜をひとり宿(ね)る |
11-2476 | |
| 59 | ひかげかづら | ヒカゲノカヅラ | あしひきの山下日陰蘰(かづら)ける 上にやさらに梅を賞(しの)めば |
大伴家持 | 19-4278 |
| 60 | ひし | ヒシ | 君がため浮沼(うきぬ)の池の菱採むと わが染めし袖濡れにけるかも |
柿本人人麿 かきのもとのひとまろ |
07-1249 |
| 61 | ひめゆり | ヒメユリ | 夏の野の繁みに咲ける姫百合の 知らえぬ恋は苦しきものを |
坂上郎女 さかのうへのいらつめ |
08-1500 |
| 62 | ひる | ノビル | 醤酢(ひしほす)に蒜搗(つ)き合(か)てて鯛願ふ 吾にな見せそ水葱(なぎ)の羹(あつもの) |
長意吉麿 ながのおきまろ |
16-3829 |
| 63 | ふぢばかま | フジバカマ | 萩の花 尾花葛花 瞿麦(なでしこ)の花 女郎花(おみなへし) また藤袴朝貌(あさがほ)の花 |
山上億良 やまのうへのおくら |
08-1538 |
| 64 | まめ | ツルマメ | 道の辺の荊(うまら)の末に這(は)ほ豆の からまる君を別れ行かむ |
丈部鳥 はせつかべのとり |
20-4352 |
| 65 | むぎ | オオムギ | 馬柵(うませ)越に麦食む駒の罵(ののし)らゆれど なほし恋しく思ひかねつも |
12-3096 | |
| 66 | むぐら | カナムグラ | 葎(むぐら)はふ賎しき屋戸(やど)も大君の 座さむと知らば玉敷(し)かましを |
橘諸兄 たちばなのもろえ |
19-4270 |
| 67 | むらさき | ムラサキ | 託馬野(つくまの)に生うる紫草(むらさき)衣に染(し)め いまだ着ずして色に出(い)でにけり |
笠郎女 かさのいらつめ |
03-0395 |
| 68 | ももよぐさ | ノジギク | 父母が殿の後方(しりへ)の百代草(ももよぐさ) 百代いでませわが来たるまで |
生玉部足国 いくたべのたりくに |
20-4326 |
| 69 | やまあゐ | ヤマアイ | 級(しな)照る 片足羽川(かたしはがは)のさ丹塗(にぬり)の 大橋の上ゆ紅(くれなゐ)の赤裳裾(あかもすそ)引き山藍(やまあゐ) |
09-1742 | |
| 70 | やますげ | ジャノヒゲ | あしひきの山菅の根のねもころに 止まず念(おも)はば 妹に逢はむかも |
12-3053 | |
| 71 | ゆり | ヤマユリ | あぶら火の光りに見ゆるわが蘰(かづら) さ百合の花の笑まはしきかも |
大伴家持 | |
| 72 | よもぎ | ヨモギ | ・・・霍公鳥(ほととぎす)来鳴く五月の菖蒲草 蓬(よもぎ)蘰(かづら)き酒宴(さかみづき 遊び慰(な)ぐれど・・・) |
大伴家持 | 18-4116 |
| 73 | わかめ | ワカメ | 比多潟(ひたがた)の磯の若布(わかめ)の立ち乱(みだ)え 吾(わ)をか待つなも 昨夜(きそ)も今夜(こよひ)も |
14-3563 | |
| 74 | わすれぐさ | ヤブカンゾウ | わすれ草わが紐に付く香具山の 故(ふ)りにし里を忘れむがため |
大伴旅人 おおとものたびと |
03-0334 |
| 75 | わらび | ワラビ | 石(いは)ばしる垂水の上のさ蕨(わらび)の 萌え出づる春になりにけるかも |
志貴皇子 しきのみこ |
08-1418 |
| 76 | ゑぐ | コログワイ | 君がため山田の沢に恵具(ゑぐ)採(つ)むと 雪消の水に裳の裾濡れぬ |
10-1839 | |
| 77 | をぎ | オギ | 神風の伊勢の浜荻折り伏せて 旅宿(やどね)やすらむ荒き浜辺に |
碁檀越の妻 ごのだんおちのつま |
04-0500 |
| 78 | をみなえし | オミナエシ | 手に取れば袖さへにほふ女郎花 この白露に散らまく惜しも |
10-2115 | |
| 番号 | 万葉 植物名 |
定説 植物名 |
歌詞 | 作者 | 万葉集番号 |
| 100 | あしび | アセビ | 磯の上に生うる馬酔木(あしび)を手折るらめど 見るすべき君がありといはなくに |
大来姫皇子 おほくのひめみこ |
10-2115 |
| 101 | あじさゐ | アジサイ | 紫陽花の八重咲く如くやつ世にを いませわが夫子(せこ)見つつしのはむ |
橘諸兄 たちばなのもろえ |
20-4448 |
| 102 | あづさ | ヨグソミネバリ | 梓弓春山近く家居して續(つ)ぎて聞くらむうぐいすの声 | 10-1829 | |
| 103 | あふち | センダン | 妹が見し棟(あふち)の花は散りぬべし わが泣く涙いまだ干(ひ)なくに |
山上億良 やまのうへのおくら |
05-0798 |
|
妻が見た楝(あふち)の花は、もう散ってしまうでしょう。私の涙は、まだかわくことが無いのに。 |
|||||
| 104 | あべたちばな | コウジミカン | 吾妹子に逢はず久しも甘美物(うましもの) 阿倍橘の蘿(こけ)生(む)すまでに |
11-2750 | |
| 105 | いちし | エゴノキ | 路の辺の壱師(いちし)の花の灼然(いちじろ)く 人皆知りぬわが恋妻は |
11-2480 | |
| 106 | いちひ | イチイガシ | 愛子汝夫(いとこなせ)の君・・・・あしひきのこの片山に二つ立つ 伊智比(いちひ)が本に梓弓・・・ |
乞食者 ほがひびと |
16-3885 |
| 107 | うのはな | ウツギ | ほととぎす鳴く声聞くや卯の花の 咲き散る岡に田草(くさ)引く乙女 |
10-1942 | |
| 108 | うまら | ノイバラ | 道の辺の宇万良(うまら)の末(うれ)にはほ豆の からまる君を離れか行かむ |
上総国防人 かづさのくにさきもり |
20-4352 |
| 109 | うめ | ウメ | 袖垂れていざわが苑にうぐいうの 木傳(こづた)ひ散らす梅の花見に |
藤原永手 ふぢはらのながて |
19-4277 |
| 110 | え | エノキ | わが門の榎の実もり喫(は)む百千鳥 千鳥は来れど君ぞ来まさぬ |
16-3872 | |
| 111 | おみのき | モミ | ・・・に湯のう上の樹群(こむら)を見れば臣の木も生に継ぎにけり 鳴く鳥の声も変わらず・・・ |
山部赤人 | 03-0322 |
| 112 | かし | アラカシ | 静まりし浦波さはぐわが背子が い立たせりけむいつ橿(かし)が本 |
額田王 ぬかたのおはきみ |
01-0009 |
| 113 | かしは | カシワ | 稲見野のあから柏は時あれど 君を吾が思ふ時は実無(さねな)し |
安宿の王 あすかべのおほきみ |
20-4301 |
| 114 | かづのき | ヌルデ | 足柄の吾(わ)を可鶏山(かけやま)の穀(かづ)の木の 我をかづさねも穀割かずとも |
14-3433 | |
| 115 | かつら | カツラ | 黄葉(もみじ)する時になるらし月人(つきひと)の かつらの枝の色づく見れば |
10-2202 | |
| 116 | かには | チョウジザクラ | ・・・敷妙の枕も纏(ま)かず桜皮纏(かにはま)き作れる船に 真楫貫(かにはま)き吾が漕ぎ来れば・・・ |
山部赤人 | |
| 117 | かはやなぎ | カワヤナギ | 山の際(ま)に雪は降りつつしかすがに この河楊(かわやぎ)は萌えにけるかも |
10-1848 | |
| 118 | かはらふぢ | サイカチ | 皀筴(かはれぶぢ)に延ひおぼとれる屎葛(くそかづら) 絶ゆることなく宮仕せむ |
高宮王 たかみやのおほきみ |
16-3855 |
| 119 | かへ | コノテガシワ | ほととぎす来鳴く五月に・・・見が欲し御面(みおも)直向かひ 見む時までは松柏(まつかべ)の栄えいまさね・・・ |
大伴家持 | 19-4169 |
| 121 | かへるで | イロハカエデ | わが屋戸(やど)に黄変(もみ)つ鶏冠木(かへるで)見るごとに 妹を懸け恋ひぬ日は無し |
田村大嬢 たむらのおほいらめ |
08-1623 |
| 122 | からたち | カラタチ | 枳(からたち)の棘原(うばら)刈り除(そ)け倉立てむ 屎遠(くそとほ)くまれ櫛造る刀首(とじ) |
忌部首 いみべのおびと |
16-3832 |
| 123 | くは | クワ | たらちねの母が園(その)なる桑すらに 願へば衣(きぬ)に着すとふものを |
07-1357 | |
| 124 | くり | クリ | 瓜食(は)めば子等(こども)思ほゆ栗食めば 況(ま)してしぬばゆ何処(いづく)より来たりしものぞ |
山上億良 やまのうへのおくら |
05-0802 |
| 125 | ごとう | アオギリ | 梧桐(ごどう)の日本(やまと)琴一面この琴夢に妹子(おとめ)になりて | 大伴旅人 おおとものたびと |
05-0810 題書 |
| 126 | こなら | コナラ | 下毛野(しもつけの)美可母(みかも)の山の小楢如(こならの)す ま麗(ぐは)し児(こ)らは誰が笥(け)か持たむ |
14-3424 | |
| 127 | このてがしは | コノテガシワ | 奈良山の児手柏(このてがしは)の両面(ふたおもて)に かにもかくにも侫人(ねぢけびと)の徒(とも) |
16-3836 | |
| 128 | さいかち | サイカチ | 皀莢(かはらふぢ)に延(は)ひおぼとれる 屎葛(くそかづら) 絶ゆることなく宮仕(みやづかへ)せむ |
高宮王 たかみやのおほきみ |
16-3855 |
| 129 | さかき | サカキ | ひさかたの天の原ゆ生まれ来る神の命(みこと) おくやまの賢木(さかき)の枝に白香著(しらかつ)け木綿(ゆふ)とり・・ |
坂上郎女 さかのうえのいらつめ |
03-0379 |
| 130 | さきくさ | ミツマタ | 春さればまづ三草(さきくさ)の幸くあれば 後にも逢はむな恋ひそ吾妹(わがも) |
柿本人麿 かきのもとのひとまろ |
|
| 131 | さくら | ヤマザクラ | 春雨に争ひかねて吾がやどの 桜の花は咲き始(そ)めにけり |
10-1869 | |
| 132 | ささ | ササの総称 | 子竹(ささ)の葉はみ山もさやに乱るとも 吾は妹思ふ別れ来ぬれば |
柿本人麿 かきのもとのひとまろ |
02-0133 |
| 133 | さなかづら | サネカズラ | 玉くしげみむろの山の狭名葛(さなかづら) さ寝ずはつひに有りかつまし |
藤原鎌足 ふりはらのかまたり |
|
| 134 | しきみ | シキミ | 奥山の 樒(しきみ)が花の名の如や しくしく君に恋わたりなむ |
大原今城 おほはらのいまき |
20-4476 |
| 135 | しひ | マテバシイ | 家にあれば笥(け)に盛る飯を草枕 旅にしあれば椎の葉に盛る |
有馬皇子 ありまのみこ |
02-0142 |
| 136 | しらかし | シラカシ | あしひきの山道も知らず白橿(しらかし)の 枝もとををに雪のふれれば |
柿本人麿 かきのもとのひとまろ |
10-2315 |
| 137 | すぎ | スギ | 古のひとの飢ゑけむ杉が枝に 霞たなびく春は来ぬらし |
柿本人麿 かきのもとのひとまろ |
10-1814 |
| 138 | すず | ヤノタケ | み薦(すず)刈る信濃の真弓わが引かば 貴人(うまびと)さびて否と言はむかも |
久米禅師 くめのせんじ |
02-0096 |
| 139 | すもも | スモモ | わが園の李(すもも)の花か庭に降る はだれのいまだ残りたるかも |
大伴家持 おほtものやかもち |
19-4140 |
| 140 | たく | コウジ | 水沫(みなわ)なす微(もろ)き命も栲縄(たくなは)の 千尋(ちひろ)にもがと願ひ暮らしつ |
山上憶良 やまのうへのおくら |
05-0902 |
| 141 | たけ | マダケ | 梅の花散らまく惜しみ吾が苑の 竹の林に鶯鳴くも |
阿氏奥島 あうぢのおきしま |
05-0824 |
| 142 | たちばな | ニホンタチバナ | 橘は実さへ花さその葉さへ 枝(え)に霜降れどいや常葉の樹 |
聖武天皇 しやうむてんのう |
06-1009 |
| 143 | たへ | コウゾ | 春過ぎて夏来るらし白細(しろたへ)の 衣乾したり天の香具山 |
持統天皇 じとうてんのう |
01-0028 |
| 144 | たまかづら | ツルデマリ | 玉葛 花のみ咲きて成るらざるは 誰(た)が恋ひにあらめ吾は恋ひ思(も)ふを |
巨勢女 こせのいらめ |
02-0102 |
| 145 | ちさ | エゴノキ | ・・・知佐(ちさ)のはな咲ける盛りに愛(は)しきよしその妻の児と 朝よひに笑み笑まずもうち嘆き・・・ |
大伴家持 おほとものやかもち |
18-4106 |
| 146 | ちち | イヌビワ | ちちの実の父の命(みこと)柞(ははそ)葉の母の命おぼろかに 情(こころ尽くして思うふらむその子なれやも・・・) |
大伴家持 おほとものやかもち |
19-4146 |
| 147 | ちち | イチョウ | 大王の任(まけ)のまにまに島守にわが立ち来れば柞(ははそ)葉の 母の命は御裳(みも)の裾つみ挙げかき撫で・・・ |
20-4408 | |
| 148 | つがのき | ツガ | かき数ふ二上山に神さびて立てる樛(つが)の木幹(もと)も枝も 同じ常盤に愛(は)しきよし・・・ |
大伴家持 おほとものやかもち |
17-4006 |
| 149 | つき | ケヤキ | 疾(と)く来ても見てましものを山城の 高き槻群(つきむら)散りにけるかも |
高市黒人 たけちのくろひと |
03-0277 |
| 150 | つきひとのかつら | キンモクセイ | 黄葉(もみぢ)する時になるらし月人の 楓(かつら)の枝の色づく見れば |
10-2202 | |
| 151 | つげ | ツゲ | 君なくばなぞ身よそはむ匣(くしげ)なる 黄楊(つげ)の小梳(をぐし)もとらむとも念はず |
播磨娘女 はりまのをとめ |
09-1777 |
| 152 | つた | ツタ | ・・・遠つ国 黄泉(よみ)の堺にはふ蔦の 各(おの)が向向(むきむき)天雲(あまぐも)の別れし行けば・・・ |
田辺福麿歌集 たなべのさきまろ |
09-1804 |
| 153 | つつじ | ヤマツツジ | ・・・竜田道(たつたぢ)の丘辺の路に丹つつじの薫(にほ)はむ時の 桜花咲きなむ時に山たづの向へ参出るむ・・・ |
高橋蟲麿 たかはしのむしまろ |
06-0871 |
| 154 | つづら | ツツラフジ | 駿河の海磯部(おしべ)に生ふる浜豆良(はまつづら) 汝(いまし)を憑(たの)み母に違ひぬ |
14-3359 | |
| 155 | つばき | ヤブツバキ | 巨勢山のつらつら椿つらつらに 見つつ思(しの)ばな巨勢の春野を |
坂門人足 さかとのひとたり |
01-0054 |
| 156 | つまま | タブノキ | 磯の上の都萬麻(つまま)を見れば 根を延(は)へて年深かりし神(かむ)さびにけり |
大伴家持 おほとものやかもち |
19-4159 |
| 157 | つみ | ハリグワ | このゆふべ柘(つみ)のさ枝の流れ来(こ)ば 梁(やな)は打たずて取らずかもあらむ |
若宮年魚麻呂 わかみやのあゆまろ |
03-0386 |
| 158 | つるばみ | クヌギ | くれなゐはうつろふものぞ橡(つるばみ)の なれにし衣になほしかめやも |
大伴家持 おほとものやかもち |
18-4109 |
| 159 | つるばみ | トチノキ | 橡(つるばみ)の衣(きぬ)は人皆 事無しと いひし時より着ほしく思ほゆ |
07-1311 | |
| 160 | とが | ツガ | 滝の上の御船の山に端枝(みづえ)さし 繁(しじ)に生ひたる 栂(とが)の木のいや継ぎ継ぎに・・・ |
笠金村 かさかなむら |
06-0907 |
| 161 | なし | ヤマナシ | もみぢ葉のにほひは繁し然(しか)れども 妻梨の木を手折り挿頭(かざ)さむ |
10-2188 | |
| 162 | なつめ | ナツメ | 玉掃(たまばはき)刈来鎌麿室の樹と 棗(なつめ)が本とかき掃かむため |
長意吉麿 ながいのおきまろ |
16-3830 |
| 163 | なら | ミズナラ | 御猟する雁羽(かりは)の小野の檪(なら)柴の 馴れは益(まさ)らず恋こそ益され |
12-3048 | |
| 164 | ねぶ | ネムノキ | 昼は咲き夜は恋ひ寝る合歓(ねぶ)の花 君のみ見るめや戯奴(わけ)さへに見よ |
紀女郎 きのいらめ |
08-1461 |
| 165 | はじ | ヤマハゼ | ・・・皇祖(すめろき)の神の御代より梔弓(はじゆみ)を手握り持たし 真鹿児矢を手挟み添へて・・・ |
大伴家持 おほとものやかもち |
20-4465 |
| 166 | はねず | ニワウメ | 念はずといひてしものを唐棣花(はねず)色の うつろひ易きわが心かも |
坂上郎女 さかのうへのいらつめ |
04-0657 |
| 167 | ははそ | コナラ | 山科の石田の小野の柞原(ははそはら) 見つつや君が山路越ゆらむ |
藤原宇合 ふぢはらのうまかい |
09-1730 |
| 168 | はり | ハンノキ | 引馬野(ひくまぬ)ににほふ榛原(はりはら)入り乱り 衣にほはせ旅のしるしに |
長忌寸意吉麿 ながのいみきおきまろ |
01-0057 |
| 引馬野に匂うはんの木の林に入り乱れて交じり合い衣を染めましょう 旅の証しに | |||||
| 169 | ひ | ヒノキ | いにしへにありけむ人もわが如か 三輪の檜原(ひばら)に挿頭(かざし)折りけむ |
柿本人麿 かきのもとひとまろ |
07-1118 |
| 170 | ひさぎ | アカメガシワ | ぬば玉の夜の更けゆけば久木生ふる 清き河原に千鳥しば鳴く |
山部赤人 やまべのあかひと |
06-0925 |
| 171 | ふぢ | ノダフジ | 恋ひしければ形見にせむとわがやどに 植ゑし藤波いま咲きにけり |
山部赤人 やまべのあかひと |
08-1471 |
| 172 | ほほがしは | ホオノキ | わが背子が捧げて持てる厚朴(ほほがしは) あたかも似るか青き蓋(きぬがき) |
僧恵行 ほふしえぎょう |
|
| 173 | ほよ | ヤドリギ | あしひきの山の木末(こぬれ)の寄生(ほよ)取るりて 挿頭しつらくは千年寿(ちとせほ)ぐとぞ |
大伴家持 おほとものやかもち |
18-4136 |
| 174 | まき | コウヤマキ | 真木柱(まきばしら)太き心は有りしかど この吾が心しづめかねつも |
舎人 とねり |
02-0190 |
| 175 | まつ | クロマツ | 磐代(いはしろ)の浜松が枝を引き結び 真幸(まさき)くあらばまた還りみむ |
有馬皇子 ありまのみこ |
02-0141 |
| 176 | まゆみ | マユミ | 南淵(みなぶち)の細川山に立つ檀(まゆみ) 弓束(ゆづか)まくまで人に知らえじ |
07-1330 | |
| 178 | むろのき | ネズ | 吾妹子(わぎもこ)が見し鞆の浦のむろの木は 常世(とこよ)にあれど見し人そなき |
大伴旅人 おほとものたびと |
03-0446 |
| 179 | もむにれ | ハルニレ | ・・・この片山のもむ楡を五百枝(いほえ)剥ぎたり天光(あまて)るや 日の気に干し嚇(さへ)づるや柄碓(からうす)につき・・・ |
乞食者 ほがひびと |
06-3886 |
| 180 | もも | モモ | 春の苑(その)紅にほふ桃の花 下照る道に出でたつをとめ |
大伴家持 おほとものやかもち |
19-4139 |
| 181 | やなぎ | シダレヤナギ | うちのぼる佐保の河原の青柳(あおやぎ)は 今は春べとなりにけるかも |
坂上郎女 さかのうへのいらつめ |
|
| 182 | やまたちばな | ヤブコウジ | あしひきの山橘の色に出よ 語らいひ継ぎて逢ふこともあらむ |
春日王 かすがのおほきみ |
04-0669 |
| 183 | やまたづ | ニワトコ | 君が行き日長(けなが)くなりぬ山多豆(やまたづ)の 迎えへを往かむ待ちには待たじ |
衣通王 そとほりのおほきみ |
02-0090 |
| 184 | やまぶき | ヤマブキ | 蝦(かはづ)なく甘南備河(かむびがは)にかげ見えて 今か咲くらむ山ぶきの花 |
厚見王 あつみのおほきみ |
08-1435 |
| 185 | ゆづるは | ウズリハ | 古(いにしへ)に恋ふる鳥かも弓弦葉(ゆづるは)の 御井(みゐ)の上より鳴き渡り行く |
弓削皇子 ゆげのみこ |
02-0111 |
| 200 | いはづな | テイカカヅラ | 石綱のまた変若(をち)かへりあをによし 奈良の都をまた見なむかも |
06-1046 | |
| 201 | きくわく | ヒマワリ | ・・・宜(よろし)主に恋(しの)ぶ誠は犬馬に逾え徳を仰ぐ心 心きくわくに同じ・・・ |
吉田宜の書翰 | 05-0864 |
| 202 | くくたち | アブラナ | 上毛野(かみつけ)の佐野の茎立(くくたち)折はやし 吾は待たむゑ今年来ずとも |
14-3406 | |
| 203 | さうじゅ | ナツツバキ | ・・・所似維摩大士(そゆにゆいまだいし)も玉体を方丈に疾ましめ 釈迦能仁(しゃかのうにん)も金容(こんよう)を双樹に掩(おほ)ひ・・・ |
山上憶良 やまのうへのおくら |
05-0896 |
| 204 | しの | ヤダケ | うちなびく春さり来れば小竹(しの)の末(うれ)に 尾羽(おは)うち触れて鶯鳴くも |
10-1830 | |
| 205 | しらつつじ | ツツジの総称 | 細領巾(たくひれ)の鷺の坂山の白躑躅(つつじ) われににほはね妹に示さむ |
09-1694 | |
| 鷺坂山の白つつじよ、私の衣を白くしてくれたらそれを私のいとしい人に見せましょう。 | |||||
| 206 | ちがや | チガヤ | 浅茅原(あさぢはら)つばらつばらにもの思へば 故りにし郷に思ほゆるかも |
03-0333 | |
| 207 | つぼすみれ | ニョイスミレ | 山吹の咲きたる野辺のつぼすみれ この春の雨に盛りなりけり |
高田女王 たかだのおほきみ |
08-1444 |
| 208 | な | 山菜の類 | 明日よりは若菜採まむとしめし野に 昨日も今日も雪はふりつつ |
山部赤人 やまべのあかひと |
08-1427 |
| 209 | なよたけ | メダケ | 秋山のしたへる妹なよ竹のとをよる子らは いかさまに思ひをれか・・・ |
02-0217 | |
| 210 | にぎめ | オゴノリ | 角島の追門(せと)の稚海藻(わかめ)は人のむた 荒(あり)かりしかどわがむたは和海藻(にぎめ) |
16-3871 | |
| 211 | にれ | アキニレ | おし照るや難波の小江に・・・この片山のもむ楡を 五百枝(いほえ)剥ぎ垂り天光(あまて)るや・・・ |
16-3886 | |
| 212 | はぎ | ヤマハギ | あが待ちし秋は来たりぬ然れども 芽子(はぎ)が花そもいまだ咲かずける |
10-2123 | |
| 213 | はは | アミガサユリ | 時時の花は咲けども何すれそ 母とふ花の咲き出来ずけむ |
丈部真麿 はかせべのままろ |
20-4323 |
| 214 | みら | ニラ | 伎波都久(きはつく)の岡の茎韮(くくみら)われ摘めど 籠(こ)にも満たなふ背なと摘まさね |
14-3444 | |
| 215 | むし | カラムシ | むしぶすま柔(なご)やが下に伏せれども 妹とし寝ねば肌し寒しも |
04-0524 | |
| 216 | も | 藻類海藻水 | 沖行(おきへゆ)き辺に行き今や妹のため わが漁(すなと)れる藻臥し束鮒(つかふな) |
04-0625 | |
| 217 | やまぢさ | イワタバコ | 山萵苣(やまぢさ)の白露(しらつゆ)しげみうらぶるる 心も深くわが恋止まず |
11-2469 | |
| 218 | らに | シュンラン | 蘭室に屏風徒(いたづ)らに張りて断腸の哀しび彌(いよいよ)痛く 枕頭に明鏡空しく懸りて染ねんの涙逾(いよいよ)落つ・・・ |
山上憶良 やまのうへのおくら |
05-0794 |
| 219 | やすれぐさ | ヤブカンゾウ | 萱草(わすれぐさ)吾が下紐に著(つ)けたれど 醜(しこ)の醜草言にしありけり |
大伴家持 おほとものやかもち |
04-0727 |
| 忘れ草を下着の紐につけたけれど、忘れ草とは名ばかりで、ひどい草です。(少しもあなたのことを忘れられないのです。) | |||||
| 220 | をばな | ススキ | 初尾花花に見むとし天の川 隔(へな)りにけらし年の緒長く |
20-4308 | |
| 221 | ゆふ | ワタ | 山高み白木綿花(しらゆふばな)に落ち激(たぎ)つ 滝の河内は見れど飽かぬかも |
06-0909 | |
ココロ・ニ・マドヲ万葉集 present by JRのホームページで紹介された歌を季節ごとに分け、取り上げました。
| 春の歌 | ||||
| 9.1684 | 春山は 散り過ぎぬとも 三輪山は 未だ含(ふふ)めり 君待ちかてに | 柿本人麻呂 | ||
| 【春山のおおかたは散り果てたとしても、この三輪山はまだつぼみです。あなたをいまだにお迎えできずに。】 |
||||
| 1.21 | 紫草(むらさき)の にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに われ恋ひめやも | 天武天皇 | ||
| 【紫草のように美しいあなたが憎かったら、あなたは人妻だのに、どうして恋いしたうことがあろう。】 人妻に恋をするのは、万葉時代のタブー |
||||
| 6.993 | 月立ちて ただ三日月の 眉根掻(まよねか)き 日(け)長く恋ひし 君に逢へるかも | 坂上郎女 さかのうへのいらめ |
||
| 【新しい月になってたった三日ほどの月のような眉を掻きつつ、日々長く慕って来たあなたにお逢いしたいことよ。】 眉がかゆくなることで、恋の兆しが見える。 |
||||
| 9.1768 | 石上(いそのかみ) 布留の早稲田の 穂には出でず 心のうちに 恋ふるこの頃 | 抜気大首 | ||
| 【石上の布留の早稲田の穂と違って、表面には出さず心の内だけで恋しく思っているこの頃よ。】 早稲田の穂に自分の思いを重ねる。自然に敏感だった万葉人ならではの恋の歌です。 |
||||
| 8.1463 | 吾妹子(わぎもこ)が 形見の合歓木(ねむ)は 花のみに 咲きてけだしく 実にならじかも | 大伴家持 | ||
| 【あなたの形見の合歓木は、花ばかり咲いて、おそらく実にはならないでしょう。】 | ||||
| 10.1855 | 桜花 時は過ぎねど 見る人の 恋の盛りと 今し散るらむ | 作者未詳 | ||
| 【桜の花は、まだ散る時期ではないのに、見る人の恋しさの盛りが今だと思って、散るのだろうか。】 自ら美しさの絶頂に散ってしまう潔さが、万葉人にも受け入れられた |
||||
| 8.1421 | 春山の 咲きのををりに 春菜つむ 妹が白紐 見らくしよしも | 尾張連 | ||
| 【春山の桜が咲き満ちた下で、若菜を摘むあの子の白い紐を見るのはうれしいことだ。】 大から小へ、必然的に焦点を定めていく。技巧的であり、美しいものを発見する喜びに満ちたこの歌。 天平時代、このような美意識や、精神性の高さが読まれる時代となったのです。 |
||||
| 3.328 | あをによし 寧楽の京師は 咲く花の 薫ふがごとく 今盛りなり | 小野老 | ||
| 【美しい奈良の都は、咲き誇る花が輝くように、今が盛りです。】 万葉の頃、太宰府には、文化人や教養人の多くが赴任しています。しかし、やはり太宰府といえば、流される場所、左遷されていく場所なのです。 |
||||
| 19.4142 | 春の日に 張れる柳を 取り持ちて 見れば都の 大路思ほゆ | 大伴家持 | ||
| 【春の日に葉っぱがふくらんだ柳の枝を折って、手に取ってみると、都の大路がしのばれることよ。】 黛(まゆずみ)で書いたようなすらっとした若葉がついた柳 柳黛を折って、都を思った歌だというのです。 美人の眉を柳眉ということからも、柳から女性の眉を連想したのでしょう |
||||
| 20.4500 | 梅の花 香をかぐはしみ 遠けども 心もしのに 君をしそ思ふ | 市原 王 | ||
| 【梅の花は香りがかぐわしいので、遠く離れているにもかかわらず、心もしなえるように、あなたをお慕いします。】 宴の主催者である清麻呂の人格を梅の香りに例えています。君がかぐわしい。つまりそれは、すぐれた人格であることを表現しているのです。 |
||||
| 3.330 | 藤波の 花は盛りに なりにけり 平城の京を 思ほすや君 | 大伴四綱 | ||
| 【藤の花が波うって盛りになったなあ。奈良の都を恋しくお思いでしょうか、あなた。】 藤原氏が都で勢力を伸ばしている時代、それに伴い、大伴氏の衰退も始まります。この歌では、藤の花と藤原氏をかけてもいるのでしょう |
||||
| 10.1917 | 春雨に 衣はいたく 通らめや 七日し降らば 七日来じとや | 作者未詳 | ||
| 【降っているのは春雨なのに、着物がひどく濡れることなどありましょうか。七日降り続いたら、七日も来ないとおっしゃるつもりですか】 |
||||
| 19.4139 | 春の苑 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つ少女 | 大伴家持 | ||
| 【春の庭を、紅色に照り輝かせる桃の花。その下で輝く道に、立ち現れる少女。】 女性の比喩として桃が登場します。中国では女性を生命の根源だと考えていました。女性も桃も生命を感じさせる存在だ 桃の木の下に少女の姿などありませんでした。しかし、人の想像力によって、事実を超えるほどの美しさは描くことができるのです。 |
||||
| 10.1812 | ひさかたの 天の香具山 このゆふべ 霞たなびく 春立つらしも | 柿本人麻呂 | ||
| 【天の香具山には、この夕方、霞が立ち込めている。春になったらしい。】 「ひさかたの」は、時間だけでなく距離としても彼方遠くを意味し、「天」の枕詞になっています。 |
||||
| 10.1883 | ももしきの 大宮人は 暇あれや 梅を挿頭して ここに集へる | 作者未詳 | ||
| 【大宮人は暇があるからか、梅を髪に插してここに集まっているなぁ。】 大宮人は日常として勤務することに縛られていました。働くことが日常的である暮らし。エリートならではのオシャレ |
||||
| 8.1418 | 石ばしる 垂水の上の さ蕨(わらび)の 萌え出づる春に なりにけるかも | 志貴皇子 | ||
| 【岩の上をほとばしる滝。そのほとりで蕨が天に向かって伸びていく。ああ、春だ。】 蕨とは、水のほとりに生える「ぜんまい」のこと。 人間も植物も、同じ生命を持つ存在として捉えられてきた万葉の頃。渦巻きの形はずっと続く命を連想させ、 無限の力を感じさせました。 |
||||
| 10.1833 | 梅の花 降り覆ふ雪を 裹み持ち 君に見せむと 取れば消につつ | 作者未詳 | ||
| 【梅の花に覆い降る雪を、手で包み持って君に見せよう、と取ると消え、取ると消えてしまう。】 梅の花は、冬に春への希望を見いだす存在でもあったのです。 |
||||
| 1.51 | 采女(うねめ)の 袖吹きかへす 明日香風 都を遠み いたづらに吹く | 志貴皇子 | ||
| 【采女のゆったりとした袖をひるがえすのは、明日香の風。都がなくなった今では、ただむなしく吹いているだけ。】 当時、「揺らす」という行為には「魂を揺り起こす、魂を活発にする」という意味があり、明日香の風が釆女の袖を「揺らす」様子は、彼女らの魂が生き生きと輝いていた、つまり、明日香の都が華やかに栄えていた象徴なのです。 |
||||
| 夏の歌 | ||||
| 19.4260 | 大君は 神にし坐せば 赤駒の 匍匐ふ田井を 都となしつ | 大伴御行 | ||
| 【天皇は神でいらっしゃるので、赤駒が腹ばう田を都としてしまわれた。】 戦に勝ち、新しい都が生まれる。その歓びに満ちあふれたこの歌は、天皇を神、神そのものだとして讃えているのです |
||||
| 7.1088 | あしひきの 山川の瀬の 響るなへに 弓月が嶽に 雲立ち渡る | 柿本人麻呂 | ||
| 【山川の浅瀬を流れる音が激しくなるにつれて、弓月が嶽に雲の立ち渡るのが見える。】 聴覚と視覚の両方で、大自然の動きをダイナミックにとらえているのです。 |
||||
| 20.4448 | 紫陽花の 八重咲く如く やつ代にを いませわが背子 見つつ思はむ | 橘諸兄 たちばなのもろえ |
||
| 【紫陽花が八重に咲くように、ますます長い年月を生きてくださいよ、あなた。紫陽花を見ながら、あなたをお慕いしましょう。】 |
||||
| 1.44 | 我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも | 石上麿 | ||
| 【わが妻をさあ見ようという「いざ見」の山は名ばかりで、高々とそびえているからか大和は見えないことよ。いや、これも国遠く旅して来たからか。】
万葉人は、視力ではなく、思いの深さや、人間関係が濃いか薄いかによって、距離感も温度差も変わることを知っていました 妻の姿を見たいと詠むのは、万葉の旅の歌のパターンの一つです |
||||
| 6.908 | 毎年(としのは)に かくも見てしか み吉野の 清き河内の 激(たぎ)つ白波 | 笠朝臣金村 | ||
| 【毎年来て、このように見たいものだ。吉野の清らかな河内に激しく流れる白波よ。】 「み」「吉」「清き」「激つ白波」という万葉当時の賛美する言葉が続き、毎年見たいということを強調しています。「見る」には褒めるという意味があり、天皇に対して尊敬を表わしているのです。 |
||||
| 60924 | み吉野の 象山の際の 木末には ここだもさわく 鳥の声かも | 山部赤人 | ||
| 【吉野にある象山あたりの梢には、たくさんの鳥たちのさえずりあう声が響いている。】 吉野にある象山あたり、象山あたりにある梢、その梢で鳴くたくさんの鳥たち。順に焦点を絞って、鳥の声へとフォーカスが定まっていきます |
||||
| 1.28 | 春過ぎて 夏来るらし 白栲の 衣乾したり 天の香具山 | 持統天皇 | ||
| 【春もおわり夏がやって来たらしい。真っ白な衣が干されている、あの天の香具山に。】 万葉から平安にかけて、歌人たちは「白」を面白み、 雪、雲、純白の着物などを巧みに歌の中に取り入れました。 |
||||
| 8.1494 | 夏山の 木末の繁に 霍公鳥 鳴き響(とよ)むなる 声の遥(はる)けさ | 大伴家持 | ||
| 【夏山のこずえの繁みから、ホトトギスの鳴く声が聞こえる。その声の遙かなことよ。】 目に見えるものではなく、音から風景を描き出す感覚。この歌には、ゆったりとした万葉の“品”というものが感じられます。 |
||||
| 11.2453 | 春楊(はるやなぎ) 葛城山(かづらきやま)に たつ雲の 立ちても坐(ゐ)ても 妹をしそ思ふ | 柿本人麻呂 | ||
| 【葛城山に沸き立つ雲のように、立っていても坐っていても、愛しいあの人のことを思ってしまうのです。】 万葉の時代、人と自然には区別がなく、全く同じ生命だと考えられていました。 人が呼吸するように、山も呼吸する。そして、山が吐き出した息が雲だとされていました |
||||
| 秋の歌 | ||||
| 3.416 | ももづたふ 磐余(いはれ)の池に 鳴く鴨を 今日のみ見てや 雲隠りなむ | 大津皇子 | ||
| 【磐余の池に鳴く鴨を見るのも今日を限りとして、私は雲の彼方に去るのだろうか。】 鴨は、万葉集では雄と雌が仲の良い鳥として詠まれています。愛を象徴する鳥。作者は鴨に妻のイメージを重ねました。 |
||||
| 14.3459 | 稲つけばかかる我が手を今夜もか殿の若子(わくご)が取りて嘆かむ | 作者未詳 | ||
| 【稲をつくとあかぎれになる私の手を、今夜も若殿さまが手にとって嘆かれるだろうか。】 労働をしながら、みんなで架空の恋を歌う。それが、日々のつらい作業を乗り切るチカラとなっていたのです |
||||
| 16.3826 | 蓮葉(はちすば)は かくこそあるもの 意吉麿(おきまろ)が 家なるものは 芋の葉にあらし | 長忌寸意吉麻呂 | ||
| 【蓮の葉とはこのようにこそあるもの。意吉磨の家にある蓮の葉は芋の葉のようです。】 愛する人を妹(いも)といい、食べる芋と読みが同じ。家にあるのは芋の葉っぱと詠むことで、家には妻がいるだけと、愛する妻を謙遜して歌ったのです |
||||
| 10.2177 | 春は萌え 夏は緑に 紅の 綵色(まだら)に見ゆる 秋の山かも | 作者未詳 | ||
| 【春は若い木の芽が萌え出す萌黄色、夏は緑となり、今は紅葉をまじえて美しく見える秋の山よ。】 萌えること、若々しくなること。そしてそれらの色が混ざり合い、複雑な色合いになることで秋の山となる。 春の色、夏の色を順に歌うことで、秋の山がどれだけ素晴らしいかを感じさせる歌なのです |
||||
| 1.75 | 宇治間山 朝風寒し 旅にして 衣貸すべき 妹もあらなくに | 長屋王 | ||
| 【宇治間山の朝に吹く風は冷たい。ただでさえ旅路にあって、衣を貸してくれる妻もいないのに。】 万葉の頃は、男性が女性のもとに通う 通い婚が普通でした。愛するふたりが別れを告げる時間は朝です。だからこそ、朝は恋愛の場面において特別な意味を持ちました。 |
||||
| 2.105 | わが背子を 大和へ遣ると さ夜深けて 暁露(あかときつゆ)に わが立ち濡れし | 大伯皇女 | ||
| 【私のいとしい弟を大和に送るといって、夜もふけ、やがて明け方の露に濡れるまで、私は立ち続けたことよ。】 六八六年、天武天皇の崩御後、謀反の疑いで逮捕された大津皇子は、二十四歳の若さで死を賜りました。その直前、自分は殺されるであろうと覚悟の上で、伊勢にいる姉、大伯皇女を訪ねます。 そして、再び大和へ帰って行く弟を見送った大伯皇女が、この歌を詠みました。 |
||||
| 2.106 | 二人行けど 行き過ぎ難き 秋山を いかにか君が 独り越ゆらむ | 大伯皇女 | ||
| 【二人で行ってさえ越えがたい秋の山を、一体どのようにして、あなたは今ひとりで越えているのだろうか。】 生きて会えるのが最後になるとは考えもせずに。都へ帰る弟を想って、大伯皇女が詠んだこの歌。そこには旅路の困難だけでなく、心理的にも越えがたい悲壮感が漂っています。 |
||||
| 1.54 | 巨勢山の つらつら椿 つらつらに 見つつ思はな 巨勢の春野を | 坂門人足 | ||
| 【巨勢山のつらつら椿を、その名のごとく、つらつらと見てはほめたたえたいものだ。巨勢の春の野を。】 、「つらつら椿」とは、つるつるの椿を意味するのです。一方「つらつらに見つつ」とは、じっくり見ることを意味します リズミカルで、くすっと笑いを呼び起こすこの歌には天皇を中心とした行幸の華やかさ、そして喜びをも思い起こさせるチカラがあるのです。 |
||||
| 10.2270 | 道の辺の 尾花が下の 思ひ草 今さらさらに 何をか思はむ | 作者未詳 | ||
| 【道のほとりの尾花の下に咲く、思い草のように、今あらためて、あらためて、何を思いましょうか。】 尾花とはススキであり、そのススキの下でうつむいたように咲くのが思い草です。 人知れずひっそりと咲く思い草が、悩み、苦しんでいる作者の姿と重なって見えてきます。 |
||||
| 2.208 | 秋山の 黄葉を茂み 迷ひぬる 妹を求めむ 山道知らずも | 柿本人麻呂 | ||
| 【秋の山は黄葉が繁っているので、道に迷ってしまった妻を探そうにも山道がわからない。】 愛する人が亡くなってしまった。それを、愛する人が秋の山で道に迷ってしまった、と歌ったのは柿本人麻呂です。万葉集では死を詠んだ歌はたくさんありますが、実際に人が亡くなったときは「死」という言葉で表現はしません。 なぜなら魂は永遠だと思う万葉びとにとって、死によって肉体がほろびてしまうという現実は、あまりにも残酷だったからです。だから、この歌では黄葉に紛れたと詠んでいるのです。 |
||||
| 8.1511 | 夕されば 小倉の山に 鳴く鹿は 今夜は鳴かず い寝にけらしも | 崗本天皇 こうもとてんほう |
||
| 【夕方になると、いつも小倉の山で鳴いている鹿が今夜は鳴かない。たぶん、もう寝てしまったのだろう。】 いつも妻を求めて鳴いていた鹿が、今夜は鳴いていない。それは、やっと共寝ができる妻に出会えたということを意味します。 なぜ鳴いているのか、なぜ今夜は鳴いていないのか。 ただの動物の鳴き声と捉えていないところに、人間と変わらない生き物への愛情が感じられます。万葉のころは山や雲にも魂があると考え、心が通じるとされていました。鹿が鳴くのにも意味があると考えられていたのでしょう |
||||
| 11.2480 | 路の辺の 壱師の花の いちしろく 人皆知りぬ 我が恋妻を | 柿本人麻呂 | ||
| 【路のほとりに咲く壱師の花のように、はっきりと人はみんな知ってしまった。私のいとしい人を。】 当時は妻問い婚が基本で、男性が女性のもとにはじめはこっそりと通いました。 万葉集に壱師の花が登場するのは、この一首のみ。壱師の花は彼岸花という説があります。 |
||||
| 冬の歌 | ||||
| 2.103 | わが里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 落らまくは後 | 天武天皇 | ||
| 【わが飛鳥の里には大雪が降っている。おまえのいる大原の古びた里に降るのは、もっと後だろうね。】 天武天皇がお后のひとり、藤原夫人に贈った歌です。雪が降ったとき、藤原夫人は里帰りをしていて大原にいました。 雪が降るのは、良いことが起こる前ぶれです。雪だって、まずは立派で新しい宮殿に降るのだ。だから、おまえのいる昔ながらの里にはもっと後で降るだろうよ、と雪までもが新しい宮を祝福してくれたと自慢したのです。 |
||||
| 1.74 | み吉野の 山の嵐の 寒けくに はたや今夜も わが独り寝む | 文武天皇 | ||
| 【吉野の山の嵐は寒いのに、また今夜も私はひとりで寝るのだろうか。】 愛しい人を恋しく想ったり、ひとり寝を寒く、寂しく感じることは旅を経験する人たちにとって、一般的な感情として共有できたのです。 |
||||
| 20.4516 | 新しき 年の始の 初春の 今日降る雪の いや重(し)け吉事(よごと) | 大伴家持 | ||
| 【新しい年のはじめの今日降る雪のように、いっそう重なれ、良いことよ。】 万葉集はこの歌で締めくくられています。 四千五百首あまりある万葉集のいちばん最後は、編者であるという説が有力な大伴家持の歌で終わっているのです。 この年、とてもめずらしいことに1月1日と立春が重なり、さらに良いことがあるとされた正月の雪も降り積もりました。 |
||||
| 1.4 | たまきはる 宇智の大野に 馬並めて 朝踏ますらむ その草深野 | 間人老 | ||
| 【宇智の広々とした野に馬を並べて、朝、踏んでいらっしゃるでしょう。その草深き野を。】 草が高々と生い茂っている宇智の広い野原に、たくさんの馬を並べて朝の狩りをされる。その舒明天皇のりりしい姿と、壮大な光景を想像して詠まれた歌です。 「宇智」とは地名ですが、カラダの内(うち)に生命が宿ることからも命そのものをさしました。 |
||||
| 8.1639 | 沫雪(あわゆき)の ほどろほどろに 降り敷けば 平城(なら)の京し 思ほゆるかも | 大伴旅人 | ||
| 【沫雪がまだらまだらに降り続くと、奈良の都が思い出されることよ。】 当時、旅人は九州の太宰府に赴任していました。降りしきる雪は、遠く離れた奈良の都だけでなくそこに残してきた友人までも思い起こさせたのです。 万葉人にとって、友情を象徴するものは6種ありました。雪はそのひとつです。 友を偲ぶのが、雪・月・花。友と共有し、一緒に楽しむのが琴・詩・酒です。 |
||||
| 1.48 | 東(ひむがし)の 野に炎(かげろひ)の 立つ見えて かへり見すれば 月傾きぬ | 柿本人麻呂 | ||
| 【東の野に朝日の光がさしはじめる頃。振り返ってみると西の空には月がかたむき、地平に沈もうとしている。】 本来、太陽と月は別の世界のものとされ、一緒に歌われることがありませんでした。ここではあえてそれを打ち破ることで、雄大さ、新たな美しさが表現されています。 昇る朝日が、新しく王位に就こうとしている若き軽皇子。沈む月とは軽皇子の父であり、若くして亡くなった草壁皇子のことを比喩したという説があります。 |
||||
| 其の他 | ||||
| 5.793 | 世の中は 空しきものと 知る時し いよよますます かなしかりけり | 大伴旅人 | ||
| 【この世が空(くう)だとはじめて思い知った時こそ、いよいよ、ますます悲しかったことだ。】 亡くなった人を思い続ける限り、生きている人の胸の中でその人は生き続ける。しかし、その悲しみをもって生き続けなくてはならない。そこに、底知れぬむなしさを感じたのかもしれません。 |
||||
| 4.608 | 相思はぬ 人を思ふは 大寺の 餓鬼の後方(しりへ)に 額づくがごと | 笠女郎 かさのいらずめ |
||
| 【思ってもくれない人を思うなんて、大寺の役にも立たぬ餓鬼像を、しかも後ろからひれ伏して拝むみたいなものです。】 この歌で、恋の相手である大伴家持を餓鬼と例えたのは、笠女郎です。万葉集の巻の四には彼女が家持に贈った歌、二十四首が収められています。 |
||||
| 7.1270 | こもりくの泊瀬(はっせ)の山に照る月は満ち欠けしけり人の常なき | 作者未詳 | ||
| 【隠口の泊瀬の山に照る月が満ち欠けするように、人もまた常無きことよ。】 隠口とは、周りを囲まれている場所のこと。隠口である「泊瀬」という地名には、人の命を終えるところという説があります。 死は、次の新しい生への出発だと考えられていました。泊瀬は、人の生涯を終えると共に、新しい別の命を出発させる場所。魂を鎮める静寂さに満ちた地であると想像できます。 万葉人は、常では無いことを嘆きながらも、満ちること、つまり復活への期待も抱いていたのです |
||||
| 4.668 | 朝に日(け)に 色づく山の 白雲の 思ひ過ぐべき 君にあらなくに | 厚見王 | ||
| 【朝ごとに日ごとにもみじする山にかかる白雲のように、忘れがたいあなたよ。】 紅葉が色づくのを朝日の中で見つけ、一日経つごとに深まっていくのを感じさせる。紅葉の輝きと太陽の輝きに、高貴さの象徴である白の鮮明な色が加わる。。「君」と呼ばれるのは、男性。つまり、男性である作者が女性の立場になって男性をほめた戯れの歌なのです。 |
||||
| 15.3724 | 君が行く 道のながてを 繰り畳ね 焼き亡ぼさむ 天の火もがも | 狭野茅上娘子 | ||
| 【あなたがいらっしゃる道の、長い道のりをたぐり寄せて、それを畳んで焼き尽くしてしまうような天の火がほしい。】 宅守が越前へ送られてしまう前に、恋の相手 狭野茅上娘子(さののちがみのをとめ)が詠んだ歌です。 愛する人よ、行かないでという強い想い。この歌は、万葉の頃ならではの情熱の表し方、激しい恋の叫びなのです。 |
||||
| 18.4086 | あぶら火の 光に見ゆる わが蘰(かずら) さ百合の花の 笑まはしきかも | 大伴家持 | ||
| 【ともしびの光の中に見える私の蘰。この百合の花がほほえましいことよ。】 ユリは神聖なものであることから、接頭語の「さ」をつけて「さ百合」と言いました。万葉の頃、うごくものゆれるものに対する信仰があり、尊重されていました。静止するのは、命が止まることと考えられていたからです。 |
||||
| 4.518 | 春日野の 山辺の道を 恐なく 通ひし君が 見えぬころかも | 石川郎女 | ||
| 【春日野の、あの山ぞいの険しい道も恐れることなく通って来てくれたあなただったのに、お見えにならないこの頃よ。】 夫婦でありながら、道ならぬ恋を語るかのようにその道のりだけでなく、人妻のもとに通うという険しさをも恐れず昔はどんな事情があれ通ってくれたのにと、相手に問いかけています。 |
||||
| 2.169 | あかねさす 日は照らせれど ぬばたまの 夜渡る月の 隠らく惜しも | 柿本人麻呂 | ||
| 【あかね色をおびて日輪は今日も輝いているのだが、太陽にも似た皇子は、ぬばたまの黒々とした夜空を渡る月のように隠れてしまったことが惜しいよ。】 六八九年、草壁皇子がお亡くなりになった時、柿本人麻呂が長歌とあわせて詠んだ反歌2首のうちの1首です。 「日は照らせれど」の「日」とは天皇のこと。太陽が輝いている、それは皇位継承者が立てられ、後のことは心配ないという意味です。それでも、やはり皇子が亡くなられたことは残念で仕方がない。 |
||||
| 4.488 | 君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く | 額田王 | ||
| 【君を待ち、恋しく思っていると、家のすだれを動かして秋風が音をたてる。】 すだれを開けて愛する人が逢いに来る。その気配を願いながら、待ち続ける女性のいじらしさ。額田王が天智天皇を慕って詠んだこの歌には、まるでドラマのセリフのように、女性の優雅さが漂っています。 |
||||
| 4.507 | 敷栲(いきたへ)の 枕ゆくくる 涙にそ 浮宿(うきね)をしける 恋の繁きに | 駿河采女 するがのうねめ) |
||
| 【やわらかな枕からこぼれおちる涙があふれて、私は水に浮かぶ思いで寝ています。絶えぬ恋の苦しさで。】 采女とは、国々から天皇に献上され、仕えている女性のこと。 容姿端麗で 宮中でも華やかな存在ですが、天皇以外の方に恋をするなど、とんでもないことでした。 架空の恋だったのでしょう。 采女には“待ち続ける女性”というイメージもあるのです。 |
||||
| 1.55 | あさもよし 紀人羨き(ひとともしも)しも 亦打山 行き来と見らむ 紀人羨しも | 調首淡海 | ||
| 【紀の国の人は、羨ましい。真土山を行きも帰りも見ているのだろう。 紀の国の人の羨ましいことよ。】 海のない大和で暮らす人々にとって、明るく雄大な海をもつ紀の国は憧れの地。心躍る、紀の国への旅路を想像させるのが真土山でした。この歌には旅のはずむ心も感じられます。 万葉の頃は、生命を謳歌しようとする思想があり家族や恋人に対し、想いをきちんと表現していた時代です |
||||
| 6.992 | 故郷の 飛鳥はあれど あをによし 平城(なら)の明日香を 見らくし好しも | 坂上郎女 さかのうへのいらめ |
||
| 【故郷であり、かつて都のあった飛鳥も良いけれど、今の都である奈良の明日香を見るのも良いことだ。】 「あをによし」は奈良にかかる枕詞です。「あをに」とは青い土を意味しました。それが豪華絢爛な都になることで、華やかな青と赤を意味する言葉へと変化します。美しさの概念が変わることで、言葉の意味も変化したのです |
||||
| 2.116 | 人言を 繁み言痛(こちた)み 己が世に いまだ渡らぬ 朝川渡る | 但馬皇女 たきまのひめみこ |
||
| 【人の噂が多くてうるさいので、生まれてはじめて、私は今まで渡ったことのない夜明けの川を渡る。】 万葉の頃は、男性が女性の家へ訪れるのが普通でした。この歌はその逆。女性である但馬皇女が、愛する男性のところへ逢いに行くというのです。 一人で夜明けの川を渡る女性。そこには女性が本来持っている激しさ、ひたむきな情熱が現れています |
||||
| 2.165 | うつそみの 人にあるわれや 明日よりは 二上山を 弟世(いろせ)とわが見む | 大伯皇女 | ||
| 【この世でまだ生きている私は、明日から、二上山を弟と思って見るのでしょうか。】 朱鳥元年(686年)9月、天武天皇が崩御。その翌月の10月2日、皇女の弟である大津皇子が謀反の疑いをかけられ逮捕されました。そして翌3日、まだ24歳という若さで死を賜ります。その後、祟りをおそれてか、遺体は聖山である二上山へ葬られました。 イロは親愛を示す語で、弟の字は肉親の弟の心を現わしたもの。セは男性をいう。
|
||||
| 11.2578 | 朝寝髪(あさいかみ) われは梳(けつ)らじ 愛(いとおし)しき 君が手枕 触れてしものを | 作者未詳 | ||
| 【朝の寝乱れた髪を、私は櫛でといたりなんかしない。だって、いとしいあの人の手が、枕として触れた髪だから。】 この歌は男性が帰った後の、朝の女性の気持ちを詠んでいます。 今でいう形見分けも、当時は亡くなった人の思い出としてではなく、その人がそこに存在している、という考えのもとで分け与えられていたようです。 愛する人が触れたものを愛おしく感じる。現代の日本人にも通じるこの感情は、万葉の時代に芽生えたのかも知れません。 |
||||
| 18.4136 | あしひきの 山の木末の 寄生(ほよ)木取りて 插頭(かざ)しつらくは 千年寿(ちとせほ)くとそ | 大伴家持 | ||
| 【あしひきの山の梢の寄生木(やどりぎ)をとって髪に插すのは、千年の寿を祈ってのことよ。】 「ほよ」とは、寄生木(やどりぎ)のこと。この土地では、正月には山から寄生木(やどりぎ)を折ってきて挿頭(かざ)す、つまり髪に插す習慣があったようです。それは、「やどりぎ」は冬になっても枯れず、みずみずしさを保っているからでしょうか。千年の命を祈り、新しい年を祝うのです。家持がこの歌を詠むことで、万葉集も世界中に伝わる寄生木信仰の仲間入りをしたのです。 |
||||
| 2.87 | ありつつも君をば待たむうち靡(なび)く我が黒髪に霜の置くまでに | 磐姫皇后 いわのひめのきさき |
||
| 【居つづけてあなたを待っていよう。長く靡くこの黒髪に霜がおくようになるまででも。】 仁徳天皇が旅に出た後の、皇后の心をたどる四首のうちの一首になります。 愛する人をひたすら待ち続ける、女性の激しい決意がこの歌には表れているのです。 |
||||
| 15.3589 | 夕さればひぐらし来鳴く生駒山越えてぞ我が来る妹が目を欲り | 秦間満 はたのままろ |
||
| 【夕暮れになるとひぐらしがやって来て鳴く生駒山。この山を越えて、帰って来た。妻に逢いたくて。】 険しい峠を越えたところで眼の前に広がるのは、いとしい妻がいる都。ひぐらしが鳴く夕暮れの生駒山を越えてきたんだな、と感じ妻への慕情をかきたてました。 |
||||
| 1.30 | ささなみの 志賀の辛崎 幸くあれど 大宮人の 船待ちかねつ | 柿本人麻呂 | ||
| 【志賀の辛崎は、変わらずにあるのだけれど、大宮人を乗せた船はいつまで待っても帰ってこない。】 白村江の戦いに敗れ、667年に都は大津へと遷ります。しかし、わずか5年後、壬申の乱によって都は滅びてしまうのです。この歌の作者は柿本人麻呂。都の跡を訪れて詠んだ反歌のひとつです。 |
||||
| 3.266 | 淡海の海 夕波千鳥 汝が鳴けば 情もしのに 古思ほゆ | 柿本人麻呂 | ||
| 【琵琶湖の夕波を飛ぶ千鳥よ。おまえが鳴くと心もしなえるように、昔のことが思われる。】 672年、壬申の乱で近江の都は没落します。にぎやかだった昔の面影はすでにない都の跡。その湖畔にたたずみ、物思いにふける。「情もしのに」の「しのに」とは、「死ぬ」と同じ語源です。人は死ぬと鳥になる。万葉の頃は、そう信じられていました。だからこそ、千鳥の鳴き声を聞くと、心は死んでしまうくらいの悲しみにくれたのです。 人の生死、亡くなった人と千鳥、千鳥と波。それぞれが境界線をなくして、区別がつかないほど「まぎれている」ことに、無常を感じたのでしょう。 |
||||
| 1.27 | よき人の よしとよく見て よしと言ひし 吉野よく見よ よき人よく見つ | 天武天皇 | ||
| 【立派な人がよい所だと思い、よく見て、よいと言った。 吉野をよく見よう。立派な人もよく見たのだ。】 吉野を見て何も言えなくなった作者の心情は、俳句でいう「松島や ああ松島や 松島や」にも通じる、「よし」という言葉のくり返しで、感動を歌い上げているのでしょう。 |
||||
| 2.85 | 君が行き 日長くなりぬ 山たづね 迎へか行かむ 待ちにか待たむ | 磐姫皇后 いわひめのおおきさき |
||
| 【あなたがおいでになってから、ずいぶん日にちが経った。山路を訪ねていこうか。それとも、待ち続けていようか。】 万葉の頃では、「待つ」ということは、恋愛上の大きなテーマでした。待って、待って、やっと逢えた。そのときの恋の力強さ。それがわかる万葉人だからこそ、待つ苦しみと向き合ったのです。 |
||||
| 3.3332 | わが命も 常にあらぬか 昔見し 象の小河を 行きて見むため | 大伴旅人 | ||
| 【私の命も変わらずあってほしい。昔見た、あの懐かしい象(きさ)の小川に、もう一度行って見たいので。】 常にあらぬかとは、いつもと変わらず、一定であり、通常であること。それは旅人にとって、重みのある言葉でした。 いつもと同じであるとは、命を落してしまうことなく、無事でいたいという願望を表しています。なぜそう願うのかは、もう一度都に戻りたい。忘れられない故郷の景色があるからです |
||||
| 12.3006 | 月夜よみ 門に出で立ち 足占(あうら)して ゆく時さへや 妹に逢はざらむ | 作者未詳 | ||
| 【月が美しいので門の外へ出て、占いをしたら吉と出た。 こんな時までも、もしかしたら妻には逢えないのだろうか。】 足占とは、足を使ってどう占ったのか、記録には残っていません。今でいうジャンケンのように、当時は、誰もが知っていて当たり前のことだったのでしょう。男性も愛する人を思い、占いで事を判断したのです。 愛する人をいつも思い、相手を乞い、気持ちを込める。この歌には、恋する万葉人ならではの生きざまが見えてくるのです。 |
||||
| 16.3822 | 橘の 寺の長屋に わが率寝(ゐね)し 童女放髪(うなゐはなり)は 髪上げつらむか | 作者未詳 | ||
| 【私が昔、橘寺の長屋に連れてきて共寝をした、おさげ髪の少女は、 髪を結い上げるほどの大人の女性になって、他の男と結婚しただろうか。】 女性は大人になると、長く伸びた髪を束ねて結い上げます。髪上げとは、成人した女性になることを示し、結婚する意にも用いられました。 少女の頃しか知らない作者は、過去の思い出から、現在へと思いを馳せていく…。 作者自身も当時は若く、淡い思い出としていたものが、ふっとよみがえったのでしょう |
||||
| 11.2417 | 石上(いそのかみ) 布留(ふる)の神杉(かむすぎ) 神(かむ)さびて 恋をもわれは 更にするかも | 柿本人麻呂 | ||
| 【石上の布留の神杉のように、神さび年老いても、また私は恋をするのかなぁ。】 「神さびて」とは、神々(こうごう)しく人間ばなれすることであり、歳をとることを意味します。ずっと成就せずに恋し続けた結果、年老いてしまった自分に気づくという歌。それがいつしか、神々しくなれるはずの歳になってまでも恋してしまうという歌になったのです。年甲斐もないということに、ほんの少しあざけりたくなる時代だったのかもしれません |
||||
| 4.667 | 恋ひ恋ひて 逢ひたるものを 月しあれば 夜は隠るらむ しましはあり待て | 坂上郎女 | ||
| 【長く恋し続けて、やっとお逢いできたのです。まだ月が残っているので夜の闇は深いでしょう。しばらくはこのままいてください。】 大伴坂上郎女が安倍虫磨に贈った恋歌です。ふたりは恋人でもなく、ふたりの間に恋心が芽生えたわけでもありません。仲間として楽しく語り合い、お酒を呑んでいるときに詠まれました。万葉集にあるパターンのひとつ、引き止め歌を真似て知的な遊びを言葉の上でしているのです。 日本語には複数という概念がありません。そこで例えば、木なら木木(きぎ)という風に、同じ言葉を重ねて複数を表現していたようです。「恋ひ恋ひて」は、恋し続けるという意味になります。 |
||||
| 4.712 | 味酒(うまさけ)を 三輪の祝(はふり)が いはふ杉 手触れし罪か 君に逢ひがたき | 丹波大女娘子 | ||
| 【三輪の神官がまつる神聖な杉の木に、手を触れるような罪を犯したとでもいうのだろうか。なかなかあの方に会うことができない。】 三輪山は神が降臨する山。木や草に至るまで、神が宿るものとして、斧を入れることは許されていません。 作者である丹波大女娘子は、おそらく遊女だと考えられます。三輪山の神聖な杉を例えに歌うことで、彼女の身の上との差を、一層せつなく感じさせてしまうのです。 |
||||
| 7.1126 | 年月も いまだ経なくに 明日香川 瀬瀬ゆ渡しし 石橋も無し | 作者未詳 | ||
| 【年月もそれほど経っていないのに、明日香川の瀬に渡してあった石橋も無くなっていました。】 この歌に登場する石橋は、石を組み上げた橋ではなく、川の浅瀬に飛び飛びに石を連ねただけのものです。決して変わらないと信じていた故郷が、いつの間にか変わっていた。人はいつの時代も、懐かしいと思えるもの、ただいまと言える場所を欲しているのです。 |
||||
| 1.18 | 三輪山を しかも隠すか 雲だにも 情あらなむ 隠さふべしや | 額田王 | ||
| 【三輪山を隠してしまうのですか。せめて雲にだけでも心があってほしい。雲よ、どうかその山を隠さないで。】 天智六年(667年)、都は奈良・明日香から近江へと遷りました。朝鮮半島の白村江の戦いに敗れた日本は、万一の追撃に備え、都を遷したという説があります。すべての人々はこの遷都を悲しみ、運命を呪いました。自然と共に生きる万葉びとにとって、山は特別な存在。特に美しい三輪山は魂のよりどころだったのです。自然の万物すべてに魂があり、心を持つとされていた、万葉の時代。三輪山を覆い隠す雲の心に呼びかけたこの歌は、人と自然は「心」をもって通じ合う、という当時の自然観から生まれたのでしょう。 |
||||
平成25年10月某日
万葉集、古今集、そして西行から近代の牧水、啄木、茂吉、白秋、信夫、と作品にぼちぼち目を通してきたが、折口信夫の歌論に目を通すに従い、アララギ派とか反アララギ派から何処に向かうか、どんな歌を詠めばよいか日々疑問に思う時があります。新聞の投稿欄の歌を見ても未熟な自分でも何か物足りない物を感じていました。自分としては日々のなかで季節や花や山々や、出来事に感動したり、迷ったり、生病老死の宿命を歌に詠むのが本題と簡単に思っています。それを的確な言葉で調子も踏まえ優雅に、華麗に、時には切なく詠って行ければと思うのですがそれでも何か心もとない気がしていました。その心境を以下の三首に
短歌とは あらゆる思ひの 心もて 調べに託す 言の葉さがしか
短歌とは 疑問抱きて 知を求め 求むる程に 惑ひは増さる
蝉なくは この世あの世の あはひらし 歌こそあはひ 夢とうつつの
歌の歴史を見ても古今集以後の歌として新古今集がまだ目を通していないのが気柄りで、それを調べてメモを残そうと思います。これで万葉から近代までの大方の概要がつかめるのでは。
新古今和歌集
『新古今和歌集』(しんこきんわかしゅう)は鎌倉時代初期、後鳥羽上皇の勅命によって編まれた勅撰和歌集。古今和歌集以後の8勅撰和歌集、いわゆる「八代集」の最後を飾る。
『古今集』を範として七代集を集大成する目的で編まれ、新興文学である連歌・今様に侵蝕されつつあった短歌の世界を典雅な空間に復帰させようとした歌集。古今以来の伝統を引き継ぎ、かつ独自の美世界を現出した。「万葉」「古今」と並んで三大歌風の一である「新古今調」を作り、和歌のみならず後世の連歌・俳諧・謡曲に大きな影響を残した。
選者 源通具・六条有家・藤原定家・藤原家隆・飛鳥井雅経・寂蓮の六人に撰者の院宣が下ったが、寂蓮は完成を見ずに没した。
成立過程
建仁元年(1201年)7月和歌所を設置、同年11月撰進の院宣が下り、元久元年(1204年)に選定、翌1205年3月26日完成し奏覧・竟宴。その後、建保4年(1216年)12月まで切継作業が続いた。
構成
巻は20巻で、
巻頭の仮名序は藤原良経、巻末の真名序は藤原親経による。歌数は八代集中最多の1979首を収録し、すべて短歌である。配列は巧みで、四季巻は季節の推移順、恋歌は恋の進行程度順に並べられており、古代の歌人と当時の歌人を交互においてある。
歌風
唯美的・情調的・幻想的・絵画的・韻律的・象徴的・技巧的などの特徴が挙げられる。定家の父俊成によって提唱された幽玄、有心の概念を、定家が発展させて「余情妖艶の体」を築き上げ、これが撰歌に大きく反映されている。また、鎌倉幕府成立以降、政治の実権を奪われた貴族社会の衰退の中で、滅びや自然への見方に哀調があると指摘される。またこの頃は題詠が盛んに行われていたことにより、より華やかな技巧にあふれている
『古今和歌集』 紀貫之流の 「をかし」の趣向を重視
余情---幽玄体
妖艶---色濃さの中に奥深さが感じられるという優美のひとつ
某HPより抜粋
新古今の入集歌は、浪漫的・幻想的・主情的・絵画的、さまざまな傾向を含むが、すぐれた作に共通しているのは、詞に於ける伝統の保守と、心に於ける清新さの追求という、一見相矛盾するかのごとき志向を、危うい均衡の上に調和させようと試みていることである
古今的な規範言語への復帰、また本歌取りや初句切れ・三句切れといった手法は、俗謡風のうわついた調子に堕してかけていた和歌に緊張した語感を恢復させ、歌枕や体言止めを多用した、イメージ喚起力の強い描写は、平板な趣向主義の枷から和歌を芳醇な情感の宇宙へと解放した。和歌はここに、豊かな抒情と高い格調を取り戻し、典雅にして優艷な本姿を遺憾なく顕した。新古今時代を和歌の絶頂期とする論者も少なからぬ所以である。
HPやまとうた 八代集秀歌選 ―『定家八代抄』による―より
567首をぼちぼち読んで載せていきます
| 001 | みよし野は山もかすみて白雪のふりにし里に春は来にけり | 摂政太政大臣(九条良経) |
| 002 | ほのぼのと春こそ空に来にけらし天の香久山霞たなびく | 後鳥羽院(太上天皇) |
| 010 | 春日野の下萌えわたる草の上につれなくみゆる春のあは雪 | 源国信みなもとのくにざね |
| 011 | あすからは若菜つまむと標(し)めし野に昨日もけふも雪は降りつつ | 山辺赤人 |
| 017 | 谷川のうち出づる浪も声たてつ鴬さそへ春の山風 | 藤原家隆朝臣 |
| 018 | 鴬の鳴けどもいまだふる雪に杉の葉白き逢坂の山 | 後鳥羽院 |
| 021 | 今更に雪ふらめやもかげろふの燃ゆる春日となりにしものを | 読人しらず |
| 023 | 空はなほ霞みもやらず風さえて雪げに曇る春の夜の月 | 摂政太政大臣 |
| 027 | 降りつみし高嶺のみ雪とけにけり清滝川の水の白波 | 西行法師 |
| 030 | 梅が枝に鳴きてうつろふ鴬の羽白妙にあは雪ぞふる | 読人しらず |
| 032 | 岩そそぐ垂氷(たるひ)の上の早蕨の萌え出づる春になりにけるかな | 志貴皇子 しきのみこ |
| 037 | 霞たつ末の松山ほのぼのと波にはなるる横雲の空 | 藤原家隆 |
| 045 | 梅が香に昔をとへば春の月こたへぬ影ぞ袖にうつれる | 藤原家隆 |
| 048 | 来ぬ人によそへて見つる梅の花散りなん後のなぐさめぞなき | 藤原定頼 |
| 049 | 春ごとに心をしむる花の枝(え)に誰がなほざりの袖かふれつる | 大弐三位 だいにのさんみ |
| 051 | とめこかし梅さかりなる我が宿をうときも人は折りにこそよれ | 西行法師 |
| 052 | ながめつる今日は昔になりぬとも軒端の梅は我を忘るな | 式子内親王 しょくしないしんのう |
| 054 | 独りのみながめて散りぬ梅の花知るばかりなる人はとひ来で | 八条院高倉 |
| 055 | 照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしく物ぞなき | 大江千里 |
| 056 | 浅みどり花もひとつに霞みつるおぼろに見ゆる春の夜の月 | 菅原孝標女 |
| 057 | 難波潟かすまぬ浪も霞みけりうつるもくもる朧月夜に | 源具親 |
| 058 | 今はとてたのむの雁もうち侘びぬ朧月夜の曙の空 | 寂蓮法師 |
| 059 | 聞く人ぞ涙は落つる帰る雁鳴きて行くなる曙の空 | 藤原俊成 |
| 060 | 故郷に帰る雁がねさ夜更けて雲路にまよふ声聞こゆなり | 読人しらず |
| 065 | 水の面(おも)にあや織りみだる春雨や山の緑をなべて染むらん | 伊勢 |
| 073 | 春風の霞吹きとく絶え間よりみだれてなびく青柳の糸 | 殷富門院大輔 |
| 074 | 白雲の絶え間になびく青柳の葛城山に春風ぞ吹く | 飛鳥井雅経 |
| 076 | うすくこき野辺の緑の若草に跡まで見ゆる雪のむら消え | 宮内卿 |
| 081 | 我が心春の山辺にあくがれてながながし日をけふも暮らしつ | 紀貫之 |
| 082 | 思ふどちそことも知らず行き暮れぬ花の宿かせ野辺の鴬 | 藤原家隆 |
| 083 | いま桜咲きぬと見えてうす曇り春にかすめる世の気色かな | 式子内親王 |
| 084 | ふして思ひ起きてながむる春雨に花の下紐いかにとくらん | 読人しらず |
| 085 | ゆかん人来ん人しのべ春がすみ立田の山のはつ桜花 | 大伴家持 |
| 086 | 吉野山去年(こぞ)のしをりの道かへてまだ見ぬかたの花を尋ねん | 西行法師 |
| 0099 | 桜咲く遠山鳥のしだり尾のながながし日もあかぬ色かな | 太上天皇(後鳥羽院) |
| 0100 | いく年(とせ)の春に心をつくし来ぬあはれと思へみ吉野の花 | 藤原俊成 |
| 0101 | はかなくて過ぎにしかたをかぞふれば花に物思ふ春ぞ経にける | 式子内親王 |
| 0102 | 白雲のたなびく山の八重桜いづれを花と行きて折らまし | 京極前関白太政大臣(藤原師実) |
| 0103 | 花の色にあまぎる霞立ちまよひ空さへ匂ふ山桜かな | 権大納言長家(藤原長家) |
| 0104 | 百敷の大宮人はいとまあれや桜かざして今日も暮らしつ | 山辺赤人 |
| 0105 | 花にあかぬ歎きはいつもせしかどもけふの今夜(こよひ)に似る時はなし | 在原業平朝臣 |
| 0106 | いもやすく寝られざりけり春の夜は花の散るのみ夢に見えつつ | 凡河内躬恒 |
| 0107 | 山桜散りてみ雪にまがひなばいづれか花と春に問はなん | 伊勢 |
| 0109 | 霞たつ春の山辺に桜花あかず散るとや鴬の鳴く | 読人しらず |
| 0110 | 春雨はいたくなふりそ桜花まだ見ぬ人に散らまくも惜し | 山辺赤人 |
| 0113 | この程は知るも知らぬも玉ぼこの行きかふ袖は花の香ぞする | 藤原家隆 |
| 0114 | またや見ん交野(かたの)の御野(みの)の桜がり花の雪ちる春の曙 | 藤原俊成 |
| 0115 | 散りちらずおぼつかなきは春霞立田の山の桜なりけり | 祝部成仲 はふりべのなりなか |
| 0122 | 山ふかみ杉のむらだち見えぬまで尾上の風に花の散るかな | 大納言経信(源経信) |
| 0124 | 麓まで尾上の桜散り来ずばたなびく雲と見てや過ぎまし | 左京大夫顕輔(藤原顕輔) |
| 0126 | ながむとて花にもいたく馴れぬれば散る別れこそ悲しかりけれ | 西行法師 |
| 0128 | 花さそふ比良の山風吹きにけり漕ぎ行く舟の跡みゆるまで | 宮内卿 |
| 0129 | 逢坂や木ずゑの花を吹くからに嵐ぞ霞む関の杉むら | |
| 0130 | 山高み嶺の嵐に散る花の月にあまぎる明け方の空 | 二条院讃岐 にじょういんのさぬき |
| 0134 | さくら色の庭の春風跡もなしとはばぞ人の雪とだに見ん | 藤原定家朝臣 |
| 0135 | 今日だにも庭をさかりと移る花消えずはありとも雪かとも見よ | 太上天皇(後鳥羽院) |
| 0136 | さそはれぬ人のためとや残りけん明日よりさきの花の白雪 | 摂政太政大臣(九条良経) |
| 0139 | 桜花夢かうつつかしら雲の絶えて常なき嶺の春風 | 藤原家隆朝臣 |
| 0144 | 散る花の忘れがたみの花の雲そをだにのこせ春の山風 | 左近中将良平 |
| 0147 | 吉野山花の故郷跡たえてむなしき枝に春風ぞ吹く | 摂政太政大臣 |
| 0148 | 故郷の花のさかりは過ぎぬれど面影さらぬ春の空かな | 大納言経信 |
| 0149 | 花は散りその色となくながむればむなしき空に春雨ぞ降る | 式子内親王 |
| 0158 | 吉野川岸の山吹咲きにけり嶺の桜は散りはてぬらむ | 藤原家隆朝臣 |
| 0159 | 駒とめてなほ水かはん山吹の花の露そふ井手の玉川 | 藤原俊成 |
| 0161 | かはづなく神奈備川に影みえて今か咲くらむ山吹の花 | 厚見王あつみのおおきみ |
| 0169 | 暮れてゆく春の湊は知らねども霞に落つる宇治の柴舟 | 寂蓮法師 |
| 0174 | 明日よりは志賀の花園まれにだに誰かはとはん春の古里 | 摂政太政大臣 |
| 0175 | 春過ぎて夏きにけらし白妙の衣ほすてふ天の香久山 | 持統天皇 |
| 0186 | 花散りし庭の木の間も茂りあひて天照る月の影ぞまれなる | 曾禰好忠 そねのよしただ |
| 0188 | 夏草は茂りにけりな玉桙(たまぼこ)の道行人(みちゆきびと)も結ぶばかりに | 藤原元真 |
| 0220 | うちしめりあやめぞ香る郭公鳴くや五月の雨の夕暮 | 摂政太政大臣 |
| 0225 | 早苗とる山田のかけひもりにけり引くしめ縄に露ぞこぼるる | 大納言経信 |
| 0226 | 小山田に引くしめ縄のうちはへて朽ちやしぬらん五月雨の頃 | 摂政太政大臣 |
| 0228 | 三島江の入江の真菰(まこも)雨ふればいとどしをれて苅る人もなし | 大納言経信 |
| 0230 | 玉柏(たまがしは)茂りにけりな五月雨に葉守の神のしめはふるまで | 藤原基俊 |
| 0232 | 玉ぼこの道行人(みちゆきびと)のことづても絶えて程ふる五月雨の空 | 藤原定家朝臣 |
| 0238 | 誰かまた花橘に思ひ出でん我も昔の人となりなば | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0248 | 郭公さ月みな月わきかねてやすらふ声ぞ空に聞こゆる | 権中納言国信 |
| 0251 | 鵜かひ舟あはれとぞ見るもののふの八十(やそ)宇治川の夕暗(ゆふやみ)の空 | 前大僧正慈円 |
| 0262 | 道の辺に清水ながるる柳蔭しばしとてこそ立ちどまりつれ | 西行法師 |
| 0263 | よられつる野もせの草のかげろひて涼しくくもる夕立の空 | 西行法師 |
| 0264 | おのづから凉しくもあるか夏衣日も夕暮の雨の名残に | 藤原清輔朝臣 |
| 0270 | 秋ちかきけしきの森に鳴く蝉の涙の露や下葉そむらん | 摂政太政大臣 |
| 0279 | 山里の嶺のあま雲とだえして夕べ涼しき槙のした露 | 太上天皇 |
| 0281 | 片枝(かたえ)さす麻生(をふ)の浦梨はつ秋になりもならずも風ぞ身にしむ | 宮内卿 |
| 0283 | 夏はつる扇(あふぎ)と秋の白露といづれかまづは置かむとすらん | 壬生忠岑 |
| 0286 | いつしかと荻の葉むけの片よりにそそや秋とぞ風も聞こゆる | 崇徳院 すとくのいん |
| 0287 | この寝ぬる夜のまに秋は来にけらし朝けの風の昨日にも似ぬ | 藤原季通 ふじわらのすえみち |
| 0289 | 昨日だにとはむと思ひし津の国の生田の杜に秋は来にけり | 藤原家隆朝臣 |
| 0299 | おしなべて物を思はぬ人にさへ心をつくる秋の初風 | 西行法師 |
| 0300 | あはれいかに草葉の露のこぼるらん秋風たちぬ宮城野の原 | 西行法師 |
| 0301 | みしぶつき植ゑし山田に引板(ひた)はへてまた袖ぬらす秋は来にけり | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0305 | 荻の葉も契りありてや秋風の音づれそむる妻となるらん | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0308 | うたた寝の朝けの袖にかはるなり馴らす扇の秋の初風 | 式子内親王 |
| 0310 | 秋風は吹き結べども白露の乱れておかぬ草の葉ぞなき | 大弐三位 |
| 0311 | 朝ぼらけ荻のうは葉の露みればやや肌さむし秋の初風 | 曾禰好忠 |
| 0312 | 吹き結ぶ風は昔の秋ながらありしにも似ぬ袖の露かな | 小野小町 |
| 0320 | 七夕のと渡る舟のかぢの葉にいく秋かきつ露の玉づさ | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0321 | ながむれは衣手涼し久かたの天の川原の秋の夕暮 | 式子内親王 |
| 0325 | わくらばに天の川波よるながら明くる空にはまかせずもがな | 徽子女王 きしじょおう |
| 0331 | 萩が花ま袖にかけて高円(たかまと)の尾上の宮に領布(ひれ)ふるや誰 | 顕昭法師 |
| 0333 | 秋萩の咲き散る野辺の夕露にぬれつつ来ませ夜は更けぬとも | 人麿 |
| 0334 | さを鹿の朝たつ野辺の秋はぎに玉と見るまでおける白露 | 中納言家持 |
| 0340 | うす霧の籬(まがき)の花の朝じめり秋は夕べと誰かいひけん | 藤原清輔朝臣 |
| 0345 | うらがるる浅茅が原のかるかやの乱れて物を思ふ頃かな | 坂上是則 |
| 0346 | さを鹿のいる野の薄はつ尾花いつしかいもが手枕にせむ | 人麿 |
| 0347 | 小倉山麓の野辺のはな薄ほのかに見ゆる秋の夕暮 | 読人知らず |
| 0349 | 花すすきまだ露ふかし穂に出でて詠(なが)めじとおもふ秋のさかりを | 式子内親王 |
| 0355 | 秋風のやや肌さむく吹くなべに荻のうは葉の音ぞ悲しき | 藤原基俊 |
| 0361 | さびしさはその色としもなかりけり槙立つ山の秋の夕暮 | 寂蓮法師 |
| 0368 | それながら昔にもあらぬ秋風にいとどながめをしづの苧環(おだまき) | 式子内親王 |
| 0370 | 秋来れば常磐の山の松風もうつるばかりに身にぞしみける | 和泉式部 |
| 0373 | 高円の野路の篠原末さわぎそそや木枯けふ吹きぬなり | 藤原基俊 |
| 0380 | ながめ侘びぬ秋よりほかの宿りかな野にも山にも月やすむらん | 式子内親王 |
| 0389 | にほの海や月の光のうつろへば浪の花にも秋はみえけり | 藤原家隆朝臣 |
| 0392 | ながめつつ思ふもさびし久かたの月の都の明けがたの空 | 藤原家隆朝臣 |
| 0393 | 故郷の本あらの小萩咲きしより夜な夜な庭の月ぞうつろふ | 摂政太政大臣 |
| 0399 | 心ある雄島(をじま)の海士(あま)の袂かな月やどれとはぬれぬものから | 宮内卿 |
| 0407 | かはらじな知るも知らぬも秋の夜の月待つ程の心ばかりは | 上東門院小少将 |
| 0413 | 秋風にたなびく雲の絶えまよりもれ出づる月の影のさやけさ | 左京大夫顕輔 |
| 0419 | 月だにもなぐさめがたき秋の夜の心も知らぬ松の風かな | 摂政太政大臣 |
| 0433 | 秋の露や袂にいたく結ぶらん長き夜あかずやどる月かな | 太上天皇 |
| 0435 | おほかたの秋の寝覚の露けくばまた誰が袖に有明の月 | 二条院讃岐 |
| 0437 | 下紅葉かつ散る山の夕時雨ぬれてやひとり鹿の鳴くらん | 藤原家隆朝臣 |
| 0439 | 野分せし小野の草ぶしあれはててみ山に深きさを鹿の声 | 寂蓮法師 |
| 0440 | 嵐吹く真葛が原に鳴く鹿は恨みてのみや妻を恋ふらむ | 俊恵法師 |
| 0444 | たぐへ来る松の嵐やたゆむらん尾上に帰るさを鹿の声 | 摂政太政大臣 |
| 0452 | 過ぎて行く秋の形見にさを鹿のおのが鳴く音も惜しくやあるらむ | 権大納言長家 |
| 0458 | 秋されば雁の羽風に霜降りてさむき夜な夜な時雨さへふる | 人麿 |
| 0459 | さを鹿の妻問ふ山の岡辺なる早田(わさだ)は刈らじ霜は置くとも | 人麿 |
| 0461 | 草葉には玉と見えつつ侘び人の袖の涙の秋の白露 | 菅贈太政大臣 菅原道真 すがわらのみちざね |
| 0462 | 我が宿の尾花が末の白露の置きし日よりぞ秋風も吹く | 中納言家持 |
| 0464 | 秋されば置く白露に我が宿の浅茅がうは葉色づきにけり | 人麿 |
| 0470 | 露は袖に物思ふ頃はさぞな置くかならず秋のならひならねど | 太上天皇 |
| 0471 | 野原より露のゆかりを尋ね来て我が衣手に秋風ぞ吹く | 太上天皇 |
| 0473 | 虫の音もながき夜あかぬ故郷に猶思ひそふ秋風ぞ吹く | 藤原家隆朝臣 |
| 0474 | 跡もなき庭の浅茅に結ぼほれ露の底なる松虫の声 | 式子内親王 |
| 0475 | 秋風は身にしむばかり吹きにけり今やうつらん妹がさ衣 | 藤原輔尹朝臣 |
| 0479 | まどろまでながめよとてのすさびかな麻のさ衣月にうつ声 | 宮内卿 |
| 0481 | 故郷に衣うつとは行く雁や旅の空にも鳴きて告ぐらむ | 大納言経信 |
| 0482 | 雁なきてふく風さむみから衣君待ちがてにうたぬ夜ぞなき | 貫之 |
| 0483 | み吉野の山の秋風さ夜更けて故郷さむく衣うつなり | 藤原雅経 |
| 0484 | 千度うつ碪(きぬた)の音に夢さめて物思ふ袖の露ぞくだくる | 式子内親王 |
| 0487 | 独りぬる山鳥の尾のしだり尾に霜おきまよふ床の月影 | 藤原定家朝臣 |
| 0488 | ひとめ見し野辺の気色はうら枯れて露のよすがにやどる月かな | 寂蓮法師 |
| 0491 | むら雨の露もまだひぬ槙の葉に霧立ちのぼる秋の夕暮 | 寂蓮法師 |
| 0495 | 山里に霧の籬(かきね)のへだてずば遠(ち)かた人の袖も見てまし | 曾禰好忠 |
| 0497 | 垣ほなる荻の葉そよぎ秋風の吹くなるなべに雁ぞ鳴くなる | 人麿 |
| 0498 | 秋風に山飛びこゆる雁がねのいや遠ざかり雲がくれつつ | 人麿 |
| 0501 | 横雲の風にわかるるしののめに山飛びこゆる初雁の声 | 西行法師 |
| 0502 | 白雲をつばさにかけて行く雁の門田の面の友したふなる | 西行法師 |
| 0505 | 吹きまよふ雲井をわたる初雁のつばさにならす四方の秋風 | 皇太后宮大夫俊成女 |
| 0507 | 霜を待つ籬の菊の宵の間におきまよふ色は山の端の月 | 宮内卿 |
| 0513 | 入り日さす麓の尾花うちなびき誰(たが)秋風に鶉(うずら)鳴くらむ | 左衛門督通光 |
| 0518 | きりぎりす鳴くや霜夜のさ筵に衣かたしき独りかも寝ん | 摂政太政大臣 |
| 0522 | かささぎの雲のかけはし秋暮れて夜はには霜やさえ渡るらん | 寂蓮法師 |
| 0525 | 神なびの三室の梢いかならんなべての山も時雨する頃 | 八条院高倉 |
| 0530 | 立田河あらしや嶺によわるらん渡らぬ水も錦たえけり | 宮内卿 |
| 0532 | 時わかぬ浪さへ色にいづみ川ははその森に嵐吹くらし | 藤原定家朝臣 |
| 0533 | 故郷は散る紅葉ばにうづもれて軒のしのぶに秋風ぞ吹く | 源俊頼朝臣 |
| 0534 | 桐の葉も踏み分けがたくなりにけり必ず人を待つとなけれど | 式子内親王 |
| 0537 | 露時雨もる山陰の下紅葉ぬるとも折らん秋の形見に | 藤原家隆朝臣 |
| 0539 | 鶉鳴く交野にたてる櫨(はじ)もみぢ散りぬばかりに秋風ぞ吹く | 前参議親隆 |
| 0540 | 散りかかる紅葉の色はふかけれど渡ればにごる山川の水 | 二条院讃岐 |
| 0542 | 飛鳥川瀬々に波よる紅や葛城山の木枯の風 | 権中納言長方 |
| 0543 | 紅葉ばをさこそ嵐のはらふらめ此の山もとも雨とふるなり | 権中納言公経 |
| 0552 | 神な月風に紅葉の散る時はそこはかとなく物ぞ悲しき | 藤原高光 |
| 0554 | 筏士(いかだし)よ待てこと問はむ水上はいかばかり吹く山の嵐ぞ | 藤原資宗朝臣 |
| 0555 | 散りかかる紅葉ながれぬ大井川いづれ井ぜきの水のしがらみ | 大納言経信 |
| 0566 | から錦秋の形見や立田山散りあへぬ枝に嵐吹くなり | 宮内卿 |
| 0570 | 月を待つ高嶺の雲は晴れにけり心あるべき初時雨かな | 西行法師 |
| 0577 | 時雨の雨染めかねてけり山城の常磐の杜の槙の下葉は | 能因法師 |
| 0580 | やよ時雨物思ふ袖のなかりせば木の葉の後に何を染めまし | 前大僧正慈円 |
| 0581 | 深緑あらそひかねていかならん間なく時雨のふるの神杉 | 太上天皇 |
| 0582 | 時雨の雨まなくしふれば槙の葉もあらそひかねて色づきにけり | 人麿 |
| 0583 | 世の中に猶(なお)もふるかな時雨つつ雲間の月の出でやと思へど | 和泉式部 |
| 0585 | 秋篠や外山の里や時雨るらん生駒の岳に雲のかかれる | 西行法師 |
| 0590 | 世にふるは苦しきものを槙の屋にやすくも過ぐる初時雨かな | 二条院讃岐 |
| 0591 | ほのぼのと有明の月の月影に紅葉吹きおろす山おろしの風 | 源信明朝臣 |
| 0602 | 紅葉ばはおのが染めたる色ぞかしよそげに置ける今朝の霜かな | 前大僧正慈円 |
| 0604 | 秋の色を払ひはててや久かたの月の桂に木枯の風 | 藤原雅経 |
| 0606 | 我が門の苅田の面にふす鴫(しぎ)の床あらはなる冬の夜の月 | 殷富門院大輔 |
| 0607 | 冬枯の森の朽葉の霜のうへに落ちたる月の影のさむけさ | 藤原清輔朝臣 |
| 0615 | 笹の葉はみ山もさやにうちそよぎ氷れる霜を吹く嵐かな | 摂政太政大臣 |
| 0616 | 君来ずば独りや寝なむ笹の葉のみ山もそよにさやぐ霜夜を | 藤原清輔朝臣 |
| 0617 | 霜枯はそことも見えぬ草の原誰に問はまし秋のなごりを | 皇太后宮大夫俊成女 |
| 0618 | 霜さゆる山田の畔(くろ)のむら薄刈る人なしに残る頃かな | 前大僧正慈円 |
| 0619 | 草のうへにここら玉ゐし白露を下葉の霜と結ぶ冬かな | 曾禰好忠 |
| 0620 | かささぎのわたせる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞ更けにける | 中納言家持 |
| 0624 | 野辺見れば尾花がもとの思ひ草枯れゆく冬になりぞしにける | 和泉式部 |
| 0628 | あづまぢの道の冬草しげりあひて跡だに見えぬ忘れ水かな | 康資王母 |
| 0632 | 消えかへり岩間にまよふ水の泡のしばし宿かる薄氷かな | 摂政太政大臣 |
| 0635 | かたしきの袖の氷も結ぼほれとけて寝ぬ夜の夢ぞみじかき | 摂政太政大臣 |
| 0636 | 橋姫のかたしき衣さむしろに待つ夜むなしき宇治の曙 | 太上天皇 |
| 0639 | 志賀の浦や遠ざかりゆく浪間より氷りて出づる有明の月 | 藤原家隆朝臣 |
| 0645 | 夕なぎに門渡る千鳥波間より見ゆる小島の雲に消えぬる | 後徳大寺左大臣 |
| 0657 | 矢田の野に浅茅色づくあらち山嶺のあは雪さむくぞあるらし | 人麿 |
| 0660 | 初雪のふるの神杉(かみすぎ)うづもれて標結ふ野辺の冬ごもりけり | 権中納言長方 |
| 0662 | さむしろの夜半の衣手さえさえて初雪しろし岡の辺の松 | 式子内親王 |
| 0671 | 駒とめて袖うちはらふ影もなし佐野のわたりの雪の夕暮 | 藤原定家朝臣 |
| 0672 | 待つ人の麓の道は絶えぬらん軒端の杉に雪おもるなり | 藤原定家朝臣 |
| 0674 | 降る雪に焚く藻の煙かき絶えてさびしくもあるか塩竈の浦 | 入道前関白太政大臣 九条兼実 くじょうかねざね |
| 0675 | 田子の浦に打ち出でてみれば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ | 赤人 |
| 0677 | 雪ふれば嶺のま賢木(さかき)うづもれて月にみがける天の香久山 | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0683 | この頃は花も紅葉も枝になししばしな消えそ松の白雪 | 太上天皇 |
| 0691 | おのづから言はぬを慕ふ人やあるとやすらふ程に年の暮れぬる | 西行法師 |
| 0696 | 思ひやれ八十(やそぢ)の年の暮なればいかばかりかは物は悲しき | 小侍従 |
| 0697 | 昔思ふ庭にうき木をつみおきて見し世にも似ぬ年の暮かな | 西行法師 |
| 0698 | いそのかみ布留野の小笹霜をへて一夜ばかりに残る年かな | 摂政太政大臣 |
| 0701 | いそがれぬ年の暮こそあはれなれ昔はよそに聞きし春かは | 入道左大臣 藤原実房 ふじわらのさねふさ |
| 0703 | 石(いは)ばしる初瀬の川の波枕はやくも年の暮れにけるかな | 後徳大寺左大臣 |
| 0707 | 高き屋にのぼりてみれば煙立つ民のかまどはにぎはひにけり | 仁徳天皇御歌 |
| 0708 | 初春のはつねの今日の玉帚(たまははき)手にとるからにゆらぐ玉の緒 | 読人知らず |
| 0716 | 千年ふる尾上の松は秋風の声こそかはれ色はかはらず | 躬恒 |
| 0717 | 山川の菊のした水いかなれば流れて人の老いをせくらん | 藤原興風 ふじわらのおきかぜ |
| 0719 | 山人の折る袖にほふ菊の露うちはらふにも千代はへぬべし | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0720 | 神無月紅葉もしらぬ常盤木に万代かかれ嶺の白雲 | 元輔 |
| 0729 | 子の日する野辺の小松をうつし植ゑて年の緒長く君ぞ引くべき | 権中納言通俊 |
| 0732 | 君が代にあへるは誰もうれしきを花は色にも出でにけるかな | 刑部卿範兼 |
| 0736 | 敷島や大和島根も神代より君がためとや固めおきけむ | 摂政太政大臣 |
| 0738 | 君が代は千世ともささじ天の戸や出づる月日のかぎりなければ | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0743 | 年へたる宇治の橋守こととはむ幾世になりぬ水のみなかみ | 藤原清輔朝臣 |
| 0750 | 鳥屋(とや)かへる鷹の尾山の玉椿霜をばふとも色はかはらじ | 前中納言匡房 |
| 0753 | 近江(あふみ)のや坂田の稲をかけ積みて道ある御代の始めにぞつく | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0757 | 末の露もとの雫や世の中のおくれさきだつつためしなるらん | 僧正遍昭 |
| 0758 | あはれなり我が身のはてや浅緑つひには野辺の霞と思へば | 小野小町 |
| 0760 | 墨染の衣うき世の花ざかりをり忘れても折りてけるかな | 実方朝臣 |
| 0761 | あかざりし花をや春も恋ひつらんありし昔を思ひ出でつつ | 道信朝臣 |
| 0775 | 置くと見し露もありけり儚くて消えにし人を何にたとへん | 和泉式部 |
| 0776 | 思ひきやはかなく置きし袖のうへの露を形見にかけんものとは | 上東門院 |
| 0788 | 玉ゆらの露も涙もとどまらずなき人こふる宿の秋風 | 藤原定家朝臣 |
| 0789 | 露をだに今は形見の藤衣あだにも袖を吹く嵐かな | 藤原秀能 |
| 0796 | 稀にくる夜半も悲しき松風をたえずや苔の下に聞くらん | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0801 | 思ひ出づる折りたく柴の夕煙むせぶもうれし忘れがたみに | 太上天皇 |
| 0803 | なき人の形見の雲やしぐるらん夕べの雨に袖はみえねど | 太上天皇 |
| 0808 | ほしもあへぬ衣の闇にくらされて月ともいはず惑(まど)ひぬるかな | 藤原道信朝臣 |
| 0811 | 逢ふことも今はなきねの夢ならでいつかは君を又は見るべき | 上東門院 |
| 0830 | 世の中は見しも聞きしもはかなくてむなしき空の煙なりけり | 藤原清輔朝臣 |
| 0831 | いつ歎きいつ思ふべきことなれば後の世知らで人のすぐらん | 西行法師 |
| 0832 | みな人の知り顔にして知らぬかな必ず死ぬるならひありとは | 前大僧正慈円 |
| 0833 | 昨日見し人はいかにとおどろけばなほ長き夜の夢にぞありける | 前大僧正慈円 |
| 0834 | 蓬生(よもぎふ)にいつか置くべき露の身はけふの夕暮あすの曙 | 前大僧正慈円 |
| 0835 | 我もいつぞあらましかばと見し人を忍ぶとすればいとど添ひ行く | 前大僧正慈円 |
| 0837 | なき跡の面影をのみ身にそへてさこそは人の恋しかるらめ | 西行法師 |
| 0838 | あはれとも心に思ふ程ばかり言はれぬべくは訪ひこそはせめ | 西行法師 |
| 0848 | いつのまに身を山がつになしはてて都を旅と思ふなるらん | 左京大夫顕輔 |
| 0850 | あるはなくなきは数そふ世の中にあはれいづれの日まで歎かん | 小野小町 |
| 0854 | くやしくぞ後に逢はむと契りける今日を限りといはましものを | 藤原季縄 |
| 0859 | 北へゆく雁のつばさにことづてよ雲のうはがきかき絶えずして | 紫式部 |
| 0860 | 秋霧のたつ旅ごろも置きて見よ露ばかりなる形見なりとも | 大中臣能宣朝臣 |
| 0864 | これやさは雲のはたてに織ると聞くたつこと知らぬ天の羽衣 | 寂昭法師 |
| 0881 | かりそめの別れと今日を思へども今やまことの旅にもあるらん | 俊恵法師 |
| 0886 | 頼めおかむ君も心やなぐさむと帰らんことはいつとなくとも | 西行法師 |
| 0887 | さりともとなほ逢ふことを頼むかな死出の山路を越えぬ別れは | 西行法師 |
| 0896 | とぶ鳥の飛鳥の里を置きていなば君があたりは見えずかもあらん | 元明天皇御歌 |
| 0897 | 妹に恋ひわかの松原みわたせば潮の干潟にたづ鳴き渡る | 聖武天皇御歌 |
| 0898 | いざこどもはや日の本へ大伴の御津(みつ)の浜松まち恋ぬらん | 山上憶良 |
| 0899 | 天ざかる鄙(ひな)のなが路を漕ぎくれば明石のとより大和島見ゆ | 人麿 |
| 0900 | 篠(ささ)の葉はみ山もそよに乱るなり我は妹思ふ別れ来ぬれば | 人麿 |
| 0901 | ここにありて筑紫やいづこ白雲のたなびく山の西にあるらし | 大納言旅人 |
| 0902 | 霧にぬれにし衣ほさずしてひとりや君が山路越ゆらん | 読人知らず |
| 0903 | 信濃なる浅間の岳にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ | 在原業平朝臣 |
| 0904 | 駿河なるうつの山辺のうつつにも夢にも人に逢はぬなりけり | 在原業平朝臣 |
| 0907 | 東路(あづまぢ)やさやの中山さやかにも見えぬ雲ゐに世をやつくさむ | 壬生忠岑 |
| 0910 | しなが鳥猪名野(ゐなの)をゆけば有馬山夕霧たちぬ宿はなくして | 読人知らず |
| 0911 | 神風の伊勢の浜荻折りふせて旅寝やすらん荒き浜辺に | 読人知らず |
| 0916 | 舟ながら今夜(こよひ)ばかりは旅寝せむ敷津の浪に夢はさむとも | 藤原実方朝臣 |
| 0921 | わぎもこが旅寝の衣うすき程よきて吹かなむ夜半の山風 | 恵慶法師 |
| 0924 | 山路にてそぼちにけりな白露の暁おきの木々のしづくに | 権中納言国信 |
| 0925 | 草枕旅寝の人は心せよ有明の月もかたぶきにけり | 大納言師頼(もろより) |
| 0932 | 夏刈りの蘆(よし)のかり寝もあはれなり玉江の月の明けがたの空 | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0933 | 立ちかへり又も来てみむ松島や雄島の苫屋波に荒らすな | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0938 | 月見ばと契りていでし故郷の人もや今夜袖ぬらすらむ | 西行法師 |
| 0939 | 明けばまた越ゆべき山の嶺なれや空行く月の末の白雲 | 藤原家隆朝臣 |
| 0953 | 旅人の袖ふきかへす秋風に夕日さびしき山のかけはし | 藤原定家朝臣 |
| 0968 | 忘れなむ待つとな告げそ中々にいなばの山の嶺の秋風 | 藤原定家朝臣 |
| 0973 | 難波人あし火たく屋に宿かりてすずろに袖のしほたるるかな | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0976 | 世の中はうきふししげし篠原(しのはら)や旅にしあれば妹夢に見ゆ | 皇太后宮大夫俊成 |
| 0984 | 立田山秋ゆく人の袖を見よ木々の梢はしぐれざりけり | 前大僧正慈円 |
| 0985 | さとりゆくまことの道に入りぬれば恋しかるべき故郷もなし | 前大僧正慈円 |
| 0989 | 見るままに山風あらくしぐるめり都も今は夜寒なるらん | 太上天皇 |
| 0990 | よそにのみ見てややみなむ葛城(かづらき)や高間の山の嶺の白雲 | 読人知らず |
| 0992 | 足曳の山田もる庵におく蚊火(かび)の下こがれつつ我が恋ふらくは | 人磨 |
| 0993 | 石上(いそのかみ)布留のわさ田のほには出でず心のうちに恋ひや渡らん | 人磨 |
| 0994 | 春日野の若紫のすり衣しのぶの乱れかぎりしられず | 在原業平朝臣 |
| 0996 | みかの原わきて流るる泉川いつ見きとてか恋しかるらん | 中納言兼輔 |
| 0997 | 園原やふせ屋におふる帚木(ははきぎ)のありとはみえて逢はぬ君かな | 坂上是則 |
| 0998 | 年をへて思ふ心のしるしにぞ空も便りの風は吹きける | 藤原高光 |
| 1001 | 人づてにしらせてしがな隠沼(かくれぬ)のみごもりにのみ恋ひや渡らん | 中納言朝忠 |
| 1003 | から衣袖に人めはつつめどもこぼるる物は涙なりけり | 謙徳公 |
| 1004 | 天つ空とよのあかりに見し人のなほ面影のしひて恋しき | 前大納言公任 |
| 1006 | 我が宿はそことも何か教ふべきいはでこそ見め尋ねけりやと | 本院侍従 |
| 1007 | わが思ひ空のけぶりとなりぬれば雲井ながらもなほ尋ねてむ | 忠義公 |
| 1010 | 風吹けば室(むろ)の八島(やしま)の夕煙こころの空にたちにけるかな | 藤原惟成 |
| 1013 | つくば山端山(やま)繁山しげけれど思ひ入るにはさはらざりけり | 源重之 |
| 1025 | 秋萩の枝もとををにおく露の今朝消えぬとも色に出でめや | 中納言家持 |
| 1029 | 我が恋は槙の下葉にもる時雨ぬるとも袖の色に出でめや | 太上天皇 |
| 1030 | 我が恋は松を時雨の染めかねて真葛が原に風さわぐなり | 前大僧正慈円 |
| 1031 | うつせみの鳴くねやよそにもりの露ほしあへぬ袖を人のとふまで | 摂政太政大臣 |
| 1032 | 思ひあれば袖に蛍をつつみても言はばや物をとふ人はなし | 寂蓮法師 |
| 1033 | 思ひつつ経にける年のかひやなきただあらましの夕暮の空 | 太上天皇 |
| 1034 | 玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする | 式子内親王 |
| 1035 | 忘れてはうち歎かるる夕べかな我のみ知りて過ぐる月日を | 式子内親王 |
| 1036 | 我が恋はしる人もなしせく床の涙もらすな黄楊(つげ)のを枕 | 式子内親王 |
| 1037 | 忍ぶるに心のひまはなけれども猶もる物は涙なりけり | 入道前関白太政大臣 九条兼実 くじょうかねざね |
| 1038 | つらけれど恨みんとはた思ほえずなほ行くさきをたのむ心に | 謙徳公 |
| 1039 | 雨こそは頼まばもらめたのまずば思はぬ人と見てをやみなん | 読人知らず |
| 1041 | 須磨の海士(あま)の浪かけ衣よそにのみ聞くは我が身になりにけるかな | 道信朝臣 |
| 1048 | みくまのの浦より遠(をち)に漕ぐ舟の我をばよそに隔てつるかな | 伊勢 |
| 1049 | 難波潟みじかき蘆のふしのまもあはで此の世を過ぐしてよとや | 伊勢 |
| 1050 | みかりする狩場の小野の楢柴のなれはまさらで恋ぞまされる | 人麿 |
| 1051 | うど浜のうとくのみやは世をばへん浪のよるよる逢ひ見てしがな | 読人知らず |
| 1052 | 東路の道の果なる常陸帯のかごとばかりも逢はむとぞ思ふ | 読人知らず |
| 1060 | 涙川身もうくばかり流るれど消えぬは人の思ひなりけり | 藤原元真 |
| 1065 | 須磨の浦に海士のこりつむ藻塩木のからくも下にもえ渡るかな | 藤原清正 |
| 1071 | 由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな | 曾禰好忠 |
| 1073 | かぢをたえ由良の湊による舟のたよりもしらぬ沖つ潮風 | 摂政太政大臣 |
| 1074 | しるべせよ跡なき浪に漕ぐ舟の行方もしらぬ八重の潮風 | 式子内親王 |
| 1081 | 下もえに思ひ消えなん煙だに跡なき雲のはてぞ悲しき | 皇太后宮大夫俊成女 |
| 1082 | なびかじな海士の藻塩火たきそめて煙は空にくゆりわぶとも | 藤原定家朝臣 |
| 1084 | みるめこそ入りぬる磯の草ならめ袖さへ浪の下に朽ちぬる | 二条院讃岐 |
| 1085 | 君こふと鳴海の浦の浜楸(はまひさぎ)しをれてのみも年をふるかな | 俊頼朝臣 |
| 1087 | もらすなよ雲井の嶺の初時雨木の葉は下に色かはるとも | 摂政太政大臣 |
| 1089 | 洩らさばや思ふ心をさてのみはえぞ山城の井手のしがらみ | 殷富門院大輔 |
| 1099 | はるかなる岩のはざまに独りゐて人目おもはで物思はばや | 西行法師 |
| 1106 | ながめ侘びそれとはなしに物ぞ思ふ雲のはたての夕暮の空 | 左衛門督通光 |
| 1111 | ちらすなよ篠の葉草のかりにても露かかるべき袖のうへかは | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1114 | 我が恋は千木の片そぎかたくのみ行きあはで年の積りぬるかな | 大炊御門右大臣 |
| 1116 | 藻塩やく海士の磯屋の夕煙たつ名もくるし思ひたえなで | 藤原秀能 |
| 1117 | 須磨の蜑(あま)の袖に吹きこす潮風のなるとはすれど手にもたまらず | 定家朝臣 |
| 1118 | ありとても逢はぬためしの名取川朽ちだにはてね瀬々の埋れ木 | 寂蓮法師 |
| 1120 | 涙川たぎつ心のはやき瀬をしがらみかけてせく袖ぞなき | 二条院讃岐 |
| 1121 | よそながらあやしとだにも思へかし恋せぬ人の袖の色かは | 高松院右衛門佐 |
| 1126 | 身にそへるその面影も消えななん夢なりけりと忘るばかりに | 摂政太政大臣 |
| 1132 | ふじの嶺の煙もなほぞ立ちのぼるうへなき物は思ひなりけり | 家隆朝臣 |
| 1135 | 我が恋は逢ふをかぎりのたのみだに行方もしらぬ空のうき雲 | 右衛門督通具 |
| 1139 | 袖のうへに誰ゆゑ月は宿るぞとよそになしても人のとへかし | 藤原秀能 |
| 1141 | いく夜われ浪にしをれて貴舟川袖に玉ちる物思ふらん | 摂政太政大臣 |
| 1142 | 年もへぬ祈る契りは初瀬山尾上の鐘のよその夕暮 | 定家朝臣 |
| 1143 | うき身をば我だに厭ふいとへただそをだに同じ心と思はむ | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1145 | あす知らぬ命をぞ思ふおのづからあらば逢ふ世を待つにつけても | 殷富門院大輔 |
| 1146 | つれもなき人の心はうつせみのむなしき恋に身をやかへてん | 八条院高倉 |
| 1148 | 思ひ知る人有明の世なりせばつきせず身をば恨みざらまし | 西行法師 |
| 1149 | 忘れじの行末まではかたければ今日をかぎりの命ともがな | 儀同三司母 | |
| 1151 | 思ふには忍ぶることぞまけにける逢ふにしかへばさもあらばあれ | 業平朝臣 | |
|
あなたを恋しいと思う気持ちには我慢しようとしても負けて逢ってしまう。逢えるのならば、どうなってもかまわない。
|
|||
| 1153 | 逢ふことをけふ松が枝の手向草(たむけぐさ)いく夜しをるる袖とかは知る | 式子内親王 | |
| 今日の逢う日をずっと待っていましたけれど、お待ちするその間、幾夜涙のせいで袖がしおれているかは知らないでしょう」。 | |||
| 1154 | 恋しさにけふぞ尋ぬるおく山の日影の露に袖はぬれつつ | 源正清朝臣 | |
| 1158 | 中々に物思ひそめて寝ぬる夜ははかなき夢もえやは見えける | 実方朝臣 | |
| 1164 | 蘆の屋のしづはた帯のかた結び心やすくも打ち解くるかな | 俊頼朝臣 | |
| 1167 | あけがたき二見の浦による浪の袖のみぬれておきつ島人 | 実方朝臣 | |
| 1169 | 秋の夜の有明の月の入るまでにやすらひかねて帰りにしかな | 太宰帥敦道親王 | |
| 1171 | はかなくも明けにけるかな朝露のおきての後ぞ消えまさりける | 延喜御歌 | |
| 1172 | 朝露のおきつる空も思ほえず消えかへりつる心まどひに | 更衣源周子 | |
| 1183 | おきて見ば袖のみぬれていとどしく草葉の玉の数やまさらん | 実方朝臣 | |
| 1184 | 明けぬれどまだきぬぎぬになりやらで人の袖をもぬらしつるかな | 二条院讃岐 | |
| 1185 | 面影の忘らるまじき別れかな名残を人の月にとどめて | 西行法師 | |
| 1189 | 朝ぼらけ置きつる霜の消えかへり暮まつ程の袖を見せばや | 花山院御歌 | |
| 早朝に置いた霜がやがて消え果てるように、私の命は消え入りそうになりながら、あなたに再び逢える夕暮を待つ――その間に流した涙で濡れた袖を、あなたに見せたいものだ。 | |||
| 1196 | あぢきなくつらき嵐の声もうしなど夕暮に待ちならひけん | 定家朝臣 | |
| 1201 | いかがふく身にしむ色のかはるかなたのむる暮の松風の声 | 八条院高倉 | |
| 1205 | 頼めぬに君くやと待つ宵の間のふけゆかでただ明けなましかば | 西行法師 | |
| 1206 | 帰るさの物とや人のながむらん待つ夜ながらの有明の月 | 定家朝臣 | |
| 1207 | 君こむといひし夜ごとに過ぎぬれば頼まぬものの恋ひつつぞふる | 読人知らず | |
| 1213 | 足曳の山の影草結び置きて恋ひやわたらん逢ふよしをなみ | 中納言家持 | |
| 1232 | よしさらば後の世とだに頼めおけつらさに堪へぬ身ともこそなれ | 皇太后宮大夫俊成 | |
| 1233 | 頼めおかむたださばかりを契りにてうき世の中の夢になしてよ | 藤原定家朝臣母 | |
| 1236 | 恋しさに死ぬる命を思ひ出でて問ふ人あらばなしと答へよ | 読人知らず |
| 1237 | 別れては昨日今日こそ隔てつれ千世しも経たる心ちのみする | 謙徳公 |
| 1238 | 昨日とも今日とも知らず今はとて別れし程の心まどひに | 恵子女王 |
| 1239 | 絶えぬるか影だに見えばとふべきを形見の水はみくさゐにけり | 右大将道綱母 |
| あの人との仲は絶えてしまったのだろうか。せめて水に面影だけでも見えれば、問いただすことができようものを、形見に残していった水には、もう水苔が生えて姿も映らない。 | ||
| 1240 | 方々(かたがた)に引き別れつつあやめ草あらぬねをやはかけんと思ひし | 陽明門院 |
| 1241 | 言の葉のうつろふだにもあるものをいとど時雨の降りまさるらん | 伊勢 |
| ただでさえ楓の葉がうつろうのに、さらに時雨が激しさを増して降るのだろうか。 | ||
| 1242 | 吹く風につけてもとはむささがにの通ひし道は空にたゆとも | 右大将道綱母 |
| 1244 | 霜さやぐ野辺の草葉にあらねどもなどか人目のかれまさるらん | 延喜御歌 |
| 1245 | 浅茅おふる野辺やかるらん山がつの垣ほの草は色もかはらず | 読人知らず |
| 1256 | 逢ふことをはつかに見えし月影のおぼろげにやはあはれとも思ふ | 天暦御歌 |
| 1257 | さらしなや姨捨山(をばすてやま)の有明のつきずも物を思ふ頃かな | 伊勢 |
| 1258 | いつとてもあはれと思ふを寝ぬる夜の月はおぼろげなくなくぞ見し | 中務 |
| 1260 | 天の戸をおし明けがたの月見ればうき人しもぞ恋しかりける | 読人知らず |
| 1267 | 月のみやうはの空なる形見にて思ひも出でば心かよはむ | 西行法師 |
| 1268 | くまもなき折しも人を思ひ出でて心と月をやつしつるかな | 西行法師 |
| 隈もなく照っている折しも、恋しい人を思い出して、自分の心からせっかくの明月をみすぼらしくしてしまったよ | ||
| 1269 | 物思ひてながむる頃の月の色にいかばかりなるあはれそふらん | 西行法師 |
| 1270 | 曇れかしながむるからに悲しきは月におぼゆる人の面影 | 八条院高倉 |
| 1293 | いはざりき今こんまでの空の雲月日へだてて物思へとは | 摂政太政大臣 |
| 1294 | 思ひ出でよ誰(た)がかねごとの末ならん昨日の雲のあとの山風 | 家隆朝臣 |
| 1295 | 忘れゆく人ゆゑ空をながむればたえだえにこそ雲もみえけれ | 刑部卿範兼 |
| 1296 | 忘れなばいけらん物かと思ひしにそれも叶はぬこの世なりけり | 殷富門院大輔 |
| 1302 | 恨み侘び待たじいまはの身なれども思ひなれにし夕暮の空 | 寂蓮法師 |
| あの人のつれなさを恨み、嘆いて、今はもう待つまいと思う我が身だけれど、夕暮れになると、空を眺めて待つことに馴れきってしまった | ||
| 1305 | さらでだに恨むと思ふわぎも子が衣のすそに秋風ぞ吹く | 有家朝臣 |
| 1307 | あはれとてとふ人のなどなかるらん物思ふやどの荻の上風 | 西行法師 |
| 1309 | 今はただ心のほかに聞くものを知らず顔なる荻の上風 | 式子内親王 |
| 1310 | いつも聞くものとや人の思ふらんこぬ夕暮の松風の声 | 摂政太政大臣 |
| 1311 | 心あらば吹かずもあらなむよひよひに人まつ宿の庭の松風 | 前大僧正慈円 |
| 1312 | 里はあれぬ空しき床のあたりまで身はならはしの秋風ぞ吹く | 寂蓮法師 |
| 1313 | 里はあれぬ尾上の宮のおのづから待ちこし宵も昔なりけり | 太上天皇 |
| 1322 | 我が恋は庭のむら萩うらがれて人をも身をも秋の夕暮 | 前大僧正慈円 |
| 1323 | 袖の露もあらぬ色にぞ消えかへり移ればかはる歎きせしまに | 太上天皇 |
| 1328 | さりともと待ちし月日ぞうつりゆく心の花の色にまかせて | 式子内親王 |
| 1336 | 白妙の袖の別れに露おちて身にしむ色の秋風ぞ吹く | 藤原定家朝臣 |
| 1338 | 野辺の露は色もなくてやこぼれつつ袖より過ぐる荻の上風 | 前大僧正慈円 |
| 1339 | 恋ひ侘びて野辺の露とは消えぬとも誰か草葉をあはれとは見む | 左近中将公衡 |
| 1340 | とへかしな尾花がもとの思ひ草しをるる野辺の露はいかにと | 右衛門督通具 |
| 1349 | 君がせぬ我が手枕は草なれや涙の露の夜な夜なぞおく | 光孝天皇御歌 |
| 1350 | 露ばかりおくらむ袖はたのまれず涙の川のたぎつせなれば | 読人知らず |
| 1356 | 涙のみうき出づる海士の釣竿のながき夜すがら恋ひつつぞぬる | 光孝天皇御歌 |
| 1358 | おもほえず袖に湊のさわぐかなもろこし船のよりしばかりに | 読人知らず |
| 1359 | いもが袖別れし日より白妙の衣かたしき恋ひつつぞぬる | 読人知らず |
| 1360 | 逢ふことの浪の下草みがくれてしづ心なくねこそなかるれ | 読人知らず |
| 1361 | 浦にたく藻塩の煙なびかめや四方のかたより風は吹くとも | 読人知らず |
| 1362 | 忘るらんと思ふ心のうたがひにありしよりけに物ぞ悲しき | 読人知らず |
| 1363 | うきながら人をばえしも忘れねばかつ恨みつつなほぞ恋しき | 読人知らず |
| 1366 | 今までに忘れぬ人は世にもあらじおのがさまざま年の経ぬれば | 読人知らず |
| 1368 | 山城の井手の玉水手にくみて頼みしかひもなき世なりけり | 読人知らず |
| 1369 | 君があたり見つつををらん伊駒山雲なかくしそ雨はふるとも | 読人知らず |
| 1371 | 雲のゐるとほ山鳥のよそにてもありとし聞けば侘びつつぞぬる | 読人知らず |
| 1372 | ひるは来てよるは別るる山鳥の影見る時ぞねはなかれける | 読人知らず |
| 1375 | 夏草の露分け衣きもせぬになど我が袖のかわく時なき | 読人知らず |
| 1376 | 御禊(みそぎ)するならのを川の河風に祈りぞわたる下に絶えじと | 八代女王 |
| 1378 | 蘆辺より満ち来る潮のいやましに思ふか君が忘れかねつる | 山口女王 |
| 1379 | 塩竈のまへにうきたる浮島のうきて思ひのある世なりけり | 山口女王 |
| 1386 | 涙川身もうきぬべき寝覚かなはかなき夢の名残ばかりに | 寂蓮法師 |
| 1387 | 逢ふとみてことぞともなく明けにけりはかなの夢の忘れ形見や | 家隆朝臣 |
| 1388 | ゆか近くあなかま夜はのきりぎりす夢にも人の見えもこそすれ | 藤原基俊 |
| あなかま = 声が高いぞ。静かに。しっ。▽人の話をやめさせようとして発する語。 | ||
| 1389 | あはれなりうたた寝にのみ見し夢の長き思ひに結ぼほれなん | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1391 | 夢かとよ見し面影も契りしも忘れずながらうつつならねば | 皇太后宮大夫俊成女 |
| 1392 | はかなくぞ知らぬ命を歎きこし我がかねごと(約束の言葉)のかかりける世に | 式子内親王 |
| 1402 | いかにしていかに此の世にあり経(へ)ばかしばしも物を思はざるべき | 和泉式部 |
| 1408 | 思ひいづや美濃のを山の一つ松契りしことはいつも忘れず | 伊勢 |
| 1413 | 逢はずしてふる頃ほひのあまたあれば遥けき空にながめをぞする | 光孝天皇御歌 |
| 1420 | 住吉の恋忘れ草たね絶えてなき世に逢へる我ぞ悲しき | 藤原元真 |
| 1427 | 我がよはひおとろへゆけば白妙の袖のなれにし君をしぞ思ふ | 読人知らず |
| 1429 | 玉くしげあけまく惜しきあたら夜を衣手かれて独りかも寝ん | 読人知らず |
| 1433 | 大淀の松はつらくもあらなくにうらみてのみも返る波かな | 読人知らず |
| 1436 | 年暮れし涙のつららとけにけり苔の袖にも春や立つらん | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1446 | 梅の花なににほふらん見る人の色をも香をも忘れぬる世に | 大弐三位 |
| 1449 | 道の辺の朽ち木の柳春くればあはれ昔と偲ばれぞする | 菅贈太政大臣 |
| 1460 | 見ても又またも見まくのほしかりし花の盛りは過ぎやしぬらん | 藤原高光 |
| 1463 | さもあらばあれ暮れ行く春も雲の上に散る事しらぬ花し匂はば | 大納言経信 |
| 1466 | 今は我よし野の山の花をこそ宿の物とも見るべかりけれ | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1469 | 見せばやな志賀の辛崎ふもとなる長柄の山の春のけしきを | 前大僧正慈円 |
| 1483 | から衣花の袂にぬぎかへよ我こそ春の色はたちつれ | 法成寺入道前摂政太政大臣 |
| 1484 | 唐衣たちかはりぬる春の夜にいかでか花の色を見るべき | 上東門院 |
| 1494 | よそへつつ見れど露だになぐさまずいかにかすべき撫子の花 | 恵子女王 |
| 1499 | めぐり逢ひて見しやそれともわかぬまに雲隠れにし夜はの月影 | 紫式部 |
| 1500 | 月影の山の端分けてかくれなばそむく浮世を我やながめん | 三条院御歌 |
| 1507 | 終夜(よもすがら)浦こぐ舟は跡もなし月ぞ残れる志賀のからさき | 宜秋門院丹後 |
| 1509 | 忘れじよ忘るなとだにいひてまし雲ゐの月の心ありせば | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1511 | 心には忘るる時もなかりけり三代の昔の雲の上の月 | 左近中将公衡 |
| 1512 | 昔見し雲ゐをめぐる秋の月今いくとせか袖にやどさむ | 二条院讃岐 |
| 1529 | 住みなれし人影もせぬ我が宿に有明の月の幾夜ともなく | 和泉式部 |
| 1531 | 思ひきや別れし秋にめぐりあひて又もこの世の月を見んとは | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1532 | 月を見て心うかれしいにしへの秋にもさらにめぐり逢ひぬる | 西行法師 |
| 1533 | 終夜(よもすがら)月こそ袖にやどりけれ昔の秋を思ひいづれば | 西行法師 |
| 1536 | 更けにける我が身の影を思ふまに遥かに月のかたぶきにけり | 西行法師 |
| 1557 | 藻塩くむ袖の月影おのづからよそにあかさぬ須磨の浦人 | 定家朝臣 |
| 1562 | 雲かかる遠山ばたの秋されば思ひやるだに悲しきものを | 西行法師 |
| 1583 | 時過ぎて霜にかれにし花なれど今日は昔の心ちこそすれ | 朱雀院御歌 |
| 1587 | 大かたに過ぐる月日を眺めしは我が身に年のつもるなりけり | 慈覚大師 |
| 1588 | 白浪のはま松が枝の手向草(たむけぐさ)いく世までにか年のへぬらん | 河島皇子 |
| 1589 | 山城の岩田の小野の柞原(ははそはら)みつつや君が山路こゆらん | 式部卿宇合 |
| 1590 | 蘆の屋のなだの塩焼いとまなみ黄楊(つげ)のを櫛もささず来にけり | 在原業平朝臣 |
| 1591 | 晴るる夜の星か河辺の蛍かも我が住むかたの海士のたく火か | 在原業平朝臣 |
| 1592 | 志賀の海士の塩焼く煙風をいたみ立ちはのぼらで山にたなびく | 読人知らず |
| 1597 | 沖つ風夜はに吹くらし難浪潟暁かけて浪ぞよすなる | 権中納言定頼 |
| 1612 | 今日とてや磯菜つむらん伊勢島や一志(いちし)の浦の海士の乙女子 | 太后宮大夫俊成 |
| 1614 | 世の中を心高くも厭ふかな富士のけぶりを身の思ひにて | 前大僧正慈円 |
| 1615 | 風になびく富士の煙の空に消えて行方もしらぬ我が思ひかな | 西行法師 |
| 1616 | 時しらぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらん | 業平朝臣 |
| 1619 | 吉野山やがて出でじと思ふ身を花ちりなばと人や待つらん | 西行法師 |
| 1624 | 滝の音松の嵐も馴れぬればうちぬるほどの夢はみせけり | 家隆朝臣 |
| 1626 | おく山の苔の衣にくらべみよいづれか露のおきまさるとも | 権大納言師氏 |
| 1627 | 白露のあした夕におく山の苔のころもは風もさはらず | 如覚 |
| 1635 | 奥山のおどろが下もふみ分けて道ある世ぞと人に知らせむ | 太上天皇 |
| 1637 | 今はとてつま木こるべき宿の松千世をば君となほ祈るかな | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1644 | かざしをる三輪のしげ山かき分けて哀とぞ思ふ杉たてる門 | 殷富門院大輔 |
| 1650 | もののふのやそ宇治川の網代木にいさよふ浪の行方知らずも | 人麿 |
| 1651 | 我が世をば今日かあすかと待つかひの涙の滝といづれ高けむ | 中納言行平 |
| 1658 | 山里に独りながめて思ふかな世にすむ人の心つよさを | 前大僧正慈円 |
| 1659 | 山里にうき世いとはむ友もがなくやしく過ぎし昔かたらむ | 西行法師 |
| 1661 | 草の庵をいとひても又いかがせむ露の命のかかるかぎりは | 前大僧正慈円 |
| 1663 | 世をそむく山の南の松風に苔の衣や夜さむなるらん | 安法法師 |
| 1671 | 山里にとひくる人のことぐさは此の住ひこそうらやましけれ | 前大僧正慈円 |
| 1675 | 岡の辺の里のあるじを尋ぬれば人はこたへず山おろしの風 | 前大僧正慈円 |
| 1681 | ふるさとは浅茅が末になりはてて月にのこれる人の面影 | 摂政太政大臣 |
| 1689 | 朝倉や木の丸(まろ)どのに我がをれば名のりをしつつ行くは誰が子ぞ | 天智天皇御歌 |
| 1690 | 足曳のかなたこなたに道はあれど都へいざといふ人のなき | 菅贈太政大臣 |
| 1694 | 霧立ちて照る日の本は見えずとも身は惑はれじ寄る辺ありやと | 菅贈太政大臣 |
| 1695 | 花と散り玉と見えつつあざむけば雪ふるさとぞ夢に見えける | 菅贈太政大臣 |
| 1697 | 筑紫にも紫おふる野辺はあれどなき名かなしぶ人ぞ聞こえぬ | 菅贈太政大臣 |
| 1698 | 苅萱(かるかや)の関守とのみ見えつるは人もゆるさぬ道辺なりけり | 菅贈太政大臣 |
| 1699 | 海ならずたたへる水の底までもきよき心は月ぞ照らさむ | 菅贈太政大臣 |
| 1700 | 彦星の行き逢ひを待つかささぎのわたせる橋を我にかさなむ | 菅贈太政大臣 |
| 1701 | 流れ木と立つ白浪とやく塩といづれか辛(から)きわたつみの底 | 菅贈太政大臣 |
| 1702 | さざなみや比良山風の海ふけば釣する海士(あま)の袖かへる見ゆ | 読人知らず |
| 1703 | 白浪のよする渚に世をつくす蜑(あま)の子なれば宿も定めず | 読人知らず |
| 1707 | 蘆鴨のさわぐ入江のみづのえの世に住みがたき我が身なりけり | 人麿 |
| 1712 | そのかみの玉のかざしをうち返し今は衣のうらをたのまん | 東三条院 |
| 1713 | つきもせぬ光のまにもまぎれなで老いて帰れるかみのつれなさ | 冷泉院太皇大后宮 |
| 1714 | かはるらん衣の色を思ひやる涙やうらの玉にまがはむ | 枇杷皇太后宮 |
| 1715 | まがふらん衣の玉に乱れつつなほまだ覚めぬ心ちこそすれ | 上東門院 |
| 1716 | 潮のまに四方のうらうら尋ぬれど今は我が身のいふかひもなし | 和泉式部 |
| 1718 | 都より雲の八重だつおく山の横川(よかは)の水はすみよかるらん | 天暦御歌 |
| 1719 | 百敷のうちのみ常に恋しくて雲の八重だつ山は住みうし | 如覚 |
| 1723 | 天つ風ふけゐの浦にゐるたづのなどか雲ゐに帰らざるべき | 藤原清正 |
| 1750 | 年月をいかで我が身におくりけむ昨日の人も今日はなき世に | 西行法師 |
| 1751 | 受けがたき人の姿にうかび出でてこりずや誰も又しづむべき | 西行法師 |
| 1754 | 何事を思ふ人ぞと人とはば答へぬさきに袖ぞぬるべき | 前大僧正慈円 |
| 1761 | 和歌の浦や沖つ潮合に浮び出づるあはれ我が身のよるべ知らせよ | 家隆朝臣 |
| 1762 | その山とちぎらぬ月も秋風もすすむる袖に露こぼれつつ | 家隆朝臣 |
| 1765 | 浮きしづみ来ん世はさてもいかにぞと心に問ひて答へかねぬる | 摂政太政大臣 |
| 1776 | 老らくの月日はいとどはやせ川かへらぬ波にぬるる袖かな | 大僧正覚弁 |
| 1782 | 思ふことなどとふ人のなかるらん仰(あふ)げば空に月ぞさやけき | 前大僧正慈円 |
| 1806 | 夕暮は雲のけしきを見るからに眺めじと思ふ心こそつけ | 和泉式部 |
| 1807 | 暮れぬめり幾日(いくか)をかくて過ぎぬらん入相の鐘のつくづくとして | 和泉式部 |
| 1808 | 待たれつる入相の鐘の音すなり明日もやあらば聞かむとすらん | 西行法師 |
| 1809 | 暁とつげの枕をそばだてて聞くも悲しき鐘の音かな | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1810 | 暁のゆふつけ鳥ぞあはれなる長き眠(ねぶ)りを思ふ枕に | 式子内親王 |
| 1812 | たらちねの諌めしものをつくづくと詠(なが)むるをだにとふ人もなし | 和泉式部 |
| 1815 | 昔だに昔と思ひしたらちねのなほ恋しきぞはかなかりける | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1816 | ささがにのいとかかりける身の程を思へば夢の心ちこそすれ | 俊頼朝臣 |
| 1825 | ひと方に思ひとりにし心にはなほ背かるる身をいかにせん | 前大僧正慈円 |
| 1826 | 何ゆゑに此の世をふかく厭ふぞと人の問へかしやすく答へん | 前大僧正慈円 |
| 1827 | 思ふべき我が後の世はあるかなきか無ければこそは此の世には住め | 前大僧正慈円 |
| 1831 | 何事にとまる心のありければ更にしもまた世の厭はしき | 西行法師 |
| 1832 | 昔より離れがたきはうき身かなかたみにしのぶ中ならねども | 入道前関白太政大臣 |
| 1838 | 数ならぬ身はなき物になしはてつ誰が為にかは世をも恨みん | 寂蓮法師 |
| 1841 | うき世をば出づる日ごとにいとへどもいつかは月のいる方をみん | 八条院高倉 |
| 1842 | なさけありし昔のみ猶しのばれて永らへまうき世にもふるかな | 西行法師 |
| 1843 | 永らへばまた此の頃やしのばれん憂しと見し世ぞ今は恋しき | 清輔朝臣 |
| 1847 | 暮るるまも待つべき世かはあだし野の末葉の露に嵐たつなり | 式子内親王 |
| 1850 | 秋風になびく浅茅の末ごとにおく白露のあはれ世の中 | 蝉丸 |
| 1851 | 世の中はとてもかくても同じこと宮もわら屋もはてしなければ | 蝉丸 |
| 1854 | 補陀落の南の峯に堂たてて今ぞさかえん北の藤浪 | 春日の榎本の明神 |
| 1855 | 夜や寒き衣やうすき片削ぎの行き合ひのまより霜や置くらん | 住吉の御歌 |
|
伊勢物語に、住吉に行幸の時、おほん神現形(げぎやう)し給ひて、としるせり |
||
| 1857 | むつまじと君はしら浪瑞垣の久しき世よりいはひそめてき | |
| 1861 | われたのむ人いたづらになしはてば又雲分けてのぼるばかりぞ | 賀茂の御歌 |
| 1870 | 宮人のすれる衣にゆふだすきかけて心を誰によすらん | 紀貫之 |
| 1871 | 神風や御裳濯(みもすそ)川のそのかみに契りしことの末をたがふな | 摂政太政大臣 |
| 1882 | 神風や五十鈴の川の宮柱いく千世すめとたてはじめけん | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1889 | 月さゆるみたらし川に影見えて氷にすれる山藍の袖 | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1898 | 春日野のおどろの道の埋れ水すゑだに神のしるしあらはせ | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1902 | 我がたのむ七(なな)の社(やしろ)のゆふだすきかけても六(むつ)の道にかへすな | 前大僧正慈円 |
| 1904 | もろ人のねがひをみつの浜風に心すずしき四手(しで)の音かな | 前大僧正慈円 |
| 1907 | 岩にむす苔ふみならす三熊野の山のかひある行末もがな | 太上天皇 |
| 1908 | 熊野川くだす早瀬の水馴棹(みなれざを)さすがみなれぬ浪の通ひ路 | 太上天皇 |
| 1916 | なほ頼めしめぢが原のさしも草われ世の中にあらん限りは | 清水観音御歌 |
| 1920 | 阿耨多羅(あのくたら)三藐(さんみやく)三菩提の仏たち我が立つ杣に冥加(みやうが)あらせたまへ | 伝教大師(最澄) |
| 1923 | 寂莫の苔のいはとのしづけきに涙の雨のふらぬ日ぞなき | 日蔵上人 |
| 1924 | 南無阿弥陀仏(ほとけ)の御手にかくる糸のをはり乱れぬ心ともがな | 法円上人 |
| 1925 | 我だにもまづ極楽にむまれなば知るも知らぬも皆むかへてん | 僧都源信 |
| 1931 | 願はくはしばし闇路にやすらひてかかげやせまし法(のり)の燈火 | 前大僧正慈円 |
| 1932 | 説く御法(みのり)菊の白露夜はおきてつとめて消えんことをしぞ思ふ | 前大僧正慈円 |
| 1933 | 極楽へまだ我が心行きつかずひつじの歩みしばしとどまれ | 前大僧正慈円 |
| 1935 | 奥山に独りうき世はさとりにき常なき色を風にながめて | 摂政太政大臣 |
| 1937 | 紫の雲路にさそふ琴の音にうき世をはらふ嶺の松風 | 寂蓮法師 |
| 摂政太政大臣家百首歌に、十楽の心をよみ侍りけるに、聖衆(しやうじゆ)来迎楽(らいがうらく) | ||
| 1951 | 道の辺の蛍ばかりをしるべにて独りぞ出づる夕闇の空 | 寂然法師 |
| 1955 | 今日過ぎぬ命もしかとおどろかす入相の鐘の声ぞ悲しき | 寂然法師 |
| 1957 | 背かずばいづれの世にかめぐり逢ひて思ひけりとも人に知られん | 寂然法師 |
| 1959 | 音にきく君がりいつかいきの松まつらんものを心づくしに | 寂然法師 |
| 1960 | 別れにしその面影の恋しきに夢にも見えよ山の端の月 | 寂然法師 |
| 1961 | わたつ海の深きに沈むいさりせでたもつかひある法を求めよ | 寂然法師 |
| 1962 | うき草の一葉なりとも磯がくれ思ひなかけそ沖つ白浪 | 寂然法師 |
| 1963 | さらぬだに重きがうへのさ夜衣わがつまならぬ妻な重ねそ | 寂然法師 |
| 1964 | 花の本露のなさけはほどもあらじ酔(ゑ)ひなすすめそ春の山風 | 寂然法師 |
| 1965 | うきもなほ昔のゆゑと思はずばいかに此の世を恨みはてまし | 二条院讃岐 |
| 1966 | わたすべき数もかぎらぬ橋柱いかにたてける誓ひなるらん | 皇太后宮大夫俊成 |
| 1969 | しづかなる暁ごとに見わたせばまだふかき夜の夢ぞ悲しき | 式子内親王 |
歌碑として十国峠の歌を載せていますが、歴史的に頼朝と政子や鎌倉幕府の系列を近場の韮山や鎌倉などを訪問してその都度歌を確認してきたが改めて実朝という人物と歌を簡単にマトメてみようと思います。なんかこれを抜きには中途半端な気がする。藤原定家に歌を教えてもらったらしい。正岡子規の所でも実朝の歌を取り上げてすばらしい歌人とのことで紹介してあった。28歳で暗殺された短い生涯を嘆いてもいた。
[没]承久1(1219).1.27. 鎌倉
鎌倉幕府第3代の将軍,歌人。父は第1代将軍頼朝。母は政子。幼名,千幡。建仁3 (1203) 年,外戚北条氏に廃された兄頼家に代って将軍となり,右大臣正二位にいたったが,鶴岡八幡宮の社頭で頼家の遺児公暁に殺された。渡宋を企てたこともあったが,果さなかった。京都の貴族文化,文学を愛し,坊門信清の娘を妻とした。早くから作歌に親しみ,家臣を通じて藤原定家の指導を受けた。定家の歌論書『近代秀歌』は実朝に進献されたものである。天性の歌人で,万葉風の作品は特にすぐれており,後世,賀茂真淵,正岡子規,斎藤茂吉らが激賞している。家集『金槐和歌集』。
以下の私のページも参考になりなりそう
鎌倉ぶらり 壽福寺 韮山史跡/ N124 源実朝 箱根(十国峠)
『金槐和歌集』(きんかいわかしゅう)
源実朝の家集(歌集)。略称で『金槐集』とも呼ばれる。
成立は藤原定家より相伝の『万葉集』を贈られた建暦3年(1213年)12月18日頃とする説が有力。全一巻、663首(貞亨本では719首)掲載されている。『金槐和歌集』の「金」とは鎌の偏を表し、「槐」は槐門(大臣の唐名)を表しているため、別名鎌倉右大臣家集といわれている。但し、実朝の大納言(亜槐)や大臣(内大臣、右大臣)叙任は建保6年1218年である。
昭和4年(1929年)に佐佐木信綱によって発見された定家所伝本と、貞享4年(1687年)に版行された貞享本の2系統が伝えられている。前者は自撰・他撰(定家による撰)両説あるが未詳。後者も、奥書に「柳営亜槐」による改編とあるが、「柳営亜槐(征夷大将軍と大納言)」が誰であるかは諸説ある。江戸時代の国学者賀茂真淵に称賛されて以来『万葉調』の歌人ということになっている源実朝の家集であるが、実際は万葉調の歌は少ない。所収歌の多くは古今調・新古今調の本歌取りを主としている。
構成
「春部」、「夏部」、「秋部」、「冬部」により構成される「巻之上」、「恋之部」である「巻之中」、「雑部」である「巻之下」により構成される。万葉調の写実的、思想的歌は「巻之下」に多い。
如何にその中の何首かを取り上げてみた
巻之上
春(以下、解釈は某 HP大和うた和歌 千人万首より抜粋)
今朝みれば山もかすみて久方の天の原より春は来にけり
梅が香を夢の枕にさそひきてさむる待ちける春の山風
水たまる池のつつみのさし柳この春雨にもえ出でにけり
木のもとに宿りをすれば片しきの我が衣手に花はちりつつ
春ふかみ花ちりかかる山の井はふるき清水にかはづなくなり
散りのこる岸の山吹春ふかみこの一枝をあはれといはなむ
夏
春すぎていくかもあらねど我がやどの池の藤波うつろひにけり
さみだれに夜のふけゆけば時鳥ひとり山辺を鳴きて過ぐなり
ほととぎす聞けどもあかず橘の花ちる里の五月雨のころ
昨日まで花の散るをぞ惜しみこし夢かうつつか夏も暮れにけり
秋
吹く風のすずしくもあるかおのづから山の蝉鳴きて秋は来にけり
おほかたに物思ふとしもなかりけりただ我がための秋の夕暮
天の原ふりさけみれば月きよみ秋の夜いたく更けにけるかな
ながめやる心もたえぬわたのはら八重のしほぢの秋の夕暮
【通釈】眺めやる心も断ち切れてしまった。秋の夕暮、大海原の、その限りない潮の流れを見ているうちに――。
月をのみあはれと思ふをさ夜ふけて深山がくれに鹿ぞ鳴くなる
【通釈】月ばかりを趣深いと思っていたところ、夜が更けて、山の奧深く鹿が鳴く。
冬
秋はいぬ風に木の葉は散りはてて山さびしかる冬は来にけり
もののふの矢並つくろふ
夕されば潮風さむし浪間より見ゆる小島に雪はふりつつ
ちぶさ吸ふまだいとけなきみどりごとともに泣きぬる年の暮かな
巻之中
恋
月影のそれかあらぬかかげろふのほのかに見えて雲がくれにし
わが恋は
【通釈】私の恋は、多くの島を飛び巡って、行く先もわからず干潟に鳴く浜千鳥――それと同じで、どちらへ行けばよいのかわからずに泣いているのだ。
巻之下
雑
湊風いたくな吹きそしながどり猪名の水うみ船とむるまで
猪名(ゐな) 摂津国の歌枕 しながどり 鳰(にほ)のこと。「猪名」の枕詞
旅をゆきし跡の宿守おのおのにわたくしあれや今朝はいまだ来ぬ
【通釈】私が旅をして来たあとの留守番の者たちは、それぞれに私事があるのだろうか、今朝はまだやって来ない。
箱根路を我が越えくれば伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ
わたつ海のなかにむかひて出づる湯のいづのお山とむべも言ひけり
伊豆の国や山の南に出づる湯のはやきは神のしるしなりけり
ながむれば吹く風すずし三輪の山杉の木ずゑを出づる月影
東路の関
【通釈】東国の出入口の関を守る神へのお供えとして、杉に矢を射立てる、足柄山よ。
杉に矢たつる 武士が戦勝を祈願して杉に矢を射立てる風習があった。今も各地に「矢立の杉」と伝わる樹が残っている。
かくてのみありてはかなき世の中を憂しとやいはむあはれとやいはむ
【通釈】このようにばかり、生きていても果敢ない世の中を、辛いと言おうか、いとしいと言おうか。
神といひ仏といふも世の中の人の心のほかのものかは
【通釈】神と言い、仏と言うのも、現世の人の心以外のものであろうか。
物いはぬ
時によりすぐれば民のなげきなり八大龍王雨やめたまへ
八大龍王(はちだいりうわう) 法華経序品に見える八体の龍神。雨を司る神と考えられた。
山はさけ海はあせなむ世なりとも君にふた心わがあらめやも
【通釈】山は裂け、海は干上がる世であろうとも、あなた様に二心を抱くようなことは決してありません。
出でていなば主なき宿となりぬとも軒端の梅よ春を忘るな
【通釈】私が出て行ったなら、たとえ主人のいない家となってしまうとしても、軒端の梅よ、春を忘れずに咲いてくれ。
平成30年7月末日 記
古の歌人で見落としていた人は、また知識として知らねばならぬ人はと思いつつ、やはり家持を取り上げなくてはと思う。万葉人の概要は把握しているつもりであり、学者でもなく歌の歴史を歩み、現在に至る歌人の心の移ろいを把握できればと思うが、万葉集のマトメ人と言われる人は省けまい。略歴を調べてるとかなり分量があり、簡潔なところをコピーする。その後は代表歌などを載せることにする。
『万葉集』末期の代表歌人、官人。旅人(たびと)の子。少年時の727年(神亀4)ごろ父に伴われ大宰府(だざいふ)で生活し、730年(天平2)帰京。737年ごろ内舎人(うどねり)。745年(天平17)従(じゅ)五位下。翌3月宮内少輔(くないのしょうふ)。7月越中守(えっちゅうのかみ)として赴任した。751年(天平勝宝3)少納言(しょうなごん)となって帰京。754年兵部(ひょうぶ)少輔。さらに兵部大輔、右中弁を歴任したが、758年(天平宝字2)因幡守(いなばのかみ)に左降された。以後、信部大輔(しんぶたいふ)、薩摩守(さつまのかみ)、大宰少弐(しょうに)などを歴任。長い地方生活を経て770年(宝亀1)6月民部少輔、9月左中弁兼中務(ちゅうむ)大輔、10月、21年ぶりで正五位下に昇叙した。諸官を歴任して781年(天応1)4月右京大夫(うきょうのたいふ)兼春宮(とうぐう)大夫となり、785年(延暦4)4月中納言従三位(じゅさんみ)兼春宮大夫陸奥按察使(みちのくのあんさつし)鎮守府将軍とみえ、同年8月没。没時はおそらく任地多賀城(宮城県多賀城市)にいたと思われる。年68または69歳。名門大伴家の家名を挽回(ばんかい)しようとして政争に巻き込まれることが多く、官人としては晩年近くまで不遇で、死後も謀反事件に連座して806年(大同1)まで官の籍を除名されていた。
作品は『万葉集』中もっとも多く、長歌46、短歌425(合作1首を含む)、旋頭歌(せどうか)1首、合計472首に上る。ほかに漢詩1首、詩序形式の書簡文などがある。作歌活動は、732年ごろから因幡守として赴任した翌年の759年までの28年間にわたるが、3期に区分される。
第1期は746年越中守となるまでの習作時代で、恋愛歌、自然詠が中心をなす。のちに妻となった坂上大嬢(さかのうえのおおいらつめ)をはじめ、笠女郎(かさのいらつめ)、紀女郎(きのいらつめ)らとの多彩な女性関係と、早くも後年の優美、繊細な自然把握がみられる。
第2期は越中守時代の5年間で、期間は短いが、望郷の念を底に秘めつつ、異境の風物に接し、下僚大伴池主(いけぬし)との親密な交遊を通し、さらには国守としての自覚にたって、精神的にもっとも充実した多作の時代である。
第3期は帰京後から因幡守となるまでで、作品数は少なく宴歌が多いが、万葉の叙情の深まった極致ともいうべき独自の歌境を樹立した。『万葉集』の編纂(へんさん)に大きく関与し、第3期の兵部少輔時代の防人歌(さきもりうた)の収集も彼の功績である。長い万葉和歌史を自覚的に受け止めて学ぶとともにこれを進め、比類のない優美・繊細な歌境を開拓するが、この美意識および自然観照の態度などは、平安時代和歌の先駆をなす点が少なくない。
代表歌
あとは某HPの「千人万首」より気に入った歌を載せることにする
春
うち
雪のうへに照れる
春の苑紅にほふ桃の花したでる道に出で立つ乙女
春まけて物悲しきに小夜更けて羽ぶき鳴く鴫誰が田にかすむ
春の日に張れる柳を取り持ちて見れば京の
春の野にあさる
春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影に鶯鳴くも
うらうらに照れる
見わたせば向かつ尾上の花にほひ照りて立てるは
夏
夏山の
青丹よし奈良の都は古りぬれどもと霍公鳥鳴かずあらなくに
行方なくありわたるとも霍公鳥鳴きし渡らばかくやしのはむ
藤なみの影成す海の底清みしづく石をも珠とぞ我が見る
秋
ひさかたの
雨晴れて清く照りたる此の
冬
沫雪の庭に降りしき寒き夜を手枕まかず一人かも寝む
この雪の
賀
あしひきの山の
離別、羇旅
あしひきの山の
秋風の末吹きなびく萩の花ともに
あゆの風いたく吹くらし奈呉の海人の釣する小舟榜ぎ隠る見ゆ
越の海の
雄神川紅にほふ
恋・相聞
振り
うつつには更にも
悲傷
秋さらば見つつ偲へと妹が植ゑし屋戸の撫子咲きにけるかも
うつせみの世は常なしと知るものを秋風寒み偲ひつるかも
あしひきの山さへ光り咲く花の散りぬるごとき我が王かも
雑
玉きはる命は知らず松が枝を結ぶ心は長くとそ思ふ
馬
うつりゆく時見るごとに心いたく昔の人し思ほゆるかも
初春の
付載 家持集・勅撰集より
桜花こだかき枝の空にのみ見つつや恋ひむ折るすべもなみ
行かむ人来む人しのべ春霞たつ田の山の初桜花
神なびの御室の山の葛かづらうら吹きかへす秋は来にけり
わが宿の尾花が末に白露のおきし日よりぞ秋風の吹く
かささぎの渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞ更けにける
あしびきの山の陰草むすびおきて恋ひやわたらむ逢ふよしをなみ
くしげなる鏡の山を越えゆかむ我は恋しき妹が夢みたり
平成30年8月末日記
この人物の評価の有無は近代にいろいろあるが当時の超一流の歌詠みを素通りすることはできないだろうと改めて取り上げてみました。
略歴
平安時代の歌人,三十六歌仙のひとり。望行の子。紀氏は本来武人の家系だが,貫之のころには多くの歌人を輩出,藤原敏行,兼覧王などが知られている。御書所預,内膳典膳,少内記,大内記,美濃介,右京亮,玄蕃頭,木工権頭などを歴任。従五位上。寛平年間(889~98)の是貞親王家歌合や寛平御時后宮歌合に出詠して歌界にデビュー。延喜5(905)年醍醐天皇の命を受け,友則らと共に最初の勅撰集『古今和歌集』を編纂するにおよんで,一躍歌壇的地位を築いた。この編纂作業では,わが国初の本格的歌論書ともいうべき仮名序を自ら草するなど,終始リーダーシップを発揮。また,集中第1位の102首もの自詠歌を選入して,理知的,分析的な古今歌風の形成に大きく関与した。このころから歌人としての声望はとみに高まり,以後,多くの権門貴紳から屏風歌制作の注文が相次いだ。屏風歌の数の多さは当時の一流歌人としての証であり,これらは晩年自ら編んだ『貫之集』の前半部に500首を超える一大屏風歌歌群となって残されている。 延長8(930)年,土佐守に任ぜられたが,赴任直前に醍醐天皇より命が下り,再び歌集を編むこととなった。『新撰和歌』4巻である。ただし,これは任地で編纂中に天皇が崩じたため,惜しくも勅撰集とはならなかった。ほかにも宇多法皇,藤原兼輔など貫之を主に支えていた人々が次々と他界し失意の内に任を終えた貫之は,承平4(934)年帰京の途に就く。この折の船旅を一行のさる女性に仮託して綴ったのが『土佐日記』であり,仮名で記された日記文学の創始として,のちの女流文学隆盛を招来するきっかけとなった。 貫之の業績は韻文,散文両分野にわたり真に多大なものがあるが,ことに国風文化の台頭期にあって,たえず文学上の新しい方法を模索し,開拓していったその精神は,大いに讃えられてよかろう。代表的詠歌に「桜散る木の下風は寒からで空に知られぬ雪ぞ降りけるなどがある。<参考文献>大岡信『紀貫之』,村瀬敏夫『紀貫之伝の研究』,長谷川政春『紀貫之論』
代表歌
散文作品としては『土佐日記』がある。日本の日記文学で完本として伝存するものとしては最古のものであり、その後の仮名日記文学や随筆、女流文学の発達に大きな影響を与えた。
春
袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ(古今2)
【通釈】夏に袖が濡れて手に掬った水が、冬の間に氷ったのを、春になった今日の風が解かしているだろうか。
春日野の若菜つみにや白妙の袖ふりはへて人のゆくらむ(古今22)
歌奉れとおほせられし時、よみて奉れる
【通釈】春日野の若菜を摘みにゆくのだろうか、真っ白な袖を目立つように打ち振って娘たちが歩いてゆく。
人はいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける(古今42)
【通釈】住む人はさあどうか、心は変ってしまったか。それは知らないけれども、古里では、花が昔のままの香に匂っている。人の心はうつろいやすいとしても、花は以前と変らぬ様で私を迎え入れてくれるのだ。
桜ちる
【通釈】桜が散る木の下を吹いてゆく風は寒くはなくて、天の与かり知らぬ雪が降っているのだ。
さくら花ちりぬる風のなごりには水なき空に波ぞたちける(古今89)
【通釈】風が吹き、桜の花が散ってしまった――その風が去って行ったあとのなごりには、水のない空に波が立つのだった。
夏
夏の夜のふすかとすれば
【通釈】夏の夜は、寝るか寝ないかのうちに、たちまち時鳥が鳴き、その一声に明けてゆく、しののめの空よ。
五月雨の空もとどろに
【通釈】さみだれの降る空もとどろくばかりに、時鳥は何が辛いというので夜ひたすら鳴くのだろうか。
みそぎする川の瀬見れば
【通釈】人々が夏越の祓えをしている川の浅瀬を見ると、美しい衣の紐を「結う」ではないが、夕暮になって、波が立っているのだった。
秋
川風の涼しくもあるかうち寄する波とともにや秋は立つらむ(古今170)
【通釈】川風が涼しく吹いていることよ。その風に立って打ち寄せる波と共に、秋は立つのだろうか。
朝戸あけてながめやすらむ
【通釈】朝戸を開けて、織女は眺めているのだろうか。昨夜、牽牛と満たされずに別れた空を慕いながら。
やどりせし人のかたみか藤袴わすられがたき香ににほひつつ(古今240)
【通釈】我が家に宿った人の残した形見か、ふじばかまの花は、忘れ難い香に匂い続けて…。
秋風の吹きにし日より音羽山峰のこずゑも色づきにけり(古今256)
【通釈】秋風が初めて吹いた日から、その音がしていた音羽山の峰の梢も、色づいたのだった。
白露も時雨もいたくもる山は下葉のこらず色づきにけり(古今260)
通釈】白露も時雨もひどく漏るという名の守(もる)山は、木立の下葉がすっかり色づいたのであった。
つねよりも照りまさるかな山の端の紅葉をわけて出づる月影(拾遺439)
【通釈】いつもよりひときわ照り輝いていることよ。山の端の紅葉を分けて昇る月の光は。
秋の菊にほふかぎりはかざしてむ花より先としらぬわが身を(古今276)
【通釈】秋の菊の花が咲き匂っている間はずっと挿頭(かざし)にしていよう。花が萎むのより先に死ぬかどうか、分からない我が身であるものを。
秋の月ひかりさやけみ紅葉ばのおつる影さへ見えわたるかな(後撰434)
【通釈】秋の月の光が鮮明なので、紅葉した葉の落ちる姿さえ隅々まで見えることよ。
夕づく夜をぐらの山に鳴く鹿の声のうちにや秋は暮るらむ(古今312)
【通釈】小暗い小倉山に鳴く鹿の声――この声のうちに、秋は暮れるのだろうか。
冬
かきくらし
【通釈】空を暗くして時雨の降る空を眺めながら、今頃散ってはいないかと思い遣るのだ、神奈備の森を。
思ひかね妹がりゆけば冬の夜の川風さむみ千鳥なくなり(拾遺224)
【通釈】恋しい思いに耐えかねて愛しい人の家へ向かって行くと、冬の夜の川風があまり寒いので、千鳥が鳴いている。
冬ごもり思ひかけぬを木の間より花とみるまで雪ぞふりける(古今331)
【通釈】冬籠りしていて、花など思いもかけなかったのに、木と木の間から、花かと思うほど雪が降っていた。
ふる雪を空に
【通釈】降る雪を、空に捧げ物として手向けたのだった。冬から春への境の節分に年が越えるので。
賀
春くれば宿にまづ咲く梅の花きみが
【通釈】春が来ると、真っ先に家の庭に咲く梅の花、これをあなたの千年の長寿を約束する挿頭と見るのです。
大原や
【通釈】大原の小塩山の小松の群生よ。早く木高くなれ。千年にわたって栄え繁った木蔭を見よう。
離別
白雲の八重にかさなる
【通釈】白雲が幾重にも重なるほど遠くにあっても、あなたを思っている人に対して心を隔てないでおくれ。
むすぶ手のしづくににごる山の井のあかでも人に別れぬるかな(古今404)
【通釈】掬い取る手のひらから落ちた雫に濁る、山清水――その閼伽(あか)とする清水ではないが、飽かずに人と別れてしまったことよ。
羇旅
都にて山の端に見し月なれど海より出でて海にこそ入れ(後撰1355)
【通釈】都では山の端に出入りするのを見た月だけれども、海から出て海に入るのだった。(土佐)
照る月のながるる見れば天の川いづる湊は海にぞありける(後撰1363)
【通釈】照る月が流れるのを見ると、天の川を出る河口は海なのであった。
恋
吉野川いはなみたかく行く水のはやくぞ人を思ひそめてし(古今471)
【通釈】吉野川の岩波を高く立ててゆく水が速く流れる――早くから、あの人を思い始めたことであったよ。
世の中はかくこそありけれ吹く風の目に見ぬ人も恋しかりけり(古今475)
【通釈】人の世とは、かくも不思議なものであったのだ。吹く風のように目に見えない人も恋しいのだった。
逢ふことは雲ゐはるかになる神の音に聞きつつ恋ひ渡るかな(古今482)
【通釈】逢うことは、雲の上のように及び難いことで、雷鳴の音のように遠く噂を聞きながら恋し続けることであるよ。
大空はくもらざりけり
【通釈】時雨の降る季節だというのに、空は曇らないのだった。初冬十月、時雨の降りそうな心地がするのは私ばかりであるよ。
夢路にも露やおくらむ夜もすがらかよへる袖のひちてかわかぬ(古今574)
【通釈】夢の中で辿る道の草にも露は置くのだろうか。一夜をかけて往き来する私の袖は濡れて乾くことがない。
五月山こずゑをたかみ時鳥なくねそらなる恋もするかな(古今579)
【通釈】五月の山は梢が高いので、ほととぎすの鳴く声は空高く聞こえる――そのように私もうわの空の恋をすることであるよ。
白玉と見えし涙も年ふればからくれなゐにうつろひにけり(古今599)
【通釈】初めは白玉と見えた私の涙も、年を経ると、紅の色に変わってしまったのだ。
手もふれで月日へにけるしら真弓おきふしよるはいこそ寝られね(古今605)
【通釈】手も触れずに、長い歳月を経た白真弓――弓を起こしたり臥したりすると言うが、私は起きたりまた横になったりして、夜はろくに眠れないのだ。
【語釈】◇しら真弓(まゆみ) 白い檀の木で作った弓。「知らず」(あの人はこの思いを知らない)の意を響かせるか。◇おきふしよるは 恋に悶え苦しみ、起きたり横になったりして、夜は。起き・伏し・寄る(すべて弓を使う際の動作にかかわる語)を掛ける。◇いこそ寝られね 「い」に、これも弓の縁語「射(い)」を掛ける。
いにしへになほ立ちかへる心かな恋しきことに物忘れせで(古今734)
【通釈】昔の思いにまた立ち戻る心であるよ。恋しいことについては、うっかり忘れるということをしないで。
玉の緒のたえてみじかき命もて年月ながき恋もするかな(後撰646)
【通釈】すぐに玉の緒が絶えてしまって、本当に短い人の命――そんなはかない命でもって、長い歳月に渡る恋をすることよ。
おほかたの我が身ひとつの憂きからになべての世をも恨みつるかな(拾遺953)
【通釈】おおよそのことは私一身の思うにまかせない憂鬱が原因であるのに、おしなべて世の中のせいにして恨んでしまうことよ。
来ぬ人を下に待ちつつ久方の月をあはれと言はぬ夜ぞなき(拾遺1195)
【通釈】訪れない人を心中に待ちながら、月をすばらしいと賞美しない夜とてない。
哀傷
明日知らぬ我が身と思へど暮れぬまの今日は人こそかなしかりけれ(古今838)
【通釈】(紀友則が身まかりにける時よめる)私自身、明日の命も分からない身だと思うけれども、日が暮れるまでに残された今日という日のわずかな間は、人のことが悲しいのであった。
ほととぎす今朝鳴く声におどろけば君に別れし時にぞありける(古今849)
【通釈】時鳥が今朝鳴く声にはっと気がつけば、昨年あなたと死に別れたのと同じ時節なのだった。
君まさで煙たえにし塩釜のうらさびしくも見え渡るかな(古今852)
【通釈】あなたがいらっしゃらなくて、煙が絶えてしまった塩釜の浦――見渡せば、すっかりうら寂しく感じられることよ。
雑
大井川かはべの松にこととはむかかる
【通釈】大堰川の川辺の松に問うてみよう。このように盛大な行幸は昔もあったかと。
またも来む時ぞと思へどたのまれぬわが身にしあればをしき春かな(後撰146)
【通釈】また行こうと思っていた時なのですが、頼みにならない私の身体ですので、再び巡って来る季節とは言え、悔いの残る春ですことよ。
手にむすぶ水にやどれる月影のあるかなきかの世にこそありけれ(拾遺1322)
【通釈】手に掬った水に映っている月の光のように、あるのかないのか、定かでない、はかない生であったことよ。
平成30年8月末 記
「其の歌、古今新古今の陳套に堕ちず、真淵景樹の窠臼に陥らず、万葉を学んで万葉を脱し、瑣事俗事を捕へ来りて、縦横に馳駆する処、却つて高雅蒼老些の俗気を帯びず」(正岡子規「曙覧の話」)。
「楽しみは・・・・」個性的で気になる歌人 江戸末期の歌人として取り上げました。
江戸末期の歌人。通称五三郎,姓名ははじめ正玄尚事。号は志濃夫廼舎,黄金舎など。越前国福井石場町に生まれる。父は紙商正玄五郎右衛門,母は山本平三郎の娘都留子。弘化1(1844)年以前に正玄姓を橘に,安政1(1854)年に名を曙覧に改名した。曙覧は橘の朱い実からきている。2歳にして母に,15歳にして父に死別,仏門に入ろうとして越前国南条郡妙泰寺の僧明導に仏学を学んだがまもなく実家に戻り天保3(1832)年に結婚。同10年家業を異母弟に譲り,15年,飛騨の田中大秀に入門し,1カ月滞在した。弘化3年,全家財を異母弟に譲り,足羽山に黄金舎を結んで教授で生計を立てたが窮乏生活は免れなかった。やがて福井藩士中根雪江に見いだされ,藩主松平慶永(春岳)の知るところとなり,志濃夫廼舎の号を授かるなど寵愛を受ける。『万葉集』の素朴さを重んじ,素材の枠を超えて自由に感情を表現することを主張し,のちに正岡子規にも絶賛された。国粋主義を鼓吹する和歌も残している。家集に『志濃夫廼舎家集』(1878)がある
春
春にあけて
【通釈】春になり年が明けて、真っ先にひらいて見る書も、「天地の始めの時…」と読み出すのであるよ。
【通釈】正月になる、するとすぐ花の祝福を受けて、今年も皆で笑い合っている家。
春かけて門田の
【通釈】秋から春にかけて門田のおもてに群れていた雁――それが一羽も見えなくなる日は寂しいことである。
すくすくと生ひたつ麦に腹すりて燕飛びくる春の
【通釈】すくすくと成長して立っている麦に腹をこするようにして燕が飛んで来る、春の山畑よ。
夏
若葉さすころはいづこの山見ても何の木見ても麗しきかな(春明艸524)
【通釈】若葉が萌え出る頃は、どの山を見ても、何の木を見ても、美しいことよ。
【通釈】梅の実が熟(う)む季節――雨に倦(う)んで、昼でさえ寝ていたいと思う五月に早なってしまったのだ。
【通釈】雨を憚って家に籠るうち何日も経って、久しぶりに網戸を開けて見ると、庭に梅の実が三つ四つ落ちている。
たたまりて
【通釈】畳まっていて、蕊をまだ見せない花びら――その濡れたような色が清らかである、朝露のついた蓮の花は。
秋
【通釈】稲子麻呂がうるさく現われて飛ぶ秋の日――その天候を喜んで、農夫が豆の莢を打っている。
人は皆見さして寝たる
【通釈】人は皆見るのを途中でやめて寝てしまった夜中の月――その月明かりを窓に入れて独りひそかに眺めるのである。
【通釈】妻と寝る床――常世を離れて、この明け方、鳴いてやって来たのだろう初雁の声よ。
旅ごろもうべこそさゆれ乗る駒の鞍の高嶺にみ雪つもれり(松籟艸5)
【通釈】旅中の衣服が道理で冷えたはずだ。乗鞍の高嶺に雪が積もっている。
冬
枯れのこる茎うす赤き
【通釈】犬蓼の枯れ残っている薄赤い茎が腹ばうように生えている庭に霜が降りているのだった。
ふたりとはまだ人も見ず雪しづれ朝日におつる杉のした道(松籟艸215)
【通釈】歩いている人はまだ二人と見かけない。雪が融けて朝日の中を落ちる、杉の下をゆく道では。
【通釈】勇ましい侠士が捕えた虎――その血の飛び散ったのが門前の雪を赤く染めている。
悲傷
きのふまで吾が衣手にとりすがり父よ父よといひてしものを(松籟艸20)
【通釈】つい昨日まで私の着物の袖に取り付いて離れず、父よ父よと言っていたのに。
足羽山の黄金舎に住んでいた天保十五年(1844)春、四歳の一人娘健女を痘瘡で亡くした時の歌。
今も世にいまされざらむ
【通釈】今でも生きておられないような年齢でもないのに、ああ父はこの世になく、私には親がない。
亡き母をしたひよわりて寝たる児の顔見るばかり憂きことはあらじ(松籟艸53)
【通釈】亡き母を慕うあまり疲れ切って寝た子――その顔を見る時ほど辛いことはあるまい。同国の漢学者であり親友であった越智通世の妻が亡くなった時、弔問しての詠
雑
あるじはと人もし問はば軒の松あらしといひて吹きかへしてよ(松籟艸1)
【通釈】主人はいるかと人がもし問うたなら、軒の松よ、おまえに吹きつける「あらし」ではないが、「あらじ(いないでしょう)」と言ってその客を吹き帰してくれよ。
なかなかに思へばやすき身なりけり世にひろはれぬ峰のおち栗(松籟艸17)
【通釈】考えてみると、かえって気安い身であった。世間から捨てて顧みられない、峰の落栗のような我が身は。
抜くからに身をさむくする秋の霜こころにしみてうれしかりけり(松籟艸22)
【通釈】抜くやいなや、身の毛もよだつような刀――そんな刀をもらって、心に浸み透るばかりに嬉しいのだった。
夕貌の花しらじらと咲きめぐる
【通釈】夕顔の花が周りを白々と咲きめぐる粗末な百姓家の庭先で馬を洗っている。
綿いりの縫目に
【通釈】綿入りの着物の縫い目に頭を差し入れて、縮こまっている蝨よ、おまえたちは私の仲間だ。
とくとくと垂りくる酒のなりひさごうれしき音をさするものかな(松籟艸123)
【通釈】とくとくと酒が流れ落ちて来る瓢箪、嬉しい音をたてるものである。
【通釈】暖める酒の匂いに心惹かれて、今日も家への帰り道を夕暮にしてしまった。
【通釈】鎔けると灰と分離して、くっきりと固まって白銀の玉が残る。
眉白き翁
【通釈】眉の白い老人が家から出て来ると、千年も経つような門先の山松の木を撫でつつ褒めることよ。
なにをして白髪おひつつ老いけむとかひなき我をいかりたまはむ(襁褓艸293)
【通釈】何をして白髪が生えるまで年老いたのかと、父母は腑甲斐ない私を怒っておられるだろう。父の三十七年忌と母の五十年忌を執り行った年の感慨。曙覧五十二歳。
撫でやまぬ火桶のいろにならひもてみがきをゆかむ歌の上をも(襁褓艸341)
【通釈】いつも撫でて離さない火桶――その艶光りする色に見習って、私の歌についても弛まず磨きをかけてゆこう。
【通釈】水車が衣服を縫う時代となってしまった。やがて岩や木立が物を言い始めるだろう。
影垂るる星にせまりて薄黒き色たたなはるおぼろ夜の山(春明艸471)
【通釈】光が垂れる星にぎりぎりまで近づくようにして、薄黒い色が重なり連なる、薄暗い夜の山よ。
吾が歌をよろこび涙こぼすらむ鬼のなく声する夜の窓(春明艸517)
【通釈】私の歌を喜んで涙をこぼしているのだろう。鬼の泣く声が夜の窓に聞こえる。
【通釈】灯し火のもとに毎夜毎夜来るがよい、鬼よ。私が秘め隠している歌のある限りを聞かせよう。
独楽吟
たのしみは
【通釈】楽しみは、草庵に茣蓙を敷いて、独りで心を静めている時である。
たのしみは
【通釈】楽しみは、妻と子と仲良く集まって、頭を並べて食事をする時である。
たのしみは物をかかせて善き
【通釈】楽しみは、人が私に物を書かせて、高い代金を惜しげもなく呉れた時である。
たのしみは昼寝せしまに庭ぬらしふりたる雨をさめてしる時(春明艸577)
【通釈】楽しみは、昼寝していた間に庭を濡らして降った雨を、目が覚めて知った時である。
たのしみはわらは墨するかたはらに筆の運びを思ひをる時(春明艸594)
【通釈】楽しみは、子供が墨を磨る傍らで、筆の運びを思い巡らしている時である。
【通釈】幽冥界に入ろうとも、私は現実界にある時と変わらずに歌を詠むだけである。
歌よみて游ぶ
【通釈】私はただ歌を詠んで遊ぶよりほかすることはない。天にあろうとも、地にあろうとも。
人臭き世にはおかざる我がこころすみかを問はば山のしら雲(君来艸717)
【通釈】人間臭いこの世には置かない私の心――住処を問うならば、山の白雲と答えよう。
【通釈】現世の人の命とは、この宇宙との間に何の隔てもない魂を、しばらく体が包んでいるだけなのである。
物皆を立つ雲霧と思へれば見る目嗅ぐ鼻
【通釈】万物をすべて雲や霧のようなものと思っていると、物を見る自分の目も、物を嗅ぐ自分の鼻も、死後の世にあるのと同じことである。
【通釈】瑞々しい緑の山が垣根のように巡っている山の榊葉の繁み――その奧に私の魂が籠っている。
肝冷す腰の
【通釈】心肝を寒からしめる、腰の剣よ――私の魂は、山の松の根元に埋め鎮めてしまった。
【通釈】百年も千年もの間、我が国はさながら曇天続きであったが、ようやく空が晴れてゆく気運になったのであった。
あたらしくなる
【通釈】一新されるこの世を予想しただろうか。私の目が暗くならないうちに、その様を見ようとは。慶応三年(1876)、大政奉還・王政復古が成り、政道が天皇親政へと移り変わってゆくのを「いさましう」思って詠んだ歌。
友ほしく何おもひけむ歌といひ
【通釈】友がほしいと何を思ったのだろう。歌といい書物という友がある私であるのに。
【通釈】天下を清らかに一掃して、上古の御政道に復帰することを喜びなさい。
通釈】器に満たした水の中で魚は鰭を振らせて泳ぎ、海や川を見ない私の目を喜ばせてくれる。
窓の月浮べる水に魚躍るわが枕辺の広沢の池(福寿艸849)
【通釈】窓から差し込む月の光を浮かべる水に魚が躍る。私の枕のほとりの広沢の池で。
ひれはねて小さき魚のとぶ音に
【通釈】鰭をはねて小さい魚の跳ぶ音に、眠るともなく眠っている目が自然と開けられる。
雲ならで通はぬ峰の石かげに神世のにほひ吐く草の華(拾遺歌)
【通釈】雲以外には通うもののない高嶺の石の陰で、神代の匂いを吐いている草の花よ。
【鑑賞】「『神代のにほひ吐く草の花』といへる歌は彼の神明的理想を現したるものにて、この種の思想が日本の歌人に乏しかりしは論を竢(ま)たず。(曙覧の理想も常にこの極処に触れしにあらず)」(子規前掲書)。
「俗塵を超絶した白雲の底に咲いて、神代さながらの姿に寂しく嘯く一茎の花は、まさに孤高な彼の生涯の象徴でなくてはならぬ」(藤井乙男『橘曙覧歌集』解説)。
独楽吟 全文
元治元年(1864)、53歳ころの作品。極貧ながらも、日常の些細な出来事に楽しみを求め、その喜びを感動的に詠み上げている。明治になってからは正岡子規に絶賛され、斎藤茂吉などにも多大な影響を与えた。 平成6年(1994)6月13日、クリントン米大統領が、天皇・皇后両陛下の訪米歓迎式典において『独楽吟』のなかの一首、「たのしみは朝おきいでて昨日まで無かりし花の咲ける見る時」を引用、再び注目されるようになった。
気になる歌
たのしみは妻子(めこ)むつまじくうちつどひ頭(かしら)ならべて物をくふ時
たのしみはまれに魚煮て兒等(こら)皆がうましうましといひて食ふ時
たのしみは朝おきいでゝ昨日まで無(なか)りし花の咲ける見る時
たのしみは庭にうゑたる春秋の花のさかりにあへる時々
たのしみは心にうかぶはかなごと思ひつゞけて煙草(たばこ)すふとき
たのしみは紙をひろげてとる筆の思ひの外に能くかけし時
たのしみはそゞろ讀(よみ)ゆく書(ふみ)の中に我とひとしき人をみし時
たのしみは心をおかぬ友どちと笑ひかたりて腹をよるとき
| たのしみは草のいほりの筵(むしろ)敷(しき)ひとりこゝろを靜めをるとき
たのしみはすびつのもとにうち倒れゆすり起(おこ)すも知らで寝し時 たのしみは珍しき書(ふみ)人にかり始め一ひらひろげたる時 たのしみは紙をひろげてとる筆の思ひの外に能くかけし時 たのしみは百日(ももか)ひねれど成らぬ歌のふとおもしろく出(いで)きぬる時 たのしみは妻子(めこ)むつまじくうちつどひ頭(かしら)ならべて物をくふ時 たのしみは物をかゝせて善き價惜(をし)みげもなく人のくれし時 たのしみは空暖(あたた)かにうち晴(はれ)し春秋の日に出でありく時 たのしみは朝おきいでゝ昨日まで無(なか)りし花の咲ける見る時 たのしみは心にうかぶはかなごと思ひつゞけて煙草(たばこ)すふとき たのしみは尋常(よのつね)ならぬ書(ふみ)に畫(ゑ)にうちひろげつゝ見もてゆく時 たのしみは常に見なれぬ鳥の來て軒遠からぬ樹に鳴(なき)しとき たのしみはあき米櫃に米いでき今一月はよしといふとき たのしみは物識人(ものしりびと)に稀にあひて古(いに)しへ今を語りあふとき たのしみは門(かど)賣りありく魚買(かひ)て煮(に)る鐺(なべ)の香を鼻に嗅ぐ時 たのしみはまれに魚煮て兒等(こら)皆がうましうましといひて食ふ時たのしみはそゞろ讀(よみ)ゆく書(ふみ)の中に我とひとしき人をみし時 たのしみは雪ふるよさり酒の糟あぶりて食(くひ)て火にあたる時 たのしみは書よみ倦(うめ)るをりしもあれ聲知る人の門たゝく時 たのしみは世に解(とき)がたくする書の心をひとりさとり得し時 たのしみは錢なくなりてわびをるに人の來(きた)りて錢くれし時 たのしみは炭さしすてゝおきし火の紅(あか)くなりきて湯の煮(にゆ)る時 たのしみは心をおかぬ友どちと笑ひかたりて腹をよるとき たのしみは晝寝せしまに庭ぬらしふりたる雨をさめてしる時 たのしみは晝寝目ざむる枕べにことことと湯の煮(にえ)てある時 たのしみは湯わかしわかし埋火(うづみび)を中にさし置(おき)て人とかたる時 たのしみはとぼしきまゝに人集め酒飲め物を食へといふ時 たのしみは客人(まらうど)えたる折しもあれ瓢(ひさご)に酒のありあへる時 たのしみは家内(やうち)五人(いつたり)五たりが風だにひかでありあへる時 たのしみは機(はた)おりたてゝ新しきころもを縫(ぬひ)て妻が着する時 たのしみは三人の兒どもすくすくと大きくなれる姿みる時 たのしみは人も訪ひこず事もなく心をいれて書(ふみ)を見る時 たのしみは明日物くるといふ占(うら)を咲くともし火の花にみる時 たのしみは木芽(きのめ)煮(にや)して大きなる饅頭(まんぢゆう)を一つほゝばりしとき たのしみはつねに好める燒豆腐うまく煮(に)たてゝ食(くは)せけるとき たのしみはたのむをよびて門(かど)あけて物もて來つる使(つかひ)えし時 たのしみは小豆の飯の冷(ひえ)たるを茶漬(ちやづけ)てふ物になしてくふ時 たのしみはいやなる人の來たりしが長くもをらでかへりけるとき たのしみは田づらに行(ゆき)しわらは等が耒(すき)鍬(くは)とりて歸りくる時 たのしみは衾(ふすま)かづきて物がたりいひをるうちに寝入(ねいり)たるとき たのしみはわらは墨するかたはらに筆の運びを思ひをる時 たのしみは好き筆をえて先(まづ)水にひたしねぶりて試(こころみ)るとき たのしみは庭にうゑたる春秋の花のさかりにあへる時々 たのしみはほしかりし物錢ぶくろうちかたぶけてかひえたるとき たのしみは神の御國の民として神の敎(をしへ)をふかくおもふとき たのしみは戎夷(えみし)よろこぶ世の中に皇國(みくに)忘れぬ人を見るとき たのしみは鈴屋大人(すすのやうし)の後(のち)に生れその御諭(みさとし)をうくる思ふ時 たのしみは數ある書(ふみ)を辛くしてうつし竟(をへ)つゝとぢて見るとき たのしみは野寺山里日をくらしやどれといはれやどりけるとき たのしみは野山のさとに人遇(あひ)て我を見しりてあるじするとき たのしみはふと見てほしくおもふ物辛くはかりて手にいれしとき
|
以前よりちょくちょく目にした歌人であるが、正岡子規を知れば改めてメモすることもないと思っていた。しかし子規の後の根岸短歌会の機関誌『馬酔木』など『アララギ』の基盤を作り更新の育成にあたったという。
『短歌の生命は刹那の感動の直接的な表現「叫び」から起こる。情緒の揺れが歌となる』と論じている。
歌とは何かと以前よりの疑問や課題の一端を垣間見れそうな気がしてここに取り上げてみたい。
以下の歌は某HPより抜粋して載せました。枕詞など、万葉調の調べがあちらこちらに見受けられる。
牛飼が歌よむ時に世のなかの新しき歌大いにおこる
牛乳販売業をしていた自分を誇張して「牛飼」と古風にいったところ。卑しい職業とされた「牛飼」と優雅なものとされた「和歌」とを対比した
水害の思いと歌を
臆病者というのは、勇気の無い
(水害雑録より)
うからやから皆にがしやりて独居(ひとりゐ)る水(み)づく庵(いほり)に鳴くきりぎりす
牀(ゆか)のうへ水こえたれば夜もすがら屋根の裏べにこほろぎの鳴く
くまも落ちず家内(やぬち)は水に浸ればか板戸によりてこほろぎの鳴く
只ひとり水(み)づく荒屋(あれや)に居残りて鳴くこほろぎに耳かたむけぬ
牀(ゆか)の上に牀をつくりて水づく屋にひとりし居ればこほろぎのなく
ぬば玉のさ夜はくだちて水づく屋の荒屋さびしきこほろぎのこゑ
物かしぐかまども水にひたされて家(や)ぬち冷(ひやや)かにこほろぎのなく
まれまれにそともに人の水わたる水音(みのと)きこえて夜はくだちゆく
さ夜ふけて訪(と)ひよる人の水音に軒のこほろぎ声なきやみぬ
水づく里人の音(と)もせずさ夜ふけて唯こほろぎの鳴きさぶるかも
花ちらふ隅田(すだ)の河原の寺島に雨ふりくれて蛙(かはづ)なくなり
遠人も袖ぬれきつつ春雨のさくらの宿に茶の遊びすも
一しきり渡らふ風は春雨に千垂(ちたり)の花の露ゆりおとす
花ごとに露の白玉ふふみたるくはし桜に夕日さし来(く)も
亀井戸の藤も終りと雨の日をからかささしてひとり見に来(こ)し
池水は濁りににごり藤なみの影もうつらず雨ふりしきる
しきたへの枕によりて病み臥せる君が面かげ眼を去らず見ゆ 子規 子百日忌
をみなども朝ゆふいでて米あらふ背戸川岸の秋海棠の花 明 治三十七年
あからひく朝日おしてる花原の園のまほらに蜻蛉(あきつ)むれ飛ぶ
秋草のいづれはあれど露霜に痩せし野菊の花をあはれむ
青苔に花ちる庭におりあそび雀の子二つ朝の静けさ 明治三十八年
垣外田(かきつだ)の蓮の広田を飛び越えて庭の槐(えんじゆ)に来鳴く葦切(よしきり)
秋立つとおもふばかりをわが宿の垣の野菊は早咲きにけり
九十九里の磯のたひらは天地(あめつち)の四方の寄合に雲たむろせり 明治四十年
ひむがしの沖つ薄雲いり日うけ下辺(したべ)の朱(あけ)に海暮れかへる
子規先 生の忌日
桜ちる月の上野をゆきかへり恋ひ通ひしも六とせ経にけり
明治四 十一年
天地のめぐみのままにあり経れば月日楽しく老も知らずも
恋の籬
やりがてに下思ふこころおし隠し男さびして今悔いにけり
片時も離れがてにし思ひつつのどに行き来(こ)と何に云ひけむ
わがこころ虚(から)にしあれや書(ふみ)読むと眼は落ちず妹(いも)が居らねば
軒の端の梅の下枝(しづえ)の花遠みいたも寂しも吾がひとり居り
健男(ますらを)が妻をいつはると思へやも里に一日(ひとひ)を否といひかねつ
朝日さす窓の障子(さうじ)の明らさまに堪へずよ妹(いも)と云はばよけむを
母が云へば一夜すべなし明日来むと笑みて乞ひけむわが心知り
人の住む国辺を出でて白波が大地両分(ふたわ)けしはてに来にけり 明治四十二年
天雲(あまぐも)のおほへる下の陸(くが)ひろら海広らなる涯に立つ吾れは
天地(あめつち)の四方(よも)の寄合を垣にせる九十九里の浜に玉拾ひ居り
白波やいや遠白に天雲に末辺(すゑべ)こもれり日もかすみつつ
はしけやし我が見に来れば産屋戸に迎へ起ち笑む細り妻あはれ
明治 四十三年
産屋(うぶや)住みけながき妻が面(おも)痩せのすがすがしきに恋ひ返りすも
産屋髪仮にゆひ垂れ胸広(むなひろ)に吾児掻きいだく若き母を実(さね)
我が命
今の我れに偽ることを許さずば我が霊(たま)の緒は直(すぐ)にも絶ゆべし
苦しくも命ほりつつ世の人の許さぬ罪を悔ゆる瀬もなし
生きてあらむ命の道に迷ひつつ偽るすらも人は許さず
黒髪
世に薄きえにし悲しみ相歎き一夜泣かむと雨の日を来し
日暮るる軒端のしげり闇をつつみかそけき雨のおとをもらすも
ぬば玉のはしき黒髪しかすがにおもひ千筋(ちすじ)にさゆる黒髪
花と煙
富士見野のちぐさの秋を雲とぢて雨寒かりしゆふべなりけり
諏訪の神のみすゑの子等と秋深き富士見野の花にいにしへ語るも
富士見野を汽車の煙の朝なづみ我が裳裾辺(もすそべ)に花は露けく
招魂歌
いきの緒のねをいぶかしみ耳寄せて我が聞けるとにいきのねはなし
かすかなる息のかよひも無くなりてむくろ悲しく永劫(とは)の寂(しづ)まり
よわよわしくうすき光の汝(な)がみたま幽かに物に触れて消(け)にけり
曼珠沙華
曼珠沙華ひたくれなゐに咲き騒(そ)めく野を朗かに秋の風吹く
ほろびの光り
おりたちて今朝の寒さを驚きぬ露しとしとと柿の落葉深く
1912年(大正元)年11月「アララギ」に発表された。この歌を冒頭にした一連五首は、伊藤佐千男晩年の絶唱と言われる。この翌年には脳貧血で五十年の生涯を閉じることになる。
静なる家
おとろへし蝿の一つが力なく障子に這ひて日はしづかなり
死にたるとおもへる蝿のはたき見れば畳に落ちて猶うごめくも
厠(かはや)に来て静なる日と思ふとき蚊の一つ飛ぶに心とまりぬ
南房総の春
九十九里の波の遠音(とほと)や下り立てば寒き庭にも梅咲きにけり
春早き南上総(みなみかづさ)の旅やどり梅をたづねて磯に出にけり
月寒き梅の軒端にわがこころいやさや澄みて人の恋(こほ)しも
ゆづり葉の若葉
世にあらむ生きのたづきのひまをもとめ雨の青葉に一日(ひとひ)こもれり
ゆづり葉の葉ひろ青葉に雨そそぎ栄ゆるみどり庭に足らへり
わかわかしき青葉の色の雨に濡れて色よき見つつ我を忘るも
2021年8月18日記
近代短歌を正岡子規、伊藤左千夫、斎藤茂吉などを取り上げたが島木赤彦の存在は整理しておく必要があると思う。コロナ禍の自宅待機時間を利用してまとめてみました。
| 年号 | 年齢 | できごと | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1876明9 | 生誕 | 12月17日上諏訪村角間「塚原浅茅・さい」の4男 浅茅は神官,後に豊平村で教員。下古田にも赤彦生誕地碑 |
神風連の乱 |
| 1885明18 | 9歳 | 母さい4月・弟文夫6月死去。翌年、父みを(藤森)と再婚 | 84秩父事件 |
| 1890明23 | 14歳 | 諏訪高等小学校卒業。泉野小学校傭教員 | 第1回帝国議会 |
| 1894明27 | 18歳 | 長野県尋常師範学校入学。「少年文庫」等に新体詩、和歌を投稿 | 日清戦争 |
| 1897明30 | 21歳 | 下諏訪町久保田政信の養嗣子となり長女うた(1877-1902)と結婚、仮祝言 | 足尾鉱毒 |
| 1898明31 | 22歳 | 師範学校卒業。北安曇郡池田尋常高等小学校訓導。 3/29久保田家で結婚披露宴 |
|
| 1900明33 | 24歳 | 長男政彦誕生。新聞「日本」短歌1首入選。 玉川尋常高等小学校に転任。宿直室「禰牟庵」で教育・作歌等を論じる |
北清事変 治安警察法 |
| 1901明34 | 25歳 | 諏訪文学、諏訪青年の短歌選者となる。4月、長女たけ生後2週間で夭折。 | |
| 1902明35 | 26歳 | 1月、出産後体調不良だった妻死去。7月義妹ふじの(1886-1965)と結婚。 玉川村の歌作詞 |
|
| 1903明36 | 27歳 | 次女初瀬誕生。木外らと「氷むろ」(後に氷牟呂)創刊 | |
| 1904明37 | 28歳 | 高島小学校に転任。11月伊藤左千夫を諏訪に迎え初対面 | 日露戦争 |
| 1908明41 | 32歳 | 3月教職を辞め養鶏。年末養鶏業不振のため教職復帰を図る | |
| 1909明42 | 33歳 | 3月、東築摩郡広丘尋常高等小学校校長。中原静子も赴任 氷牟呂は、アララギと合併 |
新聞紙法 |
| 1910明43 | 34歳 | アララギ信州号を編集 | 韓国併合 大逆事件 |
| 1911明44 | 35歳 | 4月、諏訪郡玉川尋常高等小学校校長。 | 関税自主権 青鞜社 |
| 1912明45 | 36歳 | 6月、諏訪郡視学。 | 中華民国建国 |
| 1913大2 | 37歳 | 7月、中村憲吉と合著歌集,第1歌集「馬鈴薯の花」東雲堂書店刊。 筆名久保田柿人。以降島木赤彦。左千夫の死を斎藤茂吉より知らされる。 |
芸術座 |
| 1914大3 | 38歳 | 視学退職。単身上京アララギ再建を。私立淑徳高等女学校非常勤講師。 | 第1次世界大戦 |
| 1915大4 | 39歳 | アララギ編集兼発行人。第2歌集「切火」アララギ発行所刊 | 対華21条要求 |
| 1916大5 | 40歳 | 万葉会を起こし諏訪、長野で講義 | |
| 1917大6 | 41歳 | 東京雑司が谷に妻子と同居。「信濃教育」編集主任。長男政彦急逝 | ロシア革命 |
| 1920大9 | 44歳 | 「東京朝日新聞」歌壇選者(-1923)。第3歌集「氷魚」岩波書店刊 | 世界恐慌 |
| 1921大10 | 45歳 | 斎藤茂吉渡欧送別歌会/上諏訪温泉寺。 赤彦・憲吉互選歌集「島記赤彦選集」「中村憲吉選集」 |
|
| 1922大11 | 46歳 | 「赤彦童謡集」古今書院刊。「万葉集燈」 | 全国水平社 |
| 1923大12 | 47歳 | アララギ震災報告号を上諏訪で発行。南満州鉄道招請で満州各地講演。 「第2赤彦童謡集」古今書院刊。 |
|
| 1924大13 | 48歳 | 「歌道小見」岩波書店刊。第4歌集「太虚集」古今書院刊 | |
| 1925大14 | 49歳 | 自選歌集「十年」改造社刊。「万葉集の鑑賞及び其批評(前編)」岩波書店刊 | 治安維持法 |
| 1926大15 | 50歳 | 3/27柿蔭山房で死去。胃癌。49歳3カ月。戒名:俊明院道誉浄行赤彦居士 6月「第3赤彦童謡集」古今書院、7月第5歌集「柿蔭集」岩波書店刊、 10月「山房漫語」古今書院刊 |
|
| 年号 | 年齢 | できごと | 備考 |
主な歌集に「馬鈴薯の歌」「切火」「永魚」「太虚集」「柿蔭集」がある
作歌は「鍛錬道」であると言い、その目ざすところは「幽寂境」「寂寥相」だ、と言います。短歌は遊びではない。勉強し、研究し、きびしく追求する世界。彼がイメージした作歌は、まっ直ぐにひたすら突き進むべき「道」である。宗教的な修行を思わせる厳しいものでした。以下にに歌集よりいくつか取り上げて作風を解ればと思うのだが、自分にはわからないかも
『馬鈴薯の花』
1913年(大正2年)に中村憲吉との合著として刊行。1909年(明治42年)から1913年(大正2年)の歌を収録している。柿の村人として発行しているが、赤彦が歌人として初めて世に問うた重要な歌集である。以前とは一転して、新視点、新表現が表れてきている。
げんげ田に 寝ころぶしつつ 行く雲の とほちの人を 思ひたのしむ
夜寒の手 栗を焼きたる 真白き手 さびしかりし手 うれしかりし手
『切火』きり‐び
1 ヒノキ・モミなどの堅い材に細い丸棒をもみこみ、その摩擦熱でおこす火。
2 火打ち石と火打ち金(がね)を打ち合わせておこす火。
3 旅立ちや外出などの際、火打ち石で身に打ちかける清めの火。「—を打つ」
1915年(大正4年)発刊。「アララギ」再建のための上京前後の1913年(大正2年)、1914年(大正3年)の作に属し、1913年(大正2年)に初めて島木赤彦の筆名用いて作歌した以降の歌である。上京前後の激しい心の揺れが歌われている一方、八丈島の連作には心の平安を得ていく姿もある。前作に続き僅か2年後の歌集であり、1913年(大正2年)に刊行された斎藤茂吉の『赤光』が好評だったことにも影響されてか、作歌上様々な工夫が見られるが、字句の混乱と内面の動揺を表現することになり、その結果、赤彦自身のためらいもあってか、ここの歌集は再版することなく絶版とされた。『切火』という歌集名は、中原静子との恋の火を断ち切る意味を込めたとも言われている。
夕焼空 焦げきはまれる 下にして 氷らんとする 湖の静けさ
人に告ぐる 悲しみならず 秋草に 息を白じろと 吐きにけるかも
行く雲はささやかなれど切れぎれに都の夜を流れ居る見ゆ
『氷魚』
氷魚
1920年(大正9年)の発刊。1915年(大正4年)から1918年(大正9年)の歌が収録されている。この間は「一心集中」や「鍛錬道」を提唱した時期であり、入念な写生に立脚した赤彦調が現れている。
窓の外に白き八つ手の花咲きてこころ寂しき冬は来にけり
うどん売る声たちまちに遠くなりて我が家の路地に霙ふる音
『太虚集』たいきょしゅう
1924年(大正13年)に発刊。1918年(大正9年)から1924年(大正13年)の作を収録している。長崎に斎藤茂吉を見舞う歌から始まり、関東大震災からも『アララギ』を守り抜き、同誌を背負う赤彦の自信に満ちた時期を詠っている。作家態度に動揺はなく、自己の作風を確立している。すなわち自然と人間とが一体になった「寂蓼相」と呼ばれる赤彦の独自の世界を実現している。
戸をあけて即ち向ふ落葉松のしげりを透す朝日の光
限りなく晴れたる空や秋草の花野にとほき蓼科の山
みづうみの氷は解けてなほ寒し三日月の影波にうつろふ
『柿蔭集』しいんしゅう
1926年(大正15年)に発刊。1924年(大正13年)から1926年(大正15年)の歌であり、病のため自分で編纂ができず、死後に発刊されている。枯淡の風韻を湛えるとともに、病床詠は生への愛惜がにじみ出ている。
わが馬の歩み自ら止まりて野中の萩の花喰ひにけり
秋早く稲は刈られてみちのくの鳥海山に雪ふりにけり
みちのくの谷川はたのし杉黒し茂吉が生れし家の屋根見ゆ
西吹くや富士の高根にゐる雲の片寄りにつつ一日たゆたふ
たゆたふ【揺蕩ふ / 猶予ふ】揺れ動く。漂う決心できずに迷う。ためらう。
富士が根に夕日残りて風疾し靡きに靡く竹むらの原
葦枯れのいづれの山を人に問ひても天城の山のつづきなりといふ
魂はいづれの空に行くならん我に用なきことを思ひ居り
箸をもて我妻は我を育めり仔とりの如く口開く吾は
我が家の犬はいづこにゆきぬらむ今宵も思ひいでて眠れる
父は正二位大納言源経信。母は土佐守源貞亮の娘。源経信は以前より調べていたが其の息子が抜けて居り改めてメモを取る。
(2021年10月9日)
篳篥の才があり、はじめ堀河天皇近習の楽人となる。のち和歌の才も顕わし、堀河院歌壇の中心歌人として活躍。また藤原忠通・顕季を中心としたサロンでも指導的な立場にあった。康和二年(1100)の源国信家歌合、長治元年(1104)の藤原俊忠家歌合など、多くの歌合で判者を務めた。
父経信譲りの長の高い叙景歌から卑俗な誹諧歌に至る多様な風体を詠み分け,用語,素材の拡充にも積極的で,万葉語,俗語,奇語を盛んに摂取し,故事,説話への関心も高かった。秀歌の要件として「珍しき節」を重視し(『俊頼髄脳』),「我ハ歌ヨミニハアラズ。歌ツクリナリ」と任じていたというが(『顕昭古今集注』),「エモイハヌ詞ドモヲトリアツメテキリクム」自らの詠法には少なからぬ自負を抱いていたと思われる。連歌をも好んだ。
以下に 某HPより抜粋して歌を載せました。
春
春のくるあしたの原をみわたせば霞もけふぞ立ちはじめける
なみたてる松のしづ
山桜咲きそめしより久かたの雲ゐに見ゆる滝のしら糸
白川の春の木ずゑを見わたせば松こそ花のたえまなりけれ
夏
おぼつかないつか晴るべきわび人の思ふ心やさみだれの空
日ざかりはあそびてゆかむ影もよし真野の萩はら風たちにけり
解説 「遊びてゆかむ。影もよし。」と、二句・三句切れが弾んだような心持を伝える。夏の昼間のあふれる光、緑陰の涼しさ、歌枕真野(琵琶湖畔)の入江のひろがる情景など、言わずしてイメージが広がってくる。自由奔放な歌いぶりは俊頼の独擅場で、彼の特長が最も良く出た一首である
秋
夕まぐれ恋しき風におどろけば荻の葉そよぐ秋にはあらずや
さまざまに心ぞとまる宮城野の花のいろいろ虫のこゑごゑ
なにとなく物ぞかなしき菅原やふしみの里の秋の夕ぐれ
木枯しの雲ふきはらふ
【通釈】木枯しが雲を吹き払う――そうして現れた高嶺から、冴え冴えと澄んで月が昇ることよ。
松風の音だに秋はさびしきに衣うつなり玉川の里
故郷はちる紅葉ばにうづもれて軒のしのぶに秋風ぞ吹く
なきかへせ秋におくるるきりぎりす暮れなば声のよわるのみかは
冬
いかばかり秋の名残をながめまし今朝は木の葉に嵐ふかずは
木の葉のみ散るかと思ひし時雨には涙もたへぬものにぞありける
しぐるれば夕くれなゐの花ころも誰がそめかけし
日暮るれば逢ふ人もなしまさきちる峰の嵐の音ばかりして
その他
わするなよかへる山路にあとたえて日かずは雪のふりつもるとも
死なばやと思ひあかしの浦を出ていく田の森をよそにこそみれ
あらぬ世にふる心ちして悲しきにまた年をさへへだてつるかな
【通釈】この世に生きている心地もしないで悲しいところへ、さらに年を隔て、亡き人からいっそう遠ざかってしまったのだな。
葦の屋のしづはた帯のかたむすび心やすくもうちとくるかな
あさましやこは何事のさまぞとよ恋せよとても
つくづくとひとり
世の中を思ひつづけてながむれば身はくづほるる物にぞありける
世の中は憂き身にそへる影なれや思ひすつれどはなれざりけり
【通釈】世の中は辛いことばかり多い我が身に伴う影なのだろうか。思い捨ててもこの身から離れないのだった。
追記
【俊頼髄脳】としよりずいのう
平安後期、院政期歌壇の指導者源俊頼(としより)が書いた歌論書。1112年(天永3)ごろ、藤原勲子(後の鳥羽(とば)院皇后・高陽院(かやのいん)泰子=改名)のために述作したらしい。『俊頼無名抄(むみょうしょう)』『俊秘(しゅんぴ)抄』『俊頼口伝(くでん)集』などの別名でも伝わっている。入門指南のための和歌概説ながら、歌体論、歌病論、和歌効用論から始めて、題詠論、秀歌論、歌語論に及ぶ広い体系的述作を志している。全体に実作の立場から具体的に作品を解明し、和歌説話も豊富に取り込んでいる。俊頼の新風志向がはっきりうかがわれ、後の歌学、歌論に大きな影響を与えた。
【俊頼髄脳】 『歌のよしあし』
和歌が優れているか否かを真に知ろうとする事は,大層,大変な試みなのであろう.四条中納言・藤原公任卿に,その子息である中納言・藤原定頼が,「和泉式部と赤染衛門とでは,(歌人としては)どちらが優れているでしょう」と,尋ねなさったところ,「一口に優劣を云々出来る歌人では無い.和泉式部は『ひまこそなけれあしの八重ぶき』(注:『津の国のこやとも人をいふべきにひまこそなけれあしのやへぶき(後拾遺集,691)』の歌の事)との秀歌を詠んだ歌人である.誠に優れた歌人である」との返事だったので,中納言定頼卿は,不思議に思い,「和泉式部の歌でしたら『はるかに照らせ山の端の月』(注:『暗きより暗き道にぞ入りぬべき遥に照らせ山の端の月』(拾遺集1342の歌の事)という歌の方こそ良い歌だと世間の人は申します様ですが)と申し上げたところ,公任卿は「その世評こそ,人は十分に知り得ない事を言うものだ.『くらきよりくらき道にぞ』という初二句は,法華経の教典の文言ではないか.だから,和泉式部がどの様に考えついたであろうとも思えない.下の『遥に照らせ』という句は,上の句に引き寄せられて,容易く詠めた事であろう.それに比べて,私が挙げた『津の国を来やとも人を』と表現し,『ひまこそなけれ』とも表現した詞は凡人が思い付く物では無い.(注意:『来や』と『(摂津の国の)昆屋』を掛け,更に『小屋』を暗示して『暇(ひま)』=機会の事,と『ひま』(隙間の無い葦の八重葺)を表現した事を賞賛している.)素晴らしい発想である.」と強調されたのであった. 天徳の歌合(うたあわせ)の折りにも,壬生忠見が「ねざめざりければ」(注:『小夜更けて寝覚めざりせば郭公(ほととぎす)人伝てにこそ聞くべけりかれ』の歌の事)と詠んだ,時鳥(ほととぎす)の歌は,何とも言え様のない善い歌では在るけれども,(この歌と優劣を競われた)「人ならば待てといはましを」(『人ならば待ててふべきを郭公二声とだに聞かで過ぎぬる』藤原元真,の歌の事)と詠んだ歌は,最近の人にとっては,文字の続き方など『て』が続いているので,良く無い歌だと言われるに違いない歌ではあるが,この歌合では,両方の歌は,判定は『待(じ)』で同じ位優れた歌とされている.これらの事を考えると,当世風だけの考えの人が,歌の優劣を批評する事は,何とも恐ろしい事であろう.こういう人々が,「だから」だの,「いや,そんな事は無い」だの批評するのは,人まねに言うのであろう.
江戸中期の歌人。名は玄仲(はるなか)、通称は帯刀(たてわき)。観荷堂と号する。父はもと大和宇陀(やまとうだ)(奈良県)の藩主織田(おだ)家に仕えた小沢喜八郎実郡(実邦)(さねくに)。大坂で育ち、尾張(おわり)藩成瀬家(また竹腰家)の京都留守居役本庄勝命(ほんじょうかつな)の養子となり本庄七郎と称した。30歳ごろ冷泉為村(れいぜいためむら)に入門して歌道を学んだ。人間性尊重の独自の歌論をもつようになり,安永2 (73) 年頃為村に破門される。寛政(かんせい)期(1789~1801)京都地下(じげ)歌人四天王の一人に数えられ、伴蒿蹊(ばんこうけい)、上田秋成(あきなり)、本居宣長(もとおりのりなが)などと親交があった。門人には妙法院宮真仁(しんにん)法親王をはじめ小川布淑(ふしゅく)、前波黙軒(まえばもくけん)、橋本経亮(つねあきら)など多くの歌人がある。歌は心情を自然のまま技巧を凝らさずに詠出すべきであるとする「ただこと歌」の説を提唱する。これが、教えを受けた香川景樹(かげき)などによって、江戸後期の京坂地下歌壇の主流となる。家集に『六帖詠草(ろくじょうえいそう)』がある。歌論書に『ちりひぢ』『振分髪(ふりわけがみ)』『布留(ふる)の中道(なかみち)』がある。古典和歌の研究にも熱心で、多くの歌書の写本を所蔵していた。
「ただごと歌」当世の平語を用いて自然な感情、心をあるがままに表出する。
---ただ今思へることを吾が言はるる詞を持ってことわりの聞ゆるやうに言ひつづる。「歌はこの国のおのづからなる道なれば、詠まんずるやう、かしこからんとも思はず、気高からんとも思はず、面白からんとも、やさしからんとも、珍しからんとも、すべて求め思はず、ただ今思へることを、我が言はるる詞をもて、ことわりの聞ゆるやうに言ひいづる、これを歌とはいふなり」(『布留の中道』)
以下に歌を載せて「ただごと歌」の理解が出来るかも。自分はまだ理解をしていないが。
春
小雨ふる春の夕べの山がらす濡れて寝にゆく声ぞ淋しき
春雨の音きくたびに窓あけて軒の桜の
夏
ひびきくる田歌も今は友となりて稀に聞こえぬ暮ぞ淋しき
わがごとや老いて疲れししづの女がおくれてかへる小野の山道
秋
霧りわたる苔路しめりてひややかに来る秋しるき庭の
こん秋もなほ世にあらば
冬
松にふく風もあらしになりにけり北窓ふたげ冬籠りせん
降りつもる雪はうすゆき松竹もわかるるほどの夕ぐれの色
雑
我が松のこずゑのからす
朝がほの花の物いふ心地してみやびし
すなほなる心詞ぞ行末にのこらん道のすがたなりける
言ふことはみな心より出でながら心を言はんことの葉ぞなき
鳥取藩軽輩荒井小三次の次男に生まれ、銀之助といったが、7歳で父に死別し、伯父奥村定賢の養子となって奥村純徳と改めた。年少のころから学問を好み、清水貞固(さだかた)に和歌を学んだ。26歳で和歌修業のため京都に上り、荒井玄蔵の変名で按摩(あんま)をしながら刻苦勉励し、29歳で二条派地下(じげ)の宗匠香川梅月堂景柄(かげもと)の養子となり、香川式部景樹といった。このころ小沢蘆庵(ろあん)の「ただこと歌」に啓発されて、古今伝授を伝統的権威とする二条派和歌に反発し、37歳で梅月堂を離縁となり、独立して桂園派の一派をたてた。景樹の主張の一つは中世的伝統歌学の否定であり、他の一つは復古主義歌学の否定である。賀茂真淵(かもまぶち)の『新学(にいまなび)』に対して『新学考』(1815年に『新学異見』として出版)を書いて、真淵の『万葉集』尊重と古代精神復活の主張を批判し、『古今集』を尊重しながらも「今の世の歌は今の世の詞(ことば)にして今の世の調(しらべ)にあるべし」と「調の説」をたてて和歌の現代性を強調し、近世歌論に新しい展開を示し、熊谷直好(くまがいなおよし)、木下幸文(たかふみ)をはじめとして概数1000人の門人たちは全国に桂園派の新歌風を拡大した。
景樹の歌の理解にと幾つかの歌を載せました。
春
はるばると霞める空をうちむれてきのふもけふも帰るかりがね
おぼつかなおぼろおぼろと我妹子が垣根も見えぬ春の夜の月
夏
茜さす日はてりながら白菅(しらすげ)の湊にかかる夕立の雨
大空に月はてりながら夏の夜はゆく道くらし物陰にして
秋
鴫(しぎ)のゐる沢辺の水はすみにけり草かげみゆる秋の夕ぐれ
今すめる月や都の空ならむ思ふ人みな見えわたるかな
山川の岸をひたして行く水にぬるでの紅葉ちらぬ日ぞなき
冬
てる月の影の散り来る心地して夜ゆく袖にたまる雪かな
さ牡鹿の啼きて
雑
若草を駒にふませて
袖のうへに人の涙のこぼるるは我がなくよりも悲しかりけり
思ふこと寝覚の空に尽きぬらむあした空しきわが心かな
はかなくて木にも草にもいはれぬは心の底の思ひなりけり
まづゆくを慕ひ慕ひてつひに皆とまらぬ世こそ悲しかりけれ
ちちこ草ははこ草おふる野辺に来て昔恋しく思ひけるかな白川の末の草河冬がれてほそき流れに千鳥鳴くなり
富士のねを木の間木の間にかへり見て松の蔭ふむ浮島が原