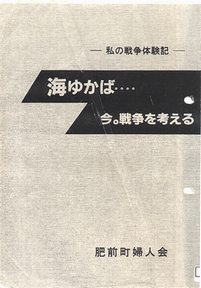こちらは、地方公共団体のご協力により、寄贈いただきました
戦争体験記集の紹介です。
 |
私の戦争体験記
『海ゆかば・・・・今。戦争を考える』
|
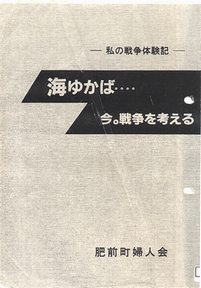
| 発行 |
|
肥前町婦人会 |
|
| 発行責任者 |
|
井上秋代 |
|
| 印刷・製本 |
|
中央印刷 |
|
|
|
伊万里市大坪町 |
|
| 発行日 |
|
1990年6月1日第1刷発行 |
|
| 価格 |
|
定価1200円(発行当時) |
|
| 頁数 |
|
176ページ |
|
|
| 目次 |
巻頭写真集
朝日新聞(昭和16年12月8日)、ビルマ作戦、南方諸島作戦、比島作戦、銃後、第二次ソロモン海戦、ガダルカナル島沖海戦、特攻機、空襲、連合軍日本本土進駐 |
| 「海ゆかば」発刊にあたって |
肥前町婦人会会長
(当時)
井上秋代 |
| 「四百五十二柱」のご冥福を祈ります。 |
肥前町長(当時)
井上良富 |
| 戦争体験記 |
| シッタン河を死守せよ −戦友達が眠るビルマ戦線 |
宮口 崇 |
| 伊万里・浦之崎造船所 −戦時中の学徒動員 |
宮口通正 |
| 見た目は楽しく暮らせども −若き日の思い出 |
井上幸枝 |
| 海南島第十五警備隊 −戦中戦後を生きて |
大浦 寛 |
| ラバウル・ガゼレ岬 −我が青春は海の彼方に |
大浦 栄 |
| 夫の戦死公報 |
榎本サミ代 |
| 厳しかった農作業 −私の青春はなかった |
井上静江 |
| かんころだごとよもぎ団子 −戦争の思い出 |
井上シツ |
| 物価統制令 |
岩本 強 |
| 南支・ルソン島・ジャワ島 −そして広島で・・・・・・ |
井上伸夫 |
| シンガポール攻略に参加して |
井上繁光 |
| 闇の彼方に |
井上誠也 |
| 引揚げで受けた中国人の情 −私の青春と軍隊生活の思い出 |
山口福治 |
| つぎはぎズボンコンテスト |
瀧川正真 |
| 恐ろしい戦争 |
諸岡マサ |
| ビルマは苦しかった |
諸岡九十郎 |
| マレー作戦 −スンゲイスプトにおける第八中隊の戦闘 |
山口源一 |
| ビルマの惨状 −ビルマ戦線に思いをはせて |
徳田新一 |
| 私の見た東京大空襲 |
古舘義治 |
| 菊一一一部隊 |
石田政吉 |
| 戦時徴雇船の悲劇 |
渡辺アサヨ |
| 質素を旨とすべし |
北原福造 |
| 呼び合う魂 −鹿児島沖漂流 |
美間坂 寿 |
| 食糧買出し |
松村アイ子 |
| 夫の戦死をのりこえて |
川口ミ子 |
| 軍国主義の教育 |
中山甚太郎 |
| 戦艦「金剛」とソロモン・ポポラン島 |
山口禮造 |
| 食糧増産の特別表彰 |
山口今吉 |
| 私の青春時代 |
船岡八郎 |
| 農業に頑張った |
藤田八千代 |
| −兄弟二人が戦死− 戦争時代を思う |
山添義男 |
| 嬉しかった夫の復員 |
高田萩枝 |
| 特攻機「紫電改」の整備員として −徴用と海軍生活の思い出 |
藤原広幸 |
| 広島原爆の思い出 |
井上留吉 |
| 戦時中の学校生活 |
濱井幸雄 |
| ビルマ最後の電波警戒機 |
岩本義一 |
| 戦死者の妻として |
浜井静子 |
| フィリピン戦線・戦友の死 |
浜井三郎 |
| 戦禍の中の悲しい在留邦人 |
浜井三郎 |
| ある被爆少年の死 |
松永すなお |
| 復員の悲しみ |
浜井精治 |
| 「国破れて・・・・」 |
富永 孝 |
| 「右八百に魚雷!」 −戦争の思い出 |
松本次郎 |
| 厳寒のソ満国境 −北満と台南の戦争体験記 |
城 寅雄 |
| バターン半島攻略 −私の戦歴 |
山添常五郎 |
| 兄の戦死 |
山添ハマヨ |
| 軍艦「妙高」とともに |
鶴 一幸 |
| 「お母さん」と呼んで逝った戦友 |
出 勝實 |
| 坑州湾敵前上陸 |
出 三治 |
| 北満から本土決戦へ −日本軍の衰退 |
諸岡孝映 |
| バンタム湾上陸作戦 |
山口紋治 |
| シベリア抑留 |
浜部増雄 |
| どんぐりの粉 |
川添 強 |
| 英霊南より還る |
坂本スミエ |
| 通信兵と大陸の夕陽 |
山口陽太 |
| 工兵第五十六聯隊 −内地よりラングーンまで |
浜口栄治 |
| 後方部隊として |
坂口佐太郎 |
| 旗艦「出雲」に乗艦して |
石橋専太郎 |
| 戦時中の火事 |
平田テルヨ |
| もうコリゴリです |
宮崎 均 |
| 苦しかった食糧統制 |
小田 始 |
| 三人の子供と夫の戦死公報 |
宮崎テル |
| 原爆に想う |
堀田陸奥 |
| 衛生上等兵 |
堀田 久 |
| 夢や希望もなかった |
堀田清治 |
| 竹やり訓練 |
堀田トク |
| ヤップ島守備隊 −大東亜戦争の回顧 |
畑中 実 |
| 編集後記 |
井上常憲 |
*注意
1.
こちらは、地方団体発行の書籍の紹介です。
こちらは佐賀県東松浦郡肥前町の教育委員会社会教育課藤井様(ご寄贈当時)のご協力により、ご寄贈頂いたものです。有難うございました。
なお、原本のみのため、藤井様が全ページコピーされ、お送りいただいたものです。御手数をお掛けしまして申し訳ございませんでした。本当に有難うございました。
町内の婦人会が町内の戦争体験者の体験記を纏め、発行したものです。
趣旨は『当時のことを知る人もだんだんと高令化し時と共に風化しつつあります。戦争中の苦しかった事を書き残し一人でも多くの人にどんなに悲惨なものか平和とはどんなに尊いものかを十分理解していただき、これから育ち行く子どもの心の中に平和の砦を築いて欲しいのです。』
肥前町婦人会会長(当時)さんの「発刊にあたって」より一部引用いたしました。
ホームページ掲載まで日時がそうとう掛かってしまいましたことをお詫びいたします。
2.
こちらのものは、私の資料として集めた物です。
通常の出版では無く、関係者に配布する目的で発行されていますのでお求めは難しいと思います。
3.
今後出来る限り上記の資料の本文をご紹介できるようにしていきたいと思います。それには発行者・著者の方の許可が不可欠ですので、すべては無理かもしれませんが可能な限り、許可を頂いたものを載せていこうと思います。
4.
本の内容紹介で本の表紙を掲載しておりますが、これは私が皆様に情報提供する場合に、少しでも詳しく知っていただくために私の所蔵しております本の表紙から写しております。本来なら全ての発行者及び著者の方に許可を頂かなければいけないと思いますが、出来る限り本の詳しい情報をお伝えしたいという私の考えから現在のところ許可を頂かずに掲載をしております。但し、本の発行所・発行者・編集者・著者・印刷所・発行年月・ページ数・表紙題字揮毫者・イラスト作者等その本に関してわかる限りのデーターを掲載するように注意しております。本の表紙写真のみの掲載はしておりません。
もし、著作権等の問題で表紙写真の掲載は不可の作品がございましたら、ご連絡いただければ対応いたします。
自費出版及び地方公共団体発行の本のため、通常情報をなかなか得られない事が多いので、どんなものであるかを視覚的にもお伝えしたいと私は考えております。関係者様各位のご了解・ご協力をいただければ幸いです。
戦友会・遺族会等が発行した戦争関連の本の情報を求めています。
その他の団体や個人の方からの情報もお待ちしております。ご連絡ください。
こちらへ bunkokan@ab.thn.ne.jpどうぞ
スパムメール対策のため、@は大文字にしてあります。
お手数ですがメールの際は@を小文字に変えて送信ください。
|