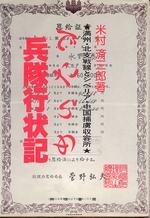こちらは、個人の方の御協力を頂いて収集した戦争体験記集及び
私自身が調べ、収集した自費出版・共同出版等関連の戦争体験記です。
 |
| 『でたらめ兵隊行状記』 |
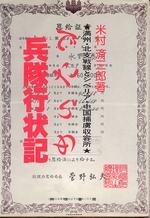
| 著者 |
|
米村済三郎 |
| 発行者 |
|
水野泰夫 |
| 発行所 |
|
図書出版 共栄書房 |
|
|
東京都千代田区神田和泉町(発行当時) |
| 印刷所 |
|
中央精版印刷KK |
| 発行日 |
|
1983年6月10日 第1刷印刷 |
|
|
1983年6月15日 第1刷発行 |
| 価格 |
|
定価1400円(発行当時) |
| 頁数 |
|
340頁 |
| 装丁 |
|
松前九馬 |
|
| 目次 |
| はじめに |
| 第1章 貧しい農村は兵隊の温床 |
| 越後の貧農の生活 |
| 野良仕事の手伝い |
| 娘は桑摘みか女工 |
| 男は兵隊か出稼ぎ |
| 地主に納める年貢米 |
| 青年会の若者たち |
| 満州事変勃発 |
| 第二師団(多門師団長)の凱旋 |
| 村祭りの夜に・・・・・ |
| 第2章 ”ひとのいやがる軍隊に” |
| 「甲種合格、看護兵!」 |
| ”勝たずば生きて帰らじと” |
| 遊郭で命の洗濯 |
| 2・26事件突発 |
| 宇品出航、大連へ |
| 歩兵第十八連隊での特訓 |
| ハルピン陸軍病院で看護兵教育 |
| 自動車操縦教育 |
| 古年次兵の気合 |
| 三年兵除隊、初年兵入隊 |
| 支那事変に発展、野戦病院編成 |
| 張家口から大同に |
| 分院に赤十字看護婦 |
| 情欲のはけ口 |
| 患者の収容と火葬 |
| 敵襲の危機を脱出 |
| 太源陥落、任務終了 |
| 灰田勝彦も内地帰還 |
| 三等症で入院 |
| 満期除隊 |
| 第3章 赤紙を手に再び大陸へ |
| 妻子との別離 |
| 仙台陸軍病院に入隊 |
| 日・米英開戦、戦果に湧く |
| 召集兵の出番 |
| 二度目の宇品出帆 |
| 朝鮮を縦断して北支へ |
| 莱撫に患者療養所開設 |
| 現地人の施療 |
| 師団特別訓練隊へ |
| 吉信挺身隊に配属さる |
| 衛星兵、前へ!! |
| 戦果なき作戦の終末 |
| 第二次河南(老河口)作戦開始 |
| 方城に先発 |
| 内郷に前進 |
| 帰還要員で済南に急行 |
| 帰還列車に乗り遅れ |
| 本土防衛のため転進 |
| 朝鮮で対ソ戦の陣地構築 |
| 無条件降伏の玉音放送 |
| ソ連軍が武装解除、三郷里収容所へ |
| 収容所の医務室勤務 |
| 夢を乗せて出港したが・・・・・ |
| ポセット港に入港、下船 |
| 第4章 あわれ、シベリア送り |
| 運を天に任せて |
| ハバロフスクからタシュケントへ |
| グリンチマザールでの強制労働 |
| 薄切り黒パンとおカユが常食 |
| 移動、ラーゲリでの白み鳥シラミ捕り |
| ドビーズ造りのノルマ |
| 女囚のハプニング |
| ベグワードの運河掘り |
| 民主運動の集会 |
| トラック運転手の特権 |
| ダンパ造りの土方 |
| ダモイの噂さ |
| 帰国運なく石敷作業に |
| 炭鉱のビヤ樽女性監督 |
| 処罰!コルホーズ送り |
| 鼻毛も凍る厳寒 |
| ハバロフスクに移動 |
| 行き先不明のダモイ列車出発 |
| 第5章 3度目の中国は戦犯管理所 |
| ソ連軍から中国解放軍に移管 |
| 撫順の監獄に |
| マージャンは中国のご法度 |
| 朝鮮戦争勃発、ハルピン監獄に |
| 学習開始 |
| 満腹と運動不足で胃腸病 |
| 三民主義の学習 |
| 撫順に復帰、労働にありつく |
| 優秀労働者の表彰 |
| 朝鮮戦争に関する学習 |
| 草取り作業 |
| 多発性神経炎の防止対策 |
| 早水のスキャンダルと宮下の自己批判 |
| 運動会と日本人指導部員の活躍 |
| 野外ステージで初演奏会 |
| 自己批判のための集会 |
| 映画「白毛女」による学習 |
| 社会党訪中団の慰問と中国側の取調べ |
| 山西中尉の謎の自決 |
| 六年目の正月の贈り物 |
| 文化祭の田植え踊り |
| 罪状調査報告書を提出 |
| 第6章 恩恵を以て罪に報ゆ |
| 撫順炭鉱の参観 |
| 誰か故郷を思わざる |
| 中国参観の旅行に出発 |
| ハルピンで中国料理の歓待 |
| 長春で工場、瀋陽で農業合作社参観 |
| 鞍山製鉄所を参観して山海関へ |
| 首都北京の偉観 |
| 武漢の大鉄橋を見る |
| 長沙―南昌―杭州―蘇州 |
| 上海の工場参観 |
| 南京で中山陵参拝 |
| 参観旅行を終えての総括 |
| 起訴免除の発表 |
| 帰国準備と放免 |
| 集会所で送別会を挙行 |
| 天津で待機、タンクーから乗船 |
| おわりに |
*注意
1.
こちらの本は、私が古書店にて購入して手に入れたものです。
内容は
『著者自身の経験を本書の主人公修に置き換えて、半生を振り返っています。
十五年戦争の半分を軍隊で過ごし、戦場に駆り出された修の軍隊時代のこと、終戦後シベリヤに抑留させられ、強制労働に服すこと5年、そしてさらに、中国軍に戦犯として収監され6年、合わせて11年もの長きにわたって捕虜生活を体験させられたことなどを、当時の若者としての心境で2年の歳月を費やして書かれたものです。』
著者は本書の「おわりに」内にこう記しています。
『前略。大切なことは、侵略戦争に対しての反省である。私たちのように従軍したものは、自分の意思であるかないかに関わらず、皆戦争の実行者であった。しかるに戦争の全責任は、当時の軍閥や財閥、一部の為政者にあるとして、その責任の全部を転嫁し、自分達の責任を忌避しようとしている。これで済まされるものではない。戦争実行者としての私たちも深く反省し、率直に謝罪する気持ちが必要であり、その上にたっての有効こそ真の友好関係であると信ずる。 以下略。』
これは非常に重い言葉だと思います。実際に戦争を経験した方の率直なご意見だと思います。戦争経験者で無い人が、あの戦争の責任は誰々云々・・・と公然と話したり、文を書かれたりしていることは何なのでしょうか? 上記の言葉の意味をよく考えなければいけないのではないでしょうか。
(文責 管理人)
2.
こちらのものは、私の資料として集めた物です。
だいぶ以前の発行ですので、お求めは難しいと思います。図書館や古書店にお問い合わせください。
3.
今後出来る限り上記の資料の本文をご紹介できるようにしていきたいと思います。それには発行者・著者の方の許可が不可欠ですので、すべては無理かもしれませんが可能な限り、許可を頂いたものを載せていこうと思います。
4.
本の内容紹介で本の表紙を掲載しておりますが、これは私が皆様に情報提供する場合に、少しでも詳しく知っていただくために私の所蔵しております本の表紙から写しております。本来なら全ての発行者及び著者の方に許可を頂かなければいけないと思いますが、出来る限り本の詳しい情報をお伝えしたいという私の考えから現在のところ許可を頂かずに掲載をしております。但し、本の発行所・発行者・編集者・著者・印刷所・発行年月・ページ数・表紙題字揮毫者・イラスト作者等その本に関してわかる限りのデーターを掲載するように注意しております。本の表紙写真のみの掲載はしておりません。
もし、著作権等の問題で表紙写真の掲載は不可の作品がございましたら、ご連絡いただければ対応いたします。
自費出版及びそれに近い発行の本のため、通常情報をなかなか得られない事が多いので、どんなものであるかを視覚的にもお伝えしたいと私は考えております。関係者様各位のご了解・ご協力をいただければ幸いです。
戦争関連の自費出版、手記の情報を求めています。
どんな事でも良いです。
ご連絡ください。
こちらへ take916@ca.thn.ne.jpどうぞ
|