和船(千石船)とヘダ号(洋式帆船)の違い
この写真は東海大学海洋学部の
学芸さんが杉村さんと言う
清水市の船大工さんと全国を
調査してヘダ号の復元を
計画して完成した物です
何時もは東海大学に有りますが
新世紀創造祭西暦2000年の時
戸田造船博物館に特別展示
された時のです
日本で最初の洋式帆船の
骨組みが解りますかね? |

 |
|
|
  
 
 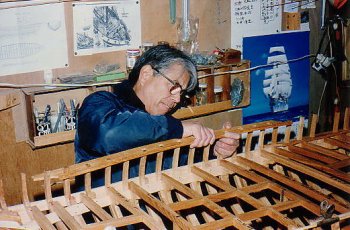
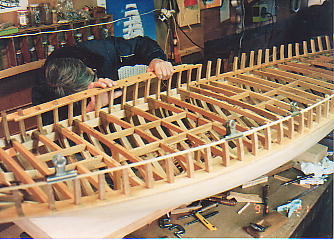 
 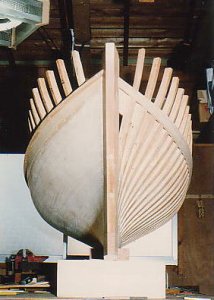
戸田号はロシア人の帰国船が地震の為の津波で結局駿河湾へ沈み、帰る為の船として造りましたが、
大変な難工事でした。例えば言葉の問題です。
ロシア語からオランダ語それから日本語、メートル法から尺貫法。
ヘダ号を造っている時に下田に於いて日露交渉をしていたので
オランダ語の通訳が下田に同行しているので
英語の通訳を通してヘダ号の図面 造船工事をしたようです
また幕府からの命令で、貰うな・やるな・付き合うな
船の構造が根本的に違うので理解をするのが大変でした。
しかしロシア人も早く帰りたい、日本の船大工も職人の誇りと、
外国へと安心して航海できる、丈夫な船をとの思いが通じ、わずか3ヶ月で出来ました。
この設計図が一番大事です。
右側が船の前から見た人間で言う
あばら 骨の形です。
左側は船の後ろから見たものです。

ではヘダ号(洋式帆船)の構造はどの様に成っているかと言いますと、
人間と同じ構造で、背骨があります。洋船の場合(キール・竜骨)と言います。
肋骨、あばら骨を(肋木・フレーム)と言います。鯨の剥製を見ると判りやすいです。
和船(千石船)は箱舟・樽などと同じです。
簡単に言いますと骨が無く、外板などで出来ています、丸木船など川船で使う、
鵜飼船などが同じです。
追い風 又は良い風向きの時しか走れません。
だから風待ち港が沢山有りました。
又洋式帆船(ヨット)は
向かい風でも走れますが(45度にジグザグに)
和船は向かい風では殆ど前には進めません。これは和船は骨が無いので、
構造が弱く三角マスト
| 
