![]()
| オーディオ圧縮をアナログ音源のデジタル化に利用する | ||
| ●カセットテープを沢山お持ちの方なら、音楽だけではなくラジオの野球中継や深夜放送などを長時間丸ごと録ったテープもきっと何本かお持ちではないしょうか? あるいはビデオが無かった時代にはテレビの音声だけを記録したテープもあるかも知れない。 ●音もそれ程良くないし、かさばる、かといって捨てられない。デジタル化してもC-60じゃ同じ枚数だけCDが必要だしC-90や120では逆に1枚に収まらないからばかばかしくてやる気にもなれない。 ●その他、語学をはじめとして教材用にカセットで録音されたもの、ラジオ講座などの長時間連続のテープを持っている方もいると思います。 ●そんな場合にはC-60が1枚のCD-Rに10本以上収まるMP3やWMAに代表されるオーディオ圧縮を利用する事をオススメします。うまく利用すれば1本に収まりきれなかった長時間録音テープも楽に管理できます。 それだけでなくファイル名をうまく付けておけば教材用ならすぐに自分の聴きたい部分を反復再生できます。 ●本来MP3やWMAは専用のメモリプレーヤに取り込んだりハードディスク内に格納して音楽を再生する目的にする事が一般的ですが、当サイトでは音源の圧縮による保存と検索の容易さというメリットに焦点をあててみたいと思います。 |
||
| POINT | ||
| ■アナログ音源を圧縮するにはWAVEファイル変換機能のあるソフトを使う ■複数の圧縮方式があるがMP3かWMAが無難 ■一旦圧縮したら再変換しても元の音質には戻らないので注意する ■アナログ音源はいきなり圧縮せず必ず編集後に行う ■MP3以外の圧縮方式で、WAVEに再変換可能か事前に確かめる |
| オーディオ圧縮とは | ||
| ■圧縮といって思い浮かべるのはLHAやZIPなどのアーカイバ(書庫)ではないでしょうか?あるいはJPEGなどの画像圧縮形式が身近かも知れません。 ■オーディオ圧縮はLHAやZIPのようにファイルを書庫化しないで、専用ソフトで解凍しながら再生する方法で、ビデオ圧縮規格であるMPEGから派生した方法が主流です。同一ビットレートのWAVEに比べ容量を10分の1以下にできるので非常に保存性に優れます。 ■ちなみにLHAでWAVEを圧縮したところ2割位減っただけでした。それをWAVEの10分の以下に圧縮できて、しかも解凍という行為自体を意識せずに利用できる利便性があります。 ■非公開の圧縮方式も多いのですべてこうだとは言えませんが大体次のような仕組みで圧縮を行っていると考えられます。 ■倍音部分の高域周波数をカットする ■マスキング効果を利用して小さい音をカットする ■余分なステレオ(2チャンネル)成分をカットする などの処理を行ってデータ容量を削減しています。これを定型的に「10KHz以上の周波数は完全にカットする」という処理なら簡単ですが、まるでAMラジオみたいな音質になってしまいます。 そこがオーディオ圧縮の「複雑系」の処理技術の画期的なところで、人間の耳の特性を考えて、聴感上は音の劣化を最小限にくい止めているようです。 このページの下にMP3をWAVEに再変換した周波数特性グラフを掲載してありますが、グラフ上では高域がかなりカットされた事がわかるのにも係わらず、聴感上はグラフほどにはわかりません。 |
||
| オーディオ圧縮の種類 | ||
| 音源メディアに関心を持っている方なら誰でも名前は聞いたことのあるMP3とWMAがほぼ主流を占めています。 ●MP3(MPEG1 Layer3) インターネット上で音楽配信をできる画期的な形式として普及したが、違法サイトがネット上に続々と登場して問題に。しかし現在でもオーディオ圧縮の標準的フォーマットとしてほとんどのPC用再生ソフトで再生できます。 ●WMA(Windows Media Audio) Microsoftの標準オーディオ圧縮形式。Windows Media Player 7(無料配布、WindowsME標準搭載)からは音楽CDから直接エンコードできる機能が追加されました。 ※この他MPEG4のオーディオ圧縮形式に採用されたNTTが開発したTwinVQ、DVDやBSデジタル圧縮規格であるMPEG2圧縮形式AAC(Advanced AudioCoding)など。 ※その他にはストリーミング配信などでよく利用されるREALやMDで使用されているSONY独自のATRACxなど色々な圧縮技術があります。 こうした優れた技術が普及すると逆に誰でも簡単に、ネットワークで音楽配信ができてしまうため、著作権を保護する様々なプロテクト方法も同時に組み込まれるようになっています。 |
||
| どの圧縮方法を選ぶか? | ||
| オーディオ圧縮は、一旦圧縮するとWAVEに再変換しても元の音質には戻りません。アナログ音源をオーディオ圧縮化して、オリジナルを処分してしまう場合ほとんどその形式で再生する事になるため、将来性も考えないと若干不安も残ります。 一時色々な形式が登場しましたが2002年現在では対応する変換・再生ソフトはMP3とWMA以外は非常に限られます。したがってWindows Media Playerで再生できるこれらの形式で保存しておくことが無難でしょう。 |
||
| 音質は? | ||
| 音楽の保存であれば当然音質が気になるところです。MDもそうですがいずれもCDクォリティーをうたい文句にしています。 結論から先にいえばCDと同等というのはちょっと大袈裟です。 聴感上は楽曲により異なるが古い音源でもMP3を96Kbpsで圧縮した場合は、かなり歪んだように感じられるものがありました。WMAでは96Kbpsでもオリジナルに近い感じに聞こえました。 「WaveSpectra」でポップス曲(原音はPCM録音の音楽CD)をMP3で圧縮し再度WAVEへ伸張したグラフを下記に掲載しましたが圧縮率の変化により高域周波数のカットの仕方も異なっており結構「複雑系」の処理をしてるんだなぁとアナログオヤヂは感心しました。 なお圧縮は「MP3 JUKUBOX4.4」というソフトでおこないました。同じ圧縮率でもWMAの方が若干時間がかかりました。 また、エンコードソフトにより同じ圧縮率でも音質は変わる事があるからグラフは「圧縮率により、このように変わる」という部分だけ確認していただければ良いと思います。 |
||
| 以下の図の赤の波線は曲の開始から一時停止するまでのピークレベル、緑は曲の一時停止時のレベルの周波数特性をそれぞれ表示している。図1の元のWAVEは-120dbまでで測定、以下のMP3伸張の図2・3は-140dbまで表示してある。 オリジナルWAVE音源の波形 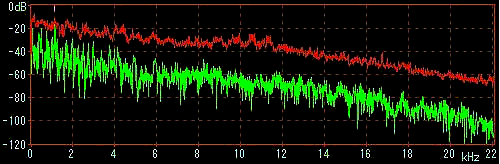 図1 元のWAVE音源.。周波数は22.05KHzまで伸びている。静止画では判らないが限界周波数まで緑の波形が上下に踊っている。ノイズではない高域の倍音声分がハッキリと存在していることが確認できる。 |
||
MP3、128Kbpsの波形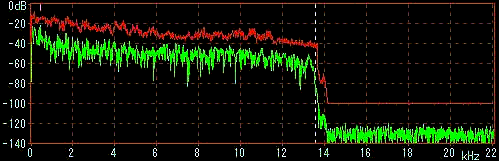 図2 MP3、128KbpsをWAVEに伸張したもの。14KHz以上の部分から一気に-120db以下になる。このレベルは緑の波形はサウンドの変化にほとんど反応していない。「音成分」というより変換などで生ずる「ノイズ成分」でしかない。-100dbというのは、ほぼ無音に近い音量だ。赤のピークレベルが-100dbで直線になっているという事は、積極的にカットしているという事でしょう。 カットされるまでの音域のピークの波形(赤)はオリジナルにかなり近い。 |
||
MP3、96Kbpsの波形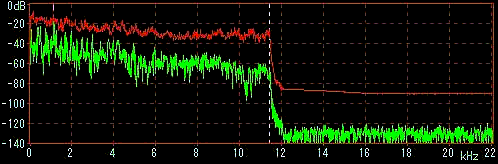 図3 MP3、96KbpsをWAVEに伸張したもの。12KHz以上の部分から一気に-120db以下になる。ピークレベルは-80〜-90dbで16KHz付近までダラダラと存在する。感覚として倍音成分が認識できるかできないかというレベルか?128kbpsでエンコードするより若干上の周波数まで取り込んでいるようです。しかし歪みの発生していた音源では伸張しても同じように歪んで聞こえました。 |
||
| 【参考】テレビ番組の周波数波形(WAVE変換) 図4 これは管理人が1970年にテレビのラインからオープンリールに録音したバラエティ番組の音楽部分の波形。9.5cm/secで録音したもの。19cm/secで録音したものでも10KHz以上に周波数特性は伸びていない。 ※上記のように高域の倍音部分の周波数は積極的にカットされてはいるが、ヴォーカル中心のポピュラー系音楽ではMP3で128Kbps、WMAでは96Kbps程度でもまぁ聞けるだろうと思いました。 参考にTVの録音周波数を掲載しましたが、AMラジオではさらに帯域は狭くなります。すなわちTVやAMラジオを録音したテープであれば、十分MP3の圧縮帯域でカバーできるといえるでしょう。ましてやモノラル音源ですので聴感上全く劣化を感じさせずに再生できます。 古くなったカセットテープの収納に困っている、でもそのまま捨てるのもちょっと淋しいという方は是非、MP3やWMAのCD-Rを制作してスッキリと整理してみてはいかがでしょうか?以下の頁に圧縮とCD-R制作の手順を掲載してあります。 |
||
| [WAVEファイルの変換の手順] [MP3・WMAファイルを追記しながらCD-Rに焼く] |
||
| (C)Fukutaro 2000.12. Last Update 2002.3 | ||
| TOP |