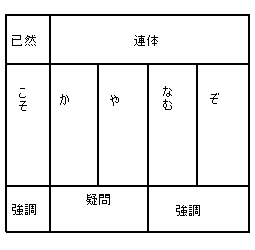�Z�̂̊�{�m���̐��� |
����22�N1�P���L
�@���܂ŒZ�̂Ƃ������̂ɂ͈�؋����͂���܂���ł����B�u���Ëߍx�v�̃y�[�W�Ő�{�l�⍁�юR�Ɏ�R�q���̉̔肪����A�q���ɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B��R�q���̉̂̂Ȃ��Ɏ����r���̂�����A���e�͎����ɂ��������Ɏv�������邱�Ƃŗ����ł��܂��B������T�V�T�V�V�Ƃ����Z���t���[�Y�œI�m�ɕ\�����Ă��芴�������̂����̓��@�ł��B
���̃z�[���y�[�W�͑����̎ʐ^���ڂ��Ă��܂����A����͋L�^��ړI�ɂ������̂��犴��������ʁA�i�F�ȂǐF�X����܂��B���̎��X�ɒZ�̂����ڂ��ꂽ���肻�̂Ƃ��̈�ۂ��N���Ɏc��Ȃ����ȂƎv�����̂����̓��@�ł��B
�Z�̂̕��ނ͒��w�A���Z�Ŋw�L��������܂����A����ȗ��ŁA�Z�̂̒m��������܂���B�Ƃ肠�����Z�̂����ɓ�����ǂ�Ȓm�����K�v�����ׂ܂����B���낢���HP���������Ēm�������܂����B
||�\��||�{���E����||���Ђ� ���j�I���ȂÂ��Г���||�C���Z�@||�Z�̂̕��@||�o��̊�{||�Z�̂̊Ϗ�||
�\��
��R�@�q���̈��
���ʂ́i����j�@���ɂ��݂Ƃق�i���j�@�H�̖�́i�O��j�@���͐Â��Ɂi�l��j�@���ނׂ��肯��@�i����j
���ʂ̎��ɂ��݂Ƃق�H�̖�́i��̋�j�@���͐Â��Ɉ��ނׂ��肯��i���̋�j
��{�͂T�E�V�E�T�E�V�E�V�̂T��o���߂����i����j�A���A�A�A�A�܋�i����j�p�R�P���̉C���ō\������A���A���ƌĂ�
�n�߂̂T�V�T����̋�c��̂V�V�����̋�Ƃ���
��{�̂T�E�V�E�T�E�V�E�V�������O�ꂽ���̂Ɂu���]��i�����܂�j�v�u�����炸�i�����炸�j�v������
�����̐�����
�����ȁu���v�̂悤�ȑ����i��������j�͂��ꂾ���łP�����B
�u�[�v�̂悤�ȐL���������ꕶ���Ɛ����܂��B
�u��v�u��v�̂悤��冉��i���傭����j�͑O�̕����ƂP�łP�����ɂȂ�
�i���s�̏������͂��ꂾ���łP�����B����ȊO�̏������͑O�̕����ƂP�łP�����Ɗo����j
���ׁi���Y���j
�Z�͎̂��ł���̂ł�����Ƃ������Ƃ͎U���ł͂Ȃ��C��
�Z�̂́u�Ӗ��v�����łȂ��u���ׁi���Y���j�v�ɂ��Ĉӎ����ĉr��
�C���́A���̒��q�����Y�~�J���ɂȂ�悤�ɁA���܂������ԂɂȂ�ׂ邱�Ƃł��B���́u�C���v�ɂ͑傫�������ĂQ�̎�ނ�����܂��B
�@�P�j�u�T���v�Ɓu�V���v�ł��낦��Ƃ������́i���������j�B
�@�Q�j�ŏ����Ō�̉������낦����́i�����C�j
�̂ɂQ�ɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�Q�l
���{�̎��̂̓A�N�Z���g����{�ɂ��Ă��Ȃ��ŁC�����ς猾�t�̔����������̐��ɂ���ĉC��������ꂽ�B���Ȃ킿�������ƌĂ����̂�����ł���B���̒����Ƃ́C���̉�����������ɗv���鎞�Ԃł���B���Ȃ킿��̒��Z�����Ԃ̒��Z�������B���������ĉ����̋K�����������Z�W���C�C����������̂ł���B�×��̓��{���̂͂����ނ˒Z�E���C���邢�͒��E�Z�̌`���Ƃ�C���ꂪ7����5���Ƃ̊W��������1����������B���̂������ނ�5�E7�ł���C���l��7�E5�ł���C�Z�̂́C���̂�2�唽���ňӖ����C���̂��ƂɍŌ��7�����������̂ł���B���̌��^�����t����ɂ͎���Ă������C���Â���5�E7�E5��1��ƁC7�E7��1��Ƃ�2�����ꂽ�B�����7�E5��4��̍��l�̂����̌�̘a�]�⑽���̖��w�̗̉w�ɔ��W�������Ƃ��C�ŏ���5�����ŏ��̔������Ƃ��ė����Ĕ����������߁C�̏��̌`�����ω����C��3���5���ňӖ���邱�ƂɂȂ����B�s�Í��W�t�Ȍ�̒Z�̂͂���ł���B
�܁E�����@�@�Q�E�R�C�Q�E�Q�E�R| 3�E�Q�C�R�E�Q�E�Q| �Q�D�R�D�Q
���E�ܒ��@�@�R�E�Q�C�R�E�Q�E�Q�C�Q�E�R|�@�Q�E�R�E�Q�C�Q�E�Q�E�R
�Ӗ��̐�Ă��镔��
�����A�O���͎��ܒ��Ƃ��������I�ȓ��������i�₳�����A�D��A�Ȃ߂炩�j�Í��W
���/�l���͌����Ƃ����j���I�ȓ��������i�f�p�A�Y��A�͋����j���t�W
�j
����ƌ���
�u����i�Ԃj�v�Ƃ͕����ʂ蕶�͂������Ƃ��ȂǂɎg���A�������t�̂��ƁB
���͂������Ƃ��̏������t�u����v�ɑ��āA����͂Ȃ��Ƃ��ɗp���錾�t���u����i�������j�v�ƌ����B
�u�������ƐV�����v�ɂ���
�u�����������i���イ���ȂÂ����j�v�Ƃ́A��������ȗ��p�����Ă������������̂��ƂŁA�u���j�I���������i�ꂫ���Ă����ȂÂ����j�v�Ƃ������܂��B
���Ƃ��ΐV���������ł́u�������i��j�v�̂��Ƃ������������ł́u���ӂ��v�A�u���傤���傤�i�����j�v�̂��Ƃ��u�ĂӂĂӁv�ȂǂƏ����\���܂��B
�u���㉼�������v�͌��������Ȃŏ����\���ꍇ�̊�ŁA��Ƃ��Č���ɓK�p�����B
����̒d�ł͈��̉̂̒��ł̕���ƌ���̍����͂قڋ��e����Ă��܂����A�����������ƐV���������̍����͈�ؔF�߂��Ă��Ȃ��B
����A����A�������u���j�I���Ȃ������v�A�V�����@���̕ӂ��킩��ɂ����̂ŁA�ēx���ׂ�B
- ��������
- ���{��̉����ŕ�����Ԃ鎞�̌��܂�B���ォ�ȂÂ����ŏ����Ƃ��ł����A�����ʂ�ɂ��̂܂ܒԂ�����Ƃ�����ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�����L���G�i�̉��ł��A�u�搶�v�́u�����v�łȂ��u�����v�ƒԂ�A�u�o����v�́u�˂�����v�łȂ��u�˂�����v�ƒԂ邪�A����͈��̒P��ɂ���āA�ǂ���̉����ŒԂ�̂����܂��Ă��邩��ł��邵�A�����́u���v�u�G�v�u�I�v���u�́v�u�ցv�u���v�Ə����̂��A���̌��܂�䂦�ł���B
- ���j�I���ȂÂ���
- �������㒆���ȑO�̕����ɂ����āA�P�ꂪ�ǂ̂悤�ɒԂ��Ă���������ɂ������������B���N���̊ԁA���������͕������̂��̂���{�Ƃ����������𗬓��I�ɕς���̂�����̓`���ł������B�������(�Ă���)(1162�`1241)�͓����������Ă��������������A���������ɂ��܂Ƃ߂ċK�͂��m�����A��Ɍ_��(1640�`1701)�͒�Ƃ̌��𐳂��A����͌���܂Ŏg��ꑱ�������j�I���ȂÂ��Ђ̋K�͂ƂȂ����B�i������Ƃ̂��ȂÂ��Ђ��u��Ƃ��ȂÂ��Ёv�ƌĂԂ��Ƃ�����B�j
�Z�̖̂{��
���V�a���̐l�� �l���r
�t�ďH�~�̎��R�@���R�r
�Z���̃e�[�}�͖����̐����̒��ɂ���
���̓���ɖڂ�z��
�@�@�Z�͎̂����i��l�́j�̎��䂦�Ɏ��������߂�
�@�@�������g���q�ϓI�ɑ�O�҂̖ڂŌ���
�@�̂�G�ɂȂ�e�[�}�������o��
�Z�̂��r�ނ��ƂŎ��Ȃ̑��ݏؖ���
�̂̑ΏۂƂ��Ă̕���
���t�ȗ��Z�͎̂��R�ɐG��A�����̏�ŁA�܂��Љ�̗���̒��ɂ����āA�l�Ԃ̐S�݂̍�l��\���������̂ł���A���ׂĂ��R��ł���Ƃ�������B�������A�Z�̂̐��E�ł͑Ώۂ̑��������A
���i���i���R�̕��i�����r�́j�A
�������i����������̂܂܂ɏq�ׂ��́j�A
�R����i����A�������q�ו\�����́j�Ƃ��������������Ă����B
�X�㒼�ړI�ɒZ�̂̑ΏۂƂȂ��������𑨂��āA���X�r�Ƃ����Ăѕ������Ă���B
�@[�߂�]
�Z�̂̍���
���X�̏��̔����i�^HP���j
�����̎��Ɖ̂̎��̈Ⴂ�@�i�{���钷�j
���̂łȂ����ʂ̕��͂́A�v���Ƃ�������܂��܂ƌ��������āA�𗝂͏ڂ����ʂ��܂�����ǂ��A��͂������Ɍ����ʊ����S��̂����ނ��́A�̂łȂ��Ă͏q�ׂ������̂ł���܂��B���̌����Ɍ����ʏ��̐[���Ƃ��낪�̂ɕ\�������͉̂��̂��ƌ����܂��ƁA�̂͌���\���ɕ�(����)�\�\���ʂȋȐ܂�ω������邩��ł���܂��B����(����)�ɂ���āA����Ȃ��u���͂�v���\����̂ł���܂��B���Ă��̉̂Ƃ������̂́A���ʂ̕��͂̂悤�ɕ����̓��e���ڍׂɏq�ׂ���̂ł͂Ȃ��A�܂����̌��t�ɐ[���Ӌ`�������Ă��Ă�����̂ł�����܂���B�����S�ɐ[���������Ƃ�����ӂƌ��ɏo�����܂ł̂��Ƃł�����ǂ��A���̒����ی����Ȃ����[�����������̂ł��B����͉̂̕\������(����)������̂ł���܂��B
��(����)����Ƃ́A���̂悭�ƂƂ̂Ђ���ЂāA����ʂ��ƂȂ�B����܌��������ɂƂƂ̂Ђ��邪�A�Í��둭�ɂ킽��āA�قǂ悫�Ȃ�v�Ƃ������Ă���A�܉��Ǝ�������Ȃ鉹�������u��(����)�v�̗v�f�ƍl���Ă����悤�ł��B
����y�����^�~���̉��
-
�P ���̕\�ʂɌ��ꂽ���܂��܂Ȍ`��͗l�B���ɁA�����߂Ɍ�������͗l�B
-
�Q ���ɋ�S�����A�����̌����B�܂݂̂���\��������ȃj���A���X�B�u���t�́\�v
-
�R �\�ʓI�ɂ͌����Ȃ����A���ǂ�ƌ����Ă���Љ�␢�̒��̓���g�d�g�݁B���\�B�u�l���́\�v
-
�S �i���j���낢��Ȗ͗l��D��o�������D���B���₨��B���₨����́B
�̂͒��ׂȂ�@�i����i���j
�����ȂׂāA�l�̐S�����Ɋ�����A���Ȃ炸������������̂ł���܂��B�����������ɂ́A���̐��͒����Ȃ�܂��B���̒����̂��̂Ƃ��A��������̂��̂��Ƃ����̂ł���܂��B�㐢�A�����f�B�[�����ĉ̂��̂����{���̉̂ƐS���Ă���̂́A�{���]�|�������̂ł���܂��B�܂�Ƃ���A�V���̐����̂Ƃ����̂ł���܂��B�Ɍ�����A�u���I�v�ƌ�������A�u��I�v�ƌ������肷���̂��A�̈ȊO�̂��̂ł���܂���B�܂���(����)�͂Ȃ��ƌ����܂��Ă��A�����l�̐S�����̂́A�ЂƂ��ɂ��̐��̒��ׂɂ��̂ł���܂��B�������Œ��ׂƂ����̂́A�����ĝn�������������̂��Ƃł͂���܂���B���R�ƗN���o�Ă��鐺�A�����u���I�v�ƌ����A�u��I�v�ƌ����Ă��A��т̐��͊�т̊���o�A�߂��݂̐��͔߂��݂̊���o��Ƃ�������ɁA���l�̎��ɂ͋�ʂł�����̂ł���܂��B����ʒ��ׂƌ����̂ł���܂��B
��ΐ^���u���t�W���A�w�Ԃׂ��B��̉̕��v
�Êw���w�Ԃ����ɌÑ㐸�_�͖��t�̘a�̂Ɍ���ċ���A�a�̂𐳂�����������K�v������B�a�̂̒��_�́u�V�Í��W�v�ł���ƌ���������ɂ����Ė��t�W�͊w�Ԃׂ��B��̉̕��ƌ������B���t�́u�܂��炨�Ԃ�v�𒆐S�Ƃ��閜�t�_��W�J�����B
�����b���u�������Ɖ́v
�u���i�v�A�u����v�Œm�I�ȐS�������Ȃ��B�S���̂āu���v�͕���B
����i���u���ט_�v
�̂́u�S�v�{�u���v�{�u���v
�������͉̂r�ނׂ��A���ׂȂ��͉̂r�ނׂ��炸�B�ŏ�̉̂Ƃ͍ŏ�̊��������������̂��B�ŏ�̊����Ƃ͒[�I�̊������B�[�I�̊����Ƃ͑���ہB����ۂ����̂܂܂ɐ��������ƕ\������̂����Ȃ킿���ׂł���B�u���v�͐��Ƌ��Ɉڂ�ς���čs�����l�̐S�ɐ��ނ���̂́u���ׁv�����ł���B�u���v�^�S������u���v�͒����ɓ�����B
�Ȍ�A�����q�K�̒Z�̂̋ߑ�Z�̂ɂȂ���̘_�u�̉r�ɗ^���ӂ鏑�v��
�̂��w�ԍۂ̐S��
�a�̂ɂ͎t�Ȃ��i��������j
�É̂��A���t���A�V���������ꂽ�̂ւ̗B��̓�����
�݂̂͂Â�������̂Ȃ�@�i��������j
�u�̂��C�Ƃ��铹�̂�́A�Ǐ��〈�����L�߂�悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���̂�̐S����N���N����A��������̂ł���v
�m�Â̕K�v�@(�������j
�a�̂���ނ��Ƃ́A�K�������w��œ����m���ɂ���ĂłȂ��A�����S�̒�����N���邱�Ƃ��Ɓi��B�́j�\��������ǂ��A�̂̏�������K�����ƂȂ����ẮA���\�̕]���邱�Ƃ͓���B
�̂̎��ɂ���
���̗p�́@�i�`��������j
�a�̂ɂ����Ă̏d�厖�́A���̑I�ѕ��\�\�ǂ��p���A�ǂ���̂Ă邩�\�\�Ƃ������Ƃł���܂��傤�B
�p���ׂ����@�i�������j
���ЂƂ��É̂ɂ���悤�Ȏ����g���ׂ��ł��B�A���A�����ǂ��悤�Ȏ��́A����ȑO�ɉ̂ɂ�܂ꂽ�Ⴊ�����Ă��A�g���Ĉ����͂��͂���܂���B����̉̂̒��ɂ͂��������Ⴊ�����̂ł��B�܂��A�Â��̏W�ɂ��邩��ƌ����āA���͒N����܂Ȃ��悤�Ȍ��t����ׂ��肵����A�����ɂȂ�̂������ł��B
�̌�ɂ��ā@�i�����ؐM�j�j
�]��̌�Ȃǂƌ��āA�������鎖�������B����X�ɐV��⑭�������ɂ��y�ʁB�����̂炵���Ɖ]�ӂƂ����Y�ꂸ�ɐS�����āA���R�Ɍ��p���悢�B�����ē��ɕ������ӂ��đ����̌���L�����A��b��L���ɂ��Ă����A���̎��ɗՂ�ŁA����ɑ�������������R���݂ɋ�g������l�ɂȂ�˂Ȃ�ʁB��ɏ]���̌�̂����ɂ��A��ۂ̖��炩�Ȍ��I��ŗp���₤�ɂ������B���ׂ̈ɂ͑����̌Ì�̐��m�ȈӋ`�ƁA�p��Ƃɒʂ���K�v������B�����ĔV���͑����ǂݑ�����ċ��邤���ɒ��ӂ��ւ��ċ���Ύ�������ė���B
�ǂ��̂Ƃ�
�̂͐����ɂ���ėǂ����������Ȃ�@�i�����r���j
�̂͂����A���ɏo���ēǂ�r�����肵�Ă݂�ƁA���ƂȂ��D���ɕ�������A���[���������肷�邱�Ƃ�������̂ł��B���������u�r�́v�ƌ����悤�ɁA�����ɂ���āA�ǂ�����������������̂Ȃ̂ł��B
�S�͐V�������@�i��������j
�i���Ƃ�)�͒����N���g���Ă�������炢�A���e�E���͍��܂łɂȂ��V�����������A�y�т��������z�̎p������āA�����ȑO�̉́i���F�Í��W�̂�ݐl���炸�̂�A�Տ��E�ƕ��E�����ȂǘZ�̐厞��̉̂��w���Ǝv����j����{�Ƃ���A���̂�����ǂ��̂��o���Ȃ��킯������܂��傤���B
�S�Ǝ��@�i�`��������j
�S�Ǝ��Ƃ����˔����Ă���悤�Ȃ̂�ǂ��̂Ɛ\���ׂ��ł��傤�B�S�Ǝ��̓�́A���̍��E�̗��̂悤�ȊW�̂͂����Ƒ����܂��B�����A�S�E���̓�����˂Ă���̂����z�ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂��A�S�������Ď��̍I�݂ȉ̂��́A�S�������Ď��̂��Ȃ��̂̕����܂��ł��傤�B
�ǂ��̂Ƃ͐S�̐[���̂ł���@����
�\�[�i�H���[�E���R�[�E���[�E�L�S�[�E�����[�E���[�E�ʔ��[�E�L����[�E�Z�[)�̒��ł́A�ǂ��[�ɂ��Ă��A�L�S�[��肷����Ęa�̖̂{������Ă����[�͂Ȃ��Ƒ����܂��B�����[�������̂͑�ϓ���̂ł���܂��B���ꂱ��ƍl�������炵�Ă��ẮA���炳��r�݂���������̂ł͂���܂���B�悭�悭�S�܂��āA��̋��n�ɖv�����Ă����A�܂�ɉr�߂邱�Ƃ͂���܂��B�ł�����A�ǂ��̂Ɛ\���܂��̂́A�ǂ̉̂ɂ��Ă��A�S�̐[���݂̂̂������\���悤�ł���܂��B�������܂��A���܂�ɐ[���S�����悤�Ƃ��āA�Ђ˂�߂���A�u����ق��̂��肭��́v�ƌ����āA�܂Ƃ܂�̂Ȃ��A�킯�̕�����Ȃ��̂ɂȂ�A����͐S�̖����̂�������Ɍ��ꂵ�����̂ł���܂��B���̋����킫�܂��邱�Ƃ������ւ�厖�Ȃ��Ƃł���܂��B�d�X�悭�悭�l�����Ȃ���Ȃ�܂���B
���ۂ̉̂̍���
�܂��S�܂��@�i�`��������j
�̂ɂ����ẮA�܂��S�܂��i�������A�W��������j���Ƃ́A��̂Ȃ�킵�ł��B�����̐S�ɓ����D�܂����v��ꂽ���ł��̂ł�����A�����O���ɒu���āA���̗͂���ĉ̂��r�ނ̂��X�����B
�������p���ʼnr�ށ@����
���肻�߂ɂ����𐳂����������ĉr��ł͂Ȃ�܂���B
����͍Ō�Ɍ��߂�@����
�̂̍ŏ��̌ܕ����́A�S�̂�[���l���āA��Œu���̂��X�����̂ł��B
�̂͏��傩�珇�ɍ����̂ł͂Ȃ��@�i������j
�̂�n��Ƃ��ɁA�ŏ��̌ܕ������珇�ɂ�݉������ȂǂƂ́A���Ƃ��l���Ă͂Ȃ�܂���B�����łȂ��A�̂���̏K�킵�Ƃ��ď���������Ă���܂����̂́A�܂����̎����̋���悭�v�O���Đ����܂��B���̂��ƁA���傩��l���߂��炵�܂��B���Ă��̂��ƂŁA�ŏ��̌ܕ������A�S�̂̃o�����X�ɓK���悤�ɁA�悭�悭�l���Ē�߂�̂���낵���Ƃ̂��Ƃł����B��傩�珇�X�ɉr��ł䂭�����ɁA�����キ�Ȃ邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���̂��߂̗p�S�Ǝv���܂��B
��r�ɂ���
��r�̂����߁@�i�����ؐM�j�j
�×��̉̑�́A�����Ԃ̉̐l�̌o���̊ԂɁA�����̑I������Đ����ė������̂ł���B���Ӗ��Ō��ւA�×��̉̑�͌����Ė������邱�Ƃ��o���Ȃ��B��ɏ��w�҂͂܂Â��ꂩ�����̂��K���ł���B�i�����j
���w�҂�����ׂ̈ɂ́A�܂Îl�G�̑肩��r�ނ̂��悢�B�l�G�̕����Ɋւ����̂́A���f�N�������������鎖�ʼnr�݈Ղ��B���ɂ͎G�̑���r�ނ��悢�B�i�����j
���w�̐l�́A�܂ÉԂƂ��A���Ƃ����ӁA���ʂ̑�ɏA���āA�����܂Ŏ��R�ɉr�ނ̂��悢�B
��r��̐S���@�i�`��������j
��̎����㉺�̋�ɕ�������ł����A�ꎚ��i�u�ԁv�u�g�t�v�ȂLj�ꂩ�琬���j�̏ꍇ�́A���̌����ɉ���ɕ\���ׂ��ł���܂��B��O���ȏ�̑�i�u�����v�u�̋��ԁv�u�����t�]�v�̂悤�ɓ��ȏ�����ѕt������B����ɓ����j�̏ꍇ�́A�e����㉺�̋�ɐU�蕪���Ēu���ׂ��ł��B����̊e�����ӏ��i��傩����̂ǂ��炩��j�ɂ܂Ƃ߂Ēu���͍̂ł����ނׂ����Ǝv���܂��B�Â��ďG��ȉ̂̒��ɂ��A���̂悤�ȗႪ���邱�Ƃ͂���܂����A��{�ɗp����ׂ��ł͂���܂���B���ꂮ��������Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃł���܂��B�������܂��A���ɂ悭�o���Ă���̂ɂ��ẮA����ɑ�̌ꂪ�u����Ă��Ă��A��O�Ƃ��ċ������Ǝf���Ă���܂��B
�y�⑫�z�Ⴆ�u�g�t�v�Ƃ�����ꂩ��Ȃ����o���ꂽ�ꍇ�A�u�g�t�v�̌�͉���ɒu���̂��]�܂����Ƃ���Ă��܂��B����́A�ʏ퉺��ɎR�ꂪ����Ƃ����Z�̂̌`�����v�����邱�Ƃł���A���ɂ��Ȃ����������Ǝv���܂��B�܂��u�̋��ԁv�̂悤�ȑ�̏ꍇ�́A�u�̋��v��\����Ɓu�ԁv��\������㉺�̋�ɐU�蕪����̂��ǂ��Ƃ���Ă��܂��B�Ⴆ�ΐ�ڏW�̕����x�́u�̋��ԁv���ɂ������́u�����Q���u��̓s�͂���ɂ���̂Ȃ�����R���������ȁv�̂悤�ɁB���������ۂɂ͂������������Ɉᔽ����G�̂��������Ƃ������ł��B��Ǝ��g�A�Ⴆ�ΐ�ڏW�Ɍ�����u���J�v�ꎚ��̉̂Łu���J���^���̌��[�̂قǂȂ��ɂ₪�Ă������錎�̂������ȁv�Ƒ�̎�������ɒu���Ă���A����������͖����ɉɂ�����܂���B���قNjC�ɂ���K�v�͂Ȃ��ł��傤���A�S�̕Ћ��ɂ͗��߂Ă������ق����ǂ���������܂���B
�ޑz�������@�i�����ؐM�j�j
�����͓̂��N���r�ݗ����̂ŁA���Ԃɂ��̂Â���ޑz�Ƃ��ӂ��̂��o���ċ��āA�Ԃ̉̂Ȃ甒�_�Ƃ܂��ւ�Ƃ��A�~�Ȃ�ΈÖ�ɍ����Ƃ߂ĒT��Ƃ��A�Ε�Ȃ�Ή��ɂ����Ȃ��ԂɔN�̕�ꂽ�̂��ɂ����Ƃ��A���Ɗ���̂₤�Ɍ��ċ���B���w�҂��̂��r�ނɏA���Ă��A�z�����ӕ��ɗ����邱�Ƃ́A���߂���x�����˂Ȃ�ʁB�ޑz������r��ŋ���ƏI�Ђɂ��̂������o�鎖���o���Ȃ��ȂāA�������Ȍ����̉̂�������₤�ɂȂ�B�������߂���ł���B��������ł��A���߂��炻�̍l�ŁA�×��̗ޑz�Ɋׂ�Ȃ��₤�ɁA���ł��������^�Ɋ����������̂ӂ₤�ɂ��˂Ȃ�ʁB
�Z�̂̊Ϗ܁^�̘_
�F�X�ȉ̐l�̉̂�����ɂ��Ăǂ̂悤�ȓ_�ɒ��ӂ����Ă䂯�悢���A�����_���Ɏ��グ�܂����B
���̂��Ƃ͉̂��r�ނ̂ɂ��Q�l�ɂȂ�͂��Ȃ����B
���т����������܂��Z�̂̒��Ō㐢�Ɏc���Ă䂭�̂͂����͂��ł��낤���l���S�̋Ր��ɐG�꓾��|�p�Ƃ͑f���炵���A�A�܂����Ǝv��
�̂͂ǂ����č��B�����ƊρA�����ƈ����A�����ƕ������߂č��B�Ȃɂ��B�^�����B
���s
�̂͑����@���i���j�̐^�̎p�Ȃ�A����Έ��r��ł͈�̂̕�����グ��v���A�閧�̐^����������v�����v�B
�u�a�̂͂���͂����r�ނׂ��Ȃ�B�Í��W�̕��̂�{�Ƃ��ĉr�ނׂ��B���ɂ��G�̕�����Ɍ���ׂ��B�A���Í��ɂ����ʑ̂̉̏��X����B�Í��̉̂Ȃ�ƂĂ��̑̂��Ήr�ނׂ��炸�B�S�ɂ��t���ėD�ɂ��ڂ������̂̕������r�ނׂ��v
���
��̉̂ɂ͖��l�������̂ӂ邳�Ƃւ̎v������������Ր�������
���h�ȉ̂�ǂދC���Ȃ�����A����Ȃ����t�ʼn����Ȃ��o������S�̓������r�����Ƃ��o�����B�t�̕��w�������Z�̂��A�����l�X�̓���̐S�̓����������������̂֍L���A100�N��̍��ɑ����Z�̂̃X�^���_�[�h�������
�t�A�a�C�A�n�R�A�]���A�s��̌ǓƁA�Љ�ϊv�̈ӎ��A�Ƒ��Ƃ������ߑ���{�́A�����Č���ɑ����d�v�Ȏ�肪�S�������Ă���
�Z�̊Ϗ܂̃|�C���g
�Z�̊ӏ܂̎���
��Ȃ��Ƃ́u���v�u�ǂ��Łv�u�ǂ������Łv�u�Ȃ��v������̂���z�����A�Ȃ�ׂ���̓I�ɃC���[�W���Ȃ���A��҂̊����̒��S��ǂݎ��A���������������̌��������̂悤�Ɏ������邱�Ƃł��B����ɂ͐��ɏo���ēǂ݁A���Y���≹�𖡂킢�Ȃ���C���[�W����̂��悢�Ǝv���܂��B
�@�ȏ�̊ӏ�̒��ӓ_��^�Ӗ쏻�q�̎��̒Z�̂Ŋm�F���Ă݂܂��傤�B
�@�@�@���̎q��\���ɂȂ���鍕���̂�����̏t�̂�����������
�@ ����@�̌��~�߂��ڈ�ɂȂ�A�����ł��B����������������ƂɂȂ�܂��B
�A ���]���@�u�Z�������v�ŏ��傪���]��ł��B���Y��������A���ʓI�ɋ�������܂��B
�B ��������@�����ʂɂ���Əȗ����|�u���Ȃ��A�u���ɂȂ���鍕���́v�Ɓu������̏t�́v�Ƃ����ꂼ�ꌋ��́u�����������ȁv�ɂ������Ă����āA�܂Ƃ܂��Ă��܂��B
�C �~���@����́u���ȁv�ŏ����~�߂ɂȂ��Ă��āA�r�Q��\���Ă��܂��B�B�̂�����ƍ��킹�čl����ƌ���́u�����������ȁv���̂̒��S�ł��邱�Ƃ�������܂��B����ɁA���]�����̂��Ƃ����킹�čl����ƁA����ƌ���ɉ̂̒��S������Ƃ�����ł��傤�B
�D �����@����̕ꉹ�̔z��ׂ�Ɓu���̎q��\�v�ł�����u�I�I�I�A�A�A�v�ɂȂ��Ă��܂��B���ɏo���ēǂނƁu��\�v�������A�傫����������Ă���悤�Ȋ������Ȃ��ł��傤���B
�@�u�A�G�C�I�E�v�̏��Ŕ������Ă݂�ƕ�����܂����A���̊J�������������ɂȂ��Ă����܂��B����ɏ]���ĉ��̈�ۂ͑傫���͂����肵���u�A�v���炾��������������ۂ́u�E�v�ւƕς���Ă����̂�������Ǝv���܂��B���̂悤�ɍl������u�A���E�v�́u�����Áv�u������v�Ƃ�����ۂ������Ƃ�����ł��傤�B�������A���̂悤�Ȉ�ۂ͂����܂ł���r���đ��ΓI�ɂ����邱�Ƃł����āA�u�w�A�x����ΓI�ɖ��邢�v�Ƃ��u�w�E�x�������͕̂K���ア�v�Ƃ�������킯�ł͂���܂���B
�@�u��\�v�����ɖ��邭�A�����A�傫����������Ă���悤�Ȉ�ۂ��������Ƃ��Ă��A����́u���̎q�v�̂��Ƃɂ��邩��ł��B�u�I�I�I�v�ƕ����݂̌��ŎO�������������ƂɁA�}�ɖڈ�t�����J���āu�A�A�A�v�Ɓu�A�v�����O��A�������邩��ł��B���̑Δ䂪���̂悤�Ȉ�ۗ^����̂ł��B����ɁA���̂��Ƃ����Ɂu���ɂȂ����v�Łu�N�v�ƈ�C�Ɍ������������邱�Ƃ��u��\�v����ۂÂ���̂ɖ𗧂��Ă���Ƃ�����ł��傤�B
�@����ƌ��傪��������Ă��܂����A���̂Ȃ��ł��u��\�v�����ɑ厖�Ȍ��ł��邱�Ƃ��킩��Ǝv���܂��B�܂�A���̉̂́u���̎q�v�����������Ƃ��r�̂ł����A����ɏ����̔��������r���̂ł͂���܂���B���̔������͓�\�˂Ƃ����N��̎��̏����̋P�����r���̂Ȃ̂ł��B
�@���̂ق��̔����ׂ�Ɓu�́v���������ƂɋC�Â��܂��B������ꉹ�ׂ�Ɓu�I�v���͎��ɋ����o�Ă��܂��B�O�\�̂����̋㉹���A�������l��i��\�܉��ځj�܂łɏW�����ČJ��Ԃ��o�Ă��܂��B����͉�����\���������̂ł��傤���B�����炭�������u�Ȃ����v�l�q���ے��������̂ł��傤�B�u�I�v���̔��������������Ƃ����Ă���悤�Ɋ������܂���ł��傤���B
�@����͂Ƃ������A�u�́v��u�I�v���̔����͖{���ɈӐ}���ꂽ���̂ł��傤���B���R�ł͂Ȃ��̂ł��傤���B����͋��R�ł͂���܂���B���������O�\�����Ȃ��̂ł�����A��҂͍אS�̒��ӂ��Č��t�≹��I�т܂��B�܂��A���̉̂̏ꍇ�u�Ȃ���鍕���́v�́u�́v�́u�́v�ł��邽�߂Ɂu�����������ȁv�ɂ������Ă����̂��킩��ɂ����̂ł��B�Ⴆ�u������v�Ƃ��u������v�Ƃ������悤�ɐ��Ă��܂����ق����͂邩�ɈӖ��͂킩��₷���Ǝv���܂��B���̂킩��₷�����]���ɂ��Ă��A�����ƍ�҂��S�̗̂�����厖�ɂ��Đ�Ȃ��悤�ɂ����̂ł��傤�B
�E ��g�E�ے��@�u������̏t�̂����������ȁv�́u�t�v�͎��ۂ̏t�Ƃ����G�߂������Ă��܂���B��\�̎����̔��������t�̃C���[�W�ŏے����������̂ł��B��\���l���̏t���ƍl���Ă��悢�ł��傤�B
�@�u�Ȃ���鍕���́v�́u�����v�͎��ۂ̔��̔��������r�ݍ����̂ł����A����������̔��������ے����Ă���ƍl�����܂��B���������������Ɖr�킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B�������������ő�\�������̂ł��傤�B���̂悤�������������ɑ�\�������\������Ɋ��g�Ƃ����܂��B���Ƃ��A�w�̍����l���u�̂��ۂ���v�ȂǂƌĂсA���̐l���g���w�������̂Ɠ����ł��B
�F �C���[�W�@���̉̂̒��ɂ͑Η�����C���[�W���r�ݍ��܂�Ă��܂���B�������A�V�N�Ŏ�X�����C���[�W�œ��ꂳ��Ă��܂��B�Ⴆ�u�Ȃ���鍕���v�͔��̔����ł͂Ȃ������Ȃ̂ł��B����͂���Ɂu���v�Ƃ��������Ⴓ�������ł���ł��傤�B����Ɂu�Ȃ����v�Ƃ������ƂŎq���̂悤�ɒZ���Ȃ������Ƃ������Ƃ��������ƂŁA���n�����Ⴓ���Ƃ������Ƃ��킩��܂��B
�@�܂��A�u������̏t�v�͉Ăł��H�ł��~�ł��Ȃ��t�Ȃ̂ł��B�u��\�v�u�Ȃ����v�u�����v�u�t�v���C���[�W�Ƃ��ĂƂ炦��ƁA�̑S�̂Łu���n������X�����������v����т��ċ������Ă���Ƃ�����ł��傤�B
�G �����̕\�L�@�ӂ������ŏ����u�Ȃ����v�u�����������ȁv���Ђ炪�ȕ\�L�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȃ��͍̂�҂ɈӐ}������܂��B�ǂ���������ŕ\�L��������A���Ȃ₩�Ȉ�ۂ��c���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�����v�͉搔�������d�X�����̂ŁA�͋�����������Ƃ���A�u���̎q�v�̔������͂��Ȃ₩�A���A�͋������̂��Ƃ�����ł��傤�B
�H �a�̂Ƃ̈Ⴂ�@���͉̉̂���I�ɐV�������̂ł����A���̐V�����͉̂̓��e�ɂ���܂��B�܂��A�������������Ɖr��ł��܂������Ƃ͏Ռ��I�ł����B������u���̎q�v�Ƃ����悤�ɋq�ϓI�ɂƂ炦�Ĕ������Ƃ����̂ł���������ł��B�͂����肢���āA���䂩�����̂�������Ȃ�����������������ł��B
�@����ɁA�����̕����̒��ł̂��ƁA����������Ƃ����Ă��邱�Ƃ��r�̂��A�Ռ��I�ł����B���ς�d�Ԃ̒��ł���l�������悭�������錻��ł͕�����ɂ������o�ł����A�����͂��̂悤�Ȏp�͐�Ό�����ׂ����̂ł͂Ȃ����A�����Ă������Ȃ����̂������̂ł��B�܂�A���̉̂͌����ɂ���ẮA���i�ŁA�p�m�炸�ŁA�݂��Ƃ��Ȃ��̂Ȃ̂ł��B
�@�������A�����̒j���͂��̉̂�ǂ݁A��i��z�����ăh�L�h�L�������ƂƎv���܂��B�܂��t�ɁA��҂̗���ɂȂ��čl����ƁA���̂悤�Ȏp���̂ɉr�ނ��Ƃ͑�ςȗE�C���K�v�������Ǝv���܂��B�Ȃ��Ȃ�A�����Ŕ����Ƃ����p���������Ɖr�ނ��Ƃ͂���܂ł̔��ӎ��i����������Ƃ��邩�Ƃ������Ɓj�ȂǁA�a�̂̓`����A�Â������⊵�K�ɔ��������킷�邱�Ƃ��Ӗ����邩��ł��B�Ƃɂ�����_�ȍs�ׂł���A����I�Ȃ��Ƃ������̂ł��B�ł����炫���Ə������h�L�h�L�����Ǝv���܂��B
�̂̎�`�I����
�����Ώd�A������`�Ȃǂɑ������ςɏd������������A�̉^���ł���A�ÓT��`�Ƒ��Ȃ��B�����^���A�����ӎ��̍��g�A�����ւ̓��ۂƂ����������������A�ߑ㍑�����ƌ`���𑣐i�����B���̓����͕��|�E���p�E���y�E�����ȂǗl�X�Ȍ|�p����ɋy�B�̂��ɁA���̔����Ƃ��Ďʎ���`�E��ς��d������Q���I�ȒZ�̂�ڎw���A�^�Ӗ�S�����y�o�����B����33�N�i1900�N�j�A�S���́w�����x��n�����A�^�Ӗ쏻�q��i���ĘQ����`�Z�̂̑S�������z�����B����40�N��ɂ́w�����x����o���^���h�̖k�����H�A���R��`�I�Ȏ�R�q���A�Љ��`�I�X�����������ΐ���̌����J�Ԃ����B
�^����`
�����I�ł��邱�Ƃ�P�ł��邱�Ƃɉ��l��u�����ɁA�u���ł���v���Ƃ݂̂ɉ��l��u���A�s�����E���ł��邱�Ƃ𗝗R�ɔے肷��悤�ȏ펯�������Ȃ���`�ł��B
�^����`�҂́A�O���R�I�v�̍Ŋ����A�u���������ɕ��������v�Ǝv���B
�J�菁��Y�@�O���R�I�v�@�k�����H
���R��`
�P �N�w�ŁA���R��B��̎��݁E�����Ƃ��āA���_���ۂ��܂ވ�̌��ۂ����R�Ȋw�̕��@�Ő������悤�Ƃ��闧��B
�Q �ϗ��w�ŁA�����Ɋւ��鎖�ۂ�{�\�E�~�]�E�f���Ȃǐl�Ԃ̎��R�I�v�f�Ɋ�Â��Đ������闧��B
�R ���w�ŁA���z�����s�킸�A�X���Ȃ��̂�������A����������̂܂܂ɕ`�ʂ��悤�Ƃ��闧���B19���I�㔼�A���R�Ȋw�̉e���̂��ƂɃt�����X�𒆐S�ɋ��������̂ŁA�l�Ԃ��Љ������w�I�����ɏ����Â�������̂Ƃ��ĂƂ炦���]���Ȃǂ���\�I�B���{�ł͖���30�N��ɂ����炳��A���蓡���E�c�R�ԑ܁E���c�H���E���@�����炪��\�B�����A���Y�����w
����w�ŁA�l�Ԃ̎��R�̐�����d�A���̉~���Ȕ��B������̖ړI�Ƃ��闧��B���\�[�̒B
��R�q��
�i����炬�j�͓��{�̒Z�̌��Ў��B1903�N�i����36�N�j�Ɉɓ�����v���͂��߂Ƃ��������q�K�剺�̉̐l�炪�W�܂������ݒZ�̉�̋@�֎��w�n���x�������Ƃ��A1908�N�i����41�N�j�ɍ���v��n�^��Y�𒆐S�Ɂw�����X�x�Ƃ��đn���B���N�A���ؐԕF���n�������w�䖴�C�x�ƍ������A�w�A�����M�x�Ɖ��肳�ꂽ�B�Ǝ��̉̕����m�����ăA�����M�h���哱�������ؐԕF��A��������߂Đ������قƂ���̂��r���֓��g���o���B�w�A�����M�x�͐ԕF���ҏW��S�������吳���ɉ̒d�嗬�ƌ����Ă������W�𐋂���
���A�����M�h
�X�g�C�b�N�ȉ̕�����F�Ƃ��邻�̔��w�ƌ��ГI�����͈ꕔ�Ŕ����������A�吳13�N�i1924�N�j�ɌÐ��~�A��狋��A�Ό������V�G���w�����x�̑n���ɎQ�����āw�A�����M�x�𗣒E����ȂǁA�w�A�����M�x�̕���ݏo��
�Z�̂̍����@����
�P�D�A�X�g�[���[��c��(5W1H�j
�@�P�����ǂ�
�u�`����ˁv�`�������A�����ł��邩
�u�����Ȃv�����������Ƃ�
�u�Ԃ̊�����Y�ꂸ�Ƀ������Ă���
�傫����ʂ��珬�������̂�
��̂��̂�g�ݍ��킹��
��������������r��
�ŗL�����𒆐S�ɂ�����Ό��I�ȉ̂ɂȂ�
���퐶���̒��ł��邨��������
��ό� �E����I�Ȍ��t�͂Ȃ�ׂ�������
�Q�D�Z���ɂ܂Ƃ߂�
�R�D�Z������ɕϊ��@
�@����̋�ɕϊ������בւ�
�@�Q����P��Ɍ���������ɂ́i�œK���j
�@���ɁA�����͖�����
�S�D�C���Z�@�͎g���Ȃ���
�T�D�T�V���i�j���I�j�A�V�T���i�����I�j�ǂ���Ɂi���q�A���Y���́j
�U�D�P��ɂ܂Ƃ߂�
�V�D����
���̑��̏��
�W�D�u�o��I���z�v�@��荇�킹�ɕs�v�c�ȗ́@
�@�i��j�@�D���̈�����俁i���݂�j�̏������ȁ@�t�����������Ă������̒��@�@�D����俁@�t���Ə�
�������������A���z��T�Ɂ@�������̕�炵�̒��ɂ����ĕs�f�ɔ�����K�������o���Ă���
�ȏ�^�V���̔o��R�[�i�[��蔲��
�X�D�Z�̂��r�ޏ�ŋC�ɂȂ錾�t
���сA������i�����̈Î��j�@�Z�̂̏�ׂ݂̍͌����C���֗~���琶�܂��h��̌����ł͂Ȃ��B�ق����܂܂ɕ����Ēu���Ď����N�R�Ƃ��ē��������A�S�𗩁i�����߁j�ߋ���u�Ԃ̉e�@�E�E�E�܌�
��炬
�C�荇�킹
�����@���q�̒�������ɒP�����~���Ȑ܂̂��邱��
�Â����A�����݁A���Ȃ₩���A�������A�S�苭���@�Ȃǂ��������Ă��邩
��M�@�\���̋�Y��ςނق��ɁA�B��̈�������@���A�Z�H�̏�ǂ�˔j������ł��낤�B�Ñ㎍�ɒ��������ꂽ��M�ł���B���̌������������A�\���̒i�K���ꋓ�ɔ���߂�
�[�����ȁA�Â��ȊϏƂ���A�Ђ������������Ђ��o���l�ɂ��鎖���A�X�ɉ̂��悭���A�l�ԂƂ��Ă̐[�݂������邱�ƂɂȂ��E�E�E�܌�
�Z�̂͒��ׂ̈�{�����i�Z�̂��U���ƈႤ�B��̕����j
�C���́A���̒��q�����Y�~�J���ɂȂ�悤�ɁA���܂������ԂɂȂ�ׂ邱�Ƃł��B���́u�C���v�ɂ͑傫�������ĂQ�̎�ނ�����܂��B
�@�P�j�u�T���v�Ɓu�V���v�ł��낦��Ƃ������́i���������j�B
�@�Q�j�ŏ����Ō�̉������낦����́i�����C�j
�̂ɂQ�ɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B
������ȁA���Ȃ���ނ�
�@
���Ђ� ���j�I���ȂÂ��Г���
���㉼�����Ђ���j�I�������Ђɒ����Ƃ��̌���
![]() �������A����
�������A����
| �匴�� |
�@�a��̌��㉼�����Ђ���j�I�������Ђɒ����Ƃ��̑�܂����匴���͎��̒ʂ�ł���B
| ���㉼�������ŕ��͂������Ă݂ĉ������B
���̒��Ɂu��A���A���A���A���A���A���v�̉���������܂����B �Ȃ����͂��̂܂܂ł悢�̂ł��B |
��̓I�ɂ����ƁA���㉼��������
�@�u���v�A�u�C�v�A�u�E�v�A�u�G�v�A�u�I�v
�@�u�I�E�v�A�u�R�E�v�A�u�\�E�v�A�u�g�E�v�A�E�E�E
�@�u�W�v�A�u�W���v�A�u�W���v�A�u�W���v�A�u�Y�v
�@�Ə����������������j�I���������ŕʂ̉����ɂȂ�\��������̂ł�
�����ꓪ�ȊO�́u��A���A���A���A���v���u�́A�ЁA�ӁA�ցA�فv�Ƃ���B
���u���v���u�Áv�Ƃ���B��ꓪ��@�@�@�@||��@||���@||���@||���@||���@||
��ꓪ�ȊO��@||���@||���@||���@||���@||���@||
||���@||
||���@||
||����||
�@
�@
��ꓪ��
�ꓪ�́u���v�Ɓu�E�v�͂��ׂāu��v�Ɓu���v�B
��O
�@��@�@�a���@�@���䍂�@�@�c�Ɂ@�@���@��@�@�В���@�@�������@�@����
�@�@�i�u�C���b�V�����A�C���b�V�^�A�C���V�^�A�C���V�e�v�Ȃǂ́u���v�ł悢�B�R���́u����@���点���v�B�j
�@�@�i����u�݂��v�́u���܂��v�B�u���i��j�܂��v�Ƃ͕ʂ̌�B�j
��O
�@�G�@�@�`���@�@����@�@�P��@�@�a�@�@�݁@�ށ@�@�����W��
�@�@�i�u���E�v�́u��Ӂv�B�u��Ӂv�͌Ì`�B�j
��O
�@���@�@���@�@���@�@���i���Ёj�@�@�I�ւ�@�@�Y�X�i�����j�����@�@�u�@���@�@����
�@�@�@�Ƃ��@�@�q�ށ@�@���@�@���@�@�������܂����@�@���R�[�@�@���@�@���������@�@�c��
�@�@�@���߂�@�[�@���@�C�@�@�f���@�����i�����j�@�@�ɂ����@�@���ւ�@�@��������
�@�@�@���V�h���@�@�Y�@���@�@���͂�@�@�v�@�@�j�@�@�����i���ƂƂЁj�@�@���N
�@�@�@�����i���Ƃ߁j�@�@���@�@�x��@�@���@�@���̂̂��@�@�f��@����@������@�@���~�i�w�V
�@�@�@�B�@�@�܁@�@�܂�@�@����@�@�����`�@�@�I�͂�@�@��
�@�@�u�I�E�v�́u�I�v���u���v�ł�����́B
�@�@�@���ӂ��@��@�@���ӂ��@�����@�@���ӂ݁@�ߍ]�@�@�����݁@�C�@�@�����߁@�~
��ꓪ�ȊO��
��O
�@���I�����́u���v�́u��v�B�i�W�����u�́v�Ƃ͕ʁj
�@�@�@�`����@�@�`�킢�@�@�`��ˁ@�@�Q�V�����Y�ꕨ�����@�@�o���o���@�@�Ȃ�
�@�@���̑��u��v�ł�����́B
�@�@�@����@�A�@�@���킽�������@����Ă�@�Q�@�@���키�@�����@�@���킵�@��
�@�@�@�����@�A�@�@���킭�@���@���@�@����@�D�@�@�����@�f�@�@�����@����
�@�@�@���Ƃ킴�@���@�@���Ƃ��@�f�@�@���킢��@���F�@�@���킮�@���@�@���킴��
�@�@�@����߂��@�@����@ᰁ@�@�����@���@�@�����@���@�@���킢�Ȃ��@������
�@�@�@����ށ@���@�����@�@�͂ɂ�@���ց@�@��킢�@��
��O
���`�e������́u�C�v�͂��ׂāu���v�B�i�C���ցB�R���́u���v�u���v�j
�@�@�@�Ԃ��@�@�����@�@�������@�@�Ȃ�
�������́u�`�i�C�A�^�C�A�}�C�A���V�C�A�~�^�C�A�i�T�C�A�N�_�T�C�v�͂��ׂāu���v�B�v�C���ցB�R���́u���v�u���v�j| �����́u�`�i�C�A�`�C�^�v�ƌ`�e���́u�`�C�v�́u���v�B
��O�Ȃ� |
�u�Ȃ��v�͌Õ����i����j�ɕςւ�Ɓu�����v�u�����v�ɂȂ�܂��B
�u�����āv�u�҂����v�́u�����āv�u��������v�ɂȂ�܂��B
�u�Ԃ��v�́u�����v�u�����v�ɂȂ�܂��B
�s���Ȃ��@�@�s�������@�@�s���Ȃ����@�@�s���܂��@�@�s���݂����@�@�s���炵��
�@�@�@�s���Ă��������@�@�Ȃ�
���������ߌ`����́u�`�C�v�͂��ׂāu���v�B�i�C���ցB�R���́u��v�j
�����@�@�����@�@���Ă��@�@�Ȃ�
�������̉��`�u�C�^�A�C�_�A�C�e�A�C�f�v�́u���v�B�i�C���ցB�R���́u���v�u���v�j
�҂����@�@�炢����@�@�����ā@�@�E���ł��@�@�Ȃ�
�������́u�`�C�v�́u���v�B�i�C���ցB�R���́u��v�u��v�j
�����@�@�����@�@�킢�@�@�Ȃ�
�����u��v�s�̓����́u�C�v�́u���v�B
�i�V����A������A���@���̎O�̂��j
���C�i�̉��������������߂̔��́u���v�B
�@������Ɓ@�Ȃ�
���̑��u���v�ł�����́B�i�C���ցA�t�����A�������A��s�́u���v�ȂǁB�@�ꓪ�ȊO�Ɍ��X
�@�@�@���s�́u���v�ł�����̂͂Ȃ��B�j
�@�@�@�����@�@�����ɂ��@�����@�@���邢�́@�@�������@�@�����ς��@�@�����i�|�����j
�@�@�@�V���@�V���炭�@�V����@�@�����i�Ăт����j�@�@���������@�����@�@�����ā@��
�@�@�@�����Ł@�@������@�����@�@���ق��Ɂ@��@�@�����@�D�@�@����������@�~��
�@�@�@�������ց@��Y�@�@���������@�~�o�@�@�����܂��@�~���@�@�����܂݂�@�_�Ԍ�
�@�@�@���͂����@���@�@���͂������@���z�@�@�����@�@�`���������@�@�����@�@������
�@�@�@��������@�@�`�������܂��@�@�����Ȃށ@�Ձ@�@�����͂Ё@�K�@�@��������@��
�@�@�@�`���Ⴂ�@�@����܂��@�@�������@���s�@�@�����Ɓ@�@�����Ԃ�@�@�����܂���
�@�@�@�����@�w�@�@���������ς��@�@���������@�@����܂��@�@�����@�@��������
�@�@�@���������@�@�����ԁ@�啪�@�@�����܂@�����@�@���킢�@�����@�@���i��������j
�@�@�@���@�@�@�����@�z�n�@�@�������@����@�@�����ā@���@�@�`�ɂ���
�@�@�@���Ł@���@�@���Ł@���@�@���ށ@��@�@�`�����Ⴂ�@�@�ǂ���
�@�@�@�����Ă��@����@�@�Ȃ�������@�́@�@�`�Ȃ����@�@�ɂ�����@�Z�@�@�͂��i�Ԏ��j
�@�@�@�Ђ����@�ۛ��@�@�Ђ��ł�@�G�@�@�ӂ��i�ʖځj�@�@�ӂ����@��@�@�ւ��i�͂��j
�@�@�@�ق��ق��@�@�܂��ɂ��@�����@�@�ނ����@�Z���@�@�ނ����@��@�@�₢�i�Ăт����j
�@�@�@�₢�̂₢�́@�@�₢�@�n�@�@�킢�킢�@�@������傢
�@�@���̂��̂́u��v�ł��B
�@�@�@����@���@�@��������@���z�ԁ@�@���ʂ�@���@�@�����@�ʁ@�@�`�����
�@�@�@����Ȃ�@�g�@�@�����@���Ɓ@�@���ق���@�����@�@������@�~���@�
�@�@�@����@�ŋ��@�@����i���ׁj�@�@�Ƃ��@�����@�@�Ђ����@���@�@�܂��@�Q
�@�@�@�������@�p�@�@���Ƃ�@��
�ꓪ�ȊO�́u�E�v�͑����́u�Ӂv�B�v�i�u�E�v�ŏI�铮���́u�E�v�͂��ׂāu�Ӂv�j�ł����A
�@�@�@��O�͎��̒ʂ�ł��B�@�@�@
��O
���`�e���̊��p�́u�`���v���u�E�v�ƂȂ������̂͂��ׂāu���v�B
�@�����낵���@�@�����@�@�������i���j���@�@�Ȃ�
�@�������i��ӁA���ӁA����@���̎O�̂��j�̊��p�́u�Ёv���u�E�v�ƂȂ������̂́u���v�B��i���j���ā@�@�����ā@�@�₤���@�@�Ȃ�
�i����ł͑��̓����ł����ׂāu���v�B
�����ā@�ǂ��ā@�����ā@�@�Ȃ�
�@�������̐��ʁA�ӎu��\�킷�u�`�E�v�͂��ׂāu���v�B�i�E���ցB�R���́u�ށv�u��v�j�s�����@�@�͂��@�@���悤�@�@�Ȃǁ@
�@���i����̂�s�����́u�`�E�v�́u���v�B�A���A�Q���A�����@���̎O�̂��j�@�i�A���@�A����@�@�Q���@�Q����@�@�����@������ǁ@�@
�@���E�i�A�I�i�̉��������������߂̔��́u���v�B�@�������Ɓ@�@�ǂ���@�@�Ȃ�
�@���̑��u���v�ł������
�@�@���肪�����@�@���키�@�����@�i�u��키�v�͌Ì`�j�@�@�����Ⴄ�@��ǁ@�@�������Ɓ@��
�@�@�@�`����@���@�@���Ƃ�����@���@�@���Ƃ��Ɓ@��@�@���͂₤�@�@���߂ł���
�@�@�@���肤�ǁ@��l�@�@�`���炤�@�@���炤���ā@�h�@�@���͂������@���z
�@�@�@�����Ⴄ�@�j�[�@�@������@�ӉZ�@�@���낤�Ɓ@���l�@�@�����i�`���A���ӁA����A�Ȃ�j
�@�@�@�������������@�_�X�@�@�������@�i�q�@�@�������@���H�@�@�������@���@�@�������@��
�@�@�@���������@���@�@�����ׁ@���@�@�����ׁ@�_�ˁ@�@�����ނ�@��@�@��������@��
�@�@�@������@�s���@�@��������悤�@�@�����������܁@�@���₤�Ȃ�@�@�`���イ�@��
�@�@�@�����Ɓ@�n�@�@�����Ƃ߁@�Ɓ@�@���Ⴄ���@���I�@�@���Ⴄ���Ȃ��@�@���Ⴄ�ԁ@�Ҋ�
�@�@�@���낤�Ɓ@�f�l�@�@�����i�`���A���ӁA����A�Ȃ�j�@�@�`�����i�`���A�ȁj
�@�@�@�������������@���X�@�@������Ӂ@��@�@�������@��@�@�`���炤�@�@�`���炤
�@�@�@�Ă��Á@�萅�@�@���Ⴄ�ǁ@���x�@�@�Ă��ȁ@�蕀�@�@�`�ł����@�@�ǂ��@�@��
�@�@�@�������@���@�@�Ƃ�����@���@�@�ǂ����@�@�ǂ����@�@�����Ă��@����@�@�����Ƃ��@����
�@�@�@�Ƃ��Ɂi�����Ɂj�@�@�ǂ����@�@������Ł@�����@�@�ǂ��Ⴄ�@�D�Ӂ@�@�Ȃ����ǁ@���l
�@�@�@�̂��̂��@�@�Ђ����@�����@�@�w�E�@�^�@�@�ӂ��@���ʁ@�@�Ԃ����@�����@�@�`�͂��@��
�@�@�@�͂����@ⴁ@�@�͂��ނ�@���@�@�ق��@�{���@�@�`�܂����@�@�߂����@䪉�
�@�@�@�߂��Ɓi�~���[�g�Ɠǂޏꍇ�j�@�v�w�@�@�����i���Ɂj�@�@����[�܂��� �܂�]�i�X�Ɂj
�@�@�@�܂�����@�݁@�ׁ@�@�܂����@�\�@�i�u�܂����v�͌Ì`�j�@�@�܂��ł�@�w�@�@�₤�i�`���A�ȁj
�@�@�@�₤���@�����@�@�悤�����@�@�₤���@�l�q�@�@�₤�₭�@�Q�@�@����@���_
�@�@�@�킩���ǁ@��l�@�@���������@��؍�
�@�@����Ȃ��́B
�@�@�@�����ف@�ԕ�@�@�����݁@�C�@�@�����߁@�~
��O
�����u��v�s�̓����́u�G�v�́u���v�B�i�R���͂�s�́u���v�j
�@���܂���@�Á@�@������@���@�@���т���@���@�@���ڂ���@�o�@�@������@��
�@�@�@��������@���@�@������@�z�@�@������@��@�@��������@���@�@������@��
�@�@�@��������@�h�@�@������@�]�@�@���т���@�ށ@�@������@��@�@�Ђ���@��@��
�@�@�@�Ȃ���@�ށ@�@�ɂ���@�ρ@�@�͂���@���@�@�͂���@�f�@�h�@�@�Ђ���@��
�@�@�@�ӂ���@���@�@�ق���@�i�@�@�܂݂���@���@�@�݂���@���@�@������@�R�@�@������@�G�@
�@�@�@��������@��@�@�ȏ��\���̓����̂�
�@
���G�i�̉��������������߂̔��́u���v�B�@�@���ꂦ�@�@�����́@�@�Ȃ�
�@�@���̑��u���v�ł�����́B�i�t�����A�������A��s�́u���v�ȂǁB�@�ꓪ�ȊO�Ɍ��X���s�́u���v��
�@�@�@������̂͂Ȃ��B�j�@�@�@�������@�@���܂��@�Á@�@�������@�@���肦�@���]�@�@�`���i�l���̍]�A�}�j
�@�@�@�����i�����j�@�@���т��@���@�@���ڂ��@�o�@�@�������@���@�@�����@��@�@�������@��
�@�@�@�����낦�i��j�@�S���@�@��������@�Ձ@�@�����@��@�@�������@�h�@�@�T�U�G
�@�@�@���������@��X�@�@�Ђ��@��@�@�����@���@�@�Ȃ��@�ށ@�@�ɂ��@�ρ@�@�ʂ��@�K
�@�@�@�˂��i�Ăт����j�@�@�˂�����@�o�@�@�͂��@�h�@�@�Ђ��@�B�@�@�Ђ��@��@�@�ӂ��@�J
�@�@�@�ւ��i�͂��j�@�@�݂��@���h�@�@�������@��
�@�@�u��v�ł�����́B
�@�@�@��������@�b�@�@�����@�A�@�@�����@�Q�@�@�`��i�l���̌b�j�@�@����@��
�@�@�@������@���@�@����@���@�@�����@���@�@��@��@�@�Ƃ���@�b�@�@�قق�ށ@����
�@�@�@���@�́@�@����@����
��O
�@�u���v�ł�������B�i�ꒆ�̂₤�Ɍ����Ď��͌ꓪ�ł�����́B�@�ꓪ�ȊO�Ɍ��X�u���v�ł�����@�̂͂Ȃ��B�j
�@�͂���@�͂���@�H�D
�@�@�u���v�ł�����́B
�@�@�@�����@�@�@�������@���@�@�����@���@�@�`���i�l���̒j�A�Y�A�v�j
�@�@�@������@������@���@�@�����@���@�@�����@�Ɓ@�@�����炵���@�@������@�x
�@�@�@�������@�ށ@�@�����₩�@�@������߁@��㏗�@�@������@��܁@�@�Ƃ��@�\
�@�@�@�܂�����@�v�r�j�@�@�݂��@�Y�@�@�݂����@���@�@�߂��Ɓ@�v�w�@�@�����
�@�@�u�Ӂv�ł�����́B
�@�@�@���ӂЁ@���@�@���ӂ��@��@�@�@���ӂނ��@���@�@���ӂ�@��
�@�@�@���ӂ��@���ӂ��@�|
�����̐��ʁA�ӎv��\�킷�u�`�I�E�v�͂��ׂāu�͂��v�B�i�R���́u�͍s�������R�`�{�ށv�j
��͂��@�@���͂��@�@���͂��@�@�Ȃǂ��ׂ�
�@�@�u�I�E�v���u�키�v�ł�����́B
�@�@�@���키�@�����@�i�u��키�v�͌Ì`�j
�������i�u�I�E�A�R�E�A�\�E�A�E�E�E�A�L���E�A�V���E�A�`���E�A�E�E�E�A�L���E�A�V���E�A�`���E�A�E�E�E�v�j�ɂ���
�������̐��ʁA�ӎv��\�킷�u�I�i�{�E�v�́u���i�{���v�B���͂��@���@�@�������@�s�@�@���Ȃ��@���@�@���܂��@�Z�@�@�������@���@�@���炤�@�U
�i�������u���E�v�ł�����̂͂��̂܂܁u�悤�v�B�j�B�i�R���́u���i�{�ށv�j
�@�@�@���悤�@�@�݂悤�@���@�@�����悤�@�J�@�@�Ȃ�
�����̐��ʁA�ӎv��\�킷�u�`�I�E�v�͂��ׂāu�͂��v�B�i�R���́u�͍s�������R�`�{�ށv�j
��͂��@�@���͂��@�@���͂��@�@�Ȃǂ��ׂ�
���ꊲ���A�i�ŏI��`�e���́u�`���v�̕ω��u�`�E�v�́u���i�{���v�B
������ȊO�ɂ��u�I�i�{�E�v���u���i�{���A�Ӂv�ł�����̂�����B�u�I�E�v�́u�I�v���u���v�ł�����́B
�@�@�@���ӂ��@��@�@���ӂ��@�����@�@���ӂ݁@�ߍ]
�@�@�@�i����Ȃ����@�����݁@�C�@�@�����߁@�~�j
�@�@�u�I�E�v�́u�I�v���u��v�ł�����́B
�@�@�@���키�@�����@�i�u��키�v�͌Ì`�j
�@�@�u�R�E�v�́u�R�v���u���v�ł�����́B
�@�@�@�i����Ȃ����@�����ف@�ԕ�j�@�@�����i�`���A���ӁA����A�Ȃ�j�@�@�������������@�_�X
�@�@�@�������@�i�q�@�@�������@���@�@�������@���@�@���������@���@�@�����ׁ@��
�@�@�@�����ׁ@�_�ˁ@�@�����ނ�@��@�@��������@�啁@�@������@�s���@�@�Ȃ����ǁ@���l
�@�@�@�ނ���[�܂��� �ނ���]�i�����j�@���@�@�킩���ǁ@��l�@�@���������@��؍�
�@�@�u�S�E�v�́u�S�v���u���v�ł�����́B
�@�@�@�܂��Ӂ@���@�݂܂��Ӂ@����
�@�@�u�\�E�v�́u�\�v���u���v�ł�����́B
�@�@�@���͂������@���z�@�@�����i�`���A���ӁA����A�Ȃ�j�@�@�`�����i�`���A�ȁj
�@�@�@�������������@���X�@�@������Ӂ@��
�@�@�u�g�E�v�́u�g�v���u���v�ł�����́B
�@�@�@���肪�����@�@���߂ł����@�@�������@��@�@���䂽�Ӂ@�h���@�@�������@��
�@�@�@�����Ă��@����@�@���ӂƂ��@���ӂƂԁ@���@�@�����Ƃ��@�����@�@�Ƃق��ӂ݁@���]
�@�@�@�ӂ��̂����@�����V�@�@�ق��@�{��
�@�@�u�h�E�v�́u�h�v���u���v�ł�����́B
�@�@�@������Ł@�����@�@�Ԃ����@�����@�@����@���_
�@�@�u�z�E�v�́u�z�v���u�́v�ł�����́B
�@�@�@�`�͂��@���@�@�͂����@ⴁ@�@�͂ӂ͂ӂ̑́@�@�͂��ނ�@���@�@�͂ӂ�@��
�@�@�u���E�v�́u���v���u�܁v�ł�����́B
�@�@�@���܂Ӂ@���o�@�@�`���܂Ӂ@���@�@�܂�����@�݁@��
�@�@�@�܂����@�\�@�i�u�܂����v�͌Ì`�j�@�@�܂��ł�@�w
�@�@�u���E�v�́u���v���u��v�ł�����́B
�@�@�@���͂₤�@�@���₤�Ȃ�@�@�₤�@�l�@�@�₤���@�����@�@�₤���@�l�q�@�@�₤�₭�@�Q
�@�@�u���E�v�́u���v���u��v�ł�����́B
�@�@�@�`���炤�@�@���炤���ā@�h�@�@������Ӂ@��@�@�`���炤�@�@�`���炤
�@�@���̑������ꊲ���A�i�ŏI��`�e���́u�`���v�̕ω��u�`�E�v�́u���i�{���v�B
�@�@�@�����������@���@�@���������@���@�@�߂����@��@�@�Ȃ�
���u�E�i�̝X���{�E�v�́u���i�{���A�Ӂv�B�u�L���E�v�́u�L���v���u���v�ł�����́B
�@�@�@������@�ӉZ
�@�@�u�V���E�v�́u�V���v���u���v�ł�����́B
���`�e���́u�`�����v�̕ω��u�V���E�v�͂��ׂāu�����v�B�i�E���ցB�R���́u���v�j�������@�@�������@�@�߂����@�@�Ȃ�
�@�@�@���Ɂu�����v�ł�����́B
�@�@�@�@�����Ɓ@�n�@�@�����Ƃ߁@��
�@�@�u�W���E�v�́u�W���v���u���v�ł�����́B
�@�@�@���Ӂ@�\
�@�@�u�`���E�v�́u�`���v���u���v�ł�����́B
�@�@�@�`���Ӂi�ƌ��Ӂj
�@�@�u�j���E�v�́u�j���v���u�Ɂv�ł�����́B
�@�@�@�͂ɂӁ@����
�@�@�u�q���E�v�́u�q���v���u�Ёv�ł�����́B
�@�@�@�Ђ����@����
�@�@�u�����E�v�́u�����v���u��v�ł�����́B
�@�@�@���肤�ǁ@��l
���u�I�i�̝X���{�E�v�́u���i�{���A�Ӂv�B�@�u�L���E�v�́u�L���v���u���v�ł�����́B
�@�@�@���Ӂ@����
�@�@�u�V���E�v�́u�V���v���u���v�ł�����́B
�@�@�@�`�ł����@�@�`�܂���
�@�@�u�`���E�v�́u�`���v���u�āv�ł�����́B
�@�@�@�ĂӁ@���@�@�Ă��Á@�萅�@�@�Ăӂ���@�ĂӂĂӁ@���X�@�@�Ă��ȁ@�蕀
�@�@�u�q���E�v�́u�q���v���u�ցv�ł�����́B
�@�@�@�w�E�@�^�@�@�w�E�^���@�Z�\
�@�@�u�~���E�v�́u�~���v���u�߁v�ł�����́B
�@�@�@�߂����@䪉ׁ@�@�߂��Ɓ@�v�w
�@�@�i�u��Ӂ@���v�͌Ì`�B�����́u��Ӂv�B�j
�@����O�I�Ɂu�I�i�̝X���{�E�v���u���i�̝X���{���v�ł�����̂�����B�@�u�L���E�v�́u�L���v���u����v�ł�����́B
�@�@�@�����Ⴄ�@�j�[
�@�@�u�V���E�v�́u�V���v���u����v�ł�����́B
�@�@�@���Ⴄ���@���I�@�@���Ⴄ���Ȃ��@�@���Ⴄ�ԁ@�Ҋ�
�@�@�u�W���E�v�́u�W���v���u����v�ł�����́B
�@�@�@�ǂ��Ⴄ�@�D��
�@�@�u�`���E�v�́u�`���v���u����v�ł�����́B
�@�@�@�����Ⴄ�@��ǁ@�@���Ⴄ�ǁ@���x
���u�W�A�Y�v�ɂ���
��O
�@���@�@���@�@�������Ȃ��@�@�A�a�T���@�@�Ӓn�@�@���������@�@�����߂�@�@�����炵��
�@�@�@������@�@���@�@���������@�@����i�����j����@�@��������@�@�|����@�@�ǁ@�@��
�@�@�@�b��@�@�~�@�@�����߁@�@�������i���j�@�@�n�@�@���@�@�`�H�@�@��i�����j����
�@�@�@�����@�����i���j�@�@�����i��j�@�@�n���@�@�V���a�@�@����@���Ⴀ�i�ł́j
�@�@�@�`����i���A�ł́j�@�@�`����Ӂi�ł��܂Ӂj�@�@�`���イ�i���j�@�@�d�X�i���イ���イ�j
�@�@�@�@�@���������@�@�����낮�@�@�z�n�i�����j�@�@�ǂ��@�@�D�Ӂi�ǂ��Ⴄ�j�@�@����
�@�@�@�i���N�a�@�@���@�@�l�a�@�@�˂���@�@�p�@�@�I�@�@���@�@���������@�@���i�����j��
�@�@�@�g�t�@�@�����@�@�����a
��O
�@�������́u����v�����������̂͂��ׂāu���v�B
�@�@�@�Ă���@������@������@�f����@������@�u����@�Ȃ�
�@�@�@�Â�@�a��@�Ȃ�
�@�@�������̑ŏ����́u�Y�v�́u���v�B
�@�@�@�������@�����@�Ȃ�
�@���̑��u���v�ł�����́B
�@�@�@�ǎq�@�@�b�i��������j�@�@���������@�@�������܂�@�@���@�@�K���@�@���@�@��
�@�@�@���i������j�@�@���s�i�������j�@�@�����Ɓ@�@�����Ԃ�@�@��@�@���@�@��@�@������
�@�@�@�X�Y�V���@�@�X�Y�i�@�@���@�@���@�@����������@�@��������@�@�����Ɓ@�@���Δ�����
�@�@�@����@�@���Ԃ́@�@���Ԃ��ԁ@�@���Ԃʂ�@�@���ڂ�@�@���炷�@�@�����
�@�@�@���藎����@�@���邢�@�@���邸��@�@�����@�@����@�@����@�@��������
�@�@�@�l�@�@���@�@��������@�@�~�~�Y�@�@�ނ��ނ��@�@�S��@�@�s������@�@�M�q
�o����ׂ���i���2�j
[��]�@��@�a���@���䍂�@�c�Ɂ@���@��@�В���@�������@����@����@��������z�ԁ@���ʂ�@�����ʁ@�`�����@����Ȃ�g�@�����Ɓ@���ق�����@������~���@臁@����ŋ��@����ׁ@�Ƃ����@�Ђ���闦�@�܂��Q�@�������p�@���Ƃ��@[��]�@�G�@�`���@����@�P��@�a�@�݁@�ށ@�����W���@��������b�@�����A�@�����Q�@�`��i�l���̌b�j�@����@������@����@����鐘�@���@�Ƃ���b�@�قق�ޔ��@���́@���ȁ@[��]�@���@���@���@���i���Ёj�@�I�ւ�@�Y�X�i�����j�����@�u�@���@�����@�Ƃ��@�q�ށ@���@���@�������܂����@���R�[�@���@���������@�c���@���߂�@�[�@���@�C�@�f���@�����i�����j�@�ɂ����@���ւ�@��������@���V�h���@�Y�@���@���͂�@�v�@�j�@�����i���ƂƂЁj�@���N�@�����i���Ƃ߁j�@���@�x��@���@���̂̂��@�f��@����@������@���~�i�w�V�@�B�@�܁@�܂�@����@�����`�@�I�i���́j��@���@����@���������@�������@�`���i�l���̒j�A�Y�A�v�j�@������@�����鍁�@�������@�����Ɓ@�����炵���@������x�@�������ށ@�����₩�@������ߎ�㏗�@�������܁@�Ƃ��\�@�܂�����v�r�j�@�݂��Y�@�݂��𑀁@�߂��ƕv�w�@�����
[��]�@����A�@���킽�������@����Ă�Q�@���키�����@���킵��@�����A�@���킭���@���@����D�@�����f�@�����Ɓ@���Ƃ킴���@���Ƃ��f�@���킢�됺�F�@���킮���@���킴��@����߂��@����ᰁ@�������@����鐘�@���킢�Ȃ��������@����ޝ��@�����@�͂ɂ���ց@��킢���@
[��]�@�����@�����ɂ������@���邢�́@�������@�����ς��@�����i�|�����j�@�V���@�����i�Ăт����j�@�������������@�����ĉ��@�����Ł@�����牴���@���ق��ɑ�@�����D�@����������~���@�������։�Y�@���������~�o�@�����܂��~���@�����܂݂�_�Ԍ��@���͂������@���͂��������z�@�����@�`���������@�����@�����@��������@�`�������܂��@�����ȂމՁ@�����͂ЍK�@���������@�`���Ⴂ�@����܂��@���������s�@�����Ɓ@�����Ԃ�@�����w�@���������ς��@���������@����܂��@�����@��������@���������@�����ԑ啪�@�����܂����@���킢�����@���i��������j�@���@�����z�n�@����������@�����ď��@�`�ɂ��ā@���Ŏ��@���ŏ��@���ޑ�@�`�����Ⴂ�@�ǂ��@�����Ă�����@�Ȃ�������́@�`�Ȃ����@�ɂ�����Z�@�͂��i�Ԏ��j�@�Ђ����ۛ��@�Ђ��ł�G�@�ӂ��i�ʖځj�@�ӂ�����@�ւ��i�͂��j�@�ق��ق��@�܂��ɂ������@�ނ����Z���@�ނ�����@�₢�i�Ăт����j�@�₢�̂₢�́@�₢�ΐn�@�킢�킢�@������傢�@
[��]�@���肪�����@���키�����@�����Ⴄ��ǁ@�������Ɩ��@�`���链�@���Ƃ��ƒ�@���͂₤�@���߂ł����@���肤�ǎ�l�@�`���炤�@���炤���Đh�@���͂��������z�@�����Ⴄ�j�[�@������ӉZ�@���낤�ƌ��l�@�����i�`���A���ӁA����A�Ȃ�j�@�������������_�X�@�������i�q�@���������H�@���������@���������@�����������@�����ד��@�����א_�ˁ@�����ނ��@���������啁@������s���@��������悤�@�����������܁@���₤�Ȃ�@�`���イ���@�������n�@�����ƂߌƁ@���Ⴄ�����I�@���Ⴄ���Ȃ��@���Ⴄ�ԏҊ��@���낤�Ƒf�l�@�����i�`���A���ӁA����A�Ȃ�j�@�`�����i�`���A�ȁj�@���������������X�@������ӌ�@��������@�`���炤�@�`���炤�@�Ă��Î萅�@���Ⴄ�ǒ��x�@�Ă��Ȏ蕀�@�`�ł����@�ǂ��@���@���������@�Ƃ����@�ǂ����@�ǂ����@�����Ă�����@�����Ƃ������@�Ƃ��Ɂi�����Ɂj�@�ǂ����@�ǂ��Ⴄ�D�Ӂ@�Ȃ����ǒ��l�@�̂��̂��@�Ђ��������@�w�E�^�@�ӂ����ʁ@�Ԃ��������@�`�͂����@�͂���ⴁ@�͂��ނ鑒�@�ق��{���@�`�܂����@�߂���䪉ׁ@�߂��Ɓi�~���[�g�Ɠǂޏꍇ�j�v�w�@�����i���Ɂj�@����[�܂��͂܂�]�i�X�Ɂj�@�܂�����݁@�ׁ@�܂����\�@�܂��ł�w�@�₤�i�`���A�ȁj�@�₤�������@�悤�����@�₤���l�q�@�₤�₭�Q�@������_�@�킩���ǎ�l�@����������؍��@
[��]�@���܂���Á@��������@���т��鋺�@���ڂ���o�@��������@�������長�@������z�@�������@�������铀�@�������@��������h�@�������]�@���т����ށ@�������@�Ђ����@�ׁ@�Ȃ���ށ@�ɂ���ρ@�͂��鐶�@�͂���f�@�h�@�Ђ����@�ӂ��鑝�@�ق���i�@�܂݂��錩�@�݂��錩�@������R�@������G�@���������@�������@�������@���肦���]�@�`���i�l���̍]�A�}�j�@�����i�����j�@������@�����낦�i��j�S���@��������Ձ@�T�U�G�@����������X�@�������@�ʂ��K�@�˂��i�Ăт����j�@�˂�����o�@�Ђ��B�@�ӂ��J�@�ւ��i�͂��j�@�݂����h�@
[��]�@�͂���@�͂���H�D�@
[��]�@���ӂЈ��@���ӂ���@�@���ӂނ����@���ӂ���@���ӂ��@���ӂ��|
[�����E����]�@���ӂ���@���ӂ������@���ӂߍ]�@���키�����@�����i�`���A���ӁA����A�Ȃ�j�@�������������_�X�@�������i�q�@���������@���������@�����������@�����ד��@�����א_�ˁ@�����ނ��@���������啁@������s���@�Ȃ����ǒ��l�@�ނ���[�܂��͂ނ���]�i�����j���@�킩���ǎ�l�@����������؍��@�܂��ӕ��@�݂܂��ӌ����@���͂��������z�@�����i�`���A���ӁA����A�Ȃ�j�@�`�����i�`���A�ȁj�@���������������X�@������ӌ�@���肪�����@���߂ł����@��������@���䂽�ӗh���@���������@�����Ă�����@���ӂƂ��@���ӂƂԑ��@�����Ƃ������@�Ƃق��ӂ݉��]�@�ق��{���@�Ԃ��������@������_�@�`�͂����@�͂���ⴁ@�͂ӂ͂ӂ̑́@�͂��ނ鑒�@�͂ӂ���@���܂ӑ��o�@�`���܂Ӌ��@�܂�����݁@�ׁ@�܂����\�@�܂��ł�w�@���͂₤�@���₤�Ȃ�@�₤�l�@�₤�������@�₤���l�q�@�₤�₭�Q�@�`���炤�@���炤���Đh�@������ӌ�@�`���炤�@�`���炤�@�i�����ݐC�@�����ߐ~�@�����ِԕ�j
�@[�����E����]�@������ӉZ�@�������n�@�����ƂߌƁ@���ӏ\�@�`���Ӂi�ƌ��Ӂj�@�͂ɂӏ����@�Ђ��������@���肤�ǎ�l�@
[�����E����]�@���Ӎ����@�`�ł����@�`�܂����@�ĂӒ��@�Ă��Î萅�@�Ăӂ���@�ĂӂĂӒ��X�@�Ă��Ȏ蕀�@�w�E�^�@�w�E�^���Z�\�@�߂���䪉ׁ@�߂��ƕv�w�@
[�₤]�@�����Ⴄ�j�[�@���Ⴄ�����I�@���Ⴄ���Ȃ��@���Ⴄ�ԏҊ��@�ǂ��Ⴄ�D�Ӂ@�����Ⴄ��ǁ@���Ⴄ�ǒ��x
[��]�@���@���@�������Ȃ��@�A�a�T���@�Ӓn�@���������@�����߂�@�����炵���@������@���@���������@����i�����j����@��������@�|����@�ǁ@���@�b��@�~�@�����߁@�������i���j�@�n�@���@�`�H�@��i�����j����@�����@�����i���j�@�����i��j�@�n���@�V���a�@����@���Ⴀ�i�ł́j�@�`����i���A�ł́j�@�`����Ӂi�ł��܂Ӂj�@�`���イ�i���j�@�d�X�@�@���������@�����낮�@�z�n�i�����j�@�ǂ��@�D�Ӂi�ǂ��Ⴄ�j�@����@�i���N�a�@���@�l�a�@�˂���@�p�@�I�@���@���������@���i�����j��@�g�t�@�����@�����a�@[��]�@�ǎq�@�b�i��������j�@���������@�������܂�@���@�K���@���@���@���i������j�@���s�i�������j�@�����Ɓ@�����Ԃ�@��@���@��@�������@�X�Y�V���@�X�Y�i�@���@���@����������@��������@�����Ɓ@���Δ�����@����@���Ԃ́@���Ԃ��ԁ@���Ԃʂ�@���ڂ�@���炷�@�����@���藎����@���邢�@���邸��@�����@����@����@�������ށ@�l�@���@��������@�~�~�Y�@�ނ��ނ��@�S��@�s������@�M�q�@c �u���j�I�����������v�@2003-2010
�V�[�g�R�D��O�����@�i�V�[�g�Q�D��蓮���݂̂𒊏o�������́j
���ӂ��@��@�@���ӂ��@�@�@���ӂނ��@���@�@���ӂ�@���@�@���܂���@�Á@�@����Ă�@�Q
������@���@�@�����߂�@�Ձ@�@������@�M�@�@���@��
�����i����@�����j�@�A�@�@�����i����@�����j�@�Q�@�@�������܂�@�L�@�@�����@�A�@�@����@��
����@�`�@�@���@�P�@�@��ށ@��
������@�V�@�@���ւ�@�I�@�@�������@�Ɓ@�@�����ށ@�q�@�@�����߂�@���@���@�C�@�@�����ށ@�Ɂ@�@�����ւ�@���@�@������@�|�@�@�����͂�@���@�@���ǂ�@�x�@�@���̂̂��@�Ɂ@�@���т���@���@�@���ڂ���@�o�@�@����@���@�@����@�܁@�@���͂�@�I
����������@�~���@�@���������@�~�o�@�@�����܂݂�@�_�Ԍ��@�@������@���@�@���킭�@��
������@���@�@��������@��
������@��
�����ނ�@��@�ց@�@������@�z�@�@������@��@�@��������@���@�@�����낦��@�S���@�@���Ƃ��@�f
�����Ȃށ@�Ձ@�@��������@�Ձ@�@������@��@�@��������@�h�@�@���킮�@�����@�@����߂�
�������@��
������@�]�@�@�����i����@�����j�@���@�@�����ށ@���@�@����������@�@���ʂ���@�@���炷�@�@���肨����@�C���@�@����@�C�@���@�@���邯��@�@�����@�@�����@���@�@�����@��
������Ӂ@��@�@���т���@��
������@��@�@���ӂ��@�|�@�@������@��܁@�@���ӂ��@�|�@�@�����낮�@�@�������ށ@�ȁ@�@����ށ@��
�Ђ���@��@�ׁ@�@���ށ@��
���ǂ݂̊����ꎚ�Ɂu����v�������u�Ă���A������A�E�E�E�v�Ȃǂ̓����͏ȗ����܂������A�����͂��ׂāu�`����v�ł��B�i�R���́@���� �����j
�P�ǂ݂̊����ꎚ�Ɂu��v�������u�Â�A�a��A�E�E�E�v�Ȃǂ̓����͏ȗ����܂������A�����͂��ׂāu�`������v�ł��B�i�R���́@���� �����j
����̂�́A�o���Ȃ��Ă悢
������i���͌����̕��́B�`���܂ӁA�Ƃ��A�`����A�Ƃ��j���(�����낤�Ԃ�)�i�`�ɂČ�A�Ƃ��̕��́B��O�͂��Ȃ��ʓI�Ŏ莆�ɂ��悭�g��ꂽ�j�́A�{���ɕK�v�Ȃ���Ζ����ɏ��������o���Ȃ��Ă悢�̂ł��B
���̑���A�܂��͎������ɂ��Ȃ��ݐ[��������ŁA���j�I���ȂÂ��Ђ��������K���n�߂܂��傤�B������ŏ����̂Ɋ���Ă��āA�����]�T������Ȃ�������Ƃ��ɃX�e�b�v�A�b�v����悢�̂ł�
�������ȂÂ��Ёi���ǂ݊����̗��j�I���ȂÂ��Ёj�́A�o���Ȃ��Ă悢
��A�u���܂��傤�v���u���܂����v�Ə������ƁB
��A�u���傤���傤(���X)�v���u�ĂӂĂӁv�Ə������ƁB
�@���̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���ł��傤���H�@�@�����́A��͑�a���t�i�a��j�A��͊����̉��ǂ��ł���Ƃ������Ƃł��B�@���ǂ݊����̗��j�I���ȂÂ��Ёi�������ȂÂ��Ёj�Ƃ����̂́A�������ɓǂݕ����������ƁA��a���t�̗��j�I���ȂÂ����ɔ�ׂ�Ɗo����̂Ɏ��Ԃ���������̂ł��B���ɁA��O�Ɉ�������{�l���A��a���t�̗��j�I���ȂÂ��Ђ͓�Ȃ����Ȃ��Ă��A�������ȂÂ��Ђɂ͂����ԋ�J�����Ƃ����l�����������ł��B
�����i�����E�]���j������
���ォ�ȂÂ����Ɨ��j�I���ȂÂ��ЂŒԂ�̈Ⴄ���t�̂����A�ł��p�ɂɎg���錾�t�ł��B
����i����j�����
����́u��v
| �u�`�e�C���v���u�`�Ă��v�Ə����B
��O�Ȃ� |
�u���Ӂv�Ɏ����ŕp�ɂɎg���錾�t�ł��B�܂��A�z���t���Ǝv���܂����A�u���Ȃ��v�u���܂���v�u���܂��v�́u��Ȃ��v�u��܂���v�u��܂��v�ɂȂ�܂��B
�悤�i��j���₤
�������r�I�p�ɂɎg���錾�t�ł��B�Ⴆ�A�u���̂悤�ȁv�́u���̂₤�ȁv�ɂȂ�܂��B�@�������A�u���悤�v�u�҂悤�v�u�����悤�v�̂悤�ɁA�u�������悤�v�́u�悤�v�́u�悤�v�̂܂܂ŁA�u�₤�v�Ƃ͏����܂���B�u�悤�v���u�₤�v���s���Ȃ�A�ȒP�Ɍ���������@������܂��B�����Łu��v�Ə�����u�悤�v�����u�₤�v�A�ł��B
��j�����₤�ȉf�`(��)���߂Č������A���x�̓��j���܂����悤�l�A�ƉԎq����͑��Y����Ɍ������₤�ł����B�i�u�₤�v�̕��������͊������Ɓu��v�ł��邱�Ƃɒ��ځj
���낤�����炤�@
��j�����ƁA�u����͖����炤���v�ƌ��ӂ������炤�B
�l���遨�l�ւ�
��j�u�悯���Ȏ����l�ւ��ȁv�Ƃ����l���͊Ԉ���Ă��B
���炢�i�ʁj�������
�������A�����Łu�ʁv�Ə����u���炢�v�����ł��B�u�Â��v�́u���炢�v�̂܂܂Ȃ̂Œ��ӁB
��j�ǂ�������ł������ƁA������������������Ȃ�A�����ł������̂ɁB
�p���遨�p���i�A�p�Ђ�j
�u�p����v�́u�p���v�ɂȂ�܂��B���ꂪ�����ł͂���܂����A�u�p�Ђ�v�Ə����̂��ꉞ���e�͈͂ł��B�u�p���v�́u�p�Ӂv�ł��B
��j�ǂ̕��@���p������ǂ��A�p�����Ƃ�ӂ邭���Ȃ�
[�߂�]�C���Z�@
�����i�܂��炱�Ƃj
�����Ƃ͘a�̂ɂ݂���C���p��̂ЂƂŁA���̌�̏�ɂ������Ă����̏�I�ȐF�ʂ�Y������A�咲�𐮂����肷��̂ɗp������B
�����̑����̌�傪�܉�����o���Ă��邽�߁A����Z�̂̐��E�ɂ����Ă��C�����ƂƂ̂��邤���Ŕ��ɗL���ł���B
�Ђ������̌��̂ǂ����t�̓��Ɂ@���ÐS�Ȃ��Ԃ̎U���ށ@�i�I�@�F���j
���Ƃ����̉̂̏ꍇ�́A�u�Ђ������́v���u���v�ɂ������āi���������o���āj���閍���ł��B
| ���� | ��C���� |
| �����˂��� | ���E���E���E�Ƃ�E�N |
| �����Ђ��� | �R�E��i���j |
| ���Â���� | �����E����E�t�E�{�E���E���E���E���ւ� |
| ���炽�܂� | �N�E���E���E��E�t�E |
| �����ɂ悵 | �ޗǁE�����i���ʂ��j |
| �����ȂƂ� | �C�E�l�E��i�Ȃ��j |
| ���͂��� | ��E����(�����)�E�W�C(���ӂ�)�E�ߍ]�i���ӂ݁j |
| �����݂� | ���E�l�E���E�� |
| �����܂��� | ���E���ԁE���Ӂi��Ӂj�E���E�I�E���� |
| �������ւ� | ���E�߁E���i���Łj�E���E�ƁE�� |
| ���낽�ւ� | �߁E�сE�������E�����ƁE�Ђ��E�Ђ�E�_�E�� |
| ����(��)�݂� | ��a�i��܂Ɓj |
| ���܂��͂� | ���E���E���E��E���� |
| ���܂����� | �����E�J���E��(�ӂ�)�E�O(��)�E�� |
| ���܂Â��� | �g�i���Ёj�E��(����) |
| ���܂ق��� | ���E�� |
| ���炿�˂� | ��E�e |
| ���͂�Ԃ� | �_�E�F�� |
| �ʂ��܂� | ���E���E��E���E�[�E�Â��E�����E�Q�� |
| �Ђ������� | �V(����)�E�J�E���E���E���E���E��E�_�E���E���E��E�j�E�s�E�� |
| ���������� | ��{�E�� |
| �킩������ | ��(�v�E��)�E�V�i�ɂЁj�E�r�i����Ёj�E�Ⴕ�E�v�Ђ� |
�����i���傱�Ƃj
�����Ђ��̎R���̔��̂�������̂Ȃ��Ȃ�������ЂƂ肩���Q�ށ@�@�i�`�{�@�l���C�j
�O��ځu�����Ђ��̎R���̔��̂�������́v�܂ł��A�u�Ȃ��Ȃ�����v�������o�������ɂȂ��Ă��܂��B
�i���̉̂͏���Łu�����Ђ��́v�Ɓu�R�v�������o�������������Ɏg���Ă���j
�����͂悭�u�����́����A����ł͂Ȃ����A����ɂ悭���āv�ƁA�悭��܂��B
���̉̂̏ꍇ�Ȃ�u�R���̒������ꉺ�����������������A����ł͂Ȃ����A����ɂ悭���Ē������������l�Ŗ��邱�Ƃł��낤���Ȃ��v�Ƃ����������̈Ӗ��ɂȂ�܂��B
�|���i�������Ƃj
�u�ЂƂ̌��t�ɂӂ��̈Ӗ���������v�Ƃ������Ƃ���B
�Ԃ̐F�͂���ɂ���Ȃ����Â�ɂ킪�g���ɂӂ�Ȃ��߂����܂Ɂ@�@�i���쏬���j
���쏬���̂��̉̂́A�|�����g�����ł��L���ȉ̂̂ЂƂł��B
���́u�Ȃ��߁v�ɂ́u���J�v�Ɓu���߁v���A�܂��u�ӂ�v�ɂ́u�~��v�Ɓu�o��v���|�����Ă��܂��B
���̑��̏C���Z�@
- �����@
- ��@
- ���C�@����܂��͗ގ��̉C��������������̉ӏ��ɗp���邱�Ƃ�����
- �|�u�@�@����ɂ����Ēʏ�̌ꏇ��ύX�����邱�Ƃł���@�i��j�@���������ˁA�N�ɂ�
- ����
- ���p�A���p
- �̌��~���@�̌��i�����E������j�ŕ��͂��I���邱�ƁB�i��j�u���������v�Ƃ������̎��E�q��̏��Ԃ��t�ɂ��āu����鐅��v
- ��g
- ���g�A�Úg�i�B�g�j�A���g�A�[�l�@
- �[����A�[�Ԍ�
- �����@ ���̒��ɈӖ���֘A������A�z�I��2�ȏ�p���邱�Ƃʼn̂ɏ���������
�Z�̂̕��@
���@�𐳂����m��K�v�@�i�����ؐM�j�j
�a�͕̂��w�ł��邩��A�����Ƃ��ĕ��@�𐳂������˂Ȃ�ʁB��҂̖��w�Ɋ�Â����\�Ȏ��Â��Ђ�A�j�i�Ȍ�@�́A���ꊮ�S�ȉ̂ɉ��āA�����ׂ��炴����̂ł���݂̂Ȃ炸�A�䂪���̌�́A�Ăɂ��̗͂p�@�������Ȃ��̂ł��āA����ƊԈ�ӂƑ�ςȈӖ��̑���𗈂��B��ւu����Ȃށv�Ɓu����Ȃށv�A�u�܂��v�Ɓu�܂��v�A�u���v�Ɓu���v���A�����Ă��ꂼ��Ӗ�����ӂ̂ł��邩��A���@�𖾗Ăɒm�Ă��Ƃ��ӎ��́A�a�̂��r�܂ނƂ���ɁA�ł��K�v�Ȏ��ł���B��ɓ����̊����A�Ăɂ��͂̈Ӗ��A�����ƂĂɂ��͂Ƃ̂Â����A�܂��W���̊W�Ȃǂ́A�\���������m�Ă���v����B
���@�ɍS�D���Ă������Ȃ��@����
���@�͂��₵���������Ŏ����̍l�\���悤�Ƃ���ȏ�͕K�v�ŁA���Ęa�̂̏�ɂ��K�v�ł��邪�A�����a�̂ɉ����ẮA���������@�ɍS�D���Ă͂����Ȃ��B
���̕��@�̖@���́A�����͕���������̕��͂ɑ������|�ł���B���͂��ϑJ����Ƌ��ɁA���@���ϑJ����B�a�̂͌�������ł͖�������A��̂ɉ����Ă͌Õ��̖@���ɕ�ӂׂ��ł��邪�A�������ɂ��A�����Õ��̖@����j�Ă��悢���R��L���Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�ʁB
�܂��a�̂ɂ͔��I�Ɍ��Е\�����Ƃ��A���ɕK�v�ł��邩��A���ׂ̈ɂ́A���ɂ͐��m�ƌ��ӎ������]���ɂ��˂Ȃ�ʐ܂�����̂�Y��Ă͂Ȃ�ʁB
�����̊��p�i����ҁj
���͂������Ƃ��Ɏg���錾�t���u����v
�u���ꊈ�p�\�v
���R�`�i�@�j���@//���Ԃ������i���܁j���R�i�����j�炸���܂�A�܂��������Ă��Ȃ���Ԃ�\���`
�A�p�`�i�@�j����,�ʁA�ā@//�p���i�����E�`�e���E�`�e�����̑��́j�ɘA�Ȃ遄�Ƃ����Ӗ�
�I�~�`�i�@�j�I�~�@//�����������ďI���`�ŁA�����̊��p�̊�{�`
�A�̌`�i�@�j���@//�̌��i�����j�ɘA�Ȃ铭�������銈�p�`�@�p���ɘA�Ȃ�A�p�`�Ƃ͑ΏƓI�Ɉʒu�Â�����
�ߑR�`�i�@�j�ǂ��@//���Ԃ����łɐ������Ă����Ԃ�\���܂��B�ŏ��ɏ��������R�`�ƑΏƓI
���ߌ`�i�@�j���߁@//����ɑ��čs�ׂ��Ԃ����������悤�Ƃ��镶�̏q��Ƃ��ėp������`
���Ƃ��u�s���v���Ɓc
���R�`�@�@�s�i���j��
�A�p�`�@�@�s�i���j����
�I�~�`�@�@�s�i���j�I�~
�A�̌`�@�@�s�i���j���A��
�ߑR�`�@�@�s�i���j�ǂ��A��
���ߌ`�@�@�s�i���j����
���p�̎d���ɂ�铮���̎�ށi����ҁj
||�l�i���p||���i||����i||���i||����i||�J��||�T��||�i��||����||������u���A���A���A���A���A���v�ƌ\���}�̃J�s�̃A�i�A�C�i�A�E�i�A�G�i�i�����A�����A�����A�����j�̎l�̒i�Ɋ��p����̂Łu�l�i���p�i���̏ꍇ�A�J�s�Ȃ̂ŃJ�s�l�i���p�j�v
����̕ꉹ��(a)(i)(u)(u)(e�ie�j)�̂S���ƂȂ���̂ŁA�l�i���p
�u�l�i���p�v�@�@�@�@�@�\���}�́A�A�C�E�G�̎l�̒i�Ɋ��p����B
�炭�@�@�@���@���@���@���@���@���@�@�i�J�s�̎l�̒i�j
| ���p�` | ||
| ���R�� | �炩(a) | �b�� |
| �A�p�� | �炫(i) | �b�� |
| �I�~�� | �炭(u) | �b�B |
| �A�́� | �炭(u) | �b���� |
| �ߑR�� | �炯(e) | �b�� |
| ���߁� | �炯(e) | �@ |
| �s | �J�s |
�\���}�̕ꉹ�̗�Ō����ƁA�A�E�C�E�E�E�E�E�G�E�G�̌`���Ŋ��p����B�����ł͂��̃^�C�v���ł������B�Ȃ��s����t��(��)�͎������A(��)�͑�����������킷�B�i�������Ƒ������ɂ��ẮA�������Ƒ��������Q�Ƃ��ꂽ���j
| �s | ��{�` | �ꊲ | ���R�` (�`��) |
�A�p�` (�`��) |
�I�~�` | �A�̌` (�`����) |
�ߑR�` (�`�ǂ�) |
���ߌ` | ���� |
| �J | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �J(��)��(��) �O�� �\�� ����(��)��1 �s�� �F�Â� �u�� ���� ���� ��(����)��(��) ���� ���� �ӂ�(��) ��(��)�� �炭 �~�� �p(��)�� �@(��)�� ���� �w��(��) ���Ȃт� �t���^����(��) �˂� �т� ����(��) �͂�(��) �����^�� �Q�� ���� ���� �Ђ炭 ���� ���� ����(��) �Ă�(��) ����(��)��2 ��(��)����3 |
| �K | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� �j�� �k�� ���₮ ���� ���� �킮 ���悮 �p�� �E��(��) �h�邮 |
| �T | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ��(����)�炷 ��(����)�� �Ȃ� �}��(����)�� �݂� ���͂� �Ԃ��^�A�� ��炷�^�Â� ���� �z�� ���� ��܂��^�o�܂��^��܂� �U�炷 �s���� �Ƃ炷 �ʂ� �r���� �ς� �c�� ����(��) ���� �f�͂� �ς� ��(��)�� �\�� �n�� |
| �^ | �҂� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �ł� ��(����)�� ��(��)�� ��(����)�� ���(��) ���ڂ���4 ��(����)�^���� ����(��) �o�� ��^�f�^�ق� �u��(��) ����(��)��5 ���� |
| �n | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ����(��) �j�� �̂� ����� �v�� ��(��)��(��) �ʂ� �H�� �U�� �Y��(��) ��� ��� ������(��) �`��(��) �ƂԂ�� �K�� ���� �D�� ���� ���Ӂ^�|����6 ���� �f�� ���� ���� ������(��)��7 �� |
| �o | �� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ����(��) �I�� ���� ����8 ��������9 ��� ����(��) ���� ��� |
| �} | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ��(����)����10 �ɂ��� �������� ���� ����(��) ���ڂ�(��) ������(��) �Z�� ���� ����(��) ������11 ��� �ڂ�(��) �E�� �ς� �x�� �Ƃ��(��) �Ԃ�(��) ��(��)��(��) ���� �ǂ� �� |
| �� | ��� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ������ �V��(���܂�)�� ��� ����ǂ� ���� �ڂ�^�f��^�ʂ� ����^���� ��� �|���� �삯�� �Ă� �d�Ȃ� ��� �ς͂� �A�� ���� ��� �� ��(��) ���� ���� ��(�����^�ӂ�)�Ԃ� �܂� ��� �Ă� ����^�X�� ��(����)�� ��(����)�� �T�� ���� ���� �ɂ� �(����)�� �m��(��) ��(����)��^�ނ�(��) �}��(����)�� �C��^����^����(��) �Y�͂� ��(����)�� ��(���Ă܂�)�� �H�� ���� ���͂� ���� �_�� �U�� �Ԃ� �ς��� �Ƃ� ���� ���� ��� ���� ���� �~(��)�� �u���� ������ �܂��� �Z(�܂�)�͂���12 ��� ��(��)�� �R��^�k����13 �h�� ���� ��� �����͂� ������/��(�킩)����14 �܂�(��) |
��2�u�����v�͎l�i�E����i��������B�����͎l�i���p�ł������炵���B
��3�u��(��)���v�͌����͏��i���p�ł��邪��������ɂ͎l�i���p���B�̂�����i���p�ƂȂ�B
��4�u���ڂ�(�Â��́u���قv)�v�͏��i�ɂ����p����B
��5�u���v(������)�͓ޗǁE��������͎l�i���p�B���̌���i�ɂ����p����B
��6
�Ж�Ȃǂ���������Ӗ��́u�P�Ӂv�͉���i�ɂ����p����B
��8�u�Âԁv�͕�������Ȍ�A�u�E�ԁv�ƍ���������i���p�����ꂽ�B
��9�u�����ԁv�͓ޗǎ���͏��i���p�A�����Ȍ�͑����l�i���p�B
��10�u���ށv�͎������㍠���牺��i���p��������B
��11�u(�l��)���҂�����v�u���Ăɂ�����v�ӂ́u���ށv�͉���i���p�B
��12�u�Z(�܂�)�͂�v�͉���i�ɂ����p����B
��13�u�R��(�k��)�v�͉���i�ɂ����p����B
��14�u�����ł���v�u��������v�Ȃǂ̈ӂ́u�킩��v�i����E����j�͎l�i���p�B�u��(�킩)��v�͎l�i�E����i��������B
------------------------------------------------------------
�u���i���p�v�@�@�@�@�\���}�̃C�i�Ŋ��p����B
����@�@�@�Ɂ@�Ɂ@�ɂ�@�ɂ�@�ɂ�@�ɂ�@�@�i�u�ɂ��@�ɂ���@�ɂ���@�ɂ���v�Ńi�s�̈�̒i�j
�߂���̔ے�`�i�`�Ȃ��j���l���āA
�u�@���i���p�́A�\���}�ł����Ƃ���̃C�̒i�A�܂�ꉹ���i���j�P�i�ɂ����ω����Ȃ����p�����܂�
|
�o����̂́u����E����E�݂�E�ɂ�E�Ђ�v�̌܂̌��t�����ł�
| ��{�` | ���R�i���j | �A�p�i�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i���Ɓj | �ߑR�i�ǁj | ���� | �s |
| �ς� | �ρi�Ɂj | �ρi�Ɂj | �ς� | �ς� | �ς� | �ς� | �i�s |
| ���� | ���i�Ёj | ���i�Ёj | ���� | ���� | ���� | ���� | �n�s |
| ���� | ���i�݁j | ���i�݁j | ���� | ���� | ���� | ���� | �}�s |
| �˂� | �ˁi���j | �ˁi���j | �˂� | �˂� | �˂� | �˂� | ���s |
���ɂ��A�Ō�Ɂu�݂�v���t�������A�u���݂�v�u�ځi������j�݂�v�Ȃǂ����i���p�@
�u����v�u����v�u����v�u�ς�v�u�˂�v�u����v�u����v�u����v�u����v------------------------------------------------------------
�u����i���p�v�@�@�@�@�\���}�̃G�i�Ŋ��p����B
����i�͂ƂĂ��ȒP�ł��B�Ȃɂ�����i���p���铮���́u�R��v�ЂƂ݂̂�����ł�
| ��{�` | �ꊲ | ���R�` | �A�p�` | �I�~�` | �A�̌` | �ߑR�` | ���ߌ` |
| �R�� | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ���� |
�R��@�@�@���@���@����@����@����@����@�@�i�u�����@������@������@������v�ŃJ�s�̈�̒i�j
�A�u�`�i���j�Ȃ��v�ƂȂ���͉̂���i
------------------------------------------------------------
�u���i���p�v�@�@�@�@�\���}�̃C�i�ƃE�i�Ŋ��p����B
�C�E�C�E�E�E�E���E�E���E�C���̌`���Ŋ��p����B�I�~�`�ƘA�̌`���قȂ�_�A���ɒ��ӂ��K�v�B
| �s | ��{�` | �ꊲ | ���R�` (�`��) |
�A�p�` (�`��) |
�I�~�` | �A�̌` (�`����) |
�ߑR�` (�`�ǂ�) |
���ߌ` | ���� |
| �J | �s�� | �s(��) | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ����(��) �N�� ��(��)����1 |
| �K | �߂� | ��(��) | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ��(��)�� |
| �^ | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | ���� | ���� ���ڂ���2 ����(��)��3 |
| �_ | �� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | ���� | �|(��)�� �p�� ��(��)��(��)��4 �g�t(����)����5 ��(��)�� |
| �n | ���� ��6 | ��(��) | �� | �� | �� | �ӂ� | �ӂ� | �Ђ� | ��(��)�� ��(��)�� |
| �o | �т� | ��(��) | �� | �� | �� | �Ԃ� | �Ԃ� | �т� | ���� �r(����)�� �_���� �Z�� �K�� �E�� �L��(��) �ł� �̂� |
| �} | ���� ��7 | ��(����) | �� | �� | �� | �ނ� | �ނ� | �݂� | ��(��)�� ���� �Ƃ��(��) |
| �� | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | ��� | ��� | ���� | �V�� ��(��)�� ��� |
| �� | �� | ��(��) | �� | �� | �� | ��� | ��� | ��� | ��(��)�� ���� |
��1
�u��(��)���v�͌����͏��i���p�ł��邪��������ɂ͎l�i���p���B�̂�����i���p�ƂȂ�B
��2�u���ڂ�(�Â��́u���قv)�v�͎l�i�ɂ����p����B
��3�u���v(������)�͓ޗǁE��������͎l�i���p�ł��������A���̌���i�ɂ����p����悤�ɂȂ����B
��4
�������́u�Ђ�(�Â��́u�Ђv)�v�͖{���l�i���p�ł��������A����������������i���p�ɕω������Ƃ����B
��5�u�g�t(����)�Áv�͓ޗǎ���ɂ́u���݂v�Ŏl�i���p�B�����Ȍ�A�����������i���p�ɓ]�����B
��6�u���Ӂv�͎���������l�i���p��������B
��7�u���ށv�͍]�ˎ���ɂ͎l�i���p�ƂȂ����B
�u�߂��v�A�J�s���i���p�̓����ł��B�߂���̔ے�`�i�`�Ȃ��j���l���āA�u�߂��i���j�Ȃ��v�Ȃ̂ŁA���i�̓����ƕ�����܂��B
�����I�ȂƂ���͂ǂ����Ƃ����ƁA�����A�́A�ߑR�̌`���A�l�i���p�����Ƃ͈Ⴂ�܂��B
����������Ȃ��`�A�u�߂���v�A�u�߂���v�ƂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ɁA���i�ł́A�A�̌`�ƛߑR�`���A���ꂼ��u����v�u����v�ƂȂ�̂ł��B������a�������邩������܂��A����Ԃ������Ē蒅�����Ă��܂��Α��v�ł��B�ߑR�`���A�����Ɠ����悤�ɍl���āw�߂���ǁx�Ƃ��Ȃ��悤���ӂ��ĉ������B
�łԁ@�@�@�с@�с@�ԁ@�Ԃ�@�Ԃ�@�т�@�@�@�i�u�т��@�Ԃ��@�Ԃ���@�Ԃ���@�т���v�ŁA�n�s�̃C�i�ƃE�i�̓�̒i�j
------------------------------------------------------------
�u����i���p�v�@�@�@�@�\���}�̃E�i�ƃG�i�Ŋ��p����B
�G�E�G�E�E�E�E���E�E���E�G���̌`���Ŋ��p����B�l�i���p�̎��ɑ����^�C�v�B���i�����Ɠ������A�I�~�`�ƘA�̌`���قȂ�ȂǁA����Ƃ͊��p�̎d�����傫���قȂ�̂ŁA���ɒ��ӂ��K�v�B��p�̕p�x���ł��������p�^�Ǝv���邽�߁A�����Ȃ�ׂ��������ꂽ�B
| �s | ��{�` | �ꊲ | ���R�` (�`��) |
�A�p�` (�`��) |
�I�~�` | �A�̌` (�`����) |
�ߑR�` (�`�ǂ�) |
���ߌ` | ���� |
| �A | ��(��) | (��) | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | �\�\ |
| �J | �X�� | �X(��) | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ���� ����(��) �� �v�Њ|�� �|�� �삭 ��(����)��(��) ��(��) �ӂ�(��) ��(��)���^���� ���� �w��(��) ���� ��(��)���^茂� ���(����)�� �t���^����(��) ����(��) �͂�(��) ������1 �ӂ肳�� ���� ����(��) �Ă�(��) ��(��)����2 ����(��) |
| �K | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ��(��)�� �f(����)�� ��(��)�� ���� �W(���܂�)�� ���� ���� �E��(��) |
| �T | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ��(��)�� ��(��)�� ��(����)�� �Q�� �y�� ����(��) |
| �U | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ��(��)�� |
| �^ | �̂� | ��(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �Ă� | ���� ��(��)�� ��� ���(��) ����(��) �`(��)�� ��(��)�� �ʂ� �u��(��) ����(��) |
| �_ | �o�� | �o(��) | �� | �� | �� | �Â� | �Â� | �ł� | �t�� ���� ��(��)��(��) ��(��)�� �w(�܂�)�� |
| �i | �Q(��) | (�Q) | �� | �� | �� | �ʂ� | �ʂ� | �˂� | �Q(��)�� �d�� ���� �q�� �K�� ���� ���� ���� �ς� |
| �n | �o(��) | (�o) | �� | �� | �� | �ӂ� | �ӂ� | �ւ� | ����(��) ���� �^�� �i�� �J��(�D��) �T���� �I(��)�� ���� ���� ���� ���� �ςӁ^�ւӁ^���Ӂ^��� ��(��)��(��) ���� ���� ��(��)�� ���� �Y��(��) �����͂�(�~�ӁE����)��3 ������(��) �̂� �d�� �`��(��) �Ȃ����(�i��ӁE����) �P�� �Z(�܂�)�͂� ������(��) ��(�悻)�� |
| �o | �q�� | �q(��) | �� | �� | �� | �Ԃ� | �Ԃ� | �ׂ� | ����(��) �����Ȃ� ���� ��(��)�� �H�� ����(��) �L��(��) |
| �} | ���� | ��(�Ȃ�) | �� | �� | �� | �ނ� | �ނ� | �߂� | ��(����)�� ���� �W�� ��(���炽)�� �Ђ� ���� ���� ��� �ɂ� �Ă� ��� ��ށ^�o�ށ^��� �F(������/�݂�)�� ����(��) ���ڂ�(��) ��� ����(��) ������(��) ���� �ӂ� ��(��)�� ������4 �ڂ�(��) �~(��/��)�� ��� �Ԃ�(��) �G�� ��(��)��(��) �n�� ��� ���� ��� |
| �� | ���� | ��(��) | �� | �� | �� | ��� | ��� | ���� | �Â� ���� ���� �o�� �v�ق� ������ ��(��)�� ��(����)�� �z�� ��� ��� �h�� ��(���ȁ^��)�� ��� �ς� ��(��)�� �f(��)�� ��� ���� �i�� ���� �G�� �R�� |
| �� | �G�� | �G(��) | �� | �� | �� | ��� | ��� | ��� | ��(������/������)�� �r�� �\�� ��� ��(�����)�� ��(��)�� �n�� ������ ����Ԃ� �x��^��� ���� �K�� �M�� �B�� �͂� ��(��)�� ��(��) ���� ��� �q�� ��(����)�� ��(����)�� ��� ��� ���J(����)�� �m��(��) ��(����)��^�ނ�(��) �C��^����^����(��) �Y(���͂ށ^����)�� �|(����)�� ������ ���� ��� �ׂ� �A�� ���� ����^��� �O�� ��(�͂�)�� ���� �G(��)�� ���� ���ڂ� �Q�� � ������^�ʂ� �Y�� �܂�(��) |
| �� | �A�� | �A(��) | �� | �� | �� | ���� | ���� | ��� | �삤 ���� |
��1�u�����v�͕��ʎl�i�����ł��邪�A�u���R�Ƌ�����v�ӂ̏ꍇ����i���p�ƂȂ�B
��2�u��(��)���v�͌����͏��i���p�ł��邪��������ɂ͎l�i���p���B�̂�����i���p�ƂȂ�B
��3�u�����͂�(�~�ӁE����)�v�͓ޗǎ���ɂ͎l�i���p�B
��4�u���ށv�́u(�l��)���҂�����v�Ƃ������Ӗ��ŗp����Ƃ�����i���p�B�u(�l��)���݂Ƃ���v�Ȃǂ̈ӂŗp���鎞�͎l�i���p�B
�A�s���p���铮���͈�A�u����v�́u���i���j�v���������B
������̃A�s���p�u���i���j�v�́A�u����v���u���i���j���v�Ȃ̂ʼn���i�̊��p
| �A�s | �� | �� | �� | �� | �� |
| ���s | �� | �� | �� | �� | �� |
| ���s | �� | �� | �� | �� | �� |
��̂悤�ɁA�Õ��ł́u���v�u���v���A�s�ƃ��s�ŁA�u���v���A�s�ƃ��s�ŁA���Ԃ��Ă��܂��Ă���̂ł��B�������A�u�A�s�͓��i���j�����v�Ƃ������Ƃ��o���Ă����A���s�ƃ��s�ł͂��Ԃ��Ă���Ƃ���͖����̂ő��v�B
�u�i�ւ��j�@�@�@�ā@�ā@�@��@��@�Ă�@�@�i�u�Ă��@���@����@����@�Ă���v�ŁA�^�s�̃E�i�ƃG�i�̓�̒i�j
------------------------------------------------------------
�����Ĉȉ��́u�J�s�ϊi���p�v�u�T�s�ϊi���p�v�u�i�s�ϊi���p�v�u���s�ϊi���p�v�́A��̌܂ɓ���Ȃ��ς����̂̊��p�Łu�J�ρv�u�T�ρv�u�i�ρv�u���ρv�Ɨ����ČĂ�܂��B
------------------------------------------------------------
�J�s�ϊi���p�@�@�@�@�@�ϑ��I�Ȋ��p������B�u���i���j�v�̈�ꂵ���Ȃ��B
| ��{�` | ||
| ���R�� | ���i���j | �b�� |
| �A�p�� | ���i���j | �b�� |
| �I�~�� | ���� | �b�B |
| �A�́� | ���� | �b���� |
| �ߑR�� | ���� | �b�� |
| ���߁� | ���� |
------------------------------------------------------------
�T�s�ϊi���p�@�@�@�@�@�ϑ��I�Ȋ��p������B�u�ׁi���j�v�̈�ꂵ���Ȃ��B
�ׁi���j�@�@�@���@���@���@����@����@����
| ��{�` | ���R�i���j | �A�p�i�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i���Ɓj | �ߑR�i�ǁj | ���� | �s |
| �� | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | �T�s |
| ���͂� | ���͂� | ���͂� | ���͂� | ���͂��� | ���͂��� | ���͂��� | �T�s |
------------------------------------------------------------
�i�s�ϊi���p�@�@�@�@�@�ϑ��I�Ȋ��p������B�u���ʁv�u���i���j�ʁv�̓�ꂵ���Ȃ��B
�i�s�ϊi���p���铮���́u���ʁv�Ɓu���i���j�ʁv�݂̂ł��B
| ��{�` | ���R�i���j | �A�p�i�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i���Ɓj | �ߑR�i�ǁj | ���� | �s |
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���ʂ� | ���ʂ� | ���� | �i�s |
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���ʂ� | ���ʂ� | ���� | �i�s |
------------------------------------------------------------
���s�ϊi���p�@�@�@�@�@�@
| ��{�` | ���R�i���j | �A�p�i�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i���Ɓj | �ߑR�i�ǁj | ���� | �s |
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���s |
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���s |
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���s |
| ���܂����� | ���܂����� | ���܂����� | ���܂����� | ���܂����� | ���܂����� | ���܂����� | ���s |
���s�ϊi���p�̓����́u�L��i����j�E����i����j�E����i�ׂ͂�j�E���܂�����v�̎l�B������u�`��v�ɂȂ��Ă�����̂����s�ϊi���p
------------------------------------------------------------
�Õ������̕ω��̎d��
�E�u�`�Ȃ��v��t���āA�u�`�ia�j�Ȃ��v�ɂȂ邩�ǂ��������A�Ȃ���̂܂܁A�Ȃ�Ȃ���u�`�Ȃ��v�̑O�̕������iu�j���ɕς���B
| �E�炭��� | �炭�{�`�Ȃ����炩�Ȃ��A�@�炩�u�ia�j�Ȃ��v�ƂȂ�̂ŌÕ��ł����̂܂܁B |
| �E�H�ׂ饥� | �H�ׂ�{�`�Ȃ����H�ׂȂ��@�u�ia�j�Ȃ��v�ƂȂ�Ȃ��̂ŁA�u�ׁv���iu�j���A�܂�u�ԁv�ɕς��āA�u���ԁv |
�`�e���̊��p
�`�e���Ƃ́A�����Ō����ƁA�u�����v�u���������v�u�͂������v�Ȃǂ��u�`���v�ŏI���A����l�̏�Ԃ�\�����t�ł��B�Õ��`�e���ւ̕ω��̎d���ɂ͓����Ɠ��l�ɓS��������܂��B����́A�u�`���v�́u���v���u���v�ɕς��āA�u�`���v�Ō������A�Ƃ������́B
�@�@�@�@�@�����肪�u���v�ŏI���B�N���p�ƃV�N���p�̂Q��ނ�����B
�`�e���̊��p�̎d���@�i�N���p�E�V�N���p�j
�����v�̂悤�Ɂu�`���v�ŏI���A�u���v���u���v�ɕς��邾���̂��̂́A�N���p�A�u���������v�Ȃǂ́u���v����銈�p�̓V�N���p
�u�����v�́A���R�`�́u�`�v���t�����Ƃ��u�����v�A�Ɓu���v�ɂȂ�̂ŃN���p�A�u���������v���u���������v�Ɓu�����v�ɂȂ�̂ŃV�N���p�Ƃ����̂ł��B
�u�`���v��t���Ė��R�`�Ɋ��p������̂̓J�����p�Ƃ����܂��B���p�\�����Ă��������B
| ��{�` | ���R�i�E���j | �A�p�i�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i���Ɓj | �ߑR�i�ǁj | ���� | ���p |
| ���� | �����i�j �������i���j |
�����i�āj �������i�āj |
�����i�B�j �����i�B�j |
�����i���Ɓj �������i���Ɓj |
������i�ǁj �@�@�� |
�@�@�� ������ |
�N���p �J�����p |
| ������ | �������i�j ���������i���j |
������ �������� |
������ ������ |
������ �������� |
���������� �@�@�� |
�@�@�� �������� |
�V�N���p �J�����p |
| ���� | ���� ������ |
���� ������ |
���� ���� |
���� ������ |
������ �@�@�� |
�@�@�� ������ |
�N���p �J�����p |
| �悵 | �悭 �悩�� |
�悭 �悩�� |
�悵 �悵 |
�悫 �悩�� |
�悯�� �@�@�� |
�@�@�� �悩�� |
�N���p �J�����p |
| �y�� | �y���� �y������ |
�y���� �y������ |
�y�� �y�� |
�y���� �y������ |
�y������ �@�@�� |
�@�@�� �y������ |
�V�N���p �J�����p |
| ������ | �������� ���������� |
�������� ���������� |
������ ������ |
�������� ���������� |
���������� �@�@�� |
�@�@�� ���������� |
�V�N���p �J�����p |
�`�e����
������Ŋ��p������A�������Ԃ�\���P��ŁA�q��ɂȂ�P��B�����肪�u�Ȃ�v�u����v�ŏI���B�i�����p�ƃ^�����p�̂Q��ނ�����B
�i�����p�i���͂�Ȃ�̏ꍇ�j
�����ł́A�u�`���v�ŏI���܂����A�Õ��ł́u�`�Ȃ�v�ŏI���܂��B�u�Ɂv�u����v�̂Ȃ��������̂ł��ˁB�����́u�`���v���A���̂܂܁u�`�Ȃ�v�ɒ��������ł���
| ��{�` | �ꊲ | ���R�` | �A�p�` | �I�~�` | �A�̌` | �ߑR�` | ���ߌ` |
| ���͂�Ȃ� | ���͂� | �Ȃ� | �Ȃ� �� |
�Ȃ� |
�Ȃ� |
�Ȃ� |
�Ȃ� |
�u�āv�u����v���Ȃ��������̂ƍl���܂��B
| ��{�` | �ꊲ | ���R�` | �A�p�` | �I�~�` | �A�̌` | �ߑR�` | ���ߌ` |
| ���X���� | ���X | ���� | ���� �� |
���� |
���� |
���� |
���� |
������
1.�Ӗ�������̏��������t������Ɏ������錈�܂����Ӗ��̂���
2.���p��������Ɠ����悤�ɁA���������ɖ��R�A�A�p�A�I�~�A�A�́A�ߑR�A���߂̂U�̊��p�`�������Ă��܂��B
3.�ڑ�����ڑ��Ƃ����̂́A�������ɕt�����ꂪ�A���̏������ɂ���Č`�����߂��Ă���̂ł����A���̌`�������܂�
���
||��g�A���h�E�E�E||�ߋ��A����||����||�f��||�ŏ���||��]||| �Ӗ� | ������ | ������ | (��)�炭�Ɗ��p |
| ��g�A���h�A�\�A���� | ���E��� | �`�i���j��� | �炩�� |
| �g���A���h | ���E�����E���� | �`������ | �炩�� |
| �ߋ� | ���E���� | �`�� | �炫�� |
| ����(����) | ���E�ׂ��E��ށE���ށE�܂��E�����E�߂�E�炵�E�܂ق��E�Ȃ� | �`���낤 | �炩�� |
| ���� | ���E�� | �`�i���āj���܂� | �炫�� |
| �i�s(����) | �����E�� | �`�Ă��� | �炫���� |
| �f�� | �Ȃ��E���� | �`�� | �炭�Ȃ� |
| �䋵 | ���Ƃ� | �`�̂悤�� | �炭���Ƃ� |
��g�̏������w��x�ɂ͐�ɖ��R�`�̓������t���A�ߋ��̏������w���x�ɂ͐�ɘA�p�`�̓������t���̂ł��B
��@���i��g�E�\�E�����E���h�j
�ڑ�
�u��v�l�i�^�E���ό^�E�i�ό^�Ɋ��p���铮���E�������̖��R�`�ɕt���B���̑��̊��p�^�̌�̖��R�`�ɂ́u���v���t��
�Ӗ��Ƃ��ẮA��g�����Ɂu�`�i���j���E����v�Ƃ������̂���ɂȂ��Ă��܂�
| ������ | ���R�i�`���j | �A�p�i�`�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i�`���Ɓj | �ߑR�i�`�ǁj | ���� | �ڑ� | �i��j������ |
| �� | �� | �� | �� | ��� | ��� | ��� | ���R | �炩��(�炩���) |
| ��� | ��� | ��� | ��� | ���� | ���� | ���� | �H�ׂ��(�H�ׂ���) |
�ڑ��͖��R�`�ł�����A�Ⴆ�w�炭�x�ł͍炩��A�w�H�ԁx�ł͐H�ׂ��A�ƂȂ�܂��B
�Ƃɂ����w��x�w���x�̏�ɂ͂ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����R�`�̓������t���Ƃ����킯�ł��B���Ȃ݂ɁA�������̒��͈Ӗ��ɂȂ��Ă��܂��B
e�Ae�Au�Au��Au��A�܂艺��i�̓����̊��p�Ɠ����ł��B
�y�@�\�z
�����B�u���R�Ɓ`�����v�u�`���Ȃ��ł͂����Ȃ��v�B
�S���△�ӎ��̓����\�킷�����ɕt�����Ƃ������B
�u�v�Ӂv�u�v�Џo�Áv�u�����v�u�Q���v�u�m��v�u���ށv�u���̂ԁv
�S���△�ӎ��̓����\�킷���O�R�������̕��̉������܂����ɓ~�̉����m������@�@�a��
�O�R���l���ɋ߂��R�B���R�E�[�R�ɑ���@�@�܂����Ɂ�������
�H��(��)�ʂƖڂɂ͂��₩�Ɍ����˂ǂ����̉��ɂ����ǂ납���ʂ� �@�����q�s���b�i�ӂ����̂Ƃ��䂫������j
�\�B�u�`���邱�Ƃ��ł���v�B�����Ƌ�ʂ���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B
�w�\�x���ŏ����̏������u���v�ƃZ�b�g�ŗp�����邱�Ƃ������ł��B
�������u��v�u���v�Ə������u���v�̑g�ݍ��킹���l����ƁA�������u���v�����R�`�ɐڑ����邽�߁A�������u��v�̖��R�`�u��v�Ə������u���v�̖��R�`�u���v�̌�ɑ����܂��B�u�ꂸ�v�u��ꂸ�v�u��ʁv�u���ʁv�u��ˁv�u���ˁv�̂U�������Ɍ��ꂽ�ꍇ�A�w�\�x�ŖāA���ꂪ�s���R�łȂ���w�\�x�̈ӂł���ƍl���Ă悢
�t���Ƃɗ�������Ԃƌ��Đ܂����ʐ��ɑ���G��Ȃށ@�@�ɐ�
�l�̎q�̐e�ɂȂ�Ă��䂪�e�̎v�Ђ͂��Ƃǎv�Вm�����@�N������i�₷���������̂͂́j
��g�B�u�`�����v�B
�w��g�x�́A ���҂���̓�����p���邱���������\���܂��B
�����ł́A�u�`���v�u�`����v�ƌ����\���܂��B
�}���Ȃ��l�ɐ܂�������Y�ԍ������Ɏc���A��䂪����
�Ԃ����͂��Ȃ��g��������̉ԂɌ����������̉�
���h�u���`�ɂȂ�v�u�`�Ȃ���v
���Ƃ����̂́A�u�N���v�Ƃ������ƁB �q��Ƃ����̂́A�u�N�Ɂv�u�N���v�Ƃ������ƁB
�`���ӁB���B�̂��܂ӁB���h��B
���h��͑���̓�������߂邽�߂Ɏg���܂��B
�w���h�x�́A����̎�̂ɑ���h�ӂ�\���܂��u�̂��l�������v�B�����ł́A�u�`���v�u�`����v�ƌ�������A���ɂ��u���`�ɂȂ�v�u�`�Ȃ���v�ƌ����ĕ\�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�⑫�@������
�`���B�`������B�`�\���B�\���B������͎����̓�����ւ肭����`
����̋q�̂ɑ���h�ӂ�\���B�u�̂��l�Ɍ����v
��,����@�����E�\�E��g(���h�͂Ȃ��j
�ޗǎ���ɂ́u��v�u���v�Ƃ�����g�E�\�E������\��������������܂����B���ꂪ�����������u�`��v�ŏI��铮���ł��B
�����́u������v�Ƃ��u�R����v�Ƃ����A�Õ��ł́u����v�Ƃ��u�R��v�Ƃ��ɂȂ�܂��B�����ЂƂ�������������܂��B�u�����v�Ƃ��u�R�₷�v�ł��B���Ƃ��Ƃ́A�u�`�������v�Ƃ��������������Ƃ��āA�����Ɏ�g�̏������́u��v������B�Łu����v�ɂȂ��Ă����킯�ł��ˁB�u�������v�ł��B
| ���R�` |
�A�p�` |
�I�~�` | �A�̌` |
�ߑR�` |
���ߌ` | ��ɂ����̊��p�` | |
| �� | �� | �� | �� | ��� | ��� | ���� | ���R(�l�i�E�i�ρE����) |
| ���R�` |
�A�p�` |
�I�~�` | �A�̌` |
�ߑR�` |
���ߌ` | ��ɂ����̊��p�` | |
| ��� | �炦 | �炦 | ��� | ���� | ���� | �炦�� | ���R(���E���E����E����E�J�ρE�T��) |
�������ɂ́u������v�u������v�Ȃǂɉ��ΓI�Ɏc���Ă���B
�v�����@�Â����@�������@�Y����u�v�ق�v�́u�v�͂�v����̓]�a�B���@�����i�g���A���h�j
�قƂƂ����������Ȗ����ЂƂ苏�ě��̐Q�����ʂɕ����ꂵ���i���t�W�A���Y���j
(1)�u�����ق�v�u���ڂ�v�u������v�u����v�Ȃǂ́u��v���A���ƁA���̏������ł��������A�����́u��v�ƕ����������̓����ƍl������B(2)�����̘A�̎��u������v�u������v�́A�u����v�u���Ӂv�̖��R�`�ɁA�A�̌`�́u���v���ڑ����ČŒ艻�������̂ł���B
�g��
�u���v�@�l�i�E�i�ρE���ό^�Ɋ��p���铮���E�������̖��R�`�ɕt���B����ȊO�̊��p�^�̓����E�������ɂ́u�����v��p����B�������ĉ���������A���邢�͉��炩�̎��Ԃ������N��������\�\�������g��������킷�B�u�`����v�u�`������v�B
�u�����v�@�l�i�E�i�ρE���ϊ��p�^�ȊO�̓����E�������̖��R�`�ɕt���B
�炩���@�������@������
| ������ | ���R�i�`���j | �A�p�i�`�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i�`���Ɓj | �ߑR�i�`�ǁj | ���� | �ڑ� | (��)������ |
| �� | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ���R | �炩��(�炩����) |
| ���� | ���� | ���� | ���� | ������ | ������ | ������ | �H�ׂ���(�H�ׂ�����) |
�g���ƌ����̂́u�`������v�Ƃ����Ӗ��B������u��A���v�Ɠ����悤�ɖ��R�`�ڑ�
�l���Ȃ��Â�ɂ����ɂ���l���߂�����N�����Ɏ�������
�v���̌��̌j�i����j���܂����Ƃ̕������������Ă��������h
���h�܂��͌���������킷��Ƌ��ɗp���Ă��̈ӂ����߂�B�u�`�����Ӂv�u������v�Ȃǁi���h�\���Ƃ��Ă͍ō��h��ƂȂ�j�B
[�߂�]
���@�����i�ߋ��A�L���z�N�j
| ������ | ���R�i�`���j | �A�p�i�`�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i�`���Ɓj | �ߑR�i�`�ǁj | ���� | �ڑ� | (��)������ |
| �� | �i���j | �� | �� | �� | ���� | �� | �A�p | �炫��(�炢��) |
| ���� | �i����j | �� | ���� | ���� | ���� | �� | �炫����(�炢��) |
�A�p�`�ڑ����鏕�����ł��B
������Ƃ��Ă͉ߋ��Ȃ̂Łu�`���v�ł��B�A�u���v�͑̌��ߋ��A�u����v�͓`���ߋ��A�ƂȂ��Ă��܂��B�܂�͏������l�A�M�҂�
���ڑ̌��������Ƃł�������u���v���A�ԐړI�ȑ̌��ł�������u����v���g���A�Ƃ������Ƃł�
�����i�J�ρE�T�ϓ����������j�E�������̘A�p�`�ɕt���B
- �J�ϓ����i�u��(��)�v�j�̏ꍇ�́A���R�`�ɂ��A�p�`�ɂ��t���B
��(��)���l�^��(��)�����@��(��)���l�^��(��)������
�u��(��)���v�A���邢�́u��(��)���v�Ƃ͗p���Ȃ��B
- �T�ϓ���(�ׂ��j�̏ꍇ�A�I�~�`�u���v�͘A�p�`�ɁA�A�̌`�u���v�E�ߑR�`�u�����v�͖��R�`�ɕt���B
��(��)���^��(��)�����^��(��)�����@�������^�������l�^����������
�L���ɂ��邱�ƁA��z���ꂽ�����ł���Ƃ̔��f������킷�B���ۂɌo�������g�߂ȉߋ��������ꍇ������
�V�̌��ӂ肳���݂�Ώt���Ȃ�O�}�̎R�ɏo����������
����ȗp�@
�����@���R�`�u���v�{�ڑ������u�v�B�u�����`�������Ȃ�v�Ɖ�����������邪�A�����ɂ͂��蓾�Ȃ��i�����Ƃ͐����́j���Ԃ����肷�邱�Ƃ������B���ʁA���ʂ̏������u�܂��v�Ƌ��ɗp������B
���̒��ɂ����č��̂Ȃ��������t�̐S�͂̂ǂ�����܂�
���̕����͖����Ƃ����Ӗ��ł��B
���Ԃ�U��Ԃ��ĔF�����Ă������ƁA���Ȃ킿���ȓI�F��������킷�B�������u���v�i�O���j�Ɣ�r�����ꍇ�A�u���v���ߋ��ɔF���������Ƃɂ��āA���Ԃ͎z���z���ł�����������z���Ă������Ƃ������̂ɑ��A�u����v�͉ߋ��E���݂��킸�A���Ԃ�������݂āA���ꂪ�z���z���ł���i�ł������j�����F�����Ă������Ƃ�����킷�B
�ߋ��̂��Ƃɂ��Ắu�̂́`���������̂��v�u���ɂ��Ďv���`�������v�Ƃ̉r�Q�I��ڂɂȂ邱�Ƃ�����(1)�A���݂̂��Ƃɂ��Ắu�`���Ă���̂������v�u�`���Ă��邱�Ƃ�v�Ƃ����������E�C�Â��Ȃǂ�����킷���Ƃ�����(2)�B
(1)���Ђ݂Ă̂̂��̐S�ɂ���Ԃ�ΐ͕̂����v�͂������������[���֒��̕S�l���̖���
(2)�c�q�̉Y��ł��o�łČ���ΐ^���ɂ��s�s�̍���ɐ�͍~������
���������@�u����v�̘A�̌`���r�Q�̏����u�����v�ƌ��ѕt�������́B�F���ɔ��������r�Q������킷�B�u�`�����̂��Ȃ��v�B
���������@�u����v�̘A�̌`���r�Q�̏����u���ȁv�ƌ��ѕt�������́B�Ӗ��́u���邩���v�ɓ������A�F���ɔ��������r�Q������킷
�@���i�����j
| ������ | ���R�i�`���j | �A�p�i�`�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i�`���Ɓj | �ߑR�i�`�ǁj | ���� | �ڑ� | (��)������ |
| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �Ă� | �A�p | �炫��(�炢�Ă��܂���) |
| �� | �� | �� | �� | �ʂ� | �ʂ� | �� | �炫��(�炢�Ă��܂���) |
�P�D�����Ƃ����̂́u�`���Ă��܂����A�`���Ă��܂��v���̈Ӗ��ł��B�ڑ��́u�E�ʁv�Ƃ��A�p�`�ł��B
�u�v����דI�E�l�דI�ȈӖ��̓����ɗp������X��������A�u�ʁv�����דI�E���R���ړI�ȈӖ��̓����ɗp������X�����������B
�܂����Α������ɂق֔~�̉Ԃ���Ƃ₱������̖�
�Ђނ����̖�ɂ�����Ђ̗������Ă��ւ茩����Ό������Ԃ����i���t�W�A�`�{�l���C�j
�Q�D�����i����j�̎����ɂ��āA���̓��������̎����ł��邩�̂悤�Ɍ��Ȃ��Č����ꍇ�ɂ��p������B
�M�Z�Ȃ��Ȃ̐�̂�������N���������ʂƏE�͂�
�R�D���łɏI���Ă��܂������Ƃ��ߎ��ƌ��Ȃ��A���̂��ƂŌ��������A�������\�\���邢�͂�����s�Ȃ������҂��\�\�ӂ߂�C�����܂߂Č������Ƃ�����B
�����ނƌ��Ђ�����ɒ����̗L���̌���҂��o�������f���@�t
�y�������Ƃ̌�����z
���܂��@�����̏������u�v�̖��R�`�u�āv�{���z�̏������u�܂��v�B�u�`�������낤�Ɂv�u�`���Ă����悩�����v�Ȃǂ̈ӁB���Ɂu���v�u���́v�u���̂��v�����Ƃ������B
�H���̐����ɂ��Ă��Ƃ͂ʂ��ȉ��̗t�Ȃ�Ή��͂��Ă܂�
�����@�����̏������u�v�̖��R�`�u�āv�{���ʂ̏������u�ށv�B�u�i�����Ɓj�`���Ă��܂����v�u�i�����Ɓj�`���낤�v�̈�
�Z�݂�тʍ��͌���ƎR���ɂܖ���ׂ��h���Ƃ��Ă����ƕ�
���܂��@�����̏������u�ʁv�̖��R�`�u�ȁv�{���z�̏������u�܂��v�B�u�i�����Ɓj�`�������낤�v�u�`���Ă��܂��悩���₷��͂ŐQ�Ȃ܂����̂�����X���Ă����Ԃ��܂ł̌����������Ȃ��v�Ȃǂ̈ӁB���Ɂu���v�u���́v�u���̂��v�����Ƃ�����
�₷��͂ŐQ�Ȃ܂����̂�����X���Ă����Ԃ��܂ł̌�����������
�����@�����̏������u�ʁv�̖��R�`�u�ȁv�{���ʂ̏������u�ށv�B�u�`���Ă��܂����낤�v�u�i�����Ɓj�`���낤�v�u�`���Ă��܂����v�u�`�ł��邾�낤�v�Ȃǂ̈ӁB
�s���ĕ��ӂ��Ȃ��݂�����
�������@�����̏������u�ʁv�̘A�p�`�u�Ɂv�{��z�̏������u����v�B�u�`���Ă��܂����v�u�`�����̂��Ȃ��v�Ȃǂ̈�
������@�����̏������u�ʁv�{���ʂ̏������u��ށv�B�u�i�����j�`���Ă��邾�낤�v�u�i�����j�`���Ă��܂������낤�v�Ȃǂ̈�
��̂����ɏt�͗���������̕X���܂��܂�Ƃ����
���炵�@�����̏������u�ʁv�{���ʂ̏������u�炵�v�B�u�`�����炵���v�̈�
���钆�Ɩ�͍X���ʂ炵�傪���̕�����������n�錩��
����@��i�i�s�E�����j
�ڑ�
| ���� | �c�����E�����̈Ӗ��������A���ό^�̊��p�ŁA���p��̘A�p�`�ɁA���B |
| ��{�` | ���R�` | �A�p�` | �I�~�` | �A�̌` | �ߑR�` | ���ߌ` | ���p�̌^ |
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���ό^ |
| �� | �c�����E�����̈Ӗ��������A���ό^�̊��p���A�T�ϓ����̖��R�`�A�l�i�����̖��ߌ`�ɂ��B |
| ��{�` | ���R�` | �A�p�` | �I�~�` | �A�̌` | �ߑR�` | ���ߌ` | ���p�̌^ |
| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ���ό^ |
�炯���@�s�����@�������@�������@
�炫�����@�������@�o�������@��(��)�����@��(��)����
1.���삪���Ɋ��������Ƃ̔��f������킷�B�u�`�����v�B
�ʂ�Ă͍�����������ւ��Ă�琢�����o�����S���݂̂������� �ɛ�
2.���삪�������A�Ȃ��p�����Ă����Ƃ̔��f������킷�B�u�`���Ă���v�A�u�`���Ă����v�B
�t�߂��ĉė���炵�����ւ̈ߊ��������V�̍���R
3.�u�v�u�ʁv�Ɠ������A�����̎��Ԃɂ��A����̎����ł��邩�̂悤�ɉ��z���Č����ꍇ�ɂ��p������
�����Ђ��̎R���ԓ����i���Ȃ�j�ׂĂ����炫�������Ɨ��Ђ߂���R���h�H�Ԑl
�i�s�A�����ƌ����̂́u�`���Ă���v���̌��ݐi�s���Ă���A�Ƃ����Ӗ��B�������u����E��v�ɂ͏�̂悤�Ȋ����̈Ӗ�������A��ʂ͂ǂ���̈Ӗ����K�������l���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���
���삪�p�����Ă����Ƃ̔��f������킷�B
���Ў��Ȃތ�͉����ސ��������̂��߂����������܂��~�肷���i���t�W�A�唺�S��j
���삪�������A�Ȃ����̏�Ԃ������Ă����Ƃ̔��f������킷
���R�̊₪�����ɖ̗t�����Ē������S�l�����߂��i���Řa�̏W�A�������j
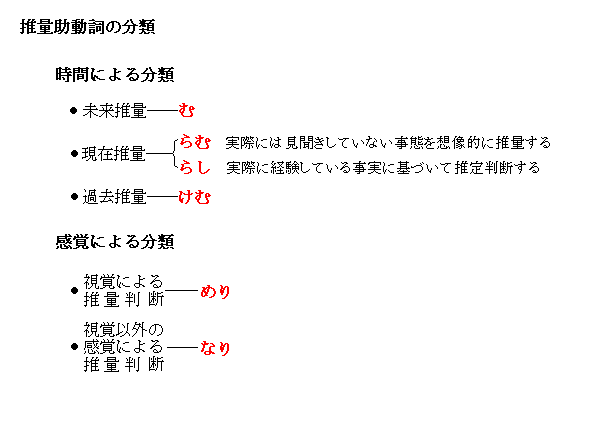
���ʂƂ����͖̂����A�\���̂��ƂŁA�u�`���낤�v�Ɩ�
| ������ | ���R�i�`���j | �A�p�i�`�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i�`���Ɓj | �ߑR�i�`�ǁj | ���� | ���p | �ڑ� | (��)������ | �������̈Ӗ� |
| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �l�i | ���R | �炩�ށi�������낤�j | ���� |
| �ނ� | �� | �� | �ނ� | �ނ��� | �ނ��� | �� | �T�� | �炩�ނ�(�炱���Ƃ��Ă��邾�낤) | ���ʁE�ӎu | |
| ���� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | �� | �l�i | �A�p | �炫���ށi�炢�Ă������낤�j | �ߋ����� |
| ��� | �� | �� | ��� | ��� | ��� | �� | �l�i | �I�~ | �炭��ށi�炢�Ă��邾�낤�j | ���ݐ��� |
| �߂� | �� | �߂� | �߂� | �߂� | �߂� | �� | ���� | �炭�߂�i�����������A�炭���낤�j | ����(��ρj | |
| �炵 | �� | �� | �炵 | �炵 | �炵 | �� | ���ω� | �炭�炵�i�炭�炵���j | ���� |
���ʂ̏������̑����͖��R�A�A�p�A���ߌ`������܂���B�Q�i�ɕ�����Ă�����͓̂�̊��p������ƌ������Ƃł��B
�u�ށv�����A�����@
�P�A�܂��N��Ȃ�����z�����u�`���낤�v�Ɛ��ʂ���B�ڑ��͖��R�`�B���g�̍s�ׂɂ��Ă��A���҂̍s�ׂɂ��Ă������B
�����т��̎R���̔��̂�������̒��X�����Ƃ肩���Q��
�Q�A�b���莩�g�̔\���I�ȍs���Ɋւ���ꍇ�A�u�`���悤�v�u�`�������v�Ƃ̘b����̈ӎu�E��]������킷�B
�����͂�݊�ɂ��������̂��Ă����Ɉ������Ƃ��v��
�R�A�����N�邾�낤�Ɛ��ʂ���鎖�����������ɂ����āA�����Ɂu�ށv��t���Ă��̍s�ׂ�����̂��Ƃł����Ǝ����B
�Ƃ����т̖��Α��ɓ���������Ԃ��ʂ�ȂމƂ̂����茩��
�S�A����v�Ȃǃ��s�ϊi���p�̗p���ɑ����ꍇ�A�u��ށv�Ɠ������ݐ��ʁE�������ʂ̈ӂ�\�����Ƃ������B�Ⴆ�A�u�������v�u��(��)�����v�͂��ꂼ��u�����ށv�u�����ށv�Ɠ����Ӗ��ɂȂ�ꍇ������̂ł���B����͏������u��ށv�����������u����-�ށv���痈����ł��邽�߁A�u����-�ށv�Łu����-��ށv�̈ӂ��p���������̂Ǝv����i�u��(��)��v�́u��i���j����v����̓]�Ɛ��������j�B
�����肭�̔����̎R�̎R�̍�(��)�ɂ�����Ӊ_�͖��ɂ����������`�{���b�l��
�������������ꍇ�A�K���u�ށv�͍Ō�ɗ���B�u�ށv�̂��Ƃɑ��̏��������t�����Ƃ͂Ȃ�
�����@�����̏������u�v�̖��R�`�u�āv�ƌ��ѕt���B�u�i�����Ɓj�`���Ă��܂����v�u�i�����Ɓj�`���낤�v�̈ӁB
�Z�݂�тʍ��͌���ƎR���ɂܖ���ׂ��h���Ƃ�����
�����@�����̏������u�ʁv�̖��R�`�u�ȁv�ƌ��ѕt���B�u�`���Ă��܂����낤�v�u�i�����Ɓj�`���낤�v�u�`���Ă��܂����v�u�`�ł��邾�낤�v�Ȃǂ̈ӁB
���̐��ɂ��y��������Η��ސ��ɂ͒��ɒ��ɂ���͂Ȃ��Ȃ�
�u�ނ��v�����A���ʁu�`���悤�Ƃ��Ă���v�u�`���悤�v�u�`���낤�v�u�`����悢�v�Ȃǂ̈ӁB�ڑ��͖��R�`
�u���ށv�ߋ����ʁ@�ߋ��̎��Ԃ𐄗ʂ����ꍇ�ɗp������B
�P�A�ߋ��ɋN�������Ԃ��u�`�����̂��낤�v�Ƒz������B�����E�������̘A�p�`�ɕt���B
�܂��������(�䂫)��蕉�Ђďo�łčs���Εʂ��ɂ��ݒQ��������
�Q�A�ߋ��ɂȂ��ꂽ�s�ׂ̌����E���R�E�ꏊ�Ȃǂɂ��āA�u�i�`������j�`�����̂��낤�v�A�u�i�Ȃ��^�ǂ��Ɂ^�N���c�j�`�����̂��낤�v�ȂǂƐ�������B
�_���̈ɐ��̍��ɂ�����܂����������������N������Ȃ���
�R�A�`���������ߋ��̍s�ׂɎv����y���Č����B�u�`�����Ƃ����v�u�`�����������v�B
�����̐^�Ԃ̓��]�ɑł��r���ʑ����������莙�����v�ق�
�������@�����̏������u�v�̘A�p�`�u�āv�ƌ��ѕt���B�u�`�������낤�v�u�`���Ă��܂������낤�v�̈ӁB
�䂪���߂Ƃ��Ȃ��߂̂��̏h�ɐD�锒�}�͐D������������
�S�ϖ�̔��̌Î}�ɏt�҂Ƌ��肵����ɂ�����
�u��ށv���ݐ����A���������@
�P�A���N���Ă��鎖�Ԃ��u���`���Ă��邾�낤�v�Ƒz������B�ڑ��͏I�~�`
���Ђ��Ăނ��т����̕X�����t�����ӂ̕���Ƃ����
�Q�A����̍s�Ȃ��錴���E���R�E�ꏊ�Ȃǂɂ��āA�u�i�`������j�`�Ȃ̂��낤�v�A�u�i�Ȃ��^�ǂ��Ɂ^�N���c�j�`�Ȃ̂��낤�v�ȂǂƐ�������B
�v���̌��̌j���H�͂Ȃٍg�t�����Ƃ�܂������
�R�A�`���������s�ׂɂ��u�`����Ƃ����v�ƛU�ȂɌ����Ȃ��B
���ɂ��ւɗ����������跌���������������䂪�v�ւ邲��
������@�����̏������u�v�̏I�~�`�ƌ��ѕt���B�u�`���Ă��܂����낤�v�u�`�����̂��낤�v�u�i�����j�`���Ă��邾�낤�v�Ȃǂ̈ӁB
�v�Ђʂ��l�̌�����������ƒm�肹���߂���܂���
���Ɩ����Ɩڂ���ʕ���~�̉Ԃ��̐l�܂ɂ�����ʂ��
�u�߂�v�@
�P�A���o�ɂ�鐄�ʔ��f�ŁA�u�`�̂悤�Ɍ�����v�̈ӁB�����E�������̏I�~�`�ɕt��
���c�͍g�t����ĂȂ����߂��n��ђ��₽���Ȃ�
�u�炵�v
�P�A���ݐ����@�q�ϓI�Ȏ���������Ă����蔻�f������킷�B�u�`�炵���v�u�`�ɈႢ�Ȃ��v�B�ڑ��͏I�~�`
�t�߂��ĉė����炵�����ւ̈ߊ�������V�̍���R
���炵�@�ߋ��̏������u����v�̘A�̌`�u����v�ƌ��ѕt�����u����炵�v�̖�B�u�`�����炵���v�̈ӁB�r�Q�̏����u���v��t�����u���炵���v�̌`�ŗp�����邱�Ƃ������B���̏ꍇ�A�u�`�����̂��Ȃ��v�Ƃ������r�Q�̈ӂɂ��p����ꂽ�B
���ԍ炫�����炵�������Ђ��̎R�̂��Ђ�茩��锒�_���炵�@�����̏������u�ʁv�̏I�~�`�ƌ��ѕt���B�u�`�����炵���v�u�`���Ă��܂����炵���v�B
�璹�����ۂ̐얶�����ʂ炵�R�̖̗t���F�ς͂�䂭
�u�܂���@�������z�̏������ƌĂ��B�b����̉��z�̒��ŁA�����ɂ͂��蓾�Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�]��A�����Ɣ��̂��Ƃ�z�������肷���ꍇ�ɗp������B�����̏ꍇ�A�u�`�܂����i�܂��j�v���邢�́u�`���v�Ȃǂ̏����߂��B���R�`�ɐڑ�
�u�ׂ��v���R�A���ʁA�\�A�ӎv�@�u�����Ȃ�̂����R�A�K�R�ł���v�Ƃ����b����̔��f������킷�B�I�~�`(���ς͘A�̌`)
�u���v�ŏ��������@�u�����Ȃ邱�Ƃ͂���܂��v�Ƃ����b����̐��ʔ��f������킷�B���ʂ̏������u�ށv�̔ے�ɂ�����B�܂��N��Ȃ�����z�����u�`���Ȃ����낤�v�Ɛ��ʂ���B���g�̍s�ׂɂ��Ă��A���҂̍s�ׂɂ��Ă������B�b���莩�g�̔\���I�ȍs�ׂɊւ���ꍇ�A�u�`����܂��v�Ƃ̘b����̔ے�I�ӎu������킷�B�܂���l�́i���邢�͌Ăт�����Ώہj�̍s���Ɋւ���ꍇ�A�u�`���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����֎~������킷�B�����E�������̖��R�`�ɕt���B
�u�܂��v �ŏ��������@�u�����Ȃ邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��v�Ƃ����b����̔��f������킷�B���ʂ̏������u�ׂ��v�̔ے�ɂ�����B�����i���ϓ����ȊO�j�E�������̏I�~�`�ɕt���B���ϓ����ł͘A�̌`�ɕt���B
�u�Ȃ�v����A�`���@���o�Ɋ�Â������f������킷�u�߂�v�ɑ��A���o�ȊO�̊��o�Ɋ�Â������f������킷�̂��u�Ȃ�v�ł���B�����E�������̏I�~�`�ɕt���B
�Ȃ�@�@�i�`���A����j�@
| ���R�` |
�A�p�` |
�I�~�` | �A�̌` |
�ߑR�` |
���ߌ` | ��ɂ����̊��p�` | |
| �Ȃ� | �\ | �Ȃ� | �Ȃ� | �Ȃ� | �Ȃ� | �\ | �I�~�`(���ς͘A�̌`��) |
�y�ڑ��z
- �����E�������̏I�~�`�ɕt���B
���Ȃ��@�������Ȃ��@��(��)�Ȃ�
-
�w��E�f��̏������u�Ȃ�v�ƕ���킵�����A�`���E����́u�Ȃ�v���I�~�`�ɐڑ�����̂ɑ��A�w��́u�Ȃ�v�͑̌����̌������̘A�̌`�ɐڑ�����B�A�̌`�ƏI�~�`�������l�i��������i�����ł͂�����Ƃ����ʂ���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B
���J�߂��Ȃ��@�`������B�u�i�����Ƃ���ɂ��j���J���߂��Ă���悤���v�ӁB
���J�߂����Ȃ��@�w��B�u���J���߂���̂ł���v�ӁB
���o�Ɋ�Â������f������킷�u�߂�v�ɑ��A���o�ȊO�̊��o�Ɋ�Â������f������킷�̂��u�Ȃ�v�ł����B�͂��߂����o�Ɋւ��鎖���Ɍ���ꂽ���A�̂��A�G�o�E�k�o�E��Z���ȂǁA���o�ȊO�̊��o�Ɋւ��鎖���ւƗp�r���L�������̂Ǝv����B
���o�ɂ���Ĕ��f���Ă��邱��������킷�B�u�`����ƕ����v�u�`����̂���������v�u�i�����Ƃ���ɂ��Ɓj�`����悤���v�B�l�͂������ɖ̗t�͎U��͂ĂĖ�Ȗ�Ȓ��͐������Ȃ�
�`���i�l�̉\�Ȃǁj�ɂ���Đ��ʔ��f���Ă��邱��������킷�B�u�`�炵���v�u�`���Ă��邻�����v�B
�䂪���͓s�̂��݂��������ސ��������R�Ɛl�͂����Ȃ�
���o�ȊO�̊��o�Ɋ�Â��Ĕ��f���Ă��邱��������킷�B
�g��̎R�̔������炵�×����ނ��Ȃ�܂����Ȃ�
���Ƃ�(�䋵)
���̂��̂��Ƃ�����ł������Ƃ������B�u�`�Ɠ������v�B�u�`�̒ʂ肾�v�B�䋵�ƌ����̂́A���̂��̂Ƃ�����̂��ׂāA�����悤�Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ������܂��B�܂�A�u�`�̂悤���v�Ɩ��Ƃ��o���܂��B��r����킯�ł��B��g�Ƃ����Ă�������������܂����B���p��̘A�̌`�A�����u���v�u�́v�ɕt���B
| ������ | ���R�i�`���j | �A�p�i�`�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i�`���Ɓj | �ߑR�i�`�ǁj | ���� | �ڑ� | ���p |
| ���Ƃ� | ���Ƃ� | ���Ƃ� | ���Ƃ� | ���Ƃ� | �� | �� | �A�� | �`�e�� |
�w��A�f��
�Ȃ�A����i�w��A�f��j
| ������ | ���R�i�`���j | �A�p�i�`�āj | �I�~�i�B�j | �A�́i�`���Ɓj | �ߑR�i�`�ǁj | ���� | �ڑ� | ���p |
| �Ȃ� | �Ȃ� | �Ȃ� �� |
�Ȃ� | �Ȃ� | �Ȃ� | �Ȃ� | �̌� �A�̌` |
�i�����p |
| ���� | ���� | ���� �� |
���� | ���� | ���� | ���� | �̌� | �^�����p |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ŏ��̏������i���@����@���@�܂��j
���@�ŏ�
| ���R�` |
�A�p�` |
�I�~�` | �A�̌` |
�ߑR�` |
���ߌ` | �ڑ� | |
| �� | �\ | �� �i�Ɂj |
�� | �� | �� | �\ | ���R�` |
�y�ڑ��z
- �����E�������̖��R�`�ɕt���B
�炩-���@����-���@�R��-���@��-���-���@�s��-����-���@�m��-���@��-��-�ǂ�
- �`�e���A�������u�ׂ��v�Ȃǂɕt���ꍇ�́A�����u����v����ĕt���B
�߂��������i�߂����\����\���j
����ׂ������i����\�ׂ��\����\���j - �u���v�̂��Ƃɏ����E���������ڑ�����ꍇ�A�����u����v����ĕt�����Ƃ�����i�����u����v�Q�Ɓj�B
�炩�����ށi�炩�\���\����\�ށj�@����������i���\���\����\����j
�y�@�\�z
�[����Ώ��q�̎R�ɖ����͍����͖����Q�˂ɂ��炵��
�y�������Ƃ̌�����z
�������A�p�`�u���v�{�ߋ��̏������u����v�B�u�`���Ȃ��̂ł������v�u�`���Ȃ��̂��Ȃ��v�B���t�W�Ɍ����A��������ɂ́u���肯��v�Ɏ���đ����邪�A�㐢�̖��t���̐l�����������A�ߑ�ȍ~�̉̐l�ɂ��p����ꂽ�B
��������Č����炷��͎����݂Đ�������ɂȂًy��������
�����Ƃ̌�����z
�����^�������@�A�̌`�u�ʁv�A�^��̏����u���v�A�r�Q�̏����u���v�B��]��\���B�u�`���Ȃ����̂��v�u�`���Ȃ����Ȃ��v�̈ӁB
�䂪������ɂ����ʂ��̌����ۂ̏�����s���Č��ނ����������@�A�̌`�u�ʁv�{�r�Q�̏����u�����v�B�ŏ��̉r�Q�B
�F��̉Y�̕l�ؖȕS�d�Ȃ��S�͎v�ւǂ����Ɉ����ʂ��������@�I�~�`�u���v�{�r�Q�̏����u���v�B�ŏ��̉r�Q�B
���̂��Ɖ_���Ɍ���鈢�g�̎R�����ĞԂ��M����m�����������@���R�`�u���v�{�ڑ������u�́v�B���z�E�����̂��Ƃɂ��Č����B(1)�u�`���Ȃ��Łv�u�`������́v�B(2)�u�����`���Ȃ��Ȃ�v�B(1)�̗p�@�͎�ɖ��t�W�Ɍ�����B(2)�̗p�@�́A�㐢�u���v�Ƒ����Ă��p������B
(1)���Ȃ������v�������ꚭ�̑����������ނׂ�����炵�����@�ߑR�`�u�ˁv�{�ڑ������u�v�B���z�E�����̏����߂�����u���́v�ɑ��A�m�肵���������q�ׂ�����߂�����B���ɂ����Ă͏��ځE�t�ڗ����ɗp����ꂽ���A��������Ȍ�͏��ڂ݂̂ƂȂ�B(1)���ځu�`���Ȃ��̂Łv�B(2)�t�ځu�`���Ȃ��̂Ɂv�B
(1)���̒���J���Ƃ₳���Ǝv�ւǂ���ї������˂��ɂ������˂�
�y����ȗp�@�z
- ���@�A�p�`�u���v�ɐڑ������u�āv�u���āv���t�����u���āv�u�����āv�̖�B��������Ȍ��ʉ������B
�v�А�₦������鐅�̖A�̂��������l�Ɉ����������߂�
���ώR�e�������R�̈�̐S���Ⴊ�v���Ȃ���
����@�ŏ�
| ���R�` |
�A�p�` |
�I�~�` | �A�̌` |
�ߑR�` |
���ߌ` | �ڑ� | |
| ���� | ���� | ���� | �i����j | ���� | ���� | ���� | ���R�` |
�y�ڑ��z
- �����E�������̖��R�`�ɕt���B
�炩�����ԁ@�R����������@�������ǂ�
�߂����������i�߂����\����\����j
�y�@�\�z
- �������u���v�Ɠ����u����v����Ȃ�u������v�̖�B�Ӗ��́u���v�Ɠ����B�������u����v�u�ׂ��v�u�ށv�ȂǂɂÂ����߂ɐ����������̂ŁA�I�~�`�͌����I�ɗp�����Ȃ��B
���Ђ݂Ă̂̂��̐S�ɂ���Ԃ�ΐ͕̂����v����������
�y�����z
�������u���v�ɓ����u����v���t�������́B�������ł��u���������Ȃ��v�ȂǂƂ������`�Ŏc���Ă���B
�y����ȗp�@�z
- �����߂�^�����߂���^�����߂���@���R�`�u����v�ɁA���ʂ̏������u�ށv�̛ߑR�`�u�߁v�A����̏����u��v�u����v�u��́v���t�������́B��������Ȍ�́u����߂�́v�������B�u�`���Ȃ����ƂȂǂ��낤���v�u�`���Ȃ��͂��͂Ȃ��v�̈ӁB
�ʂ̏����ɝ���Č��ׂ�݂�Č�ɂ���������߂��
�⑫�z
- �ߑ�ȍ~�̒Z�̂ł́u����v���I�~�`�Ƃ��ėp����Ⴊ�����Ό�����B
�͂��炯�ǁ^�͂��炯�ǗP(�Ȃ�)�킪����(���炵)�y�ɂȂ������^���Ǝ�������i�ꈬ�̍��A�ΐ��j
���@�ŏ�����
| ���l�̂Ɓu�ށv�u���v | ||||||||||||
�������u�ށv�̑ŏ������u���v�ł���A�l�̂ɂ���āA���̂悤�ɋ�ʂ����B
|
| ���R�` |
�A�p�` |
�I�~�` | �A�̌` |
�ߑR�` |
���ߌ` | �ڑ� | |
| �� | �\ | �\ | �� | �� | �� | �\ | ���R�` |
�y�ڑ��z
- �����E�������̖��R�`�ɕt���B
�炩���@�������@�R�����@�Y������@�s��������
- �`�e���ɕt���ꍇ�́A�����u����v����ĕt���B
�߂��������i�߂����\����\���j
�y�@�\�z
�u�����Ȃ邱�Ƃ͂���܂��v�Ƃ����b����̐��ʔ��f������킷�B���ʂ̏������u�ށv�̔ے�ɂ�����B
- �܂��N��Ȃ�����z�����u�`���Ȃ����낤�v�Ɛ��ʂ���B���g�̍s�ׂɂ��Ă��A���҂̍s�ׂɂ��Ă�����
�b���莩�g�̔\���I�ȍs�ׂɊւ���ꍇ�A�u�`����܂��v�Ƃ̘b����̔ے�I�ӎu������킷�B�܂���l�́i���邢�͌Ăт�����Ώہj�̍s���Ɋւ���ꍇ�A�u�`���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����֎~������킷�B
���ق����͌������߂������ꂼ���̂���ΐl�̘V���ƂȂ����
�ׂ�
���R�E���ʁE�\�E�ӎu
| ���R�` |
�A�p�` |
�I�~�` | �A�̌` |
�ߑR�` |
���ߌ` | ��ɂ����̊��p�` | |
| �ׂ� | �\ | �ׂ� | �ׂ� | �ׂ� | �ׂ��� | �\ | �I�~�`(�����͘A�̌`) |
- �u����v�Ȃǂ̃��ϓ����A�y�т���Ɠ������p�^�̏�����(�u��v�u����v�u�Ȃ�v)�̏ꍇ�A�A�̌`�ɕt���B
�����ׂ��@�Ȃ��ׂ��@�����ׂ��@�������ׂ�
�u�����Ȃ�̂����R�A�K�R�ł���v�Ƃ����b����̔��f������킷�B
- ���R�E�`���E�����B(1)�u�`����̂��悢�v�B(2)�u�`����͂��ł���v�B(3)�u�`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B
���Ȃ������v�͂��͈ꚭ�̑������������ׂ�����炵
�Q�D�K�R�E�^���B�u�`���邱�ƂɂȂ�v�B
�N�����Ă܂��z���ׂ��Ǝv�Ђ��▽�Ȃ肯�肳��̒��R
�R�D�m���Ȑ��ʁA�����m�M�B�u�����Ɓ`���邾�낤�v�u�`����ɈႢ�Ȃ��v�B
�S�D�b����̔\���I�ȍs�ׂ̏ꍇ�A�����ӎu�E������\���B�u�K���`���悤�v�u������肾�v�B
�T�D�\�B�u�`���邱�Ƃ��ł��������v�B
���킽���Δ�ǂ̍����ɐ�����Ď���ׂ���͂Ȃ�ɂ���
���ׂ��@�����̏������u�ʁv�{���ʂ̏������u�ׂ��v�B�u�i�����Ɓj�`���Ă��܂����낤�v�̈ӁB
���܂ł���ӂɐS�̂�������މԂ��U�炸�͐琢���o�ʂׂ�
���ׂ��@�����̏������u�v�̏I�~�`�ƌ��ѕt���B�m�M���Ȃė\�z����S�B�u�`���Ă��܂��������v�u�i�����Ɓj�`���邾�낤�v�u�`�ł��������v�u�`�ɂ������Ȃ��v�u�`���Ă��܂����v�Ȃǂ̈ӁB
���͂�ɂ��݂����ɂ����u���Ȑ������ׂ����̐��Ǝv�ւ��i��ڏW�A���r���j
�܂��@�ŏ�����
| �܂� | �c�ŏ����̐����E�ŏ����̈ӎu�E�ŏ����̓��R�E�s�K����֎~�E�s�\�̈Ӗ��������A �@�`�e���V�N���p�^�̊��p�ŁA���p��̏I�~�`�A���ό^���p��̘A�̌`�ɂ��B |
| ��{�` | ���R�` | �A�p�` | �I�~�` | �A�̌` | �ߑR�` | ���ߌ` | ���p�̌^ |
| �܂� | �i�܂����j �܂����� |
�܂��� �܂����� |
�܂� |
�܂��� �܂����� |
�܂����� |
�� | �`�e���V�N���p�^ |
| ���u�ށv�u�ׂ��v�u���v�u�܂��v�̊W | ||||||||||||
|
�y�ڑ��z
- �����i���ϓ����ȊO�j�E�������̏I�~�`�ɕt���B���ϓ����ł͘A�̌`�ɕt���B
�炭�܂��@�����܂��@�����܂��@�����܂��@�Y����܂�
- �`�e���ɕt���ꍇ�́A�����u����v����ĕt���B
�y�@�\�z
- �u�����Ȃ邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��v�Ƃ����b����̔��f������킷�B���ʂ̏������u�ׂ��v�̔ے�ɂ�����B
���̐��ɂ͖��������܂��~�̉Ԃ������Ȃ�Ƃ����Ȃ���
�܂�
| �܂� | �c�������z�E���߂炢�̈ӎu�E�����̈Ӗ��������A����^�̊��p�ŁA���p��̖��R�`�ɂ��B |
| ��{�` | ���R�` | �A�p�` | �I�~�` | �A�̌` | �ߑR�` | ���ߌ` | ���p�̌^ |
| �܂� | �i�܂��j �܂��� |
�� | �܂� | �܂� | �܂��� | �� | ����^ |
(1)�������z�c�m�����`�Ƃ�����`���낤�n
�b����̉��z�̒��ŁA�����ɂ͂��蓾�Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�]��A�����Ɣ��̂��Ƃ�z�������肷��ꍇ�ɗp������B�����̏ꍇ�A�u�`�܂����i�܂��j�v���邢�́u�`���v�Ȃǂ̏����߂��B
�P�A�����ɂ͋N�蓾�Ȃ����������ɑz������B�u�i�����`��������j�`���邾�낤�v�B
���̒��ɂ����č��̂Ȃ��肹�Ώt�̐S�͂̂ǂ������܂�
�Q�A���ۂɋN���������Ƃ͔��̂��������z����B(1)�u�i�����`��������j�`�������낤�Ɂv�B(2)�u�`������悩�����̂Ɂv�B
�䂪�w�q�Ɠ�l���܂������������̍~���̊��������܂�
����l���Ȃ��R���̍��Ԃق��̎U��Ȃތゼ�炩�܂�
�炩�܂��@�����܂��@�R���܂��@��(��)�܂��@��(��)�܂�
| �܂� | ����قǂ̎�����肽���܂����A���������Ă܂��B�i�\�P���E��Z�|�O�j �@�i����i�a�̂Ɠ������炢�j�قǂ̊���������Ă����Ȃ�A�]�����グ�Ă������낤�B�j �@ |
�m���R�n |
| ���̕����܂�����܂��肵���A�����Ďc�鏊�Ȃ����܂��B�i��������E���j �@�i���̕������������~�܂��ɐ����Ă����Ȃ�A�����ɂ̂܂�Ďc�炸������Ă������낤�B�j �@ |
�m�I�~�n | |
| �킪�g��Ȃ�A���炩�Ȃ��܂����A�i�X�����L�j �@�i�����̐g����ł���A�s�����Ȃ��̂ł��낤���A�j �@ |
�m�A�́n | |
| ���̂�����ނƂ���ɂāA���Ƃ����́A�r���܂����B�i�����q�E���i�j �@�i���́i�قƂƂ����̐����j�������ƌ����ꏊ�ŁA���₭�̂��r�߂悩�������낤�ɁB�j |
�m�ߑR�n |
| �܂� | ����ɂȂɂ������܂��B�i�����q�E�O���i�j �@�i����ɉ���������������B�j �@ |
�m�I�~�n |
| ��Ή͂ɂ◎��������܂��Ȃǎv�ւǂ��A�i�F���E�╨��E�Z�|�Z�j �@�i�ł���Ή��ΐ�ɔ�э���Ŏ���ł��܂������Ǝv������ǁA�j |
�m�A�́n |
|
(3)�����c�m�`���낤�n
| �܂� | ����炩�Ɍ��Ђ����������́A���ƂȂ������������܂��B�i�k�R���E��O�l�i�j �@�i�B�����ĂȂ��������������Ȃ�A���₩�ɕ����������낤�B�j �@ |
�m�I�~�n |
| ���Ȃ炸���邳�܂ɂĂ����͂��܂��B�i��������E�h�j �@�i�i�P�N�������Ă���ꂽ��j�����Ƃ���������p�ł������������ł��낤�B�j |
�m�A�́n |
�܂ق�
|
�U��U�炸�����܂ق������̋��̉Ԍ��ċA��l�����͂Ȃ�
����(��]�j
|
�m�������@�������@�H�������@����������@�s�����������u�`�������v�Ƃ�����]������킷�B
���قȂ�����������ނ��݂ƐU����������E�тĂ��邩���������̊�]�̏������u�����v�Ɍq�����Ă���