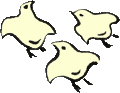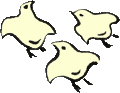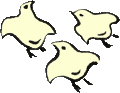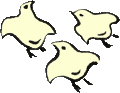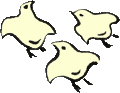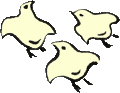よもやまなえっせい 番外編
よもやまなえっせい 番外編 
 よもやまなえっせい 番外編
よもやまなえっせい 番外編 
'05.07.09 作成
た、ゆ、た、ふ
ドウシテ コンナコトニ ナッテシマッタノダラウ―――。
隊服よりも薄い浅葱色の死に装束。
儚くて朧げで・・・冷たい。
今の自分にはお似合いだな、と山南は苦笑した。
山南は、総長という立場でありながら、局中法度を破り、明里という女とともに東へ脱走した。
途中、追っ手の沖田に追いつかれ、京へ戻ってきた。
「京へ戻る」ということがどんな意味を持つのか・・・。脱走を心に決めた時点で覚悟の上だった。
沖田には「逃げてくれ」と懇願されたが、追いつかれてしまった以上その気は毛頭なかった。
切腹の刻限も決まり、山南は前川邸の一室で静かにその時を待っていた。
障子の向こうに気配を感じふっと顔を上げると、そこには、土方が立っていた。よく見ると目の周りが真っ赤になっている。
悲しんで・・・くれているのか?
心の奥がくすぐられる様な―――こんな事態において有り得ない感情の発露なのかもしれないが―――そんな心地の良さが山南を支配した。
土方は何も言わず山南を見つめている。長い沈黙。その重い空気に耐えられなくなったのか、土方はそのまま部屋を後にしようとした。
「待ってください」
土方を呼び止める。僅かだが土方の肩が反応した。
「そこに座ってください」
土方の顔が僅かながら山南の方へ動いた。それを見た山南は、わざと視線を土方から逸らし前を向いた。
「何もいわなくて結構です。私の独り言を聞いていてください。後にも先にもこんなことお話しする事は無いと思いますから。・・・といっても、もう後はないですが」
そういうと山南は静かに微笑んだ。
土方は、これから親の説教を受けるかのごとく項垂れたまま、山南に背を向けた状態で座り込んだ。
「あの夜のこと―――君は覚えていますか?」
あの夜―――、それは土方や山南らがこの京にやってきて間もない頃の春のことだった。
その日の土方はいつになく荒れていた。
たぶんあの人と何かあったのだろう―――。その場に居合わせた隊士達の間に、暗黙の空気が流れた。土方がこんな無茶な呑み方をする時は大抵そうだったからだ。
あの人と土方とは多摩にいた頃からの無二の親友である。普段の彼は皆の意見に真摯に耳を傾け、熟慮し、行動に移すのだが、最近では頓に松平容保公の信頼が厚くなりだしたが故の『慢心』とも思しき言動が見え始め、山南や土方ともしばしば言い争いをするようになっていた。
あまりにも近すぎる存在が故のやり場のない怒りがこみ上げる。
「あいつはよぉ・・・、こっちへきてから何かが変わっちまったんだよ」
「しょうがないじゃないですか、土方さん。あの人にだって・・・きっと何らかの考えがあるんですよ」
横に座って話を聞いていた沖田がそう慰める。
「そうですよ、土方さん。ここはどうか堪えてやってはもらえませんか?」
源三郎もいつもの口調でやんわりと諭す。
「何判った風なこと抜かしてんだよッ! てめぇらにあいつの一体何が判るってんだよ!」
土方は膳の上の皿や銚子を床へ落とした。
ガシャガシャ、パリーンッ・・・。
瀬戸物が割れる時特有の高音が店内に響く。
我々以外の数名の客がその音でこちらを振り向いた。
これはいくらなんでも拙い。
「土方くん・・・、少し酒が過ぎたようだ。ここら辺で切り上げようじゃないか」
「うるせぇ! 俺はまだ呑みたりねぇんだよ!」
土方はそうタンカを切ったが、呂律は回らず、足元も覚束ない。このままでは他の隊士はおろか、店の者達までにも迷惑をかけかねない。
宿へ送り届けてきます―――、他の隊士にそう告げると、山南は土方の脇を抱え、店を出た。
店を出てもなお、暫くは小声でなにやら呟いていた土方も、少し冷静になってきたのか、一言も発せず、山南に少し凭れ掛かるような体勢で歩いていた。
春とはいえ外の空気は若干湿気を帯びていた。
「これは一雨来そうだな・・・」
山南は誰に言うでもなくそう呟いた。
ならば急がねばなるまい。一人ならまだしも、自分よりも体格のいい酔っ払いと一緒だ。濡れてしまったら余計始末が悪い。
山南は、気持ち足早に宿を目指した。
宿に戻った途端、ポツッ、ポツッと空から雨粒が落ちてくる音が聞こえ始め、それは徐々に大きくなってきた。
何とか間に合ったな・・・、安堵の表情を浮かべた山南は、土方の部屋へと向った。
「土方くん、着きましたよ。・・・今日はもう休んだほうがよさそうですね」
そういって土方を座らせ部屋を後にしようとしたものの、土方は襖の側に腰を下ろしたまま動こうとしない。
このままでは風邪を引いてしまうではないか。全く世話が焼ける人だ・・・。山南はふっと微笑んだ。部屋の隅に出したままになっていた布団を敷くと、土方をそこまで連れて行こうと手を差し伸べた。
が・・・。
いきなり土方が、差し伸べた山南の手首をかなりの速さで掴んだ。
面食らった。
あれだけ酩酊している人間にそんなことをされるとは夢にも思っていなかった。
「あの・・・、土・・・方・・・くん?」
恐る恐る土方の顔を覗き込もうとした瞬間・・・、土方に押し倒された。
あまりに突発的な出来事だったせいで、身構える事も抵抗する事も出来なかった山南は、ただされるがまま、仰向けの状態で布団の近くへ寝転んだ。
酔っ払いの悪ふざけか?
初めはそう思った。
しかし、目の前の土方の表情にただならぬものを感じた。
兎も角、この状況を打破しなければ。
「・・・何の・・・つもりです? 戯言は大概に・・・」
そこまで言った所で山南の唇は土方によって塞がれた。
苦しい・・・。
痛い・・・。
先程までの状態は全部芝居だったということか?
山南は何とか逃れようと必死に足掻いたが、両手首をがっしりと掴まれ、更に身体は馬乗りになって押さえつけられてしまっていた。
「ど・・・うし・・・て・・・」
山南の口からようやく出たのはその一言だけだった。
険しい表情のままの土方は、
「オレはなぁ、山南さん。アンタの、いつでもそうやって毅然としてる所が大ッ嫌いなんだよ! 反吐が出るぜ!」
そういうと、また山南の唇を塞いだ。
「そ、それならば何故!?」
やっとの思いで土方を押しのけることが出来た山南は、突然の土方の理不尽な行動に思わず声を荒げた。
「何でだろうな・・・。オレの虫の居所がよっぽど悪いのか・・・。酒のせいか・・・。まぁ、自分の運の悪さを恨むんだな」
そう呟くと、土方は先程よりも更に力を込めて山南を押し倒し、首筋に、胸元に唇を這わせた。
言いようもない嫌悪感が全身を取り巻く。しかし何故か、徐々に抵抗する気が失せていった。
山南は・・・俗に言う『手篭め』にされたのだ。
大の男が、男に・・・。
「あれほどの屈辱はありませんでした。私はあの場できみを八つ裂きにして、その後、喉を突いて死んでしまおうかと思いました。でも、まだ我らはこの京で何ら目覚しい働きをしているわけではなかった。帝の為、上様の為にこの命を捧げるつもりで京へ赴いたというのに・・・。その志を遂げるまでは死ぬわけにいかなかった。幸いにも、この事を知っている人間がきみと私しかいなかった。だから・・・、あの日のことは・・・、悔しさや憎しみ・・・そういったもののすべてを『何かの悪い夢だったのだ』と私の心の奥底にしまい込んでおくことに決めました。」
「芹沢さんの粛清や池田屋の一件・・・、その辺りからきみは“鬼”と化した。それもこれもすべてあの人の為。あの人を守る為には手段を選ばない、自分はどうなっても構わない・・・、そんなきみの姿を見て、私は危うさを感じていた。このままでは、きみは人の心を失って本当の“鬼”になってしまう。私は何とかしたいと思うようになった」
「その後も何度かきみは私を求めてきた。それも決まってあの人と何らかの諍いが起きた時だけ・・・。それを承知の上で拒まなかったのは・・・、その一時でもきみが“鬼”の鎧を脱ぐ事が出来るならと・・・、その一念だった。女々しい奴だと思われても・・・厭わなかった」
「しかしきみは本当の“鬼”になる道を選んだ。あの人の為に。結局私はあの人には敵わなかった。まぁ、争った相手の器が違った・・・といえばそれまでですが・・・。そう思ったら何だか空しくなった。ここにはもう、私の居場所はないんだ、と」
山南は淡々と、時折微笑を浮かべながら語った。
「それが・・・、それが理由だってのか?」
背中を向けたままただ黙って聞いていた土方がようやく口を開いた。
「あ・・・あの・・・明里とかいう女は・・・」
「明里は私にない物をすべて持っている、とても素直ないい女です。私は明里のおかげで随分と救われた。隊のことも、・・・きみとの事も、明里は忘れさせてくれた。だから、彼女とならば尊皇攘夷などという大義名分を捨てて、平凡で慎ましやかな日々が送れるのではないか・・・、そんな夢を抱くことが出来た。・・・結果的には夢で終わってしまいましたが」
そういうと、突然、山南はすっと立ち上がった。土方の背後に座り直すと、土方を後ろから抱きしめた。そして耳元で何かを囁くと、困ったような笑顔を浮かべ、元の位置へ座りなおした。そして
「もう・・・、行って下さい」
その場で呆然としている土方に退室を促した。
礼節を重んじる山南らしく、切腹の儀式は粛々と執り行われた。
最期のその瞬間まで、山南は笑顔を絶やす事はなかった。
土方は近藤とともに縁側に佇んでいた。
土方は激しく後悔した。
何故・・・、何故俺は言えなかった。
アイツは・・・、言ってくれたというのに・・・。
ワタシハ アナタヲ アイシテイマシタヨ・・・。
コノヨノ ダレヨリ キット・・・。
俺は・・・。
多分、アンタが試衛館を訪ねてきたときからきっと・・・。
きっと・・・。
土方の大きな瞳からは大粒の涙がとどまることなく流れた。
<了>