ついに第四章です。
この章の章名、ちょっと気に入ってます。
それにしても、この辺りは何度読み返しても高耶さんがツライ……(泣)。
ところで冒頭部分、
二人の松本での出会いについて書いてありますが、
あそこのシーン、原作の文章ではわりとサラリと流してあるんですよね。
だからアニメの「熱い……。胸が、灼ける……」は、
かなり感動しました。
やはり30年ぶりの再会なんだから、これくらい演出がほしいですよね~。
しかしこの小説書いた当時はまだアニメ化してなかったので、
確かコミックスの方を参考にしたんでしょう。
to be continued…
2002/10/28
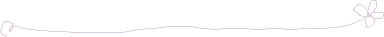
第四章 「すべての道は、開かれる」
15.
思えば記憶を失っていた年月の間、自分は決してすべてを忘れていはしなかったと、今ならば言える。
たとえば一人でいる時ふと、背中にあったぬくもりを思い出してみたり、たとえばある時突然、「誰かと一緒にこの道を歩いた……」というような、既視感に襲われたり。
あの時も、硬く冷たい床の上でうずくまって震えながら、何故かあの、あたたかいいつも自分を見つめていた微笑が脳裏に浮かんで、無性に悲しくて、あたたかくて、涙を流したんだった……。
忘れてなんかいなかったんだ。
他のことは、何一つ覚えてなんていなかったのに。
なぁ、覚えているか。高耶とおまえが初めて逢った日。
オレはおまえを思い出すことはできなかったけど、
どうしてだか、胸がどうしようもなく熱くなったんだ。
長秀や晴家と再会した時は、〝会った覚えがある〟とは思っても、あんな気持ちにはならなかったのにな……。
あれはきっと、記憶を封じ込めた景虎が、喜びのあまり泣いていたんだ。
オレはおまえとの苦しみを、おまえを忘れたいから記憶を封じたのに。
オレは記憶をなくしていた十六年間、ずっとおまえに会いたかったんだ……。
おまえに見つめてほしかったんだ……。
なのに、今は、
おまえの瞳はオレを映さない。
あの日からもう……二十三日……。
***
「中川!」
ここは浦戸アジト本部。
早朝の館内で、嶺次郎は中川の姿を見つけて声を張り上げた。
「ああ、嘉田さんおはようございます」
廊下を歩み寄る嶺次郎に中川は、外の曇天よりはいくらか明るい笑顔で返事をした。
「おはよう」
「嘉田さん、ちくっと疲れちょるんじゃないですか?眼の下にクマが出来てますよ。忙しくても栄養と睡眠はきちんと摂るようにしてくださいね」
と、顔を見るなり健康チェックをしてみせた。
嶺次郎は苦笑して言い返す。
「そういうことならわしよりも仰木に言ったらどうじゃ。あいつはここんところロクに寝てないようじゃき。もとから健康そうな顔はしちょらんかったが、今は度を越して真っ青じゃ。ありゃぁ酷い」
「……そうですね」
中川は瞳に影を落とした。自分だとて十分やつれて不健康そうな顔をしている。
「でも、言っても聞かないです。あん人は……」
「……橘の身体は」
中川は顔を少し俯かせて、ゆっくりと首を振った。
「変わりありません……」
「そう、か……」
ここ三週間ほど、毎朝の挨拶のように交わされるようになってしまった会話だ。
「見ていられません。仰木さん……」
中川は右手で額を押さえた。
「橘さんの結界を一日でも多く持続させようとして、ただでさえ危険な状態なのに、自分の魂核のことも顧みずに神経を無理矢理注ぎ込んで……。それでも通常通り仕事をこなして、尚且つ橘さんの調査に明け暮れている……。あんなことやっちょったら、いつオーバーヒートして魂核の寿命が尽きてもおかしくない!……そんなこと、橘さんが望むわけないのに……」
痛そうな声で中川は言った。一つ呼吸をおいて、再び口を開く。
「……気づいてますか、仰木さんの変調」
「……ああ」
無表情に嶺次郎は返した。
「《力》がひどく不安定です。ここ最近はずっと、これほど乱れることはなかったのに……。まるで最初に出会った頃のようです」
中川は嶺次郎に訴えかけるように言った。
「橘さんが赤鯨衆に入ってからですよ。仰木さんの《力》が安定したのは」
「…………」
「早く橘さんを、……いえ、直江信綱の魂をどうにかすべきです。そうでないとこのままこんなことを続けていけば……」
中川の目に鋭さが帯びた。
「下手をすれば、仰木さんは」
「分かっちょる」
嶺次郎は中川の声を遮った。感情を押し込めたような声だった。
窓の外に視線を移しながら、こう呟く。
「それだけ仰木にとって……橘は大きい存在だったんじゃろうな……」
存在だった───過去形。
中川は嶺次郎の真意を読み、沈痛そうに唇を咬んだ。
「ええ……」
「橘の結界は、持って三週間だと仰木は言っちょったな」
もうあれから二十三日が経つ。決断を、下さねばならない……。
「仰木……、タイム・リミットじゃ」
嶺次郎の瞳には、鋭い閃光が宿っていた……。
***
「……っ」
誰かに呼ばれたような気がして、高耶は眠りから覚醒した。
だが気のせいだったのだろうか、周りを見渡しても誰もいない。
(眠っていたのか……)
壁にかけてある時計を見て、二時間ほどうたた寝をしていたことに気づく。
「そんなことしてる暇はないのにな……」
そして目の前に横たわる人物を見つめる。
サイドチェアに座りながら、白いベッドの端に頭をうつぶせにして眠っていた。
「でも、もう少し覚めないでほしかったかもしれない……」
そう言って上体を起こし、右手でその人物の頬を撫でた。
指先に伝わる冷たさに、高耶は瞳に影を落とした。
「おまえの夢を見たんだ」
高耶はゆっくりと瞼を閉じた。
「オレが、まだ生きてた頃の。おまえと会った時の夢だった」
高耶は脳裏にその姿を思い描く。
──景虎殿。
無機質な表情。ひどく硬い声。
──謙信公がお呼びになっておいででした。
生前この男と言葉を交わしたことは、それほど多くはなかったと思う。
──そうか、すまないな。直江殿。
──いえ。
義父の腹心の家臣の嫡子。その程度の認識だった。
御館の乱で景勝方に付くより前から、どちらかというと苦手だった。
誰でも嫌いなタイプの人間というものがあるものだ。自分の場合、それがこの男だった。
勿論この男の人となりなんてそう知りはしない。けれど、この男の纏う空気がわけもなく無性に嫌いだったのだ……。
(夢の中のオレはそのまま、あの頃のようにおまえを嫌っているのが……おかしかった)
高耶は眼を開けて、いくら話しかけても返事をしないその人を見つめる。
高耶は手を離す。
──それでも見たかった。
たとえ憎んでいた頃の記憶でも、……おまえなのだから──。
高耶の瞳に感情は無かった。
微動だにせず見つめ続ける。
そこに扉が開く音が室内に響いた。
「仰木、いるか?」
高耶はハッとして視線を動かす。
医務室の扉には、潮の姿があった。
「武藤……」
「よう、久しぶり……元気だったか?」
潮は明るい笑顔を作ってみせて、後ろ手にドアを閉めた。
正午を過ぎて室内はほの暗い。窓を背にする高耶の表情は、逆光になって見えなかった。
「ちょっと暇できたからさ……。おまえ、どうしてるかと思って。近くまで来たから寄ってみたんだ」
そう言いながら潮はスタスタと歩き、白いパイプベッドを挟んで高耶と向かい合う位置で立ち止まった。
そして二人に挟まれて横たわる人物に視線を落とした。
「橘……まだ起きないのか」
高耶がピクリと身体を揺らす。
「……ああ」
そんな高耶を潮は痛ましそうな瞳で見た。
このところ忙しかったおかげで、高耶と会うのは一ヶ月ぶりだ。
橘のことは嶺次郎から直接聞いた。高耶の様子が気になって、すぐにでも駆けつけたかったのだが、重要幹部となってしまった今ではそう我侭も言えなくなってしまった。
橘がこんな事態に陥って高耶が普通でいられるわけがないということを、潮は身をもって知っている。
だからこそ、今日もそう暇という訳ではなかったのだが、無理をして訪ねて来たのだ。
(なんつー顔してんだよ……)
潮は高耶の顔を見た瞬間、その幽鬼のような姿に絶句した。
普段から高耶は無表情だ。ここ最近は笑うこともなく、しかめっ面しか潮の記憶にはない。どんな状況でも、上に立つ者として表情を崩さない。
けれど今はどうだ。なんなのだ、この、側にいるだけで切り裂かれるような威圧感に満ちた空気は。眼窩が落ち窪み、ランランと光る赤黒い瞳。その姿はまるで死神のようだ。
張り詰めに張り詰めいてる。今にも爆発したっておかしくない。
潮の杞憂は見事に的中してしまっていた。……いや、想像以上にヤバイ。
潮は何と声を掛けて良いのか分からず、一つ溜息をついて再び視線を落とした。
ベッドに横たわる直江は、紙のように肌が白く、息をしていないので身体も微動だにしない。
瞼が硬く閉ざされた横顔は端整で、死体と言うよりは蝋人形のように見えた。
「よく見るとキレイな顔してんだな……」
潮は何とはなしに手を持ち上げ、直江の前髪に触れようとした。
すると……。
「さわるなッ!」
突然の叫び声に驚いて顔を上げると、高耶がこちらを鬼のような形相で睨みつけている。
「おう、ぎ……」
眼を瞠って思わずこぼした呟きで、ふと高耶は我に返ったのか、身体を一瞬揺らして気まずそうに俯いた。
「……橘の身体は結界を張ってある。なるべく他の者の気を触れさせない方がいいんだ……」
無論、術をかけた高耶は別だ。
けれど潮には、高耶が無理に言い訳をしているように聞こえた。
(誰にも触らせたくねぇって、俺には見えるけどな……)
「けどもうその結界も、とっくに切れる頃じゃねぇのか」
潮は真剣な顔をして高耶に言った。
「まだ結界が切れずに残ってんのは、仰木、おまえが無理してるせいだろ……!」
「ち、が……っ」
「嘘つけよ!そんな青い顔しやがって。おまえの方こそよっぽど死にそうじゃねぇかっ。俺だって多少は呪術も分かるんだ。こんな無理なことやって、ただですむと思ってんのかよ……!」
「武藤っ」
「そうじゃぞ仰木」
突如聞こえた第三者の声に、二人が同時に振り返ると、入り口に嶺次郎と中川が立っていた。
嶺次郎はゆっくりと三人に近づきながら、言葉を続ける。
「おんしは確か、この結界は持っても三週間が限度だと言った。だがもうとっくに三週間は過ぎた」
隣りに立つ中川も口を開いた。
「これ以上続けるのはあまりにも危険です。結界を保ち続けると共に、確実にあなたは自分の命を削っているんですよ!」
「ちがう!」
「仰木、もう諦めるんじゃ。わしらはおんしを失うわけにはいかんがじゃ。……おんしの気持ちは分かる。だが……」
「分からないッ!」
今にも射殺すかのように強烈な両眼で嶺次郎を射抜き、高耶はいきなり叫んだ。
「分からない分からない分からないっ!ここにいるヤツらに直江とオレのことは分からないっ、分かるわけがないッ!」
高耶は立ち上がって叫び散らした、禍々しい光を放つ両眼は既に焦点が合っていない。錯乱状態に陥っている。
「分からないんだ!そんな、オレ達のっ、直江のッ」
「仰木っ、落ち着け!」
「なおっえ……な……ッ」
その時。
いきなり背後の窓から黒い物体が室内に飛び込んで、高耶に体当たりした。勢いで高耶は床に膝を付く。
「小太郎っ、なにやっ……!?」
潮が驚いて声を上げる。黒豹は高耶に近寄って顔を覗き込んできた。そして高耶は小太郎と眼が合った瞬間、ビクリッと大きく身体を揺らした。
そのまま五秒程度両者はピクリとも動かずに、まるで時が止まったかのように見つめ合う。
(何なんだ……!?)
潮ら三人がわけが分からず茫然としていると、高耶が口を開いた。
「そう、か……小太郎。おまえがいたな……」
高耶は正気を戻したようであった。そうしてそのまま顔を俯かせて黙り込んでしまう。
潮達には何故、小太郎が現れたことによって高耶が鎮まったのかが分からなかった。
だがこの小太郎こそが、景虎が四百年を越えて抱き続けた直江に向ける狂気じみた執着を肌で知る、数少ない人物の一人であり、そして一番の被害者でもあるのだ。
もっとも、小太郎の正体を知らない三人には、想像すべくもないことだ。
「仰木……」
「…………」
高耶は答えない。
「橘は死ぬわけではない、また換生し直せばいい。……もう会えないわけではないんじゃ……そうじゃろ仰木?」
嶺次郎は静かに、言い聞かせるように話しかける。
「だからもう、諦めるんじゃ」
高耶は無言のままだった。横顔は前髪で隠れて、表情を読むことができない。
「仰木……っ」
潮が、たまらず声を上げた。
「おまえが無理して自分の魂削って、そんなことして一番苦しむのは橘だろっ!?」
その時初めて高耶が顔を上げた。そしてめいっぱいに見開いた双眸で直江を見つめた。
「自分のせいでおまえの命が傷ついて、橘が喜ぶとでも思ってんのかっ。そんなことおまえが一番分かってんだろ、仰木!」
高耶は茫然としていた。
直江が望むことを誰より知っているのは自分であるのに……自分は……。
嶺次郎が再び口を開いた。
「仰木……」
「…………」
「仰木、ケリをつけろ」
高耶は苦しげに、ゆっくりと眼を閉じた。
(直、江……)
分かっているのだ、高耶も。こんなことを続けるわけにはいかない……。
決心を、つけなければ……。
「出ていってくれ」
高耶の呟きに、嶺次郎は顔を歪める。
「仰……」
「最後に」
嶺次郎の声に重ねるように、高耶は告げた。
「最後に別れを……」
高耶の声は抑揚がなく、横顔は彫像のように無表情だったが、その眼には引き裂かれたような痛みが灯されていた。
「そう、か……」
厳しい表情で呟いて、三人と黒豹は医務室を辞した。
for your and my eternal happiness.
Someday, I will pray to the meteor
オレ
オレ
・ ・ ・