 煙の酸でボロボロです。 |
 プラスチックの波板で補修。 |
 このような状況です。 |
 片側のトタンを外しました。 |
 丸太を組んで作ってあります。 |
 両側のトタンを外しました。 |
 4月2日、 柱が腐っていました。 |
 濡れないようにブロックを。 |
 全部で6箇所です。 |
 4月6日、トタンを張りました。 |
 6尺のトタンですが足りません。 |
 ポリの波板を継ぎ足しました。 |
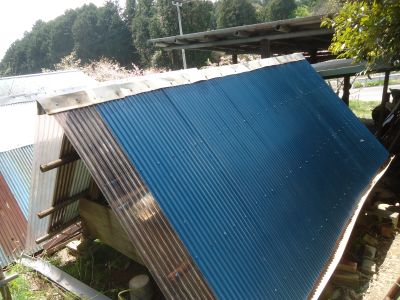 |
 |
 |
 4月9日、窯の修理開始。 |
 壁や天井を崩します。 |
 土のう袋で保管します。 |
 4月12日、天井を崩しました。 |
 厚みはおよそ10センチ。 |
 ここも同じようです。 |
 穴の空いた方は5センチ。 |
 天井を更に崩しました。 |
 壁の上端が出ました。 |
 4/21、前回修理した壁です。 |
 この耐火レンガを再利用。 |
 50個以上ありました。 |
 土のう袋も80枚弱使いました。 |
 レンガをこの形で使います。 |
 入口に向かってこんな形です。 |
 新しい粘土を篩ってきれいに。 |
 半分は使った窯の土を使います。 |
 捏ねた土をレンガに載せて。 |
 またその上にレンガを載せて。 |
 丈夫な壁を作ります。5月16日 |
 2号窯の天井が落ちました。18日 |
 まずは1号窯から直します。 |
 今4段目を積んでいます。 |
 新たに土を篩って準備。5月22日 |
 石灰も少し入れて。 |
 5段目を積みます。5月26日 |
 入り口に向けて。 |
 6段目を積んでいます。6月1日 |
 壁の最上段になります。 |
 湿った土を乾燥させてから |
 篩います。6月5日 |
 いよいよ左側の壁、完成。 |
 土が大量に必要でした。6月9日 |
 右3段目を積みます。6月13日 |
 右6段目を積みます。6月25日 |
 あと、1段積むかどうか思案中。 |
 レンガはなしにしました。7月1日 |
 こんな感じになりました。 |
 左側も積直しをしました。7月7日 |
 垂直に積めなかったためです。 |
 右側に取り掛かりました。 |
 少ししか積めません。7月18日 |
 畑仕事の合間の仕事。8月3日 |
 熱中症に気をつけて。 |
 無理なく進めています。 |
 あと少しで釜の淵完了。8月7日 |
 8月中に壁を作る予定。 |
 出入り口の作業にかかります。 |
 出入り口の壁作り。8月20日 |
 |
 |
 入り口の仕上げ。8月26日 |
 天井を突くときの支え。 |
 壁づくりの完成。 |
 窯に竹を詰めました。12月17日 |
 天井を突くときの土台です。 |
 天井を固めるのに必要です。 |
 3月1日、竹の上に丸太を置いて。 |
 木の枝を置いて打ち付けました。 |
 自然なカーブになるように |
 上部は薄くカットして |
 下部もカットして釘止め。 |
 これぐらいでしょうか。 |
 篩に穴が空きました。 |
 新たに篩を作りました。 |
 あとは土を篩って準備するだけ。 |
 土を運ぶ、約80kg。4月12日 |