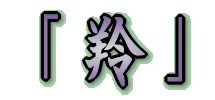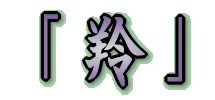| ◇ |
明治42年11月15日岡山市西大寺にて生まれる。 |
| ◇ |
17歳で俳句を学び、鋭い感性で新しい句を詠む青年俳人として、岡山、呉、広島で活躍、召集を受け入隊。戦後、焦土と化した広島に同志を糾合し、俳誌『野火』を創刊。昭和35年ごろ、高柳重信が率いる『俳句評論』の広島支部長となり、赤尾兜子、阿部青鞋、野田誠、永田耕衣、細谷源二、金子兜太などと交流、俳句研究誌『木椅子』を発刊。 |
| ◇ |
広島県県庁職員として勤務し、定年退職後は、原爆福祉センターに勤める。 |
| ◇ |
昭和50年、富士山麓、猪之頭に転住。創作の場を島田市の田中陽主宰の『主流』に拠る。新しく口語俳句を始め、昭和53年には口語俳句協会賞を受賞する。 |
| ◇ |
昭和56年、富士宮市「富士脳研病院」内の俳句会(オレンジ句会)の講師となり、昭和59年、「羚」を立ち上げ初代代表となる。 |
| ◇ |
句集 『魚族の列』 (平成9年刊) |
| ◇ |
句碑 富士宮の田貫湖に近い天子の森に建立。 (平成11年5月) |
|
−霧の五戸よるは夜霧のともしび五つ− |
| ◇ |
平成12年、口語俳句協会相談役に就任。 |
| ◇ |
平成13年、口語俳句全国大会(富士大会)実行委員長をつとめる。 |
| ◇ |
平成14年、富士宮市「フジヤマ病院」にて逝去。 (享年93歳) |