| 50ヘルツと60ヘルツ | |
| わが国の電気は、地図で示すように、標準周波数が50ヘルツ(Hz)の地域と60ヘルツの地域に大別されている。 | |
| 50Hzと60Hzの違いは、家庭における電化製品の使用にも影響を及ぼすことがある。特に電子レンジとか蛍光灯などは、それぞれのヘルツに合ったものでないと作動しないなどの現象もあらわれてくる。 | 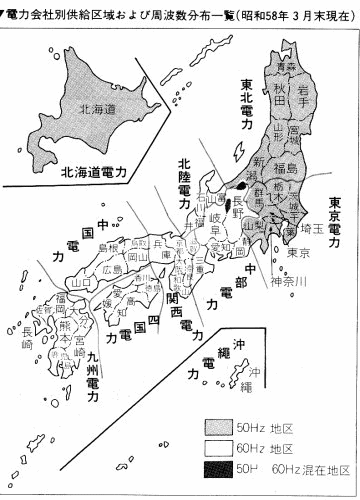 |
| また、工場で使われる機械類にも、それぞれのヘルツに対応する設計が要求される。このような違いはどのようにして生じたのだろうか。 | |
| これは、その昔、わが国の電気事業、特に発電機の設置の時代までさかのぽらなくてはならない。 | |
| 交流式の発電機による発電は、明治29年12月、浅草にドイツのアルゲマイネ社製三相交流式発電機(3000ボルト出力265キロワット)6台が設置されたのがはじまりである。これが50Hzの発電機であった。このために、同発電所への系統連系の必要から、東京電燈の供給区域では、50Hzが広く使われるようになった。そして、昭和に入ってから、東日本の標準周波数50Hzが採用されるようになった。 | |
| これに対し、西日本では、明治29年、大阪電燈が米国のゼネラルエレクトリック社の60Hzの発電機を大阪幸町の発電所に設置したのがはじまりで、京阪神を中心に60Hzが普及し、これが西日本の標準周波数として今日に至っている。 | |
| このように、ヘルツの違いは、はじめに設置された発電機の種類によって、東日本と西日本と2つにわかれるようになった。しかし、現在でも長野県の北部は50Hzと60Hzが入りくんでいたり、新潟県の西南部と佐渡島は60Hzであったりする地域もあるが、これはごくわずかである。 なお、Hzの違いによって電気器具は、右のような影響を受ける。 |
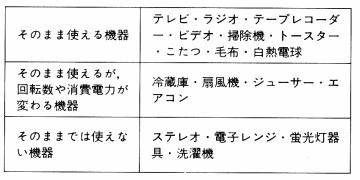 |