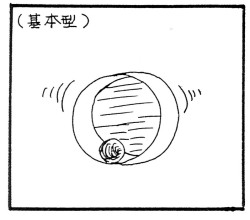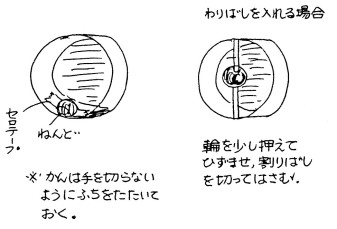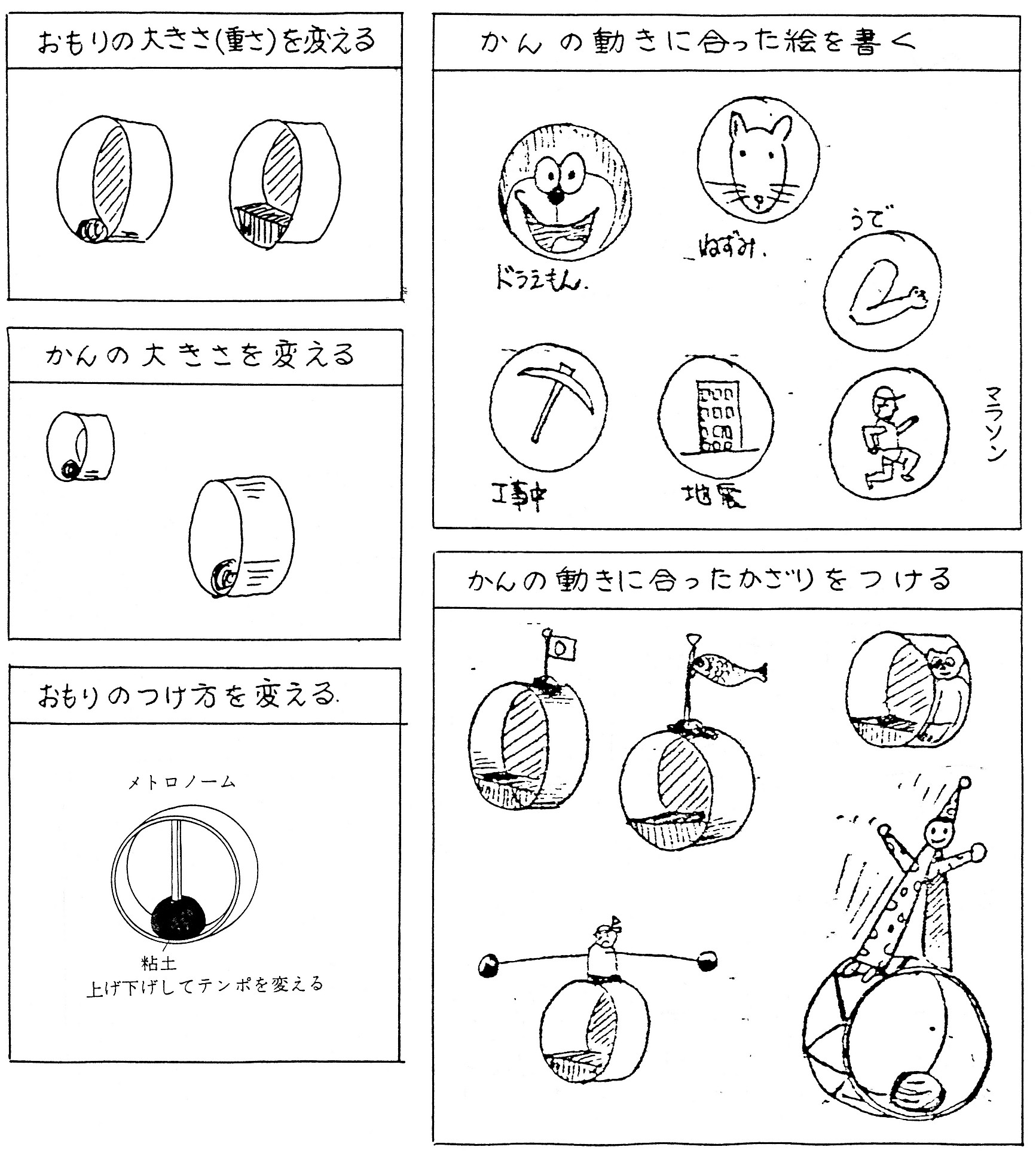| おきあがりこぼし |
|
あきかんの中におもりをつけて、左右に傾けたり、ゆらしたり、ひっくり返しても、もとのような状態に戻る様子を楽しむものである。原名は、「起き上がり小法師」(おきあがりこぼうし)である。
だるまや、卵形のものが、幼児のおもちゃや民芸品の中に数多く見受けられ、日本人に古くから親しまれている。 |
 |
|
| ◆しくみと動き |
|
|
○ |
転がったり、左右にゆれたりしても、必ず一定の位置に戻ることが基本である。 |
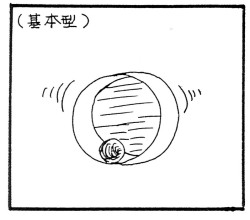 |
|
○ |
重心が低いところにあるものほど安定がよく、ゆらすと、支点は、左右に移動するが、最終的には、おもちゃの重心の真下に来てとまる。 |
|
○ |
つくりの上では、「ゆりかご」や「かんころがし」に類似しているが、おもりの数やはたらき、あるいは、求められている動き方などの点では、はっきりした違いがある。たとえば、「ゆりかご」は、揺れ続けることが生命であり、「かんころがし」は、転がり方の楽しさが生命である。そして、おきあがりこぼしは、必ず元にもどる、いわゆる復元力が生命である。 |
|
|
|
| ◆児童の自然認識 |
|
|
|
おもりの重さや位置を変えることによって、ゆれる速さや時間の長さを変わることに気付く。 |
| 1 材料と道具 |
|
|
|
あきかん(魚などの缶詰)
印画紙用芯、ガムテープの芯、厚紙 |
数種類 |
| 粘土、ビー玉、釣り用おもり |
数種類 |
| セロハンテープ |
少々 |
| 割りばし |
少々 |
|
| ABC 3段階 |
| 扱い |
作りやすさ |
A |
| 材料の入手しやすさ |
A |
| 安全性 |
A |
| 魅力 |
動きのおもしろさ |
A |
| 活動するおもしろさ |
A |
| 工夫 |
改良のしやすさ |
A |
| 発展性 |
A |
|
|
|
|
|
| 2 作り方 |
|
○ |
右の図のように作る。 |
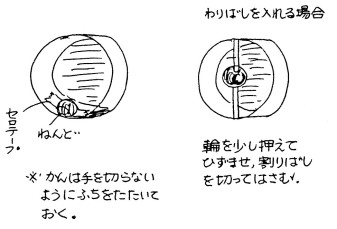 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 3 工夫できること |
|
|
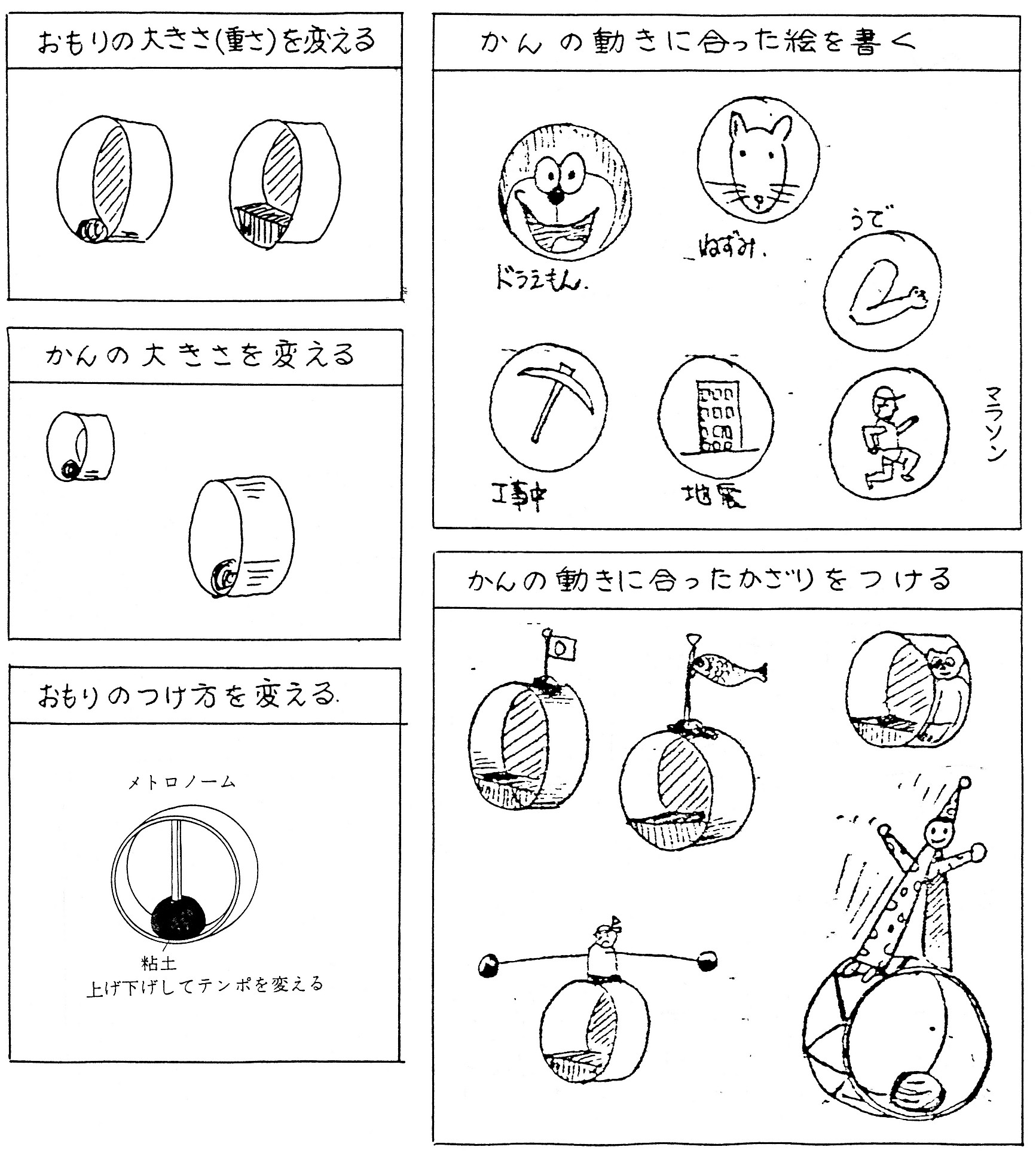 |