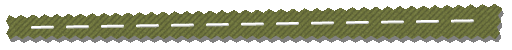
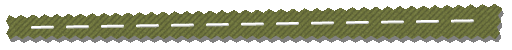

☆大石一太郎支部長挨拶要旨
東部地域全体でみた場合、山間部や伊豆地区では人口減少は切実な問題となっている。三島市は幸いなことに建設は校長であるが、それでも空き家が増えている。本日の講演は、まさに時宜を得たものであり、多くの示唆をいただけるものと大いに期待している。
☆豊岡武士三島市長挨拶要旨
今年もまた、三島市で中央大学学術講演会が開催されることに対し、心から感謝申し上げる。また、大石支部長には、三島市議会議員として、三島市の発展のため御活躍いただいている。空き家対策としては、①建物が朽ち果てる寸前となり、危険家屋が地域の懸案となってしまっているもの。②まだまだ十分に利用できる物件の活用策 という2つの側面がある。
少子高齢化が進む中、三島市でも移住希望者を募り、空き家を有効活用し、定住促進に取り組んでいる。新幹線を利用できる三島市は、首都圏の通勤圏内にある。平成28年度は70人が移住している。本日の野村修也先生の御講演が参加の皆様に有意義なものとなることを祈念する。
(豊岡市長には、公務の都合で挨拶のみ。なお、小坂副市長には講演を最後まで聴講頂いた。)
☆野村修也中央大学教授の講演要旨
本日の講演のテーマは「空き家は財産」という視点
先程の三島市長が挨拶の中で、空き家対策の2つの視点を述べておられたが、本日はまだ使える空き家について話したい。
空き家対策の専門家でもあるのか?と聞かれるが、私の専門は「商法」、つまりビジネスのルールである。日本は欧米などと比較すると非常に規制が多く、それがビジネスを阻害している。不要なルール、制度の見直しということで、昨年度はフィンテックであったり、本年度は空き家問題などが研究テーマとなる。
日本で空き家が増えている理由の一つに、更地は固定資産税が高いという税制上の問題がある。これについては、平成27年から「特定空家」制度が導入され是正が図られつつある。
日本には、新築神話、持家を住みつぶすという独特の考え方がある。中古車のように中古住宅の市場というものが育っていない。流通しないから住宅は価値がない、とされている。家はお荷物であり、住宅が建っている土地の売却値段は、家屋の解体費用を差し引かれる。
一方、欧米では中古住宅が流通しており、アメリカでは9割近くが中古住宅である。また、ドイツでは、住宅市場全体に占める中古住宅は50%程度であるが、空家率は1%未満である。中古住宅はどんどん売れるので、空家にならない。
中古住宅の利活用には、街のデザインが大切。つまり、街が魅力的になり人が集まれば空き家問題は解消してしまう。
日本では、建物は10年経ったら無価値になるという、都市伝説、大人の常識がある。だから、交換価値を維持するために手を加えるという考えがない。また、手を掛けてもその証拠書類を残しておかない。
中古住宅が売買の対象として広がらない背景には、「瑕疵担保責任」がある。シロアリ被害などが後からわかって、責任を追及される位なら、最初から無価値にしてしまえばよいと。
街のデザインを踏まえた子育て世帯の移住促進は全国各地で進んでいる。
自宅を空家にしないためには、(中古車売買と同じように)図面や修繕履歴等、関係書類をしっかり保管しておくこと。メンテナンスをしっかりと行う。10年で無価値などという都市伝説は信じないことだ。むしろ、手入れをした住宅は20年経っても資産価値がある、を信じる。
<質疑応答>
質問:
伊豆では、2020年の東京オリンピックパラリンピックで自転車競技が開催される。空き家は選手や観客などの宿泊施設として有望だと思う。国では具体的な動きはないのか?
回答:
はっきり言って、そうした動きは鈍い。考えても動かないのが日本の欠点。少子化問題も皆気付いていても効果的な施策が行われずに来ている。誰かがやってくれではなく、、自らが動いて変えていこう。長期滞在型の選手のための宿泊所とか・・。
挨拶及び講演要旨は、富士白門会でまとめたものです。誤りやその他不適切な表現などがありましたら、それらは全て富士白門会の責任ですので、メール等で御指摘いただければ幸いです。