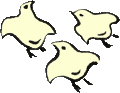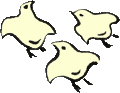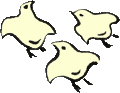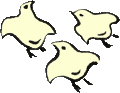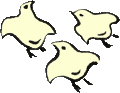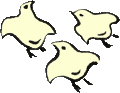よもやまなえっせい 番外編
よもやまなえっせい 番外編 
 よもやまなえっせい 番外編
よもやまなえっせい 番外編 
'06.05.19 更新
た、ゆ、た、ふ 〜大切なもの〜
近藤勇は悩んでいた。
今自分が抱いている懸念を、この場で晴らしてよいものかどうか。
きっとこの人―――山南敬助は、全ての想いを墓場まで持っていく覚悟でいるに違いない。それに、私がそれを聞くのは、何人たりとも決して立ち入ってはならぬ『聖域』を犯すような行為であるということは明らかだ。単なる興味本位と取られても仕方がないだろう。
しかし今ここで確かめなければ、アイツもこの人もきっと後悔するのではないだろうか?―――近藤はそんな妙な使命感に次第に囚われていった。
それにしてもどう切り出せばよいものか。あれこれ悩んでみた所で、気の利いた言葉が浮かんでくるわけでもない。ここは一つ、いつものように正面切って事に当たった方が、案外よい結果が生まれるのではないだろうか?
近藤は腹を決めた。
「あの・・・一つ伺っておきたいことがあるんですが、よろしいですか?」
「え?・・・えぇ、なんでしょう?」
少し間を空けて、意を決したように近藤が訊ねた。
「・・・あなたの・・・本当に大切な人は・・・誰ですか?」
「・・・それは・・・どういう・・・」
予想だにしなかった近藤からの問いかけに山南は、質問の意図が読めず若干戸惑っていた。
「先ほどいらした、明里さん・・・でしたっけ? あの方を大事に想ってらっしゃるのは・・・よく解りました。しかし・・・、私には、あの方以上に大切に想っている人が他にいるのではないか・・・、そう思えてならないのですが」
山南は眉をひそめた。
「何を・・・根拠に?」
あくまで表面上は冷静沈着を装ってはいるものの、それは心の乱れを何とか悟られまいとする山南の精一杯の演技のように近藤の目には映った。近藤は大きく一つ息をつくと、山南から視線を外し話し始めた。
「・・・いつだったか忘れましたが、総司から、山南さんの・・・この辺りに痣があったのを指摘したら、顔を赤らめて俯いた、という話を聞かされました。アイツは子供なのでそれがどういう意味なのかよく解らなかったようですが・・・」
首の付け根の辺りを二、三度指差した近藤は、照れ隠しなのかおでこを掻いた。山南もその時のことを思い出し頬を赤らめた。
「その時に、山南さんにもその・・・どなたかいらっしゃるんだな、と思ったんです。でもそれはかなり前の事だったように記憶しています。総司に聞いたら、あなたと明里さんがお知り合いになったのは最近のようですし・・・。そうすると、明里さんとは別の人なんじゃないか、と・・・」
近藤は更に続ける。
「身体に跡がつく位となると女の人ではちょっと・・・。まぁ、余程の情念を抱いている方なら稀にあるかもしれませんがそれも・・・考えにくい」
この人は何が言いたい?―――山南は明らかに動揺しはじめていた。そんな山南の姿を近藤は見て見ぬ振りをしているようだった。
「となると相手は・・・多分・・・」
近藤は苦渋の表情を浮かべ口をつぐんだ。その先に来る言葉はあえて言わずとも察しはついた。山南は下唇を強く噛み締め、目を閉じた。
「無論あなたの方から、ではなく、相手のほうから何らか行動を起こされて、いつしかそういった感情を抱くようになった・・・。そうですよね?」
あまりの洞察力に山南は何もいえなかった。膝に乗せていた掌を強く握り締めた。
暫くの沈黙の後、近藤がこう切り出した。
「もしかしてそれは・・・、トシ・・・いや・・・土方・・・ですか?」
決して悟られまいと思っていたのだが、『土方』という名を聞いて無意識に山南の身体がびくっと反応してしまった。その姿を見て近藤は「やはりそうだったか」という表情で天を仰いだ。
「私が思うにアイツは・・・、かなり前からあなたの事を・・・その・・・想っていた様に思います」
近藤の口から出た突拍子もない推論に、山南は驚きを通り越した表情を浮かべた。
「何故・・・そう思われるのです?」
困惑まじりの笑顔を浮かべながら山南は聞いた。
「私もアイツとは付き合いが長いので、なんとなく・・・、素振りでわかるんです。アイツはそれまで、本気で誰かをいとおしいと思ったことはなかったと思います。あの通りの顔立ちですから、アイツが何もしなくても女の方が放ってはおきません。ですからアイツは・・・そういったことでは何一つ不自由したことはなかったですし、本気になる必要もなかった」
私も結構被害に遭いましたしね、そういって近藤は苦笑した。
「確かに初めは、・・・あいつも頭の良いヤツなので・・・、博識で剣の腕も立つあなたのへ嫉妬心から、あなたの事を疎ましく思っていたのではないかと思います。しかし暫くたった頃、私は、アイツのあなたに対する態度に変化が出始めたことに気付きました。口では結構強がってましたけど・・・。ちょうど・・・そうですね・・・。あ、幼いころにいませんでしたか? 好きな者をわざと困らせて気を惹こうとする悪がきが。多分、そんなところだと思います。・・・そう考えるとアイツも子供だな。総司の事は言えない」
近藤は楽しそうにくすくす笑った。が、すぐに「あ・・・、失礼しました」と詫びると真面目な顔に戻って話を続けた。
「多分アイツはあなたの事を心からいとおしいと思っているはずです。アイツは素直じゃないから、きっと、あなたには何も伝えてはいないと思いますが・・・」
確かに、逢えばお互い出るのは毒のある言葉だけだった。だからといって・・・、いや、そんなことは・・・。そんな山南の心を見透かしたように、
「『そんな事、あるはずがない』・・・とでも言いたそうですね。でも、そう言い切れますか? きっとあなたも薄々気付いていたはずだ」
近藤はきっぱりとそう言い切った。近藤の言葉に山南は狼狽していた。
「し、しかしそれは・・・。あの人はあなたの事を・・・」
山南がそこまで言いかけたところで近藤は笑顔で首を横に降った。
「アイツにとって私は・・・、いわば自分の一部のような存在なのではないでしょうか。例えば親兄弟や子供とか・・・。そういったものに対する感情―――、『恩愛』・・・でしょう。あなたへ抱いている感情とは・・・また違う」
そう語る近藤の視線は、まるでいとおしいわが子を見つめる時のような『慈愛』に満ちていた。『近藤勇』という人は単なる無骨で堅物な男ではないのだ。
「あなたが脱走したと判ったときのアイツの動揺の仕方は尋常じゃなかった。その時に・・・アイツのあなたへの想いを確信した。だから改めて伺います。・・・あなたの本当に大切な人は・・・誰ですか?」
痛いほどまっすぐな眼差しを向けられた山南は寂しげに微笑みながらこう言った。
「やっぱり・・・、あなたには敵わない」
床に両手をつけ、こう続けた。
「・・・お察しの通り・・・私は土方歳三を愛しております。人の道に外れたこととは重々承知の上ですが・・・。この世で一番・・・大切に想っております」
近藤の眼差しに負けないほど、まっすぐ、強い口調でそう言うと、深々と頭を垂れた。男色嫌いの近藤から侮蔑した態度をとられても致し方ないと思っていたのだが、意外にも、
「それを聞いて・・・安堵しました。出来ればそれを・・・直に言ってやって下さい」
まぁ、アイツが素直に喜ぶとは思いませんけど―――。そう言って苦笑していた。
その時―――。近藤勇の度量の大きさ、懐の深さに改めて敬服した。この人についていこうと決めた自分の判断は、やはり間違いではなかったのだ―――と山南は確信した。
「私の・・・最期の願いを聞いてもらえますか?」
「ええ」
「私に・・・遠慮は無用です」
いつもの微笑をたたえながらも、その口調は凛としていた。
「私が腹を切ることで、新選組の結束はより強固なものになるでしょう。しかしこれが、結果的に、あなた方を引き返せない所まで追い込んでしまう事になりはしないかと・・・、それが心配なのです。私の事はどうでもいい。『私』という足枷を作らないで欲しい。どうか・・・それを・・・」
目を真っ赤にした山南が言葉を詰まらせた。
「私より・・・トシが・・・。私もそうだが、アイツはそれ以上にあなたをこんな形で失いたくはなかったはずだ。アイツがもう少し素直なヤツだったら・・・」
「素直じゃないのは・・・お互い様です」
一人の愛すべきものを案ずる二人の目には大粒の涙が光っていた。
山南の切腹の後、近藤と土方は縁側で佇んでいた。
「なあ、トシ・・・」
近藤が長い沈黙を破った。
「お前・・・山南さんと逢ったのか?」
「・・・ああ」
土方から返ってきたのは、心此処に在らず、という返事だった。
「あの人・・・、なんか言ってたか?」
「ん?・・・うん・・・まあ・・・な」
近藤はそれ以上深く聞くつもりはなかった。土方のその返事だけで全て読み取れた気がしたからだ。
「俺も山南さんと話をしたよ。あの人とあんな風に話すの、多分初めてだったと思う。・・・もっと早く・・・そうするべきだった・・・。そうすれば、こんなことにならずに・・・済んだかも・・・しれないのに・・・」
近藤は目に光るものが零れ落ちぬ様、必死で堪えながらそう呟いた。
暫くすると、土方が堰を切ったように体裁も構わず泣き崩れた。多分こいつがここまで泣いた姿を見たのは、初めてのような気がする。辛かったのだ、こいつが一番・・・。
土方の肩をぐっと抱き寄せて近藤も泣いた。同時に、これからの新選組の行く末に一抹の不安を感じていた。