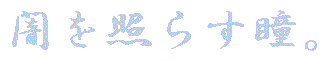 ―前篇―
―前篇―
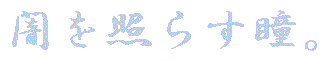 ―前篇―
―前篇―
駅馬 如
ひとの目に見える存在(もの)など、たかが知れている。
ひと、或いは もの―――それがどんな存在(もの)であっても、
それそのものがそこにあるという事実を、証明することは難しい。
そのひと、或いはそのもの―――それらを構成するのは、
あくまでも見て(観て)いる者の思い。
観る(見る)者が変われば、また、その姿も異なる。
では、貴方は何ですか……?
―――私は……本物ですか……?
|
「……な……」 かろうじて口を出得(う)る言葉はそれだけだった。直江は自分の目の前の現状に、咄嗟に声も出せなかった。 解らない。何がどうなっているのか―――何が起こっているのか―――。 辺りを見回す。 ……どこだ、ここは……。 直江の眼前に広がっているのは、見渡す限りの闇。一体どこまで続いているのかなど解らない。ただ、そこには何もない。唯一分かるものといえば、自分の身体(からだ)の輪郭のみ、である。だが、それすらもおぼろげながら解る程度で、ともすれば容易に翳(かす)んでしまう程、闇が深い。 その唯一の身体で振り返ろうとして、直江は更に困惑した。 ……動かないのだ。たった今まで自分の意志で自由に動いていた直江の身体が、持ち主の意思を無視する。 ―――何故だ。 気づいてみれば、身体どころか、指一つ―――今まで何不自由なく動いていた筈の彼の一部が、動いてくれない。まるで、何者かに拘束されてでもいるかのように身動きすらできないというのに、その相手の姿すら、見ることができない。 それどころか―――その《何者》かが本当に存在するのかすら、定かではない。 直江の意識が関知しないところで、知らずに込み上げる、《恐怖》という名の《不安》。 そして、闇。見渡す限りの、闇―――。 ―――分からない解らない判らない……! 一体自分はどこにいるのか。どうなっているのか―――今の直江に解ることは、自分が計り知れない《闇》の中にいるということ。そして、身動きすらできない、ということ……。 彼は、自分を襲う困惑に、声にならない悲鳴を上げた。
ぅわぁぁぁぁ……っっっっ!!
「……ま、……え様、……直江様っ!!」 「……っ……!」 自分を揺さ振る振動に、思わず直江は瞼を開く。眼前に広がるのは、眩しい程の光。先程まで、彼の意思に関わり無く否が応にも彼を包み込んでいた、あの深淵まで続く闇は存在しない。 「……は……っ……」 一体どうなっているのか、直江は咄嗟に判断できなかった。 あの闇はどうなったというのだろうか……? まるで、今直江の周囲に広がる光にかき消され一掃されてしまたかのように、たった今まであったはずの闇が存在しない。 何がどうなっているのだろうか。 荒く乱れる吐息をもらし、自身の状態に困惑する直江の視界に、ふと、見知った顔が映る。 「直江様……」 「―――はっかい、か……?」 僅かに信じられないという響きを乗せて、呟く。それは小さな声(もの)であったが、目の前の男には届いたようだ。 漸(ようや)く自分に気づいた直江に、八海は小さく安堵の溜息を漏らした。同時にそっと手を差し伸べ、直江の前髪に触れる。 「一体どうなさったのですか? 随分とうなされていらっしゃいましたが……」 「……うなされ……?」 そう言った途端、直江は、やけに自分の掌(てのひら)が湿っていることに気づいた。―――否、掌だけではない。身体全体が常とは違う。 知らずの内に力を込めていたらしい両の掌を、そっと開く。そこは、何故かしっとりと湿っている。 「ええ、うなされていらっしゃいましたよ……」 目の前の彼の言葉に、成る程、と思う。ならば、これは冷汗か。 更に見渡せば、直江は白いシーツに包まれている。身体に触れる、柔らかい感触―――。 何もかもが、先程までの彼の居た世界とは大きく異なっている。 黒と白―――何か意味のあるものなのだとは思わないが、あまりにも対照的過ぎて、この現実が彼の中にすんなりと入ってはこない。 「直江様……?」 漸(ようや)く目覚めたはいいが、未(いま)だぼんやりとして返答も覚束(おぼつか)ない直江に、八海は再度声をかける。 気遣わしげな、いつもの八海。直江は八海を見上げた。 「……夢を見た。悪い、夢を――な……」 そう、夢だ。自分の身体が、まるで拘束されてでもいるかのように身動きすらできず、声すらもでない―――そんな現実は存在しない。こうして、八海が――彼の信頼する部下が――、気遣わし気に覗き込んでいる。 優しく、それでいてどこか心配しているような表情で接してくる八海―――それは、常と同じ情景である。それまで、幾度となく繰り返された、彼ら二人の日常……。 だから、こちらが現実。あの、計り知れない闇の中にいるのではなく、こうして八海が側にいる、これが、現実―――直江はすんなりとそう思った。 「夢……ですか?」 そっと目を閉じ、溜息をつきながら言う直江に、八海は幾らか不思議そうな様子で問う。 「……ああ、夢、だ……」 「……貴方があまりにうなされておいでだったので、一体どうなさったのかと、心配しましたよ……」 僅かに苦笑しながらの八海のその声には、直江への気遣いが多分に含まれている。直江にはそれが嬉しい。直江への心配と―――そして、僅かな安堵。 「……心配――したのか……?」 そっと見上げて問う直江に、八海は尚も苦笑して――或いはそう心掛けて――答えた。 「当たり前です。貴方が苦しんでおられるのを見て、私が心配しないとでもお思いですか……?」 「―――そう、だな……」 強い意志。それを、彼の口調から感じる。そう―――彼の言葉通り、八海は今まで何より直江のことを一番に考え、行動していた。直江自身、それはよく実感している―――否、せざるを得ない程、八海は直江に尽くしているのだ。 「心配など、するのは当然です」 再度はっきりと口にする八海に、目を向ける。お互いの瞳が交わったその瞬間、直江はふ、と、微笑んだ。 八海の気遣いが―――その優しさが、嬉しい。仄(ほの)かに自分を包む柔らかい雰囲気(もの)は、間違いなく彼から齎(もたら)されるものなのだ……。 「済まないな……お前には、いつも、心配ばかりかけて……」 交わった視線をそっと外し、眺めるでもなく天井を眺めながら、言う。その、彼らしからぬ力の無い言葉に、聞いている八海の方が慌てた。 「とんでもありません。私は、貴方だからこそ心配するのです―――私が、自分の意志でしていることであって、貴方が気になさることなど何一つありません」 「……そう、か……」 「そうです」 じっと直江を見つめる強い視線のまま、八海は言葉を続ける。未(いま)だ視線を合わせないまま聞いていた直江が、呟くように答えると、不意に横に顔を向けた。 自然と合わさる互いの瞳―――。 「八海」 ふ、と。直江は微笑んだ。形の良い瞳が、声もなく細まる。 「直江様……?」 「―――いや、何でもない……」 何かを言いかけたのでは、と思い、八海は言葉と視線で問い掛けるが、笑みを浮かべたままの彼の主(あるじ)は答えようとはしない。 「直江様……」 軽い溜息と共に紡がれる名前。何も言わない直江を責めるでもない、優しい声色。 そして―――彼はそっと直江の髪を掬(すく)い、何度もそれを繰り返した。彼のその動作は優しく、知らず、直江を安心させる。 何故、なのだろうな……お前が側にいるとこんなにも安心するのは……。 八海の手が触れる度、彼の手が髪を掻きあげる度、微(かす)かに掠(かす)める心地良さに、直江はいつの間にか瞳を閉じている。 八海は直江に触れる動作を繰り返しながら、安心している様子の直江を、愛しげに眺める。 時折見せてくれる、直江の―――彼の主(あるじ)の自分を信頼してくれていることが解るこうした仕種(しぐさ)に、嬉しさが込み上げる。 「………………」 互いに言葉もなく、暫(しば)らく静かに時が流れる。 ……繰り返し―――繰り返し直江の髪を掬(すく)っていた八海は、ふと、一つの疑問が頭を掠(かず)めた。 「そう言えば……直江様の見られた夢とは、一体、どのような夢だったのですか?」 それは、本当に何気無い問い。そのため彼は僅(わず)かに驚いた。 その問いを口にした途端、今まで心地良さ気に瞳を閉じていた直江が、はっと瞳(め)を見開いたのだ。一瞬だけ八海の方を見、そしてすぐに顔ごと視線を逸らす。 ぎこちない、それ―――。 「……直江様……?」 どうされたのですか、と問おうとして、自分から逸らされた白い頬を覗き込もうと、上体を傾(かたむ)ける。 「……いや、気にするな。ただの―――夢だ」 「………………」 『ただの夢』と言いながらも、未(いまだ)だこちらを見ようとはしない直江。八海は何かを口にしようとして―――だが、できなかった。逸らされた直江の瞳が、僅かに揺れているのを見てしまったのだ。 「ただの……夢、だ……」 まるで、“そうである筈だ”と自分に言い聞かせてでもいるかのように、繰り返し呟く。 ―――そう、ただの夢だ。例えどんなに実感があったとしても、あれは単なる夢に過ぎない。この両腕に、未(いま)だ実体の無い《闇》に掴まれてでもいるかのような感触が残っていようとも、それは現実ではないのだ。 直江は、自分が夢の中で確かに感じていた《不安》を思い出し、僅かに身を震わせるが、それを悟られないよう、何気無く言葉を紡(つむ)ぐ。 「そう心配するな。ただ単に、夢見が悪かっただけだ」 心配そうに自分を見つめる八海に、変わらぬ笑顔――直江自身はそう思っている――で言う。 八海を―――自分の身を案じる八海を、これ以上心配させる訳にはいかない。直江はそう思う。ただでさえ、彼は直江のことになると心配し過ぎる傾向があるのだ。余計な気遣いをさせたくはない。 それに……本当にあれは単なる夢なのだ。八海を心配させる云々の以前に、自分こそ、気にし過ぎているのかもしれない。 そう思い、彼は笑顔を造る。 「―――夢…ですか……?」 「そうだ、夢、だ」 「ですが、直江様……っ」 「それとも―――お前は、たかが夢如(ごと)きで俺がどうにかなるほど弱い人間だとでも、思っているのか……?」 心配するな、と言われても未(いま)だ拭(ぬぐ)い難(がた)い何かを感じるのか、八海は尚も言い募ろうとするが、全てを言い終わる前に、改めて自分に向き直った直江の言葉に、先を遮られる。 僅かに見上げる眼差しで、どこか揶揄を含んだ口調―――明らかに先程までとは雰囲気が違う。 「……そうでした、ね……貴方は、お強い」 「だろう……?」 「はい」 そうして、どちらともなく笑う。形の整った直江の唇に笑みが刻まれているのを見て、八海は僅かに何かを言おうとしたが、敢(あ)えて何も口にはしなかった。 どこか引っ掛かるものがないとは言い切れない状態ではあるが、彼の至上の主(あるじ)が「何でもない」と言うのだ。それ以上に彼に何が言えるだろうか。 「では、直江様。そろそろお起きになられませんと……。今日は確か、どなたかとお会いするお約束があるのではありませんでしたか?」 「あ? ああ、そうだったな」 幾分か明る目の声で言う八海は、言いながら、直江の寝ているベッドから身体(からだ)を起こす。ぎしり、と音を立てて、ベッドが軋(きし)む。 答えた直江が上体を起こしたのを確かめて、八海はベッドのちょうど手前に位置する窓へと移動する。 白いカーテンに触れた八海は、しゃっ、音を立てて引いた。途端に差し込む、眩しい程の光―――。 ちょうど朝日が昇っている時刻なのだろう、寝室にある、さほど大きくもない筈の窓から、部屋全体をまんべんなく照らす陽光が入って来る。 「……っ……」 あまりの眩しさに、直江は立てた片膝に腕を乗せ、思わず掌(てのひら)で目を覆った。 「お逢いになるのは、確か――夜叉衆の方々、でしたか……?」 「そう、だが……」 「―――そうですか」 「…………?」 確か、今日の予定については、昨日の内に八海に伝えておいた筈だ。何故今更問うのだろうか……? ふと、微(かす)かな疑問が直江の頭を掠(かず)めたが、すぐに打ち消した。八海が幾ら優秀な部下だとは言え、忘れることがない訳ではないだろう。例えどんな人間であろうとも、当然のことである。 常日頃から過不足なく直江をサポートしてくれている彼である。たかだかこれしきのことでは、彼の評価を下げるには値しない。 ……ただ、それだけではないような―――もっと他にも何かがあるような気がするのも、また、事実だった。だが、では何が―――と問われたならば、答えられる自信はない。それ程に漠然としており、直江自身にもその違和感の正体は解らなかった。 だが、確かめようにも、ちょうど窓の前に立っている八海の表情は、逆光になっているため、直江の位置からではよく分からない。 「では、仕度をなさって下さい。私も準備をして参ります」 直江が感じている僅かな違和感など気づくことなく、八海はそう言うと、窓際から離れる。激しく差し込む陽光から僅かに離れることで、彼の表情が幾らか見えるようになった。 改めて見る彼の表情(かお)は、常の彼と何ら変わるところなどない。やはり気のせいだったのだろう―――直江はそう思った。 そのまま寝室から出て行こうとしたのか、八海は扉の方角へと足を進める。だが、数歩進んだところで、彼の足は止まった。 「直江様……?」 幾分かぼんやりしたまま自分を見つめる直江をどう思ったのか、八海は僅かに笑みを浮かべながら直江の名を呼ぶ。 いつもの―――常と変わらず直江を見つめる優しい瞳。柔らかい―――表情。 「―――いや、何でもない。これから準備をするから」 「はい」 苦笑しながら直江が言うと、彼は今度こそ直江に背を向け、寝室から出て行く。 八海の後ろ姿を目の端に捉(とら)えながら、直江は僅かに苦笑した。 何を馬鹿なことを考えていたのだろう。八海は何も変わらないというのに。そう―――先程、計り知れない《闇》に捕らわれている夢から目覚めた時と同じように、八海はいつも自分の身を案じてくれている。 常の彼。変わらない日常―――。 「さて、そろそろ起きなければ、な……」 これまでと何ら変わりのない日々の中で、直江の、これからも変わらない毎日が始まろうとしていた……。
今日は、綾子の住むマンションの一室で逢うことになっている。直江はそのマンションの前に、珍しく自ら運転して来た車を止めると、徐(おもむろ)に歩き出す。 約束の場所に自分が近づいていることに気づいたのだろう、廊下の向こうで男が一人、腕を組みながら壁に凭(もた)れかかっているのが見える。 もしかすると、腹を立てているのかもしれない。 更に近づいて行くと、薄く縁取られた眼鏡の向こうで、僅かに剣呑な色が光っているのが分かった。 目的の人物まで数メートル、という所まで行った時、案の定、怒声と言っても差し支えないような声が掛けられる。 「よぉ、随分と余裕じゃねーか、直江」 「馬鹿を言うな。俺は遅れてなどいない」 「それでもなぁ」 穏やかならざる雰囲気のまま続いてしまいそうな会話を遮ったのは、千秋とは反対側にいた綾子だった。 「ちょっと、いい加減にしなさいよ。どうだって良いじゃない、そんなこと」 「でもなぁ……っ」 「…………?」 やけに直江に絡む千秋に、綾子だけでなく、直江も僅かに怪訝(けげん)そうな表情(かお)を向ける。 彼らは同じ夜叉衆とは言え、確かにそう仲睦まじい間柄である訳ではない。だが、だからと言って、顔を合わす度に揉(も)め事を起こす程 険悪な訳でもないのだ。 その夜叉衆の中でも千秋は、これまでの長い月日の中で、直江との間で意見や考え方の相違から、多少口論になったことが全くないという訳ではないが、こうも訳もなく――少なくとも彼以外にはそうとしかとれない――直江に絡む千秋というのも、珍しい。そのため、綾子は幾分か気遣わしげな視線を、千秋と直江との両方に向ける。 これから、夜叉衆として話し合わなければばらないことがあると言うのに、彼らの間でいざこざがあることなど、歓迎できることではない。 「ちょっと、千秋、あんたらしくもないわよ。何を苛(いら)ついてるのよ?」 「……別に何でもねぇよ。誰が苛つくかっての」 諌(いさ)めようとする彼女に軽く舌打ちをして、千秋は視線を逸らす。その動作そのものが、彼が苛ついているという事実を顕著に表わしているというのに、それすらも気づかないのか、彼は苛立たしげに顔を背ける。 『何でもない』・『苛ついてなどいない』……そうは言うものの、千秋の苛立ち――少なくとも直江や綾子にはそうとしか見えない――は、彼らの話し合いが終わるまで続いた。 ―――直江がこの約束のマンションに到着して、およそ2時間が経過した頃、突然、彼の携帯電話が静かに鳴り出した。 重要とも思える会話は既に終了し、ほぼ、雑談――彼らの間でそれが成立するのであれば――になっていたとは言え、その場で携帯電話に出るのは気が引けたのか、直江は他の面々に目配せすると、身体(からだ)を反転させ、他の2人から僅かに離れた所で通信スイッチを入れる。 「……俺だ。ああ、もう終わるところだ。……そうか、頼む」 ぴっ、と小さく音を立てて通信を切り、彼は戻って来る。そんな直江に綾子は声をかけようと口を開くが、彼女の言葉は、それよりも早く横から発せられた声に阻まれてしまう。 「……誰なんだよ」 今日ここで、彼ら3人が夜叉衆として逢っていることを知っている者がいるなど、考えられない。何故なら、今回は極秘に――とは言え元々誰に言うでもないが――行われていたものなのだ。闇戦国に関わる存在は元より、一般の―――闇戦国に関わりのない人間に、直江が今日の自分の所在を明かすなど、有り得ない。 そんなことを、常の冷静な彼がする筈がない。恐らく、千秋だけでなく綾子もそう思っているだろう。 「こんな時に連絡してくるなんざ、信じらんねー」 「―――何を苛ついているんだ、長秀?」 「そんなことはどうだって良いんだよ! ……とにかく、答えろよ」 見るからに何かに苛立っている様子の千秋に、直江は何かを言いたげに口を開きかけるが、やがて諦めたかのように僅かに小さく溜息をついた。 「何をそんなに気にしているのか知らんが―――さっきの電話は、八海だ」 さらり、と。何の隔たりもない口調で、彼の口は一つの名前を紡ぐ。それが耳に入った途端、千秋の表情が僅かに変化した―――ように、彼のすぐ横に位置する綾子には見えた。 「………っ………」 何かを言いた気に――そうとしか見えない表情で――千秋は目の前の直江を見るが、突如、はっとしたかのような様子で視線を逸らす。 「……何だ、どうした、長……」 「何でもない」 その彼らしからぬ様子に、声をかけようとした直江の言葉を遮り、千秋は一向に視線を戻さない。 「―――――――」 そうして、彼らの間に俄(にわ)かに沈黙が降りる。 ……初めに口を開いたのは、それまで殆(ほとん)ど口を開くことのなかった綾子だった。 「……直江。八海には今回のこと、言ってあるってことなのね?」 それは、《訊く》・《尋ねる》というよりも、《ただ言ってみただけ》、というもの。《確認》ですら―――ない。 「…………?」 携帯電話をしまいながら、直江は僅かに首を傾(かし)げる。彼には今の彼女の台詞が、何故か気になった。 「……当たり前だろう。八海は俺の部下だ。知っていて何がおかしい?」 そう、直江の言う通り、何もおかしいことではないのだ。八海は上杉の軒猿頭。本来、彼ら夜叉衆に敵する存在ではない。 「いいえ、別におかしいことはない、わ……」 ちらり、と。直江の問いに答えながら、彼女は横を窺う。綾子の視線に気づいていないのか――それとも気づかないふりをしているのか――その視線の先では、千秋が、微動だにせずあらぬ方向を見つめている。 ―――と、当然、それまで険しい表情のまま黙っていた千秋が口を開いた。 「……おい、直江。お前最近、何か変わったことはないか……?」 「―――変わったこと?」 また突然、彼は何を言い出すのか。直江は千秋の真意が解らず、僅かに眉を顰(ひそ)める。だが―――微(かす)かに溜息をついただけで、彼は他に何も言いいはしなかった。 直江は、自分をじっと凝視する彼に目を向ける。 いつにない、真剣な表情。どちらかと言えばふざけたことを言っていることの方が多い千秋の、彼らしからぬ視線。 その視線が、直江に問い掛ける。 どうなのか、と。答えろ―――と。 ……一体、今日の彼は何を思っているのだろう。先程から、何かに苛立っているかと思えば、あらぬ方向を見つめたまま黙り込んでいたりする。 何を苛立っている……? ―――否、それとも……。 「―――お前が何を考えているのか知らないがな、変わったことなど何もない」 「そ・そうよ、何もある訳がないわ」 それまで、彼らの様子を窺っていた綾子が、直江に続いて言う。言いながら、彼女は千秋に目を向け、表情を窺う。 二人から、ともすれば探るかのようにも感じられる視線を向けられながら、千秋は意にも介さず――それとも気づいていないのか――、硬い表情を崩さない。それどころか―――益々険しい表情で、直江を凝視している。 「……おい?」 「―――何もないなら、良いんだ……」 何だ、と、問おうとした直江の言葉を遮り、千秋はそっと視線を逸らす。呟くようなその台詞は、彼らしくもなく力が篭(こも)っていない。 「長秀……」 ふ、と。直江はそっと溜息をついた。一旦瞳を伏せ、そして徐(おもむろ)に視線を合わせる。 「何をそんなに心配しているのか知らんがな、お前が気にするようなことなど何もない。―――まぁ、いつ怨将どもが動き出すか解らないのだから、この先どうなるかなど、誰にも解らんがな……」 「―――っ―――」 どことなく苦笑を含んだ言葉に、それまで暫(しば)し俯いていた千秋が反射的に顔を上げる。彼の言葉が形を成す寸前、彼らのいる部屋のドアの向こうに、人の気配を感じた。 「!?」 瞬間、3人の視線が一斉に直江の後ろの扉へと注がれる。 だが、直江には、そこにいる人物が誰であるのか解っていた。よく知った、常に自分と共にあった存在(もの)―――。 彼は静かに背後へと振り返る。 知らず、彼の表情が柔らかいものになる。その変化を、他の2人がどう見たか―――どんな思いで見つめていたのか、直江は知らない。 ……3人の見つめる前で、静かにノックする音が響く。そして―――その扉が厳(おごそ)かに扉が開かれた。 「直江様……」 果たして、直江の《予想》――《確信》と言った方が正確かもしれない――の通り、姿を現したのは彼ら上杉の軒猿頭・八海であった。彼は扉を開けるや否や、主(なおえ)の顔を視界に収め、深々と拝礼を施す。 そんな様子を見ている千秋と綾子の二人の顔には、驚きの表情は見られない。恐らく彼らも、突然の来訪者の正体を解っていたのだろう。直江はふと、そう思った。 「ご苦労、八海」 「とんでもございません、直江様」 笑顔で労(ねぎら)う直江に対し、八海もまた、笑顔で返す。彼がこの部屋の扉を開けた瞬間から、この時まで、未(いま)だ他の2人の視線が自分に注がれ続けていることに気づいているのかいないのか、八海は常と変わらず直江に接している。 「思ったより早かったな」 綾子と千秋が自分達の様子を見つめていることなど知る由もない直江は、彼らに背を向けたままで、自分を向かえに来た部下に話し続けている。 その主(あるじ)の言葉に対し返答した八海は、ふと、直江の肩越しに後ろを顧(かえり)みた。そして、軽く会釈する。 まるで、綾子達の存在にたった今気づいたかの様な彼の様子―――。 「―――相変わらずね、八海……」 苦笑を浮かべながら、あたかも呆れたと言わんばかりに綾子が言う。途端に、それまで注がれていた2対の視線が外されたことに、視線の先にあった人物は気づいているのだろうか……。 我ながら変なことを考えるものだ、などと思いながら、彼女は目の前の直江と八海の姿に、交互に目を向ける。 「……何がだ?」 言われた片方である直江は、僅かに首を傾(かし)げる。一体、八海の何が《相変わらず》なのだろうか? 自分では思い当たらないことなだけに、一層、彼女の態度が気になってしまう。 「おい、何が……」 「―――何が、八海の《1番》なのか、よ……」 言いながら、彼女は八海に目を向ける。自分の顔を見ながら言う綾子に対し、八海は何も口にしない。彼のその表情はあまりに常と変わらないため、綾子には、今の自分の台詞(ことば)を彼がどう解釈(と)ったのか、知ることはできなかった。 「………………」 綾子と八海は、言葉もなく、ただ、互いを見ている。互いに何を言うでもなく、僅かに沈黙が流れる。 一方、彼らの横で、直江は綾子の言った内容(ことば)を反駁(はんばく)していた。 彼女は《八海の1番》と言った。だが―――それだけではよく解らない。直江は僅かに眉を顰(ひそ)め、綾子を凝視する。 ふと、横から注がれる視線に気づいたのか、彼女は八海から視線を外すと、ちらり、と直江に向ける。 「解らないなら、それでも良いわ」 「―――おい」 どういうことだ、と続けようかという考えがふと頭を過(よ)ぎったが、彼は敢(あ)えてそれをしなかった。こういう時の彼女は、何を問うたとしても答えはしないだろうと思ったからだ。 直江は小さく溜息をつくと、軽く首を振った. 「……まあ良い」 よく考えてみれば、彼には今日中にやらねばならないことが幾つかあった。そのために八海がここに迎えに来ているのである。 そのことを思い出し、直江は綾子を追及するのをやめた。 丁度、綾子達との必要な話し合いも終了している頃合である。ここで自分が抜けたとしても、何ら問題はない。直江はそう判断した。 「―――――」 ちらり、と。直江の視線が一方に向けられる。その彼の視線の先では、この、誰も知らない筈の部屋に八海が現れてから一度も口を開いていなかった人物が、あらぬ方向を睨みつけたまま、未(いま)だ微動だにしない。 「………………」 そんな千秋の様子に、引っ掛かるものを感じる。先程の彼の言葉は、一体何なのだろうか……。 先程……? 自分の考えが間違っていることに、ふと、直江は気づいた。《先程》から―――否、思えば、今日の彼は初めから、どこか常の彼とは違っていた。何かに苛立ち、落ち着かない彼。 千秋らしからぬ千秋の様子に、何かを口にすべきなのかもしれない。だが、千秋の言っていた《何か変わったこと》など何もないのだ。そのため、彼に言うべき言葉が見つからないことも事実である。 もう、一体これで今日一日で幾つ目になるのかなど分からない溜息を一つ落とすと、彼は徐(おもむろ)に千秋に背を向けた。 続いて、扉の前にいる八海に視線で先に行くよう促すが、八海は軽く首を振り、動こうとしない。そんな風に自分を敬う姿勢を示す彼に、直江は軽く苦笑しながら、先に足を進める。 静かな音を立てて自分のために開けられた扉の前で、ふと、直江の足が止まる。何を思ったのか、そっと振り返る。だが―――向けられた視線の先の人物に対して、彼の口は開かれることはなかった。 何も言わずに彼らを見つめていた綾子の見ている先で、直江の姿が扉の向こうに消えた途端、それまで一向に身動ぎすらしなかった千秋が、勢いよく顔を上げた。 彼の視線は、ただ一方に―――今まさに閉じられようとしている扉へと注がれている。 「…………っ」 その扉の向こうに、直江に続いて部屋から出て行く八海の姿。千秋の口が形にならない言葉を搾り出した途端、ほんの数瞬、八海の視線と千秋のそれが微(かす)かに交差した―――ように、千秋には感じられた……。 ―――ぱたん、と。2人の視線の先で扉が閉じられていく。たった二人がこの部屋からいなくなっただけだと言うのに、まるで世界が変わったかのように感じられる。 ……さて、と小さく呟くと、綾子は徐(おもむろ)に振り返る。閉じられた扉を凝視したまま、千秋は身動ぎすらせず、彼女の方を見ようともしない。 相変わらず険しい表情―――。 「……ちょっと千秋。あんた、ホントに今日、何か変よ? ずっとイライラしてるし、アンタらしくもない」 「………………」 「一体、どうしたっていうの」 心底不思議そうに―――そして、幾分か訝(いぶか)しげに問う彼女の方を、ちらり、と横目で見ただけで、彼はすぐに視線を前に戻してしまう。 「……何でもねぇよ」 「………………」 何でもない、という表情(かお)ではない。彼は一体、何がそんなに気になるというのだろうか―――綾子にはそれが不思議でならなかった。 つかつかと、数歩、歩み寄る。千秋の側まで近づいた彼女は、そっと手を伸ばした。 「ちょっと千あ……」 「何でもねぇって言ってんだろっ!」 ぱしり、と。差し伸べられた手をはね退(の)けることで、かけられた声をも遮る。 「……悪ぃ」 数瞬後、気まずそうに千秋が言う。綾子はそんな彼の態度に、大袈裟に溜息をついた。 「―――嫌な予感がすんだよ」 未(いま)だ先程の気まずさを引きずっているのか――はたまた何かを言わずにはいられなかったのか――突然、不意に千秋が口を開いた。今までなかなか口を開かなかった彼が自ら口を開いたことに、確かに驚きつつも、彼女は、彼の心情はきっと後者だろうと、おぼろげながらそう思った。 「……嫌な予感……?」 予想もしなかった彼の言葉に、僅かに目を瞠(みは)る。もう一歩足を進め、彼に更に近づいて表情を覗き込もうとしたが、千秋は決して彼女を見ようとはしない。 「それって―――もしかして、直江……?」 それは、問いかけというより、独り言に近い声(もの)。意識的に話した訳ではなく、不意に口をついたものだ。 だが、彼女には解ってしまった。千秋の気にかかっていることが―――彼女の予想通りだということを。 「何がそんなに……」 「……それが解ったら苦労しねぇよ!」 苛立ち気に――先程から変わらずに苛立ってはいるが―――吐き捨てると、千秋は踵(きびす)を返す。綾子の側から離れると、近くの窓の前へと移動する。 乱暴に開けられた窓から温かい日差しが差し込み、昼間の喧騒が飛び込んでくるが、彼の耳には何も届かない。本来ならば、眼前で繰り広げられる光景――子供達が遊んでいたり誰かが犬を散歩させていたりする光景(もの)――が否が応にも目に飛び込んでくる筈であるが、今の彼には何も見えてはいなかった。 彼は自分の思考(おもい)に捕らわれていた。 『何がそんなに』―――ほんの数瞬前に訊かれた、綾子の言葉が頭を掠める。だが、答えは見えない。それどころか、こっちが聞きたいくらいなのだ。 何が気になるのか。彼女にはそれが不思議なのだろう。だが、千秋にも―――彼自身にも、はっきりとした理由は解らないのである。 ……不意に、直江がここから立ち去る際に言った、自分の台詞(せりふ)を思い出す。 『何か変わったことはないか』―――確かに自分はそう訊いた。何故そんなことを訊いてしまったのか……今ならそれが、おぼろげながらではあるが、解る。 僅かにみえかけている自分の思いに突き当たり、だが彼は強く首を振る。 ……不安!? この俺が!? ここへ……この約束の部屋へと直江が現れてから―――否、今日彼に逢う以前から、漠然と千秋を襲っていた思い。 馬鹿ている。こんなことを思うなど、自分らしくない。 直江が―――彼がいなくなってしまうなど……。二度と彼に逢えなくなってしまいそうな気がする、などと……全く、馬鹿げている。 何をそんなに気にすることがあるのだろう。よく考えてもみれば、不可解だ。千秋自身も含めて、彼ら夜叉衆は、闇戦国に身をおいている限り、常に危険と隣り合わせである。いつ何がおこるかなど解らない―――そんな世界で生きている限り、いつ誰に何が起きても、ある意味おかしいことではない。 それに―――と、千秋は思う。つい先程別れた直江に、特に変わったところなどみられなかった。常の―――彼のよく知る直江そのものである。 一体何が……そうは思うが、彼は、自分が拭(ぬぐ)いきれない《不安》に苛(さいな)まれていることに気づいている。 特にこれと言って、はっきりとした《何か》が気になる訳ではない。ただ何か―――そう、形にならない《何か》が、彼の中の不安を煽るのだ。 漠然とした思い。形のみえない《何か》―――解らない。解らないからこそ、尚更、苛々する。 「……くそっ!」 がんっ! と、彼はすぐ前にある壁に拳(こぶし)を叩きつけた。 苛々する。自分が訳の解らない感情(もの)に振り回されていることも、それが《不安》であるということも、千秋には信じられなかった。 何故、直江がいなくなるなどと思うのだろう。彼の何が気になるというのか―――千秋には自分の思いが解らない。 直江にはじきに逢える。そう、その筈だ。だから何を思い煩(わずら)うことがあるだろう―――彼はそう思い、口元だけで笑む。だが、それを見た綾子が一瞬言葉を失してしまう程、それはまるででき損なった笑みであった。 彼らしくない笑いを浮かべたことに、彼は気づかなかった。 「……直江……」 小さく、だが確かに形作られたその呟きは、開けられた窓から入る風に乗って、綾子の耳に届いていた……。
そうして、彼らの前から直江の姿が忽然と消えたのは、この日からちょうど五日後のことであった―――。
……ぱたん、と。小さな音を立てて、車のドアが閉められる。直江がしっかりとその身をリアシートに沈めるのを見定めてから、八海は車の反対側にまわり、運転席に座る。 キーを指し込み、エンジンをかける。静かな、だが確かな振動に身を乗せながら、直江は口を開いた。 「今日は悪かったな、八海」 「……?」 徐(おもむろ)に告げられた主(あるじ)の言葉に、言われた八海の方は僅(わず)かに不思議そうな顔をする。それを見て、直江は苦笑する。 「……いや、わざわざこんな所まで迎えに来させて、悪かった、と思ってな」 ちょうど交差点の赤信号に差しかかり、車が静かに動きを止めたところで、八海は言った。 「とんでもありません、直江様。これは私の―――私の、大切な役目ですので。直江様が気になさることは何もございません」 はっきりと、言い淀むことなどなく告げる彼に、今度は直江の方が僅かに不思議そうな表情(かお)をする。僅かに小首を傾(かし)げると、困ったかのような―――どこか、彼らしからぬ顔をする。 「……無理は―――するなよ……?」 「無理、などと……」 どことなく見上げるかのような眼差しで自分を見る直江に、八海は僅かに苦笑する。 こうして車を止めて会話しているのは、ちょうど交差点に差し掛かったからであり、一時的なものに過ぎない。八海は、信号の色が変わればすぐにでも発進できるように、と、予(あらかじ)め手にしていたハンドルから手を離す。 彼の主(あるじ)の珍しい様子に、彼は無意識に姿勢を正した。 「直江様、私は何も無理などしてはおりません。何事も私がすすんで行(おこな)っているものであって、貴方が気になさることは、何一つありません」 そう―――これは彼の本心。誰に言われたからでも、単なる忠誠心からの行動(もの)でもない。ましてや、無理などと―――決してする訳がない。 八海は自分の意志で、直江に―――彼の主(あるじ)に尽くしているのだ。 貴方を……愛しているから……。 決して口には出さない想い。―――出せない……想い。 身体(からだ)ごと直江に向き直り、真剣な表情で告げる彼を、直江は言葉もなく、ただ、見つめる。 直江の全身を包み込むような、温かい感情―――それが何であるのか解らないが、自分を一心に見つめる目の前の男から齎(もたら)されるそれに、直江はそっと瞳を閉じた……。 「……そうか」 「そうです」 きっぱりと、何の淀(よど)みもなく答える。その誠実さが―――彼の優しさが、嬉しい。 直江は瞳を閉じたまま、仄(ほの)かに笑う。それを見た八海も、同じように微笑んだ。 ―――と、その時。後ろから厳(おごそ)かなクラクションが響いた。 二人共が驚いて後ろを返り見ると、いつの間にできたのか、彼らの車の後方には幾つもの連なりができている。確か、信号に従って停車した時には、この交差点には彼ら以外の車の姿は見られていなかった筈である。 急(いそ)いで前方を見ると、ほんの数瞬前――少なくとも直江達にはそう思える――には赤かった信号が、いつの間にかその色を変えている。 即座に八海がアクセルを踏む。 とうに信号が青に変わっていたことに二人して気づき得なかったことに、二人、顔を見合わせて笑う。自然と、先程とは僅かに異なった雰囲気が流れたことに、八海はそっと安堵した。 ……幾つ目の交差点を通り過ぎた頃だろうか。それまで二人は互いに口を開かなかった。それは特に深い理由はない―――ないのだろう、と、八海は思っている。 そんな直江が、ふと、口を開いた。 「そう言えば、次は迎えはいらないから、心配するな」 「……?」 《次》、と彼は言った。一体何のことなのか、と、運転しながら八海は思う。それを察したのだろう、言った直江は僅かに苦笑する。 「いや、今回だけでは纏まりきれなかったかならな。次回、もう一度逢うことになっているんだ」 誰に―――とは、問わずにも解っている。 「今度は、はっきりとした時間も決まっていないし、先に色々と用件を果たす必要もあるからな。だから、次も俺一人で行く。帰りも、俺一人で良いから」 「―――そう、ですか……」 「……?」 前を向いたまま伝えた直江は、ふと、何かが引っ掛かり、ミラー越しに八海の顔をそっと見遣る。 「…………?」 何だろう。何か―――それが何であるのか全く解らないが、彼はたった今、八海に対して微(かす)かな違和感を感じたのだ。だが、それが、彼の中で形を成さない。 ちょうど、今朝方、あの悪夢――そうとしか思えない《闇》の記憶――から目覚めた後に、訳もなく僅かに感じた違和感(それ)と、どこか似たような感覚―――。 一体何なのだろうか、という疑問が頭を掠めるが、深く考える必要もないようにも思える。あの時とそしてたった今感じた感覚が、確かなものであるという確証がある訳でもない。それに、今日の彼は疲れている。心身共に疲労している状態では、余計なことが妙に気になってしまっても、いた仕方ないのかもしれない。 そもそも、常に彼に忠実で変わらず忠誠を尽くしてくれている八海に対して、僅かとは言え違和感を感じるなど、疲れているとしか思えない。 そう結論つけて、直江は再び視線を前へと戻す。 「直江様、今日はもうお疲れでしょう。このまま直接、お家に向かわれますか……?」 「……え? ああ、そうだな……」 突然八海からかけられた言葉に、直江は僅かに瞳を瞠(みは)る。そう―――八海はいつも、こうして彼の身を案じてくれる。そして、直江自身すらもなかなか気づき得ない身体(からだ)の不調までも、彼自身が気づくより前に察してしまうのだ。 八海のその優しさが―――心地良い。 「―――ありがとう、八海」 「いいえ、とんでもございません」 そう微笑みながら応える八海の顔は、そう、常のままの―――直江の知る彼そのものだった。 今日、本来ならば向かう筈であった方角と反対方向に、八海は車を向かわせる。目指す先は直江の自宅。 緩やかに、それこそ直江の身体に負担がかからないように静かに運転される車の中で、直江は、微(かす)かに微笑(ほほえ)みながら、そっと瞳を閉じた……。 |
to be continued ……
|
● コメントという名の言い訳 ● |
|
ぅ……何と言っていいものやら、困ってしまいます〜(あせあせ)。久し振りの直江受小説、です。しかし、長い!(汗) 我ながら「何なのコレ……(呆れ)」状態です。 いっつも、長過ぎる〜っ!と泡噴いている駅馬ですが(いやホント/汗)、今回も、またこのパターンか……状態デス(苦)。容量は、《君は僕の宝物》に次ぐ長さです。長さだけでなくて―――内容が、他のどれよりも……何じゃこりゃぁ!(呆)ですね〜(遠い目)。
まず。これまでの駅馬の作品を読まれた方々、さぞやビックリなさってるのでは??(びくびく) だって、今までのと大きく違うでしょぉ??(はらはら) ……いや、要所要所では、これまで通りの駅馬テイスト(ほら、シリアスなトコとかね?)が存分に織り込まれてますが(……恐らく)、大きく違うと言えば―――暗いこと、ですかね??(冷や冷や) 皆さん、ここまでで、既にこれからの展開の予想が、多少はついてしまうのではないかと、駅馬は思うですが―――どんなもんですか??(あせあせ) ええ、暗いです。正に「何だこりゃぁ」?(泣) 未だかつて、駅馬はこゆの(こんなに暗いの)書いたことないです〜っ!(あたふた) 初めてです!! だって、甘々書きなんですから、駅馬はぁ!(叫) あああぁあああぁあ……(嘆)。
それでも、ですね??(ちょっと復活したらしい) 駅馬、最初の辺りで、「……ぅ…こんな暗いの無理かも〜っ(苦)」とかって思ってたですよ??(真剣) だって、ウチの八海が、例によって(←ええ正に!)直江に、何て言うかこう、ラヴラブ?みたいな……(照汗)。 「あ〜っ! こんなんじゃ、てんでダメじゃ〜んっ!」と絶叫すること、実に片手じゃ足りません(マジ)。だって、そう思いませんか?? ところどころ、いつもどーりの八×直シーンじゃないですかぁ〜(苦)。 「八海、アンタ一体どうしたの……?」と思いましたが、そう言えばウチの彼は、元から単なる直江馬鹿の変な男でしたね……(って、じゃダメじゃん!)。 あちゃーーー……(遠い目)。駅馬、暫し錯乱した模様です。暫らくお待ち下さい。
そうそう(再度、復活)。一部の方々に、BBSで内容を予想して頂いたんですが……如何なもんでしょうか……?(ドキドキ) こんな中途半端じゃ、まだ予想が云々は言い難いですかね?(はらはら)
裕さん、ごめんなさい!(泣) 砂吐きのシリアスを予想して下さったのに……ううぅ(泣)。でもでも、一部においては、そのものでしょう??(あせあせ) 駅馬も、八海と直江のラヴラヴ(だと思う…)に、「いい加減にしなさいよ、貴方達……」って何度呟いたことか!(だから何だ) 裕さんの予想そのものではなかったですが、少しはあったでしょう??(上目遣い) さくらさん! 初めの予想は、結構当ってたですよね〜(苦笑)。確か、えろ+ダーク+壊れ+死、でしたっけ?(苦笑) どこがどうあたってたか、どこが違ってたかってのは、その内に解ります……多分(ヲイ)。でも、結局はさくらさんも、予想を砂吐きシリアスに変えたんでしたよね(苦笑)。う〜ん、ごめんなさい!(苦笑) まえださんも……こんなん、予想外ですよね??(はらはら) いやはや、駅馬もですよ!(←オイ)。と言うか、でも、「やっぱり八×直か〜!」って感じですか??(苦笑) ななせに関しては―――いやもぉ、何とも……(←何だ)。
取り敢えず―――。 こんなん駅馬が書くなんて、きっとびっくりなさってることでしょうね……。大丈夫、もう2度とないでしょう!(苦笑) だって……何度も言いますが、駅馬は甘々書きなんですも〜〜ん!(泣き笑い)
と、言う訳で(←?)。今回は、いつものように長々とは語れないので、これくらいで終わりです☆(←かなり語っておいて何を言う)。 最後に一言……「続いちゃってごめんなさぁぁぁ〜〜〜いっ!!!」(逃)
|