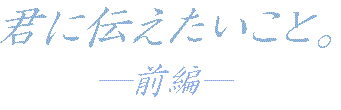
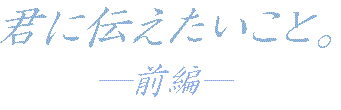
駅馬 如
|
「まったく……」 直江は心底呆れたかのように溜息をついた。 本当に不甲斐ない。これが自分の姿なのかと思うと、溜息のひとつもつきたくなるというものだ。 改めて今の自分の姿を見て、何とも言えない気分になる。 「……何でこんな……」 そう呟いてみて、その声が意外にも掠れていることに気づいて、益々うんざりしてくる。 これが直江信綱の姿か。そう問いたくなって―――だが、答えてくれる相手が側にいるでもなく、直江は瞼を伏せることで思考の流れを止めた。 そもそも、何故だか頭がぼんやりとしてしまい、思考がうまく纏まらない状態である。そんな時に、何を考えても正確な答えは出てこないものだ。 「―――何でこんなことになったんだか……」 誰に言うでもなく、ただ口をついた、それ。だが―――。 「それは、自業自得というものですよ」 何故か返答が返ってくる。直江は、未だぼんやりとした思考のままで、声のする方向へと頭を向ける。彼にしては珍しく、声の主が咄嗟には判断できなかった。それが―――直江には納得がいかない。 「ちゃんとお休みになられましたか……?」 「―――八海」 ぱたん、と扉を閉め、こちらに歩いて来る男に向かって、名前を呼ぶ。八海は足を進めながら、尚も声をかける。 「お加減は如何ですか、直江様……?」 その問いには答えず、直江は別のことを考えていた。 何故彼はここにいるのだろう。何故、自分の『お加減』を案じているのか。そもそも、自分は何故こうして寝ているのか。何故―――。 ふと、次々とそんなことを思った直江は、だから八海がすぐ傍まで来ていることに気づかなかった。 「まったく、直江様? 《何で》、なんてことは、考えるまでもないでしょうに……」 静かに告げる声。だが、直江にはその内容が解からない。何故、考えるまでもないことなのか。 それを聞きたくて―――だが彼は、それをしなかった。否、しようと思って八海を見た彼は、それができなかった。 八海が直江を見ていた。一心に直江を見つめる彼の瞳は静かで。それでも、静かなだけでなく、何かを―――何某(がし)かの感情を込めて、直江を見つめている。 いつもの八海と変わらない、同じ瞳。だが、今回は何かが違う。いつもあるが、いつもより何かが多い。直江は何故かそう思った。 それは―――心配……? そう思い当たって―――直江はふと、額にあたるひんやりとした感触に気づいた。 「こんなに……まだ、お熱があるようですね……」 「……八海?」 お前が何でここに―――口を開こうとした直江のその問いの答は、八海の腕の中にあった。 彼は抱えていたものを、そっとテーブルの上に置く。がさっ、と音を立てて袋を開けた八海は、中から赤いものを取り出した。 「……………」 「―――ああ、これですか?」 彼の手の中のそれを、じっと見つめる視線に気づいたのか、八海はふと顔を上げて、苦笑した。 「今はまだ、何も召し上がれる状態ではないでしょう? でも、何かを召し上がらないと、貴方の体力がもちませんから」 彼はそう言うと、口元にそっと笑みを浮かべる。 「これくらいなら―――お口に合うかと思いまして……」 『それ』を僅かに掲げるようにして、直江にもよく見えるように近づける。 大きな八海の手の平に乗せられた、それは―――。 「八海……」 直江がふと言いかけたその時―――ぐぅ〜っという音が、小さく、だが確実に二人の耳に届いた。 瞬時に紅く染まる直江の頬。それを見た八海が小さく笑む。益々彼のそれが色を増したことに、八海は気づかないため、その悪循環――少なくとも直江にとっては――は、直江がちろり、と非難のこもった瞳(め)で八海を睨むまで続いた。 「それでは、召し上がれるように準備して参りますね」 未だ口元に僅かに笑みを刻んだまま、そう言って八海は立ち上がる。その場を離れる際に、上掛けの端から僅かに出ている直江の足先に、タオルケットを掛け直すことを忘れなかった。 彼の背中が寝室から消えるのを横目で眺めていた直江は、八海の姿が完璧に見えなくなってから、ふ、っと溜息をついた。 恥かしい。いくら、体力を消耗した体が食物を何も受け付けないとは言え、こんな醜態を晒すとは。 微(かす)かに頬が熱い気がするが、それは異常に上がった体温のせいだと思うことにする。 ―――それにしても。と、直江は思う。 ここにいたのが八海で本当に良かった。もしもアイツだったりした時には、何と言われて揶揄(からか)われるか解かったものじゃない。 「助かった、か……?」 ふと浮かんだ旧友――否、そんな関係ではないのかもしれない――の顔を思い出しながら、苦笑しながら呟く。 彼にこんな自分の姿――先程の醜態も含めて――を見せるなど、まっぴら御免だ。そんなことをしたら、一体何をされるか、考えるだけでも頭が痛い。 予想される揶揄の言葉に、直江はうんざりした気分になってきた。そもそも彼は、揶揄(からか)われるのが何より嫌いなのだ。 ―――八海で良かった、とは思うが、だが彼のあの表情は何なのか。あれは僅かに揶揄(からか)いが含まれていたようにも思えたが、八海ならばまだマシというものだろう。―――アイツに比べれば。 そう結論付けて、直江は考えるのをやめた。何より、常よりかなり高い体温のせいで、頭がいつものようには働かないのだ。身体全体が、考えることを拒否している。 「まぁ、良い―――か……」 八海はすぐに戻って来るのだろう。先程の《あれ》を持って、直江のいる、この部屋へ。 そんなことを思いながら、直江はタオルケットを肩まで引き上げた。そして―――そっと瞳を閉じた。
「……直江様……?」 厳かな音を立てて、ドアを開け、八海は寝室へと入る。声を掛けたが、返答がない。 「直江様?」 もう一度繰り返し、足を進める。直江のベッドをそっと覗き込んだ彼は―――次の瞬間、微笑んだ。 穏やかな吐息を繰り返す彼は、静かな夢の中にいた。それを壊したくなくて、八海は手にしているものを、そっとテーブルの上に置いた。そして、音を立てないように細心の注意を払って、引き寄せた椅子に腰をかける。 八海の体重を受けた途端、椅子がきちり、と小さな悲鳴を上げた。はっとした彼は、再び直江の方に視線を向ける。 変わらない、穏やかな表情。八海はほっと息をついた。 僅かに紅く染まった頬、時折寄せられる形の整った眉。やはり、高熱のために体力を消耗しているのだろう。 閉じられた瞼に隠された、琥珀色の瞳がいつものように自分に向けられないことを残念にも思うが、それは仕方がないというものだろう。今は充分に休養を取って欲しいと望む自分とは別に、早く自分を見て欲しい―――そう願ってしまう自分がいることに、不意に気づき、八海は自分を笑った。 女々しい感情―――だが、それも仕方のないことだとも思う。直江だから。心配するのも笑って欲しいと願うのも、直江だからなのだ。 今はただ、貴方を苦しめるこの熱が、一刻も早くが下がると良い―――そう思う。 八海はそっと右手を伸ばし、直江の頬に触れる。まだほんのりと熱いそれに、いつになればこの熱が直江から去ってくれるのだろう、と心配になってくる。 そもそも―――こうなってしまった原因は何なのか。八海は知らない。 『それこそ、自業自得というものですよ』 何でこんなことに……と、我が身を嘆いていた直江に向けた自分の台詞を、ふと思い出した。 ―――ことの始まりは、八海がたまたま直江のマンションに出向いたことから始まった。 《たまたま偶然》―――この言葉は、正確には正しくない。彼は彼なりの用があって直江に逢いに行ったのだ。 ただ、直江に逢いたくなって―――。 他に理由はない。突然、無性に直江の顔が見たくなって―――ただそれだけだ。他人にとっては下らない理由であっても、八海にとっては、正当で、そして大切な理由だった。 激しく降りしきる雫に嫌気をさしながらも、運転する車を直江のマンションの前に停め、ふと前を顧みた八海は、そのまま凍りついてしまった。 マンションの入り口に立っている人物。視界に入った途端、それが直江だということが分かった。 だが、瞬間、八海の眼を奪い去ったのはそのことではなく、直江の状態だった。 全身から雫を滴り落とし、彼は立っていた。ただ立っていたのならば、八海もそこまでに気にしなかっただろう。咄嗟に、直江が風邪をひいてしまうことを心配はしても、ここまでは慌てなかった筈である。 普段は冷静な八海――少なくとも直江の前では――がうろたえてしまったのは、直江が―――彼の主(あるじ)の様子が常とは違っていたからである。 彼が近づいて行っても、それに気づくこともなく、ただそこに立っている。そんな唯ならぬ様子に、八海は慌てた。 「な・直江様……!? どうなさったのですか、一体……!」 そう問う彼の言葉も耳に入っていないのか、直江はただ、何処ともわからない遠い何処かを見つめている。 ばしゃばしゃと水溜りを蹴りながら、八海が走り寄る。しかし、直江はいっこうにこちらに気づきもしない。 そんな彼に―――まるで視界から八海を排除したかのような直江の態度に、八海は耐えられなかった。 「直江様、直江様――っ!?」 目の前にある直江の肩を掴み、揺さ振る。そうしながらも、少しでも良い、直江の変化を見逃すまいと目の前の彼の姿を凝視する。 そして、不意に―――彼の瞳に色が戻った。それまで、虚ろで、まるで何も見えていなかったような彼の瞳が、その時初めて何かを写した。 「……な、直江、様……?」 それは、一瞬の出来事。 ホンの一瞬、まるで何かに驚くかのように八海に目を向けた直江が、うっすらと唇を開いた。だがその声の内容はは、あまりに小さく、そして瞳のことに気を取られていた八海には届かなかった。 次の瞬間―――糸が切れるかのように、ぐらり、と倒れ込んだ直江の身体を、一歩前に出た八海が抱き止める。 髪と――全身を濡らした直江からしたたり落ちる雫が八海の服を濡らしていくが、そんなことは気にならなかった。八海は―――彼の瞳には、今正に目にしたばかりの直江の姿が、今尚、鮮明に残っていた。
そして―――今に至る。
八海は、目の前で静かに眠る直江に目を向ける。 貴方はまだ、ことの原因を話してはいない。口に出そうともしない。 それは、私だからですか―――? 私には話しては下さらないと……? それとも―――話せるようなことではないのですか……? 沸き起こる疑問。何が彼をあそこまで追い詰めたのか―――。そして、何が彼の身に起こったのか。それを知りたくて―――だが、それを知ってしまってはいけないような、もどかしい思いに捕らわれる。 問いたくて、でもできなくて。 直江の瞳に映る存在(もの)に気づきたくて―――それでも、気づきたくもない、そんな、思い。 八海は、そっと手を差し伸べる。眠る主(あるじ)の前髪を、そっと掻き上げる。 私は貴方を―――。 相変わらず仄(ほの)かに色を残す頬に手を動かし、それと同時に上体を傾ける。吐息を紡ぐ直江の唇に、八海のそれが触れる正にその瞬間―――。 「……ん……?」 微かに発せられた言葉。否、声と言った方が正しいだろう。正確には意味を伺うこともできないような小さな声。だが、それでも、八海の動きを止めるには充分だった。 「……は…はっか、い……か……?」 ふと、直江が瞳を開く。まだ視界がはっきりしないのか、数回、瞬きを繰り返している。 その、年齢以上に幼く見せる表情に―――八海は、ぐらり、と揺れる自分の感情に気づき、僅かに苦笑する。 「――お目覚めですか、直江様?」 自分の中に芽生える――正確には常に抱えているもの――を直江に悟られたくなくて、八海は敢えて普段通りに振舞う。 否、例えそうでなかったとしても、自分は直江に対して常の態度を崩すことはないだろう―――そんな、漠然としたものを感じる。 「ああ、もしかしなくても、俺は眠ってしまっていたのか……?」 「ええ、よくお休みでしたよ」 微笑んで答える八海に、直江は僅かに首を傾ける。眠り込んでしまう前に考えていた疑問が、ふと頭をよぎる。 「そう言えば八海、何故ここにいるんだ……?」 それは、直江にとっては何気ない質問。いとも簡単に返答が返ってきて当然の。 だから彼は思いもしなかった。質問を口にした途端、八海の表情が変わとうとは―――テーブルに伸ばした手が止まるとは。 「―――八海?」 「……いえ、別に大したことではないんですよ……」 確かに大したことではない。少なくとも、直江にとってはそうだろう。 そう思い、八海は僅かな一瞬だけ止めていた手を動かし、目的のものを持ち上げる。 「そんなことより―――これをどうぞ」 言いながら、手にしたそれを掲げて見せる。 そんな八海に―――まるで話を逸らそうとでもしているかのような彼に、直江はふと、触れてはいけない話題(もの)にでも触れてしまったかのような気分になった。 特に変なことを訊いたつもりはない。だが、事実、八海はそのことに触れたがってはいない―――触れたくはないのだろう。その理由は判らないが、彼がそう思っているのなら、触れるべきではない。直江はそう解釈した。 常に直江に誠実な八海が「大したことではない」と言うのなら、本当に大したことではないのだろう。ならば、改めて訊くこともない。 「―――お前が、これを……?」 八海の手にした《それ》に目をやり、直江は苦笑する。 「勿論ですとも。さぁ、どうぞ」 そう言って、爪楊枝(つまようじ)に刺さったそれを、直江の口元に運ぶ。 慌てたのは直江である。確かに今自分は病人で(認めたくはないがそうらしい)、臥せってはいるが、ものを食べるくらい自分でできる。 「ちょ・ちょっと待て、それくらい自分で……っ」 慌てて起き上がろうとするが、即座に八海に止められる。 「ダメです。貴方はご病気なんですよ? こんな時くらい、他人に甘えたらどうです」 「だが、これくらい……」 「ダメです」 尚も言い募ろうとした直江だったが、目の前でにっこりと笑う八海に再度止められ、仕方なく、その身体を横たえた。 こんな時、八海は呆れるほど過保護になる。直江とて子供ではない。自分の健康管理くらい自分でできる―――そうは思っているのだが、八海からすれば、全然できていないのだ。 何でこんなに―――とは思うが、その理由に気づかない直江は、僅かに眉を寄せる。 「お前……」 「直江さま、ご無理はいけませんよ?」 誰も無理などしていない―――そう言いたかったが、恐らく八海に止められることは予想がついたため、諦めた。 「さぁ、直江様……」 どうぞ、と差し出されたそれを見て、直江は僅かに不本意そうな視線を送るが、八海は気づかない様子で――はたまた気づかないふりをしているのか――尚もそれを近づける。 ふ、と溜息をつくと、直江は仕方なく口を開いた。 途端に、しゃりという感触と、甘くまろやかな味が口腔に広がる。 「―――甘い」 「そうですか?」 口元を抑えながらも口を動かす直江の様子に、八海は目を細める。彼が食べてくれたことが、何とも嬉しい。 「もう一口、どうですか……?」 「……ああ」 こうなっては、もう『自分でできる』と振り払う気も起きない。今はもう、八海の手から齎(もたら)されるその味が、直江の身体に染み渡っている。 しゃり、と、音を立てて噛む。広がる甘さに、直江はそっと瞳を閉じた。 そんな彼の様子を、八海はただ、静かに眺める。直江もそれを口にする以外のことをしないため、二人は会話もなく、ただ時間だけが静かに流れていった。 直江が嚥下し、口内になくなったと見ると、八海がそっと新しいそれを差し出す。直江はただ、与えられたそれを静かに味わっている。 ―――丁度、5口ほど終わった時、直江がふと、八海の方を見遣った。それまで閉じられていた瞳が、じっと八海に向けられる。 「それにしても、お前がそんなに器用だとは思わなかったな」 「……そうですか?」 そっと微笑んだ直江の、その言葉の意味が解からず、八海は僅かに首をかしげる。それに気づいた直江は、それだ、と言って八海の手の中の《もの》を指差す。 それは―――林檎。先程、直江が初めて目覚めた時に八海が抱えていた紙袋の中身、その一部。 今は、食べやすいように切られ、皮が剥かれている。しかも―――ただ形良く切られているだけでなく、何と、兎の形になっているのだ。一般的に、子供の弁当箱によく入れられている、あれだ。 八海の意外な一面を見たような気がした。普段から仕事をそつなくこなし、直江の指示に忠実な八海。だからこそ、器用であることは普段からも窺い知れたが、こうして改めて見ると、少しだけおかしくなってくる。 「何も、そこまでしなくても……」 そこまでも、とは、兎の形にしなくても―――という意味なのだろう。そう思い、苦笑する直江につられて八海も苦笑する。 「ですが、この方が直江様も食欲が湧くでしょう?」 「―――確かに」 そう言い、二人は顔を見合わせて笑う。ひとしきり笑った後、ぽつりと八海が言った。 「私は、何だってできますよ―――貴方のためなら」 最後の一言が紡がれた途端、直江はふと、笑いを止めた。 「―――八海……」 自分に注がれる視線に気づき、八海は不意に苦笑した。そして、僅かに居ずまいを正す。 「さぁ、もう少しどうですか……?」 視線を直江から逸らし、手の中の林檎に向ける。その中の一つに爪楊枝を刺すと、直江の口元まで運んだ。直江がそっと表情を窺い見ると、八海は微笑を浮かべ、直江を見ていた。 「少しでも召し上がって、またお休みになられた方が良いですよ……」 「……ああ」 そうだな、と続け、直江は差し出された林檎を口に含む。時を待たずして広がる甘さに、思わず頬が緩むが、先程の八海のことが気にかかり、視線を彼に向ける。 八海は直江を見ていた。僅かな微笑すら浮かべて、いつも通りの彼が直江を見ている。 まるで、ふと漏らしたあの一言は直江の空耳であったかのような、普段通りの彼―――。優しく直江を見つめる彼からは、何の思惑も窺い知れない。 では、あれは何だったのか―――。 直江の中にちょっとした疑問が浮かぶが、ふいに襲った眠さがそれを邪魔する。 身体(からだ)は正直だ。休養を欲している身体は、食欲が満たされた途端、睡眠を要求しだしたらしい。 八海の方に目を向けようとするが、既に視界もぼやけてきている。八海の表情すらあやふやにしか見えない。 「……お、前にもやるべき…こと…があるだろう、に……もう、帰っても良……」 途切れ途切れになりながらも言葉を紡ぐ直江に、言いたい内容を悟ったのか、八海は直江の言葉が全て紡がれる前に遮った。 「―――私のことでしたら、お気遣いいりません。どうぞ、ゆっくりお休み下さい」 その台詞に何かを返そうとしたが、思うように思考が纏まらない。それどころか、八海の言葉すら、直江は正確には理解できずにいた。 「直江様、私ならば……」 彼がまだ何かを言っているのは解かるのに、耳がそれを受け取れない。訊かなければ―――そうは思うが、思考は今にも持ち主の元を離れようとしている。 「……はっ…か、い……」 その一言を最後に、彼は完全に意識を手放した―――。 ……すぅっ、と吐息を漏らして眠る直江―――だから彼は知らない。傍らに佇(たたず)む八海が、切なげな視線を向けていたことを。 「―――直江様……」 そして、八海の表情に、僅かに何かが混ざっていたことを―――。
未だ剥かれずに残っていた林檎が、テーブルの上から緩やかな弧を描いて落下する。その、ぼとり、という音だけが、二人のいる室内に静かに響いた……。
|
to be continued……
ご・ごめんなさぁ〜〜〜いっ!!(涙)
|
● コメントという名の言い訳 ● |
|
はい、ご存知、某バカップル大会用に書き散らした(←…散らす?)八×直です。でも、掲載期間3日間という、サイアクな作品(死)。 いやはや、いつもよりラヴ度が高いとの感想をちらほら頂きまして、駅馬も我ながら、「あらら〜(苦笑)」とか思ってるところです(笑)。 だって、「やっぱりバカップル大会だしぃ!」と息巻いて(……たかどうかは不明だけど)書いてたような記憶があるんですよ……(苦笑)。でも、結果としては、いつも通り、八海が直江ラヴしてて余計な伏線がいくつも存在してて直江が八海の気持ちに気づいてない――という、いつものパターンに(苦笑)。やっぱ、いつも通りでした〜!(笑) 駅馬、自分がアホだと解かってますけど、ここまでとは……(苦笑)。ウチの八海って、報われないですね〜。
ホントは、ただ2人がラヴラヴしてるだけのお話にする予定だったんですよ。マジに。……でも、無理でした(涙)。 ど〜しても、シリアス&切ない系になってしまうんです〜〜〜〜っ! 何故に……(苦笑)。 ――あ。駅馬としては、シリアス&切ない系に見えるんですが、皆さんには見えないですかね……(はらはら)。今の時点でそう見えないとしても、今後の展開はそうなる可能性大ですよん♪ 伏線の存在からすると。 あ、伏線と言えば。駅馬、いっつも小説書く時って、何かしらの伏線を張ってしまうんんですが(それはもぉ、無意識的に/苦笑)、一本で完結ならともかく、続き物で、しかも間が開いちゃったりすると、駅馬、伏線の内容、忘れたりするんですよ〜(死)。アホの子なので(自覚あり)。 今回こそは、そ〜ならんようにしたいもんです……。つ〜か、しなきゃならんですね(苦笑)。
この話、うさ林檎を直江に食べさせる八海と、それをもらう直江が、読んで下さった皆様に妙にうけました〜★(笑) 嬉しい限りですv 何せ駅馬、この前篇の中で一番書きたかったのが、そこなんですもの〜♪ 勿論、他のトコもそうですが、一番はやっぱりあそこですね〜♪ ……の割にうさ林檎のあたりは短いですが、それは、製作時間があまりになかったからなのでした……(涙)。ホントはもっともっと長く書きたかったのに〜〜〜〜っ!(泣) ――それにしても、この直江を「可愛い」と言って下さった方々、……ホントですかぁ??(苦笑) 嬉しいです〜v きっと、ウチの八海も同じような気持ちなんでしょう……(笑)。駅馬は、「仄かに紅い顔して眠る直江を前にして、よくぞ堪えた!」――と、八海を褒めてあげたい気分です♪(笑) ……あ、堪えない方が良かったですか?(爆笑) それはそれでも良いかも……(ぼそっ)。
某友人(←…?/苦笑)に首締められて脅されて、聞き出されそうになった、直江曰く《アイツ》のこと――ですが。きっとその内に出てきますんで。……多分(←オイオイ)。きっと、後篇かな? ちゃぁ〜んと出て来る(予定)ですんで★ ←こうやって書いとかないと、多分駅馬、忘れるから……(死)。
さてさて。大会に掲載時に、「続編は〜?」・「後篇は?」と言っ下さる方々が結構いらっしゃって、駅馬は嬉しい悲鳴を上げてます。……一部、ホントの悲鳴も上げてますが(苦笑)。 その後篇ですが―――。なるべく早くに書く予定です。ええ、駅馬自身も、早く書きたいんで〜♪ ただ、駅馬の『なるべく』は、一般的な『なるべく』とはちょ〜っと違うみたいなので……何とも(苦笑)。仕事が、あんまりにも忙しいので、何とも……。 ――だって、駅馬がヘタなこと言おうもんなら、某な○せ(←伏せても意味なし)がすっ飛んで来て、嬉々として駅馬の首締めそうなんですもん……(泣き笑い)。
―――と、言う訳で(←どういう訳だ)。後篇がアップされた暁には、是非、読んでやって下さいませ〜♪ そんでもって、感想頂けると、駅馬は嬉しいです〜〜〜♪ TOPのメルフォかBBSでお待ちしてま〜す☆
|